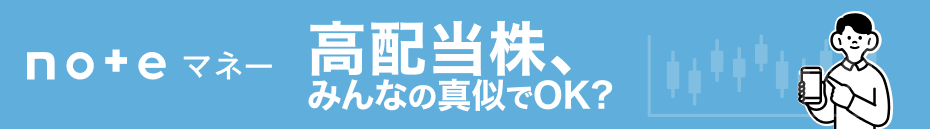社会課題構造化マップ「身寄りのない高齢者等問題」を公開します
JANPIA出資事業部では、インパクト投資を通じた社会課題の解決を後押しするために、専門家の支援を得て、「社会課題構造化マップ(以下、構造化マップ)」の作成に新たに取り組みました。今回、取り上げる社会課題は「身寄りのない高齢者等問題」です。
この構造化マップは、本領域の専門家である黒澤史津乃様(OAGウェルビーR 代表取締役)と、沢村香苗様(日本総研創発戦略センターシニアスペシャリスト)のご協力・監修のもとで作成いたしました。
黒澤史津乃
株式会社OAGウェルビーR 代表取締役
金融機関にて経済調査に従事した後、専業主婦を経て、約25年にわたり家族に頼らずに老後とその先を迎える「おひとりさま」の支援に携わっている。2007年行政書士登録。2019年消費生活アドバイザー及び消費生活相談員登録。2023年より現職。一般社団法人横浜イノベーション推進機構代表理事として、横浜市内の地域課題解決にも取り組む。内閣官房「認知症と向き合う幸齢社会実現会議」構成員、厚生労働省「身寄りのない高齢者等の生活上の課題実態把握事業」有識者委員。日本初の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」の今秋設立へ向けた準備委員会委員長をつとめている。
沢村香苗
日本総研創発戦略センターシニアスペシャリスト
東京大学文学部卒業。同大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻博士課程単位取得済み退学。保健学博士・精神保健福祉士・公認心理師。研究機関勤務を経て、2014年に株式会社日本総合研究所に入社。研究・専門分野は高齢者心理学、消費者行動論で、「高齢者の身元保証人、身元保証等高齢者サポート事業に関する調査研究」など単身高齢者問題に関する実績多数。
この記事では、この構造化マップをつくった背景や概要について、お2人の専門家のコメントを交えてお届けします。
構造化マップで「全体像が見えにくい社会課題」を捉える
「身寄りのない高齢者等問題」は、誰もが耳にしたことはあっても、全体像を把握するのが難しい社会課題です。高齢化社会の一断面として語られることはあっても、医療・介護・生活・死後の事務処理などにおいてどのような困難が生じ、誰がその負担を担っているのか、具体的にイメージするのは簡単ではありません。
また、「身寄りのない」とは、家族がいない/頼れない/頼らない方を含む広い概念であり、すでに高齢の方だけでなく、現在40~50代の方にとっても、将来的に切実な課題となり得ます。
社会課題の中には、原因と結果がシンプルで可視化されやすく、共感を得やすいものもあります。一方で、「問題として認識されにくいが、確実に存在するもの」も少なくありません。「身寄りのない高齢者等問題」はまさに後者にあたり、既存の制度や支援体制だけでは十分な対応が難しい課題です。だからこそ、より根本的な制度設計の見直しや、新たな仕組み・事業によるアプローチが求められています。
この構造化マップは、そうした「構造が見えにくい社会課題」を整理・可視化することで、社会全体での理解を促し、課題解決に向けたアクションの起点となることを目指しています。新たなプレイヤーや資金を呼び込むきっかけにもなればと考えています。
「身寄りのない高齢者等問題」構造化マップの見方
この問題の全体像をシンプルに捉えるために、大きく「本人」「制度」「周囲にいる関係者」の3つの視点で整理を行いました。
「本人」のところは、身寄りに期待できない背景、事前の備えに至らない背景などの代表的なものを記載し、「制度」のところでは、仮に本人が備えたとしても、現在の制度ではすべてが網羅されるわけではないことを表現しています。問題解決を担う民間の事業者もいますが、それらもまだ十分ではない点にも言及しています。
これらを背景として実際に起きている問題を、中央のところで典型的な場面ごとに整理しています。そして、これらの問題を解決するために、「周囲にいる関係者」がそれぞれ少しずつ無理をして対応している現状を事例とともに解説しています。
専門家が語る「身寄りのない高齢者等問題」
構造化マップの作成にあたり、多大なるご協力いただいたお二人に、この問題に関する背景や本質、解決への道筋等についてお話を伺いました。
ーーまず、「身寄りのない」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか?今後、このような高齢者が増えていく見通しについても教えてください。
沢村:身寄りというのは、その人をよく知っていて、様子がわかり、何か困ったら助けてくれる人のことです。といっても頼れる程度には差があります。日常的に、病院に送り迎えしてくれたり、役所の書類の手続きを手伝ってくれたりすることもあれば、亡くなった後のご遺体の引きとりと火葬だけ対応するという場合もあります。
身寄りとしてイメージしやすいのは配偶者や子などの親族ですが、知人やかかりつけのお医者さんであることもあります。最近は高齢者等終身サポートなどの事業者という場合もあります。
配偶者や子がいない高齢者はこれから増加する見通しですし、子がいても側には住んでいないことも多いです。頼れる親族のない(子がいない、子・配偶者ともいない)高齢者の数は2050年には今の2倍以上に増えるという推計もあります。
具体的には、2024 年から 2050 年までの間に、子のいない高齢者は 459 万人(人口の 12.7%)から 1,032 万人(同 26.5%)に増加。子・配偶者ともいない高齢者は 371 万人(10.3%)から 834 万人(21.4%)に、三親等内の親族がいない高齢者は286 万人(同 8%)から 448 万人(同 11%)に、それぞれ増加すると見込まれています。また、親族がいても支援を期待できるとは限らず、「いざというときのお金の援助」を頼れる相手がいない高齢者は 2024 年時点で 790 万人規模と推計されています。(いずれも日本総研による推計値)
ーー「身寄りのない高齢者等問題」の全体像を構造化するにあたっては、「本人」「制度」「周囲にいる関係者」という3つの視点で整理しました。それぞれの視点のうち、まず「本人」「制度」について、どのような課題があるのか教えてください。
黒澤:最大の課題は、「本人」視点でも「制度」視点でも、いざというときに頼れる身寄りがないということが、これまで想定されてこなかったことです。
身寄りがない「本人」が困るのは、病気や認知症になった場合に治療や生活を維持するための適切な意思決定や金銭管理ができない、死亡後の対応をしてくれる人がいないことです。そうなる前に備えておけば良いのですが、いざとなったら誰かが何とかしてくれるという思考が働きがちで、今はまだ困っていないご本人に、事前に備えておくインセンティブが起こりにくいという事情があります。
「制度」については、介護保険制度、成年後見制度、生活保護制度等がありますが、それらではカバーできない困りごとが多数あります。そこを埋めるための民間サービスについても、社会的ニーズの増大に対して整備がまったく追いついていなかった状況から、ようやく政府が「高齢者等終身サポート事業」のガイドラインを策定し、民間事業者側でも業界団体設立へ向けて動き出したところです。
ーー「周囲にいる関係者」──例えば医療・介護の現場や不動産・地域などのプレイヤー──はどのような困難に直面しているのでしょうか?
沢村:ご本人が自分でできない用事を、身寄りが代わって行ってくれない場合に、損害を被るというのが1つです。たとえば利用料・家賃の支払いや、亡くなった後のご遺体の引き取りや持ち物の片づけをしてもらえなければ、医療・介護の提供者も、大家さんも困ります。また、ご本人とのコミュニケーションがうまくいかない場合にも、間に入ってくれる人がいないと困ります。
もう1つは、そういった損害を被ることを避けるため、現場の職員の方が、本来の仕事ではないけれども、家族の代わりに用事をしてあげることになりがちということです。一概に悪いこととはいえませんが、例えばお金を扱うことには不正を疑われるリスクが伴いますし、勝手に本人の物を処分することにもリスクがあります。時間的・費用的な負担ももちろんありえます。無報酬で、こういったリスクも引き受けて支援をしなければならない状況になってしまうことがあるのです。
身寄りのない高齢者等問題の現場で起こっていること
ーー具体的に現場でどのような問題が起きているのか、印象的なエピソードなどがあれば教えてください。
黒澤:つい先日、急性期の病院から、70歳代後半の一人暮らしの女性についてご相談がありました。検査の結果、末期ガンと判明してそのまま入院しましたが、夫とは死別、ひとり息子とは疎遠になっていて20年以上音信不通。子供がいても「身寄りがない」ケースです。入院費はきちんと支払われるのか、今後の治療方針や転院先や療養先の相談を誰にしたら良いのか、危篤や死亡の連絡を誰にして、誰が夜中でも連絡を受けてくれて、ご遺体の引き取りをしてくれるのか、誰もいないとなると病院も困ります。
判断能力があってお金もあれば民間の高齢者等終身サポート事業者を、判断能力がなければ成年後見制度を、お金がなければ生活保護制度を利用することになりますが、この方の場合、今のところ判断能力があるので成年後見制度は使えない、預貯金はほとんどないが生活するのにギリギリの遺族年金と夫から相続した資産価値のあるマンションがあるので生活保護制度も使えない、民間事業者と契約するには預貯金がないということで、このままでは、宣告を受けた余命を過ごすホスピスに転院できないというご相談でした。
ーー制度等のはざまに落ちてしまうのですね。その後、その方はどうされたのでしょうか?
黒澤:ご相談を受けて何とか解決策を考えて動き出そうとした矢先に、容体が急変して逝去されました。その時点で、その女性に関する権利義務のすべてが唯一の相続人である音信不通の息子に移転するので、事前にご本人が死後事務委任契約を締結していない限り、息子以外の誰も勝手にその女性の火葬や納骨、荷物の処分や契約の解除等を行う権限はありません。
この場合、「引き取り手のないご遺体」として役所預かりとなり、息子が引き取りを拒否したら、最終的には法律の定めにより行政によって火葬され合祀されることとなります。未払いの入院費や残された荷物については、病院がコストと手間を掛けて音信不通の息子に請求するしかありません。所有しているマンションの管理費・修繕積立金の未納がつづけば、マンションの管理組合にとっては死活問題です。
このように身寄りのない状況で亡くなると、周辺の関係者が大きな負荷を抱えることとなりますが、生前のご本人は事前の備えをすることなく「後は野となれ山となれ」の心境になりがちであることが大きな課題です。
ーー今後、身寄りのない高齢者等が増加する中で、すべてを国や行政だけで対応するのは難しいのではないかと思われます。そうした中で、民間セクターにはどのような役割や貢献が期待されるとお考えですか?
沢村:身寄りのない高齢者等の問題については、実態把握がひととおり行われて、ようやく解決策についての議論が始まったところです。私たちの個人の生活上の問題なので、国や行政が関与できる部分は限定的だと思います。また、公的なサービスでは比較的経済状況のよくない人や判断能力の低下した人が優先されるでしょう。一般的なあるいはそれ以上の経済状況の人や、判断能力が低下していない人のほうが大多数なので、そういった人に対するソリューションは民間が提供することが望ましいと考えています。
具体的には、金銭管理や死後事務や、生前の生活支援、それらのコーディネートが求められています。ただ1つの事業者ではすべての領域をカバーできないので、事業者どうしでうまく協業していただくことや、判断能力の低下等に備えて公的な機関とも連携をしていただくことが良いと思います。
インパクト投資やJANPIAに期待すること
ーーこの問題に関して、インパクト投資やJANPIAに期待することを教えてください。
黒澤:身寄りのない高齢者等の問題は、その分野も当事者の資産階層もどちらも幅広いので、一つの施策ですべて解決することはなく、すべてを公的資金で対応することも不可能です。分野別、資産階層別に様々な解決策の選択肢を用意して、そのうち民間事業者が公的資金に頼らずに安定的・持続的に展開できるビジネスモデルの創出が必要です。
この課題を持続可能な収益を得ながら解決に導くためには、稀有な存在で大きな経済的リターンを目指すユニコーン企業ではなく、社会貢献と収益の二兎を追いつつ群れを形成して共創・協働しながら社会的インパクトを創出するローカル・ゼブラ企業の活躍が求められます。特に、将来身寄りのない状況になる当事者予備軍の方々が安心して事前の備えを行うことのできる仕組み作りに取り組むローカル・ゼブラ企業に、インパクト投資やJANPIAの事業がお力添えくださることを願っています。
沢村:この課題については、大体何をしなければならないかは明確になったと思います。誰がやるのかという人手の面と、そのコストをだれが払うのかという費用面が次の課題です。特に、もともと高齢者等終身サポート事業者さんが苦労されているように、日常的な支援や見えない支援(いつでも駆けつけられるような人を配置しておくこと)は利用者から適正な費用を頂くことが難しいとされています。
一方で、お金を遺して亡くなる方は多く、自分の財産を遺言によって相続人以外の人や団体に無償で譲るケースもあります。お世話になった人や事業者に、死後にお金を遺したい方も多くいるそうです。ですがお世話になった人や事業者にお金を遺すことは、利益相反の構造から逃れることができません。高齢者が生前に経済的な不安を抱えずにすみ、支援をする人も適切な報酬が得られるような仕組みを作っていただきたいと思っています。
この構造化マップを通して実現したいこと
この構造化マップは、すでにこの問題に取り組んでいる関係者の方々だけでなく、「この課題をどうにかしたい」と考えているあらゆるプレイヤーの行動を後押しすることを意図しています。
インパクト投資家
社会的意義のある投資テーマを検討し、民間事業者による解決が期待される社会課題を理解したい方
スタートアップや起業家
福祉・介護・老後の課題にイノベーションで挑戦しようとしている方
金融・不動産・ライフエンディング関連の事業者
この課題に既に関わっている、または新規参入を検討している方
NPO・NGO
地域共生社会、地域包括ケアや高齢者支援の枠組みづくりに取り組んでいる方
この構造化マップは「課題の構造図解」であり、市場機会や潜在ニーズの発見、事業化可能性の探索、投資判断の基礎資料として、多様な場面でご活用いただければ幸いです。
課題の「見える化」から、解決に向けた一歩を
私たちは、この「身寄りのない高齢者等問題」の構造化マップが、これまで関わりのなかったプレイヤーにも新たな気づきを与え、「自分たちにもできることがある」と動き出すきっかけになることを願っています。
社会課題の解決には、多様な立場からの知見と行動が必要です。
今後もJANPIA出資事業部では、こうした「構造の見える化」を起点に、資金・知恵・人材の流れを生み出し、より良い社会づくりに貢献してまいります。
オンラインイベント(6/26)のお知らせ
このたびの構造化マップ公開を記念して、マップ作成にご協力いただいたお二人の専門家をお招きし、「身寄りのない高齢者等問題」の実態や、インパクト投資をはじめとする多様なプレイヤーによる貢献の可能性について語り合うオンラインイベントを6/26(木)に開催します。
「身寄りのない高齢者等問題」とインパクト投資の可能性
~社会課題の構造をひもとき、解決に向けたアクションを考える~
開催日時:2025年6月26日(木)11:00-12:00
開催場所:オンライン(Zoomウェビナー形式)
※参加登録をいただいた方へ前日までにウェビナーURL等のご案内をお送りします。
お申し込み:以下イベントページよりお申込みください。
<https://www.kyuplat.com/media-channel/event-notice-janpia_2506/>
【申込締切】6月24日(火)17:00まで
すでにこの領域で活動されている方はもちろん、
・社会課題解決に資する事業や投資を検討しているインパクト投資家の皆さま
・福祉・医療・介護・ライフエンディング分野に携わる事業者や起業家の皆さま
・高齢者支援に関心のあるNPO・自治体関係者の皆さま
など、多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
一緒に、課題の「見える化」から、解決に向けた一歩を踏み出しましょう。
※本記事は作成時点で入手可能なデータに基づき作成しています。また、記事内容はインタビュー対象者個人の見解を含むものであり、当機構の公式見解を示すものではありません。
記事構成・編集:JANPIA出資事業部note編集チーム