大喜利の必勝法
「死ね! 死ね! 死ねっ!」
俺は隣の参加者から奪い取った描きかけの絵回答で、床に倒れた主催者を何度も何度も殴りつけた。途中で手応えが変わったのは頭が割れたからだろう。
主催者はぴくりとも動かなくなっている。しかし俺は殴り続けた。さっきまで横並びで大喜利をやっていた奴らは、会議室のもう一方の端まで逃げてしまっていた。
七十回くらい殴ったところでバキッと音を立てて絵回答が折れ、八十五回くらい殴ったところでとうとう真っ二つにはじけた。飛んでいった方の破片には絵回答の右半分が描いてあったが、擦過でかき消えた上に血が付着して全く判別不能だった。もはや絵回答とは言えない。
「クソが!」斜めに折れた回答の切断面のうち鋭角になっている方を主催者の太腿に突き刺した。「おらあっ!」
そのまま回答をえぐるように動かすと、穿たれた穴から噴水のように血が噴き出した。その出血の一定のリズムは、目の前の人間の心臓がまだ止まっていないことを示している。
鼻を殴るような生臭さと鉄の匂いに思わずえずいたが、回答を傷口から引き抜こうとした。血まみれの手では何度も滑り、両手を使ってようやく抜けた。回答も真っ赤なので俺の肘から回答までが一続きの赤い塊になっている。
回答を投げ捨て、近くの床に転がっていたボードマーカーを拾い上げた。そして、排水口のような音を立てて血を吐いている主催者の右目に突き立てるつもりで、俺はマーカーを振り上げた。
「やめろ!」
そのとき一人の男が、背後から覆い被さるようにして俺の手首を掴んだ。今日のこの大喜利会で、主催とは別に司会として回答者の指名などの回しをやっていた奴だ。最初に黙らせようと殴って床に転がしておいたのに、もう目を覚ましてしまったらしい。
「主催を殺してなんになる!?」
「うるさい! どけ!」
俺は振り払おうと激しく暴れた。それで手を跳ね除けることには成功したが、勢いづいた拍子に床一面の血糊で足を滑らせてしまった。
そのまま転倒して胸と腹を強く打ちつけ、呼吸が一瞬止まるほどの衝撃が走り、俺は声にならない悲鳴をあげた。もちろん男はその隙を見逃すことはなく、あっという間に組み伏せられてしまった。
「くそっ……」
「落ち着いたか?」
「…………」
血の海と化した床を見つめながら、強い痛みのショックによって急激に頭が冷えていくのを感じていた。しばらく沈黙が続いたあと、俺がもう暴れ出さないと見たのか、男はおもむろに俺の上から離れた。
俺はよろけながら立ち上がると、血みどろの服のまま長机の自分の席に戻った。
トドメは制止されたものの床に転がる主催はどう見ても助かる状態になく、司会も手当てなどはしようとせず放置してあった。
こうした大喜利会では、参加者が数人ずつローテーションで回答者席に着き、残りは客席で観覧および審査をする。だがそこに座っていた奴らも会議室の後ろへ逃げて固まっており、パイプ椅子の客席は空っぽだった。
すでに全ては意味をなくしている。俺は大喜利を放棄し、回答することから逃げ、人を殺した。どうしてそんなことを? 先ほど自分を駆り立てていた正体不明の激情は失せ、なにもかも滅茶苦茶にしてしまった後の虚しさだけが残った。
他の回答者たちは相変わらず一人も席に戻ってこない。力が抜けて立てなそうな奴もいれば、不自然な姿勢のまま硬直している奴もいる。驚きすぎると人間ああなるらしい。誰もなにも言わないので、会議室の中は時間が止まったようになっている。
クズ共が、と俺は内心で毒づいた。また無性にイライラしてきた。今度はこいつらを一人ずつ殺していってやろうか。
「……なるほどな」
ため息をついて男が言った。
「は?」
「なあ、勝ちたくないのか?」
「なにに?」
「大喜利だよ。まだ勝てるとしても、勝ちたくないのか」
「うるさいな、さっきからなにを言ってる? だいたい──」
「いいか、よく見てみろ。今の時間で、誰もこの会議室から出ていってない」
言われてあらためて眺めてみると、自分たちを除いて十四名の参加者たちが、たしかに一人も欠けていないように思える。
「目の前であんなことがあったのに、一人残らずこの部屋に留まってる。それがどういうことか分かるか?」
「…………」
「会を中座するときも、誰かが答えてる最中にドアを開けて出ていく奴はいない。それは、人の回答を妨害してはいけないという、大喜利プレイヤーたちの暗黙の了解があるからだと思わないか」
男はホワイトボードとペンを俺の前に投げた。
「衝動的な人殺しで場を台無しにしたというのは、お前の思い込みでしかない。ただ回答権を持つ者の一人が長いフィジカル回答を一つ出しただけに過ぎないと、この場は判断している」
俺はその場で振り返ってスクリーンを見た。『満腹だと人権がなくなる世界でありそうなこと』というお題が表示されていた──大嫌いな世界お題。
キッチンタイマーが鳴った。時間切れだ。いや正確には、ここから10秒の間に最後の一答を用意することが許される、マジックタイムと呼ばれる時間が始まったのだ。
まだ大喜利は続いている。
「お前の一答目はたしかにヒドかった。浴びたのは客席の笑いじゃなく主催の血だけ。これじゃ評価されるわけもない」
男は司会席に戻り、鳴り続けていたタイマーを止めた。
「しかし、チャンスでもある。その答えに時間を使いすぎたせいで、他の回答者たちはまだ一答もできていないんだからな」
話し終える前に、俺はもう最後の回答を書き始めていた。
大喜利に必勝はないと思っていた。だが、席を放棄してなにも答えようとしない他の参加者たちは必敗だ。一答した者とゼロ答の者がいて、一答の方がどれほど最悪だったとしても、ゼロ答の方を審査で勝たせることは原理的にできないからだ。
最初の一答で時間を使いきり、主催者を殺害し、他の回答者の思考を麻痺させて以降なにも答えさせず、さらにダメ押しの二答目を出して決める。誰でも考えつくが誰もやらない戦法を、知らず実践していたらしい。
「ペンを置いてくれ」
数秒の後に男が言った。
「司会としての仕事を果たそう。……最後の一答が出せる人は、指名していくので挙手を」
誰もなにも書いている様子はなかった。応じて手を挙げたのも、もちろん俺一人だけだ。
男の語ったことが、凶器を持って興奮していた俺をなだめるための理屈に過ぎないのは分かっていた。これ以上ヤケを起こさせず、さっさと最後の答えを出させ、適当に満足させてこの場から追い出してしまおうということだ。
だが俺にはまだ、大喜利をやるならば勝ちたいという気持ちがあったらしい。勝てると思った瞬間、ひとりでにペンを取っていたのだから。
しかも俺はこの答えに少し自信があった。いくら頭をひねろうとろくなものを思いつけたことがなかった世界お題だが、繰り返し主催者を殴打したことにより脳に充溢したアドレナリンのせいなのか、お題が求める芯を真っ向から射抜くような発想が、なんの苦もなく最初から手にしていたかのごとく閃いたのだ。大喜利プレイヤーなら誰もが体験する、完成した形で降ってくる一答というやつだ。
思いついたことを言いたいという気持ちもまだ残っていたのだ。
「それじゃ、すり……」
「あのっ」
裏返った声で、今まさに俺を指名しようとした司会をさえぎり、会議室の後ろで手を挙げた女性がいた。
ばつが悪そうにうつむいている彼女は、比較的最近この界隈にやってきた『とら子』というプレイヤーだ。大喜利会にも積極的に参加して大会では結果を残しているようで、若手の注目株らしい。
俺も会の最初の方に客席から彼女の大喜利を見たが、ちまちまとお題をつつきまわすような小賢しい回答をする奴という印象だった。
苛ついて内心で舌打ちした。彼女もまた先ほど横に並んでいた回答者の一人だが、だからといって会の進行を止める権限などない。トイレなら黙って勝手に行け。俺の渾身の回答を邪魔するな!
男はこちらに一瞥をくれてから、彼女の方に向き直った。
「とら子さん、なん」
パンと鋭い破裂音が鳴り響いた。
男はその続きを口にすることができなかった。
糸が切れた人形のようにその体は崩れ落ち、顔面がリノリウムの床に叩きつけられた。鼻の骨の潰れる音が響いた。
痙攣する彼の頭から流れ出た血が広がっていく。それをのんびり眺めている余裕など、誰にもなかったにちがいない。
「これ以上、指名はさせません」
とら子が片手で構えたピストルの銃口から、硝煙がたちのぼっていた。彼女の声は小さかったが、それでも静まりかえった室内の全員の耳に届いているだろう。
俺は動けなかった。たった今までそこで喋っていた男の命と共に、奇跡の一答もあっけなく頭の中から吹き飛んでしまっていた。
「火器厳禁だろ」
やっと口にした一言がそれだった。動揺の中で大喜利プレイヤーとしての本能が少しの諧謔をそこに含ませたが、当然誰も笑わない。
「どうして殺した」
「勝つためです」
平坦にとら子は答えた。
「どうしてか分かりませんが……主催を殺した上に一答して帰ろうとするあなたを見て、思ったんです。これからも大喜利を続けていくのであれば、今日この場で、どんな手を使ってでもあなたに勝たなければならないと」
「だったら俺を撃ち殺せばよかったんじゃねえのか?」
「他の参加者の回答を暴力で妨害するのはマナー違反です。それに、あなたに『負けた』と思わせなければ意味がありません」
彼女の目は真っ黒に輝いていた。
休日にやる軽いゲームやスポーツであっても、なんらかの勝負の世界に身を置いている者は、誰でも他人のこういう目と相対したことがあるはずだ。みっともなく勝利にこだわる闘争心を湧き上がらせる一方、無駄な焦燥に振り回されることのない静けさをも湛えた目。
人は「勝ちたい」ではなく「勝たなければいけない」と確信したとき、自身をそのように動かそうとする大きな力に対して一種のあきらめを抱き、その達成のために行動することがある。それが真に執念と呼ばれるものだ。
しかし。
「残念だったな」
「…………」
「指名役が死んだ今、回答が出せないのはお前も一緒だろ? そして俺はすでに一答していて、お前はゼロ。つまり勝つ可能性もゼロってわけだ。……馬鹿な奴だ。司会を殺したりせず素直に答えを出しておけば、逆転の目はあったかもしれないのにな」
もっとも実際そうなっていたとしても、こっちが用意してた回答に勝てたとは思えないけどな、と俺は内心で呟いた。
とら子はしばらく黙っていたが、突然くくっと冷ややかな笑いを漏らした。
「指名なら、すでにされました」
「は?」
思わず素っ頓狂な声が出た。
こいつはなにをわけの分からないことを言っているのだろう。だいたいこの女は、仮に指されたとしても出すための回答を用意していなかったはずで……。
そこまで考えて、俺は息を呑んだ。
そうだ。こいつはさっき、間違いなく手を挙げていたじゃないか。そして、司会が『とら子さん、なん』まで言ったところで引き金を引き、頭を撃ち抜いた。
手を挙げ、指名され、答える。何度考え直しても否定のしようがない。明らかに彼女はルールを遵守し、正しい手順に則って最後の一答を出したのだ。
思い返してみれば、彼女は手を挙げるとき「あのっ」と声を出していた。ささいなことのようだが、もちろんあれも計算の内だったのだろう。いかにもばつが悪そうに、会の進行を止めてしまう個人的な用事を申し出るような言い方をわざとすることで、最初に自分を指名するように仕向けた!
「まさか、こんなに堂々と模倣してくるとはな」
「かぶせ? ああ、これのこと」とら子はピストルを振ってみせてから、ポケットにしまい込んだ。「流れを読んでやったまでです」
自分だけを指した後で司会者が死ねば、他の者は回答が出せなくなり勝てる。大喜利プレイヤーなら誰でも一度は考えたことがあるだろう。それもまた最も単純な必勝法の一つといえた。
「一問一答ずつの勝負に持ち込まれたってわけか」
俺は主催者を、彼女は司会者を殺した。これ以上はなにも起こらない。あとは客席の審査によって、この二つの殺人のどちらかの勝ちが決するだけだ。
「つまり……主催の殺害と司会の殺害、どっちの方が面白かったかってことになるな」
だとすればこの勝負、俺に分がある。
司会は大喜利の試合に対して権限を持ち、回答に対する反応などで場の印象を左右することもある、いわば大喜利プレイヤーにとっては直接の利害関係がある存在だ。その司会を殺す行為は意図が前面に出すぎており、面白みに欠けるはず。
一方、会の主催を殺す行為はナンセンスだ。現にあの男も『主催を殺してなんになる』と叫んでいたじゃないか。司会を殺す行為が多少なりともなにかになってしまうということを考えれば、ここにはハッキリと面白さに差がある。
俺は勝ちを確信していた。
だがまたしても、とら子は笑った。隠しきれない嘲りを表して。あるいは、いっそ憐れむように眉をひそめて。
「なにを馬鹿なこと言ってるんですか? すり美さん」
「なんだと……」
「ベテランが聞いて呆れますね。ここは大喜利会で、わたしたちがやっているのは『大喜利』ですよ」
「そんなことは、お前みたいな新参に言われなくても──」
「勝つのは、お題に沿った答えをした方に決まってるじゃないですか」
思わず言葉を失った。
スクリーンに表示された現在のお題は、『満腹だと人権がなくなる世界でありそうなこと』──彼女の言葉の意味するところは、すぐに理解できた。
とてもシンプルな話だ。このお題で、殺人が『お題に沿ったフィジカル回答』になる条件が一つだけある。
つまり、殺した相手の胃に食物が詰まっていた方が勝つ。
どんな手を使ってでも勝たなければならないと、とら子はあの目で俺に言った。それは同時に、
「受けて立ってやる」
俺は立ち上がって、自分が手にかけた方の死体のところへ近づいていった。
今や俺の方も、彼女に勝ちたいと強く思うようになっていた。新参に挑発され、古参として負けるわけにはいかないというプライドの問題か、それとも同じ女性としての対抗心なのか。
いや、根拠なんてどうでもいい。主催を力まかせに殴りつけていたときは、大喜利で勝とうなどという気持ちはみじんも残っていなかった。そのとき体に満ちていたのは、なにかあいまいなものに対する激しい苛立ちや怒りだけ。それが今は、まぎれもなく「勝ちたい」という気持ちに変わっているのだ。しかもさっきまでの漠然とした思いではなく、はっきりと「こいつに勝ちたい」という気持ち。
真剣勝負というものはいつも、当事者にしか分からないレベルで展開される。
俺は主催を殺して大喜利から逃げたあげく、その行動によって勝ちが近づいたと諭されるや戻ってきて、最後の一答を発表しようとした。そのような行為が許せなかったとら子は、対等な立場から叩き潰すために自身も司会を殺した。
もし俺が勝った場合「人殺しといて勝ったも負けたもない」と言われるだろうし、この言葉は負けた場合に自分を守る言い訳にも使えてしまう。しかし勝った側も人を殺していて、人殺し同士の勝負であればこんなことは言えなくなるということだ。
他人と同じルールの次元から逸脱してしまった俺を、あの女は逸脱によって追いかけてきたのだ。「どうしてかは分からないが、勝たなければならない」というだけの理由で。
横たわる主催の死体を見下ろす。少しだけためらったが、傍らに捨ててあった回答の破片を手に取った。
これでこいつの腹をかっさばいて、胃を取り出して中を見せる。あるいは空っぽかもしれないが、とにかくやってみなければ始まらない。少しでも勝てる確率があるならば賭けてみたい。
そこで俺はいったん顔を上げて、彼女の姿を探した。
同じように死体の胃を取り出そうとしているだろうか?
「とら子……」
彼女は司会者の死体のそばにいた。
その場にうずくまってなにかをしているようだった。当然、そいつの腹の中を探っているのだろうと思った。
だが──おもむろに立ち上がったとき、その手にはホワイトボードが握られていた。しかもオモテ面を自らの方に向け、そこに書かれた内容を隠すように。
それを見た瞬間、すべてを悟った。
「そんな……」
俺の撲殺にかぶせてとら子が銃殺し、殺人同士のフィジカル回答勝負になったというのは、こちらが勝手にそう解釈していただけに過ぎない。指名されてから今に至るまで、全ては回答の前振りだったのだ。
お題を見るように誘導したのも、俺の注意を死体の方に向けるため。その間に彼女も司会者のところまで行って、死体を検分するふりをしながら、ホワイトボードに回答を書き上げた。
置けと指示されたペンの代わりに、床にあふれたドス黒い血をインクにして。
やめろ──!
そう叫んだつもりだった。しかし、どういうわけか声が出なかった。あるいはそれは、人の回答を邪魔してはならないという大喜利プレイヤーの矜持かもしれなかった。
満腹だと人権がなくなる世界でありそうなこと。とら子はボードを客席に向けてオモテ返しながら、声を張った。
「晴れた日の公園にゲロ吐きながらうんこ漏らしてるおじさんがいて、失ってるのか取り戻してるのか誰にも分からなかった!!」
皆、彼女の方を見ていた。
ホワイトボードに反射的に彼らの目は吸い寄せられたものの、起こったことを理解するまでにはもう少し時間が必要だったらしい。
「────」
誰かが控えめに手を拍った。二人三人とそれは波及していき、まもなく会議室中を大音響が満たした。拍手笑いですらない純粋な拍手を彼らはいつまでも鳴らし続けた。長く続いた争いが終わり、自分たちの正義が証明されたことを称える市民たちのように。
俺は床にへたり込んだ。
どちらが勝ったか考えるまでもない。
ゼロ答と一答で、ゼロ答の者が勝つことは絶対にありえないのだから。
とら子がやってきて俺を見下ろしている。
彼女が司会を殺して指名を妨げたのは、同じ回答数の勝負に持ち込むためだと思っていた。だが実際は、対等に競っていると思わせた上で必敗を味わわせるのが目的だったのだろう。
相手を叩きのめす方法としてはこれ以上ない。テニスの試合を相撲だと思い込まされて、ぶつかり稽古をしてからまわしでコートに来てみたら、相手だけラケットを持っていてサーブを全球決められたようなみじめな気持ちだった。
真っ正面から叩き潰してもらえるなどということ自体、甘ったれた期待だったのだ。
「俺の負けだ。最後の回答の意味こそよく分からなかったが、とにかく完敗だ」
「…………」
「けど、これでお前は本当に満足なのか? この勝ちはお前にとって意味があったのか?」
単なる負け惜しみでもあり、もちろん自分が言えたことではないが、あえて尋ねたかった。
自分は必勝に飛びついた。彼女は必勝を利用した。しかしそもそも必勝とはなにか。ゲームの中に自分しかいない状況を作り出し、そこで行われているなにもかもを茶番にしてしまうことではないのか。
いや、勝負はそもそも茶番だ。適当なルールで誰かを勝ちと決めて、残りを負けとするだけのこと。勝ち負けにこだわっても、勝ち負けしか存在しないどこかに行き着くだけ。そんなことを考えて、いつからか俺は健全に勝ちたいという気持ちをなくした。けれどもさっき死体を引き裂こうとしたときだけは、明らかに異なる衝動に突き動かされて、なにかを得ようとしていた。
だが俺は負けた。だから、どんな手を使ってでも勝たなければならないと言って実際に勝った彼女が、その勝ちを今どんなふうに感じているのか知りたかった。
「なにか勘違いしてるようですね」
とら子はあくまでも冷ややかに答えた。
「わたしは、大喜利であなたに勝ったんじゃありません。大喜利をあなたに勝たせたんです。この勝負は最初から最後まで、すり美v.s.大喜利だったんですよ」
「ああ──」
その言葉で、すべてに合点がいった。
最後に起こった拍手を思い出す。あれはこの女の回答を賞賛して勝利を称えるものではなく、大喜利が勝ったことに対する喝采だった。
十年以上大喜利をやってきた。勝ち負けに一喜一憂し、勝つために必死になってやっていた頃もあった。それなのに、大喜利に負けて帰る日がくるとは思いもしなかった。
どこでまちがってしまったのだろう?
主催を殺したことか? いや、それは最後の部分に過ぎない。もっと前のどこかで俺はまちがえて、今日までまちがった歩みを続けてきたのかもしれない。
せめてもの弔いとして、二体の死体の顔にホワイトボードを載せ、俺は地域区民センターを出た。とら子も一歩下がってついてきた。
それから俺たちはあてもなく歩き続け、その間お互いに言葉を交わすことは全くなかった。ただし日が没する頃、彼女は一言だけなにかを呟いたように思う。俺が振り返ると、すでにその後ろ姿は角を曲がって消えていくところだった。
なお会の様子は全編にわたって撮影されており、後で動画サイトにアップされた。
そこには二人の人間による殺人の様子が映っていたが、事前の本人たちの希望の通り二人とも顔が丁寧に編集で隠されていたため、犯人が特定されるには至らなかった。
動画の編集を担当した者は警察の取り調べに対して、疲れた表情で以下のように述べたという。
「後から顔の部分だけ修正する作業は本当に大変でやりたくないので、身バレが嫌な人はマスクやサングラスを着けてくるよう呼びかけていたんです。それなのに、どうしてこんなことに……」
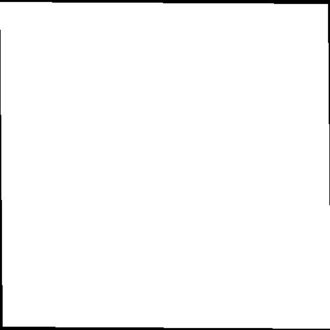

コメント