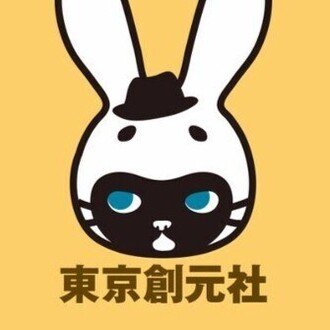【6月12日刊行】鯨井久志/ラヴァンヤ・ラクシュミナラヤン『頂点都市』(新井なゆり訳、創元SF文庫)解説[全文]
本稿は2025年6月12日刊行の『頂点都市』巻末解説を転載したものです。(編集部)
本書は、インドの作家ラヴァンヤ・ラクシュミナラヤンによる連作短編集The Ten Percent Thiefの全訳である。ローカス賞およびアーサー・C・クラーク賞の候補作にも選出されている。
大規模な気候変動によって資源が欠乏し、国家そのものが消滅した近未来。〈ベル機構〉なる統治組織によって、人びとはその能力に応じて上位九〇%の「ヴァーチャル民」と、下位一〇%の「アナログ民」とにランク付けされている。ヴァーチャル民とアナログ民とは、住む地域が区別されているだけではなく、アクセスできるテクノロジーにも差がある。ヴァーチャル民はVRを駆使した最新鋭の技術に囲まれ、効率的で便利な生活を送ることができるが、アナログ民はいたって物理的な現実(つまり〝アナログ〞だ)での暮らしを余儀なくされる。いわば本書は、近未来を舞台にしたディストピアSFのひとつとして数えることができるだろう。
本書の特色を挙げるとすれば、それは大きく二点ある。まずは連作短編集という形式で描かれたディストピア小説であること。そして、インド発のSF作品であること。
〈ベル機構〉が提示する思想、それは完全なる能力主義だ。連作の二作目「ベッドの下の怪物」に掲げられた『ベル人権憲章』前文には、「能力本位の普遍的な体制によって、社会における個人の価値が決まるのだ。/能力主義的技術統治。/われわれこそが人類の未来だ」とある。つまり、本書で描かれる世界は、社会における個人の価値=社会にもたらす生産性、という図式の価値観に貫かれたものだ。〈ベル機構〉は個人の社会への貢献をスコア化し、それによって個人の社会でのランク付けがなされる仕組みになっている。
こう書けば、それぞれの能力が反映されるのだから、極めて理想的/効率的な社会なのでは? と思う方もいるかもしれない。確かに現実でも、企業組織において成果に応じた評価がなされ、それが賃金や昇進といった形で反映されることは、そう珍しくない。それによって生まれる適度な競争は、結果として企業全体における効率の追求に結びつくかもしれない。だが、それが社会全体にまで拡大されるとどうなるか?
生まれつきの能力の差、あるいは資質によって、どうしても〝生産的〞になれない人もいる。例えば、持病によってフルタイムで働けないという人。持病でなくても、例えば女性であれば妊娠の期間は、従来通りの業務をこなすことは、一時的にではあれど、難しいだろう。そして、生まれ持った知的能力の差というものは、どうしても存在する。〈ベル機構〉は、すべての人間を〝生産性〞というひとつの尺度でもって判定し、その鋳型にはまらない者は社会の外へ「アナログ民」として放逐することで、社会全体を維持しようとする。会社でいえば解雇だ。だが、社会において「解雇」されるということはどういうことか? 本書の世界においては、見せ物にされ、人間としての尊厳をも奪われ、物理的にも疎外される。臓器工場に送られて上位民の〝役に立つ〞こともありうるという有様だ。
現実の社会においては、例えば日本国憲法に「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と記されているように(実態はともかく名目上は)、人権は保障され、生活もある程度保障されている。だが、そんなものもなく、ただ放り出されて悲惨な生活を送る下位一〇%の人びとが常に存在する社会はどうなるか無論、不満が溜まり、あわよくば社会体制の転覆を試みようとする。本書でも、「アナログ民」たちによるレジスタンス運動が描かれる。
しんどいのは下位民たちだけではない。「ヴァーチャル民」のなかでも、上位二〇%の階級と、その下の七〇%の中間民との間には確固たる線引きがなされている。結果、上位民は日々降格の恐怖と戦いながら生産性の向上に努め、七〇%の中間民は何とか這い上がろうと、己の尊厳を押し殺してでも〈ベル機構〉に媚びへつらい、取り入ろうとする。
先ほど社会体制の転覆に触れたが、むろん〈ベル機構〉側でもそうした各階層ごとの不満は予測しているので、徹底したプロパガンダを展開し、〈ベル機構〉が理想とする生産性第一の価値基準を人びとへ刷り込もうとする。そして、その価値基準を絶対とする統治体制への忠誠心も、〈ベル機構〉側が測定するスコアの項目に含まれている。「ベッドの下の怪物」で、視点人物であるジョンは上位二割民への昇進を打診されるが、アナログ民出身という出自から社会への忠誠心に疑念を抱かれ、思想面のみならず趣味にまで踏み込む厳しい面接を受ける。この社会の中でのしあがろうとするには、成果を出すだけでなく、〈ベル機構〉が掲げる思想への忠誠を誓い、全身を「生産性の奴隷」として差し出さなければならないのだ。
こうした「生産性第一主義」に貫かれた全体主義社会を、本書は連作短編集という形を取って、さまざまな視点からモザイク状に描き出す。例えば、生産性の観点から自然分娩を否定され、葛藤するインフルエンサー。巧妙に価値基準を「修正」していくVRテクノロジー。上位民の子どもたちへ「アナログ」の暮らしを紹介する仕事に従事するも、自らの出自や家族とのジレンマに苦しむツアーガイド。元アナログ民ゆえ、補助としてのVR技術を利用できないものの、養親らの支えもあり、音楽の才能を開花させていく少女。アナログ/ヴァーチャルそれぞれの階層の立場から〈ベル機構〉が統治する社会のあり方が描かれるうちに、それぞれの問題点や人びとの苦悩、戦いが、読み手の中に多角的な結晶として抽出され、澱のように沈殿していく。見事な構成だ。
現実の社会においても、生産性は大きなテーマだ。加速する資本主義社会において、どこまでを温存し、どこからを切り捨てるか。例えば、日本においては高齢者の医療費が増加し、財政面での立て直しの議論が活発になっている。高額療養費制度の負担上限額引き上げが、世論の反発によって一旦棚上げになったのも記憶に新しい。それだけでなく、「同性愛者は生産性がない」という政治家の発言や、生活保護申請者への悪質な水際対策も、昨今話題を呼んだ。本書はそういった観点からも、SFという一種の思考実験を通して、読者に現在進行形の社会問題への視座をもたらしてくれるだろう。
そして、「自己責任」という言葉がたびたび聞かれる世の中ではあるが、はたしてどこまでがその人の「責任」なのか? という問題にも、本書は切り込む。つまり、格差の再生産の問題だ。
〈ベル機構〉のネーミングの由来となったであろう「ベル曲線 Bell curve」とは、もともと正規分布を描く曲線が教会の鐘(ベル)のような形をしているところから名付けられたものだが、ラクシュミナラヤンは、リチャード・ハーンスタインとチャールズ・マレーによるThe Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life(1994)という本も念頭に置いているようだ。全米でベストセラーになったこの本は、「黒色人種は生得的に知能が低い」という主張を行ったとして批判にさらされたのだが(この解釈にも議論がある。なお、ラクシュミナラヤンは同書の主張に賛同していない)、内容としては知能の階層化とその固定化を、IQを指標として論じたものだ。要するに、頭のいい人たちの生む子どもは頭がいいことが多いし、頭のいい人は社会で稼ぎの多い職につくことが多く、子どもへの教育費を多く掛けることができる。その逆も然り。よって、世代を経るごとにコミュニティごとの知能格差が生まれ、それは再生産され、固定化されていく……という理屈である。単純な図式ではあるが、文化資本の問題や「親ガチャ」という言葉の流行があったように、現在の経済的格差は「生まれた時点での埋められない格差」に原因の一端があるのではないか、という考え方が広まってきているのも事実だ。
本書では、アナログ民の出自ゆえに差別を受けたり、不遇を被る人物が多く登場する。アナログ民に生まれた子どもは十分な教育を受けられず、テクノロジーの恩恵もない。よって、そこから這い上がるのは、中間民の子どもが上位民になるよりも数段難しい。そういった社会構造が、本書では描写されている。
また、インドにはカースト制度が古来より存在し、いまもなお継続している。おそらく作者はその歪さも踏まえたうえで、テクノロジーが格差の再生産に拍車を掛ける未来を描いたのであろう。本書の舞台となる「頂点都市」は、かつてのインドの都市ベンガルールの成れの果てである。インドにおけるIT産業の中心地として現在は知られ、作者ラクシュミナラヤンの故郷でもある都市に起こるかもしれないディストピア的ヴィジョンを、本書は表現したのだともいえる。
インドSFはまだまだ本邦では紹介が進んでいるとは言えないが、文学研究者の難波美和子によると、二〇〇〇年ごろから英語での文学作品の出版点数の増大に伴い、各種ジャンル小説も多く書かれ、ベストセラーとなった作品もあるという(「最新インドSF状況」、〈SFマガジン〉二〇二三年十月号)。英米の賞に絡む作家も登場しており、例えば短編にいくつか邦訳のあるヴァンダナ・シンや、『マシンフッド宣言』(金子浩訳、ハヤカワ文庫SF)のS・B・ディヴィヤはインド出身だ。未邦訳作家では、スリランカ出身ではあるが、Vajra Chandrasekeraが長編The Saint of Bright Doorsで二〇二四年にネビュラ賞・ローカス賞を受賞するなど、めざましい活躍を見せている。神話や歴史をモチーフにした作品も多く、本書を嚆矢にさらなる紹介が進むことを願うばかりだ。
最後になったが、作者の紹介を。ラヴァンヤ・ラクシュミナラヤンはインド・バンガロール(現ベンガルール)生まれ。現在もインドを拠点に活動する。大学卒業後はビデオゲームデザイナーとして活動し、Mafia Wars やFarmVille などの製作に携わった。本書は二〇二〇年にAnalog/Virtual and Other Simulations of Your Futureとしてインドで出版されたのち、The Ten Percent Thiefと改題・改稿のうえ、二〇二三年にイギリスでも出版された。冒頭にも述べたが、本書はローカス賞およびアーサー・C・クラーク賞の候補作になったほか、インドの文学賞タイムズ・オブ・インディア・オーサー賞とバレー・オブ・ワーズ賞を受賞している。昨年十一月に刊行された最新長編Interstellar MegaChefは、食をテーマにした宇宙規模の物語(タイトルにあるInterstellar MegaChefは、銀河系でもっとも権威のある料理コンテストの名前)とのこと。
■鯨井久志(くじらい・ひさし)
書評家・翻訳家。1996年大阪府生まれ。〈S-Fマガジン〉などで書評やインタビュー、翻訳を担当。訳書にスラデック『チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク』がある。