インドネシア語が習得しやすく感じる要因として思い当たること
インドネシア語は習得が容易と言われていて、その要因として文法構造が簡単なこと、語彙が少なめなこと、発音が日本人にとって簡単なことがよくあげられます。
私はそれ以外に、インドネシア語の発音や語感が日本人にとってなぜかそれらしい意味を持って聞こえるという要因をあげたいです。
マニアックな話で、インドネシアに長期間滞在している人にしか通じないかもしれませんが、その場合は申し訳ありません。
根拠があいまいなまま、個人的にはそう感じるんですよね的な話が多いです。
表意文字に慣れ親しむことの弊害
日本人の外国語習得が難しいのは、漢字を中心とした表意文字のせいなのではないかと私は考えています。
全員が全員そうではないと思いますが、私の場合、馴染みのない日本語を聞くと漢字をイメージし、その漢字の意味によって言葉の意味を理解しようと脳が動くタイプです。忖度とか。
おそらくそのせいで、余計な翻訳作業や変換プロセスが入り、言語の処理能力が落ちるのではないかと思っています。
表音文字の文化で育った人は、素直に音声や語感から意味をイメージするくせがついていると思いますし、音への集中力も高いのではないでしょうか。
聞こえた言葉やアクセントを、そのまま再現する能力も高いと思います。
アメリカに最初に駐在したとき、ESL(English as second language)でいろいろな国から来た生徒と一緒に英語を勉強しました。
お国訛りは誰しもありましたが、東欧や南米からナニーとしてやってきた若い女性たちが、先生の言う言葉をきれいにリピートするのに驚いたことがあります。
総合的な英語力は当時の私よりも低かったと思います。
日本人でも美空ひばりはそうだったと聞きます。彼女の場合は天才的な音感の持ち主だったので特別かもしれませんが、全く意味が分からないまま外国人が歌っている歌をそのまま再現できたそうです。
私も音源を聞いたことがありますが、無茶苦茶英語の発音がきれいで驚きました。完全にネイティブの発音です。
インドネシア語は表音文字のまま意味が入ってきやすい
これは私だけではなく、日本人によくある話のようです。
理由はよくわからないのですが、もしかすると日本の大和言葉(漢字が入ってくる前からある言葉)に近いのかもしれないと思いました。
日本語でも大和言葉は無理やり漢字を当てはめてはいますが表音文字です。漢字でいうと音読みというやつですね。
英語を聞くときは表音文字の脳回路が働かないのに、インドネシア語を聞くとなぜか聞こえた音のまま意味が頭に浮かんでくる感覚があります。
英語をしゃべるときに動かす脳と、インドネシア語をしゃべるときに動かす脳が違っていて、インドネシア語は日本語をしゃべっているのに近い自然な感覚があるのです。
語源がインドネシア語ではないかという説のある言葉を例にみなさんがどう感じるか試してみます。
一つ目は「あんぽんたん」。
頭が悪いバカな人間というイメージですよね。
これはもともとオランダの商船に人夫として乗っていたインドネシア人が、オランダ人や中国人にしかられて「あんぽん とぅあん(すいませんご主人様の意)」と何度も頭を下げて謝っていた様子を見た日本人がバカにして言い始めたと言われています。
お前はあのバカみたいに何度も謝っているアンポンタンな奴だ、というわけです。
言葉の語感と、体の動きのイメージが一致する感覚はないでしょうか。
二つ目は「のるかそるか」。
うまくいくか失敗するかの分かれ目といったイメージですよね。
インドネシア語では、ノルガが地獄、スルガが天国の意味です。
まさに、天国にいくか地獄にいくかの分かれ目にいるという感覚です。
これも日本語で無理やり「のる」と「そる」にそれらしい意味を与えているのですが、インドネシア語の方が合っている感覚が私はします。
三つ目は「長い」
インドネシア語でナガは大蛇のこと。大きなへびは長いから渡来人がナガのようだと言っているうちに長いという言葉になった可能性があります。
四つ目は「ちゃんぷるー」
これは沖縄の言葉と思っている人も多いと思いますが、元はインドネシア語です。
ご機嫌な感じで何かを混ぜている雰囲気が語感から感じられないですか?私だけかですかね。
ちゃんぽんにするという言葉を使いなれているせいなのかもしれません。
他に日本人の駐在員同士で会話に自然に出てくるインドネシア語は、「チョバ」試してみると言いたい時に「チョバしてみたら?」、といった感じで使います。
あるいは「ボン」お会計ですね。「もうボンしよう」とか。他に「バギバギ」。割り勘でという時に「バギバギで」と言います。「チョパット」早くも使います。「チョパットやっちゃって」みたいな感じです。
もうキリがないですね。
インドネシア語を学ぶと脳が他の言語よりインドネシア語を優先する
私は学生時代に第一外国語を中国語にし、中国にホームステイしたり、バックパッカーで中国を何度も旅していましたので、当時結構中国語がしゃべれました。
ちなみにゼミは現代中国法です。
これがインドネシア語を勉強したとたん、中国語をしゃべろうとするとインドネシア語しか出てこなくなります。もちろん中国語を使わず忘れてしまっていたというのはあると思います。
中国に仕事で出張し、タクシーに乗ってさあ中国語をしゃべろうと思ったらインドネシア語しか出てこずに困りました。
私の妻の場合は、英語が追い出されてインドネシア語しかしゃべれなくなっていました。英語をしゃべろうとするとインドネシア語が出てきてしまうらしいのです。
インドネシア語は日本語からインドネシア語に翻訳する脳のプロセスなく、日本語をしゃべるような感覚で自然と言葉が出てくる感覚があります。
私はインドネシアにいるとき、日本の大和言葉がインドネシア周辺で生活していた海洋民族に由来したものではないかと勝手に想像し、いろいろな本を読んで調べたことがあります。
日本に渡来した民族の一部はインドネシアから来たと言われています。
風習に関しては、例えば「ふんどし」は海洋民族由来だったり影響を受けた形跡がありましたが、言語に関しては一つもそのような説を唱えている人はいませんでした。
これを知ったときは本当にがっかりしました。と同時に、なんでこんなにインドネシア語がしゃべりやすいのか謎が深まりました。
まとめ
今回はインドネシアに住んだことがあるか、インドネシア語を学習したことがある人にしか通じない話だったと思います。どうも申し訳ありません。
何を言っているのかさっぱり感覚的につかめないという方が多かったかも知れません。大変申し訳ありませんでした。
インドネシア語の不思議な感覚をどうしてもお伝えしたく書きました。
以上

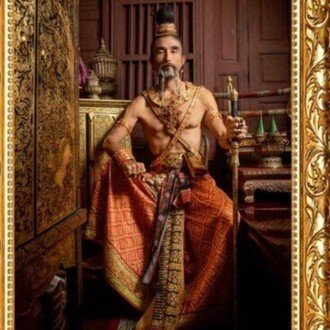
コメント
6インドネシア語が属するオーストロネシア語族と日本語の関係を研究している研究者には崎山理先生がいらっしゃいます。『オーストロネシア語族と日本語の系統関係』等の論文がネットで読めます。私は今台湾在住で、台湾のオーストロネシア語の一つ、アミ語を勉強中ですが、崎山先生の論文も参考にさせてもらっております。台湾はかつて日本が統治していた場所ですから、日本語からアミ語に入った単語も多いのですが、固有のアミ語なのに日本語のように感じるものが多いですね。どおりで台湾のオーストロネシア語系民族の日本語は日本人の日本語と全く変わるところがなく、漢族系台湾人の日本語とは格段の違いがありますね。
アミ族の人たちは太平洋戦争の時に高砂義勇隊としてインドネシアに来てます。中村輝男が有名です
インドネシアの現地人と言葉が近く、結構通じたらしいです。台湾の少数民族の言語は、オーストロネシア語のもっとも原型に近いと聞いたことがあります。
アミ語と日本語に近い言葉があるというのは面白いですね。論文を探して読んでみます。
まさにまさに、本当に似たような言葉がたくさんありますよね。あと気付いたのは、言葉の繰り返しですね。サマサマ、チンチン(指輪ですかね)、スス。日本語の擬音語、擬態語なんかに似ているものが多々ありますよね。DUOLINGOで勉強されたようですね、私も近い将来にそちらに移って隠居するつもりなので、勉強しようかと思っていました。
DUOLINGO良さそうなので試してみます。温泉のNOTEを参考に私も全島にある温泉巡りしようかと思案中。素晴らしいNOTE ありがとうございます。
繰り返し言葉は本当に興味深いですね。わたしも一時繰り返し言葉を集めていた時期があります。何か法則性があったり、日本語と似たところがあるんじゃないかと思ったのですが、これだというのがなく、中途半端に終わってしまっています。
デュオリンゴは無料とは思えないほどしっかりしています。ある程度文法もカバーしていますが、どちらかというと語彙をのばすのに使うのがいいかもしれません。
温泉は野湯に近いものが多いですが、その分泉質は最高で日本以上です。