課題提起に“嫌ならやるな”──自治体システム標準化ヒアリングで威圧的な対応
<要約>
5月に実施された自治体システム標準化ヒアリングでは、デジタル庁など国側が事業者に威圧的な質問を浴びせ、SNSで批判が噴出した。料金設定については「強気な価格だ」と決めつけて追及し、公共SaaSへの懸念を示した事業者には「メリットがないならやらなくてよい」と突き放す姿勢を見せた。投資回収期間など企業機密の開示を迫る場面もあり、価格圧迫に利用される懸念から独占禁止法上のリスクまで指摘されている。運用コスト3割削減をめぐっては「貴社がコミットしたのではないか」と詰問し、事業者を弁明に追い込む一幕もあった。一方、国はモダン化や公共SaaSを万能の“銀の弾丸”と位置づけるものの、効果検証や現場負担への配慮は後回しのまま。
全国1,741自治体を巻き込む国家プロジェクトだからこそ、官民の信頼が揺らげば計画全体が瓦解しかねない――今こそ対立ではなく「共創」のテーブルを再構築しなければ、デジタル社会の足場そのものが崩れる。
政策協力者への対応に問題指摘
自治体システムの標準化・ガバメントクラウド移行を巡り、デジタル庁や内閣官房などで構成するワーキングチームが5月に実施した事業者ヒアリングで、国側が威圧的で高圧的な質問を繰り返していたことが議事要旨で明らかになった。SNSでは「パワハラまがいだ」「建設的な対話になっていない」との指摘が出ている。
ヒアリングは、標準化対応により自治体の運用経費が大幅増加している問題の実態把握を目的に実施された。しかし、政策実現に協力している事業者に対し、国側が不適切な姿勢で臨んでいた実態が浮き彫りになった。
「嫌ならやるな」「事業方針は事業者が考えろ」の突き放し
特に問題視されているのは、事業者Bが公共SaaS推進における競争上の懸念を表明した際のワーキングチーム側の対応だ。
事業者側は「ガバメントクラウドは非常にセキュリティの高い強固なもの。その一方で現行DCの方が安価に提供できるところの方が多いと認識しており、価格差が生まれる可能性がある」(事業者B議事要旨)と合理的な課題を指摘。政策推進のためのインセンティブ設計を求めた。
これに対し国側は「事業方針を検討するのは、国ではなく、事業者ではないか」(事業者B議事要旨)、さらに「メリットがないと事業判断されるのであれば、ガバクラで公共SaaSをやらなくてもよいのではないか。推進する側として推進する気持ちはあるが、すべてガバクラを利用してほしいという意思で取り組んでいるわけではないので、ご理解をいただきたい」(事業者B議事要旨)と回答。
自らが推進する政策への協力を求めておきながら、事業者の建設的な懸念や提案に対してこのような対応を取る姿勢について、「政策責任の放棄」「共創の意思がない」といった批判の声が上がっている。
急にケンカ始まってるやんけ
— はちみつ(20) (@honeycomb_bnbn) June 2, 2025
あれだけ「理想とする公共SaaS」って言ってたのにw
最後はもはや逆ギレである。誰が言ったのだろうか pic.twitter.com/FoyaggrN1G
「強気な価格設定」連発で事業者を追及
このほか、議事要旨によると、ワーキングチームは事業者の料金設定について「強気な価格設定」という表現を繰り返し使用。「そういう強気な価格設定をしても大丈夫だと判断しているのはなぜか」(各社議事要旨)など、市場支配力の濫用を前提とした決めつけ的な質問を連発した。
バカげた質問 pic.twitter.com/QE9K10blxf
— はちみつ(20) (@honeycomb_bnbn) June 2, 2025
このほか、パートナ企業の価格決定についてもヒアリングがあり、自治体から「パートナー企業から『開発元から増額すると言われていますから』といって説明が終わってしまう」という声があることについて、国側が事業者Cに「貴社からはなんとかならないのか」と改善を求めた際、事業者は「我々が関与してしまうと法的に問題がある。そこまで関与するのは、厳しい」(事業者C議事要旨)と回答している。
これは独占禁止法上の再販売価格維持行為に該当する可能性があり、メーカーが販売店の価格設定に介入することは法的に禁止されている。SNSでは「法的にも商売としても、やってはいけない/できないことを、国が事業者にせっついてどうすんだ」との批判が上がっている。
政策を推進する立場にある国のワーキングチームが、こうした基本的な法的制約を理解していない姿勢は、民間事業者との適切な関係構築および正しい政策判断を困難にしかねない。
黄色は国(デジタル行財政改革会議)の質問で、水色が、民間事業者の回答です。法的にも商売としても、やってはいけない/できないことを、国が事業者にせっついてどうすんだ😭
— ふじた_🐱♨️💻雑用係 (@nfujita55a) June 2, 2025
国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会 関係者ヒアリング 事業者Chttps://t.co/yWPCCpGcAa pic.twitter.com/pWFUj2f8Ze
企業秘密を利用した価格圧迫の懸念
企業の内部情報を聞き出した上で、それを価格引き下げの材料として利用しようとする姿勢についても懸念の声が上がっている。
「社内の投資回収期間のルールは、何年ぐらいを想定されているか」(事業者C議事要旨)といった質問に対し、事業者が「申し訳ないが、企業の機密情報になるため、回答は遠慮させていただきたい」(事業者C議事要旨)と断った後も、投資回収に関する質問を重ねている。
最終的に「開発経費を利用料で回収している、ということか」「つまり、開発経費を利用料で回収している、ということか」(事業者C議事要旨)との追及で、「そのとおり。アプリケーションの開発に投資した分、その分を回収する前提で、新たな料金設定をしている」(事業者C議事要旨)という回答を引き出している。
投資回収は正当な企業活動だが、内部情報を材料にした価格圧迫は独占禁止法上の問題となる可能性もある。情報開示を求めること自体は調査の一環として理解できるが、その使い方については慎重な検討が必要だろう。
優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方
— kokumin_a (@kokumin_a) June 3, 2025
想定例「⑩ 取引の相手方から,社外秘である製造原価計算資料,労務管理関係資料等を提出させ,当該資料を分析し,「利益率が高いので値下げに応じられるはず」などと主張し,著しく低い納入価格を一方的に定めること。」https://t.co/nekz7QuNbO pic.twitter.com/mCtO9kgatc
「3割削減をコミットした」 詰問調の追及も
事業者Aに対する運用経費削減目標についての執拗な追及も行われていたようだ。ワーキングチーム側は「モダン化したら、クラウド利用料は下がるが、ソフトウェア利用料は下がらないと、3割削減は難しいのではないか。他方で、貴社は3割削減の実現についてコミットメントしたと思うが、どのように3割削減するのか」(事業者A議事要旨)と畳み掛けるように質問。
これに対し事業者側は「当社としては、3割削減にコミットしたというよりは、努力すると申し上げた」(事業者A議事要旨)と訂正する場面があった。国側が「コミットした」と決めつけて追及し、事業者が弁明を余儀なくされる構図は、対等な協議というよりも尋問に近い印象がある。
国では思いつかないから事業者を問い詰めてるのかな?
— はちみつ(20) (@honeycomb_bnbn) June 2, 2025
そしてその手法は東京都さんが否定していたようなきが・・・! pic.twitter.com/vfVsRoQkRY
この点については東京都が3割減のロードマップを国が提示すべきとして共同要請を5月に総務省に対して提示している。
公共SaaS政策の課題も浮き彫りに
今回の問題の背景には、国が推進するモダン化、公共SaaS政策の構造的課題がある。
ワーキングチームは、これまでに公開された資料から、今後、公共SaaSを運用経費削減の切り札として位置づけている一方、事業者側は「年単位での検討が必要」「具体的計画は未定」と慎重姿勢を示している。コスト削減効果の定量的根拠も示されておらず、事業者にはさらなる投資負担を強いる可能性が高い。
ある事業者関係者は「検証もせずにモダン化を銀の弾丸扱いしている。現場の実情を無視した政策ありきの姿勢だ」と批判。そのほか「公共SaaSで本当にコストが下がる根拠はどこにあるのか」「モダン化にさらに投資が必要なのにコスト削減って矛盾している」といった疑問の声が上がっている。
モダン化すれば必ずしも業務効率化につながるということではないと思います。
— 井上ひろき(ITゴリさん)@墨田区議会議員 (@gorisan_it) June 2, 2025
各業務に適合している仕様なのか、注意深く進める事が重要と考えてます。 https://t.co/SJWFxvC4SO
真の協力関係構築が急務
自治体システム標準化は、全国1741の市区町村及び47都道府県が対象となる国家的プロジェクト。その実現には国・事業者・自治体の三者が一体となった協力が不可欠だが、今回のような一方的な高圧的な姿勢が続けば、政策そのものの成功が危ぶまれる。
今後も公共サービスメッシュなど、さらなるシステム改善や機能拡充が続く可能性もあるが、現在のような対話不足や相互不信のまま進めば、同様の問題が繰り返される恐れが強い。例えば「共創プラットフォームへの事業者参加」などを通して三者が直接議論できるようにするなど、建設的な協働関係を築くための施策が必要になるだろう。
政策実現のために必要なのは、威圧や対立ではなく、ステークホルダー間の信頼関係に基づく真のパートナーシップだ。国には、対話の姿勢を根本から見直し、官民が共に課題解決に取り組める環境づくりが求められる。デジタル社会の基盤となる重要な政策だからこそ、その進め方も時代にふさわしいものであるべきだろう。
以上

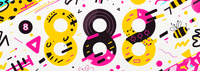

コメント