下読みのお仕事、或いは応募者の地獄
■まえがき
表立って『下読み』という人がその仕事について語る、というのはあんまりなくて、もしかすると業界的にはタブーなのかもしれないが、そこんところをアウトサイダーである俺はよく分かっていないので、こうして語ってしまうのである。昔、『小説新人賞はこうお獲り遊ばせ:下読み嬢の告白』(https://amzn.asia/d/iLWnZH9)という名著があったし、いいだろ。
大前提としての追記
いかん、これは書いておかねば。
どんな世界、分野、ジャンル、カテゴリーでも、そこにいる人間はぶっちゃけピンキリ。ある上澄みだけを掬いとったグループも、次第にピンとキリに分かれていくのが世の常だ。
俺は個人的に、可能な限り、いやそれ以上に、誠実に応募作と対峙してきたと思う。もし今後があるとしてもそのつもりである。それは自分も応募者・志望者だったからということが大きい。自分をピンとは言わないが少なくともキリではないと信じている。
だが、自分のことは自分にだけ通用する。見聞した範囲で色んなことを記していくが、見聞の範囲外で、思いも寄らぬキリが存在しているのかもしれない。残念ながらその可能性は否定できない。
もしあなたがそうした「キリ」とぶつかってしまったとしたら、お気の毒と言うしかない。すまん。だが、「ピン」であろうとする人間は、別に俺に限らず必ずいるし、むしろそちらの方が多いはずだ。
「ピン」にだって会える。そこは信じて欲しい。
■下読みってなに? どんなことするの?
「下読み」という言葉には、必要な資料を前もって一度読んでおくこと、という意味がある(サ変名詞)。そこから転じて、本選考の前に予備選考的にふるいをかけることも意味に含めるようになったのではないだろうか。
ほか、アナウンサーが本番前に原稿を再確認する、ということも「下読み」と呼ばれたりする。SNSでは、小説を書いているアマチュア作家が、「綿密な推敲をする前に、誰か他人に読んでもらってざっくり評価をもらうこと」を「下読み」と呼んでいるケースも見ている。
現在の文芸賞において、読者/応募者側が用いる「下読み」は、「一次審査を実際に行う担当者」という意味だろう。
面白いことに、この「下読み」はサ変じゃなくてただの名詞だな。今気付いた。
閑話休題。
一次審査は最初の行程だから、応募規定違反で選考対象外となったもの以外の、すべての作品が対象になる。一番数が多い状態だ。エンタメ系なので、多いところでは長編3000本も送られてくるのだし、この数を編集部員だけで、通常業務に加えてこなしていくのは大変だ。なので、まず審査を外注して数を減らすのだ。この外注先が「下読み」と呼ばれる、ということになる。
一回のサイクルで十本から二十本ほどの作品を読むことになるのが多いだろう。このひとつのサイクルを「一便」と呼んだりする。昔は原稿の紙束を郵送していたので、その名残だろうか。
一便の全てを読み、評価をして、編集部に送り返す。それが「下読み」の仕事だ。一作ごとに多少のコメントをつけたり、評価点を付けたりするが、その具体的なスタイルは賞ごとに異なるのでなんとも言えない。
通過させられるのは、だいたい受け持ち数の内「一割」くらいであることが多い。一便が10作なら一作しか通せない。狭き門なのだ。
稀に、一次審査からすべて、出版社/編集部の人間が読む、と豪語している賞があるが、それが「編集部員が読む」という意味なのだとしたら、気の毒なレベルで大変だな、と正直思う。普段通りの仕事をしつつ、さらに応募作を読むって地獄では(過労死的な意味で)。
ちなみになのだが、「中の人」として自身を「下読み」と名乗ったり、関係者からそう呼ばれたりしたことはないです。
■下読みなんてアルバイトがやってるんだろ?
……という話は(恨み節として)よく聞きますね。その期間だけの短期の仕事、臨時の雇われという意味ではアルバイトかもしれないが、実際にこの仕事を請け負っているのは、
・編集プロダクション
・フリー編集者/ライター
・書評家/評論家
・小説家(デビューしたての人も含む)
といった辺り。ただ読むだけではなく、評価までしなければならないので、そこらの学生アルバイトにやらせることはない。仕事上の信頼関係が既に主催側との間に出来ている人か、そういう実績のある人からの「この人なら出来る」という紹介でないと発注は来ない。たまーに、『下読みをしたいがどうすればいいか』という人がいるが、そんなわけで「既にこの業界で実績がある人」じゃないとほぼ無理です。
編プロはアルバイト従業員にやらせているかもしれないが、会社として請ける仕事なのだから能力がない人間には任せないし、やらせられる人材が内部いないなら、人を探してさらに外注(孫請け)することになる。
自分の場合は、ライターとして活動しつつ過去には商業小説の経験もあるということで白羽の矢が立った。
昔は、その賞でデビューした作家の最初の仕事は、翌年の同じ賞での一次審査、という流れがあったが、今はそうでもないらしい?(それより執筆優先という話も聞く)
これも昔の話だが、エンタメ文芸のジャンルで、書評家のコラムか何かで、「自分の出身大学、出身サークルの後輩でめぼしい奴に声をかけて、下読みの仕事をさせていた」という内容を読んだ記憶がある。「下読みはアルバイトがやっている」という誤解の大元は、案外こういう与太話かもしれない。念のため付け加えると、くだんの「下読みさせられた大学生」たちは後年多くが作家デビューしたということだ。
■じゃあ「下読みガチャ」はなんで起きる?
確かに、公募で落ちた作品を、別の賞へ(または同じ賞へ再度)応募したら上位選考まで残った、という話を聞くことがある。いやちょっと待って。俺自身が別の賞で落選した作品を、右から左でソノラマ文庫大賞に送って受賞したんだった。
そういう落選もあることから、近年では「下読みする人間の好みと相性の問題」として「下読みガチャ」と称していることは承知している。
これについては、『すまん、それはある』と言うしかない。自分でも「なんでだ」と思っていた側だったが、実際に審査に携わって見えたこともある。
どうしてなのか。ちゃんと理由がある。
まずひとつ。
小説の公募賞にはそれぞれのレーベルカラーだとか、募集ジャンルが持っている様式だとかがある。様式とは、ミステリで地の文が嘘をついてはいけないとか、SFCはセンス・オブ・ワンダーがなければいけないとか、ライトノベルはキャラが立ってなければならない、といった、そのジャンルであると胸を張るための条件、みたいなもののことだ。
「下読み」という業務に関係なく、読書人というのはその人ごとに、あるレーベルのカラーや、ジャンルの様式について、異なる基準を持っているものだ。たとえば「ライトノベルに美少女ヒロインは必須、主人公とのロマンスも必須」と信じている人のところに、ド硬派な男臭い物語が割り振られると、作品に穴が少なくても評価が低くなる可能性がある。
これは「下読みがアルバイトで作品を評価する能力がない」から起きるのではなく、担当者ごとの評価基準の個人差が原因。
大人数でかかる仕事の仕組み上、どうしても避けられないものなのだ。その人ごとに評価の基準が異なってしまう以上、組み合わせ/相性でどうしても評価が変動してしまうのは避けられない。これは何も一次審査に限ったことではなく、編集部員が読む段階に入ってからも、結局は編集者一人一人の違いというのは出てしまう。
そう聞くと、編集部が評価基準をしっかり示せば良いのでは、と思う人がいるかもしれないが、それは難しい。選考基準を厳密にすると、そこから外れたものは容赦なく弾かれることになってしまうからだ。
それを実践したら、究極的には「編集部がイメージした通りの作品」しか選考に残らなくなるだろう。
だが編集部が本当にそのような作品だけが欲しいなら、デビュー済みの作家に案を持っていき、「こういう作品を書いてくれ」とすれば良い話なのだ。何もアマチュアから新たに書き手を募ることはない。
編集部が評価基準を固めない(だいたいは「面白いものを通してくれ」しか言わない)のは、そういうことなのだ。出来れば編集部の想像を超えた面白さを見せてくれる作品を採りたいはずだ。公募賞の意義はそこにある。
その意義を失わないために、評価基準をガチガチに固めることはない。その代わりに多少の相性問題(下読みガチャ)が生じてしまうことはやむを得ない、というのが現状ではないかと思う。
さて下読みガチャ落選が起きる理由、ふたつめ。
これはもう、選んでいるこっちだって胸が痛い話なのだが、我々は「面白いな」と思った作品を何本でも通して良い、という状況で仕事をしていない。ほとんどの場合、受け持った数の「一割」くらいが通過させられる上限だ。「一割」といっても、実際に一つの便には10から20程度の作品しかないのだ。その中で一作、多くて二作しか上位選考に上げられない。
その一つの便の中に、良い作品が二つ三つ四つと重なっていた場合、どうなるか。
心の中では一次審査通過クラスの評価をしていても、どれか一作は落とさねばならない、という悲しいケースが生まれてしまうのだ。
これは選んでいる側からしたら「ガチャ」ではないのだが、応募している人から見れば「良い作品なのに一次すら通過しなかった」ということになり、「一次審査をしている下読みに見る目がないんだ」という怨嗟に繋がるであろう。
気持ちは分かる。
でも、どうしようもない。申し訳ないが飲み込んでもらうしかない。ライバルの作品を上回れなかったのだ、という事情すら、応募者には知る術がなく、こちらには伝える術がないのがつらいところである。
意外と理解されていないかもしれないことだが、公募小説賞の審査は、一次審査から既に「競争」だ。一定の水準を上回ればただちに上位通過、という仕組みにはなっていない。
同じ枠、同じ便、同じ箱(すべて同義)にいる他のライバル作品との競争に打ち勝ち、数少ない通過枠に入らねばならないのが審査なのだ。
これに敗れて落選する、というのは下読みに対する「ガチャ」ではなく、応募タイミングによって強力なライバルとかち合ってしまうという意味での「ガチャ」と言えるのかもしれない。(だいたいの場合、受付順で便にまとめられるらしいよ。俺の体験だとそうだった)
こんな不運を避けるには、ライバルの追随を許さないくらい、圧倒的に面白い作品を投じてもらうしかない。がんばってほしい。どうせデビューしたなら、次から次へと新しいものを生み出していかなくてはならないのだ、その練習と思って次回作を構想してもらいたい。
■本当に何十本も読んでるの?
うん、読んでる。
他の担当者さんの仕事ぶりは知らないが、個人的には一本ごとに最初から最後まで、「可能な限り全部」読んでいる。一本読んで評価を付けて報酬を得る、という仕事なのだから、当たり前といえば当たり前の話。
ただ例外もある。稀に、本当に『日本語として成立しない文章で書かれている』応募作があって、そんな作品は途中を猛スピードで読み飛ばす。無理なのだ、だって。読めないんだよ。すごいんだ。もう「不可能」と言うしかない応募作はあるのだ。
それと、単純に面白くならない作品も、読むスピードが上がりがち。
■書き出しの数ページだけ読んで切り捨てるってよく聞くけど?
その「切り捨てる」が、「これは落選させることになるな」という予想が立つ、という意味ならよくあること。それくらい読むと、心の中でもう最終的な評価点を想像し始めている。
書き出しの数行を読むだけでも、面白さに期待できそうか否かは分かるものだ。
良い作品は、わずかな文章の中に配慮があり工夫がありセンスが見える。
冒頭でそういうものを感じない作品は、読み進めてもたいがい面白くはならない。
序盤で感じたそれらの予感は、だいたい外れない。その後は予感が正しかったことを確認するかのように読み進めることになることが大半だ。
こういう経験を何十年と続けているベテランさんなら、本当に読むのを止めてしまっているケースもあるかもしれない。
そんな程度の量を読むだけで分かるのか? と思われるかもしれないが、分かる。というか、これが分かる人間だから審査に携われている。それは基本的に読書経験(読書量と内容の含味)で培った審美眼だ。センスある人なら、たぶん千冊くらい読めばどうにかこうにか。やりたい人はたくさん読みましょう。
■落選させられたのは、下読みが応募作をパクって自分ものにするためなんじゃ?
青葉か。
大半の一次審査担当者は小説家じゃないので、その点で心配するほどのことはないかなと。かくいう俺が「小説家」経歴ありの下読みですが、今現在、どこかの出版社とそういう方向性で仕事をしているわけではない休眠状態だし。
まぁ杞憂です。
仮にそういう悪巧みする人間がいても、ただ落選させるだけしか出来ないし、であれば今時の応募者さんなら、別の公募賞へ再応募することもあるじゃないですか。それで受賞でもした日には「なんで似てるんだ」と問題化する。バレたらもう、事実上の業界追放でしょう。そんなリスク負ってまでパクるかどうか。
そもそも作風ってものがあるから、パクったって自分の作品に溶け込ませることは難しい。そこから続編なんて思いつかない。先が続かないのだからパクってもあまり意味はない……とも言える。
(ライトノベルで盗作騒動があったけど、あれは受賞作が既存作品の剽窃を多く使っていたって話でしたね)
「下読み」かつ「小説を書ける人間」の個人的所感としては、応募作を読んで「パクりたい」なんて感じたことは一度もないです。
これを書いたのが自分じゃないなんて悔しい、と感じることはあります。こういう話が書ける作者でありたかった、とか。すげえなあ、と感心する作品とかにもたまに出会える。巧いなこの人、という感心の仕方もある。受賞に至るような作品でなくとも、少数ながらそういう面白さを感じる応募作はあります。なんで受賞しなかったんだろうなアレとかアレとか。もう一度読んでみたいがwebにも公開されてないのだよなぁ……もったいない。
■なんでこんなこと書き始めたの?
審査のために原稿を読みながら「ここはこれだと弱い」やら「他人に読まれることを考えてないな」やら、いろいろ考えるけれども、それを誰かに伝える手段が「下読み」にはないのです。
もともと自分も「小説家志望」だったこともあって、応募者の気持ちって分かるんですよ。その上で、ただ評価点を付けて落選させるだけ、通過させるだけということが、そろそろ心理的にツラい。いろいろ積み重なってきてツラい。
審査中の自分が感じている、作品の良い点悪い点改善点。そういうものを作者が渇望していることを、当事者だった一人として知っている。でも何も言えない、ということが苦しい。特に近年は応募作のレベルが上がっていて、「このレベルの作品を落とさなきゃならんのか」と思ったこともあった。
応募者のためという以上に、自分のその苦しさがイヤになってきたので、ガス抜きのようなものとして書き始めた、という感じです。
■おまえが俺の応募作を落としたのか
その可能性はゼロではない。
次は、俺が「こいつは落とせない」と屈服するような作品を書き上げて、かかってくるがいい。
受けて立とうではないか。(そういう仕事ではありません)
おふざけではなくしっかりと言うと、好きに・嫌いになることに理由はないのだが、評価して通過させる・落選させることには言語化できる明確な理由があるので、一次に限らず落選した人の作品にはなんらかの瑕疵があるわけです、やっぱり。だから恨むな。
その評価軸が多種多様で、かつ応募者からはブラインドになっていることで生まれる苦しみを、ほんの少し軽減するような解説を、この後の記事でやっていきたい。
■こんなの書いて公開してまでして怒られない?
正直、分からん。なるようになれ。

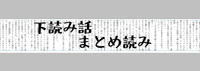
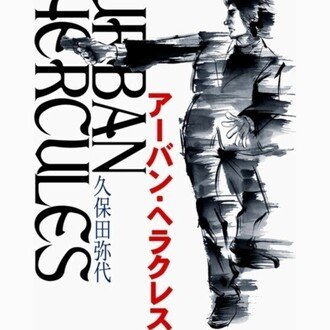
コメント