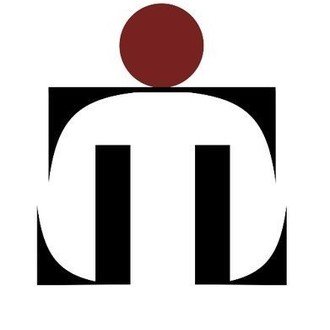関わりたい人がいないということ
はじめに
いったん気づいてしまうと、あまりにも当たり前のことであると感じられるにも関わらず、気づくまでに途方もない時間がかかってしまったということがある。
おそらくこの記事に書くことは、そのほとんどがわたくしが20年前に気づいておくべきだったこと。
わたくしはパターンを抽出することが好きではあるのだが、自分が当事者として遭遇しているような関係性をめぐる問題について、感度が鈍いかもしれない。だからパターンを抽出するまでに時間がかかってしまうことが多い。
他者との関係。
自分にとっての創作や研究。
わたくしにとって重要なことではあるはずなのだが、ふだんは当事者として考えることはあまりない。
おそらくほとんどの人にとって、建物の中にこもって読書をしたり文章を書いたりゲームをしたり、そういうことに没頭している日々が続いているような時期には、建物の外壁に思いを馳せることはほとんどないだろう。
雨漏りなどがあって困った状況になって初めて、構造的なことについて考えたりすることはあるかもしれない。
やはりものごとには、タイミングというものがある。
今回の記事「関わりたい人がいないということ」は、2025年3月から構想を練り始めて、実際に書き始めたのは2025年4月26日。
ある意味では、自己紹介兼マニフェストとしての性質を持つ記事になりそうだ。
約2年前の2023年夏に書いた、わたくしが「ジェネシスブロック記事」と呼んでいる以下の記事についても、自己紹介兼マニフェストとしての性質を持つはずだった。
2023年7月のプロフィールページ刷新、そして各種Webサービスに思うこと|cleemy desu wayo(2023-08-31)
https://note.com/cleemy/n/n96474b06fa3b
でもこの「ジェネシスブロック記事」では肝心なことをまったく語っていなかったかもしれない。
わたくしは数年前から『分類しない暴力』というシリーズを構想中であり、そこで語る予定のことについては「ジェネシスブロック記事」では意図的に避けたということもある。
分類しない暴力【A面】|cleemy desu wayo|note
https://note.com/cleemy/m/m3c861812c2a0分類しない暴力【B面】|cleemy desu wayo|note
https://note.com/cleemy/m/m438414762279
今回の記事「関わりたい人がいないということ」については、『分類しない暴力』を構成する記事ではない。でも『分類しない暴力』で語る予定のことと内容的に重複することを恐れずに書く。だから今回の記事が予告編としての性質を持つことになる可能性もある。
『分類しない暴力』では様々な形で性格分類について書くつもりだが、それを書いているわたくし自身の性格のこと、つまり読者からみて「で、お前はどうなの?」ということについては曖昧にすることが多くなるかもしれない。
今回の記事では、自分のことについてはっきり書いておく。
もしかしたら、今回の記事を読む前に中井久夫のエッセイ「世に棲む患者」を読んでおくと、よりスムーズかもしれない。
でも別に読んでいなくてもかまわない。
また、問題意識を共有しないまま「世に棲む患者」を読んでもわけが分からないということになる可能性の高い人が、わたくしの今回の記事を先に読んでから「世に棲む患者」を読むとよく理解できるというようなこともあったりするのかもしれない。
「世に棲む患者」は精神疾患についての話がベースではある。ただ、病的なレベルとはいえない人のことを考えるうえでも参考になるはずである。入手しやすいものとしては、2011年刊のちくま学芸文庫版『世に棲む患者』がある。この文庫で、エッセイとしての「世に棲む患者」は約30ページである。非常に濃密だが、同時に前提知識をあまり必要としない。
発表時点(1980年)では野心的な内容だったはずだが、意見が割れやすい要素はさほどないようにも思える。
わたくしがこれを読んだのはおそらく2008年で、ちくま学芸文庫のシリーズが出る前だった。わたくしは論文のつもりで読み始めたため、想像していた内容とあまりにも違っていて鮮烈な印象があった。
ちなみにわたくしは精神科に入院したことはない。睡眠障害で通院していたことはあるし、スキゾタイパルの傾向があるかもしれないと思うことはある。
最近SNSなどで流行しているMBTIやそれに影響を受けた性格分類では、わたくしはINTPということになると思っている。
こういった性格分類については、「疾患」や「障害」とは切り離して論じることができるのが気楽でいいと感じる人もいるかもしれない。
MBTIの元になったユングのタイプ論については、中井久夫は「血液型性格学を問われて性格というものを考える」というエッセイの中で「病気をモデルとする偏りがなく、常識的といえる」と書いている(2009年刊『臨床瑣談 続』P.53、みすず書房版『中井久夫集 10』P.207)。
今回の記事についてもそうだし、『分類しない暴力』についてもそうなのだが、性格分類についての記述については、同意してくれなくてもかまわない。「話半分」あるいは「そういう風にとらえる人もいるんだねえ」という感じでいい。Wikipedia用語で言うなら、「独自研究」が多すぎると感じる人もいるだろう。
ただし、独特すぎるようにみえる仮説も、いずれは人間に対するハードウェア的な解析によって裏づけがとれる日が来ると信じているものもある。
今回の記事はもちろん、元々わたくしに興味があった人や、わたくしに物理的に会ったことがある人が読むかもしれないことを想定はしている。でも具体的な宛先があるわけではない。10年経ってフタを開けてみると、そういう人は誰もこれをまともに読んでいなかった、ということが判明したとしても別にかまわない。
別にわたくしには興味がないという人にとっては、INTPを自認する人間がどのように世界を見ているのかというサンプルとして機能することもあったりするかもしれない。
INTPが周囲の人間にもたらしがちな困惑についての答えがこの記事にあると考える人もいるだろう。
今回の記事ではINTPが「油絵法でタネをつくる」存在であることも明らかにし、そのことと日本のネット史との関係についても触れる。
INTPは「論理学者タイプ」などと呼ばれたりすることもあるようだ。
INTPは創作や研究に向いていると考える人も多いようだが、INTPを自認する人による創作や研究についての入念な考察をSNS上ではあまり見かけない気がする。今回の記事は、INTPが創作や研究という営みを真剣に「研究」の対象とするとどのようになるのかというサンプルにもなるかもしれない。
今回ここに書くことはわたくしが考えてきたことのほんの一部にすぎない。
また、小説を書いたりする人々や「字書き」と呼ばれる人々の総意だとも思わないでほしい。
INTPの中にも社会適応の良い人もおり、そういうINTPはここで語られているイメージとはかなり異なっていたりするかもしれない。
また、わたくしにスキゾタイパルの傾向があるがために、あまりスキゾタイパル的でないINTPのことが忘れ去られがちということもあるかもしれない。
ちなみに、実はわたくしはINFPなのではないかと思うこともあることは付記しておく。
表記については、わたくしが例えば「INxx」と書く場合、EI指標でI型であること、SN指標でN型というのがわたくしと共通していて、それ以外の要素(TF指標とJP指標)については不明ということである。
「x」は包括という意味を込めることもあるし、特定の対象についての話であれば判定不能や中間的という意味を込めることもあるし、自認の場合は本人が開示したくないとか、有効な分類方法として認めないとか、いろいろな可能性がある。
この「x」により、ある時には対極の存在であったはずの二者が、別の視点においては同じグループを構成する、ということが起こる。
ちなみにエッセイとしての「世に棲む患者」については、病気の人だけではなく、xNxP(N型かつP型)であるような人全員に当てはまるようなことがたくさん書いてあるように思う。
たいていの職場ではxSxJ(S型かつJ型)が強い影響力を持っていることを考えると、「生きづらい」とか「自分に合った職業というのが存在しない」と感じるすべての人にとって「世に棲む患者」は参考になるかもしれない。
1980年発表の「世に棲む患者」では、患者や元患者は思わぬところに思わぬ知り合いがいるようなタイプが多いとしており、これを「オリヅルラン型」と呼んでいる。この逆は「ヤマノイモ型」で、同心円的な関係性を重視する。日本のサラリーマンの場合、いつの間にかあらゆる人間関係が自分が勤める会社を中心としたものになりがちなのは、2025年現在においてもさほど変わっていないだろう。
わたくしには、この「オリヅルラン型」はxNxP(特にINxP)に近いように見え、「ヤマノイモ型」はxSxJ(特にESxJ)に近いように見えるわけだ。
なお、今回の記事「関わりたい人がいないということ」は賞味期限が最低でも10年くらいはある記事だと思ってもらっていい。日本社会の傾向も、わたくしの性格も、そう簡単に変わることはないだろう。
APDと相貌失認
まずは『分類しない暴力』では詳しく書かないかもしれないことから。
そして、INTPやスキゾタイパルとはあまり関係がないかもしれないこと。
これはかなり昔からの傾向なのだが、わたくしは呼びかけられても気づかなかったり、声が音として聞き取れているにも関わらず何度も聞き返したりすることがある。
もしかすると、わたくしは軽いレベルでAPD(Auditory Processing Disorder)かもしれない。APDは「聴覚情報処理障害」と表記されることもある。
イヤホンを使用したり軽音部に入ったりするようになるよりもずっと前からなので、生まれつきの傾向だと思っている。また、ノイキャンが一般的になってからもノイキャンとしての性質を持つイヤホンは使用したことがない。
子供のころによく耳の検査に連れて行かれたが、むしろ耳は良いと言われることもあった。
機械的な音などはよく聞き取れるが、人間の発話で問題が出る。人の声でもマイクを通すのであれば、あまり問題が起こらないかもしれない。
静かなところで一対一で話している時も、あまり問題は起こらない。
雑音の多い環境が厄介なのである。
あまり何度も何度も聞き返すと気分を害する人もいるため、本当は聞き取れていないのに、ついごまかしてしまうということに慣れてしまっている。
聞き取れないこと以外に、耳で聞いたことをすぐ忘れるという問題もある。すぐにメモして視覚情報に置き換えないと、急速に薄れていく感じがする。
わたくしは2023年11月からVRChatをやっているが、こういうものでも同様だ。人数が多いと急に聞き取りが難しくなる。お互いにChatBoxを使用して、かつ一対一の会話というのが落ち着く。
VRChatでは設定や通信環境のせいで音が途切れ途切れになることが多いため、聞き返すハードルが低いという側面はあるかもしれない。
聴覚のことと自分の創作や研究については、長らく結びつけて考えることはなかった。でも最近になって、わたくしにあるAPDの傾向は、のちに述べる「油絵法」に向かわせる要因の一つになっている可能性があることに気づいた。
また、社会的には、APDというのは読字障害(ディスレクシア)の聴覚版という側面があるかもしれない。このことも最近になってから気づいた。
視覚の面においては、近視や乱視以外では深刻なものはないつもりではいる。でも顔が覚えられないとか誤認しやすいというのはあるかもしれない。
明確に相貌失認とは言えないと思うが、実物の印象と写真や映像で見た時の印象とがうまく一致しないことがある。どうしても別人に見えてしまうことがあるのだ。
顔をさらしている人で、かつわたくしがその存在を写真や映像などでよく認識していたとしても、いざ実物を見るとその人だということに気づかない可能性があるということである。
物理的に何度も会った人については、比較的遠いところから気づくこともある。わたくしに同行している他の人よりも先に気づいて、「ほら、あそこにいる」「どこ?」「ほらほら」のようなやり取りが生まれることもある。だから、典型的な相貌失認とはいえないはずである。
物理的に何度も会っているけれども、写真や映像では一度も見たことがないという場合、やはり不一致が起こることがある。画面に表示されているその人が、本当に会ったことのあるあの人なのだというのが信じられないことがある。
物理的に何度も会った人ついては、顔を3次元的にとらえている可能性もありそうだ。
また、顔と名前が一致しないことも多いが、これは顔を認識しているのに名前を覚えていないことが多いためである。
だいたい以上のような感じで、声と顔の認識において、軽度ではあるが混乱が生じることがある。
認知特性においては、聴覚優位か視覚優位かという対比で見れば、わたくしは明らかに視覚優位だと思っている。視覚優位と言語優位ならどちらになるなのかというと、よく分からない。
わたくしは幼い頃から本は身近にあったが、ハイパーレクシアではないと思っている。
対話と油絵法
子供のころは、会話が苦手だなんて微塵も思っていなかった。
呼びかけられても気づかないことがあったり、音として聞こえていても言葉として聞き取れないことがある傾向については認識はしていたが、そういうことはあまり重要だとは思っていなかった。
小学4年生のころから小説を書いたりして、文章を書くこと自体は好きではあった。
でも会話より文章のほうが得意とか、そういう風に考えたこともなかったように思う。自分ではうまく会話をこなしているつもりだったからだ。
ちなみに小学生のころは、どちらかというと衝動的で騒がしい子供でもあった。
1999年1月から2000年12月にかけて、プログラマーとして仕事をしていた時期もある。
プログラマーとしての仕事では、メールでつい長文を書くことも多かった。コードを書くのと同じくらい、メールを書くのが楽しかった。この2000年前後というのはSlackもChatworkもなく、何よりもまず電子メールだった。メールを推敲しているうちに、いつのまにか「作品」と化してしまうことがあった。
打ち合わせの時には、それなりに発言はしていたと記憶している。打ち合わせが苦手だとも思っていない。ただし、打ち合わせで発言する時は、いったん文章として考えたことを話していた可能性が高そうでもある。
果たしてわたくしは、どのあたりから会話に苦手意識が生まれたのだろう。
口頭の会話ではとっさに反論が思いつかないことが多いことに気づいたのは、2001年〜2003年あたりかもしれない。
あとから一人でじっくり考えてみると相手がデタラメなことを言っていたことがよく分かる、ということも多い。でも物理的に会ってなされる会話の、その「現場」において、会話の真っ最中に反論が浮かんでこないのだ。相手がずっとデタラメなことを話しているのに、まともなことを言っていると思ってしまうこともある。
単に反論が思いつかないというだけでなく、文章でないと自分の考えがまとまらないことが多いことに気づいたのは、おそらく2006年あたりである。
文章に込めることの出来る豊かさや構造的複雑さと、口頭の会話での貧相さのギャップが、あまりにひどすぎるように思えてきたのだ。
話を合わせるのが上手い人と会話する機会が減ったこともあるのかもしれない。
内容の貧困さとともに、自分は間が長過ぎることが多いかもしれないと思うことも多くなった。
このことはEI指標と関係があるかもしれない。MBTIあるいはその影響下にある性格分類における、E型とI型の対比。わたくしの「INTP」の、最初の「I」。
『MBTIへのいざない』(邦訳は2012年刊)のP.182〜P.185に、このE型とI型の特性の違いについて、お互いに信用できない状態になりやすいことについて書かれている。
E型は相手からすぐに反応がない場合に何か隠しているのではないかと邪推しがちだし、I型は活発に人と関わろうと動きまわる他人を見て軽薄さを感じ取ったり表面的な対応をしているだけだと誤解しがちだという話である。
以下はP.183〜P.184のE型の「ジョージ」とI型の「ジョン」のやり取りで、「ジョン」の側の発言である。
僕は内向指向。僕の場合は, 誰かが何か質問してくると, ビー玉がとおるくらいの穴があいている板が何層にも重なっているあそび道具があるじゃないか。あのように, ビー玉がまず上から落とされ, ビー玉が穴を目指して転がり, 穴に落ち, もうひとつ下の層の板にたどり着く。そしてだんだんスピードを増しながら, また穴をさがすようにしてビー玉が転がり, また穴に落ち, さらに下の層の板に落ち, 最後に一気に一番下に落ちる, というように, 一番下についた段階で, はじめて反応するんだよ。意識的に情報を隠しているわけでもなければ, 頭が悪いのでも, のろいわけでもない。ただ反応する前に, 自分のなかで考え通したいだけなんだ。むしろすぐに反応するときは, それこそなにか別のことを隠すためにつくりあげた答えだな
I型にとっては誠実になろうとするからこそ沈黙を必要とする。
I型であっても、あらかじめ文章として組み立てておいた頭の中のストックを活用できるなら、誠実さと即答の両立が可能になることもあるかもしれない。
沈黙と不信を結びつける傾向は、読書によって強化されてしまうこともある。ビジネス書や自己啓発やハウツーの系統の本には、読み手のファンタジーに寄り添ったものが多く含まれる。
例えば『超一流の諜報員が教える CIA式 極秘心理術』(邦訳は2020年刊)という本のP.310〜P.313には、わたくしからするとかなり不可解な判別方法が書かれている。
相手を動揺させる質問をして、すぐに返事をせず「しばらく沈黙が続く」ような人間を信用するなという主旨である。
わたくしがあのような質問をされる側であれば必ず動揺するだろうし、度胸のある人間かどうかをテストしているのだろうかなどと考えて、やってもいないことをしゃべってしまうかもしれない。
初対面であのような異様な質問をされて動揺せずにスラスラ答えられる人というのは、わたくしは詐欺師なのではないかと思ってしまうだろう。わたくしの場合は動揺を「しない」人に対して、「あまり深くは関わりたくないなあ」ということを考えてしまうわけだ。
もちろん、I型からは詐欺師だと思われるリスクがあったとしても、タフさのある人間かどうかを見極めたいという需要はあるのかもしれない。頼りがいのある人間なのかどうかという判定。
あるいは意図的に、E型からのみ信用される人間を抽出したいという場合。
こういう構造的な性質を理解したうえでなら有用だが、信用できる・できないということを安易に判定しようとするのは、ほとんどの民間人にとっては危険である。
ちなみに『MBTIへのいざない』のP.282には以下のような箇所もある。
たとえば, 質問にすぐ答えない人は信用できないと別の機会で教わった人がいるとする。するとその人は, 内向を指向する人のそうした行動の表れを見て信用できない人だととらえてしまう。
ちなみにこの箇所は、MBTIで学ぶことと世間での「教え」がバッティングすることについての話の流れの中である。内向指向(I型)であると判定されることの動揺は、日本よりも海外で大きい可能性もある。これは日本人にとっては意外なことかもしれない。
ちなみに『MBTIへのいざない』P.229〜P.230には以下のような箇所もある。
内向指向の人は, 聞くことの刺激よりも, 読むことなど視覚による刺激を好むことが多い。読むスピードの平均は1分間で約420単語といわれ, 話すスピードは1分間で75から100単語といわれている(訳者注:原著が書かれた英語に関してのこと)。外向を指向する人がよりすばやく反応し行動に移している間, もしかしたら内向を指向する人のほうがより複雑な情報を, よりすばやい時間で処理しているかもしれないのである。
そういえば、頼りがいと実務能力は、ある程度は連動しているかもしれない。
わたくしが会話における間が長いことに気づいたのと近い時期だったと思うが、自分の実務能力の無さもはっきり認識した。とにかくあらゆることについて、作業が遅い。単に遅いだけでなく、他人との連携に問題も出やすい。
わたくしは一時期だけ三線を弾くアルバイトをしていたこともあり、こういうものであれば作業という性質は薄い。他者との連携もあまり必要ない。
それなりに最近のこととして、2017年秋から2年以上コールセンターで仕事をしてみたこともある。未経験かつ最末端の要員として電話を受けた。電話あるいは会話についての苦手意識はかえって強くなった。相変わらず実務能力が低いことも実感した。とにかくいろんな意味で、現場受けが悪い。
でもそんなことより、コールセンターではもっと重要な発見があった。わたくしは自分で思っていたよりもチャットが苦手なのではないかということだ。
文章を書くのは好き。でも業務でのチャットは苦痛が大きい。これはどういうわけなのか。
コールセンターを辞めてから、精神科医の中井久夫が文章を書くことについて「油絵法」という言い方をしていたことに気づいた。
「油絵法」は「私の日本語作法」というマニュアルめいた文章の中に出てくる。以下のように解説されている(ちくま学芸文庫版『「伝える」ことと「伝わる」こと』P.342、みすず書房版『中井久夫集 2』P.158)。
油絵法。あっちを塗り、こっちを塗り、下塗りをし、削り、上塗りをし、遠くから眺めては修正し、最後にニスを塗って仕上げる方法です。
そうなのだ。チャットの場合というのは「あっちを塗り塗り、こっちを塗り塗り」というわけにはいかないのだ。
チャットも文章だといえば文章なのだが、過去の発言を修正したりはできない。Discordなどシステム的に修正可能なものもあるが、まとまった分量の文章で公開前に広範囲に修正を何度も加えていくのとは意味合いが違う。
油絵の場合は、完成を宣言する前に、部分的に塗りつぶして無かったことにしたり、すでに描いたものにまったく違う意味づけをしたりするのも容易だ。
わたくしにとって重要なことは、文章であるかどうかよりも、プロセスにおいて油絵的な要素を持っているかどうかだったのだ。
ちなみに、中井久夫の説明の「遠くから眺め」るというのは比喩だと思ってもよさそうではあるが、必ずしもそうともいえないことが「ワープロ考」(みすず書房版『中井久夫集 4』に収録)を読めば分かる。
油絵法について考えているうちに、どうやらわたくしは、口頭の会話においても頭の中で油絵をやってしまっているらしいことに気づいた。
先ほど引用した『MBTIへのいざない』の「ジョン」の発言は、かなり的を射たものだという感じはするのだが、わたくしの場合はビー玉というのは少し違う気がするのである。
会話の最中にもつい「さっきの発言、やっぱこう修正したいなあ……」とか、「もし今わたくしがこういう風に答えてしまうと、今構想中の小説のあの登場人物のあのセリフが別の意味を帯びてしまうかもしれないなあ、いやちょっと待てよ、あのセリフは本当はこう修正したほうがいいのかもしれない……」とか、そういうことを考えてしまうわけだ。もちろん、その頭の中の小説と目の前にいる人とは何の関係もない。
表面的には沈黙の時間が長くなりがちだが、のんびりしているわけではない。いろんな考えが常にめまぐるしく頭の中を駆け巡っている。同時に複数の言葉について検討しようとしていることもある。文章というよりは、小説や記事の全体の構成についての修正を同時にしていることもある。どんどん脱線していって、会話の内容とまったく関係のないことを思い浮かべてしまうこともある。
この「同時に」というのも、2つか3つぐらいを同時並行で、というものとは少し違っている。場合によっては、次々と枝分かれしていって、収拾がつかないと感じることもあるのだ。
いわゆるマルチタスク作業とも違う。頭の中の同時並行であって、作業という形で表面化するとは限らない。
考えるべきことは次から次へとわいてくる。頭の中は常に忙しい。事件は現場でも会議室でもなく、頭の中で起こっている。
原田憲一『精神症状の把握と理解』(2008年刊)の「第5章 思路の障害」には様々な会話の例が挙げられている。この本のP.109の連合弛緩の例の「統合失調症 二八歳 男性」のものなどは、わたくしが疲れている時にこのようになりやすい例だといえるかもしれない。「流れがはっきりしない」「意味上の連なりがしっかりしていない」と解説されていて、まさにそういう感じの発話になってしまうことがある。
わたくしの場合は、連合(連なり)の弛緩というよりは、あまりにも多くのことが頭に浮かぶために結果として上記の例に近くなると考えたほうがいいのかもしれない。
これは口頭の会話だからこそ違和感として表に出るのであって、絵や文章ではさほど大きな問題にはならないといえる。
問題にならないどころか、メリットになることもあると思っている。
油絵なら、ある箇所を絵筆で塗りながら頭の中では他の箇所について考えてもかまわない。あるいは絵とまったく関係のないことを考えてもかまわない。
文章でも、文字を打ち込みながら別の箇所の文について考えてもかまわない。
また、実際に手を動かしながらある特定の一点に意識を向けるということが、収拾がつかないほどに枝分かれしていくのを防止する効果があると感じることもある。
この枝分かれは、口頭の会話以外にも、他人と連携しながらの作業においてデメリットとなるかもしれない。
自分の身は一つだし、自分の作業が他人の作業に影響を与える状況下では、自分の判断で勝手に「あっちを塗り塗り、こっちを塗り塗り」ができない。
他人との連携が必要ない一人作業なら、具体的な作業であっても問題が出にくいだろう。例えば、部屋の片付けなど。もちろん、依頼者や監督者がいないというのが前提である。
人によってはそういう場合でもテキパキと計画的に実行できるのかもしれないが、わたくしのような人間には到底無理な話である。あっちを片付け、こっちを片付け、せっかく片付けたものをまた戻したり、新しい分類方法を思いついて片付けの方針を根本から変えてしまったり。収納についてのトリッキーな手法を思いついて、延々とその構想を練ったり。そして昔の雑誌を見つけたりすると、懐かしくなって読みふけってしまう。
退去しなければならないなどの切迫した理由があるなら、そういうやり方をしていてもいつかは終わるものだ、とはいえる。
おそらく林業なども似たような性質がある。
山の中の一人作業は死亡事故が多いとされるが、そもそも他人と連携しながら作業することが苦手だからこそ林業に関わるというケースも多いのではないかと思う。
林業がどうかは知らないが、求人誌などでは「自分のペースでできる」という言い方を見かけることがある。こういう表現がある場合、実際にはペース配分そのものよりも、「あっちに手を付け、こっちに手を付け」について承認を得たり交渉したりする必要がないという意味合いが込められることもありそうだ。「裁量が大きい」という言い方がされることもあるかもしれない。
今回の記事の執筆などもまさにそうである。
誰かに頼まれたわけでもない。わたくしの背後にプロデューサー的な人がいるわけでもない。自分が書きたいから書き始めた。
構想を練る段階においても、構想が固まって箇条書きで全体像を書く時も、記事本文を書いている時も、あらゆる段階で、「油絵法」がある。「あっちを塗り塗り、こっちを塗り塗り」である。
そして誰に対しても、詳細について報告の義務がない。
今回の記事を書いている最中の2025年5月4日には、急に新しい記事「xSxJ階段とxNxPジャンプについてのメモ」( https://note.com/cleemy/n/n6451e95a3ca5 )を書いたりもした。書き始めてから11時間後にはもうアップロードしていた。最初は2,000字程度の簡単なメモにするつもりだったが、完成した段階では約5,000字の記事になってしまった。
2025年5月12日早朝(日本時間)からは、なりすましがいる可能性が急に気になり始め、新しい記事「LINEやインスタにアカウントはない」( https://note.com/cleemy/n/ne2efcb31a2dd )を書いたりもした。こちらは1万字を超えた。
さっきまで「あっち」に熱中していたのに、なぜ今「こっち」なのか。
そういうことは他人に説明できるようなものではない。とにかく気になるとか、今急速にイメージが固まってきているから早く形にしておきたいとか。
すべては衝動でしかないのだ。
小説では、最初の一行が決まると書き進めるのがラクだということがよくいわれる。でもわたくしの場合は違う。最初の一行目から書き始めるわけではないからだ。
今回の記事についても、「いったん気づいてしまうと……」の書き出しは本文をある程度書いてから思いついたものだ。
今回の記事は全体の構想については2025年3月前半から練り始めた。最初は頭の中だけだが、3月半ばあたりからB5のルーズリーフ1枚に断片的なアイディアを少しずつ書き足していった。4月26日午前02:40あたり(日本時間)からテキストファイルでの執筆に移行し、最初の数時間はまず箇条書きのメモを書いた。このメモによってセクションのタイトルや順番もほぼ固まった。それぞれのセクションの中身については何を書くかだけの箇条書きで、語る順番などは一切決めない。
セクションを分割したり並び替えたり削除したりセクションのタイトルを微妙に変更したりするなど、本文を書きながら全体の構成を多少は変更したりもしているが、基本的には4月26日早朝(日本時間)にほぼ固まった箇条書きを尊重しながら本文を書き始めている。それぞれのセクションの中身については、どんな順番で語るのかは書きながら何度も何度も変更している。
本文を書きながら、このセクションで語っていることをやっぱりこっちのセクションに持っていこうとか、そういう移動も頻繁に発生している。
毎回こうするわけではないが、今回の場合はこうなったというだけだ。そして、こんな風に書くというのも最初から決めていたわけではないし、いつ頃どういうフェーズに移行するのかということについてもスケジュールは一切存在しない。すべてはその時の気分である。
この頻繁に起こる「あっちからこっちへ」を考えるうえで、わたくしが重要だと思う要素を5つ挙げておく。
ランダムアクセス
同時処理
衝動性
飽きっぽさ
自生思考
「1. ランダムアクセス」については、コンピュータ用語としてのランダムアクセス(random access)を意識している。シーケンシャルアクセス(sequential access)の対義語だ。シーケンシャルとはつまり、順番にとか、連続的にとか、そういうことだ。読書でいえば、1ページ目から順番に読んでいくのがシーケンシャルであり、付箋を貼った場所にいきなりジャンプして読み始めたり巻末索引からページを調べてそこにジャンプするのはランダムアクセスだ。
電子データにおいては、検索はランダムアクセスと親和的だ。
そんなわたくしも、一人の読者としては、小説の場合はシーケンシャルに読んでいくことがほとんどだ。
エッセイ「世に棲む患者」では、「オリヅルラン型」に関連して何度も「思わぬ」「思いがけない」といった言葉が登場する。これはランダムアクセスと親和的だ。いろんな意味で「ジャンプ」が見いだせるわけだ。文脈切断的ともいえる。
文章の場合は最終的な完成品はシーケンシャル的あるいはリニア(線形)なものである。プロセスにおいてランダムアクセス的であるがゆえに、完成品においては美しく整ったシーケンシャル性が表れる場合もある。
ふだん長い文章を自分で書く機会がない人は混乱するのかもしれないが、その場合は作曲や曲のアレンジの場合をイメージするといいかもしれない。最初の10秒をまず入念に作曲してから次の10秒に移る、というのは音楽では通常はやらないだろう。もちろん、あえてそうするとどうなるのかは興味のあるところではある。特に、複数人でリレーで10秒ずつ作曲するようなもの。
ここ数年のAIの話題では、LLM(大規模言語モデル)の存在感が圧倒的である。わたくしはChatGPTを使ったことはないが、Grokを少しだけ使用してみたことはある。ほぼ常に油絵法で文章を書くわたくしからすると、LLMの出力というのは、油絵法で書いたとしか思えない文章を、視覚的にはシーケンシャルに出力していくため、やや異様に感じることがある。
連載という形態が、いつまで経っても完成しないことを防ぐ仕組みとして機能することもあるだろう。一回あたりの分量が3,000字から2万字程度であれば、それぞれの回に油絵法を適用しつつトータルとしてはシーケンシャルでもあるという、良いとこどりが可能かもしれない。
先ほど提示した5つの要素の「2. 同時処理」というのは、認知特性としての継次処理(sequential processing)と同時処理(parallel processing)の対比における話だ。シーケンシャルとランダムを対比的に見る視点とは別に、シーケンシャルとパラレル(並列、同時)を対比的に見るわけだ。
この対比でも、わたくしはおそらくシーケンシャルではなく反対側の同時処理(パラレル)の側だろう。読書をしていても、「いま読んでいるところ」というのは点としては存在しておらず、行ったり来たりしながら読んでいることがある。複数の文章を同時に処理しているわけだ。これについては小説を読む場合でもそうだ。
「3. 衝動性」というのは、必ずしも病的なものとは限らない。ちなみにわたくしは22歳のころにADHDの概念を知り、これかもしれないと思ったことがある。
「4. 飽きっぽさ」は、衝動性とも関連が強い。ミクロレベルの飽きとマクロレベルの飽きがあり、油絵法において重要なのはミクロレベルの飽きである。
マクロレベルの飽きというのは、絵画でいうなら、昨日まで「あっちの絵」を描いていたのに今日はなぜか「こっちの絵」を描いているとか、あるいは絵画と全然関係ないことに没頭し始めるとか、そういうものだ。このマクロレベルの飽きについては今回の記事の「戦闘消耗と離岸流」のセクションであらためて述べる。
「5. 自生思考」というのは統合失調症の症状だ。次々といろんな考えが自動的に浮かんできて、それを制御できない。ここでは、必ずしも病的なレベルとはいえないようなものも想定している。
「考えなきゃ」とか「答えを出さなきゃ」という構えで考えるのではなく、自動的に浮かぶものが重要だ。
わたくしも、次々といろんな考えが浮かんで収拾がつかなくなることが多い。でも日常生活が送れないというほどではない。
そしてこの思考のめまぐるしさから、わたくしにはいわゆる「暇」や「退屈」が存在しない。もちろん、義務でやる単調な作業などについて「退屈」という言い方をすることはある。でも「することがない」という意味での「暇」とか「退屈」は、わたくしにはないのである。
「油絵法」と自生思考は単に親和性が高いというだけではない。これは私見だが、自生思考やそれに近い要素がある人の場合は、何らかの形で油絵法を気兼ねなく試すことができる対象を必要としていて、無理にシーケンシャル性の世界観に引きずり込むと不安定になりやすいのではないかと思う。
xSxJの人の中にはシーケンシャル性の「効能」を強く確信している人がいる。その人の成功体験と強く結びついている場合もある。S型はそもそも、自分の経験を特別視しがちである。
ちなみに中井久夫が気になることを書いている。以下は「働く患者」というエッセイより(ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.60、みすず書房版『中井久夫集 1』P.269)。
たとえば同じく間接的アプローチであっても、より間接性の高い「手紙」に訴える患者は、もっぱら「電話」にたよる患者よりも予後がよいように思う。そして、患者は、現在のわが国では、非患者よりもよく手紙を書く人であると私は思う
ところで、アインシュタインは息子が統合失調症だったために、その言動が病跡学(パトグラフィー)の観点から注目されることがある。
アインシュタインの言葉として、以下のようなものを見かけることがある。
私は何ヶ月も何年も考える。99回はその結論は間違っている。100回目には、私は正しい。
英語版は以下。
I think and think, for months, for years. Ninety-nine times the conclusion is false. The hundredth time I am right.
2025年5月28日時点のWikiquoteでは、上記の言葉はソースが不明瞭という扱いのようだ。
Talk:Albert Einstein - Wikiquote
https://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Albert_Einstein
アインシュタインが実はそんなことは言っていないのだとしたら、こういうものが本人の発言として流布しているのは問題かもしれない。
問題かもしれないが、それはそれで興味深いともいえる。世間の人々がアインシュタインのような存在に何を期待しているのかという指標になるかもしれないからだ。
100回目で正しければ、それまでは間違っていてもかまわない存在。
30回間違った結論を提示したあと、「待ってくれ、せめてあと30回結論を提示するチャンスをくれ」などと誰かに承認を求めたり、交渉が必要になったりする状況下では、これは発揮できない。
でもこういう例え方も、本当はおかしいかもしれない。実務においては、結論を何度も提示するなどということは許されないことが多い。何度も提示できるなら、それは結論ではないということになるだろう。
だからこういう姿勢は個人主義と相性が良いといえる。
2020年あたりから、日本ではネガティブ・ケイパビリティという概念が注目されている。
早々に結論を出してしまうのではなく、もっと良い解があるのではないかとか、そもそも問題設定は妥当なのかとか、濃厚な待ちの構えで考え続ける姿勢だ。
作業のための仮定が必要になっても、それはあくまでも仮定にすぎず、あとからいくらでも変更の可能性がある。
当然これは、すぐに結論を出さないという姿勢が重要なのであって、大事なことを自分以外の誰かに決めてもらうという話ではない。むしろ、良い解がやってきたぞという、その機会をとらえる時というのはものすごく「おいしい」瞬間なのであり、それを他人にゆずるなどありえないと思う人もいるかもしれない。
このネガティブ・ケイパビリティは、JP指標におけるP型に親和的であるように思う。
そもそも油絵というのは、どうなったら完成なのかが曖昧である。
本人の納得がこそが重要だ。
どうなったら完成なのかが曖昧ということは、「進行」を問うということが難しいということでもある。
中井久夫の「執筆過程の生理学」には、自分の頭の中の「批評家」についての解説で以下のような箇所がある(みすず書房版『中井久夫集 5』P.25)。
実際、「批評家」が賢明ならば、すでに完成した部分に新しい意味を見出して、進行というよりも完成へと鼓舞するはずである。
「進行というよりも完成へと鼓舞」というのは示唆的だ。
シーケンシャル性が前提の世界観では、「進行」の連続によって「完成」に至るのが当たり前だ。
この「新しい意味」のためには、自分でも説明できない要素を散りばめておくことも有効だとわたくしは思っている。「なんでこうしたの?」と聞いてくる人がいる環境だと、各要素について理由をいちいち説明しなければならない。「説明不可能だけどとにかくこうするんだ」という姿勢が容認される必要がある。
最初から明確に伏線のつもりだったり、あるいは伏線としての色気をうっすら出したうえでの配置ではなく、特に理由はないけどこれでファイナルアンサー(conclusive answer)だというつもりで配置したはずのもの。それがあとから全然ファイナル(conclusive)ではなかったことが分かるのが重要だ。
わたくしの場合、特に小説でこれが起こりやすい。特別な意味を持たせていないものや、文脈切断的だったものが、書き進めていくうちに自分でもまったく想像だにしない関連が明らかになるような瞬間があるのだ。それは自分で考えたというより、小説の世界から「知らされる」という感覚が近い。
そういう意外性は、がんばってひねり出すという姿勢からは決して生まれてこない。
中井久夫は、自分の中の「批評家」が「鼓舞」することに注目しており、見いだされた「新しい意味」を文章に反映させるべきだとは書いていないことには留意する必要がある。
でも実際に「新しい意味」を明確に反映させることができることこそが油絵法のメリットだとわたくしは思っている。
ちなみに中井久夫の「私の日本語作法」には、ワープロによって油絵法が容易になったという記述もある。中井久夫は早くからのワープロユーザーだった。以下の記事には、ワープロを使っている中井久夫の1993年撮影の写真が掲載されている。
連載「中井久夫さんが教えてくれたこと」⑴⑵|神戸新聞公式「うっとこ兵庫」(2024-01-09)
https://note.com/kobedx/n/n75effd492eeb
もちろん、油絵法のような関与のあり方を油絵以外のものに適用するのは現代社会特有だということではない。
日本の古代の火焔型土器などは、約5,000年前につくられたとされている。油絵法の感覚なしにあのようなスタイルに至ったとは考えにくい。
こういうものに関わっていた人の中には、おそらく食料獲得や子育てなどにおいて直接的にはほとんど何の貢献も出来ないような人も含まれていた可能性が高そうである。
パフォーマーという存在、あるいは花とタネ
わたくしは大学という存在を拒絶したし、研究者になりたいという意識は若いころはあまりなかった。
「自分がやっていることを研究なんかと一緒にするな」みたいなことを考える時もあった。
若いころのわたくしは、自分は表現者なのだという意識が強かった。表現という言葉に神秘的な含みを持たせることもあった。
日本語で表現活動というと、例えば楽器の演奏なども含むのが通常である。
わたくしは最近はほとんど楽器に真剣に向き合っていないが、それなりのエネルギーを投入したこともある。でも明らかに、プレイヤーというのはわたくしの本分ではないという感じがする。
楽譜の通りに演奏するのであれば、通常は「創作」とは言わない。「創作」よりも「表現」のほうが適用範囲が広いものだといえそうだ。
いろんなことがあって、わたくしにとっては「創作や研究」という言い方が一番落ち着くものとなった。
「創作と研究」だと、それぞれは別物だと区別しているという感じが出る。「創作や研究」であれば、実はすべては創作なのだというのが正しいかもしれないし、実はすべては研究なのだというのが正しいかもしれない。
ちなみに、ちょうどわたくしは今回の記事を書き始める直前の2025年4月21日〜4月25日あたりに、短編小説の構想を練っていたところだ。この時にタイトルも固まった。
タイトルからは小説の内容を推測するのが難しいような、そんな小説。
現代日本では、成人してからほとんど小説を読まず、ましてや書く側の事情なんてまったくイメージできない、という人がそれなりに多いらしいということは理解している。
おそらく小説をめぐる営みよりも、音楽をめぐる営みのほうが、多くの人にとってイメージがしやすい。
作曲をしている人が友人や知人にいなかったとしても、演奏と作曲の対比というのは、その質的な違いがイメージしやすいはずだ。
演奏だけに注力している人と作曲だけに注力している人とでは、何か性格的な違いがあるのではないかということについても。
もちろん、シンガーソングライターなどが典型だが、両方の性質を持つことはある。
また、テクノロジーによって演奏のあり方は変質しつつある。
20世紀に起こったことで最も大きい出来事が録音の登場だろう。せっかくこの現代に生まれて、音楽に強い関心があるならば、良い録音を残すことにエネルギーを注ぐべきと思う人は多い。
そして録音を残すということと、ライブパフォーマンスには明らかな違いがある。ライブパフォーマンスは一回性が重要で、残らないからこそ意味があるのだと考える人もいる。
演奏という行為そのものではなく、「録音を残す」あるいは「トラックをつくる」という行為は、果たして作曲に近い行為なのだろうか?それとも演奏に近い行為なのだろうか?
原曲からの逸脱の度合いとか、どんな音の重ね方をするのかとか、そういうことで決まるのだといってしまえば、それまでではある。
インターネットの存在によって、パフォーマンスのあり方は急速に変質しつつある。
例えば最近、わたくしはよくVRChatをやっている。
今回の記事を書いている時も、基本的にはずっとVRChatをデスクトップモードで立ち上げたままにしている。
VRChat内のイベントでは、「会場」が確かに存在していて「会場」にいる人にライブパフォーマンスをみせるような、そういうイベントもある。
基本的には「ライブ」といっていい。
でもその会場の様子を同時にYouTubeでも流していて、しかもYouTubeにおいては「アーカイブ」という形であとから誰でもいつでも再生できるようにしている場合がある。
こういうものは、どう考えればいいのだろう。
最近はこういうケースがとても多いのだということは頭の片隅に置いておく必要はありそうだが、こういった事情は今まさに変質しつつあるところでもある。
1990年代のインターネットのことを思い返してみると、わたくしにとってはインターネットというのはとにかく文章を読むための場所だった。
特に印象に残っているのが1998年ごろの「絶望の世界」や、桑島由一( https://x.com/e_ticket )による「クリアラバーソウル」である。
インターネットは何よりもまず文章を発表するための場所であり、人々は面白い文章を求めてインターネットに引き寄せられてくるというのが当然のことだと思っていた。
日本では2005年あたりからブログブームということがいわれていたが、これも当然ながら文章を発表する場所としてのブログというのが前提である。2005年前後に一時的にブログによって文章の存在感が高まったように見えたが、結局は「SNS前夜」であると同時に「動画サイト前夜」だった。
ブログブームの時は真性引き篭もりhankakueisuu( https://x.com/makoto_e_tanaka )が印象に残っている。ただし、2007年になってからのものをわたくしはほとんど読んでいない。
わたくしの場合、文章を求めて人々がインターネットに引き寄せられてくるはずだという前提はかなり最近まで続いた。
2023年11月にVRChatを始めてから、VRChat内には小説投稿サイトを利用している人が極端に少ないことに気づいて、かなり違和感があった。
「小説家になろう」ユーザーでありカクヨムにもハーメルンにもアカウントがある人がVRChat内で話しかけてきて、VRChat内でのフレンド登録をしたりもしたのだが、「小説投稿サイト使ってる人、少ないですよねー」というようなことをお互いに言い合って、わたくしは微妙に落ち込んでしまった。ちなみにフレンド登録はしたけど、その人とやり取りをしたのはその一回限りだ。
思ったよりも若い世代が多いことにも気づいた。2024年時点で20歳の人はつまり2003年か2004年の生まれで、3歳時点ですでにYouTubeがあった世代だ。「生まれる前から家庭用インターネットがある」なんてのは序の口で、物心ついた時にすでにYouTubeがあった世代なのだ。これはある意味ではショックだった。
わたくしは2024年夏にようやく、ことの重大さというものを認識した。
インターネット全体が、タネをやり取りする場所から、花を展示する場所へと変質してしまっていたのだ。
わたくしがジェネシスブロック記事( https://note.com/cleemy/n/n96474b06fa3b )を書いたのは2023年夏で、この時点ではこの変化をはっきりとは認識していなかった。実際に記事を読んでいただければ分かるが、動画を面白い存在として認めつつも、動画を周縁的存在として認識しているのは明らかだろう。「そういう時代なのか」などと言いつつ、どういう時代なのか分かっていない感じがする。
このジェネシスブロック記事では触れなかったが、1990年代の個人サイトといえばランキングサイトの「ReadMe!JAPAN」が有名だった。
「ReadMe!」が全サービス終了へ - ITmedia NEWS(2008-02-08)
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/0802/08/news052.html
「Wayback Machine」によるアーカイブは以下。
https://web.archive.org/web/19990000000000*/http://readmej.com/
これが2008年に終了したというのは象徴的かもしれない。2008年というのは、まさに動画とSNSが重要になってくるタイミングだ。
ちなみに小説投稿サイトとして非常に有名な「小説家になろう」の登場は2004年である。
この「タネから花へ」の変質を認識していたとしても、実際に2025年時点で小説投稿サイトを利用する人々の大部分は「どこ吹く風」という感じではあるのかもしれない。
動画や音声コミュニケーションを求める人が多数派であったとしても、それは世の中の全体の傾向なのであって、インターネットという存在の位置づけとは関係がないと考えるのが当然になっているのだろう。
1990年代はインターネットを利用している人間であるという時点で偏りがあった。全員がパソコンユーザーだった。もう今はスマートフォンが前提で、生まれる前から動画サイトがあったような人々がインターネットを利用している。
1990年代は確かに「ネットユーザー」が存在した。
でももう今は存在しないのだ。
わたくしのような人間を置き去りにしたまま、彼らはいったいどこに行ってしまったのだろう、と思うこともある。
わたくしは2025年現在でも、スマホをほとんどまともに使っていない。ある程度の時間を投入したスマホのゲームといえば、『Monument Valley』とテトリスぐらいのものだ。ソシャゲの「ガチャ」と呼ばれるものには1円も使ったことがない。
日本のスマホユーザーはLINEの使用率が高いが、わたくしはLINEに一度もアカウントを作成したことがない。インスタグラムやTikTokも同様だ。
わたくしがスマホになじむ日は来ないかもしれない。
わたくし個人の感傷はさておき、またインターネットがからむかどうかとは無関係に、人間のあらゆる活動というものを俯瞰的に考えてみたい。
その活動は、花に近いものなのか、それともタネに近いものなのか。
例えば教師は通常、授業の時には見られる自分を意識して授業を行う。日本の義務教育では、教室で授業をしている時の教師を写真に撮れば、たいていはその人が教師であることは一目瞭然だ。授業をしている最中を撮影したものであることについても。これらは「見たまま」だ。だから花に近い。
そして授業では教師の視点は状況の一部だ。教師がどこに立つのか、どの方向を見ているのか、興奮しているのか落ち着いているのか、こういったすべてがリアルタイムで影響を与える。
これとは対極のものとして、時計の修理を考えてみる。これはタネに近いだろう。分解された状態の時計を見ても、ふだん時計の修理をしている人でなければ、それぞれの部品が何を意味しているのかは分からない。
そして、修理をしている人が居眠りをしているスキに部品が逃げ出したりはしない。
時計本体や部品が並んでいる周辺こそが宇宙なのであり、修理をしている人は宇宙の外から介入する。
このように考えていくと、1990年代の「ネットユーザー」というのは、タネに親和的な人々の比率が高かった人々だったといえるのだろう。
1990年代からイラストを公開している人はいた。文章よりはイラストのほうが花に近い。でもここで重視したいのは比率のことである。
そういえば、VRChatを初めてから、あらためて気づかされたことがある。
わたくしはつくづく、他人から見られる自分というものに興味がないのだ。物理現実において、身につけるものによってあまり気分が変わらないことには気づいていた。これはVRSNSにおいても同じだった。
VRChatではアバター改変と呼ばれるものに多大なエネルギーを注ぐ人が多いが、ワールド制作に関心を持つ人はかなり少ない。これにも軽いショックを受けた。
いずれはわたくしもアバター改変をしてみるかもしれないが、わたくしの場合は技術的制約が気になるからであり、ほとんどのユーザーと動機が違うかもしれない。
ワールド制作の場合は、花とタネの両方の性質がありそうである。そして配布を前提としたギミックなどはかなりタネ寄りだ。
そしてイベントはアバター改変よりもさらに花寄りだろう。
花の側のユーザーに、タネ寄りの営みへの敬意が欠落していたり、極端に単純化したりすることがあるように見えるのは気になるポイントだ。
もちろん逆に、タネの側のユーザーが花の側の営みを単純化しているようなケースも多そうだ。
外集団同質性バイアス(out-group homogeneity bias)のようなものが作用していることもあったりするかもしれない。
外集団同質性バイアス - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E9%9B%86%E5%9B%A3%E5%90%8C%E8%B3%AA%E6%80%A7%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9
ちなみにわたくしは物理現実において、服のデザインにまったく関心がないというわけではない。でも、自分もまた服を着る存在であり、服を着ている自分を見られる存在でもあるという事実は混乱をもたらす。
人々が服を着るという営みは、あくまでも宇宙の外から眺めていたいのだ。
VRChatを始めてから、わたくしはOutvoke(アウトヴォーク)というライブラリ兼フレームワークを書き始めたのだが、これもタネとしての性質がかなり強い。
cleemy desu wayo / outvoke · GitLab
https://gitlab.com/cleemy-desu-wayo/outvoke
説明すると長くなるのでここでは控えるが、これはVRChat専用のプログラムではない。そしてVRChat専用でないということと、タネとしての性質は関連がある。
また、2025年5月時点ではまだ書きかけの状態なので注意。2025年になってからコミットがまったくないが、開発が放棄されたわけではなく、わたくしは一人のユーザーとして活用し続けており、わたくしの環境ではずっと快調に動いている。
なお、これはUnityの仕様とはほぼまったく無関係のものであり、Unityを開発環境として使う人のためのライブラリではないことにも注意。また、基本的にはLinuxユーザー向けであると同時に、Rubyのコードを書きたい人のためのものである。
ところで、この「タネから花へ」の流れは、3Dゲームの隆盛とも関係があるかもしれない。
おそらくは「レトロゲーム」のほうがタネ寄りだ。特に2D。
ほとんどの2Dゲームは、状況を神の視点で眺めながら操作する。宇宙の外からの操作と言ってもいい。たいていの2Dゲームでは視点が状況の一部ではないが、一人称視点の3Dゲームは視点が状況の一部となっている。
ここまではまあ、当然といえば当然の話ではあるのだが、ここに実に興味深い撹乱をもたらすのが鏡という存在である。
VRChatでは、物理現実では難しい巨大な鏡を設置可能である。空中に設置したりすることも可能である。そして多くのワールドでは、鏡をオンオフできるスイッチがある。
こういう鏡を前に複数人で集まると、一人称視点をキープしながらも鏡を経由して状況をある程度は俯瞰的に見ることが出来る。
そしてこれはVR感覚やファントムセンスとも関連してくる。ここでは掘り下げず、以下の動画を紹介しておくだけにする。
メタバースで五感フル活用!VR感覚・ファントムセンスとは!? - YouTube(2022-07-08)
https://www.youtube.com/watch?v=yE2muevVXsw
(「ツタエルちゃんねる / tsuta-l channel 大蔦エル」、9分20秒ほど)
ちなみに鏡についての話題は03:10〜あたりから。
ゲームは必ずしもオタクのものとはいえないが、オタク史においても「タネから花へ」はあるだろうか。
AKB48のスタートが2005年だったというのは、今から考えると象徴的ではあるのかもしれない。ちょうど動画やSNSが浸透する前夜だからだ。
ライブ会場のような場所に物理的に足繁く通ったりするような、そういうオタクというのはAKB48登場以前はさほど目立つ存在ではなかった。
1990年代のインターネットにおける個人サイトでは、アイドルのライブのレポートというのはかなりマイナーなものだったはずである。それをやるとしても、構築感のある濃厚な批評という側面があるものが目立っていた。
ライブの批評をするという行為は明確に「タネから見た花」になるわけだが、現代のSNSではひたすらに中身のない言葉で一体感を強調するのが普通だ。ペンライトやケミカルライト(サイリウム)などの使用などについては、自分たちもまたライブを彩る存在であり、花の一形態であるというのが前提となる。
現在でもオタ芸(ヲタ芸)などの言葉にオタクらしさが残っているとはいえるのかもしれない。場の空気を読んでひたすらに大人の対応を続けるのはまったくオタク的ではなくむしろヤンキー的であり、オタクというのは一体感を拒絶するものだというのが何となくかつての暗黙の了解としてあったような気がするのだ。
場を荒らすという行為がオタク的というわけではないことには注意が必要だろう。一体感を拒絶しつつ、ギリギリのところで場を荒らすことにはならないというのがポイントだ。
ライブ中にひたすらメモをとるなど、どこまで意図的にやっているのか分からない行為もオタク的といえるかもしれない。
なじむならなじむ、荒らすなら荒らす、というのがヤンキーであり、どちらでもないというのはヤンキーの世界観においては不気味であり異様である。
ここであらためて、このセクションの冒頭で示した演奏と作曲の対比を考えたい。
曲というのがタネの側なのは明らかだろう。楽譜を見ても、ほとんどの人は実際に演奏した時にどんな音になるのかがイメージできない。でも演奏を聴けば、どんな曲なのかは「聴いたまま」だ。
2007年登場の初音ミクなどのボーカロイドがもたらしたものとして、パフォーマーの友達がいない作曲者が完成品のトラックの発表を容易にしたという要素がある。
せっかく曲があっても、ボーカルが乗った時にどうなるかが「聴いたまま」でないというのが、歌ものを発表する時のハードルだったはずだ。
ボーカロイドの表現力が限定的だったことが、歌い手による「自分ならもっと良い花に出来る」という意識を喚起して、カバーがたくさんアップロードされるという流れも生んだ。
もし曲がタネなら、作曲する人はタネそのものではなくタネをつくる人なのではないか、ともいえる。あるいはタネを設計する人、でもいいかもしれない。
でも基本的には「タネに親和的」という言い方でいい。
プレイヤーと違って、作曲をする人は「いかにも」という要素がないことが多い。「作曲とかやってるんですけど」と言われて初めて「ああ、そうでしたか」となる。「見たまま」ではないのだ。
パフォーマーは自分自身が見られる存在であり、そのことが本人の意識にも影響してくる。
視覚表現において、「美術」よりの人は、なぜ服がダサいのか?ということについても説明がつくかもしれない。
この「美術」はおそらく「アート」ではない。
2025年現在の日本でアートという言葉はあまりにも多様な場面で使われるようになってきているが、美術という言葉には、社会人が社会人のまま足を踏み入れることを許さないような空気がある。この敷居をまたぐのであれば、ひとまず社会人であることはやめていただきます、というわけだ。
アートにはこれがないため、アートという言葉が侵入的に感じられることすらある。すべてを社会人の事情の中に回収してしまおうという密かな企みを感じてしまう。「作品」が「コンテンツ」と化しやすいともいえる。
もちろんこういったことは、わたくしの被害者意識が強すぎるだけなのかもしれない。
だが、とりあえずここではひとまず「アート」については考慮せず、「デザイン」と「美術」を対比したい。デザインはヴィジュアルデザインに限定していると考えてもらっていい。
当事者の意識はともかく、世間的な期待としては、やはりデザインをやっている人はそのデザイン性を「見たまま」として体現していてほしいというのがある。
つまり、デザインは花に親和的で、美術はタネに親和的なのではないか、ということだ。
これはあくまでもデザインと美術を対比するとこうなるというだけである。音楽におけるパフォーマーと比較するならば、やはりデザインと美術はともにタネの側ということになるだろう。
パフォーマーという言葉からは、俳優を連想する人も多いかもしれない。
花とタネの対比は、実写映画や実写ドラマなどにおいて、原作者の扱いが雑になりやすいのはなぜなのかということを考えるヒントにもなりそうだ。アニメの場合は原作者が生々しい存在なのに、実写ではまるで原作者という人間が存在していないかのようになってしまうことがある。
通常、パフォーマー同士の集まりやパフォーマーを立てることが前提の集まりにおいては、「見たまま」が通用しない人は認知負荷が大きい存在となる。
演劇における脚本家兼演出のようにほとんど神であるも同然の存在であれば、例外的存在として尊重されることもあるだろう。
ボーカロイドの場合は、ボカロP(作曲者)と歌い手の間に初音ミクなどがいたわけだが、実写映画や実写ドラマではそういう存在はいなかった。生成AIの登場によって今後どうなるかは分からない。
ちなみにわたくしは小説よりも先に演劇の台本を書く面白さに気づいた。でもこれは遊びの延長線上でしかなかった。
わたくしの過去における「見たまま」のエピソードでは、漫画のことがある。
わたくしは小学3年生の時に漫画を描いていたのだが、このことは他のクラスの生徒にとって強い違和感を感じるらしいことを知った。
わたくしは小学校6年間ずっとメガネをかけていて、ガリ勉っぽく見えていたらしかった。その雰囲気と、自由帳に漫画を描いている生徒というのが一致しないようだった。
小学校のころからわたくしがINTPらしかったのかというと、よく分からない。同じクラスの人間には、表面的にはENFPっぽく見えていたかもしれない。
花とタネの対比について、性格分類との対応関係についても考えてみたい。
まず、見られるということとリアルタイムでの関わりが重要であることから、パフォーマンスはEI指標におけるE型に親和的といえそうである。
I型は見られることに無頓着すぎるか敏感すぎる状態になりやすく、リアルタイムよりは非同期コミュニケーションに親和的だ。
また、パフォーマンスは通常、パフォーマーが見られる存在となる現場を必要としており、その現場の一部となって自分自身が機能する必要がある。これはTF指標におけるF型に親和的といえそうだ。
T型は状況の一部となるよりは、状況から離れて状況を対象化するほうが落ち着く。
つまり、花はExFxに親和的で、タネはIxTxに親和的ということになる。
潜在的な親和性を考えるとそうなるというだけで、パフォーマーはExFxばかりであるということを意味しない。
義務教育の教師の場合は他の教師との差別化に悩む必要はないが、表現活動においては違和感も重要である。他のパフォーマーと同じということは、埋没するということでもある。
IxTxだからこそ出せる違和感が良い方向に作用しているパフォーマーもたくさんいるだろう、ということだ。
ここでIT(Information Technology)という存在についても考えてみたい。
おそらく世間的には、タネの側の職業というのはITエンジニアのイメージと一致しているのではないかと思う。一日中パソコンに向かって何か作業をしている人々。
ただし、ITエンジニアリングの実務もそれなりに多様ではある。
例えば、インフラの管理よりもコードを書くことのほうがタネとしての性質が強い。コードを書くこと(プログラミング)においては、アプリケーションを書くよりもライブラリやフレームワークを書くほうがタネとしての性質が強い。そしてコードを書くことよりも、設計をしたりアルゴリズムを考えたりすることのほうがタネとしての性質が強い。
脱Excelのメリットをいくら強調してもなかなかうまくいかないのは、Excelには「見たまま」の強力さがあるからかもしれない。それぞれのデータに直接触るという分かりやすさがある。
Excelシートはそれ自体が完成された花なのである。
Excelとかけ離れた性質を持つものとして、Xにおけるデジタルアートの #つぶやきProcessing タグは注目に値する。140字以内という制約のコードから、複雑な画像やアニメーションが生まれる。ここではURLだけを示しておくが、例えば以下のようなものがある。
https://x.com/nagaT9090/status/1844564622852202501
https://x.com/KomaTebe/status/1871902272269242584
https://x.com/yuruyurau/status/1890751857116532978
実際に見てもらえれば分かるが、コードから実行時の様子(アニメーション)を想像することはプログラマーでも難しい。
実行時のアニメーションだけを見れば花としての性質が強そうに見えるにも関わらず、コードはタネとしての性質が強く、コードを書く行為はタネの設計に近くなる。
そしてアニメーションのここをこう変えるにはコードのどの部分をどう変えればいいのかというのは、直感的にはすぐには分からないことが多い。
Excelの場合は、このセルをこのデータに変えたい、という操作が直感的に出来る。
IT方面の人がExcelのデメリットをいくら強調しても、それはExFxにとっては自分たちが大切にしている感覚を否定され続けるようなものになってしまうかもしれない。
プレゼンを重視する会社とExcelとの親和性の高さも、これで説明がつく。
「IT」は「IxTx」の略でもあるのかもしれない。
2024年あたりからは、AI(特にLLM)との相性の良さからYAMLが再注目されているのは気になるところだ。YAMLは花とタネの両方の性質があるかもしれない。
このあたりのことは、わたくしが2013年ごろから構想を練っていたデータフォーマットのこととも関連してくる話で、わたくしの言語についての関心のいわばメインテーマといえることでもあるのだが、それはまた別の機会にしよう。
ちなみに #つぶやきProcessing に類似したものとして、英語圏における1980年代のメガデモ文化がある。極端に小さいプログラムから、実行時に想像もできないようなアニメーションを表示する。
新型コロナのパンデミック以降には、GitLabが標榜するドキュメント文化が日本で注目されたりもした。これはIxTxに親和的といえる。
プレゼンを重視する職場はドキュメントを重視しない。文章というものは業務用チャットかプレゼン資料の中にしかなく、揮発性が高い。彼らにはタネをつくるという発想がないのである。
GitLabにとってのドキュメントとは、残り続けるものであり、書いた直後には誰も必要としていない文章であったとしてもいずれ役に立つ日が来るのが前提であり、個人の興味や問題意識にいつでも応える形で検索によってたどり着ける先がドキュメントだという前提だ。質問があった時にはドキュメントへのポインタを示すことで回答とする文化を生む。
なんとなく想像がつくと思うが、今回の記事についてわたくしは「それについてはあの記事に書いたから」とあとから言いやすいように書いているつもりだ。
論理性や厳密性が重要なのではなく、一度書いておけば、つまり一度タネとして機能するように作り込んでおけば、あとから何度でも展開することが出来るというのがポイントだ。
たとえ論理的で厳密であっても、非常に多くの言葉を用いており、それでいて特定の状況にしか適用できないものはドキュメント志向とは相性が悪い。特定の状況にしか適用できないというのは、揮発性が高いともいえる。花の寿命は短い。
GitLabのような環境については、ExFxにとっては苦痛でしかない可能性があったりするかもしれない。
ExFxでありかつ才能のあるプログラマー、という人だっているだろう。わたくしは、すべての職場がGitLabのようであるべきなどと考えているわけではない。
ところで、ITは全体的にタネ寄りだとはいえるものの、研究活動と対比するならば、そもそも実務というのは花の側である。
だからこそ、実務にプライドを持っている人が創作や研究について論じると混乱をもたらすことがある。
サイバーセキュリティでは研究と実務の境界は曖昧かもしれないが、プログラミングにおいては研究と実務はかなり乖離している。
研究者から見れば、ほとんどのITエンジニアは花の側なのだ。
ちなみにニュートンは卵の代わりに時計を茹でたことがあるとされる。
これも実際にあったエピソードなのかどうかは分からないが、事実だとしたら実務能力の無さは驚異的だ。こんな人にいったい何を任せられるのか、ということになりそうだ。
でもニュートンは根っからの研究者ではあったのだろう。
そういえば1990年代のインターネットでは、実務能力の高さを誇ったりするというのはものすごく下品で恥ずかしいことだったはずである。
現代のSNSというのは、ものすごく下品で恥ずかしい場所になってしまっているのではないかという疑いがどうしても拭えない。
研究の場合でも、何らかの形で実務がからむことはあるだろう。特に実験を必要とするもの。ニュートンも錬金術に関しては実験をしていたようだ。
たいていのジャンルでは、応用研究よりも基礎研究寄りのほうが、タネをつくるという要素は濃くなりやすいかもしれない。
「基礎研究」という言葉は、「イロハのイ」ということではない。基礎(basic)ではあっても初歩的(elementary)ということではなく、つまり他の大勢の研究者たちが研究の土台にできるような研究ということである。
基礎研究寄りのことであっても、聴衆を前にした講義などの活動はタネよりも花に近くなりそうだ。
ここで、アインシュタインにもう一度ご登場をお願いしてみよう。
数学者の小平邦彦がアインシュタインの講義を聴いた時の様子が「プリンストンの思い出」に書かれている。以下は岩波現代文庫版『怠け数学者の記』(2000年刊)のP.174より。
アインシュタインは上着なしの襟のつまったジャケツを着て現われ、何かボソボソ言いながら黒板に式を書きはじめた。はじめ何をいっているのかわからなかったが、よく聴くと、式の文字を「アー」、「ベー」、「ツェー」、……とドイツ流に読んでいるのであった。時々英語の単語を忘れて「transponie…」などとドイツ語で言いかけると、聴講者の一人が「transpose」と言って後押しをする、といった調子であった。
そういえば、アインシュタインの場合は評価が高まるまでの時間差も、実に「タネ」らしさがあるといえそうだ。
もちろん、ニコラ・テスラのような人もいることには留意する必要があるかもしれない。研究内容とパフォーマンスが結びついていて、しかも研究が実際に革命的だったようなケースもあるわけだ。
「研究者」という肩書には、いろいろなものが含められることがある。
実際にはサイエンスコミュニケーターといえるような場合があり、これは花に近くなる。
また、コーディネーターやプロデューサーとしての性質が強い人もいるだろう。こういう活動も、パフォーマーとしての性質を持っている。
表現活動などにおいては、パフォーマーとプロデューサーを対比させる場合は、パフォーマーが前に出てプロデューサーが奥に引っ込むことがイメージされやすい。特に2007年あたりからの「アイマス」シリーズのヒットにより、「プロデューサー」という言い方に父親目線でパフォーマーを育てるというニュアンスが込められることがある。
しかし実際には表現活動でも、録音などを前提としてパフォーマーが奥に引っ込む場合も多々ある。
ライブ活動をまったくしない場合は特にそうだが、プロデューサーこそが見られる存在として動き回ることになり、逆転現象ともいえることが起こる。
プロデューサーが素顔をさらして公に発信したりしていなかったとしても、舞台裏においての各種調整などの立ち回りにおいて常に見られる存在として機能し続けることが求められる。
花とタネの対比においては、重要なのはパフォーマーであるかどうかというよりも見られる存在としてリアルタイムに関わり続けることである。
プロデュースの一環としてパフォーマーを育てるような活動はイメージはしやすいが、タネの側の人を育てるような活動についてはどう考えればいいだろうか。タネを発芽させて花へと育てるということではなく、タネの側の人を育てるような。
花の場合はいろんな意味で、リアルタイムでの関心を呼び起こす。現場において、素早く注意を引きつける存在。
花は「起こす」のが仕事だ。
でもタネは逆だろう。動物に食べられることによって遠くに運ばれるような場合は顕著だが、タネの場合はとにかく目立たないことが重要だ。短期的には、他者の関心を「眠らせる」必要がある。
何よりもまず、タネをつくるのは静かな環境が必要だ。
おそらくこの場合、プロデュースというよりは「寝かせる」という行為になるのではないか。
うまく寝かしつけるのは、何もしないということではない。
たとえ本人が放っておいてほしいと強調したとしても、本当に何もしないことが良いことだとは限らない。
タネの側の人の才能が認識されると、権力志向の強い人間が的はずれな関与をしたりコントロールしようとしたりする機会にさらされやすくなる。
本人を喧騒やパワーゲームから隔離するための巧妙な立ち回りこそが重要になる。
これはのちのセクション「一人の時間とダウンレギュレーション仮説」や「音と住環境」で語ることとも関連する。
ところで、タネにはそれ自体に意外性を内包しているという側面がある。
タネそのものを外側から視覚的にとらえても、美しい花を想像することは難しい。
例えば現代の日本で発売される様々な書籍の中では、岩波文庫などはタネとしての性質が強い。有名イラストレーターの大きなサイズの画集と比較してみると明らかだ。
岩波文庫はおそらくは意図的に同質性が強い外観になっている。
カバーを含めたものも考えると、2025年現在では講談社現代新書や光文社古典新訳文庫なども同質性が強いといえるかもしれない。ただし、2004年10月からの講談社現代新書はせっかく抑制的なデザインがウリだったのに、かなり派手な帯が巻かれることが多い。
太宰治(1948年没)は、死後約60年後の2007年に小畑健のイラストによる表紙で集英社文庫版『人間失格』がヒットしてしまったために、表紙をめぐる議論に巻き込まれやすい存在である。2009年には男性アイドルであり俳優の生田斗真が表紙の角川文庫版『人間失格』も出版された。
もちろんこういう表紙に対する反発もある。これはつまり、「古典文学を花として提供して何が悪い」と考える人と「タネはタネのままであるべきだ」と考える人の対立かもしれない。
ちなみに太宰治には、小説の表紙が重要な要素となる短編「東京だより」があったりする。
3,000字に満たない短い小説だが、2007年から巻き起こったことを前提にすると、かなり笑える内容となっている。
そういえば、なぜライトノベルはタイトルに情報を詰め込むものが多いのかというのも、タイトルから内容が推測できるほうが花としての性質が強くなるからかもしれない。
短歌や俳句などでは、同じように情報を詰め込むとはいっても、折りたたまれた状態のものが多い。展開を必要とするものはタネに近い。
展開を必要とするということは、いざ展開に失敗すると滑稽な状況が生まれることがある。
古典落語の「ちはやふる」が有名だが、タネを展開する時の失敗は江戸時代から意識されていた。
古典文学においては、書き手が男性に偏っているかもしれない。女性から見た花が語られにくい可能性がある。
日本では平成の約30年間(1989年〜2019年)に女性の欲望が様々な形で可視化された。少女漫画の『花より男子』(連載は1992年〜2004年)は男性も花であることが前提の世界だ。女性向け恋愛アドベンチャーゲーム『うたの☆プリンスさまっ♪』(2010年発売)では主人公の女性が作曲家志望で、その周囲にはアイドル志望の男性たちがおり、つまり明確に「タネから見た花」を意識したものとなっている。
こういった欲望がどれだけ可視化されようと、IxTx女性が学校などにおいて異端視されやすい傾向についてはあまり変わっていない可能性もありそうだ。
「意外性」と「見たまま」を対比的に考えてみると、基本的には「見たまま」というのはS型に親和的といえる。S型は世界を「あるがまま」にとらえることが可能だと考える。
「見たまま」が通用せず、意外な意味があったり、想像だにしないものとつながっていたりするのはN型と親和的である。
つまり、タネというのは、タネであるという時点でうっすらとN型との親和性をまとっている。
ただし、似たようなタネを見慣れている人にとってもそうなのか、という視点もまたありうるだろう。
例えば時計の修理を考えてみる。時計の内部構造に詳しくない人が机に並べられた部品を見た時には、これらの小さな部品が組み合わさって時計として機能するのがほとんど奇跡的に思えるということがありそうな一方で、似たような時計を毎日のように修理をしている人が見れば、ただの日常でしかないということになるかもしれない。
タネだから門外漢には驚きがあるという話のか、それとも専門家あるいは同業者にとっても驚きのあるタネといえるのか。
おそらく、専門家や同業者にとって「このようなタネはいまだかつてない」という驚きをもたらすような活動は、INTxに親和的といえそうである。
逆に、すでによくあるタネを堅実につくりあげる活動はISTxに親和的だ。「そうそう、タネとはそうあるべきだ」という他者の期待に応えるもの。
S型と話が噛み合わないと感じるxNTxは多いが、高知能のISTxが相手の場合は、会話が出来ないというほどではないことが多い。これはISTxが専門領域における定番や定石に馴染みのあるものとして取り込みつつ、世間的には理解不能とみなされるものを扱うことに慣れているからかもしれない。相手がISFPの場合もそれなりに噛み合うかもしれない。
そして、この「よくある」と「思いがけない」の対比はパフォーマンスの中にもあるだろう。
偶然性を取り込み、驚きをもたらす花はENFxに親和的であり、あらかじめ定まった「そうそう、そこにはそういう花があってほしいんだよ」という期待に応える花はESFxに親和的であるといえるかもしれない。
パフォーマンスの場合は、セトリ(セットリスト)を考えるということがパフォーマンスの活動の一環になることがある。本番でのパフォーマンスより、むしろセトリを考えるという行為の中で「思いがけなさ」が発揮されることもありそうだ。
アドリブには予定調和を強化するようなアドリブもあり、アドリブの有無だけに着目するべきではないだろう。関係性を揺さぶるかどうかが重要だ。
なお、本番のパフォーマンスと比較するならば、セトリというのはやはりタネの側ではある。
私見だが、ESFxとINTxの対比というのは演技性パーソナリティとスキゾタイパルの対比に近いものがある。特にDSMが定義するようなものはESFPとINTJの対比が近いかもしれない。
これはあくまでも対比すれば、ということである。ESFPの大部分は演技性パーソナリティ障害ではないし、INTJの大部分もスキゾタイパルではない。
あるいは、「あるもの」に注目するならさほど類似しているとはいえないが、「ないもの」に注目すると類似性が際立つといえるかもしれない。
つまり、ESFPに欠落しているものと、演技性パーソナリティの傾向のある人に欠落しているものというのは、強い類似性がある。そして、INTJに欠落しているものと、スキゾタイパルの傾向のある人に欠落しているものというのは、強い類似性がある。
演技性パーソナリティについては、牛島定信『パーソナリティ障害とは何か』(2012年刊)の解説が良い。
「ヒステリー」という用語をめぐる話やジェンダーの話題を避けることなく、フロイトという存在も無視することなく、それでいて精神分析の世界観を押し付けるわけではない解説となっており、非常に巧妙なものとなっている。新書で15ページほどである。
また、パフォーマーとしての有名人を挙げていないというのもポイントかもしれない。具体的な誰かを挙げてしまうと、もしそれが当たっていたとしても、演技性パーソナリティの傾向がある人の戦略に巻き込まれているという側面がある。
ちなみにこの本は講談社現代新書である。
2025年現在の日本では「承認欲求」という言葉があまりにも気軽に使われる。「承認欲求」という言葉はそれによって何でも説明できてしまうため、実際には何も説明できていないということがある。
でもSNS社会において自分たちが感じている違和感の答えがどうしても欲しいと思っている人は多い。真剣に知りたいのであれば、おそらく演技性パーソナリティ障害について勉強してみて、さらにスキゾタイパルのことも知っておくというのが良いかもしれない。
ちなみに、何でも説明できてしまうような用語をわたくしは「心理学的飛び道具」と呼んでいる。
スキゾタイパル(失調型パーソナリティ)については岡田尊司『パーソナリティ障害——いかに接し、どう克服するか』(2004年刊)の解説が良い。
ASDとも類似しているために索漠とした人生を送っていると思われがちなスキゾタイパルだが、そのヴィヴィッドな内面がよく分かる解説になっている。新書で14ページほどである。
同じ作者の別の本でのスキゾタイパルの解説ではなく、あくまでもこのPHP新書の『パーソナリティ障害』の中での解説をオススメしたい。
この本でのスキゾタイパルの解説については良いと個人的には思うのだが、有名人をあまりに気軽に断定的に「診断」する作者の姿勢は批判を浴びることもある。去年(2024年)には星新一の遺族が声明を出したりもした。
ちなみにこの本のスキゾタイパルの章で直接的に名前が挙がっているのは、ユング、ヘルマン・ヘッセ、夏目漱石の3人である。
スキゾタイパルについては、どれくらい広くとるのかによって話が変わってくることには注意する必要がある。
デイヴィッド・ホロビン『天才と分裂病の進化論』(邦訳は2002年刊)には以下のような箇所がある。邦訳P.162〜P.163より。
分裂病型人格という概念にひとたび敏感になると、ほとんどの人々が以下の事実に気づくようになる。ことによると人口の十パーセントから二十パーセントにこのカテゴリーに属する何らかの特徴がみられるのではないか。
20パーセントというのはかなり多い。DSMで定義されているシゾイドパーソナリティの傾向がある人や、スキゾタイパルを熟知している人にとっても「さすがにこれはASDでいいのではないか」と思うような人も含むということになりそうだ。
また、20パーセントを「スキゾタイパル」だとみなすと、INTPはほぼ全員が「スキゾタイパル」だということになってしまうかもしれない。
しかしながら、確かに20パーセントぐらいは該当すると考えていいのかもしれない、と思うことはある。
「類は友を呼ぶ」ということわざが当てはまることもあるし、バーダー・マインホフ現象(Baader-Meinhof Phenomenon)などのバイアスのせいもあるかもしれない。
演技性パーソナリティの傾向もスキゾタイパルの傾向も、病的なレベルではなく深刻なトラブルもないというのなら、それは個性として考えていいということになりそうだ。
ネット史における「タネから花へ」は、スキゾタイパルから演技性パーソナリティへ、という流れでもある。
発達障害ブームによってこれまでスキゾタイパルの存在が覆い隠されていたため、スキゾタイパルという概念はパンドラの箱かもしれないと思うこともある。人口比としてスキゾタイパルの人が減少傾向にある、ということではないのである。
スキゾタイパルと演技性パーソナリティの傾向がある人はまったく別の世界に住んでいるように見えて、様々な形での共犯関係がある。「オタサーの姫」や「サークルクラッシャー」などの概念を考えるうえでも新しい洞察が得られるかもしれない。
さて、ここで前のセクション「対話と油絵法」での議論を思い出してみたい。そしてこのセクションにおける「花とタネ」の議論と組み合わせて考えてみたい。
前のセクションでは、対話のシーケンシャル性に着目しつつ、シーケンシャル性とxSxJが親和的であり、油絵法のランダムアクセス性はxNxPに親和的である、とした。
組み合わせると、以下のような対応関係をつくることが可能かもしれない。
ESFJ……シーケンシャルな関与で花であり続ける
ENFP……油絵法的な関与で花であり続ける
ISTJ……シーケンシャルにタネをつくる
INTP……油絵法でタネをつくる
これはかなり強引なマッピングだということには注意してほしい。現実はきれいに割り切れるものではない。
Xには「類型界隈」と呼ばれるものがある。INTPを自認しつつ類型界隈で継続的に発信し続けるという行為は、「シーケンシャルな関与で花であり続ける」というものにどうしても近くなる。つまり、INTPによるそういう発信は、どこかで無理をしているものだと思ったほうがいいかもしれない。
もちろん、そういうフォーマットに合わせるからこそ見えてくるINTPの特徴もあるはずだ。
もしINTPを自認する人が全員「油絵法でタネをつくる」という姿勢でしか発信しないとしたら、INTPの考えていることはなかなか共有されないかもしれない。xNxPであるがゆえに、いつまで経っても完成しないということもあるだろう。
「油絵法でタネをつくる」という行為は、自分が産み出すものについては残り続けることを期待することになる。
すぐに話題になることよりも潜行性のようなものを求めつつ、一方で人との関係においては揮発性を求めるという逆説がある。
残り続けるものというのは、その間接的影響が蓄積していくと、土壌としての性質を持つようになる。
わたくしがこういう記事を書くのも、土壌を豊かにする効果が多少はあると信じているわけだ。
関わりたい人
油絵法についても、花とタネの対比についても、この記事で語ったことはほんのダイジェスト的なものにすぎないのだが、その本質は決して複雑なものではない。
わたくしの言動に関して違和感があったという人も、これまでのセクションで書いたことを読んで謎が解けたと思う人もいるのではないかと思う。
そして世界に対するわたくしの基本的な構えが「油絵法でタネをつくる」というものであることを理解してもらったうえでなら、語りやすくなることがある。
それはつまり、わたくしには関わりたい人がいないのだ、ということ。
関わりたい人がいないということは、誰とも関わりを持ちたくないということを意味するわけではないし、世界全体を拒絶したいということでもない。
でも、ただただシンプルに、関わりたい人というのがいない。
これは2017年あたりから、特にそうだ。
では2016年あたりとか、あるいはもっと以前には関わりたい人がいたのかというと、実際のところはよく分からない。
自分では関わりたいと思っているつもりでも、結局のところ「あの人は自分に関わりたいと思っているはずだ」という根拠のない確信がベースにあって、わたくしが関わりたいというわけではなかったのかもしれない。場合によっては、わたくしの側にほとんど関係妄想といえるようなものがあったこともあるだろう。
2017年夏にあった出会いでは、「なぜ今までこの人の存在を知らなかったのだろう」と思うこともあった。関わりたい人をあらかじめ設定してしまっていたとすると、この出会いはなかったかもしれない。
ところで、「あなたという個人に興味があるわけではない」ということは、証明しようと思ってもできない類いのことである。
「私に興味があるんでしょう?」と急に質問されると「えっどういうことだろう」と思って実際に興味を持ってしまうこともあるだろう。
わたくしは中井久夫ですら、死んだことに4ヶ月以上も気づかないという有様である。これを読んでいるあなたが、たとえ執筆時点のわたくしがその存在を認識している相手であったとしても、あなたが死んでも4世紀ぐらいは気づかないと思っておいてほしいのである。
「関わりたい」とは少し違う視点として、他者との関わりにおいて「これがしたい」というのがないのもある。
どちらかというと、わたくしはやりたいことがたくさんある人間だ。ただし、「やりたいこと」で思い浮かぶのは基本的には一人で出来ることばかりだ。
この一人でやりたいことについても、具体的なことを挙げてもあまり意味がない。要するに、考えることと書くことがメインなのだ。具体的な作業が発生する場合でも、それはあくまでも考えるためのトリガーとしての作業だ。
オゴってくれる時に「何が食べたい?」という質問も、かなり悩むことが多い。「いやいや、あなたは何が食べたいの?」とつい思ってしまうからだ。話したい話題が特にない時は「一人でマクドナルドに行きたい」などと思ってしまうが、それを言うわけにはいかない。
「どこに行きたい?」のような質問をされる機会はほとんどない気がするが、何かガイドなどをお願いできる相手でもない限り、もし聞かれても「いやいや、あなたはどこに行きたいの?」と思うだろう。
もちろん、個人的なことを勝手に決めてほしいという話ではない。
ちなみに、わたくしは基本的には、他者との情緒的なつながりというのは求めていない。
ただし、自分に似ていて、しかも自分と同じことに悩んでいるような誰かが情緒的なつながりを求めてきたという場合、それをはねつけるということはない。
わたくしは自分に興味がある人に興味がある。
だからこそ、どんな風に興味があるのかは重要である。
わたくしの書いたものをじっくり読んで、それでもなお興味を持つのかどうかは気になっているポイントだ。
例えばcdwact(活動報告)には、ふだんわたくしが考えていることが書かれている。
cdwact(cleemy desu wayo活動報告)|cleemy desu wayo|note
https://note.com/cleemy/m/mb0f02523402c
実際に書かれていることは考えていることのごく一部でしかないが、それでもかなり広範囲の話題に触れている。また、わたくしが興味がないことというのはほとんど書かれていないといっていい。
わたくしに興味がある人であるにも関わらず、cdwactに書かれていることについてどこにも引っかかるポイントがないのだとしたら、その人は何か大きな勘違いをしているということになる。
cdwactや長文記事の中の気になる話題をプリントアウトして「これのここの記述なんだけど」と話を振ってくれるのはとても助かるかもしれない。そういう人に遭遇したことはまだないのだが。
わたくしにとっては、そういうものこそが自己紹介として機能するのは確かだ。
その人がアピールしたいことを口頭で聞いても、しばらく経つと忘れてしまうか、あるいは逆に「ああ……いや、まあ、もう知ってますけど」という感じのことが多いだろう。
それよりも、「なるほどこの人は、あのわたくしの文章の中の、そこに興味を持ったんだ!」と視覚的に確認できるほうが印象に残る。聴覚ではなく視覚というのがポイントだ。
また、わたくしは印刷されたものを他人が取り扱う様子から、多くの情報を受け取っているように思う。本であっても、ただのコピー用紙であっても。
どの部分にどう反応するのが正解なのかといったことではなく、その人の個人としての興味や解釈が重要だ。そのほうが意外性が生まれやすい。
わたくしにとって文章を書くという行為は、非常に広い意味でのコミュニケーションにはなっているわけだ。
ただのひとりごとのようにしか見えないものも、地球上の誰かには刺さるはずと信じて書いている。特定の誰かではないけれど、たしかに人類に対して話を振っているのだ。
同時に、別に誰にも刺さらなくてもかまわないという気持ちもある。
文章を書くことに熱中しているような時期の場合、自分以外の全人類が死亡したとしても一週間ぐらい気づかない可能性がありそうだし、また気づいたとしても、しばらくの間は文章の発表のあり方に特に変化がないという可能性もある。
わたくしのあらゆる活動は、宇宙との内緒話という性質がある。
同時代の人間の理解力をさほど信用していない、というのもあるかもしれない。
本当にわたくしのことを理解しているのかというのは気になっているポイントではあるのだが、だからといって「理解度チェック」のようなものは自分で設定したくない。
また、わたくしでない誰かの手によって「これとこれを理解しておかないとまずい」みたいなことが勝手に設定されないでほしいとも思っている。
そういうものが設定されてしまうと、正解を暗記しようとする人も出てくるかもしれない。たとえ内容的に妥当であったとしても、あらかじめ準備をされてしまうと「わたくしに嫌われないように準備をしている人」でしかなくなってしまい、その人のことが余計に分からなくなることがある。
人間だから、考え方や感じ方が違うのは当たり前なのだ。
自分に似ている人のことは気にはなっているけど、似ている人としか関わりたくないということではないし、似ているフリをされるのも混乱する。
正解を探り当てようとするのをやめてほしいとも思う。それより質問をしてほしい。確認をしてほしい。
わたくしは「お題箱」というサービスも利用しており、ログイン不要で、誰でもいつでも質問できるようにしている。
cleemy desu wayoへのご質問 (@cleemy_desu_wayo) | お題箱
https://odaibako.net/u/cleemy_desu_wayo
こういうことに関連して、「わたくしのことを理解したいならせめてこの本ぐらいは読んでおいてもらわないと」みたいなものも設定しないほうがいいと思っている。
中井久夫のエッセイ「世に棲む患者」にしても、今回の記事を理解するうえでの助けになるというだけであって、わたくしと関わるうえでの義務ではない。
今回の記事そのものについても、自己紹介として機能するようにしているつもりではあるが、これを読むことが義務のようになってほしくない。
ちなみに、以下は2021年から2024年までわたくしが「小説家になろう」で連載していた小説だ。
ダグラス・ジェネルベフトと7人の暗殺者
https://ncode.syosetu.com/n9355gw/
わたくしはこれを一次創作の同人誌として印刷して、名刺代わりに配ってまわろうかとも思っている。でも、ふだんあまり小説を読まない人が無理をして読んでも余計に誤解が生まれるかもしれない。
ところで、わたくしは2023年に小説家の田辺青蛙の以下のポストの存在に気づいた。
https://x.com/Seia_Tanabe/status/1487259100929212416
https://x.com/Seia_Tanabe/status/1487261499764912130
https://x.com/Seia_Tanabe/status/1487961085319999491
夫の円城塔の小説は読まないのだそうだ。
興味深いのが、2人とも商業的な領域で小説を書いているにも関わらず、「お互い書いたのは読まないよ」と明言していることだ。
若い世代の場合、「読まないと決めている」とは別に、「今は読まないというだけ」という姿勢もあったりするのかもしれない。
ウィンストン・チャーチルは、若い時に無理をして本を読むことについて戒めていた。このことについては『天才たちは学校がきらいだった』の1994年刊の邦訳でP.160〜P.161に解説がある。
何かと理由をつけて若者から本を遠ざけようとする大人もいるので注意が必要ではある。チャーチルの警告はどちらかというと、放っておくと「あれも読んどけ、これも読んどけ」と詰め込まれる事態に陥りがちな環境にいるような若者に向けたものだととらえたほうがいいだろう。
ちなみに小平邦彦の『怠け数学者の記』にも、読書というよりは教育全般における適齢についてのエッセイ「このままでは日本は危ない」がある(2000年刊の岩波現代文庫版でP.79〜P.82)。
年齢とは別に、特定の経験の有無とか、特定のジャンルの小説の面白さに目覚める前と後とか、社会的状況の変化とか、そういうことが重要な要素となることもあるだろう。
「なるほどこの作者はこういうことを作品に込めることもあるのか」ということをあらかじめ知ってから読むとインパクトが減ってしまう場合もあり、とにかく寝かせればいいというものでもない。
確かに本には、出会うべきタイミングというものがある。
内容をいい加減に把握してしまったり時間が経ちすぎてしまったりすることで、新鮮な驚きを獲得できるチャンスが失われてしまうのは、本にとっても読者にとっても不幸である。
ジョブ型の関係とメンバーシップ型の関係
重要なことはだいたい語ってしまった。このセクションからは蛇足にすぎないと思ってもらってもいい。
ここでは、「関わりたい」について少し補足をしておきたい。
わたくしのような人間であっても、「関わりたい」とは別に、他人に「手伝ってほしい」と思うことがある。
2025年5月時点では、「やりたいこと」でイメージされるのは一人で出来ることばかりだが、これは依頼するためのお金がないからというのもある。
小説なんていつでも書けると思っていたら、思いのほか時間が経ってしまって焦っているというのもある。
若いころはゲーム制作や映画の撮影についての構想をよく練っていた。
ゲームや映画についてのいくつかのアイディアについては、今でも完全に死んではいない。でもわたくしにとってのゲームや映画は、VRChatを始めとしたVRSNSの存在によって少し意味合いが変わりつつある。
AIが進化したことも大きい。いっそのこと、わたくし以外は全員AIでもかまわないと思うこともある。
でも人間の創造性や、人間がどのように偶然性を取り込むのかということについては、ずっと大きなテーマであり続けている。人間同士でなければ生まれない協業というのも重要視している。
ゲームや映画ならある程度の期間は継続的に手伝ってもらうというのが前提になるわけだが、そういうものとは別に、単発での「手伝ってほしい」もある。
分かりやすいところでは、わたくしが自作の小説を印刷しようとする時の表紙をどうするか、というのがある。こういう表紙にお金を出して依頼したりすることがあるのかどうか、2025年5月時点ではまだ決めていない。
もしお金を出すとしたらそれは単に外注ということになる。外注というのはいろんな意味で気楽さがある。
ちなみにわたくしはフリーランスのプログラマーだった時期もある。わたくしは組織になじまない一方で、フリーランスで仕事を請ける場合は納期という問題がつきまとう。だから依頼される側は向いていないと思っている。
若いころは、納期のことで何度も深刻なトラブルがあった。
どんな形でもいいから、納期のある世界から逃れたいと思っていた。でも納期のある世界から離れようとすると、メンバーシップ型の匂いがする雇用に接近せざるをえないような場面が多くなる。
ところで、日本はフリーランスに冷たいといわれる。
現代日本では、フリーランスの側に花を持たせるのは同心円的な世界観を壊すことになるからかもしれない。
権力と同心円は結びつきやすい。権力があるからこそそこに同心円が生まれるし、同心円の中心に意識的に行こうとする人は、権力志向の強い人の比率が高くなる。
同心円は「ウチとソト」を生み、メンバーシップ性との相性が良い。
そしてメンバーシップ性と食事も相性が良い。
そのため、食と権力はうっすらと結びつくことがある。
食事を一緒にとって「俺とお前の仲なんだからな」という場面を経由したことが、良く言えば結束につながり、悪く言うなら脅しとして機能する。
「同じ釜の飯」というのが、形のないはずのメンバーシップ性に具体的なものをもたらす。
そんなわたくしも、重要なイベントの直後やマイルストーンの通過時点などにおける打ち上げには、それなりに意味があると思っている。
打ち上げは良いのだが、わたくしは日本の「飲み屋」というカルチャーは苦手だったりする。
逆に、「喫茶店」は落ち着く。
こういうことも、ある程度はメンバーシップ的関係が苦手であることで説明がつくかもしれない。「飲み屋」カルチャーでは常連が別の飲み屋に行ったことをお店の側が「浮気」と表現したりすることがある。わたくしが直接言われたわけではないが、こういったものは、わたくしには脅しのように感じられることがある。
そういう言葉を使わなかったとしても、様々な形でメンバーシップ的関係を背景とした「つなぎとめ」の仕掛けがある。
日本では、「飲み屋」よりは「バー」のほうが、そういう要素は薄いのかもしれない。
また、喫茶店であっても常連だけで固められているような店の場合はメンバーシップ的要素があったりするのかもしれない。でもそういう喫茶店にはほとんど行ったことがないので、うまくイメージが出来ない。
おそらく、ある程度の広さがあってテーブル席がメインであるような喫茶店のほうが、よりメンバーシップ感は薄くなりやすいのではないかと思う。
日本語では俗用表現として「いつメン」という言葉が使われる。「いつものメンバー」というやつである。わたくしはあれが苦手である。
もちろん、「いつもの」というのが実は毎日ではなく2週間に1回とかそういう場合もあるだろう。こういう「いつもの」であれば、わたくしも苦痛ではない。
中井久夫の「世に棲む患者」でも、「いつものグループ」の存在を患者から告げられて驚いた経験のことが出てくる。患者なので、「オリヅルラン型」の側についての話だ。そのあとに続く説明から考えると、おそらく毎日のように集まる関係という話ではないのだろうし、行き先が物理的に家の近くではないことが多いようだ(ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.11〜P.12、みすず書房版『中井久夫集 1』P.201〜P.202)。
ちなみにわたくしはキャバクラやガールズバーやホストクラブやゲイバーといった系統の店には、一度も行ったことがない。
よくキャバクラについて「おしゃべりをしに行く」という言い方を聞いたのだが、「お金をもらっておしゃべりをするならともかく、なんでお金を払っておしゃべりをしに行かなあかんの?」などと思っていた。このように思っていたのは、会話そのものに苦手意識が生まれるよりも前である。
ちなみにコンカフェにも行ったことがないが、こちらについては少し興味はある。「まあそのうち」と思いつつ時間が経ってしまい、実際に物理的に足を踏み入れたことはない。オタク文化を都合よく取り入れたキャバクラにしか見えない店もあり、詳しくないわたくしには外からどんな店なのか判断できない。
スナックは2回だけある。自腹ではなくオゴリである。
「いつメン」や同心円について考えるうえで、湘南乃風の2006年のヒット曲「純恋歌」に注目してみたい。作詞・作曲のクレジットは「湘南乃風」。
以下はオフィシャルのMVである。
湘南乃風 「純恋歌」MUSIC VIDEO(オリジナルver.) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=YQSS7SgGia8
(「湘南乃風」チャンネル)
序盤の歌詞には、「大親友の彼女の連れ」という非常に有名な箇所がある。
もしここが「大親友の彼女の大親友」だとしたら、とっくに出会ってるはずなんじゃないの?ということになるかもしれない。
この「彼女の連れ」というのがリアリティになっていると同時に、同心円での位置関係がある程度推測できるものになっている。
つまり、「俺」と「大親友」が同心円の中心にいて、「大親友の彼女」は中心付近ではあるけど少し外れている。そして、その「連れ」はもっと外れている。
でも「パスタ」や「大貧民」によって、その「連れ」が中心付近へと一気に突入してきそうな流れが、ありありとイメージできるわけだ。
「世に棲む患者」では、「ヤマノイモ型」について構造的に同心円志向であるということ以外にも、連続性が重視されている。「大親友の彼女の連れ」というその言い方には、「思いがけなさ」がない。同心円の中にはいなかったものの、強力な文脈的連続性がある。
「オリヅルラン型」の言動の「思いがけなさ」についての解説で、「世に棲む患者」には以下のような箇所がある(ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.12〜P.13、みすず書房版『中井久夫集 1』P.202)。
これらが“思いがけない”のは、どうも、生活圏を一歩一歩、連続的に同心円的に拡大してゆくことが、一般に生活圏の拡大であると、(少なくともわが国では)観念されているからである。
「ヤマノイモ型」は連続的かつ同心円的で、文脈的連続性を重視する。逆に「オリヅルラン型」のほうはランダムアクセス的であり、文脈切断志向である。
ここで歌の後半の「馴れ合いを求める俺 新鮮さ求めるお前」という箇所に目を向けると、なかなか示唆的である。その直前には「全て見えてたつもり」というフレーズもある。
「新鮮さ」を求めているという「お前」は、実はメンバーシップ的な関係を苦手としているのではないか、思わぬところに思わぬ知り合いがいるようなタイプなのではないか、ということをわたくしはつい考えてしまうのである。
もちろんこれは解釈の一つにすぎないし、余計なお世話だということになるのかもしれない。
でもこのことは、じっくり考えていくといろんな可能性が浮かぶ。
例えば、「大親友の彼女の連れ」という言い方はあくまでも「俺」の視点であり、「お前」の側から本当はどう見えていたのかというのは、分からないのである。
実は「お前」にとっては、初めて会った時はもっと文脈切断的だった可能性だってあるのだ。
映画の配役では「ホワイトウォッシュ」あるいは「ホワイトウォッシング」と呼ばれる概念がある。LGBTQに関連して、「ヘテロウォッシュ」という言い方がされることもある。
「ヤマノイモ型」と「オリヅルラン型」の対比では、少なくとも日本においては「ヤマノイモ型」が支配的であるため、わたくしから見ると「ヤマノイモ・ウォッシュ」とでもいえるようなものが散見される気がする。
これはつまり、実際にはランダムアクセス的で文脈切断的だったものが、ムリヤリ「ヤマノイモ型」の世界観にフィットするように過去が改竄されたり、「ものは言いよう」とばかりに文脈的連続性があたかも存在していたかのように設定を上書きしたりするということだ。
例えば、わたくしは2012年に初めて沖縄に来たのだが、この時点では沖縄に親戚や友人知人は一人もいなかった。わたくしと沖縄をつなぐものは、社会的には何も存在しない。このことについて、「ヤマノイモ・ウォッシュ」と思えるような誤った解釈をする人がいた。
わたくしは友人や知人が一人もいない場所だからこそ沖縄に来たのであり、そこを改竄するとまったく違う話になってしまう。
通常は、この「ヤマノイモ・ウォッシュ」というのは「ヤマノイモ型」の人によってなされる。特に、自分たちが違和感を感じる具体的な誰かと実在する組織との結びつきを連想する場合は、自分たちと敵対する勢力との関連について考えるケースが多く、「下衆の勘繰り」のようなものに近くなる。
自分以外の具体的な誰かと実在する組織とが結びついている可能性を「オリヅルラン型」の人が疑う時というのは、文脈切断的で関係妄想的なものである可能性が高くなり、「ヤマノイモ・ウォッシュ」とは色彩が異なる。
ところで、これは今になって思い返すと、ということでしかないのだが、わたくしにとってインターネットの存在はランダムアクセス的・文脈切断的な出会いや移動を促進するものであるはずだった。
でも2025年5月時点では身近な人とSNSでつながっておくというのも一般的になっており、むしろ「ヤマノイモ型」を強化するためにインターネットが利用されることがある。そしてインターネットを通じてあらゆる場面で「ヤマノイモ・ウォッシュ」が盛んに行われるようになってしまった。
わたくしがもともとN型かつP型であり、ほとんど常にランダムアクセス的・文脈切断的であり、そういう人間の多感な時期にインターネットが「登場」してしまったために、軽視されていると感じる自分の大切な感覚が当然インターネットによって守られ続けるものだと信じて込んでしまっていた。
でもそれは甘かったということになる。
SNSなどで「勢」や「界隈」という言葉が流行しているのは、こういう言葉によって社会的な背景とは切り離して考えることができる効果があるからかもしれない。ヤマノイモ・ウォッシュへのうっすらとした抵抗のように見えることがあるのだ。
「界隈」の場合、人や組織などの何らかの具体的な中心が存在していることもあるが、そういう時には界隈の中の人の発信よりは外からの発信の時に「界隈」がよく使われる。あるいは自嘲的な意味合いを込める場合。
「勢」や「界隈」という言葉は相対化を促進する効果がある。権力志向の強い人が何らかの同心円の中心付近にいると、その同心円を非常に独特で特別なものとして扱われるのを好み、相対化されるのを嫌うようになる。
ところで、わたくしは生活者であったことが一度もないかもしれない。
「生活者」には、富裕層ではないという意味が込められることがあるが、ここで考えているのはそういうことではない。
富裕層には富裕層を生きるという「生活」があり、富裕層には富裕層の同心円があるということを前提にしている場合がある。
そもそも、いかなる同心円からも距離を置くような場合はどう考えればいいのか。
日本において生活者であるということは、それ自体が同心円とともに生きることになりそうだ。
「世に棲む患者」に書かれていることを前提にするなら、「オリヅルラン型」の人についても「いやいや、これはそういう生活者なのだ」と考えることも可能ではあるのかもしれない。
文脈についても、「これは文脈がないのではなく、そういう種類の文脈なのだ」という場合がある。
文脈的連続性を前提にする姿勢は正統性の重視ともいえる。xNxPは正統性が存在しないことを重視するというよりは、奇跡的な偶然とか、宇宙的な導きとか、そういうものをより強力な正統性と感じると考えたほうがいいかもしれない。
もっとも昨今のSNSでの論調などから、トンデモだと思われたくないとか、スピリチュアル系だと思われたくないとか、そういう理由で「正統性」を隠すことも多そうだ。
N型にとっては確かに文脈があり、まったく切断的ではないのに、S型にとっては文脈がまったくないように見えてしまうこともある。N型からすると、この関連性が見えないなんてとても信じられない、というわけだ。そういう時にもヤマノイモ・ウォッシュは起こりやすいかもしれない。S型にとって理解しやすい文脈で上書きしてしまうわけだ。
文脈切断志向やN型の感覚にフィットする文脈を重視する姿勢は、S型にとっては冷淡に見えることがあるのは確かだ。
でもその冷淡さが居心地の悪さにつながっているからといって、安易にヤマノイモ・ウォッシュを発動してしまうと、それはそれで残酷さが生まれたり文脈切断的になったりすることもあるかもしれない。
結果的に残酷になるようなヤマノイモ・ウォッシュは、S型かどうかよりもExFxによってなされることも多いかもしれない。
他人にとって気になる冷淡さと、自分が避けたい残酷さがなかなか一致しないのはそれなりにつらいものがある。
冷淡さや残酷さを考えるうえでは、xSFxとxNTxの対比も重要だ。
xSFxの美点とされることと、オキシトシンがもたらすことには共通点がありそうである。
オキシトシンは仲間意識を強めるとされる。一方で、仲間ではない存在に対してはとことん残酷になれる。
xSFxから見るとxNTxの言動は冷淡で残酷に見えるかもしれないが、xNTxから見るとxSFxが突如として発揮する攻撃性は不可解だ。
どこに行っても、xSFxは自分らしくいられてうらやましいと思うこともある。
わたくしはxSFxに助けられる機会が多いような気がして感謝すると同時に、ほとんど常に、物理的には宇宙人に囲まれて生きているという感じもする。
特に2004年秋あたりから、20年以上ずっと。
身内と呼べる人間は地球上に一人もいない。
20年以上ずっと。
別にそれでかまわないと思うこともある。
xSFxから見ると、わたくしのほうが宇宙人に見えるかもしれないということも理解しているつもりだ。
理解をしていたとしても、不利を強いられる状況が改善するわけではない。
自分とは違うタイプの人が物理的にすぐ近くにいることによって、孤立無援感(sense of helplessness)がかえって強まってしまうこともある。
このことについては、のちの「音と住環境」や「SN指標についての雑感」のセクションであらためて述べる。
この孤立無援感は、沖縄に来たからではないことは強調しておきたい。わたくしが沖縄に来たのは2012年春だが、当時は大阪市内にワンルームマンション(正確には1K)を借りたままの状態だった。もし2012年のうちに大阪に戻っていたとしたら、もっと悲惨なことになっていたかもしれない。
また、沖縄に来てから2人ほど、自分に似ているかもしれないと思う人との出会いがあったことも強調しておきたい。おそらく2人ともN型だ。でも残念ながら、その2人は沖縄にいないことも多い。いないと思ったらいる、という時も多いけど、いずれにせよ頻繁に会うわけではない。
ちなみにカフカは手紙の中で以下のように書いている(新潮社版『決定版 カフカ全集 11 フェリーツェへの手紙 II』P.430)。
それでもしかし——ごらん、ぼくが(力やスケールの点で彼らに自分が近いというのではありませんが)自分の本来の血族と感じている四人の人間、グリルパルツァー、ドストエフスキー、クライスト、フローベールの中で、結婚したのはドストエフスキーだけであり、正しい逃げ道を見出したのは、外的内的な苦難がつもりつもってヴァンゼーでピストル自殺したクライストだけかもしれません。
「自分の本来の血族と感じている四人の人間」の箇所は、頭木弘樹『カフカはなぜ自殺しなかったのか? 弱いからこそわかること』(2016年刊)では「ぼくが本当の意味で血縁を感じている4人」という訳になっている(P.170)。
わたくしは2001年春ごろから2004年秋ごろまで師匠的存在の音楽の研究に協力していたが、この師匠的存在の人については宇宙人ではなかった。「本当の意味で血縁を感じ」るような人だった。
ただし、類似しているがゆえの問題はあったかもしれない。バルザック『絶対の探究』でバルタザール・クラース氏が2人いるような。なお、この師匠的存在の人は言動や全体的な雰囲気が映画『π』(1998年公開)の主人公マックス・コーエンにも似ていた。おでこも広かった。
わたくしが知る限り、師匠は2025年5月時点で、有名人ではない。
2003年夏ごろから2004年春ごろまではわたくしにも恋人と呼べる存在がいたのだが、この人も宇宙人ではない。こちらの場合は、わたくしとは違っている点も多い人だった。明確に「付き合っている」といえる状態だったのはわたくしの人生ではこの時が唯一である。
2人とも、その後のことをまったく知らない。
ところで、エッセイ「世に棲む患者」では、団地に流入してくる人々の傾向の変化について述べられている箇所がある(ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.22〜P.24、みすず書房版『中井久夫集 1』P.211〜P.212)。これは沖縄への移住にもある程度は当てはまるのではないかと思っている。沖縄の場合、2012年以降に移住してきた人は「第三群」の「思いがけない趣味の持主」の比率が若干高い気がするのである。
もっとも、わたくし個人としては「思いがけない趣味の持主」の人々と出会うことに失敗し続けているという感じはする。今後のことは分からない。
以下のような記事を見れば、やはり沖縄にもいろんな人がいるんだなあ、ということが分かる。
那覇技術同人誌読書会に参加してきた|いぜ a.k.a taktic(2019-10-18)
https://note.com/taktic/n/n6dbe7c78204d那覇見聞録「技術同人誌読書会を通して見た那覇」|底辺亭底辺(2019-10-21)
https://note.com/teihentei/n/na979f485b42b
わたくしはこういう集まりに参加したことは一度もない。
ちなみに2002年〜2012年あたりに沖縄に移住してきた人に「第二群」の「組織指向性」が強い人の比率が若干高い気がする。
なお、ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.22には誤記がある。「第一群である。」となっているべき箇所が「第二群である。」となっており、混乱するので注意。これは「2011年3月10日 第1刷発行」および「2024年6月10日 第10刷発行」のもので確認。
ところで、必ずしも金銭が発生するものではない形での、ジョブ型の関係のようなものに憧れることは、わたくしにもあるかもしれない。
それぞれの能力や特性を活用し、揮発性が高く、「非公式的」であるという色彩も強いような。
タスクフォース志向とでもいえるかもしれない。
ただし、このタスクフォース志向においても、何か具体的に他人と一緒にやりたいことがあるわけではない。他者との関わりということになると、「これがしたい」というのがないのだ。
結局わたくしは一人で考えて一人で書くことがメインである。そして、考えることや書くことを他者と連携しながらやりたいわけではない。
だからわたくしがタスクフォース志向で何をやりたいのかと疑問に思っても無駄である。結局はわたくしの側が「いやいや、あなたは何をやりたいの?」と思うことになるわけだ。あるいは、「わたくしがどういうことに取り組むのがいいとあなたは思ってるの?」でもいいかもしれない。
そして「この人と一緒にやりたい」みたいなものが2025年現在のわたくしにはまったくない。
だからやっぱり「関わりたい人がいない」ということには変わりはないのである。
戦闘消耗と離岸流
いつメン(いつものメンバー)が苦手ということについての別の視点も提供しておきしたい。
別の視点とは言っても、要するにただシンプルに飽きっぽいという話でしかないともいえる。
この飽きるという現象にも、ミクロレベルの飽きとマクロレベルの飽きがある。
ミクロレベルの飽きが「油絵法」と相性が良いことについては、すでに「対話と油絵法」のセクションで述べた。油絵法がもたらす、「こっち」でしばらく作業して飽きたら「あっち」に移行、という自由。
ずっと新鮮さを保ったまま作業が出来るし、終わったと思った部分を新しい意味で包み込みやすくなる。
わたくしの場合、複数の「絵」を同時並行で描くということは滅多にやらない。別の「絵」へと移行する時というのは、たいていはマクロレベルの飽きがあった時だ。
マクロレベルの飽きについては非常に厄介で、わたくしが納期が守れないという問題ともつながる。
今回の記事「関わりたい人がいないということ」のようなものは、納期とはまったく無縁なところで書いている。依頼する人間も管理する人間もいない。
今回の記事については、書いている最中に衝動的に短い記事を2つ書いたりもした。でもこれらはすぐに完成させることが出来たため、同時並行というよりは息抜きだ。すぐに元の「絵」に戻ることができたため、マクロレベルの飽きがあったわけではない。
ミクロレベルの飽きに素直になって、一つの「絵」の部分から部分へと自由に関心を移動させ、時には息抜きをしたりすることは、ある程度は飽きにくさをもたらす。でもある日、「絵」そのものから急に離れたくなる日というのは必ずやってくる。
このマクロレベルの飽きは人間に対しても起こる。
毎日同じ顔を見ていると嫌になるのだ。
これは誰に対してもそうで、例外はない。
文字だけの発信があるSNSアカウントなど、顔や声が直接届かない場合でもそうだ。同じユーザー名やアイコンが毎日視界に入ると嫌になることがある。
何か理由があって、特定の人の発言を追いかけてみようとする時もある。でも2ヶ月程度が限界だ。必ず嫌になって、とにかく視界に入れたくないと思ってしまう時期がやって来る。
それが誰であっても。どのようなジャンルの人であっても。
単純接触効果の逆バージョンともいえるようなものが作用しているのかもしれない。
単純接触効果 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E7%B4%94%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E5%8A%B9%E6%9E%9C
ちなみにわたくしは2005年夏にはてなのアカウントを作成し、この時から「cleemy」を名乗り始めた。
https://web.archive.org/web/20051030030928/http://d.hatena.ne.jp/cleemy/about
このころのはてなはSNS的ではなかったのだが、同じユーザー名が毎日視界に入ることが苦痛になることに気づいた最初のプラットフォームがはてなだった。苦痛だとは言っても、別にその人を嫌いになったわけではない。居心地の悪さがどんどん濃厚になっていくという感じだ。
おそらく、VRChatなどでも今後それは起こるのではないかと思う。現在は長い期間にわたって毎日顔を合わせるようなユーザーがいないというだけで。
こういうのも残酷に感じる人がいるかもしれないことは分かっている。でもあまりにも長い期間我慢をし続けると、何もかも遮断してしまおうという方向に傾いてしまう。
1日おきで顔を合わせる、みたいな感じだとどうなるのかは分からない。いずれ試してみたいと思うが、相手がいることなので気軽に試せるものでもない。
あらためて強調するが、具体的な対象が嫌いになったわけではないことがほとんどである。
嫌いになったわけではないけど、嫌いになりそうなのが怖くて、嫌いになりたくないからこそ遠ざけたいと思ってしまうことも多い。
遠ざけたいのは、具体的な対象だけではない。状況を根こそぎ遠ざけたいと思うことが多い。
例えば、何か楽器を練習していて飽きてくると、練習だけをやめるということはない。聴くほうもやめてしまうことが多い。その楽器に関連したジャンルの音楽だけを遠ざけるのではない。音楽という存在そのものを遠ざけてしまうのだ。
そう、わたくしには音楽をまったく聴かない時期というのがあったりするのだ。しかもそれが、1週間だけとかそういう短い期間ではない。
プログラミングについても、まったくコードを書かない時期がある。
文章に関しても同様で、今年(2025年)になってから2万字を超えるような長い記事を書くのは今回の記事が初めてである。
コードも日本語の文章も、書かない時はとにかく一行たりとも書かない。
そういうことに熱中していたこと自体を完全に忘れているかのような毎日をおくることもある。
文章との関わりにおいては、読者という立場でも同様だ。半年以上活字の本をほぼまったく読まないような時期があったりする。
わたくしはやや極端かもしれないが、xNxPはたいてい強力な飽きる力を持っていると思う。あるいは、飽きることに正直である。
わたくしは自分自身がxNxPであること、自分が飽きっぽいことは強く自覚しているつもりではある。
でも熱中している最中には、この「飽きることになる」というのがどうしても信じられないという状態になりやすい。
どうしても。
熱中している真っ最中というのは、いまだかつてない事態が起こっているという感じがする場合がある。これは今までの「熱中」とは次元が違うのだという確信。わたくしという個人の歴史における重要な場面というだけでなく、人類史におけるターニングポイントに違いないという思い。
何気なく開いたページに、まさに今考えているテーマと関連することがズバリ書かれていたりするなど、奇妙な偶然の一致が次々と起こる。
宇宙から歓迎されているという感覚。
ついに覚醒の時が来て、このまま死ぬまでずっとこの状態が続くのだという確信。
おそらく、単に熱中しているというだけではなく、「いまだかつてない」という感覚が重要なのだろう。
2020年あたりからは、だいたいこういう過剰な集中は年に2回〜6回程度は訪れる。いつ訪れるのかという、そのタイミングはまったく読めない。
たとえ年に6回目の集中だったとしても、「今年はもう6回目だなあ。今年はなかなか豊作だったなあ」というようなことはあまり考えない。熱中している時は、その年のこれまでの集中状態とはまったく性質の違うものだという確信があることが多いからだ。
今回のこの集中によって、すべてが変わりつつあるのだという確信。
それでも、やがて飽きる日はくるのだ。
いざ飽きてみると一目瞭然である。
ああ、またか、という。
心の底からどうでもええわ、という。
飽き始めている時期にそのことに気づくこともあるのだが、「もうちょっと区切りのいいところまで」とか「飽きる前にいまやってることを完成に持っていきたい」とかそういう欲が生まれることもある。
マクロレベルの飽きを阻止しようともがくことについては、わたくしは離岸流と呼んでいる。
離岸流の本来の意味は、岸の近くで発生する、沖に引きずり込まれるような急激な流れのことである。
日本では、ちょうどお盆の時期に離岸流が多いとされる。
流れに抵抗しようとして岸に向かって泳ごうとすると、いつまで経っても岸には近づけない。流れと直角(岸と平行)に泳ぐか、あるいはいったん沖に流されてからあらためて岸を目指すほうが安全とされる。
わたくしの場合、飽き始めるタイミングとして要注意なのが、過剰な集中が始まってから40日〜50日が経過したころである。
ここで、戦闘消耗(battle exhaustion)という概念に注目したい。中井久夫はたびたびこれに言及している。
以下は『災害がほんとうに襲った時——阪神淡路大震災50日間の記録』(2011年刊)のP.129より。
「戦闘消耗」とは、ベテランの下士官など、戦争のプロが、程度の差はあっても突然戦闘を継続するのがバカバカしくなり、武器をかなぐり捨ててどうでもなれという態度に出ることであって、ナチス・ドイツが戦争末期までこまめに兵士に休暇を与えて鉄道で故国に帰していたのも、米軍がベトナム戦争で三週間ごとにヘリコプターで兵士を前線からサイゴンに送り返していたのも、四〇日から五〇日をピークとする「戦闘消耗」を避けるためであった。ここで、興味を感じたのは、軍事精神医学では「戦闘消耗」は困った病的状態とされるが、実際は、戦闘という無理を自己激励によって心身に強いてきたのが限界に達して、雪の積もった竹が跳ね返るように、精神が正常化する事態だということである。
この箇所は本編ではなく付録の「私の日程表 1995.1.16 - 2.28」の中のものであり、無料公開の分には含まれていないかもしれない。また、おそらくはみすず書房版『中井久夫集 5』の中にもこの箇所はない。
なお、この箇所は『1995年1月・神戸——「阪神大震災」下の精神科医たち』(1995年刊)ではP.97である。
ちなみにこの『災害がほんとうに襲った時』は中井久夫の1.17(1995年1月の阪神・淡路大震災)での体験の記録である。中井久夫は1995年2月23日、つまり地震発生後37日後に「全身の筋肉弛緩」が起こり、これを戦闘消耗だと思ったようだ。
以下は「統合失調症とトラウマ」より(2004年刊『徴候・記憶・外傷』P.139、みすず書房版『中井久夫集 8』P.14)。
戦闘消耗は第一次世界大戦でわかったことですが、日本は第一次世界大戦の経験がないため知らされていません。占領地に釘づけになった日本軍の士気は低下し、戦闘消耗を来たして伸びきったゴムのようになったと言われています。
戦争や災害のようなものに限らず、「一念発起」に近いものや、急にアイディアが浮かんでそのまま熱中するようなプロジェクト。そういうものに軽躁状態やそれに近い状態で取り組んでいたとしても、40日〜50日が経過したころは要注意である。
それがたとえ小説のような、一日中椅子に座っているようなものであっても。
わたくしの場合、2020年からの新型コロナウイルスのパンデミックのおかげで、自分が個人的に取り組んでいることについて40日〜50日経過のタイミングで飽きやすいことが鮮明になった。
パンデミックがもたらしたものによって直接的に何かに取り組まざるを得なかったということではなく、パンデミックのおかげで余計なことに惑わされる機会が減ったということだ。
パンデミック発生前は、自分がなぜ飽きたのかということについて原因がよく分からなかった。たいてい、何らかの邪魔が入ったりするからだ。わたくしは予想外の事態を取り込むのは得意ではあるが、12時間〜48時間程度の完全な中断を余儀なくされるようなものをどう考えるか。
そういう中断について、「あの出来事のせいで」とか「あの人のせいで」とか。そういうことを考えがちだったわけだ。
本当はあれがなかったら無事に完成まで持っていくことができたのだ、と。
パンデミック以降、外部からの邪魔がまったく入らなかったとしても、確かに40日〜50日が経過すると飽きやすくなるというのが何度も何度も確認できたのだ。
熱中している個人的なプロジェクトの場合、マクロレベルの飽きがまだ来ていないなら、48時間程度の中断があってとしてもまたすぐに復帰できるのだ。それに飽きていないならば。
わたくしがこの「戦闘消耗」で重要だと思っているのは、身体的な休息をこまめにとっていても、緊張状態が40日〜50日の間ずっと続くと嫌気がさしてくるということである。
これは私見だが、飽きるということこそが重要なのであり、体力の問題ではないということだ。物理的に動き回るような任務の場合、「しばらくデスクワークをやらせておけばいいだろう」とは思わないほうがいいということだ。状況から根本的に遠ざけるということが必要なのである。
士気の問題もあるだろうから現実的には難しい場面もありそうだが、戦略や立案に関わる人間であっても、状況から完全に遮断したほうがいいのではないかと思う。
ちなみに中井久夫はよく、「戦闘消耗」という言葉を使わずに40日〜50日というタイミングに言及することがある。
例えば、「時間精神医学の試み」というエッセイ。以下はちくま学芸文庫版『隣の病い』P.18より。
私は、患者が社会復帰的な活動を止めたくなる時が、三日目、四十〜五十日目、三カ月目、一年目に多いことに気づき、これを予告し、その時の凌ぎ方を話しておくことで多少事態を改善してきたように思っています。職人のことわざにも、三日、三十日、三カ月という言葉があるそうです。これらの節目に、私はそれぞれの理由を推定していますが、仏教での死者の弔いの日取りに似ているのは、面白いことです。
社会的に意味のある活動だけでなく、病的な状態にもこのタイミングはあるようだ。以下は『精神科治療の覚書』の「発病の論理と寛解の論理」の章より(1982年刊の旧版でP.92、2014年刊の新版でP.78)。
しかも、困ったことに、急性精神病状態が終りかけるのは、始まってから三、四〇日のことが多い。これは、一つのキャンペーンを人間がはじめてから、消耗して気を抜きたくなるまでの期間にほぼ相当していると思われるフシがある。
ここでも「戦闘消耗」という言葉は登場しない。
創作や研究における離岸流は、基本的にはこの戦闘消耗やそれに類似した概念を知ったうえで、「いや違う、まだ飽きてない」というあがきを続ける状態だ。
いま飽きると困るんだ、という思いが強いと、どうしても飽きることを異常事態とみなしたくなる。でも実際は「雪の積もった竹が跳ね返る」だけでしかない。
ちなみに「雪の積もった竹が跳ね返る」現象と実際の海で発生する離岸流というのは、メカニズムとして類似している。
わたくしに離岸流が起こりやすいのは、あと少しで完成という確信がありつつ、40日は確かに経過してしまっていて、でもはっきり飽きているという実感はない、という時だ。ペースは落ちていても、集中しようと思えば集中できる。
あと少しで完成だからこそ、ここで休まずに続けようと思うのは無理もない。でも続けてしまうと、まずいことになる。徐々に、単にペースが落ちてきているというレベルではなくなってくる。そういう状態なのに悪あがきを続けてしまう。
悪あがきが続くと、その対象の周辺事情ごと、根こそぎで遠ざけたくなる。
この根こそぎで遠ざけたいという感覚は、物理的な移動を促進することもある。
ひょっとすると、この感覚は狩猟採集の時代には乱獲を抑止する効果があったのかもしれないと思うこともある。
おそらくこういう飽き方というのは、マイケル・バリント(マイクル・バリント)のオクノフィリアとフィロバティズムの対比においては、フィロバティズムのほうに親和的なのではないかと思う。
そういえば、わたくしは同時代の人間に対して「いま何してる?」ということが気になることはほぼない。もしそれが気になるとしたら、何か手伝ってほしいとか、話したいことがあるとか、そういう場合だ。
わたくしは密着的な関心が苦手ともいえる。そういう風に関心を持たれるのも苦手だし、わたくしがそういう風に誰かに関心を持ち続けるのも苦手だ。
ところで、何かを仕上げるという行為はものすごくエネルギーが必要だ。文章に限らずそうだ。わたくしのような人間にとっては。
なんとなく仕上がる、ということがない。
飽きる前に駆け抜けるように完成できることもあるが、どちらかというとレアケースだ。いったん飽きてからのちにサルベージが必要になることが多い。
もし今回の記事が2025年5月のうちに公開できたとしたら、それは駆け抜けるように完成できたということになる。
でもそれはレアなのだ。
わたくしが中井久夫に直接的に何度も何度も言及した長文の記事というのは、おそらく今回のものが初めてになるかと思う。
でも実はわたくしにとって、そういう記事を書くのはこれで3回目である。
2021年12月から翌年1月にかけて書いていた「思考所」の後編が最初だ。この後編は5万字以上すでに書いたものがあるが、未完のまま放置状態である。
なお前編については公開済み。以下である。
作業所はあるのになぜ思考所はないのか・前編|cleemy desu wayo(2021-12-17)
https://note.com/cleemy/n/n0084ba60c4cc
そして2回目が、約2年前の2023年3月〜6月に書いていた「おつきさまと殺意」というタイトルの長大なエッセイだ。これはわたくしの幼少期や10代のころにフォーカスしつつ、同時に中井久夫の各種エッセイや論文をかなり広範囲に紹介するという要素があるものだった。
2023年4月あたりなどは、ほぼ毎日起きてから寝るまでずっとこの「おつきさまと殺意」のことを考えていて、莫大な時間とエネルギーを投入し、14万字以上書いた。わたくしにとっての文章を書くという営みについてのマニフェストという側面もあった。
でもやはり未完のまま放置。
ちなみに2023年は6月から短編小説に没頭し始めたりもした。これも5万字以上書いたが未完。
2023年前半は、膨大なエネルギーを投入して書いたのに未完のものが複数あるわけだ。
ただし、未完の「おつきさまと殺意」や短編小説があったからこそ、2023年夏のジェネシスブロック記事( https://note.com/cleemy/n/n96474b06fa3b )はあのような内容になったのだともいえる。
とにかく、わたくしには未完のものが大量にあるのだ。
正直、放置状態のものをどうすればいいのか分からないと思うこともある。一部は未完のまま公開したり、箇条書きの状態で公開したり、そういうものが今後はあるかもしれない。
こんな風に飽きっぽいわたくしでも一つの作品に熱中できる期間が持てるのは、わたくしが「最後の壁バイアス」と呼んでいるもののおかげかもしれない。
このバイアスはつまり、本当は最後の壁というわけではまったくないのに、あたかも最後の壁に直面しているように誤認するということだ。クライマックスではないのにクライマックスだと思いこむ傾向、といってもいいかもしれない。
今回の記事を書くにあたっても、2種類の「最後の壁」がある。
今回の記事はわたくしがこれまで書いてきたものとしては「いまだかつてない」ものであり、これを完成させることにより、わたくしの状況が劇的に改善されそうだという期待。これはいわばマクロレベルの「最後の壁」だ。
何十年と続いてきたこんな苦労は、この記事が公開されればたちまち消えることになるにちがいないという確信。
前述の「思考所」の前編(2021年12月)の公開時や [cdwdoc-2023-001] (2023年3月)の公開時は、記事を公開すれば note.com のチップ機能(当時の名称はサポート機能)によって1億円ぐらいの収入が入ってくるのではないか、などと真剣に考えていた。チップ機能とは要するに投げ銭の機能だ。もし1億円に届かなかったとしても、自分の状況を劇的に変える何かが起こるはずだと。
でもそんなことは何も起こらなかった。
上記の2つの記事に限らず、note.com のチップ機能ではまだ1円たりとも収入につながっていない。
以前ALISというサービスを利用していた時は、以下の記事の完成直前にも、この記事が莫大な富をもたらすにちがいないという確信があった。でもまったくそうならなかった。
ずっと変わらないでいてほしい | ALIS(2018-10-25)
https://alis.to/cleemy/articles/3Lq8bo95650B
ちなみにこの「ずっと変わらないでいてほしい」は、生まれて初めて4万字を超える長文を完成させることができたと同時に、サルベージが始めてうまくいった記事でもある。2018年6月時点でほぼ完成していたのだが、完全に飽きてしまい、しばらく放置していたのだ。9月後半だったか10月前半あたりだったか、そのころにサルベージを開始して完成まで持っていくことができた。
「思考所」の前編については、書き始めたのが2021年11月初旬であり、前編だけ見れば飽きる前に駆け抜けるように完成することが出来たレアな例だ。
マクロレベルの「最後の壁」はいつもこういう感じで、ミクロレベルの「最後の壁」のほうは、具体的な執筆の進み具合についてのことだ。今まさに最後の難関に遭遇しているという、根拠のない確信。
この難関を超えたあとのことが極端に単純化されて認識されている。
マクロレベルの「最後の壁」とミクロレベルの「最後の壁」が組み合わさると、大胆な借金などに走ることが多くなってしまう。これをわたくしは「xNxPジャンプ」と呼んでいる。
ちなみに2023年になってからは、大胆な借金というのは一切していない。
今回の記事の場合、書き始めた4月26日時点では「できれば4月中に完成すればいいな」などと考えていた。そして2025年5月に入ってからは「あと5日程度で完成」という状態がずっと続いている。
5月からはずっと、今回の記事の執筆において「まさに今、重要な局面を乗り越えようとしている」という確信が続いているわけだ。この壁さえ越えたら、あとはごくごく簡単な微調整だけで完成するだろう、という。
「あと5日程度なら頑張れる」と思うからこそ、集中が続くのである。
ちなみに今回の記事は、初期段階ではなんとか2万字以内におさめる予定だった。
拙作の小説『ダグラス・ジェネルベフトと7人の暗殺者』( https://ncode.syosetu.com/n9355gw/ )では、「月曜日」の回を2021年4月5日の月曜日の夜に公開し、次の「火曜日」の回は4月6日の夜、のように毎晩公開していって、1週間で完結させる予定だった。実際は完結に3年以上かかった。
この小説の時は、3月25日あたりから5月4日あたりの約40日間が集中状態だった。その後5月後半や6月にも書いてはいたが、「土曜日」の回を2021年のうちに完成させることができず、放置状態になった。
今回の記事は、はたしてどうなるか。
ちなみにいまこの行を書いている時点で、2025年5月に入ってから20日以上が経過しており、ずっと続いていた「あと5日程度」という確信は勘違いだったことが明確になっている。8万字を超えるボリュームになりそうなのも確実だ。
最終的にどうなるのかは分からない。
本当に完成まで持っていけるのかどうかも。
下書き機能により、URLはすでに確定している。
もし非ログイン状態で https://note.com/cleemy/n/n0e5af5951bcf にアクセスして記事の本文が読めているのであれば、ひとまず公開まで持っていくことに成功したとはいえる。
発信恐怖
前述のように、2017年秋からのコールセンターの仕事では、会話がより苦手になってしまい、チャットが苦手だったことも判明した。
それでも2年以上続けられたのは、職場がさほどブラックではなかったこともあるし、発信ではなく受信がメインだったことも大きいかもしれない。
軽いレベルではあるが、わたくしには発信恐怖とでもいえるものがある。
この発信恐怖の話題は、基本的にはEI指標におけるI型についての話題だと思ってもらっていい。
日本語で「発信」といえば幅広い文脈で使われるが、ここで考えているのは英語の「outgoing」と「incoming」の対比における「outgoing」のほうだ。
だから、このセクションで考える「メッセージ送信」というのはXなどにおける不特定多数へ向けたポスト(リプライではないポスト)よりも、宛先がはっきりした送信を指す。
VRChatの場合は「join」という概念がある。わたくしの発信恐怖は、このjoinをためらうという形で発揮されることもある。無理にjoinしようとすると、異様なことになりやすい。
参加者が流動的で、かつ無言で来て無言で帰ることが前提のイベントであれば、joinしやすい。あるいはJPST [vrcw.net] のようにワールドが街のようになっていて、目的がはっきりしないjoinが当たり前であるようなワールドも。
VRChatを始めて分かったのは、わたくしは3人以上の会話が本当に苦手なんだな、ということ。
一対一は比較的マシだというだけだ。3人以上は壊滅的だ。
Discordなどのテキストメッセージであれば、口頭での会話とは違って少し間が空いても目立たないメリットはある。でも別の問題もある。久しぶりのメッセージ送信や、少し途切れた時に「発信」としての色彩が強くなって迷うことになるからだ。
相手が返信をしないことで悩むこともある。
電子メールなどの場合、たいていは自分を少し出した時にそうなりやすい気がする。
我慢して相手に合わせていると表面的にはラリーを続けられることもあるが、あまり我慢をし続けるのも苦痛が大きすぎるので、しばらくラリーを続けてから自分を出すこともある。
でもほんのちょっとでも自分を出すと、急に返事が返ってこなくなったりすることが多い。
返事が返ってこなくなったこと自体より、結局わたくしは相手を欺くことによってしか対話が成立しないのかもしれない、などと考えてしまって落ち込むこともある。
わたくしがこのように感じるということは、相手も似たようなことを感じる可能性もあるということでもある。これは頭では分かっているつもりだ。
表面的にわたくしの反応が薄いように見えても、拒絶されたとは思わないでほしいな、と願うこともある。
こちらとしては、相手に対して誠実になろうとすればするほど油絵法的になってしまい、タネをつくるモードへと入ってしまう。
また、「1打ったら10返してほしい」みたいに思うこともある。あるいは「こちらが10km移動したら1000km移動してほしい」みたいなことも。
こちらが何も返信しなかったからといって、「追撃をしてはいけない」ということはない、ということだ。特にDiscordのDM(一対一のメッセージ)では、こちらの反応を気にせずにどんどん連投してほしいと思うことも多い。
わたくしが沈黙したからといって、あなたもそれに引きずられて沈黙しないでほしい、というわけだ。
もちろんこれについてもやはり、相手が同じように思うタイプである可能性がある。
自分に似た人のことは気になってはいるものの、直接的なコミュニケーションにおいては非対称性を求める、という逆説は常に付きまとっている気はする。
ところで、若い女性の場合は「1打ったら10返してほしい」などと表明してしまうと、どうでもいい人からの異様なメッセージであふれ返ってしまうこともあるのかもしれず、それを表明したくてもできないということがあるかもしれない。
わたくしの場合、発信についての苦手意識には相手の状態を変えたくないというのもあったりする。
ちなみにわたくしは起こされること自体は苦痛ではない。
眠たかったらまた寝ればいいだけだ。
予想外のタイミングで起こされることにより、夢の内容をメモすることができる場合もある。これが創作や研究に生かされることもある。起こしてくれた人は、こういう意外な形で貢献してくれているわけだ。
INTPは人間関係が希薄化しやすいといわれる。わたくしの場合、発信恐怖のおかげで余計にそうなりやすいかもしれない。
この発信恐怖については、海外のミーム画像もある。
英語圏では有名なintroverts(内向的な人・I型の人)のミーム画像については [cdwact-2024-05] でいくつか紹介した。
[cdwact-2024-05] 2024年5月活動報告|cleemy desu wayo(2025-02-28)
https://note.com/cleemy/n/n385ff88b787e
記事としては8万字以上あってかなり長いが、ブラウザのページ内検索機能を利用して「ミーム画像」で検索していただければ、該当箇所にすぐたどり着けるはずだ。
これらの画像が日本で有名でないだけでなく、類似した視点のものも見かけないのは少し不思議な感じはする。
むしろ、「そんなことに悩んでいるのは日本人くらいなのではないか」と思っている人も多そうだからだ。
一人の時間とダウンレギュレーション仮説
一人の時間の重要性と、わたくしが「ダウンレギュレーション仮説」と呼んでいるものについて簡単に説明しておきたい。
これも当然ながら、EI指標におけるI型についての話ということになる。
だが、このセクションで語るのは単に一人でいるのが好きだという話ではない。
これは特にINxx(I型かつN型)と関係が深いといえるかもしれない。あるいは一部のISFPやENxPにも。
そしておそらくは、HSPあるいはスキゾタイパルの傾向がある人にも。
E型とI型の違いとして、他人と一緒にいる時が充電の時間なのか、それとも一人でいる時が充電の時間なのか、というのがよくいわれる。
それだけを唯一の判断基準とするべきではないだろうけど、かなり重要なポイントではある。
今回の記事を執筆している期間中は、いろんな意味で「周囲の人」が存在しない状態だった。
構想期間中もそうだし、本文を書き始めた2025年4月26日からはほとんどの時間、建物内に一人で居続けることが可能だったのが大きい。
VRChatにおいても、毎日会うような「いつメン」はいなかった。
おかげでかなり集中できた。
わたくしの場合、特に寝起きの時間というのは重要だ。
ヴァレリーのいう「非社会的な時間」かもしれない。
執筆を開始する前の、まだ完全に目が覚める前の段階から、今回の記事のことがぼんやりと頭に浮かぶ状態の日も多かった。
起きてから最初の4時間を、通知の数をゼロにするためのチェック作業とか、ひたすらメッセージの返信を続けるような作業とか、そういうものに浪費するようなことは最近はない。
でも忙しい日々では、起きたらメッセージを返すというのが前提になってしまうこともある。非社会的な時間を確保するには、局所的にそういう時間があればいいというだけでなく、トータルとしての非社会性のようなものがある程度は必要となる。
「非社会的」ということについての効能を理解してくれる人が近くにいたほうがいいのかもしれない。
今回の場合は、周囲の人がいないがゆえにそういうことについて理解を求める必要すらなかった。
一人でいる、というのは、単に音が静かであればそれでいいということではない。音がなくても、濃厚な気配を持つ人というのは、確かにいる。
気配もそうだし、「人がいる」というその事実が乱される要因となることもある。
小説を書いたりする身としては、カフカが書いていることが気になる。
以下は、新潮社版『決定版 カフカ全集 10 フェリーツェへの手紙 I』の1913年1月14日〜15日より(P.225)。
いつかあなたは、ぼくが書いているあいだ、そばに坐っていたい、と書いてきました。考えてもごらん、そうしたらぼくは書けないでしょう(それでなくてもたくさんは書けないのです)、しかしそうなれば全然書けないでしょう。書くということは、過度なまで自分を開くことなんだから。
「過度なまで自分を開くことなんだから」の箇所は、スーザン・ケイン『内向型人間のすごい力 静かな人が世界を変える』(2015年刊)の第3章「共同作業が創造性を殺すとき」では、「自分をなにもかもさらけだすことだから」という訳になっている(P.138)。ちなみにダイジェスト版の『内向型人間が無理せず幸せになる唯一の方法』(2020年刊)では、P.79である。
同じ手紙には以下のような箇所もある。
だから書くときは、いくら孤独でも十分ということはなく、書く人の周りが静かすぎるということはなく、夜はまだあまりに夜でなさすぎるのです。
以下のような箇所も。
ぼくはもうしばしば考えたのですが、ぼくにとって最良の生活方法は、筆記道具とランプを持って、広々とした、隔離された地下室の最も内部の部屋に居住することでしょう。食事が運ばれ、いつもぼくの部屋からずっと遠く、地下室の最も外側のドアの背後に置かれます。食事のところへ行く道、部屋着のまま、地下室の丸天井の下をすべて通り抜けて行くのがぼくの唯一の散歩でしょう。それから自分のテーブルに戻り、ゆっくりと慎重に食事をし、またすぐに書きはじめるでしょう。それからぼくはなにを書くことでしょう! どんな深みから、ぼくはそれを引き出すことでしょう!
当時も今も、地下室というのは象徴的な存在である。
実際に物理的に地下にある場所を求めていなくても、地下室というその比喩が重要だ。
カフカの書くものについては、手紙であれば大量に残されているが、長編小説の完成を放棄したりするタイプの人だったのも気になるポイントだ。
カフカのような人にとっては、自分が地下室を必要としているということを、愛する相手が本当に理解してくれるのかどうかというのはとても気になることのはずである。
自分から地下室というキーワードを出してしまうと、相手が話を合わせているだけなのかどうかが分からなくなってしまうため、地下室やそれに類似するキーワードを相手のほうから出すのかどうかを見極めたいと思うこともあるかもしれない。
下手をすると、かいがいしく世話をしてほしいというニュアンスに解釈されてしまう可能性もあったりするのが怖いところだ。干渉されたくないから地下室なのであって、干渉を前提にするのは論外である。
カフカの手紙の1913年1月14日〜15日というのは、フェリーツェがカフカの作品についての話をしないことに不満を述べた少しあとである。
自分の作品への理解とは別に、「せめてこれぐらいは」という思いがあったのかもしれない。
せめて地下室の効能については理解している人であってほしいし、地下室があればもっと優れたものを生み出せるというその可能性に着目してほしいという気持ち。
カフカほど過敏であれば、何気ないほんのちょっとした発言に振り回されてしまうかもしれない。
たとえ相手が自分の過去の作品の理解者であったとしても、十分ではない。相手が実は「あの時のあなたは輝いていたが今のあなたの書いているものには魅力がない」などと内心では思っていて、書くことをやめさせようとしたりする可能性があったりするのかどうかが気になってくるかもしれない。
カフカは自分自身とフェリーツェについて、どこが似ていてどこが似ていないのか、何度も何度も考えたはずだ。
「類は友を呼ぶ」というのは、ある程度は当てはまると感じることはあるものの、正反対だから惹かれ合うということもある。
「せめてこれぐらいは」と思うことがまったく共有できていないことが判明して愕然とする、というのは過敏な人の人生でたびたび起こる。
カフカとフェリーツェの手紙のやり取りについては、以下の記事でも紹介されている。
あらゆることにぼくは失敗する――今こそ読みたいカフカの日記と手紙 | 単行本になりました | web春秋 はるとあき(2016-12-31)
https://haruaki.shunjusha.co.jp/posts/749
ちなみにわたくしの過去のことでいうと、2001年春〜2004年秋における、師匠のプロジェクトへの協力。あの時も地下室が問題だった。
あのころというのは、結局は師匠の側の「地下室を用意してほしい」という要求に苦しめられていたのだということが、今になってみるとよく分かる。「地下室」という言い方はしなかったけれども。
お金も人脈もないわたくしに、そういうものが用意できるわけがなかった。
しかも、わたくしもまた地下室を必要としている人間だったのだ。そのことに気づいたのは、2004年秋に師匠と縁を切ってからである。
デイヴィッド・ホロビン『天才と分裂病の進化論』(邦訳は2002年刊)のP.182〜P.183には偉人のリストがある。音楽家や作家や哲学者や科学者や発明家の中で、「分裂病」あるいは「分裂病型人格」の可能性がある有名人のリストだ。
アインシュタインやジェイムズ・ジョイスは子供が統合失調症ということでも有名だが、上記の偉人リストの中にはこの2人はもちろんのこと、カフカやニュートンの名前もあることに注目したい。
前述のように、『天才と分裂病の進化論』では「分裂病型人格」はかなり広くとっている可能性があることには注意する必要がある。
なお、この偉人のリストに名前があるのは、フランケンシュタインの母であるメアリー・シェリーなどの例外はあるものの、ほとんどが男性である。
また、おそらく世間的なイメージとして、地下室の主というのは男性を前提にするのが通常である。
中井久夫の「世に棲む患者」では、ヴァージニア・ウルフの「女がひとりでいられる部屋」に言及がある(ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.27、みすず書房版『中井久夫集 1』P.215)。
同じく中井久夫の『精神科治療の覚書』の「治療の滑り出しと治療的合意」の章には、以下のような箇所もある(1982年刊の旧版でP.65、2014年刊の新版でP.52)。
時には“母親が自分の部屋を持つこと”が最大の協力でありうる。(一日中忙しく働いて憩う場もない親のそばで患者が緊張を解いて休めるだろうか。)
ヴァージニア・ウルフが『自分ひとりの部屋』を発表したのは1929年だが、女性が自分の部屋を持つこと、特に母親が部屋にこもることを冷淡や無責任と感じる傾向は約100年が経った現在でもありそうだ。
人間味や温かさの強要によって、失われてしまうものがある。
人口比ということでいうと、男性の中ではI型は珍しいわけではないが、おそらく女性のI型のほうが女性同士の集まりの中では異端視されやすい。
現代における女性の書き手であり、同時代の書き手に向けたアドバイスを書いているジュリア・キャメロンの『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』(原題は『The Artist's Way』)には、第5章(第5週)に以下のような箇所がある。P.191。
アーティストは何もしないでいる時間をもたなければならない。こうした時間をもつ権利を守るには、勇気や信念、さらには切り替えの能力がいる。
ひとりで静かに過ごしていると、家族や友人には引きこもりと映り、心配の種となる。だが、アーティストにとって、引きこもりは必要である。創造のための孤独が確保されないと、私たちの中のアーティストはイライラして怒りをつのらせ、不機嫌になる。そのような状態が続けば、やがて意気消沈して憂うつになり、他人に敵意を抱くようになる。
電子書籍(ASIN: B083X758NX )で確認するかぎり、「何もしないでいる時間」は原文では「downtime」であり、「引きこもり」は「withdrawal」である。
この少しあと、かなり過激な記述がある。以下はP.191〜P.192。
しかし、ひとりになる充電期間をもてないと、創造性は枯渇し、ゆくゆくは、不機嫌になるだけでは収まりがつかなくなる。「死の脅威」が出てくるのだ。
最初のうち、この「死の脅威」は親しい人たちに向けられる。自分をひとりにしてくれない友人や恋人、配偶者や子どもや家族に殺意を覚えるのだ。しかし、いくら警告を発しても、それが無視されつづけると、他人を殺したいという衝動が自殺願望に取って代わる。「お前を殺したい」が「もう、死んでしまいたい」になるのだ。
「死の脅威」は原文では「death threats」となっており、要するに殺害予告である。
世界的ベストセラーであり「INFP必読」のような感じで紹介されることがあったりもするこの本。そして女性の読者も多いはずだが、こういう記述もあったりする本なのだ。
ちなみにINFPは「おとなしい」とみなされることも多い。
上記の殺害予告についての箇所がSNS等であまり引用されていないように見えるのは、INFPであるがゆえにこの箇所を「自力で見つけ出してほしい」というようなことを思ってしまうこともあるかもしれない。あからさまは嫌なのだ。
なお、INFxはINTxよりも究極の理解者といえる存在を求める傾向が強いかもしれないことは強調しておきたい。関係性を美化するからこそ、無理解の怒りも強くなる。
INxxにとっては、人の気配を消すことができればそれでいいというわけではない。
耳栓やマスキング音では限界があるのだ。
人の気配を気にしなくていいということではなく、人がいないというその気配ごと深く吸い込みたい時があるのだ。
これはノイズごと深く吸い込むということでもある。
日本語で「夜のしじま」といった時、わたくしが連想するのはまったくの無音ではない。夜空全体を覆う微弱な気配が重要だ。
ノイズごと深く吸い込む時というのは、自我境界が拡大しているように感じることがある。あるいは、自我境界の曖昧さ。部屋全体と一体化しているように思ったり、あるいは空全体と一体化しているように感じたり。
あるいは、自分というものが存在しない感じ。
この状態は非常に深いリラックスともいえるが、ノイズに振り回されやすくなることもある。
岡田尊司『パーソナリティ障害——いかに接し、どう克服するか』(2004年刊)のスキゾタイパルについての解説に、以下のような箇所がある。P.198。
例えば、自分がトイレのノブに手をかけた拍子に、隣の車のクラクションが鳴ったのは、何か特別な意味があるのだと考えるのである。
こういう偶然の一致について、何か特別な意味があるに違いないと考えて乱されてしまう傾向は、気を付けていてどうにかなるものではない。
何か関連があるのだろうか、と考え続けて無理にこじつけているわけではない。それは自動的に、すぐにやって来るものだ。
瞬間的にわく、「何かある」という確信。
だからわたくしは集合住宅そのものが苦手である。
明確に同居人といえる人がいなくても、他者の動きが知覚できてしまうと、様々な形で関連付けて考え、疲れ果ててしまう。
自分の意識と他人の意識が連動しているように感じたり、特別な装置によって頭の中の思考が読み取られているのではないかと思うこともある。
人為的に引き起こそうとする偶然の一致には人間的な「くさみ」のようなものがあって、個人的にはあまり乱されない。簡単には人為的に引き起こすことができないような偶然の一致は、謎めいていて、いつまでも余韻が残ったりする。
自分のこととの関連付けが頭の中で生まれなかったとしても、様々な付随情報が次々とやって来ることもある。
ちょっとした電子音の音程に重要な意味があるかもしれないとか、自分ではなく別の誰かに向けた暗号なのではないか、とか。
とにかく、わたくしは情報過多の世界を生きている。
この情報過多はASDの特徴とされることもあるが、どちらかといえばスキゾタイパルやHSPの特徴と考えたほうがいいかもしれない。
HSPはともかく、ASDやスキゾタイパルの傾向がある人が向いている職業として真っ先に連想するのが、プログラマーである。わたくしは納期が守れないのでわたくし個人としては仕事でコードを書くべきではないかもしれないと思っているが、あくまで一般論としての向いているかどうかの話である。
オフィスの中は活気があるべきだと思う人がそれなりに多いらしいことは、わたくしがプログラマーとして初めて仕事をした1999年の時点で気づいていた。
また、人の声があるほうが集中できるという人もいるらしいことは、最近知った。自分がそうだからといって、「きっとあの人も人の声があるほうが集中できるはず」などとは決して思わないでほしいと思う。
もちろん、いろんろな人がいていいのだが、オープンオフィスやブレインストーミングを熱狂的に支持するような人もおり、ほとんど新興宗教のように思えることもある。わたくしが物理的に会ったことがある人の中にそういう熱狂的な支持者がいたということではない。
前述のように、スーザン・ケインの『内向型人間のすごい力 静かな人が世界を変える』(2015年刊)およびそのダイジェスト版『内向型人間が無理せず幸せになる唯一の方法』(2020年刊)の第3章では、そばに人がいると書けないという主旨のことをカフカが手紙に書いた話が紹介されているのだが、この第3章ではオープンオフィスやブレインストーミングへの批判も紹介されている。
オープンオフィスやブレインストーミングは環境面において共同作業を重視するものである。
この第3章ではソロモン・アッシュやグレゴリー・バーンズらによる有名な実験も紹介されていて、これは内容面における共同作業の危うさを示すものだ。
集団思考あるいは共同作業は、まさにカフカのような人が持つ創造性を葬り去るアイディアである。
ちなみに中井久夫は48歳前後に発表された「病跡学の可能性」というエッセイの中で以下のように書いている(ちくま学芸文庫版『「思春期を考える」ことについて』P.239、みすず書房版『中井久夫集 1』P.284)。
「天才」概念は、ヨーロッパにおける神の退潮と交替して次第に高められた。
天才の西欧語ゲニウス Genius は氏神クラスの低い位階のローマの神であり、それは長くその地位にとどまっていた。
この箇所のあと、中井久夫の人生のテーマともいえる魔女狩りのこと、天才輸出国としてのイギリスやニュートンのこと、性格(character)や人格(personality)という概念の「民主化」のこと、さらに日本文学史にも話がおよぶ。
確かに神と天才は交替し、神の死後は天才がずっと崇拝の対象としてその座に座り続けるかに見えた。でも1960年代や1970年代あたりから、天才を放逐するための武器として集団思考が用いられるようになっているのではないかという疑惑がわたくしにはある。
少なくとも現代日本において、天才という概念を認めない人々、オープンオフィスやブレインストーミングを信奉する人々、性格分類を認めない人々、これらは重なり合っている気がするのである。この重なり合いの中には、リベラルな人も自己責任論者もいる。
集団思考の危うさについては、ターリ・シャーロット『事実はなぜ人の意見を変えられないのか』(邦訳は2019年刊)の第8章「「みんなの意見」は本当にすごい?」も参考になるかもしれない。
ところで、「対話と油絵法」のセクションでも述べたような、同時に複数のことを考え、しかも延々と枝分かれしていくようなようなもの。こういうものはいわば、内なる声のようなものである。
内なる声は受け身の構えがないと受け取ることができない。受け身であり、待ちの構え。前のめりになったり動き回ったりすると、声が消えてしまうこともある。
『MBTIへのいざない』(邦訳は2012年刊)のP.14〜P.16では、「外向」の「刺激を求めにいく」という構えと「内向」の「刺激を受け取っていく」という構えが対比的に解説されている。
若いころからこの内なる声に耳を傾けて過ごすと、一生それなしでは生きていけなくなる可能性があるのかもしれないとも思う。
わたくしの若いころは、他人の存在によって乱される度合いはさほど大きくなかった気がする。数時間ほど一人の時間を過ごしていれば、いわば「急速充電」とでもいえるものが可能であったことも大きいかもしれない。
年をとってしまった現在は、充電のためには連続した一人の時間を必要とする。
若いころは、集中している時に他人の声が聞こえてきたりしても、短い時間であれば意識的に無視できることも多かった気もする。
現在のわたくしは、意識的に無視する能力を失ったというよりは、別の能力が開花したと考えたほうがいいのかもしれない。若いころよりもずっと、内なる声を聞くマイクの感度が高くなったのかもしれないのだ。でもその感度の高さの代償として、外界から聞こえてくる声により一層敏感になったという可能性がある。
内なる声の存在はデメリットになるが、油絵法のような関与が可能な対象を持つならば、さほど大きなデメリットにはならない。それどころか、メリットになることもある。
統合失調症の症状である思考吹入に近いようなものとして、わたくしに対する突然の「声かけ」とでもいえるものだったり、わたくしの言動をリアルタイムで批評するような言葉が浮かぶこともある。
でもわたくしの場合、それらは明確に音声として聞こえるわけではない。音声ではないが、生々しい他人の存在を感じることはある。存在は感じるのだが、物理的な位置関係はない。どのあたりにいるとか、近くとか遠くとか、そういうことを問うことはできない。ただ、存在がとにかく生々しい。
構想を練ることに熱中している時などはそれらの「声」は小さいが、文章を長時間書いていたり、外を歩いていると少しずつ「声」の存在感が大きくなってくる場合がある。
基本的に惑わされることはないし、「誰それを殺せ」だとかそういうものはない。アドバイスとして機能することもないわけではない。
おそらくはサードパーソン現象(サードマン現象、third person syndrome)のようなものとも、うっすらと関連しているのではないかと思う。
ちなみにわたくしにとってのイマジナリーフレンドはまた別で、架空の会話の相手という感じである。これはまったく健康的で、「議論をしているという空想」の延長線上でしかない。存在の奇妙な生々しさがない。
内なる声の場合は、自分が生成した空想というよりはループバックのようなものであり、自分でも内容が予想外であり、存在が生々しい。
内なる声のほうについては、全体的に少し不気味で鬱陶しいと感じることもあるけど、ごくまれにアドバイスとして機能することもあるから有用でもある。わたくしが書いている最中の文章に内なる声が的はずれな解釈をして、「なるほど、そういう誤解をする人がいるかもしれない」と気づかされて修正したり書き加えたりすることもある。
こういう的はずれな解釈というのは、イマジナリーフレンドはしない。
ここから、この内なる声についての個人的体験と仮説について述べることにする。
わたくしの場合、外界からの刺激が過多である状態が続くと、ごくまれに、この内なる声が消失したように感じることがある。
消えたから頭がスッキリして良いことだ、などと喜んでもいられない。ないことによる居心地の悪さも同時に感じる。
個人的には、おそらくこれは一時的に鈍感になっただけなのではないかと思っている。
つまり、内なる声をキャッチするマイクの感度が悪くなった状態。
もちろん、マイクというのは比喩的な意味だ。
マイクの側が鈍感になっただけであり、内なる声を感じとることが出来ない時も実際にはずっと内なる声が発せられているのではないか、という疑惑があるわけだ。
内なる声の「発声」には脳内でそれなりのエネルギーが消費され続けているはずなのだが、それを受け取ることが出来ない。だから無駄に疲れやすい状態ともいえる。
無駄に疲れやすいかもしれないが、外界の他者の気配にはさほど敏感ではなくなる。
外界の他者の気配に過敏になっている時期というのは、つまりマイクの感度が高まっている時期でもあるのかもしれない。
内なる声を効率的に拾うためのマイクが、自分の外からの刺激も一緒くたに拾ってしまっているということだ。
ここまでは、いわば当たり前のことといえる。
問題はここからで、マイクの感度が悪くなった状態がずっと続くと、内なる声が出力を上げようとするのではないか、と思うことがあるのだ。
内なる声を必要としているにも関わらず、ずっと聞こえない。何らかの理由で、マイクの感度も上がらない。そういう時に、内なる声の出力のほうが上がってしまう。
出力が上がった状態というのは疲れやすくなり、怒りも増す。声の中に「誰それを殺せ」などが混じったりすることはないが、攻撃的な考えが浮かぶ頻度というのは若干高まる。
わたくしの仮説で重要なポイントは2点ある。
まず1点目は、内なる声が消失したように感じても、それは内なる声が出力をやめたのではなく、内なる声をキャッチする側のマイクの感度が鈍感になっただけなのではないかということ。
つまり、ダウンレギュレーション(downregulation)のようなものである。
そして2点目は、マイク感度が悪い状態があまりに長く続くと、内なる声の出力が上がる場合があるのではないかということ。
統合失調症についての知識がある人なら、まさにこの出力の上がった内なる声こそが幻聴や妄想の正体なのではないかということを連想するだろう。
実際のところは分からない。わたくしが「ダウンレギュレーション仮説」と呼んでいるものはとりあえず前述の2点であり、統合失調症の陽性症状との関連を確信しているわけではない。
もしこの2点が正しいとしても、3点目の疑問として、なぜ出力が上がりきったまま固定されてしまう場合があるのか、というものがありうるだろう。一過性であれば統合失調症とはいえない。
ところで中井久夫は「世に棲む患者」で気になることを書いている(ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.10、みすず書房版『中井久夫集 1』P.200)。
さらに言えば、統合失調症を病む人々は、「うかうかと」「柄になく」多数者の生き方にみずからを合わせようとして発病に至った者であることが少なくない。これは、おそらく、大多数の臨床医の知るところであろう。
内なる声を消そうとしないほうがいい。
音と住環境
最近よくコンテナハウスに住みたいと思うことがある。
なぜそう思うのかという背景について、簡単に説明しておきたい。コンテナハウスという結論ではなく、あくまでも背景についての話。
実際のところ、コンテナでなければならないということはない。どちらにしろ今のわたくしにはお金がないのでコンテナを購入できない。
この話は単にわたくしの趣味というわけではなく、EI指標におけるI型の人でコンテナハウスなどのタイニーハウスが適している人は多いのではないか、という話でもある。
日本は少子化なので、今後はますます家や土地が余ってくる。古民家は文化財的な価値のあるものとして残したほうがいいとは思うが、そうでない家をどう考えるかという問題ともつながってくる。
わたくしにとって、一人でいることと音の問題というのは常に結びついている。
前のセクション「一人の時間とダウンレギュレーション仮説」では、心を乱すのは自分以外の人間だということが前提だったが、このセクションでは明確に音という存在にフォーカスして考える。
また、前のセクションでは文脈的あるいは社会的な一人の時間の重要性について考えていたが、ここで考えたいのはもっと直接的で物理的な意味での一人の時間だ。
ここではまず、感覚過敏という概念について紹介しておきたい。
感覚過敏について描かれた4ページの短い漫画があるので、とりあえずURLだけを示しておく。
https://x.com/timtimtooo/status/1410569063038812160
あくまでもこういうものに「近い」というだけであって、わたくしの場合は典型的な感覚過敏ではないかもしれない。
なお、ミソフォニアという概念もある。
「そしゃく音」や「時計の針の音」などが不快に感じる人は「ミソフォニア」かもしれない - GIGAZINE(2025-04-01)
https://gigazine.net/news/20250401-eating-sound-misophonia/音で人生が壊れる世界、自覚無く地雷源で生きているあなたへ|だっく@ニュース"物語"ジャンキー(2025-04-20)
https://note.com/dac/n/n31c32b5fe5ab
『昆虫記』で有名なファーブルは時計の音が苦手で、鳥を銃で撃ったりもしたとされる。G・V・ルグロによる『ファーブルの生涯』の「セリニアンの集い」の章にはこのことが書かれている。
以下はちくま文庫版『ファーブルの生涯』P.329より。
それから彼はまた、よく実験室の窓にきてさかんに歌いつづけるナイチンゲールに対して猛烈な憎しみをいだいていて、よくこれとはげしくたたかった。朝早くからひじょうに重要な仕事、たとえば観察の結果をりっぱに書きあらわそうとしているときなど、近くの植えこみにやってきて、さえたよい声でホーホケキョとしきりに叫びあげられることでもあると、もうがまんができない。われを忘れて、かっとなってしまうのである。いきなり憤怒の形相ものすごく、机からはなれて、しのび足で銃をとりに行く。
ちなみに2021年刊の集英社版『ファーブル伝』だと、「第17章 セリニャンの夜話」の章である。
「押しかけ弟子」をしたのがG・V・ルグロのような人だったからこそ、実像が伝わっていたと考えるべきかもしれない。
押しかけてきたのがデカルトにとってのクリスティーナ女王のような人だったとしたら、実像が歪められて伝わったかもしれないのだ。
ちなみにわたくしはファーブルと違って、インターホンを鳴らすというフォーマットを守る人を追い返すということはない。
前のセクション「一人の時間とダウンレギュレーション仮説」でカフカが地下室を求めていた件に触れたが、カフカもミソフォニアだったとされることが多い。
カフカ自身が書いたものとしては、自分の部屋のボンボン時計を止めた話や、それを止めてからも隣の部屋の時計の音や咳が気になるという話が、1915年2月11日の手紙に登場する(新潮社版『決定版 カフカ全集 11 フェリーツェへの手紙 II』P.587)。
この手紙には以下のような箇所もある。
笑わないで、F、ぼくの悩みを軽蔑しないでください。
2015年のGIGAZINEの記事で、ノースウェスタン大学のダリヤ・ザベリナ(Darya Zabelina)の研究が紹介されている。
クリエイティブな才能は注意散漫な人の方が発揮できる - GIGAZINE(2015-12-14)
https://gigazine.net/news/20151214-creative-genius-distraction/
日本語の「注意散漫」という言い方の場合、ADHDを連想する人が多そうだ。
「情報過多」や「フィルター」や「認知的脱抑制」(cognitive disinhibition)だと、スキゾタイパルを連想する人も多くなるかもしれない。
天才と変人の関係 脳の「フィルター装置」が独創性を左右? - 日本経済新聞(2013-04-25)
https://www.nikkei.com/article/DGXBZO54282560T20C13A4000000/天才と変人 解き放たれた知性 | 日経サイエンス
https://www.nikkei-science.com/201306_032.html
わたくしの場合、時計の音やテレビの音はかなり気になるが、いびきや少し離れた場所の工事の音などはあまり気にならない。
様々な音の中でも、特に気になるのが人の声や犬の声。猫の声はあまり気にならない。
APDの傾向があって言葉が聞き取りにくいのに小さな雑音が気になってしまうのは皮肉ともいえるが、結びついている可能性もある。
わたくしは小説を書いている時は特にそうなのだが、言葉が少しでも聞き取れるような人間の声は集中を削ぐ力がかなり大きい。わたくしの場合は、執筆中に不意打ちで聞こえてくるような日本語で話す声。
言葉を取り扱う活動なのだから、当然といえば当然である。
読んでいる時よりも、書いている時のほうがはるかにダメージが大きい。小説を書いている時はいくつもの言葉の糸が頭の中にある。不意打ちで人の声が聞こえると、すべての糸がいっせいに切断された感じがすることもある。
複数の言葉の糸というのがイメージしにくければ、時計の修理をしている人がいて、今まさにその人が重要な部品を精密ピンセットでつまんでいるというその腕に、急に子供がぶら下がってくるような状況を考えてみてほしいのである。
人の声というものが、いかにダメージが大きいか。
最近は何かを書いている時もずっとデスクトップモードでVRChatを立ち上げっぱなしにしていることが多いが、VRChatを経由する場合は急に人の声が聞こえてもダメージはさほどない。心理的に距離を置くことができるからかもしれない。テレビよりもラジオのほうがマシであることとも関係しているかもしれない。
スピーカーやヘッドフォンからではない生の人の声というのは、たとえ小さくても、ある種の強制力といえるものを持っている。
通販の配達などがやって来て数分間途切れるような場合も、ほとんどダメージはない。配送業者の人は必ずインターホンを鳴らしてくれる。物理的な訪問であっても、一時的な用事にすぎないことが事前に分かる。
インターホンを鳴らすというそのフォーマットを守ってくれるというのが重要なのかもしれない。フォーマットを守らない来訪者にも愛想よくしてしまうと、来訪者の脳内で「喜んでいた」と勝手に変換されてしまうこともあるので要注意である。勝手に変換したうえに、さらにそれを他人に伝えてしまうのも問題である。
宇宙との内緒話をするためにも、同時代の人間の協力というのがある程度は必要だ。
もっと気を使ってほしい、という話ではない。
「気を使わせてしまっているな」ということが分かると、それ自体がストレスである。
自分が特別な存在だから手伝ってほしいというわけではなく、あなたはあなたのほうで宇宙との内緒話があるんでしょう、それを守るためにはわたくしに何か出来ることはあるでしょうか、ということでもある。
基本的にわたくしは、よく知らない人のことについては、とりあえず「この人も宇宙との内緒話をしている人かもしれない」と考える。
中井久夫『こんなとき私はどうしてきたか』(2007年刊)のP.95〜P.96には、3つのベッドが並んでいる場合はその真ん中の患者が治りにくいという話が出てくる。両側から音が聞こえてくるからストレスということではなく、自分が出している音がおよぼす影響が1人だけの場合と2人いる場合という違いが前提になっている。
おそらくは、自分と似ている存在だからこそ相手の過敏さが想像できてしまうというのもありそうだ。
もちろん、まったく自分と感覚が違う人に囲まれるからこそストレスだという場合もある。
わたくしの場合、部屋にいる時にテレビがずっとつけっぱなしである人などもそうだ。
隣の部屋から音が聞こえてくることそのものより、テレビの音を常に出しっぱなしにしているような、そういう人が物理的に隣にいるのだというストレス。
こちらも多少は音を出しても気を使う必要はないというメリットもないわけではないが、やはりストレスである。
自分と感覚が違う人が物理的に近くにいることによって、孤立無援感(sense of helplessness)がかえって増してしまう場合がある。こういう場合は誰もいないほうがマシなわけだ。
わたくしは自己否定感や抑鬱感の強い時期が続いたりはしないため、鬱病や双極性障害ということはないと思う。
ただし、自分にとって理解不能な人が物理的に近くにいるという状態が続くと、かなりイライラが強くなるし、絶望的な気分に陥ったりする。攻撃的な発想になることもある。
もちろん、わたくしにとって理解不能であれば、向こうにとっても理解不能かもしれないという可能性は理解しているつもりだ。
やはり、理解可能か理解不能かに関わらず、お互いに気を使う必要がない状況というものを模索したい。
ここ数年、いろいろ考えていたのだが、結局は一つの建物に一人という方向にならざるをえないのではないかと思う。
わたくしは一軒家で育ったので、マンションへの憧れが強かった時期もあった。でも今はすっかりそういうものはない。
基本的に、集合住宅という存在自体を避けたいのだ。
もう、ほとほと嫌気がさした。
なぜ今まで住環境ということについてあまり深く考えてこなかったのだろう、と思うこともある。
小説は小学生の時から書いていたし、小説を書くのに適した環境などというものを真剣に模索することはなかった。音楽やゲームや映画に比べると、小説というのはそもそも環境というものを必要としないと思っていた。
でも違ったのだ。
文章を書くということ、特に、自分のために書き散らかすのではなく作品として完成に持っていくということを継続的にやるためには、環境はとても重要だったのだ。
わたくしは、同居のようなものを永遠に避けたいというわけではない。
一つの建物に一人という原則はキープしつつ、ほぼ同居といえるようなものも可能ではないかと思い始めている。
例えば、鉄骨で構成された建物の中に、複数のコンテナハウスを持ち込むような発想。建物の中にさらに建物があるわけだ。
あるいは、一つの土地の中にコンテナハウスをほどよく密集させて、連結をしないというような発想。最近ではホテルでこういうものがあり、すでに日本各地にある「HOTEL R9 The Yard」や、千葉県の「ホテルクレイドルキャビン館山」や沖縄県の「T&T Villa 宮古島」などがある。
このことについては、そのうち note.com 内で単体の記事にすることもあるかもしれない。
岡田尊司『パーソナリティ障害——いかに接し、どう克服するか』(2004年刊)のスキゾタイパルの章の中に、「創作や自分を表現すること」の効能について述べられている箇所があるが、その直後に引きこもりの効能についても述べられている。以下はP.206より。
危機を克服する方法には、他にもいくつかある。その一つは、意外に思われるかもしれないが、引きこもることである。完全に引きこもるのは、別の弊害が生じるので、お勧めできないが、世間との交わりを必要最小限にする程度の引きこもりは、破綻を防ぐ有用な方法である。世間から一歩身を引くことで、その風圧が弱まり、危機の時代をやり過ごしやすくなるのである。
スキゾタイパルの章の最後に新天地の効能についても書かれている。
一見すると相反する要素でもあるような、「引きこもり」と「新天地」。
この章の新天地についての説明には「バグが蓄積」という表現があるが、メモリリークのようなものがイメージされているのかもしれない。
スキゾタイパルが得意とすることとの関連で考えると、システムの密結合と疎結合のほうがしっくりくる気はする。
プログラミングにおいて、サンクコストを無視して新しい視点や他人とは違う視点でシステムを見つめることは良い意味での疎結合をもたらす。
スキゾタイパルは、人間関係においても密結合の解消を志向する傾向はあるかもしれない。
スキゾタイパルの人は表面的には鈍感であるように見えることがあるが、むしろあまりにも多くのことに気づいてしまうがゆえの、頭の中での密結合が負担となる。
ちなみにコンテナハウスは移動が容易なことが大きなメリットだ。
「引きこもり」と「新天地」の両方に親和的なのである。
実際にそうする日が来るかどうかはともかく、いざとなれば家ごと別の場所に移ることが可能になっているという事実が、深いレベルでの安心をもたらしそうなのである。
また、建物内に独立した建物があるというのは、システムとして疎結合であるというのも魅力的だ。
SN指標についての雑感
濃厚なN型から見たSN指標のことについても軽く触れておきたい。
SN指標というのは、MBTIやその影響下にある性格分類においてはS型とN型の対比についての話である。
これはビッグファイブにおいては開放性(openness to experience)の話だと思ってもらってかまわない。
もちろん『分類しない暴力』でもSN指標についての解説はする予定なのだが、ここではわたくしの他者との関わりということに関連した話をメインにしたい。
ちなみに「濃厚なN型」と言ってしまった時点で、MBTI公式の見解からは離れることになる。
ここではまず、数学者のグレゴリー・チャイティンが書いていることに注目したい。
以下は『メタマス!』(邦訳は2007年刊)のP.211〜P.212より。
あなた方は、自分でアイデアを求めようとしない限り、実際に信じることがない限り、それを見つけることができない。
スポーツの場合のように、そのための訓練をする方法はあるだろうか? いや、私はそうは思わない。あなた方は、魔物にとりつかれなければならない。ところが、我々の社会はそのような人があまり多くいるのを望まないのだ。
本書を書いている今、私がどう感じているか述べてみよう。
まず第一に、私が論じているアイデアは、非常に具体的で、実際に存在して手に取ることができるように思える。時には、私の周りの人よりも実在的に感じることさえある。新聞やショッピング・モールやテレビ番組は、非実在的だという感覚を常に私に与えるのだが、それらよりもアイデアの方が実在的だと確かに感じる。実際、新しいアイデアに関して活動しているときや、女性と愛し合っているとき(これも、生まれてくるかもしれない子供という新しいアイデアについての活動だ)、あるいは、山に登っているときぐらいにしか、自分が本当に生きているという感じがしない。それは強烈な、非常に強烈なものなのだ。
新しいアイデアに取り組んでいるときには、他のことはすべて脇にどけてしまう。朝の水泳をやめるし、勘定を払わないし、医者に行くのをやめる。すでに述べたように、他のすべてのことが非実在的となる。無理をして新しいアイデアに取り組むように仕向ける必要もない。
この中でも特に、アイディアが「私の周りの人よりも実在的に感じる」という箇所。
もちろんわたくしも、物理的に目の前にいる人に対して「あなたに実在性を感じない」などと口走ったりはしない。さすがに人間が物理的に目の前にいる時に実在性を感じないというわけではない。
でもついさっきまで会っていた人に対して、非実在的な何かを感じることがある。
今日会った、あの人。
あの人は、本当に実在しているのだろうか?
本当に?
間違いなく?
そういうものとは別に、自分の小説の登場人物の生々しさを奇妙に感じることもある。
2009年夏から構想を練っていた小説は特に強烈だった。主人公たち4人が活発に頭の中で動き回っていた。よく登場人物が勝手に動くというが、この小説についてはあまりにも特別で、あまりにも生々しい存在だった。
イマジナリーフレンドとも違うし、内なる声とも少し違っていた。
彼らは彼らの世界に住んでいるため、わたくしの言動にツッコミを入れてきたりはしない。わたくしと活発に議論をしたりすることもない。
でも、彼らが彼らの世界で交わしている議論から、わたくしは実にたくさんのことを学んだ。
この小説は文体についての実験的な要素を含んでおり、そうなっていることにはSF的な意味もある。
わたくしは、彼ら4人から小説という存在について教わったという感じもする。
この2009年夏からの小説については未完である。なお、この小説は二次創作やナマモノ的要素のあるものではなく、この4人に明確なモデルはいない。
2021年から書き始めた『ダグラス・ジェネルベフトと7人の暗殺者』( https://ncode.syosetu.com/n9355gw/ )でも登場人物のうち2人が似たような生々しさを持つことがあった。こちらの2人については、2024年夏に小説を完結させて以降、生々しさは完全に消えた。
完結によって、わたくしと彼らの世界のチャンネルが完全に切断されたという感じがする。
確かに彼らは今も生きているという感じはするのだが、あの世界の新しい事実を知らされるということはもはや起こりそうにない。
念のために強調しておくが、『ダグラス・ジェネルベフトと7人の暗殺者』もまた、二次創作やナマモノ的要素のある小説ではなく、登場人物たちについて明確なモデルというのは存在しない。
わたくしが物理的に会う人に対して小説を書いていることを誰かに告げることはあっても、こういったことを口頭の会話でわたくしが話すことは皆無である。
N型が現実の具体的な対象を取り扱うのが苦手であることは、N型が他人と会話していて話が噛み合わないと感じる要因の一つだろう。
これは子供のころからずっとそうなのだが、他人が考える「あいつはこういうことを考えているのではないか」ということと、実際にわたくしの頭の中にあることに途方もないギャップがあることが多い。宇宙的なギャップといっていいこともある。
他人の的はずれな「きっとこうに違いない」や「こうであってほしい」も、先にまず違和感があってその違和感の答えがほしいと思って誠実に思考を重ねた結果であるような場合もあることは理解している。
でもとにかく、わたくしはそんなことは考えていないというのが実態なのだ。
わたくしがS型に話を合わせようとしてしまうことが多いため、S型を混乱させることがあることは自覚している。
わたくしは話題をふるのも苦手である。
じっくり考えてから話題をふっても、だめだ。S型とN型の違いを考慮に入れて話題をふっても、やはりだめなのだ。わたくしが話題をふると、お通夜になりやすいのである。
だから相手に合わせるしかなくなる。
インターネットのおかげで、N型が話題のチョイスに悩んでS型に合わせてしまう問題について可視化されるようになってきた。
N型の性質が強すぎる筆者の人生失敗談|イブリース(2024-01-03)
https://note.com/luciferlove/n/nd01b17ec4f0cmbtiのSとNの見分け方|紺(2024-01-23)
https://note.com/bright_dunlin261/n/n7edfe01119c1【N型の会話の特長?】続かない会話、弾む会話|はこねのもり(2024-09-03)
https://note.com/yumotogawara/n/n87e67817b3dc
実際には会話に参加している全員がN型であるにも関わらず、気を使って全員にとって合わない話題を選んでしまっているような場合もありそうだ。
これは「アビリーンのパラドックス」と呼ばれるものの一形態かもしれない。
アビリーンのパラドックス - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
高知能のN型の場合は話の合わせ方も巧妙になることがあり、簡単に「見分ける」というのが可能だとは思わないほうがいいかもしれない。
ところで、今回の記事をここまで順番に読んできた人であればお気づきかもしれないが、2つ前のセクション「一人の時間とダウンレギュレーション仮説」はN型の世界観に寄せているセクションで、1つ前のセクション「音と住環境」はS型の感覚に寄せているセクションになっている。
「一人の時間とダウンレギュレーション仮説」のセクションでは、そもそも「一人の時間」がどういうものか曖昧である。
頭の中で起こっていることが延々と語られ、独自概念が出てきて仮説が述べられたりもする。
偶然の一致に意味を見いだす傾向もN型に親和的だ。
対して、「音と住環境」のセクションのほうでは、音という具体的な存在にフォーカスしている。何を問題にしているのかが明確である。すでに他人によって踏み固められた「感覚過敏」や「ミソフォニア」などの概念も提示し、URLも示している。すでに共有されている概念は、S型とN型の相互乗り入れがしやすくなる。
S型のほうが音に敏感という話ではないことには注意してほしい。それどころか、INxxとISxxを比較するとおそらくINxxのほうが音に敏感な人が多そうだ。
「音と住環境」のセクションに書いたことの中では、「言葉の糸」というのは比較的分かりにくい部類に入りそうだ。それを読者が分かりにくいと思うかもしれないことを予想して、時計の修理というS型にとってイメージしやすいもので例えている。
「一人の時間とダウンレギュレーション仮説」のセクションでは「地下室」という言葉を用いたが、これは比喩あるいは象徴としてである。対して「音と住環境」のセクションのほうでは、コンテナという非常に具体的なもので考えている。
そもそも衣食住というのはS型に親和的である。N型がこれらを気にする時、何らかの形で現実から遊離した理想がからんでいることが多い。
S型にも分かるようにすることで、かえって誤解が広がるということもあるかもしれない。
例えば、前述のように時計の修理で例えてしまうと、部品という具体的なものを扱っている時だけが繊細な時間なのだと思う人が出てくるかもしれない。実際には、文章を直接打ち込んでいる時よりも、ぼーっとしている時のほうがはるかに繊細で微妙なことを考えているということがある。
S型に合わせるというのが、どんな時でも良いわけではない。
それでも、S型の存在を意識するというのは、N型を現実とつないでくれる効果があるかもしれない。
N型ばかりで集まると、それぞれが尖ったことを考えてはいるけれど、チームとしての成果、あるいは会社としてのプロダクトに、これといえるものが何もないということも起こりやすくなる。
S型にとっては、文脈的なやせ細りは安心をもたらす。意外に見えるものも、「なんだ、結局そういう話か」と回収されることによる安心。
N型は逆に、文脈的に広がることに安心する。何気ないように見えるものが、予想していたよりも大きい文脈の中に位置づけられることによって生まれる安心。
この溝は簡単に埋められるものではない。
偶然の一致に意味を見いだすというのも、基本的には「ノイズ」を大きな文脈の中に位置づけるものであり、N型に親和的といっていい。
ただしS型の場合でも、自分の立場をおびやかす危機感や恋愛がからむと、偶然の一致に意味を見いだす機会が増えるかもしれない。
よく知らない人間の何気ないしぐさや行動選択について、「実は敵対勢力の意図が反映されている」とか「実はあの人は自分のことが好き」と想像するというのは、ありがちな話に落とし込むという側面がある。
わたくしが「ジョブ型の関係とメンバーシップ型の関係」のセクションで述べたヤマノイモ・ウォッシュも、無理やり同心円の中に位置づけることによって予定調和に落とし込んでいるといえる。
N型の場合は、危機感や恋愛とは無関係のことについても、大きな文脈でとらえようとする。
『MBTIへのいざない』のP.18では、N型(直観を指向する人)について以下のように書かれている。
同じように直観を指向する人も, 具体的なことに気づいていることもあるが, たとえば, 今日見た事実の意味を知るため, あるいはそれらを意味あるものとするために, もっと大きな文脈のなかでとらえようとするのである。
ありがちな話や予定調和ということでいうと、正常性バイアス(normalcy bias)との関係も気になるところである。
正常性バイアス - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E6%80%A7%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9
N型の場合、異常性バイアスとでもいえるようなものがあるかもしれない。
ところで、偶然の一致といえば、ユングのシンクロニシティ(共時性)を連想する人も多いだろう。
岡田尊司『パーソナリティ障害——いかに接し、どう克服するか』(2004年刊)のスキゾタイパルの章では、ユングのそういう側面が紹介され、「共時性」への言及もある。
中井久夫がユングやシンクロニシティ(共時性)についてどう思っていたのかについては、ちくま学芸文庫版『「伝える」ことと「伝わる」こと』に収録の「私のユング風景」や、ちくま学芸文庫版『隣の病い』に収録の「共時性などのこと」を読むとよく分かる。
河合隼雄の対談集『心理療法対話』(2008年3月刊)に収められた中井久夫による解説「河合隼雄先生の対談集に寄せて」でも、日本におけるユング心理学の受容やシンクロニシティについての解説がある。この解説はみすず書房の『中井久夫集 10』にも収録されている。
シンクロニシティのとらえ方についてはドライに見えるが、以下のようにも書いている。以下は『中井久夫集 10』P.80より。
プラグマティストの私には、偶然を偶然に返し、そこから自由連想によって思いがけないヒントを得るということでよいであろうと思う。「シンクロニシティ」はまったく人間世界に属し、「発見論的 heuristic」である。人生も精神療法も大いに偶発的に左右され、それに翻弄されることもあるが、それを活用して思わぬ展開が起こることもある。
これはまさしく、「シンクロニシティ」概念に心酔する人を「あたたかく突き放し、冷たく抱き寄せる」ものであるようにも思える。
中井久夫は「プラグマティスト」や「実践」という言葉を前面に出したりすることもあるが、自分を実務能力の低い存在とみなしていたようだ。特に精神科医になる前のウイルス研究の時代は、アイディアで他人を引っ張ることはあっても、不器用なために実験では失敗が多かったとしている。
ちなみに2017年から2019年にかけて刊行されたみすず書房の『中井久夫集』は発表順に収録されているのだが、そのスタートは1964年発表の「現代社会に生きること」と「現代における生きがい」である。精神科医になる前の30歳の時であり、上原国夫名義での発表である。
そこでは人間の「性能」を重視する「苛酷な現代」への批判的視点がある(2005年刊『関与と観察』P.139〜P.144、みすず書房版『中井久夫集 1』P.25〜P.30)。「性能崇拝」という言い方もしている(2005年刊『関与と観察』P.126、みすず書房版『中井久夫集 1』P.13)。
1964年といえば今から60年以上前である。この2つのエッセイでは、「魔女裁判」や「アフリカ社会」や統合失調症やカフカへの言及もあり、すでに自分自身への出題が完了している感がある。そして中井久夫がSFやAIやオートメーションにも関心があったことが分かるのだが、それについてはまた別の機会に、ということにしよう。
わたくし自身も実務能力が低いために本当にそうだと言っていいのか迷う時もあるが、おそらく実務というのは、基本的に文脈的なやせ細りによって成り立っているという側面がある。
何かあるたびに大きな文脈に位置づけようとすると、作業は進まない。
実務の現場では特にそうなりやすいのかもしれないが、S型はN型の頭が悪いと思いやすく、N型はS型の頭が悪いと思いやすい。
S型(感覚タイプ)とN型(直観タイプ)について、『MBTIへのいざない』のP.187には以下のようにある。
実際, お互いに簡単に相手の頭が悪いと信じ込んでしまう。
このギャップは非常に根本的で、何かに気をつけていればいいというものではない。
『MBTIへのいざない』には以下のような箇所もある。P.186〜P.187。
感覚を指向する人が三人と直観を指向する人が二人からなるチームの職場ミーティングがあったとする。一方は実際に起きていることに焦点を当てて, 問題点となっていることの具体的な要素をみようとし, もう一方は, 同じ問題点において, 今後起こりうるかもしれないことに焦点を当てながら, さまざまな解決方法の可能性を検討しようとしてしまうので, 議論は対立し膠着化してしまうことになる。そのような対立の状況下では, 必然的に, あたかも他方のグループが焦点を当てるべきところが間違っていると見え, 対立の緊張度が高まりやすい。
『アンチパターン——ソフトウェア危篤患者の救出』という本のP.254に「ミニアンチパターン: 実装溺愛」というものが紹介されている。
この本の実装派(implementationists)はS型に親和的で、抽象派(abstractionists)はN型に親和的であるように思う。
『MBTIへのいざない』P.187の「他方のグループが焦点を当てるべきところが間違っている」というのが、プログラミングにおいても際立つ。
『アンチパターン』P.254〜P.255には以下のようにある。
抽象派は、実装詳細に深入りせずに、ソフトウェアの設計コンセプトを議論することが得意だ。彼らはいわゆるアーキテクチャ的嗅覚をもっており、ソフトウェアの良質な抽象化を定義し説明できる。一方、実装派は、抽象的な概念を理解するためには自分の目の前に実際のソースコードを必要とする場合が多い。
P.255には以下のような箇所もある。
抽象派は、複雑性の管理が設計の中心圧力であることを、本能的に知っている。良質な抽象が実現しないことが多いのは、その意味や重要性を理解できないデベロッパが多いからである。その第一の結末は、ソフトウェアの異様に複雑な設計である。
私見だが、まずい設計の元で仕事をするほうが、優秀なプログラマーがやりがいを感じてしまう場合があるように思う。設計に対して疑問を呈するのではなく、まずいところはまずいままでいてくれたほうが自分の才能が際立つのである。これを「まずい設計のパラドックス」と呼んでもいいかもしれない。
このパラドックスについては、AIの活用によって一時的に覆い隠される可能性があるが、長期的にはむしろ深刻な形で表面化する可能性もある。
ところで、最近は日本でもギフテッドという概念が浸透している。
このギフテッドについての議論で、それは知能の高さの話ではなくS型とN型の認知特性の違いなのではないか、と思うことがある。
例えば『ギフテッドの光と影——知能が高すぎて生きづらい人たち』(2023年5月刊)のP.90の「自分の頭が悪いことを受け入れろ」と上司に言われたというギフテッドのエピソードなども、そうかもしれない。
この本の「自分の頭が悪いことを受け入れろ」のエピソードについては、AERA DIGITALで無料で紹介されている。
36歳「ギフテッド」男性が社会で味わった絶望 「頭が悪い」「使えない」と上司や医師が人格否定 | 概要 | AERA DIGITAL(アエラデジタル)(2023-06-18)
https://dot.asahi.com/articles/-/195008人生に失望した36歳「ギフテッド」男性はなぜ転職先で成果を出せたのか 「社会性が低い」の誤解 | 概要 | AERA DIGITAL(アエラデジタル)(2023-06-18)
https://dot.asahi.com/articles/-/195009
知能の差に見えるものをすべて性格の問題に置き換えて考えるべきだ、などと主張したいわけではない。
そもそも知能テストというのは、そのあり方によってはN型のほうが高得点になりやすいという性質がある。「高知能」というのが何を指すのかよく考える必要がある。
最近は合理性障害(dysrationalia)という概念も注目されている。
スティーブ・ジョブズが代替療法に走ったことも、この合理性障害と結びつけられることがある。
数学者のゲオルク・カントールはシェイクスピアとフランシス・ベーコンが同一人物であるという説の「証明」に熱中した。
シェイクスピア別人説 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%94%E3%82%A2%E5%88%A5%E4%BA%BA%E8%AA%AC
カントールが合理性障害かどうかは分からないが、シェイクスピア別人説は当時の高知能のN型を強く惹きつけるものだった可能性は高そうである。
N型が持つ遠さとの親和性は、非現実的なアイディアに強く惹きつけられやすくなる。
合理性障害やMBTIのSN指標についての直接的言及はないかもしれないが、サトシ・カナザワ『知能のパラドックス』(邦訳は2015年刊)でも類似した問題を扱っている。この本の邦訳のサブタイトルは「なぜ知的な人は「不自然」なことをするのか?」である。
この「パラドックス」のわたくしからの回答としては、既存の多くの知能テストはN型が高得点になるように設計されており、S型が高得点になるように設計されているような知能テストがもしあれば、その不自然さは解消されるのではないか、ということになる。一方で、創作や研究で際立った評価を受けた人は、S型が高得点になるような知能テストでは低い結果になりがちだという、別の不自然さをその知能テストが抱えることになるのではないか。
中井久夫のエッセイ「世に棲む患者」には以下のような箇所がある(ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.36、みすず書房版『中井久夫集 1』P.222)。
まず、「信頼しにくいはずのものに軽信的で、まず信じてよさそうなものへの不信」という逆転がある。これと近縁なものをいくつか挙げれば、「遠い可能性をすぐ実現しそうに思い、手近な可能性を等閑視(遠く感じる)する」という逆転もある。
これはまさに、N型についての説明にもなっている。
もちろん社会人としてはデメリットになるわけだが、ある程度はこういう要素を持っていないと創作や研究など不可能だという気もする。そして企業経営や投資などにおいても、こういう「逆転」こそがイノベーションを促進しているはずなのである。
岡田尊司『パーソナリティ障害——いかに接し、どう克服するか』(2004年刊)のスキゾタイパルの章には、スキゾタイパルの人は「技術革新に携わる仕事や研究者」に多いとある(P.196)。
また、P.199には以下のような箇所もある。
スキゾタイパルの人は、身近なことや、人付き合いが苦手である。抽象的な話を好み、現実のことよりも、非現実のことに興味を持つ。そういう傾向から、どうしても空ばかり見ていて、穴に落ちてしまったギリシャの哲学者に似るところがある。足元がおろそかになりがちなのだ。
こういうものもまさに、N型についての説明として機能する。
そういえば、SNSで目立っている理系人材はxSTxが多いように思える。また、それと意識せずにxSTxに擬態しているxNTxも多そうだ。
大衆の側を軸足にすると、どうしてもS型の世界観に合わせるのが当たり前になってしまう。
前述のように、不用意にN型の世界観を前面に出すと「怪しい人」になってしまうため、なかなか本音を言えないという人もいるだろう。
N型が本音を言うと「奇をてらっている」とか「斜に構える」とか「逆張り」などととらえられることがあるのも悩ましいポイントかもしれない。
逆にN型とっては、S型の言う「王道」というのが、テンプレをなぞる罪悪感や独創性のなさをごまかすための言い訳にしか見えないという場合がある。
S型の常識や定石との親和性の高さから、常識に守られた内側で生きるS型とその外で生きるN型、というのはイメージしやすいかもしれない。
S型から見ると、人工的だが快適なドームで暮らすのが誰にとっても最適であるはずで、ドームの外へ出たN型の人々が広大な砂漠のような場所で苦しんでいると感じることがある。「死屍累々」である。無理をして出なくてもいいのに、というわけだ。
逆にN型は、S型の人々はジャングルジムのようなところにぎゅうぎゅう詰めに閉じ込められて、かわいそうだと感じることがある。「自縄自縛」というわけだ。
日本の場合、高知能のN型が東京に集まる傾向があるのは皮肉といえるかもしれない。物理的には、人口密集地で暮らすN型が多くなるわけだ。
また、東京がN型人材を吸い上げてしまうために、地方が抱える問題を俯瞰的にとらえる人が現地にいない、ということが起こりやすい。
現実的には、目の前の具体的な問題を片付けるS型がいなければ成り立たない領域は多数ある。一方で、長期的な方針にS型の意見を反映させるとおかしなことになりやすい。
前述の『アンチパターン——ソフトウェア危篤患者の救出』でも、抽象派の意見が多数決ではよく否決されてしまう(abstractionists are often outvoted)という問題が指摘されている。
S型に対しては「手を動かす」という言い方はよく響く。でもN型に対しては、「手を動かしているヒマがあったら考えろ」とたまには言わなければならない時もあるかもしれない。
『知的労働をしている人が働き方改革で一番困るのが「効率的に働け」』……アホな上司にかかると、ひたすら手を動かしていないと効率的とは認められない。 - posfie
https://posfie.com/@Count_Down_000/p/vLFF8EH設計解がないと思われた製品にエースエンジニアが投入され、翌日あっさり大枠をまとめて来た→その解決方法がカッコよすぎた - Togetter [トゥギャッター](2022-08-06)
https://togetter.com/li/1926743『不安耐性、判断を保留する能力、抽象のままにして具象に落とさない能力』…これが無いと、いきなり問題を解決しようとするので、問題そのものを議論できなくなる - posfie
https://posfie.com/@Count_Down_000/p/LwYsv12
3つめについてはネガティブ・ケイパビリティの話で、つまりJP指標とも関係がある。ネガティブ・ケイパビリティはあくまでも自分の中での判断であって、根本的に信用していない人間(人間たち)の不穏な動きを放置する能力を指すわけではないということは留意しておく必要がある。
N型も、ただじっとしているのが良いとは限らない。散歩だったり、ノルマとは無縁のDIYだったり、そういうものが思考をうながすこともあるだろう。
プログラミングの知識がある人にとっては、クラスとインスタンスの対比は、SN指標を考えるうえで参考になるかもしれない。
先ほどの『MBTIへのいざない』P.186の引用箇所でいうと、S型は「実際に起きていること」そのものに直接的に接触しながら考える。
これはつまり、インスタンスをより生々しい存在として感じるということだ。クラスは所詮クラスにすぎず「実在」しているわけではないだろう、というわけだ。
逆にN型は「実際に起きていること」そのものよりも、起きた問題はどういう「問題クラス」のインスタンスなのか、ということを考える。「実際に起きていること」はインスタンスに過ぎないのだから、そこに拘泥しすぎてもしょうがない。「問題クラス」のほうが生々しい存在であり、「問題クラス」のほうを考えるのは当然、というわけだ。
VRChatなどではワールドにおいてインスタンスという概念があり、プログラミングの知識がない人にもインスタンスという比喩を使いやすいかもしれない。
会議などにおいて噛み合わない場合、もし可能であれば、ファシリテーターが「誰それはインスタンスに着目して、誰それはクラスに着目してるわけだね」と誘導することが有効に作用することもありそうだ。でも、そもそも会議の目的は何なのかということを定義し直すことを迫られるかもしれない。
クラスに注目するというのは、必然的に関係性に注目するということにもなる。
IxTxが持っている、宇宙の外からの介入の感覚との親和性については「パフォーマーという存在、あるいは花とタネ」のセクションで解説した。このIxTxの感覚と、N型が持つ遠さとの親和性が組み合わさると、より一層濃厚に宇宙の外からの視点を求めることになるかもしれない。
ISTxがビルの5階や10階あたりから眺めるぐらいでもいいと考える時、INTxはもっともっと遠くから眺めたいかもしれないわけだ。
日本のSNSでは「何者かになりたい」という願望について議論になることがある。「何者問題」とも呼ばれるようだ。
わたくしがこの議論をまったく理解できないことの一因として、自分は宇宙の外から眺めていたいだけだというのが当然の感覚だからというのはありそうだ。
ESFxで「何者問題」に悩むのは健全だが、INTxでありながら「何者問題」に悩むのは不健全だ、といえるかもしれない。
あるいは、INTxであるがゆえに、宇宙の外から眺めるというその状態をキープするために非常に多くの「税金」を払わなければならないと思う人はいるかもしれない。そういう人は、その「支払い」のためには便宜的に「何者」を前面に出す必要があると考えたり、焦燥感が強くなったりすることもあるだろう。
S型とN型の世界観の違いは、対数グラフで例えることも可能かもしれない。
S型は普通の目盛りのグラフで、N型は片対数グラフ。
N型のほうについては、Y軸(つまり縦方向)が対数軸になっているような、そういう対数グラフをイメージするといいだろう。
N型が対数グラフ上できれいに見える曲線を描いている時、S型はそれを普通の目盛りのグラフにマッピングし直したものを見ている。
N型同士であれば、わあ、きれいな曲線だね、となるものが、S型にとっては途中で線が切れているために混乱する。あるいは、S型でも全体が視界に収まるようにするために、何か特殊な処理を加える必要があるかもしれない。
逆に、S型が普通の目盛りのグラフ上できれいに見える曲線を描いている時、N型はそれを、グラフのごく一部だけを使ってせせこましいことをしていると感じるかもしれない。
ところでSNSでは、INTPが効率を極限まで求める性格として言及されることもある。
それは間違ってはいないのだが、INTPの効率は、無駄なことをやらないというよりは、前提を根本的に変えることを志向しやすい。
例えば湖の向こう岸へのロジスティクスが問題となる場合を考えてみる。全員が湖岸道路の整備や業務プロセスの効率化について考えている時、INTPは橋をかける方法を延々と考え続けているかもしれない。そしてINTPの意見が採用されて実際に橋の建設が始まったころには、INTPはまったく別のことに関心を向けているかもしれない。
同じように「効率を良くする」というフレーズでも、こういう違いが出る。
こういった良く使われるフレーズや「事実」や「再現性」のような言葉においても、S型とN型でイメージするものが違っているということはよくある。
同じジャンルや同じ対象に興味を持っていたとしても、S型とN型で視点が違いすぎることが浮き彫りになってしまうこともよくある。
N型の場合、端的な事実を伝えることによって実際には可能性の話をしているということもあるだろう。
例えば「近所の公園でウサギの死体があった」という端的な事実を提示することにより、実際には「次は龍の死体なのか?どうやって用意するのか?どれくらいのサイズなのか?」ということに意識を向けたがっているのかもしれない。
それはつまり、その公園ではすでにネズミの死体、牛の死体、虎の死体が見つかっていて、その流れを当然相手も知っているはずだという前提なわけだ。
もし相手が龍の死体のことを思い浮かべていないことが判明すると、そのことがN型には信じられないと感じられるかもしれない。龍の死体という可能性について直接的に言及したにも関わらず、相手から「それは今考えることではない」とか「それは我々が考えることではない」などと言われたりすると、N型は混乱するかもしれない。
構造的な違いのことを認識していれば、知能が高い側が低い側に合わせるべき、などというのは幻想だということが分かるはずである。前述のように多くの知能テストでN型が高得点になりやすいが、高知能のS型と高知能ではないN型の対話においても同様の問題がありそうだ。
S型かN型かは簡単に判別できるとは限らないこともある。知能においては、大は小を兼ねないのだと思っておくのがいいかもしれない。
N型にとっては、S型が現実との架け橋になるようなケースは多々ある。一方で、S型としか話す機会がないと、脳が物理的に萎縮していくのではないかと思うこともある。
無理をしてS型に合わせようとすると、話せば話すほど疲れることになるため、もしS型しか話し相手がいないのであれば、精神的な危機が訪れているN型は誰とも話さないほうがいいということもありそうだ。
わたくしの場合、N型やISTxと交わした会話を何度も何度も反芻することによって危機をやり過ごすこともある。ただし、あまり反芻をやりすぎると会話の内容が改竄されることもあるので要注意である。
ところで、「対話と油絵法」のセクションで紹介した『MBTIへのいざない』での「ジョン」のビー玉の例えは、ISxxに親和的という気がしている。
わたくしのように無限に分岐していく細い糸のほうが近いと感じるのは、INxxに多そうなのである。
INxxのほうが、いま何を考えているということを言語化しにくい状況が多いのではないかということでもある。
役割と意外性
そろそろこの記事も終わりだ。
「推し」という概念について書いておきたい。
わたくしには、いわゆる「推し」というのはいない。
おそらく、何かのファンになった経験というのがない。
子供のころから、「何のファン?」あるいは「誰のファン?」と質問されても、どう答えて良いのか分からないことが多かった。
これはおそらく、「この中の誰と仲良くなりたいの?」みたいなことを言われると困るというのと似ているかもしれない。
こういうのも結局、関わりたい人がいないという話とつながっているわけだ。
そして、二次創作に憧れつつ、二次創作をやらないという話にもつながる。
特定の対象に関心を持ち続けることがわたくしには難しいのだ。
もちろん、今後のことは分からない。二次創作的なものを何かやるかもしれないが、おそらく文章ではない可能性が高い。
S型とN型の違いについては、1つ前のセクション「SN指標についての雑感」で述べた。
N型であるわたくしは、具体的な対象に関心を持ち続けることが難しい。
推しというのは、今後もいないのではないかと思う。
ちなみにSNS等で使われる「尊い」という言葉は、具体的な対象よりも関係性が前提になることがほとんどである。「推しカプ」などの言葉も、特定のキャラという具体的な対象よりも、その関係性のほうが重要視される。推しキャラのカップリングということではなく、カップリングを推すというニュアンスが込められることが多い。
わたくしにとって中井久夫のような存在は、広い意味での推しだといえなくもないのだが、それでも前述のように4ヶ月以上も死んだことに気づかないのである。
そんなわたくしでも、わたくしに関わりたいと思っている人には、興味があるのだ。ここは誤解しないでほしい。
関わりたいのかどうかよく分からない状態が続くと、疲れることもある。
2016年ごろから特にそうなのだが、わたくしの周囲で無言でウロウロする人の存在をどう考えればいいのか分からない。周囲で、というのは物理的にということだ。
好意的なものもあれば凝視するだけの人もいて意図がよく分からない。明確な敵意があるほうが、かえって疲れない。意図が分かるからだ。
もしかして「話しかけてほしい」とか「積極的に関わってきてほしい」とかそういうことを考える人もいるのだろうか、思うこともある。
もしそうなら、それはわたくしからするとコペルニクス的転回になる場合があるということも、今回の記事を読んでもらえればよく分かるはずだ。
とにかく、わたくしに行動を期待しないでほしいのだ。
考えることと書くことがわたくしのやるべきことだ。
わたくしはほとんど常に「話しかけてきてほしい」と思うし「手伝ってほしい」とも思っており、わたくしに多少なりとも興味があるならそれは当然伝わっているものだというつもりでいる。
文章を書いたりコードを書いたりする人がふだん何に悩んでいるのかということも、わたくしを知っているなら多少は知っているはずだというつもりでいる。
人によっては、わたくしの文章を読んでも、どういうつもりで書いているのかよく分からないと思う場合があるかもしれないことは想定している。
わたくしは理想主義だからこそ、需要と供給をあまり気にしない。車を知らない人を対象にして需要をリサーチしても、結局は「もっと速い馬を」にしかならないだろうと思っている。
また、需要と供給というのは交換が前提である。
わたくしの文章は、交換という文脈に乗りにくい気がしている。
pixivFANBOXのようなものが今後どうなるかは分からないが、交換とは違う形の何かが定着すればいいという期待は持っている。
わたくしは2025年5月28日時点で、pixivFANBOXで支援している人が6人いる。逆に支援される側はまだゼロだ。
わたくしが支援しているのは、それぞれ毎月100円だけである。だから合計で月に600円だ。
6人ともVRChatがなければその存在すら知らなかったかもしれない人々で、すでに発表されたものがあるから支援しているわけなのだが、必ずしもすでに表に出てきているものに対しての対価のようなものとして支援しているわけではない。
もしもその人たちがまったく新しいことを始めたいと思った時に、その新しいことを後押ししたいというのもあるわけだ。
ちなみにその6人についても、物理的に会ったことがある人はいないし、ふだんXなどでどんなことを発信しているかチェックすることはほとんどない。6人の中にVRChat内でフレンドとして登録している人もいない。
この6人というのが誰と誰だったのか思い出せなくなることもある。
でもまあ、それぐらいでちょうどいいのではないかなと思う。
今後はどうなるか分からないが、わたくしが支援している間は、支援対象や周囲の人にとって「ほどよい意外性が続きますように」という思いを込めることもある。
ところで、わたくしは自分の言動について明確に説明しないことも多い。
でもこれは「気持ち」を察してほしいわけではない。
思考のトリガーになると面白いかもしれないという期待があるだけだ。
誰かを悩ませるつもりはないので、悩ませているなら先に質問をしてほしい。
ログイン不要で、誰でもいつでも質問ができる「お題箱」を設置している。
cleemy desu wayoへのご質問 (@cleemy_desu_wayo) | お題箱
https://odaibako.net/u/cleemy_desu_wayo
LINEやインスタ(Instagram)などに誘導して、そこで質問を受け付けようとするのは、すべてなりすましなので注意してほしい。
わたくしは2025年5月28日時点で、LINEやインスタには一度もアカウントを作成したことがない。
質問があるという時点で、その問いの立て方に何か重要な意味があるかもしれないとみなすつもりである。だから「検索すれば分かるだろう」だとか、「先にAIに聞いておけよ」みたいな回答はしない。
わたくしとやり取りする機会がある人が、わたくしとの直接のやり取りで疑問が解消したあとに念のために「お題箱」から送っておく、というのもかまわない。
ある人が疑問に思ったことは、別の誰かが疑問に思うことかもしれない。
インターネットを通じたもろもろについて、明らかに悪質なものや、「これが嫌がらせのつもりだとしたら悪質だ」といえるものを目撃したら、「お題箱」のようなものよりも先に警察に連絡したほうがいいかもしれない。
わたくしに関連して「おかしい」「困っている」があれば警察庁のフォームへ|cleemy desu wayo(2025-01-13)
https://note.com/cleemy/n/n2c844e1f6d0d
ところで、2008年ごろだったと思うが、わたくしが固定電話を引いた時に、友人の携帯電話に何度も電話をかけたことがあった。
この時、発信のタイミングを調整して、分がフィボナッチ数列になるようにした。
20時台だったのかどうかは忘れたが、例えば
20:01、20:02、20:03、20:05、20:08、20:13……
のような感じで着信が残るようにしたわけだ。
あくまでも謎かけであり、すぐにタネ明かしをするつもりだった。
この友人とはフィボナッチ数列の話を何度もしていたので、この未知の番号がわたくしだと分かるだろうと期待していた。でもこの時はタイミングが悪かったようで、この友人はわたくしであると気づけなかった。しかも、わたくしの知らない別の誰かとトラブルになりかけていたタイミングらしく、その別の誰かが暴走した可能性を思い浮かべてしまったらしい。
最近はなりすましが流行していることもあるので、誰なのか分からない形でこういうことをするのはやめておこうと思うようになった。
ちなみにこの友人は2022年春あたりから連絡をとっていないため、どうしているかは知らない。当時のことをどう思っているのかも分からない。
もしわたくしに関することで誰かを悩ませてしまっている時、別の誰かが何か的はずれなことを言っている可能性についても考えてみてほしい。
誰かが何か的はずれなことを言っているという可能性にわたくしが気づくこともあるが、それに気づいたとしても、ほとんどの場合は「誰が・どこで・何を」という詳細が分からない。そのことで誰かが悩んでいるのかどうかも分からない。
「誰が」と「どこで」についてはぼかしたうえで、概要だけをわたくしに提供することも可能なのではないかと思う。
状況と情報を分離してほしいのだ。
ほとんどの場合、犯人探しをしたいわけではないから。
もちろん、わたくしには何の興味もないとか、別に何も困っていないというような人が無理に「お題箱」を使う必要はない。
とにかく、わたくしには情報がない。
でも情報がないことは、わたくしは短期的には特に困らない。わたくしは関係性の中で生きていないからだ。
でも、わたくしに情報がなさすぎることで、誰かを不必要に困らせていることもあるのではないか、という気がすることもあるわけだ。
情報の流通ということを考えると、良かれと思ってわたくしを「仲間」だとみなさないほうがいいかもしれない。
連携を装うことによって利益を得ようとするというのはなりすましと同じような性質があって悪質といえるが、そういう話ではなく、善意によって広義の「連携」があるのだと宣言してしまうような場合。
「かわいそうな人だということになってしまうから」とか、「不気味な人だと思われてしまうから」とか、そういった理由で善意で「仲間」と呼んだり連携があると宣言してしまう場合もあったりしていないか、というのが気になるのだ。
また、似たような理由で、わたくしが提示したものについて「あれは内輪ネタなんですよ」と善意で宣言してしまいたくなることもあるかもしれない。
こういったものについては、長期的には、スキゾタイパルの傾向がある人を非常にまずい立場に置くことになる場合がある。
スキゾタイパルは噂話が苦手なことが多い。そういう噂話にあからさまに居心地の悪さを表明したりするかもしれない。
そういうことが続くと、誰も彼もがいかなる噂話も避けるようになってしまい、非常に基本的な情報すらも入ってこなくなることがある。
『0円で空き家をもらって東京脱出!』(2014年刊)というエッセイ漫画に、「浅い会話」が得意で幅広くいろんな人とコミュニケーションをとっている女性が登場する。そしてこの人がコミュニティにおいて重要な存在であることが強調されている。「浅い会話」が得意というとS型に多そうだが、ENxxが意図的にああいう役回りをしているケースも多そうだ。
こういう「浅い会話」によってスキゾタイパルの人にも情報が伝わり、また他の人が知りたがっていることがそれとなくスキゾタイパルの人にも伝わる。
残念ながら、ここ5年ぐらいのわたくしの周囲には、こういう「浅い会話」によって情報の流通を後押しするような存在がいない。
この「浅い会話」はコミュニティにおいて重鎮といえる存在がやるから意味があるといえそうだ。
もしも幅広くコミュニケーションをとる人が、権力志向の強い人の意向を受けて動き回るような場合には、その権力志向の強い人にとって都合の良い情報だけが流通するようになる。
いずれにせよ、「浅い会話」とスキゾタイパルの相性は悪いように見えて、そうでもないのである。
「浅い会話」が演技がかっている場合は特に、前述のように演技性パーソナリティとスキゾタイパルの共犯関係の一例ともいえる状態であるようなケースも多々ありそうだ。
もちろん、その演技というのが不誠実さとして映ってしまうと、スキゾタイパルの人は警戒するだろう。タフさのような形で肯定的にとらえられている必要はありそうだ。
こういうことがあるからこそ、わたくしは物理的なアポなし訪問を歓迎するというメッセージを何度か発したこともある。オンライン上のやり取りだとかえって目立ってしまうという場合があるかもしれないというのもある。
今回の記事の「パフォーマーという存在、あるいは花とタネ」のセクションをじっくり読んでもらえれば分かると思うが、「かわいそうな人」「不気味な人」はExFx(特にESFx)の世界観ではそうなるというだけで、IxTxにとってはそうではないという場合も多々ある。
また、F型は状況と情報を分離するのが苦手であるように見えることもある。
回覧板というのは、IxTxの人やスキゾタイパルの人にも情報が伝わるようなシステムだったのかもしれない。わたくしは長らく回覧板を見ていない気がするが、回覧板の代わりになるようなものが現代日本にはない気がするのである。
ExFxの人が「回覧板の代わり」を構想してしまうと、それはExFxにとっては「温かみ」「親密さ」としてポジティブなものになるかもしれないが、IxTxにとっては「居心地の悪さ」「まとわりつく感じ」ということになってしまい、結局は使われないシステムとして忘れられていくということもあったりするかもしれない。
名刺などは、「本当はあの人は話が合う人だったかもしれないのに、なぜあの人の連絡先を知らないのだろう?」という状態を回避するものとして機能することもあるかもしれない。
形式的なものや形骸化したものを嫌う傾向がスキゾタイパルにはあったりするが、回覧板や名刺や年賀状にはスキゾタイパルの人をつなぎとめる効果があったという可能性はある。
GitLabが重視するドキュメント文化の場合は、スキゾタイパルに親和的かどうかはともかく、明らかにIxTxに親和的ではある。ただし、あれはPC環境と少数精鋭を前提にしたものだろう。
わたくしは1999年1月から2000年12月にかけて約2年間フルタイムのプログラマーとして仕事をしたことがあり、一年以上継続的に収入を得るという経験はこの時が初めてだ。ドキュメント文化があったのかというと微妙だが、IxTxの感覚に寄り添うのが当たり前の環境ではあったため、そうでない環境というのは強い違和感になる。
前述のように、岡田尊司『パーソナリティ障害——いかに接し、どう克服するか』(2004年刊)のスキゾタイパルの章では夏目漱石の解説がある。私見だが、商業的な領域で執筆活動をする場合は編集者が情報流通を担うケースが多いのだろう。
現代日本で「伝書鳩」という言い方が軽蔑的なニュアンスでしか使われなくなってきているように思えるのも気になるところだ。スキゾタイパルの傾向がある人を重要な存在とみなすなら、それはつまり「伝書鳩」のような役割の人も重要であるとみなすということである。
スキゾタイパルの人の書くものは、読み手の偶然の一致への感度を高める。そのことによって、P型の読み手が待ちの構えを強化してしまう場合があったりするかもしれない。もしかすると、読んだ人の待ちの構えが強化されたとしたら、それはある意味では正しく読めているということになってしまうのかもしれない。
でも一方で、読み手がずっと待ちの構えで居続けるということは、すべてを台無しにすることに加担するということでもある。
情報の流通に問題が出たり、待ちの構えが強化されたりすることと同時に、読み手が精神的な結びつきを感じることが多いのかどうかも、気になるところだ。
異性の場合は特に、連絡先すら交換していないのに付き合っていると宣言してしまうような。
そこで第三者が「お前は関係ないだろう」などと責めてしまうと「でもこの精神的な結びつきは嘘ではない」と強く反発して、「これぐらいのことは言ってもいいはずだ」に発展することになる。
わたくしも文章を書きながらある種の結びつきのようなものを感じることもあるが、たいていは具体的な誰かではない。
具体的な誰かをスタートとしても、いつの間にか集合との結びつきになる。
「特定の誰か」に向けて書き始めたはずのメッセージが、いつの間にか似たような性格の人全体とか、「今はまだこのジャンルの専門家ではないけどもうすぐ研究者になる人々」とか、場合によっては「まだ生まれてない人々」とか、そういう存在が想定読者になってしまう。
そういえば、かなりうろ覚えではあるのだが、GEB(『ゲーデル、エッシャー、バッハ』)の作者が、頭の良い中学生を想定読者にしているという主旨のことを言っていた気がする。
「頭の良い中学生」を仮定するというのは、わたくしのふだんの姿勢と一致している部分も大きい。
理想化された読者というか、公理化された読者というか、そういうもの。
実年齢が若いことがいいというわけではなく、中学生のころに戻ったつもりで読んでほしい、みたいに思うこともある。
大学に行ってしまうと、どうしても知的バックグラウンドというものが出来上がる。そういうものが出来上がる前の、読むもの目にするものすべてが新鮮だった、中学生のころ。あるいは、大学に行かなかった人の場合であれば、社会人になる前のころ。
書かれている内容を咀嚼する前に、書き手の背景を読むということがクセになってしまう前の読み手。
この背景というのが、まさに今回の記事の「ジョブ型の関係とメンバーシップ型の関係」のセクションに書いた同心円のこととも関係してくる。
非同期コミュニケーションということを前提にすると、想定読者という言い方自体が的はずれになっている場合もあったりするのかもしれない。
100年後には、「中学生」という区分も無意味になっている可能性もある。
非同期コミュニケーションがもたらす様々なズレは、意外性につながることもある。
わたくしにとって、物理的な静寂は重要だが、ほどよい意外性もまた重要だ。
どうやって折り合いをつければいいのかは分からない。
毎週のようにパーティーに出かけたりするのがわたくしにとってプラスになるとは到底思えない。そして、引きこもりは確かにプラスになる。
頭の中で起こることに意外性があるから、それで十分だという考え方もできる。
そしてもちろん、今回の記事も読む人にとってほどよい意外性をもたらすものであってほしいと思っている。
INTPやスキゾタイパルについてすでに詳しい人にとっては、冗長すぎる箇所もあっただろう。
単体の記事としては、当分はわたくしのマニフェストとして機能することになると思う。
考えることと書くことについての、マニフェスト。
わたくしが今後、声を使った発信をやるのかやらないのかはまだ分からない。
声を使うようになっても、あくまでも基本的には文章がメインなのであり、文章を読む習慣のない人に寄り添うような日は永遠に来ないかもしれない。
ちなみにわたくしは2025年5月28日時点で、作業配信やそれに類似した性質のある配信を自分の意思でやったことは一度もない。そういうことをやる日が来るかもしれないが、今ではないという感じがする。
今後のことは分からないが、20年近い cleemy desu wayo としての活動において、基本的に内輪ネタというのは1ビットたりとも存在しないということも今回の記事によって明らかになったことと思う。
そもそも身内がいないのだから、内輪ネタも成立しようがない。
わたくしという一人だけの「内輪」があるから、ある意味では濃厚な内輪ネタといえることはあるかもしれない。濃厚なモノローグ志向というわけだ。でもそれはあくまでも、わたくし個人に向けられたものだ。
ひとりごとを言って、一人で笑っているだけだ。
一見すると少数の人間にだけ分かるようにしているネタであるかのように見える時も、実際にはわたくし個人の文脈によって何重にも上書きされているため、あますことなく文脈が理解できるのはわたくしだけである。
誰にも話していないしメモも残していないような、わたくしが見た夢の内容がこっそり反映されていることもある。
わたくしにしか分からないからこそ実現できる豊穣さというものがあるのだ。
自分にしか分からないからこそ、自分以外の人間を特権化しないということでもある。
全人類と等距離だし、同時代の人間と未来の世代の人間が等距離であるということでもある。
それは開放的ということでもある。
狭義の内輪ネタは同心円の内側に向けるという性質があるが、わたくしの場合は同心円の内側から素材を引きずり出して遠くの宇宙へと放出するという側面がある。
モノローグだから閉じているとは限らない。
たいていの場合、わたくしの書くものは徹底的に開放的であり、誰でもいつでも気軽に言及してもらってかまわないのである。
モノローグ志向のコンテンツなのかというと、それも少し違う。コンテンツというのは、役割がはっきりしている。わたくしはたいてい、あらゆるものとあらゆるものの関係を揺さぶり、あらゆる役割を解体したいという願いを込めている。
そのような揺さぶりによって結果的に具体的な行動を促したいと思う時もないわけではない。ある種の実用性のようなものとの両立。
そうであるがゆえに、実用性のあるものはとことん実用性をもって読まれたほうがいいという場面もある。
つまり、現実との接点であり、アンカリング。
やせ細りがあるからこそ、アンカリングとして機能することもある。
心理学用語としてのアンカリングということではない。
物理現実とつなぐもの。あるいは、へその緒。
前述のように、「お題箱」( https://odaibako.net/u/cleemy_desu_wayo )経由での質問などがあってそれにわたくしが回答をすれば、それらもアンカリングとして機能することがあるかもしれない。2025年5月28日時点では、まだまともな質問が一度も来ていないけど。
GitLab .com などでコメントが来たりイシューを立てた人がいて、それにわたくしが回答したというような場合も同様だ。
以下のような、非常にSNS的で実用的な発信をすることもある。
LINEやインスタにアカウントはない|cleemy desu wayo(2025-05-14)
https://note.com/cleemy/n/ne2efcb31a2dd
そして、こういったアンカリングがあるからこそ、また豊穣なモノローグへとつながっていく。
今回の記事「関わりたい人がいないということ」についても、多少はアンカリングとしての側面を持つことを期待して書いている。
そういえば、1990年代のインターネットにおける個人サイトではモノローグ志向のものはごく当たり前に存在していた。ランキングサイトの「ReadMe!JAPAN」に参戦しているようなサイトも含めて。
あのころが懐かしいが、あのころに戻りたいとも思わない。
実用性を狙ったものもないわけではないが、わたくしの文章というのは、ほとんどの場合、他の何かのためにあるものではない。
考えることと書くことこそが目的なのであって、それは別の何かのために奉仕する存在ではない。
別の何かに奉仕するのであれば、その別の何かのほうが価値が高いのか、ということになる。
そうではなく、作品そのものに価値があってほしい。
ああ、この作品が生まれるために、人類などというものが存在したんだなと思えるようなもの。
そういうものを突き詰めていくならば。これまでの宇宙のすべての営みが、その作品が生まれるために存在したのだと思えるようなもの。
基本的には、芸術というのはそういうものだと思っている。
関連資料
書籍と映画とゲーム
まずは書籍と映画とゲームから。
ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』……「世に棲む患者」「働く患者」
ちくま学芸文庫版『隣の病い』……「時間精神医学の試み」「共時性などのこと」
ちくま学芸文庫版『「伝える」ことと「伝わる」こと』……「私の日本語作法」「私のユング風景」
ちくま学芸文庫版『「思春期を考える」ことについて』……「病跡学の可能性」
みすず書房版『中井久夫集 1』……「現代社会に生きること」「現代における生きがい」「世に棲む患者」「働く患者」「病跡学の可能性」
みすず書房版『中井久夫集 2』……「私の日本語作法」
みすず書房版『中井久夫集 4』……「ワープロ考」
みすず書房版『中井久夫集 5』……「執筆過程の生理学」
みすず書房版『中井久夫集 8』……「統合失調症とトラウマ」
みすず書房版『中井久夫集 10』……「河合隼雄先生の対談集に寄せて」「血液型性格学を問われて性格というものを考える」
『徴候・記憶・外傷』……「統合失調症とトラウマ」
『関与と観察』……「現代社会に生きること」「現代における生きがい」
『臨床瑣談 続』 …… 「血液型性格学を問われて性格というものを考える」
『精神科治療の覚書』……「治療の滑り出しと治療的合意」「発病の論理と寛解の論理」
『災害がほんとうに襲った時——阪神淡路大震災50日間の記録』
『1995年1月・神戸——「阪神大震災」下の精神科医たち』
『こんなとき私はどうしてきたか』……P.95〜P.96のベッドの話
河合隼雄の対談集『心理療法対話』……中井久夫による解説「河合隼雄先生の対談集に寄せて」が収録
R・R・ペアマン&S・C・アルブリットン『MBTIへのいざない』
原田憲一『精神症状の把握と理解』
デイヴィッド・ホロビン『天才と分裂病の進化論』
牛島定信『パーソナリティ障害とは何か』……演技性パーソナリティ障害の章が重要
岡田尊司『パーソナリティ障害——いかに接し、どう克服するか』……スキゾタイパル(失調型パーソナリティ障害)の章が重要
小平邦彦『怠け数学者の記』……「プリンストンの思い出」「このままでは日本は危ない」が収録
トマス・G・ウェスト『天才たちは学校がきらいだった』……P.160〜P.161のチャーチルの警告
頭木弘樹『カフカはなぜ自殺しなかったのか? 弱いからこそわかること』
新潮社版『決定版 カフカ全集 10 フェリーツェへの手紙 I』
新潮社版『決定版 カフカ全集 11 フェリーツェへの手紙 II』
G・V・ルグロ『ファーブルの生涯』……「セリニアンの集い」の章
ヴァージニア・ウルフ『自分ひとりの部屋』
ジュリア・キャメロン『新版 ずっとやりたかったことを、やりなさい。』
スーザン・ケイン『内向型人間のすごい力 静かな人が世界を変える』……第3章「共同作業が創造性を殺すとき」が重要
スーザン・ケイン『内向型人間が無理せず幸せになる唯一の方法』(ダイジェスト版)
ターリ・シャーロット『事実はなぜ人の意見を変えられないのか』……第8章「「みんなの意見」は本当にすごい?」が重要
ジェイソン・ハンソン『超一流の諜報員が教える CIA式 極秘心理術』
グレゴリー・チャイティン『メタマス!』
William J. Brown ほか『アンチパターン——ソフトウェア危篤患者の救出』
阿部朋美&伊藤和行『ギフテッドの光と影——知能が高すぎて生きづらい人たち』
サトシ・カナザワ『知能のパラドックス』
ダグラス・ホフスタッター『ゲーデル、エッシャー、バッハ』
太宰治『人間失格』
神尾葉子『花より男子』(少女漫画)
バルザック『絶対の探究』
映画『π』(ダーレン・アロノフスキー監督、1998年公開)
『うたの☆プリンスさまっ♪』(女性向け恋愛アドベンチャーゲーム)
なお、本文にも書いたが、ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.22には誤記がある。みすず書房版『中井久夫集 1』P.211での記述が正しい。
今回の記事の本文では触れなかったが、『徴候・記憶・外傷』に収録されている「医学・精神医学・精神療法は科学か」は重要。精神疾患や性格分類についての議論に関して、「科学的でない」という理由で雑に退けようとする人もいるため。「科学の外見をよそおわせる」ことによってかえって「疑似科学化」するのは、ソフトウェア開発という営みと類似している気がしている。
Wikipediaの項目
外集団同質性バイアス - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E9%9B%86%E5%9B%A3%E5%90%8C%E8%B3%AA%E6%80%A7%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9単純接触効果 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E7%B4%94%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E5%8A%B9%E6%9E%9Cアビリーンのパラドックス - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9正常性バイアス - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E6%80%A7%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9シェイクスピア別人説 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%94%E3%82%A2%E5%88%A5%E4%BA%BA%E8%AA%AC
Web上の記事など
Talk:Albert Einstein - Wikiquote
https://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Albert_Einstein連載「中井久夫さんが教えてくれたこと」⑴⑵|神戸新聞公式「うっとこ兵庫」(2024-01-09)
https://note.com/kobedx/n/n75effd492eeb「絶望の世界」アーカイブ
https://web.archive.org/web/19991128125152/http://www.angel.ne.jp/~shun/aaaaaa.html「ReadMe!」が全サービス終了へ - ITmedia NEWS(2008-02-08)
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/0802/08/news052.html「ReadMe!JAPAN」のアーカイブ
https://web.archive.org/web/19990000000000*/http://readmej.com/メタバースで五感フル活用!VR感覚・ファントムセンスとは!? - YouTube(2022-07-08)
https://www.youtube.com/watch?v=yE2muevVXsw
(「ツタエルちゃんねる / tsuta-l channel 大蔦エル」、9分20秒ほど)#つぶやきProcessing の例
https://x.com/nagaT9090/status/1844564622852202501
https://x.com/KomaTebe/status/1871902272269242584
https://x.com/yuruyurau/status/1890751857116532978図書カード:東京だより
https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/card1109.html小説家の田辺青蛙の「読まないよ」のポスト
https://x.com/Seia_Tanabe/status/1487259100929212416
https://x.com/Seia_Tanabe/status/1487261499764912130
https://x.com/Seia_Tanabe/status/1487961085319999491湘南乃風 「純恋歌」MUSIC VIDEO(オリジナルver.) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=YQSS7SgGia8
(「湘南乃風」チャンネル)那覇技術同人誌読書会に参加してきた|いぜ a.k.a taktic(2019-10-18)
https://note.com/taktic/n/n6dbe7c78204d那覇見聞録「技術同人誌読書会を通して見た那覇」|底辺亭底辺(2019-10-21)
https://note.com/teihentei/n/na979f485b42bあらゆることにぼくは失敗する――今こそ読みたいカフカの日記と手紙 | 単行本になりました | web春秋 はるとあき(2016-12-31)
https://haruaki.shunjusha.co.jp/posts/749漫画家のざくざくろによる感覚過敏の漫画
https://x.com/timtimtooo/status/1410569063038812160「そしゃく音」や「時計の針の音」などが不快に感じる人は「ミソフォニア」かもしれない - GIGAZINE(2025-04-01)
https://gigazine.net/news/20250401-eating-sound-misophonia/音で人生が壊れる世界、自覚無く地雷源で生きているあなたへ|だっく@ニュース"物語"ジャンキー(2025-04-20)
https://note.com/dac/n/n31c32b5fe5abクリエイティブな才能は注意散漫な人の方が発揮できる - GIGAZINE(2015-12-14)
https://gigazine.net/news/20151214-creative-genius-distraction/天才と変人の関係 脳の「フィルター装置」が独創性を左右? - 日本経済新聞(2013-04-25)
https://www.nikkei.com/article/DGXBZO54282560T20C13A4000000/天才と変人 解き放たれた知性 | 日経サイエンス
https://www.nikkei-science.com/201306_032.htmlN型の性質が強すぎる筆者の人生失敗談|イブリース(2024-01-03)
https://note.com/luciferlove/n/nd01b17ec4f0cmbtiのSとNの見分け方|紺(2024-01-23)
https://note.com/bright_dunlin261/n/n7edfe01119c1【N型の会話の特長?】続かない会話、弾む会話|はこねのもり(2024-09-03)
https://note.com/yumotogawara/n/n87e67817b3dc36歳「ギフテッド」男性が社会で味わった絶望 「頭が悪い」「使えない」と上司や医師が人格否定 | 概要 | AERA DIGITAL(アエラデジタル)(2023-06-18)
https://dot.asahi.com/articles/-/195008人生に失望した36歳「ギフテッド」男性はなぜ転職先で成果を出せたのか 「社会性が低い」の誤解 | 概要 | AERA DIGITAL(アエラデジタル)(2023-06-18)
https://dot.asahi.com/articles/-/195009『知的労働をしている人が働き方改革で一番困るのが「効率的に働け」』……アホな上司にかかると、ひたすら手を動かしていないと効率的とは認められない。 - posfie
https://posfie.com/@Count_Down_000/p/vLFF8EH設計解がないと思われた製品にエースエンジニアが投入され、翌日あっさり大枠をまとめて来た→その解決方法がカッコよすぎた - Togetter [トゥギャッター](2022-08-06)
https://togetter.com/li/1926743『不安耐性、判断を保留する能力、抽象のままにして具象に落とさない能力』…これが無いと、いきなり問題を解決しようとするので、問題そのものを議論できなくなる - posfie
https://posfie.com/@Count_Down_000/p/LwYsv12そわそわしがちなADHDの人は「探検家」のような遺伝的特性がある可能性 - GIGAZINE(2024-02-22)
https://gigazine.net/news/20240222-adhd-genetic-traits-explorers/
わたくしの書いたものなど
ここからは、わたくしの書いたもの。
以下は、「ジェネシスブロック記事」と読んでいるもの。
2023年7月のプロフィールページ刷新、そして各種Webサービスに思うこと|cleemy desu wayo(2023-08-31)
https://note.com/cleemy/n/n96474b06fa3b
以下は、今回の記事を書いている最中に寄り道して書いた2つの記事。
xSxJ階段とxNxPジャンプについてのメモ|cleemy desu wayo(2025-05-04)
https://note.com/cleemy/n/n6451e95a3ca5LINEやインスタにアカウントはない|cleemy desu wayo(2025-05-14)
https://note.com/cleemy/n/ne2efcb31a2dd
それ以外。
cleemy desu wayoへのご質問 (@cleemy_desu_wayo) | お題箱
https://odaibako.net/u/cleemy_desu_wayo2005年から「cleemy」を名乗っていることが確認できるアーカイブ
https://web.archive.org/web/20051030030928/http://d.hatena.ne.jp/cleemy/aboutダグラス・ジェネルベフトと7人の暗殺者(小説)
https://ncode.syosetu.com/n9355gw/cleemy desu wayo / outvoke · GitLab(ライブラリ兼フレームワーク)
https://gitlab.com/cleemy-desu-wayo/outvoke分類しない暴力【A面】|cleemy desu wayo|note
https://note.com/cleemy/m/m3c861812c2a0分類しない暴力【B面】|cleemy desu wayo|note
https://note.com/cleemy/m/m438414762279cdwact(cleemy desu wayo活動報告)|cleemy desu wayo|note
https://note.com/cleemy/m/mb0f02523402c作業所はあるのになぜ思考所はないのか・前編|cleemy desu wayo(2021-12-17)
https://note.com/cleemy/n/n0084ba60c4cc[cdwact-2024-03] 2024年3月活動報告|cleemy desu wayo(2024-05-19)
https://note.com/cleemy/n/nf5e37a5ff861[cdwact-2024-05] 2024年5月活動報告|cleemy desu wayo(2025-02-28)
https://note.com/cleemy/n/n385ff88b787eずっと変わらないでいてほしい | ALIS(2018-10-25)
https://alis.to/cleemy/articles/3Lq8bo95650Bわたくしに関連して「おかしい」「困っている」があれば警察庁のフォームへ|cleemy desu wayo(2025-01-13)
https://note.com/cleemy/n/n2c844e1f6d0d