AIを根拠とした新聞写真懐疑論の真偽
先日、朝日新聞フォトアーカイブのTwitterアカウントの写真ツイートが話題になった。国鉄房総東線(現JR外房線)列車内の床に散乱する大量のゴミという写真だ(以下ツイート)。
この写真は朝日新聞の5月2日朝刊の『あふれるごみ ポイ捨て、今は昔』という昔のゴミ事情を伝える写真記事で掲載されたものだ。
昭和中期の日本のゴミマナーが壊滅的だった事はよく知られているが、この写真に明後日の方向から懐疑論をぶつツイートが、これを書いている5月18日13時現在で845RT、37.5万件閲覧されている。その根拠はChatGPT、つまりAIだ。
この画像をChatGPTで調べたら、ネット上に出現したのは2025年5月が初めてでした。それを不自然ではないかと尋ねたら以下の回答でした。 pic.twitter.com/dY7hpAh1FU
— Atsuko Yamamoto🇯🇵 (@piyococcochan2) May 17, 2025
このツイートの主張ではChatGPTは2025年にネット上に初出 → 怪しいと言いたげで、捏造とするリプライが多数ぶら下がっている。しかし、これは現在のAIが抱える問題を理解していない。ChatGPTをはじめとしたAIは、Web上の情報をクローラが収集したデータセットに頼っている。クローラが収集できるのは無料でアクセス可能な範囲ばかりで、IDとパスワードの入力を求められるWeb(ディープWeb)は収集されないのが一般的だ。
IDとパスワード入力必須の朝日新聞フォトアーカイブのサイトでは、この写真が2枚登録されている。写真IDはP121207006857。(以下写真詳細)
朝日新聞フォトアーカイブは写真のアップロード日を表示しないサイトだが、写真IDでアップされたおおよその日付がわかる。恐らくP121207006857は2012年にアップされたとみられるが、ディープウェブ上でクローラに引っかからなかったために見過ごされていたと考えられる。
報道社の写真アーカイブを利用したことがあれば分かるのだが、報道社が有する写真資産は膨大なもので、デジタル化が済んでいないフィルムも多く存在する。私もある事件の写真がアーカイブの検索で出てこなかったので、フィルムからデジタル化してもらったことがある(朝日新聞ではない)。
これだけで、AIにネット上での初出を聞いても確実でないことが分かるが、件のアカウントはAIを根拠にさらに懐疑論を展開している。
このゴシック太文字の202..についてもしらべました。このフォントは1960年代の新聞印刷技術では不可能ということでした。 pic.twitter.com/NcZYLGPW8O
— Atsuko Yamamoto🇯🇵 (@piyococcochan2) May 17, 2025
列車の床に落ちている新聞にゴシック体を使われていることを根拠に、当時の新聞印刷技術では不可能だとしている。AIで調べたことで「裏を取った」らしい。
この202..は当時の印刷技術ではあり得ないです。デジタル時代のものです。AIで裏も取りました。 pic.twitter.com/8u9ZWt8Oxd
— Atsuko Yamamoto🇯🇵 (@piyococcochan2) May 17, 2025
しかも、新聞にある「202」と見える文字だけで、2020年以降の新聞広告としている。ようは捏造と言いたいようだ。
もう、いちいち突っ込むのも面倒くさくなったので、証拠だけ上げることにする。この新聞にある「202」の文字は、1968年に三井信託銀行がさかんに出稿していた貸付信託の広告だろう。(以下画像)
件の写真を拡大すると、「202」の上に「三井」「貸付」の文字が確認できることからも、この広告とみて間違いないだろう。そもそも、新聞本文で使われる文字を印刷する活字にゴシックはなかったとしても、広告は本文でないので活字は使わないだろう。本文と広告を混同した上の誤判断だろう。AIに聞いたところで、質問者の前提知識に誤りがあったらどうしようもないのだ。
新聞広告が出たところで、ここまで読んでいる人は概ね察していると思うが、件の写真の新聞記事も確認してある。1968年5月6日の朝日新聞朝刊「月曜グラフ」に掲載されていた。(下画像)
件の写真は1968年4月28日、ゴールデンウィークで混雑する房総東線の社内に散乱したゴミを撮影したものだった。記事はこう伝えている。
評判悪い東京の客
「東京からの急行には手を焼くョ」と、掃除係のおばさんがぼやく。一列車で、軽くリンゴ箱十ぱい分の紙くずの山。(4月28日、国鉄房総東線勝浦ー安房鴨川駅間で)
かつての日本軍の戦争犯罪を否定する向きは昔からあったが、戦後のマナーについての報道にまで懐疑論が飛び出るまでになったのが本件であるが、根拠にAIを持ってきて説得力を装うのが新しいところか。
しかし結局のところ、AIの限界を理解せず、質問者の前提知識も怪しいとなると、AIが宝の持ち腐れになることを示した例だろう。
※本記事は無料で全て閲覧可能ですが、気に入ったなら投げ銭的に100円で購入頂けると幸いです。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?


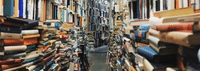

購入者のコメント