オタクは存在するか? フィクトセクシュアル当事者による「内面化されたフィクトフォビア」論考。
「フィクトセクシュアル」とは
「フィクトセクシュアル」をご存知でしょうか?
廖希文と松浦優の共著による「増補フィクトセクシュア宣言」によると、このような内実の性愛形態を指す概念です。
フィクトセクシュアルとは、架空の対象へ惹かれる人々の性的アイデンティティです。「架空の対象への性的惹かれを経験するが、生身の人間に対して同様の感覚を持つことはほとんどないこと」、あるいはより広く「架空のキャラクターに対して性的/恋愛的/結婚への魅力や欲望を感じること」を指して使われます。
https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/7236466/13_p001.pdf
つまり、美少女や美青年のフィクション・キャラクターを欲望するいわゆる「(萌え)オタク」を含む幅広い層の性愛がそこに含まれることになります。
この概念の面白さは、いままで当事者である男女のオタクにおいてすら異性愛(ヘテロセクシュアル)のサブカテゴリー的なバリエーションのひとつと見られていたセクシュアリティを、純粋な意味での異性愛とは別個の独立した性愛として捉え直すことができるところにあります。
つまり、フィクトセクシュアル概念を採用するなら、オタクがある「萌え美少女キャラクター」を性愛の対象とすることは、決して生身の女性への満たされない性愛欲求の代わりなどではなく、「それそのもの」がひとつの特異なセクシュアリティの形なのだということになるのです。
ここにはまさに発想のコペルニクス的大転換がある。
この概念をもちいる場合、オタクは生身の女性との性愛に挫折し屈折した異性愛者ではなく、ある種のクィアな性愛であるフィクトセクシュアルの当事者ということになるのですから、「オタク」という定義そのものを根底から考え直す必要が出てくる。大変な話。
もっとも、ひとりの萌えオタク、すなわちフィクトセクシュアル当事者としての実感としていうと、「架空の対象への性的惹かれを経験」しながらも、「生身の人間に対して同様の感覚を持つことはほとんどない」人は、話をいわゆる萌えオタクに限定するなら、たしかにいないわけではないにしても、決して多数派とはいえないと思います。
二次元おっぱいこそ至高で三次元はただの肉という人より、二次元おっぱいも好きだけれど三次元おっぱいも大好きだよ、という人のほうが割合的に多いでしょう。
なので、この記事ではフィクトセクシュアルという概念を後者の「より広い」定義、つまり「架空のキャラクターに対して性的/恋愛的/結婚への魅力や欲望を感じること」でもちいます。ご了承ください。
以下の文章では上記の「宣言」の著者であり、日本におけるフィクトセクシュアル研究の第一人者である松浦優の論文を引用しつつ、フィクトセクシュアル概念と、そこから派生する「フィクトフォビア」について考えていきたいと思います。
フィクトセクシュアル当事者である「萌えオタク」は長年にわたって攻撃的かつ差別的な言説にさらされてきました。もちろん、ぼくもいろいろひどい目に遭った。
「精神障害などの当事者が、自身の困り事を研究対象として、自分自身や仲間たちと協力して解決策を見つけ出す自助活動」を「当事者研究」と呼びますが、この記事はいわばフィクトセクシュアル当事者によるフィクトセクシュアル差別の当事者研究として理解してください。
フィクトセクシュアル差別は実在するのか?
さて、フィクトセクシュアル差別といいますが、そのようなものはほんとうにあるのか、考えてみましょう。
まず、現実的な問題として、フィクトセクシュアルの当事者が、フィクトセクシュアルであることによって不当な態度を取られることは往々にしてあると考えます。
「萌えオタク」であることを理由に攻撃されたりハラスメントを受けたりすることは、かなり少なくなってはいるにせよ、まだまだあるでしょう。
そして、それ以上に重要なのは、インターネット上のソーシャルメディア空間において繰り広げられている「萌えオタク」とそのカルチャーへの言論攻撃です。
いくらでも実例を引けるのでここであえて引用することはしませんが、この記事を読まれている皆さんもオタク的な文化をターゲットとした敵対的な言説をご存知でしょう。
それらはしばしばフェミニズムやポリティカル・コレクトネスの理論でアカデミックに粉飾されているものの、ひと皮剝いてしまえばつまりは「萌え絵」に対する根深い嫌悪に由来すると考えることができます。
オタクの側はそれを「お気持ち」として否定してきたわけですが、そもそもこういった批判者が常識的に考えればまったく無害で穏当と見えるイラストや動画を執拗に攻撃してやまないのはなぜなのでしょうか。
マンガ批評家の伊藤剛はこのようなある種、非合理的ともいえる反応を指して「萌えフォビア」と呼びました。
ぼくがこのような疑問を持つのは、「ヌード写真など実写のポルノグラフィは(条件つきでも)OK、売買春も同様。しかし、キャラを用いた性的な表現は気持ち悪いから絶対に認められない」という強い感情に、何度となく出会っているからだ。 ぼくはこの手の感情を「萌えフォビア」と呼んでいる。
これは当時としては先駆的かつ有意味な定義だったと思います。しかし、「フィクトセクシュアル」という概念が理論的に前景化したいまとなっては、むしろ「フィクトフォビア(「萌え」を含むフィクトセクシュアル全般への恐怖症)」と呼ぶべきなのではないかと考えます。
この「フィクトフォビア」こそがいわゆる「萌え絵」に対する嫌悪と恐怖の根幹にあるものであり、いくつもの「理由なき表現規制案」を生み出してきたものなのではないかとぼくは思うのです。
フィクトフォビアはフェミニズムのロジックで粉飾されるため、表現規制はフェミニズムの問題とされることが多いでしょうが、じっさいにはもっと根源的かつ情緒的な動機で駆動されているわけです。
それに対して表現の自由を掲げ抵抗していくことも必要なことではあるでしょうが、どうしても対症療法的な限界が残る。
ここではより深いところを探ってみたいのです。
そう、そのフィクトフォビアにはどのような理由があるのか。つまり、なぜ彼/彼女たちは「萌え絵」を「気持ち悪い」と感じるのか。
松浦はそれを「対人性愛中心主義」というべつの概念で捉えています。
対人性愛中心主義とは、成人した異性同士の性愛こそが唯一の正常なセクシュアリティの形であるとするいわゆる「異性愛規範(ヘテロノーマティヴィティ)」のひとつのバリエーションであるといえます。
それは人間に向かう性愛のみが唯一の自然な性愛であると考え、それ以外の性愛の形を「周縁化」して異常なものとみなすのです。
この対人性愛中心主義はあるいは奇矯な概念であるように思えるかもしれません。異性愛であれ同性愛であれ性愛の対象が生身の人間であることはあたりまえの常識ではないか、と。
ですが、まさにそう感じられるのはこの社会において対人性愛中心主義が深く深く浸透しているからに他なりません。
上記の記事において伊藤が指摘しているように、性愛の対象が生きた人間であることは当然のこと、生身の人間を対象にしない性愛は何らかの歪んだ認識が生み出した異常なものという観念は、他ならないフィクトセクシュアル当事者としてのオタク自身にすら信仰されてしまっています。
したがってオタク自身が自分の性愛の形に嫌悪を示すことはまったくめずらしいことではないのです。
この種の自己嫌悪的な心理を、同性愛者による同性愛嫌悪が「内面化されたホモフォビア」と呼ばれてきた歴史に倣って、「内面化されたフィクトフォビア」と呼びましょう。
「フィクトフォーブ(フィクトセクシュアル嫌悪者)」は非フィクトセクシュアル当事者に限らない。これは意外なようですが重要な論点です。
オタク論においてはオタクでありながらオタク文化を非常に口汚く攻撃する人物が散見されますが、それはこのフォビアが原因と考えられます。
「腐女子」によるフィクトフォビア
殊にこの「内面化されたフィクトフォビア」が最も顕著に見られるのが一部のBL文化愛好家、いわゆる腐女子たちです。
彼女たちは自分たちの性愛的な作品を恥ずべきものと考え、「徹底的に隠す」ことを倫理的課題とみなします。
そのわりにじっさいにやることといえばただアカウントにカギをかけるという程度だったりするのがおかしいといえばおかしい。
しかし、この一見すると矛盾とも感じられる態度は彼女たちが自分たちのセクシュアリティをカミングアウトすることなく「クローゼット」であることを良しとするタイプの性的少数者、「クローゼット・フィクトフォーブ(自分たちの文化の隠蔽を良しとするフィクトセクシュアル)」であると考えるとわかりやすくなります。
その「内面化」に背景にあるものは、第一には社会的な「スティグマ」の問題と見ることができるでしょう。
スティグマとは、日本語では「烙印」や「不名誉」と訳され、特定の属性を持つ人々や集団に対して、社会的に否定的な意味づけがなされ、その結果として差別や偏見を経験することです。
異性愛規範にもとづいて偏狭な趣味とみなされる腐女子に対するスティグマは強く、それを避けるために「隠れる」必要があると考えているといういうことがひとつにはいえるでしょう。
ですが、それだけではない。もうひとつ、BL文化は「倫理的に」許されざる、少なくとも大きな問題を抱えた文化である認識が大きいのだと思います。
そこでは自分たちが単なる対人性愛者ではなく、「クィア」なセクシュアリティの当事者であるという認識が欠落しているため、自分たちは男性同性愛者のセクシュアリティを侵害しているという認識に至っている。
それは倫理的、常識的な「悪」であり、本来なら避けなければならない。しかし、それはできない。
だから、せめて「まともな」人間に迷惑をかけないよう隠れなければならない――これが腐女子(や夢女子)のいわゆる「学級会」的な同類糾弾のバックボーンとなっていることなのです。
このように整理すれば腐女子が自分たちのカルチャーを「気持ち悪い」ものとみなし、「腐っている」と自嘲的に語る行為の裏にあるものが、フィクトセクシュアル当事者による「クローゼット意識」の問題と整理することが可能になります。
もっとも、「クィア」がまさにそうであるように「腐女子」も単なる自嘲を超えて当事者のプライドを意味するようになる可能性もあることはあるでしょう。
いずれにしろ、すべては「内面化されたスティグマ」、「内面化されたフィクトフォビア」が根っこにあって成立しているというのがぼくの見方です。
男性オタクのなかにも「萌え絵」に対する違和や嫌悪を主張する人はたくさんいます。
じつはそれそのものは否定しようがありません。それが「個人的な違和や嫌悪」の次元に立っているかぎり、「そうですか、あなたはそう思うのですね」という話にしかならないのですから。
しょせん「気持ち悪さ」とは、ごく個人的かつ主観的な思い込みに他なりません。たとえばぼくは納豆がきらいなので、納豆がねばつくところを見るとひどく気持ち悪いと感じますが、同じものを「美味しそう」と感じる人もたくさんいるわけです。
だから、ぼくは「萌え絵」の表象が「気持ち悪い」ことを必ずしも否定しません。しかし、その「気持ち悪さ」を当然の前提とみなし、さらには「気持ち悪いと感じないことはおかしい」などといいだすことはやはりおかしいと感じる。
そこに「人間にとって成人した異性に対する欲望のみが唯一の正常な性愛である」とする異性愛規範と同じく「生身の人間に対する欲望のみが唯一の自然な性愛である」とする対人性愛中心主義の介在を見るしかありません。
フィクトフォビアの学問的粉飾
興味深いのは、このフィクトフォビアがさまざまな倫理的/学問的粉飾をともなって主張されることです。
おそらくだれもが「自分が気持ち悪いと感じるから」その表現を抹殺せよ、というのでは説得力が足りないと感じるのでしょう。
否、それどころか自分の主張の根幹に情緒的反発があることすら忘却されている場合も少なくないと考えられます。
これはオタクでもそうです。一部のオタクはしばしば性愛の問題を些事とみなし、揶揄し、茶化し、より卑小な問題にしか過ぎないと主張します。たかがエロゲーやエロマンガじゃないか、と。
それに対し表現擁護側のオタクは「表現規制はエロから始まるんだ」などと反論するわけですが、その説の成否はともかく、正面から「そのエロゲーやエロマンガは自分の性愛生活において大切なものなのだ」と主張することができないのは、やはり自分がひとつの独立したセクシュアリティの当事者であるという認識が欠けているからだとも思えます。
そしてまた、性愛の問題をつまらないこと、くだらないことと見るシニカルな冷笑主義は、しかし、既存の性愛形態を自明で永続的なものと捉えているという意味で問題含みなものでもあります。
とはいえ、「萌え絵」が気持ち悪いという意見もわからないわけではありません。
それは人体を極端にデフォルメしたデザインであり、さらには「大人なのか子供なのか良くわからない」。そしてそれほど異形であるにもかかわらず性的な雰囲気をただよわせている。なるほど、「気持ち悪い」。
しかし、萌え絵はなぜそのように特徴を誇張されて描かれるのでしょうか?
これはいままでしばしば「オタクは精神的に未熟で大人の女性に向き合うことができないため、幼稚な子供を欲望しているからだ」などと説明されてきました。
よくよく考えてみるとわりとめちゃくちゃなロジックであるような気もしますが、オタク自身も自身のセクシュアリティを具体的に説明し的確に反論するための語彙を欠いていたため、緻密に反論することはむずかしかったように思います。
オタクとは「自身が性的マジョリティであると思い込んでいる性的マイノリティ」だったのです。
「正欲」にもとづく批判
ちょっと話が逸れますが、この社会において全面的な承認を得られない性的マイノリティの苦しさとはいかなるものなのか、そのことを象徴的に描写した作品として、朝井リョウ原作の映画『正欲』があります。
この映画は「水フェチ(対水性愛)」というセクシュアリティを抱えた人物たちの孤独と連帯を描いているのですが、かれらはそのセクシュアリティゆえにクローゼットであることを余儀なくされ、ほとんど仲間を見つけることもできず苦悩します。
そしてそこで描かれるのもまた異性愛規範という名の「正欲」にもとづく非難であり、差別であり、侮辱であり、攻撃です。
同様にフィクトセクシュアル当事者もまた異性愛者や同性愛者のフェミニストなどによってそのセクシュアリティを「抹消」され、「現実には未熟なヘテロセクシュアル当事者であるに過ぎない」と見做されます。
ここにはある種の虐殺の論理があります。
つまり、現実にイラストやフィギュアに欲望を感じている人間はそこにいるにもかかわらず、「それはほんものの欲望ではない」、「おまえはほんとうは異性愛の欲望を抱いているはずだ」と決めつけられ存在しているそのものを認めてもらえない。
そして、その意味で「そもそもフィクトセクシュアルなど存在しない」という結論が導かれます。
つまり、じっさいに存在するのは「偽装したヘテロセクシュアル」であるに過ぎず、その性的欲望はほんとうは三次元現実世界に存在する現実の女性に向けられているにもかかわらず、その欲望の成就が困難であることから代替的に二次元キャラクターを代替的存在としてまなざしているに過ぎない、と。
松浦はこのような「対人性愛中心主義」をくりかえし批判します。そして、ぼくもやはり異常な言説だと感じます。
オタクが萌え美少女や美青年を愛するのは、べつだん、彼らが異性愛において挫折したからではない。どんなに否認され抹消されようとも、紛れもなく「フィクトセクシュアルは存在する」。それが事実だと信じます。
ただ、一方でそのようなフィクトセクシュアルを「絵」に欲望する対物性愛の一種なのだ、と理解されるとそれはそれで誤解があるとも感じる。
フィクトセクシュアルの対象は一見するとたしかにある「絵」や「抱き枕」や「フィギュア」といった二次元的/三次元的物体であるように見えます。
しかし、自分をふり返って考えてみれば、フィクトセクシュアルの真の対象とは、じつはその個々の物体を通して当事者の脳裡にイメージされている「フィクションのキャラクター」であるはずです。
フィクトセクシュアルの欲望は、何らかのイラストやモノからダイレクトに喚起されているというよりは、それらを「媒介」として脳裡に思い描いたセックスから生み出されているわけです。
そして、その際、必ずしも同性のキャラクターに自己投影しているわけですらありません。
多くのオタクが(ていうかぼくが)語るところによると、フィクトセクシュアル当事者は自慰するとき、男性と女性に同時に(あるいは交互に)感情移入している自分を見いだします。一方で男性の視点を体験し、他方で女性の快楽を味わうわけです。
それはまさに松浦や東浩紀が語っているようにジャック・デリダのいう「誤配」の結果なのであり、単純に異性愛をなぞっているわけではありません。
虚構性愛を異性愛の単純な投影と見るべきではない。
とはいえ、エロゲーやエロマンガ、特に「鬼畜系」と呼ばれるような凄惨に女性を強姦する類のポルノコンテンツは(最近だいぶ減ったけれど)、最も素朴に見るならたしかに女性差別的に見える、というか女性差別的にしか見えないでしょう。
何をどう見ても女性や子供に人格的攻撃を加えながらレイプしているわけですからね。
その意味で、フィクトフォビア当事者の「萌え絵」に対する素朴な嫌悪感もまったく理解できないわけではありません。
しかし、じっさいにはそれを現実的なレイプ願望のフィクションへの投影と見るべきではありません。
それはどこまでいってもフィクトセクシュアル当事者による現実から遊離したエロティックな想像力の戯れであるに過ぎないのであり、必ずしも女性に対する差別的/攻撃的心理を意味しているとは限らないのです。
と、こう書いても納得してもらいづらいかもしれません。
ですが、膨大な統計情報は、現実にそのようなポルノを消費する人間が異性に対し差別的であったり加害的であったりする割合が高いというファクトはない、と示唆しています。
それは何を意味しているのか。従来、オタクたちは「二次元と三次元を区別することができる」ことを指しているのだ、と主張してきました。
オタクは虚構と現実を混同することなく、理性的に判断することができる人種なのだ、と。
ですが、フィクトセクシュアルの文脈で考えるなら、ぼくたちはそもそも三次元的な「人間」と二次元的な「人間であるように見えるキャラクター」は「存在論的に異なる」ものであるというあまりにあたりまえの事実を想い返すべきです。
「萌え絵」で描かれる二次元のキャラクターはいかなる意味でも生身の人間ではない。そして、生身の人間にダイレクトに繋がる回路でもない。
対人性愛中心主義をこじらせると、このあまりにも自明なことが見えなくなる。
とはいえ、オタクが独自のセクシュアリティを持っていることは少しでもこのカルチャーをかじった人間ならすぐに理解するところでしょう。
そのとき、オタクの性愛の問題を矮小化するために利用されるのが「性的嗜好(セクシュアル・プリファレンス)」と「性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)」を区別する考えかたです。
この言葉はしばしば後者を重視し前者を軽視するために使われます。
先天的であり変えることができない「性的指向」は容認し保護しなければならないが、個人の趣味である「性的嗜好」はその限りではない、というふうに。
そして、オタクの二次元性愛は単なる「性的嗜好」に過ぎないから「性的指向」である同性愛のように守る必要はないのだ、と語られるのです。
そして、多くのリベラルを標榜する性愛言説において、オタクたちのセクシュアリティは異性愛の一種「でなければならない」。
なぜなら、オタクをフィクトセクシュアルの当事者として理解し、その性的しこうをクィアでマイノリティな性愛のひとつとして認めてしまったなら、リベラリズムの理念上、その存在を擁護しなければならなくなるからです。
そもそも、女性の権利を過激に主張するラディカル・フェミニストはともかく、個人の最大の自由を認める立ち場に立つリベラリズムに依拠するリベラル・フェミニストはそうそうかんたんにオタクの自由な表現を攻撃できないはずです。
何といっても自由主義者なのですから、個人がポルノグラフィを発表する権利を否定することはむずかしいはず。
じっさい、たとえばリベラル・フェミニストであるナディーン・ストロッセンはリベラリズムの立場からポルノコンテンツを擁護する著書『ポルノグラフィ防衛論』を物しています。
それでもなおフェミニストたちが懸命にオタク文化を非難する様子を見ていると、彼女たちの心に内面化されたフィクトフォビアとスティグマの根深さを実感し慄然とせざるを得ません。
「詭弁に過ぎない」とする否認。
だから、ここまで縷々、述べてきたようなフィクトセクシュアルのロジックは、多くの「リベラル」や「フェミニスト」から「オタクはしょせんただのありふれた異性愛者である」という真実をごまかすための詭弁とみなされ、否認されることでしょう。
それはまさに『正欲』の作中で水フェチというセクシュアリティが「あるはずがないもの」として否認され、「抹消」されたその光景を思い起こさせます。
それほどまでに「フィクトフォーブ(虚構性愛嫌悪者)」たちの対人性愛中心主義は根深い。
もちろん、萌え絵に対する恐怖や嫌悪、つまりフィクトフォビアを感じることそのものは倫理的な咎ではありません。まったくもって本人の自由です。
ですが、ホモフォビアが同性愛者の問題でも責任でもないのと同様、フィクトフォビアもオタクの問題ではありません。
あきらかにフィクトフォビアはフィクトフォーブ自身が直視し、解決していく種類の問題でしょう。もちろん、そのための協力は惜しまないにしろ。
まだ語りたいことはありますが、この認識を最後として、この記事を終えることとしたいと思います。あとで有料の追加個所を書くかも。
蛇足①
この記事を読まれて少しでも「良いかもね」と思われた方は「スキ」や「フォロー」をお願いします。
蛇足➁
このnoteには過去の有料記事をすべて読める月額1000円の有料プランがあります。初月無料なので、ぜひ試しに入ってみてください。
蛇足③
ただいま、ライターとしてのお仕事を募集ちうです。何かありましたらよろしくお願いします。
でわでわ、よろしく。

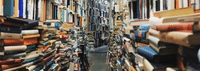


コメント