東京ディズニーシーと植民地主義 ~地理学的に解き明かす~
東京ディズニーシーと植民地主義
2001年9月4日、新たなディズニーパークが開園した。その名も東京ディズニーシー。冒険とイマジネーションをテーマにした、世界でも唯一のディズニーパーク。中心に建つモニュメントとそれを囲うように存在するエリア(テーマポート)など、構造はディズニーランドに基礎を置きつつも、アトラクションやレストラン、ストーリーなど大きな独自性が見られるのが特徴だ。
アラビアンコーストの建築について記述した前回のブログに続き、東京ディズニーシー(以下、TDSと記述)の持つ植民地主義(コロニアリズム)的な側面について記述していこうと考えている。
このアイデアは私が大学院生だった2021年頃からずっと頭にあったが、書く気が起きず放置していた。今回文章化に踏み切ったのは、あるTwitter上での投稿がきっかけだ。
でずにーC、入ったら地中海で少し奥に隣あってニューヨーク、別方向の奥に嘘アラブと嘘ジャングルがあるという構成があまりにもコロニアリズムすぎて笑ってしまうんだけど流石に現地で言わないくらいの社会性はある
— みつだしんや (@gebijk) March 11, 2025
コロニアリズムやオリエンタリズムという言葉がアカデミアのみならず一般にも広がる今、こうした印象をパークに対して持つゲストは少なくないと思われる。投稿者が続くポストに書いているように、パークが植民地主義的な側面を持つことは承知で、それを乗り越えるフェーズに入りつつあるのかもしれない。
だが、地理学を少しかじった私からすると、このパークの持つコロニアリズムは単に「入ったら地中海で、ニューヨーク、嘘アラブ、嘘ジャングルという構成」という言葉では語り切れない不可視の暴力性、そして歴史的な連鎖を感じ取ることができる。ディズニーランドの構造が奥に行くほど「他者」であることはよく言われているが、話はそれだけではないのだ。15世紀以来の植民地支配の歴史は(残念ながら)500年以上の歴史を持ち、様々な要素を抱えているが、TDSにはそうした歴史的要素を意図的なのかそうでないのか、多分に含んでいる。
この論考では、この不可視の暴力性を空間的に、いわば文化地理学的な視点から書いていこうと思う。おそらく文字数がかなり多くなると考えられるため、歴史的な連鎖については次号に引き継ぐ予定だ。
2025年にもなってディズニーパークを題材にした植民地論を書くんですか?という意見があるかもしれない。確かに、国内外含めディズニーランドにまつわる研究は数多く行われており、パーク内で見受けられる植民地主義に基づく表象が指摘されてきた。また、コロニアリズムやジェンダー・多様性に関する研究・理解が進むことによって、パーク内ではそれらを問題として取り上げられるようになり、そうした表象はテーマの変更や置かれたプロップスの撤去によって乗り越えられつつあるように思われる。いわば、ディズニーパークは脱植民地化Décolonisationが進んでいる、ということだ。そして、(賛否両論あるとしても)そうした状況は理解されつつあり、ゲスト側もまたそうした状況を分かっていながら楽しむ、ということがパークを楽しむ前提になっているのかもしれない。
ディズニーランドを植民地主義の権化として語る投稿が流れてきて、なんちゃって社会学徒としては猛烈に現地へ行ってみたくなっている。
— 私 (@choir_watashi) March 13, 2025
だが、ディズニーパークをテーマに文章を書きたいと感じていたのは、まず、やはりパークが現代においても西欧中心主義的な視点、いわば西欧中心主義的歴史観に立ち続けている、からだ。それは、Smithが自身の論文の中で「21世紀に建てられたディズニーパークにおいても植民地主義者の神話や”発見”、探検、文明への発達という西洋的な概念の評価に立っている」と書いていることにも通じる。ディズニーパークは更新され続けているとはいえ、建設時の構造/空間配置を基礎にしている、という点では変わらない。
また、大事なポイントとして、ディズニーパーク自体がゲストに対して大きな影響力を持ち続けている巨大なメディアである、ということも大切だろう。1年ほど前、あるMVの内容が植民地主義的だと炎上する事件があったがメディアというのは人々の意識に大きな影響を与える。メディア(=媒介)としてのパークの役割の大きさは頭に入れておくべきだろう。
今作では、パークという空間、そしてメディアとしての役割に光を当てつつ、東京ディズニーシーのもつ植民地主義とその問題について明らかにする。
文の構成について
進め方についてざっと記述する。
まず、TDS云々を述べる前に「空間」という概念をどのようにとらえるかざっと解説する。空間space自体は非常に抽象的な概念であるため、地理学では学派によってその定義そのものが大きく異なる。そのため、最初は空間をどのように捉えるか(空間の定義づけ)考える。
この文章は論文ではないため、なるべく専門用語を使わないよう意識しているものの、難しいと思った方は読み飛ばして頂いても問題ない。
※若干宣伝になってしまうものの、より学問的な解説を求める地理学への熱意を持つ方は、地理系同人誌『地理交流広場』に同様のテーマをよりアカデミックに書いているのでそちらを参照していただけると幸いである。今のところ、(間に合えば)本文章をより学問的に再構成したものを8月に掲載予定です。
#C105 でたくさんの方にご購入いただいた地理系同人雑誌『地理交流広場』は、同人誌通販サイトBOOTHでも書籍版・データ版を販売中です!
— みんなで地理プラーザ!(地理プラ) (@Geo_plaza) December 30, 2024
【書籍在庫あり】
地理交流広場 第4号
地理交流広場 第8号
地理交流広場 号外 道路元標研究 第1~4号
地理交流広場 小字特集号https://t.co/CBuIQTNHxd
次の節では、「TDSを解体する」という題名のもと、パークの各エリアをざっと説明しながら、問題点を解説していく。なお、各エリアにはBGS(Back Ground Story、エリアの背景の基盤となる物語)が存在しておりそのあたりはある程度幅のある解釈が見られるため、ここはそういう設定ではない!などお気づきの方はお知らせください(懇願)
解釈主義のBGSについて、なるべく出典元を書くようにしています。
最後に、東京ディズニーシーという空間がなぜ問題とされるのか、歴史上のある事例を引用しつつ考えてみたい。
先日(2025年3月22日)には「日立 世界ふしぎ発見!」にて関連付けて特集されていたように、TDSに限らずディズニーパークの構造は19世紀以降度々行われてきた万国博覧会(=万博)と類似が存在しており、相互がどのように影響しあっているかについてはまた歴史的な系譜ということで別稿で展開するつもりである。
TDSの問題性について明らかにする今作では、歴史上のある万博事例を1つ用いて解説する。万博そのものを否定するつもりはないものの、万博には歴史上大きな問題を抱えた回も数多く存在し、TDSがその問題ある万博と同様の空間論理が用いられていることを問いたい。
ディズニーと批判地理学を両方吸収している私にとって万国博覧会というのはパラドクスを感じる。
— やのゆー⛵ (@Yanou_disney) March 22, 2025
Disenylandが万博を1つのモデルに建設され、万博が世界の出会う場として機能した事実がある一方、万博ほど近代の矛盾(植民地主義や身体・空間の管理)をむき出しにした暴力的装置もないからだ・・。 pic.twitter.com/POz96JrBgg
以上がこのブログの論点であり、構成である。
「空間」からTDSを考える
この文章の根底にある考え方、それは「空間」である。つまり、パーク内で見られる様々な表象をメインのターゲットにするのではなく、パークという「空間」そのものを考察対象にしようと考えている。具体例を上げると、「カリブの海賊の人身売買のシーンが問題がある」や「スプラッシュ・マウンテンは奴隷制の過去を美化している」といった個々の表象を考えるではなく、パークの構造自体を考えよう、ということだ。空間を考えるから地理学だ、というのは短絡的かもしれないが。
結論から言ってしまおう。
①「空間」とは設計者の意図や政治思想、イデオロギーが明確に反映され、生産されるものである
②こうして生産されたTDS自体もまた、イデオロギーを持つ政治的構築物である
③(構築された)空間を経験するという行為自体にも強烈な植民地主義的構造が存在する→空間の経験をゲストはどの立場(ポジショナリティ)で行うのか?という認識
地理学は「空間」を対象として研究・考察する学問であるが、学史上においても「空間」という抽象的な概念をどう定義するかについては意見が分かれてきた。
この論考は主にディズニー好きもしくは関心がある人向けに書かれているため、細かいことは省略する(関心がある方は、『地理交流広場』を参照いただきたい)が、この「空間」というものをどうとらえるか、これを理解することが重要なのだ。
私はまず、『空間』を所与のもの(常に存在するもの)として捉えるのではなく、構築されたもの、と捉える。そして、その構築を行う主体というのはイデオロギーであり、またそれを持ち開発を行う者になる。この概念は公共空間における都市(再)開発をマルクス主義の文脈で思考する、という視点で深化されたこともあり、理論上は国家を始めとする行政や都市開発業者が当てはまるが、TDSを考える上ではオリエンタルランドや米ディズニー社と考えてよい。もしくは、パークが建設された1950年代、またTDSに引き継がれたという意味では1980年代~2000年代にかけ社会的に一定の同意された考え方、でも良いかもしれない。
如何なる空間も、政治的・イデオロギー的であることを逃れられない。ウォルトが映像や脚本制作のスキルを3次元に展開したものがディズニーランドの原型であること、「キャスト/ゲスト」の呼称、数々の映画追体験アトラクションの存在からわかるように、パークにおいて重視されるのはストーリーである。パークにおけるストーリー性の重視が空間に展開され、また秩序を重視する(服装やマナーが重視され、逸脱を起こすとネットで叩かれる現状)パークにおいては、前提となる「パーク体験」はある程度空間の生産者によるイデオロギーが影響するといえる。建築を元にした空間というのはハード面でより厳密に体験を決定づけているともいえる。
万博とディズニーパークの類似については別稿に譲るが、万博をカルチュラル・スタディーズの観点から研究した吉見(1992)は、博覧会を上映される(スペクタクル的な)文化的テクストだとすると、訪問者(ゲスト)は自由に自らの意識を投影する物語の作者として参加しているわけではなく、むしろ既に別種の書き手によって構造化され、その上演のされ方すら条件づけられていると述べる。難しいので要約すると、ディズニーパークにおいてゲストはストーリーの主人公であるようで、実は別の書き手(空間の生産者)によって構造化されている、ということだ。
これがソフト面だと、インスタ映えを狙った構造物の持つ「本来の用途」を越えた構造物の使い方、"パジャマディズニー"といった物議をかもした服装、またおひとり様ディズニーといった、1955年当時にはおそらく予想されていないような、ある種の逸脱・抵抗の文脈が考えられるが、空間構造というハード面だとそうもいかない。そういう意味で、「空間の経験」自体に空間構造というメディアがもたらす植民地主義イデオロギーを持ってしまうというわけだ。
ちなみに、「空間の経験」って具体的になんだ?ということだが、基本的には散策、食事、アトラクションあたりになるだろうか。上述したように、経験される空間自体に構造が埋め込まれているわけなので、「逸脱」しない限りでパーク内でのあらゆる体験は基本的に全て含まれる。
最後に、この構築された空間を経験するのはいかなるアイデンティティであり、何を通じて行われるか、ということにも言及しておきたい。
TDSを経験するのは、ゲストである。ゲストの属性としては、外国人観光客からも人気の東京ディズニーリゾートであるものの、訪問客の多くを占めるのは日本にルーツを持ち、日本語を話し、日本人としてのアイデンティティを持つ者であろう。
つまり、TDSの舞台であるイタリアやアメリカ、中東(広義)とは直接的な関わりを持たない人々といえる。(この観点からいえば、中国や東南アジアなどからやってくる外国人観光客もこのテーマの主役に入るかもしれない)
私がこの文章で"東京"ディズニーシー(TDS)と書くのにはそういう理由がある。この論点はアメリカやフランスでは成立しない・見えてこない、"東京"ディズニーシーだからこそ成立するものだ。
後ほどしつこいほど書くが、パークでの空間経験はこうしたゲストの自己認識(アイデンティティ)の変化の繰り返しでもある、と述べておく。
TDSを解体する
私たちゲストはこのパークでいかにして植民地主義を経験するのか。実際にゲストのつもりでパークを順番にめぐって明らかにしていこう。
読み進めると明らかになるだろうが、この文章はTDSの空間的構造に時間的な植民地支配イデオロギーを見出す、という結論ありきで話を進めている。この仮説には前提条件があり、①ウォルトがディズニーランドを設計した時と同様、時計回りでパークを体験する、②西欧中心主義的歴史観に基づいて空間設計がなされている、という2つの仮説を持つ。
根拠として①ランドと同じ順番である、②一般的にこの順番で紹介される
が挙げられる。
そのため、そのBGSをそんな風に解釈するのはこじつけじゃないか?パークを時計回りに楽しむゲストなど今時存在しないはずだ、といった意見があるかもしれない。
まず前者については、全くその通りである。そのような矛盾を発見した読者諸氏は「BGSからこうも解釈できるのでは?」といった建設的なご意見をぜひお願いしたい。
後者については、「空間は構築されたものとして捉える」という私の定義を思い出していただきたい。ゲストは構築された空間をそのまま受け取るか、あるいは自分自身で(秩序を乱さないという条件で)アレンジして受容することができよう。この文章でいう空間構造とはあくまで空間の生産者(オリエンタルランド、ディズニー社、また植民地主義イデオロギー)による設計物であり、ゲストの独自の経験は考察に含まれていない。
(植民地主義的なパークをゲストがどのようにソフトな逸脱を行うか?というのはむしろ空間の生産論でいうところの"逸脱・抵抗"の発現ともいえるので、本稿とは別に議論させていただきたいくらいである)
ちなみに、各エリアの基本的なBGS紹介の根拠として『東京ディズニーシー物語』(2007)を用いているが、本書内におけるエリア紹介はメディテレーニアンハーバー→アメリカンウォーターフロント→ポートディスカバリー→ロストリバーデルタ→マーメイドラグーン→アラビアンコースト→ミステリアスアイランド、の順になっている。
では、"冒険"に出発しよう。
①メディテレーニアンハーバー
~大航海時代を身体に刷り込む~
TDSの植民地主義を考える上で最も重要な場と考えられるのが、パークに入ってすぐ、メディテレーニアンハーバーである。
南ヨーロッパの古き港町をコンセプトにしたエリアであり、中心となるポルト・パラディーゾはその多くをイタリアのポルトフィーノやチンクエ・テッレにインスピレーションを得ているとされる。
ファンタジースプリングス・ホテルのゲートを使用しない限り、パークに入園した多くのゲストはこの風景を見ることになるだろう。
イタリアの港町に立ち、海越しに大航海時代のスペイン・ポルトガルにあった要塞をモデルにしたフォートレス・エクスプロレーションを見つめる。要塞の後ろにはプロメテウス火山が聳え立つ。
なぜ、最初がイタリアなのか?見つめる先に要塞と活火山があるのか?出オチ感すらあるがこの論考の1つ目のピークは実はここにある。
まず、この状態を客観的に言語化してみよう。
「アジア人」である私たちは、冒険とイマジネーションの旅の始まりとしてイタリアの港町を再現した空間に立ち、大航海時代のスペインの要塞をモデルにしたフォートレス・エクスプロレーション、そして火山をまなざしているのである。そして、冒険とイマジネーションの海へ出ようとしている。
この状況、世界史を少しでも勉強した者であれば記憶にあるのではないか?そう、コロンブスである。私たちはコロンブスと同じ状況に立っている。彼といえば、近年その評価が見直される歴史上の人物である。
新世界に悪夢をもたらしたコロンブスは左だ。
ゲストは、メディテレーニアンハーバーでコロンブス的なまなざしを獲得する仕掛けになっている。いうなれば、まなざし(=身体)を通じて獲得されるアイデンティティだろうか。このアイデンティティ獲得方法、めちゃくちゃ近代西洋的価値観であり、万博的であり、帝国主義的である。
いうまでもなく、この状態が既に非常に植民地主義的な観点を持った"冒険"の始まりであることは言うまでもない。私たちは未知の世界への冒険の始まりをコロンブス・アイデンティティとして体験する。世界への冒険は人類の歴史からすれば決して大航海時代ではないにも関わらず、「イタリア」から始まることで1492年に設定されている※。加えて、まなざす先にはスペイン・ポルトガルをモデルにしたとされるフォートレスが建つ。TDSの絶妙な空間構造は、私たちのまなざし、立場といった状況を身体を通じていとも簡単に操作してしまう。
※様々なブログで言われていることですが、メディテレーニアンハーバー自体の時代設定は20世紀とされる。そのため、ハーバーに限定して考えた場合はそれで問題ないものの、TDSをひとつのストーリーと捉えた場合、また今後のエリアの位置づけを考えた場合、概念的にこのエリアは15世紀と設定できる、という仮定の下書いていることを了承いただきたい。
同様の状態はアメリカンウォーターフロントでも考えられるので、ここで注釈をつけておく。
↑ハーバー20世紀説の根拠
パークでの冒険の始まりは1492年の大航海時代の始まりであり、近代の始まりであり、植民地主義の始まりである。メディテレーニアンハーバーはTDSの入り口として唯一・最適解なのだ。
実際、『東京ディズニーシー物語』には、地中海一帯をさまざまな歴史的発見のスタートと位置づけ、南ヨーロッパの持つ冒険の香りや物語性こそ、最初の一歩をしるすテーマポートとしてふさわしかった、とあるので、無意識の西欧中心主義的歴史観満載、というところである。
現代ならそこが指摘され計画倒れになる可能性も否定できないが、ディズニーシーが計画された時代ならまあ・・・という感じだ。
同時に、興味深いのがコロンブスと同じ立場になっているのが私たち「日本人」である、ということだろう。私たちは無意識に「イタリアの冒険家」になるのである。この冒険(パークで遊ぶこと)においてイタリア人であることはそこまで問題にならないが、いずれにせよ世界を俯瞰し征服する側としてのゲストの「白人化」が起きている、とは書いてもよいだろう。
このゲストの「白人化」は、私たち日本人にとって強い皮肉でもある。
私たちの祖先は明治時代になると西欧植民地主義に追従し、自らを西洋の一員と認識し世界に拡張した。「ディズニーシー」が当初アメリカに建設される予定だったので想像にすぎないが、なんという皮肉だろうか。
人種・民族・ジェンダーの階層意識が消えぬ現代とはいえ、21世紀にもなって白人男性でありたいという感覚を呼び起こされる、そんな感覚だ。
出だしから非常に濃密なテーマになってしまったが、一言でまとめるとこうなる。
イタリアの港町に立ち、イベリア半島の要塞・火山を眺める。パークに入り、これから冒険の始まりだ。
この緻密に構築された空間によって私たちの身体は「イタリア人冒険家」にされるのである。緻密に計算された空間は私たちの身体・まなざしを通じて「白人化」された。冒険の始まりは1492年、大航海時代、そして近代の始まりなのだ。
言うまでもないが、まなざし(視覚)を特権化し、視覚を通じた主体性・アイデンティティの獲得、という考え方そのものが15世紀以降西欧によるルネッサンスの中で出現した価値観、人間中心主義へのパラダイム・シフトの過程で生まれたものであることはいうまでもない。(パラダイムシフトの過程で大きな影響力を持ったのが科学である。西欧における科学の復権については、フォートレスで見ることができる。表題には入っていないが、この「科学」の立ち位置は今後重要になるため、注記しておく。)
このあたりの考え方は、フーコー然り、吉見然り、よく言われることである。
万博・テーマパークが学ぶことが多い場所だというのは事実なんですが、両方に共通する「製作者・主催者による空間を通じたイデオロギー表象」であるという点には要注意です。
— やのゆー⛵ (@Yanou_disney) April 15, 2025
M.フーコーが述べたように空間とは管理の最良の方法であり、そこに見出される描写もまた事実とは異なる可能性があるのです。 https://t.co/cgWIsVPPtx
まなざしと万博、については吉見俊哉氏の「博覧会の政治学: まなざしの近代」あたりをご参照いただくとよくわかる。
↑個人的には超名著。残念ながら絶版なので図書館などで探してみてください。
自らが自覚せずとも、ゲストはここを通過することで西欧中心主義的な意味での"探検家"になることができる。
②アメリカンウォーターフロント
~イタリア系探検家からWASPへの華麗な転身~
"探検家"となったゲストは未知の世界に向けて冒険を始めることができる。
ディズニーパークが奥に行けば行くほど「他者」を表象することは上述したが、TDSでは身体を通じ無意識に西欧の探検家となったゲストが旅をする空間としてこの「他者」が用いられる。
この状態はアメリカンウォーターフロントでも同様である。もちろん、両エリアの境界に建つコロンブスがその象徴であることは言うまでもないし、自歴史的な事実として古い植民地(※この後注釈あり)の代表たるアメリカ(=新大陸)がイタリアやスペイン(=旧大陸)の次に来ることは言うまでもないだろう。
まず、第1に、大航海時代のあとにやってくるのがアメリカスの支配と征服という西欧中心主義的歴史観の追体験である。アングロサクソン的アメリカを象徴するケープコッド、そしてアメリカの栄光を象徴する20世紀のアメリカがイタリアの次のエリアに設定されているところに、強い意思、西欧中心主義的歴史観を感じられる。
実はこの空間配置を通じた歴史観の追体験というのは今後も出続けるので、ここではもう一つのポイントに重きを置こう。
第2のポイントとして、"コロンブスのまま"世界を回っているわけではない、ということだ。アメリカを経験する上で一つのカギになるのは「人種」である。空間の経験において人種・ジェンダー・エスニシティが大きなカギになることは地理学・社会学を中心によく言われることだが、20世紀初頭のニューヨーク、そしてケープコットを経験する上で一番"不快さ"を感じないのはWASPの男性である。
↑本文とは若干視点が変わるものの、人種・民族・性別・身体によって都市での経験に差があるよ、ってことが書かれている本。
20世紀のアメリカも同様で、(例えば)白人男性とアジア人女性では街歩きをしているだけでも経験に差が出る、ということだ。
つまり、ゲストはアメリカンウォーターフロントに入ることで、イタリア人探検家からWASPにエスニック・トランス(Ethnic Trans :エスニシティの壁を越える、とでも言うべきか)するのだ。(19世紀末~20世紀初頭にかけ、イタリア系アメリカ人の地位が低かったことは頭に入れておく必要がある。イタリア系は「白人」であるが、WASPではない。)
「日本人のゲスト」は20世紀初頭のニューヨークをWASPとして歩いているのだ。もちろん、パーク内において支配者としての地位は変わらない。都市空間を自由気ままに遊歩し、「まなざす」側の立場で居続けることは支配者の特権なのだから。
↑トランスという概念は人種やジェンダーを題材に研究されている。
追記
あるBGSの専門家から、"レストラン櫻"ではゲストは日系移民として扱われている、との話を伺った。私はパークフード=路上派のため、当該レストランに赴いたことがないのだが、どうもそういった設定があるようだ。
こうした各施設ごと別個に存在するBGSについて一つ一つ触れるほどの専門性は残念ながら私にはない。
しかし、仮に櫻が日系移民向け宣伝を出していて、私達が日系移民だとしても、エリア内においてより下位とされる階層のコミュニティに入ることができる、ということもまた、マジョリティ的な立場、言うなればWASP男性の特権と言えるかもしれない。
※古い植民地
植民地支配はいくつかの段階に時間的な意味で分類することが可能だ。
前者の古い植民地とは、アメリカス(北・中・南米、カリブ海諸地域)が代表的である。一方、新しい植民地とは、1880年代のベルリン会議において欧州列強に分割されたアフリカなどが該当する。
筆者の専門がフランスなのでフランスを例にすると、絶対王政期のアメリカ、サン=ドマング、ポンディシェリ、あたりは「古い植民地」に該当し、英国との植民地戦争に敗北後、占領したアルジェリアやインドシナなどは「新しい植民地」に該当する。絶対王政時代と大革命以降の共和政で分けているとも言える。
TDSの「他者」部分をどのように区別するか、難しいところだが本稿ではアメリカンウォーターフロント(=アメリカ)を古い植民地として捉え、ロストリバーデルタ以降ミステリアスアイランドまでを新しい植民地世界と定義している。
イタリアとアメリカ、2つの世界を巡っては契約労働、奴隷貿易、プランテーション、虐殺と征服、奴隷制と法的差別、新移民の苦しい生活といった凄惨な歴史が存在しているが、肩書を変えつつ「支配者」の立場であり続けるゲストには見えないのだ。見えない歴史は存在しない、ということだ。
空想のアメリカであることは事実
③ロストリバーデルタ~新たな植民地拡大へ~
ロストリバーデルタのテーマは、1930年代の中央アメリカである。かつてはジャングルに閉ざされた未開の場所だった。1880年代前半の巨大ハリケーンによって発見された巨大遺跡とそれに集まる考古学者・開拓者の街、というものだ。
さすがは"最奥"、最も他者というべきか、嵐の跡の「発見」や一攫千金を狙う男たちにより形成された小さな村というストーリーは今までで最もわかりやすい植民地主義言説である。
アメリカンウォーターフロントでWASPの男性として変身を遂げた私たちが次に向かう場としてのロストリバーデルタは、西欧中心主義的歴史観において、全くと言っていいほど「正しい」文脈になる。
ディズニーパークは奥へ行けば行くほど「他者」を表象するエリアになることは他文献でも言われているが、その通りでロストリバーデルタは遺跡や森、動物といった"野蛮"や"非文明"(あるいはエジプトのようにかつては文明があったが現在はなくなってしまったという見方)という意味で奥地に位置づけられる。だが、このエリアは「WASP化したゲスト」が更なる世界進出を行う時代に突入したことを示す、という意味でも絶妙な位置づけがされているのだ。
まず、このエリアで注目すべきは「考古学者」という立場である。先ほど、アメリカンウォーターフロントの節にて旧植民地と新植民地の区別を記述したが、ロストリバーデルタから先は「新植民地の時代」を表象するとともに、ゲストにその体験を促すエリアになったと考えられる。つまり、奴隷貿易とプランテーションを基盤とした新大陸への進出の時代から、18世紀の啓蒙主義や「文明化の使命」、産業革命といった諸科学的発見の時代への変化である(もちろん、資本主義の発達という意味で旧大陸を象徴した奴隷制が終了したわけではない)。言い換えれば、プランテーションから科学の時代への移行だ。私たちは科学的な発見を行うための植民地への旅に出かけているのである。このエリアにおいてゲストは遺跡を発掘する考古学者、となる。フィールドワークに基づく近代を象徴する活動であり、それが非西欧世界で行われている、というところに妙にリアリティがあるのだ。
科学の発達と植民地支配の関係は実はかなり深い。
19世紀後半以降、ヨーロッパや北米において実践された諸科学の発展は植民地帝国主義と大きく結びついている。例えば「帝国のすべての科学の女王」と称された地理学(話はそれるが、後述するヴェルヌもパリ地理学協会に"情報収集のため"所属していた)、「植民地主義の申し子」とされた人類学・民族学を始め、19世紀以降学問分野は急速な発展を見た。研究対象や方法に限らず、学問としての制度そのものが植民地帝国主義と密接に関連していたのである。科学の発展は(西洋の)人々に大きな"進歩"をもたらしたが、同時に侵略の道具、あるいはイデオロギーとなり、時に人種差別を正当化する論理にもなった。19世紀の科学は産業的な近代をもたらすとともに、植民地やジェノサイドを正当化する深層的根源でもあった。
↑科学の発達と植民地・虐殺の深い関係性について、わかりやすく書かれた本です。
考古学もまた、19世紀に発達した学問である。植民地諸国に点在する遺跡の“科学”的解明は19世紀以降相次いで行われた。そこに植民地主義イデオロギーが付いていった、いや植民地主義が文明の名のもと科学的解明を推し進めたとも言える。
インディ・ジョーンズの映画においても科学の発展というイデオロギーが押し出されており、植民地や「未開」地域での「博物館収蔵保存」論を展開する教授が事実上美術品・文化財収奪を正当化しているシーンを記憶している方も多いであろう。(パークにおいても、恐竜の化石が博物館に移送されている表象がある)
収奪はハイタワー三世のように露骨に行われることもあるが、「科学」というイデオロギーを持った収奪もまた存在することは忘れてはならない。
そのほか、生活の道具が西洋に移送され「プリミティブな美術品」にその意義を替えられたり、時に現地では信じられないような保管方法をされることは良くも悪くもタワー・オブ・テラーで見ることができる。
少し話はそれたが、TDSのストーリーの後半になって科学者が前面に出てくるという点に現実味がある。
入り口には陸と海を示すカリアティード、そして地球の彫刻がある。
(筆者撮影)
(筆者撮影)
ロストリバーデルタは科学に基づく植民地支配へと時代が進んだことを証左するプロップスやアトラクションが多い。幸い、ディズニーランドのジャングル・クルーズほど露骨に表象される"原住民"がおらず(生活音はBGMで流れる)、「他者」にされているのが遺跡であるだけまだ"最奥"ではないのかもしれないが・・・・。
まあ、地理学の視点からすれば、特定地域を他者として表象すること自体に領域的な差別意識(領域のスティグマ化)が見て取れるが。
ただ、このエリアが中南米を舞台にしている、ということについては申し訳ないが、私の専門外であるため考察することができない。メディテレーニアンハーバーに始まり、アメリカンウォーターフロント、そしてこの後に続くアラビアンコーストとミステリアスアイランドについては地域的な意味で位置づけの整合性が取れていると思われるが、ロストリバーデルタが中央アメリカである理由については疑問が残る。
私の仮説に基づけば、最も奥地にあり、空間的・時間的に整合性が取れる(=西欧中心主義の世界観において最も「他者」とされる)のはベルリン会議以降にヨーロッパに占領されたアフリカ諸地域(赤道アフリカなど)だと思われる。
時系列として整合性が取れるのはもちろん、19世紀のおぞましい人種の序列において最下層(最も動物に近い)とされたのは、ホッテントットなどアフリカの特定の民族である。植民地主義に則ればそうなるのだろうが、流石にそこまで恐ろしいことはしていない。というより、20世紀後半になってそのような表象はさすがにできない。
というかこの写真、なかなかエグい植民地表象である。
(筆者撮影)
この辺りはパーク開発上の理由もあるかもしれない。詳しい方はぜひ情報をお寄せください。
神殿のようなモニュメントという意味で中米が選ばれたのか?それとも「長らく忘れられていた古代文明」という意味で選ばれたのか?後者の場合、カンボジアでも設計可能である・・・実際、アナハイムのインディはインドが舞台だ。
アナハイムにしろTDSにしろ、外観と設定が違うだけで遺跡の構造や「呪い」のような非科学的要素が全く一緒な段階でどちらも圧倒的他者でることには変わりないのだが・・・。
④アラビアンコースト
~オリエンタリズムと新たな植民地支配~
1930年代の"失われた河"を越えると、次はアラビアンコーストである。
ロストリバーデルタの次に登場する世界がアラビアンコースト、というのもまた非常に大きな意味を見出すことができる。
アラビアンコーストが「アラブ」に限らず事実上広大なイスラーム世界を表象する空間であること、また巧妙に宗教的な要素が脱色されていることについては私の過去のブログを参照していただきたい。
「イスラーム成分が脱色された」イスラーム世界がパークの比較的奥地にあり、TDSという一つのストーリーにおいて比較的後半に出現することに大きな意味を見出すことができる。というのも、イスラーム世界の西欧による植民地化もまた、15世紀から現代まで続く植民地史において後期、「新しい植民地」にカテゴライズされるからだ。
この辺りは若干ロストリバーデルタと被る。違いとしては、アラビアンコーストには科学概念が出てこないこと、オリエンタリズムの強調(西洋/東洋で二元化し、後者に非科学・非文明といったイメージを押し付けること)だろうか。
ヨーロッパにおけるイスラーム世界への蔑視と憧憬の入り混じった感情は7世紀以降現代まで続く長い歴史を持つ。イスラーム世界はかつてスペインやハンガリーまで拡大したが、西欧諸国が列強となる中でイスラーム世界の盟主"ことオスマン帝国もまた植民地支配の対象になっていく。それが19世紀末以降のことである。1830年のアルジェリアや1882年のエジプト、1920年のシリアのように、イスラーム世界は徐々に英仏を中心とした列強に植民地化・分割されていったのである。アラビアンコーストがTDSにおける冒険の後半に出現するのは、こうした時間的な流れを空間配置に置き換えたもの、と考えると筋が通るのではないか。植民地史でいうところの"植民地帝国絶頂期"である。
アラビアンコーストは映画「アラジン」の世界がモデルになっており、アメリカンウォーターフロントのように実在する世界を再現しているわけではない。ただ、西洋がイメージし、理想化するイスラーム世界を空間に描き出している、という点が19世紀にロマン主義の発達のさなか文学や芸術において出現したオリエンタリズムの最も特徴的なポイントであることを考えると、アラビアンコーストがこの位置にあるのは「正しい」といえようか。
⑤ミステリアスアイランド~植民地絶頂期と歴史観の完成~
7つの世界を探検する上で最後にやってくるのがこのミステリアスアイランドである。
このエリアについては19世紀末(1870年代、1873年とも)の海図にも載っていない南太平洋の孤島、とされている。ジュール・ヴェルヌの世界を表象するという以上の具体的な位置づけがされていないため、このブログにおいては恣意的な判断というところもある。
だが、最後に訪れる世界が"ジュールヴェルヌの世界観である"という点に、このパークの一つの線のごとく筋の通った空間構造が見られる。つまり、このエリアをもって、1492年以降続いてきた西欧中心主義的歴史観が完成するからだ。
整理しよう。このエリアにまつわる論点としては4つある。羅列しよう。
①ゲストが「科学者」として位置付けられていること
②舞台となる1870年代の南太平洋の歴史的状況
③ジュールヴェルヌという人物の思想と、彼の世界がパークの中心軸に位置していることについて
④自然の征服・支配
である。
まず①だが、ゲストの立場性(ポジショナリティ)について。このブログでさんざん書いてきたように、ゲストは各エリアにおいて「支配者」であり続けるために立場を変え続けている。ミステリアスアイランドにおいてはこれまた科学者という立場である。ロストリバーデルタで説明しているので触れないが、近代科学に基づく、博物学的に世界の分類・整理を行う者、という考えでよいだろう。私たちはあくまで世界を「まなざす」側、つまり"理性的で文明側の人間"なのだ。まなざすこと、世界を分類することの支配者性についてはもう十分だろう。疑似白人のゲストはルネッサンス以降、人間主義、啓蒙主義、理性と主体、そして科学を手に入れてきた。
次に、②このエリアの舞台となる1870年代の南太平洋の状況である。
まず、南太平洋とはどこなのか?
南太平洋とは、有名どころでいうとニューカレドニア(Nouvelle Calédonie)、など、太平洋の赤道以南の地域を指す。具体的には3つの地域に分けられるので、下の地図を参照して頂きたい。
一部島が区分けに含まれていないのは、その島が"海外県"だからだ。
この地域もまた、残念ながら19世紀西欧帝国主義の毒牙を逃れることはできなかった。そして、舞台となる1870年代はこの南太平洋の島々が植民地化される時代とほぼ合致する。
ミステリアスアイランドはヴェルヌの原作「神秘の島L'île Mystérieuse」に由来しますが、この作品の初出は1874年。1840~80年代はフランス植民地帝国によるポリネシア植民地化が進んだ時期でもあります。
— やのゆー⛵ (@Yanou_disney) March 1, 2025
原作の島(=リンカーン島)は南緯34度57分00秒… https://t.co/SMBcrcuRne pic.twitter.com/GFK517GfCN
南太平洋の島々もまた1840年~80年にかけて植民地化された「新しい植民地」である。その意味では、ミステリアスアイランドもまたロストリバーデルタやアラビアンコーストと同じ枠内に入れることができる。
そして③、このエリアのインスピレーション源となったフランスの作家ジュールヴェルヌが植民地肯定派であったことはご存じだろうか。いや、どちらかというと当時の風潮として、植民地支配の肯定にはある一定の国民間の同意があり、彼の作品はそうした帝国主義意識の普及に大いに役立っていた、というべきかもしれない。彼の作品には数々の植民地の"野蛮な"人々に関する描写が出現するが、彼もまた「文明化の使命」を肯定していたのである。
ジュールヴェルヌというと、フランスが生んだ児童文学の作家の1人であるとともに、科学と発見の世紀を見事に描く小説で名を馳せたヒューマニストである。彼は奴隷廃止論者であり、民族解放主義(=国民国家建設)という視点を持ついかにもフランス共和主義者という感じである。
だが、彼の生きた時代はいわゆる帝国主義の時代である。フランスもまた、世界第2位の広大な土地を国民多数の同意を得ながら築いた植民地共和国(矛盾するようで、矛盾しない)だった。そのような時代、当時の国際情勢を織り込んで作った作品には帝国主義の香りがあふれ、読者にとっては植民精神を植えつけるような影響力を持つ作家であった。
TDS自体をこのジュールヴェルヌで定義しようというわけではないものの、ヴェルヌの世界を再現したエリアがパークの中心にあること、そして最後に訪れるエリアが植民地帝国全盛期を表象する文学作品のエリアであるというところにTDSの歴史観が詰まっていると考えることもできるのではないか。つまり1492年の新大陸発見から19世紀末~20世紀初頭の植民地全盛期で結末を迎えるという歴史観だ。事実、1930年代の植民地帝国全盛期以後、西欧世界、特にフランスやイギリスは第二次世界大戦に突入するとともに世界への影響力を失っていく。私たちは空間を通じてその立場を変えつつ、西欧による植民地支配と帝国化の約450年を追想しているのだ。
文学・音楽、絵画といったあらゆる芸術には、製作された当時の社会・政治的文脈やそれに基づく作者の意志が存在する。スペクタクルとして「他者」が消費される際はそうした文脈(コンテクスト)が抜けた状態で消費されることも多い。(スプラッシュ・マウンテンなどはその典型例)
ミステリアスアイランドもそうした事例の一つといえようが、帝国主義文化の浸透という大きな役割を担ったメディアであるヴェルヌ作品が同様に西欧中心主義的歴史観を再生産するTDSの中心にあるというのは実に示唆に富む。ミステリアスアイランドは「無人島」であり「科学技術を人々の役に立てたいという気持ちから人々に成果を公開したネモ船長の基地」という、一見植民地主義とは関係なさそうなストーリーを持つが、モデルとなった作家、そして当時の文脈を考えると、より不可視で大衆に浸透した植民地主義のオマージュなのかもしれない。
最後に④の自然の支配である。私自身が人文地理を専門的にやってきたこともありこの論考ではあまり触れられていないが、Smithが描いているように、ミステリアスアイランドは自然の人間、もしくは近代科学による征服というテーマも見出すことができよう。ネモ船長はこのミステリアスアイランドで科学に基づく地底世界・海底世界の探検と征服を行っている。どちらもアトラクションにおいては自然による逆襲を受けているのが興味深い点ではあるが・・・。
自然からの人間の脱却・区別もまた、ルネッサンス以降西欧世界が取り組んできたパラダイム・シフトの一環であり、そこには自然の統制が含まれる。
メディテレーニアンハーバーで冒険を開始する際、火山や海をまなざしていたのは、自然もまたまなざしの対象、つまり征服対象であったということなのかもしれない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自然・非文明の支配と逆襲というスペクタクルについて
自然/人間、文明/野蛮といった世界の二元論的な区分けを行い、自分自身が主体としてもう片方を一方的にまなざす、という考え方自体が非常に近代的・西洋的な概念ではある。タワーオブテラー然り、センターオブジアース然り、インディ・ジョーンズ然りとみなまなざされる側、自然あるいは野蛮・非文明側からの逆襲がアトラクションのキモになっているところもまた、「あくまで秩序に反した行動を起こすのは文明ではない存在である」という植民地主義的な思想になっている。このあたりは空間論というより表象論がメインになるのであまり触れないが、他者をエンタメとして消費するこのパークではこういった論理がたびたび登場する。
両者を分割し、一見「人間/文明」側が襲われているように見えるが、私たちはもう片方の世界を既に統治しているからこそできるエンターテイメントである。これは、数々のディズニーアニメ、そしてディズニーランドのアメリカ河で見られるような"共生し歓迎するインディアン"像など、統制済みの自然・非文明の世界である。これもまた植民地主義の延長であることは忘れてはならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
⑥ー超・仮説 ポートディスカバリーとマーメイドラグーンー
ここまでパークの各エリアを順番に記述してきたが、具体的な地域への言及がないという理由で植民地主義的歴史観にそった解説が難しいエリアが2つある。
それが①ポートディスカバリー、②マーメイドラグーンである。どちらもBGSこそあるものの、一見パークにおいてどの立ち位置になるのか決めかねる。そこで、この節では自分なりに仮説の仮説(超・仮説)を立ててみた。
まず、ポートディスカバリーである。このエリアの大まかなBGSとしては「20世紀初頭の人々が描く、時空を超えた未来のマリーナ」であること、「地球最後のフロンティアとしての海をより理解するための海洋生物研究所」、かつては「複雑な気象を解明するための科学者が集まったマリーナ」であり、フェスティバルが行われている、あたりになるだろう。
ここから伺える1つの植民地主義的言説としてはミステリアスアイランドにも通じる自然の支配・統制というテーマだろう。人間が自然と断絶し、「見る/見られる」という非対称関係に基づく世界において不自然ではない。
もう一つは古い植民地(アメリカンウォーターフロント)と新しい植民地(ロストリバーデルタ以降)を明確に分断するエリアとしての産業革命の時代をオマージュしている、と考えるのはいかがだろうか。フェスティバルという形態からして、人間による自然の征服・統制を可能にした技術を展示する、いわば初期の万国博覧会のようだ。ポートディスカバリーは具体的に世界のどの地域を指定しているわけではないものの、建築様式のデザインやテーマから19世紀の産業革命と技術の発展の時代を暗に示していると考えることは可能だ。
↑例えば、このブログの筆者ヴェルニアン・レモ氏はポートディスカバリー=ケープコッドの理想郷説を否定し、「ワシントン州サンフアン諸島サシアアイランド」だと述べる。
↑『人生で必要な教養はすべてディズニーが教えてくれた!』氏は、ホライズンベイ・レストランのプロップスを頼りに「世紀の転換点において想像された約100年後の未来」という設定ではないか?と記述する。
『東京ディズニーシー物語』において、ポートディスカバリーの建造物は20世紀初頭の人々が思い描いた未来像をもとにデザインされており、さらにヴィクトリア朝の建築様式と、1920年代から30年代の機械化時代のデザインコンセプトも織り込まれていると書かれている。
時代としては幅のある設定であるが、この時代を象徴するのは産業革命、科学技術の発展である。そして、こうした時代の転換期においてナショナリズムを高揚させ国民国家という幻想を形成させたのは、1851年に第一回が開かれ、1930年代に縮小の道を辿る(舞台はヨーロッパからアメリカへと移っていく)万国博覧会である。
この仮説を空間に当てはめると、ポートディスカバリーとは産業革命と万博の時代ということになる。私たちは旧大陸を出てアメリカスを征服し、ついに19世紀に到達したのだ。西欧中心主義的歴史観において、この位置にポートディスカバリーがあることに問題はなさそうだ。
19世紀というと、もう一つ大きな転換期である。西欧における産業革命の時代とはすなわち、「新たな植民地」への拡張を明確に示す帝国主義の時代でもある。アメリカンウォーターフロントで若干触れたが、ここからは新しい植民地の時代へ突入する。プランテーションと奴隷貿易の時代から、啓蒙主義・科学主義、そして「文明化の使命」による植民地帝国の時代である。資本主義を勃興させた植民地から、マス、大衆による熱狂と共に迎えられた植民地文化の時代である。啓蒙主義とともに「未開」の世界へ拡張し、疑似科学による人種主義が正当化された時代である。
この後に歩みを進めるエリアがヨーロッパ的な歴史観によるところの後期植民地主義イデオロギーが押し出されていたことに気づいたろうか。科学、オリエンタリズム、両者と結びつく3つのエリアが冒険の後半に出現することに強い「意図」を感じざるを得ない。
ちなみに、ポートディスカバリーはレトロフューチャー、仮想の未来という側面も持つ。この点からも万国博覧会を表象しているのではないか?と考えることもできる。
だが、私はこのアプローチの完全な賛成はしかねる。というのも、万国博覧会において「未来の表象」という側面が明確に押し出されるのは20世紀からだからだ。もちろん、最新技術を展示するという意味では事実上未来なのだが、公式によってテーマが掲げられるのは1933年のシカゴ万博(『進歩の1世紀』)を待つ必要がある。
以上が私の考えるポートディスカバリー像である。
最後にマーメイドラグーンについて、私はこのエリアのポジションを植民地主義的歴史観において決めることができない。空間配置としてはミステリアスアイランド同様、自然の征服という意味になるのだろうか?
表象論という観点では、人魚や女性表象において語ることができよう。だが、マーメイドラグーンが空間としてここに配置される意義を考えるのは難しいのである。
マーメイドラグーンについてもロストリバーデルタが中央アメリカに設定されているのと同様、パーク開発の側面(大人向けが強調された初期TDSでの子供向けエリアの必要性?)が大きく関係しているのだろうか・・?
マーメイドラグーンの位置づけについては、議論とさせていただきたい。マメラグ専門諸氏のご意見をお待ちしております。
⑦ファンタジースプリングス ~概念としての植民地~
2024年6月6日、TDSに新たなエリアが誕生した。その名もFantasy Springsである。
このエリアが公開・誕生した際、「このエリアがTDSにあるのはそぐわない」といった意見も散見された。
確かに、現実世界の7つの海をテーマにしたTDSからするとこの(マメラグ・アラコはともかく)ディズニーキャラクターやファンタジーを前面に押し出した世界というのは違和感がある、という意見は全くその通りだと思われる。
このブログのテーマはファンタジースプリングスができる前から考えていたものであり、私自身も正直なところ、この完成することによって多少なりともTDSの植民地主義的空間構造は脱構築されるのではないかと考えていた。
だが、完成しそのテーマについて考えてみると、このファンタジーに溢れた泉がディズニーランドではなくTDSに作られたことが必然であり、植民地主義のイデオロギーを継承した、西欧中心主義的歴史観のパークにあるべきエリアだとはっきり述べることができる。
まず、このエリアの空間構造から考えてみよう。ファンタジースプリングスに向かうには、ロストリバーデルタとアラビアンコーストの空白地帯のような場所に行く必要がある。
興味深いのは、洞窟を越えた先に広がる幻想的な世界、という空間構造である。私たちは未知の世界を冒険するというTDSの基本構造を維持しつつ、新たな世界へと足を踏み入れている。
この構造こそ、非西欧世界へのエキゾチズムを空間的に表現するという意味で"理想的"と言えるのではないか。「のぞき見る」という行為に見出される支配者性・非対称性は植民地支配と非常に近接的であり、冒険者が洞窟の先に見出す理想郷という構造はTDSにあるべき世界といえよう。
次に、このエリアのBGSから考えてみよう。ファンタジースプリングス・ホテルのBGS、後半の一節を引用する。
"ある日、ダッチェスという旅と冒険を愛する者が泉の美しさを発見した。川や泉の流れをうろうろと歩き回り、ダッチェスは自分自身を魔法に溢れた場所に移すことにした。ダッチェスは魅力的な泉を愛したため、近くに小さなサマーハウスを建設した。彼女(her)の友人がどんどん訪れる中、ダッチェスは彼らを皆(all)招くことのできる大きな宮殿(grand palace)を建設した。今日でさえ、泉の水源から流れる水を辿り、おとぎ話の中にあるような寓話の王国に行くことができるだろう・・"
ここで注目したいのが、ダッチェスという者が泉を見つけ、居住し、やがて友人が訪問する中で大きな宮殿を建設した、というストーリーだ。この大きな宮殿こそがファンタジースプリングスホテルになるわけだ。
少しメタ的な視点になるが、現在のファンタジースプリングスの状況を踏まえると、このような解釈ができる。
それは、ファンタジー・スプリングスのグローバル資本主義経済への組み込み、である。
過度の理想化はエキゾチズムと表裏一体であるものの、精霊の住むファンタジースプリングスは気づけば大量の"冒険者(ゲスト)"によって埋め尽くされ、精霊が作ったおとぎ話の世界はDPAやファンタジースプリングスが巨大な利益を生んでいるように、資本主義的生産・消費のメカニズムに組み込まれてしまったのである。
まさにここには「他者との不平等な表象」という側面に限られない植民地主義、つまり資本主義と一体化した植民地主義を見出すことができる。(そもそもこのエリア自体、利益を生むために作られたおとぎ話であるということはさておき、)近代世界システムに組み込まれる新世界、という構造はTDS独自であり、ファンタジースプリングスがこのパークにあることが「正しい」ということになる。
本稿のテーマである空間から若干論理が外れてしまったが、ディズニーランドにおけるファンタジーランドが最奥にあるように、「他者」としてのファンタジースプリングスが最奥にあるというのはそれほど違和感があるわけでもない。まあ、このエリアに至っては拡張用地が奥地にあったから、というのが位置の理由なんだろうが。
ちなみに、頓挫してしまったものの仮にインディ横の拡張用地が北欧エリアになっていた場合、TDSの植民地主義的歴史観に基づく空間構造は若干変容していた可能性はある。
デンマークやスウェーデンが帝国主義的な拡張をしていたということもあり、西欧中心主義的まなざしにおける北欧の位置づけは英仏とはまた異なる。もしもの話であるが、北欧エリアがここに完成していたら、ゲストの空間経験に変容はあったのだろうか・・・・?
パークを一通り巡回して まとめ
TDSという巨大な空間型メディア装置
ここまでTDSをエリアごとに考察してみた結果はいかがだろうか。実際のところ、テーマパークを回る順番など人によってさまざまだろうし、ファンタジースプリングス・エントランスがオープンした現在に至ってはストーリー体験すら少なくとも2つになっている。だが、ディズニーランドにそって時計回りで体験するという考えにもとづいたパークだということを考えると、TDSが西欧中心的歴史観に沿った近代植民地主義を支配者になり替わりながら体験するパークだと考えることも可能だ。
私自身、2001年以降TDSを何度も訪問し、遊んできたいわば"TDSの子供"でありTDSは故郷のような存在である。そのため、激しく非難することは避けたい。
だが、TDSが空間構造として植民地を西欧中心主義的に体験する施設であり、植民地主義的なまなざしを無意識にゲストに植えつけているというメディア的な側面を持つ以上、植民地の過去が問われる現代社会において植民地主義を美化しないためにパークの根本的な改善が必要なのではないだろうか。それはコロンブスの像を撤去したり、インディ・ジョーンズの野蛮で非科学的な表象を取り除くといった部分的な一面に限定されない。TDSの空間構造・配置そのものに問題がある。
度々引用しているSmithも、TDSは植民地主義者的な側面を過去の描写という意味で持っており、個々の特定アトラクション(やプロップス)において問題含みの表象を取り除くことによってなされる「cleaned up」だけでは真の脱植民地化はなしえないと述べる。つまり、TDSの持つ空間構成そのものを脱構築しない限り、植民地主義の過去の克服という人類共通の課題は解決しない。なぜなら、TDSはそれ自体がメディアとして、テーマエリアや、ライド・アトラクションたちが20世紀転換期の神話、つまり、探検exploration、「発見discovery」、自然の征服、考古学、分類classification、進化progressといった要素を(西洋的なコンテクストの中で)再生産しているからだ。
こうしたあらゆる場での脱植民地化というのはパークだけでおこなわれているのではない。例えばTDSを語る際に結び付けられがちな学問においても、「知の脱植民地化」というのが進められている。
西欧を中心とした知識の形成・支配に対する批判的検証がその中心だが、これもまたTDSと無関係ではないのが面白くもある。
TDSにおいてはアメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアの史実的正しさが良く上げられるが、アメリカ史におけるマイノリティの不可視性、西洋的普遍主義における周縁化されたカルチャー表象ははパークにおいても無関係ではなく、"秩序を乱す存在"として見事に脱色されている。パークを通じて20世紀初頭を生きたマイノリティやカルチャーが見えなくなることが問題なのだ。
私がパークのメディア的な側面とゲストによる植民地主義の内面化を極度に恐れるのは、このまなざしに違和感を感じなくなってしまう人々が再生産され続けてしまうからだ。人種差別的な動画を見続ける人が気づけばその問題点に全く気付かなくなってしまうように、パークでの体験が無意識に植民地主義を植えつけるのだ。それは、Mrs. Green Appleの「コロンブス」が製作段階において違和感なく世の中に発表されてしまったという事件がよく示している。
TDSが問題なのは、パークが植民地支配の歴史を正当化しうるからだが、それ以上に歴史修正主義を拡散させるメディア的な役割を持ちうることにある。
— やのゆー⛵ (@Yanou_disney) April 23, 2025
ミセスの問題あるPVが作られてしまったのも、パークのようなスペクタクル装置が人々に植民地主義的視点を植えつけ再生産してきた、というのも事実だ。 pic.twitter.com/Njr2eHjhe9
メディアとしてのTDSの何が問題なのか。より具体的に理解するために同様の空間メディア装置である万博(博覧会)を例に出しつつ、考えてみよう。
植民地主義を拡散するTDS~万博に見るメディアとしての危険性~
TDSが植民地主義の広告塔のようだと考えるのには理由がある。まずはこの地図を見ていただきたい。
これは、1931年にパリで開かれた国際植民地博覧会Exposition coloniale internationaleの地図である。左にある入り口から入ると、植民地帝国絶頂期であったフランスの植民地(アルジェリア、モロッコ、カンボジア、セネガル、マダガスカルなど)が各パヴィリオンに展示されている。触れ込みにあるように、博覧会を通じて「植民地世界を一周することができる」のだ。
現地ではアンコールワットなど、実物大のパヴィリオンまであり、さながら"世界一周"をすることができた。
↑パリ植民地博覧会について書かれた、パリ移民史博物館のホームページ。パリ東部に位置するこの博物館は植民地博覧会時に建てられた建物を使用している。
フランスの東洋学者たちによる「研究」、そして万博での「スペクタクル的消費」…
すべてがTDSに存在する表象である
しかもこの博覧会、最奥には動物園を設置するという、究極の人種主義博覧会である。空間配置は意図的かつ強いイデオロギー性を持っている。
空間配置で「文明/野蛮」を分け、訪問者が気づかぬうちに人種・民族の序列を刷り込まれてしまう万博など、万博史においては数えきれない。1867年のパリ万博における"非文明国"パヴィリオン、1893年のシカゴ万博での建築様式や歓楽街ミッドウェー・プレザンスなどはまさしく空間デザインを用いた植民地主義の国家による展示である。
この回から世界各国を表象するパヴィリオンという現代に続く展示方法が始まった。
(それまでは中央のパレしかなかった)
当時の国際政治を鑑みた国別配置がなされている。
"後進国"や欧州の旧市街を模したパヴィリオンが巧妙に配置された。
1931年パリ植民地博覧会を引用したのは、この博覧会がTDSと最も類似しているからだ。両者の共通点をざっと記述する。
①空間配置を用いた西欧中心主義的世界観に基づく疑似「世界一周旅行」
②入り口に「主体」、最奥に「他者」を配置することによる、世界の分類、序列化、まなざしの特権化
③無意識の植民地主義観の拡散
④植民地の現状(衛生問題、気候、現地被支配者による反乱・蜂起の頻発)をまったく描かず「理想化されフランスによる文明化を受け入れた植民地」像を演出
ここまでブログを読んできただいた方には、この博覧会とTDSの類似が理解できるだろう。
当時はまだ海外旅行(植民地は法律上は「国内」だが)など一部の人々のものでしかなかっため、多くの大衆にとって万博は植民地や海外を知るメディアであった。国家や植民地政府は植民地主義を正当化させ国民の同意を得るため、万博という国家イベントを何度も行ったのだ。万博は究極のエンターテイメントにして、究極のプロパガンダなのである。
そういう歴史もあって、万博には強烈な拡散力がある。万博自体がメディアなのだ。そして、万博ではイデオロギーを内面化できるような空間配置がなされた。
TDSには、万博がそうであったように、空間を巧妙に配置、イデオロギー性をエンターテイメントという皮をかぶせることで不可視化した植民地博覧会としての側面がある、ということだ。
そんなのこじつけだ!と思われるかもしれない。だが、ちょっと探すだけでもこうした価値観を内面化したような発言、いわばTDSの"探検・冒険"側面の礼賛発言はたくさん見つかる。さすがにここで引用はしないが・・・。
最後に、メディアとしてTDSがどうあるべきか記述して閉じようと思う。
ミセスにしろTDSにしろ、他者をスペクタクルとして消費しようとする態度にはこうした歴史修正主義や特定の視点に立ったことによる不平等な関係性が出現してしまう。これだけ世界がつながり、言語やルーツ、宗教や歴史の壁を越えた様々な人々がスペクタクルを消費することが可能となった時代において、誰かを貶める作品を作ってしまうこと自体に問題があるだろう。そうした意味において、エンタメにおける多様性包摂はまず当たり前だと私は考える。
そうした上で大切なものは何か。まず、製作者側。表象するあらゆるものが持つ文脈を理解したうえで制作を行うとともに、消費者に理解を喚起することではないか。同時に、消費者側も文脈を理解したうえで消費する態度、つまり積極的な他者理解の姿勢が必要だと思われる。TDSでいえば、パークの持つ隠れた暴力性や問題点を理解した上で、問いを共有することが重要なのではないだろうか。ディズニー側による植民地主義表象の撤去・再解釈も重要だが、ゲストもまた理解・学習をしなくてはならないと思う。
もちろん、そうした作品が今後生まれないよう声をあげつつ、TDSに変化を促すことが求められるのではないか。
ディズニーを愛し、TDSを愛し、同時に反植民地主義・反帝国主義・反人種主義者としての筆者の思いである。
最初は1万字程度の読みやすいブログにしようと考えていたものの、気づけば2.6万字の卒論のような体裁になってしまったことをお詫びします。ここまで読んでいただけた読者には感謝してもしきれません。
感想・ご意見等あればDMやリプ、こちらのマシュマロからお願いいたします。
最後に、この文章を書く上で意見をくださったユリーカ・ロックビルトさんにはこの場を借りて謝礼申し上げます。
やのゆー
参考文献(一部)
Emmanuel Vigneron(2006):フランス領ポリネシア(管 啓次郎訳)
Michel Foucault(2020):言葉と物〈新装版〉: 人文科学の考古学 渡辺一民 , 佐々木 明 (翻訳)
Michelle Smith(2022):Colonialist HIstories in Tokyo's DisneySea Theme park
杉本淑彦(1995):文明の帝国 ジュール・ヴェルヌと帝国主義文化
竹沢尚一郎(2001):表象の植民地帝国 ー近代フランスと人文諸科学ー
東京図鑑 編(2007):東京ディズニーシー物語
中村隆之(2020):野蛮の言説 差別と排除の精神史
(2025):ブラック・カルチャー 大西洋を旅する声と音
平野暁臣(2017):図説万博の歴史:1851-1970
吉見俊哉(1992):博覧会の政治学 まなざしの近代
理論の根拠になっている文献・論文については文中にてリンクを貼っておりますので、適宜ご参照ください。
TDR公式サイト
https://www.tokyodisneyresort.jp/tds/map.html


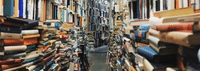

コメント