xSxJ階段とxNxPジャンプについてのメモ
はじめに
xSxJ階段とxNxPジャンプについて、単体の記事にしておくことにする。
これはxSxJ(S型かつJ型)とxNxP(N型かつP型)の特性の違いに着目したもの。
xSxJに親和的な、階段を一歩一歩登っていくような移動を好む認知スタイルあるいは行動特性がxSxJ階段。
xNxPに親和的な、大きなジャンプあるいは2Dワイヤーアクションのような危うい移動を好む認知スタイルあるいは行動特性がxNxPジャンプ。あるいはxNxPによるそういう危うい行動を指すものとしてのxNxPジャンプ。
それぞれ、わたくしが勝手にそう呼んでいるだけである。
あくまでも対比が重要で、実際にはxSxJがジャンプする時もあるだろうし、xNxPが階段を一歩一歩登る時もあるだろう。
例外的な状況は周囲に鮮烈な印象を残すこともあるが、本人にとってのふだんの認知、デフォルトの構え、安心できる手法、そういったものが重要。
あるいは本人にとっての「それしかできない」というもの。
xSxJはジャンプする時にも確実に一つ一つの手順を踏んでジャンプをしているかもしれない。逆に、xNxPが階段を一歩一歩登っているように見える時、実際には一段一段についてワイヤーアクションによる移動をしているかもしれない。
ちなみにわたくしとしては、xSxJ階段は「エスジェイかいだん」、xNxPジャンプは「エヌピージャンプ」と発音するのを前提にしている。
概説
以前作成した2つの画像を再掲することによって示す。
この2つの画像は2024年10月にもXにポストした。
https://x.com/metanagi/status/1846653968388407315
実際に画像を作成したのは2023年1月である。
xSxJ階段について
重要なのは連続的ということ。
ランダムアクセスではなく、シーケンシャルアクセス。
すでに通ってきた場所は足場としての実績があるため、それに立脚するのは当然という世界観。
常に近過去に依存した移動ともいえる。良くも悪くも意識が近過去へとロックインされがち。
未来に至るためには自分(自分たち)が何を手にしたのかに着目するのは当然。
常に「手持ち」が重要。
小さな改善がゴールにつながるという確信。
小さな進行の連続が完成だという確信。
人生全体を、長い長い階段とみなす視点。
xNxPジャンプ
重要なのはランダムアクセス的で文脈切断的ということ。
第三者から見ればすでに足場としての実績のあるはずの場所は、むしろ本人にとっては不安をもたらすものであり、より強固なものを求める気持ちが背景にある。
未来に至る重要な要素は、これまで手にしたものからはかけ離れた何かなのではないかという根拠のない確信。
可能性に立脚した世界観。
近過去よりも、遠い未来に立脚。あるいは逆に、遠い過去であることも。
進行の連続よりも、新しい視点や意外な再解釈。
人生を転機からとらえる視点。
xNxPジャンプによって、自分が生み出したものについて新鮮な目でとらえることが出来る場合もある。
文脈を切断して、まったく新しい意味が付加される瞬間。
xSxJだけで集まる場合であれば、通常は時間が経過して成員がガラッと変わってから初めて可能となるような新しい視点、あるいは外部の人間によって初めてもたらされるような視点。こういう新しい視点が、一人の人間の頭の中で起こる。
単に大胆な移動が好きということではなく、「最後の壁バイアス」とでもいえるものが重要。
「あと少しなんだ」的なセリフは、映画『π』や映画『カリフォルニア・トレジャー』に登場する。
またバルザックの小説『絶対の探求』にも登場する。
全体としては飽きっぽいように見える人が、なぜ同じプロジェクトにエネルギーを投入し続けることが出来るのかというのは、この「最後の壁バイアス」のおかげだといえる場合が多い。
最後の壁に見えたものが全然最後の壁ではなかったということが判明したり、壁を超えるためにはもっと準備が必要だったことが判明すると、飽きが来やすい。それなりに長期間、飽きたままになることもある。それで周囲は安心するが、結局また関心がぶり返すこともある。
かつてのわたくし自身がそうだったが、「最後の壁バイアス」によって借金をしてしまいやすい。この壁を超えたら事態が劇的に変化するはずだと確信しているためだ。
バルザックの小説『絶対の探求』では、バルタザール・クラース氏が何度も何度も「最後の壁バイアス」によって無茶な行動に走ってしまい、周囲の人が振り回される。
xNxPジャンプによって時には驚くような結果をもたらすこともあるが、本人や周囲の人の人生を破壊する要因になることもある。
なお、2Dワイヤーアクションといえば長らく『海腹川背』だったが、最近はインディーゲームの『SANABI』のほうが有名なのかもしれない。
【ゲーム紹介】サイバーパンクワイヤーアクション「SANABI」の魅力を5分で紹介してみた。【サンナビ/NintendoSwitch/Steam】 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=E24HkgHPG1U
(「CAITO【カイト】」チャンネル、5分40秒)
わたくしはこの『SANABI』は未プレイ。
関連しているかもしれない概念
関連しているかもしれない概念をいくつか紹介しておくことにする。
マイケル・バリント(マイクル・バリント)のいうオクノフィリアとフィロバティズムの対比
具体的な対象に密着(直接的な接触)あるいは一体化をして、対象なき空間を恐怖するオクノフィリア。
具体的な対象を遠ざけて、接触を恐怖し、スリルに依存するフィロバティズム。
中井久夫のいう「ヤマノイモ型」と「オリヅルラン型」
1980年発表のエッセイ「世に棲む患者」より。
同心円的な構造との親和性があるヤマノイモ型と、「思いがけなさ」との親和性があるオリヅルラン型。
わたくしには、「ヤマノイモ型」はxSxJ(特にESxJ)に近いように見え、「オリヅルラン型」はxNxP(特にINxP)に近いように見えるわけだ。
「世に棲む患者」には以下のような箇所もある(ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.36、みすず書房版『中井久夫集 1』P.222)。
まず、「信頼しにくいはずのものに軽信的で、まず信じてよさそうなものへの不信」という逆転がある。これと近縁なものをいくつか挙げれば、「遠い可能性をすぐ実現しそうに思い、手近な可能性を等閑視(遠く感じる)する」という逆転もある。
わたくしの画像解説の中の「小さい可能性が大きく感じられる」の元ネタがこれ。
他人から見れば「なんて危ういやり方で」と思うけど、本人にとってはすごくカタいように見えている、というのがポイント。
ちなみに、ちくま学芸文庫版『世に棲む患者』P.22には誤記があるので注意。「第一群である。」となっているべき箇所が「第二群である。」となっている。みすず書房版『中井久夫集 1』P.211は正しく「第一群である。」になっている。
中井久夫のいう「油絵法」
「油絵法」という言い方は「私の日本語作法」というマニュアルのようなものの中に出てくる。
以下はちくま学芸文庫版『「伝える」ことと「伝わる」こと』P.342、みすず書房版『中井久夫集 2』P.158より。
あっちを塗り、こっちを塗り、下塗りをし、削り、上塗りをし、遠くから眺めては修正し、最後にニスを塗って仕上げる方法です。
さっきまでこっちを作業してたのに、なんで今はこっちなの?というのはいちいち他人に説明しているヒマはない。
今回のわたくしの記事「xSxJ階段とxNxPジャンプについてのメモ」の文章の部分についても、最初から順番に書いているわけではない。
一貫して「あっちを塗り塗りこっちを塗り塗り」である。
ところで、絵画と違って、文章はリニア(線形)だ。
ランダムアクセス的に文章を書くからこそ、完成品ではシーケンシャル性が表れることもある。完成品だけを読んでも、順番に書いていったのかランダムアクセス的に書いたのかは分からない。
小説では特にこれが重要。
ADHD
いわずもがな。
検索すればいくらでも出てくるだろう。
クロニンジャーのいう「新奇性追求」(novelty seeking)
新奇探索と呼ばれることもある。
関連する遺伝子(DRD4遺伝子)が見つかっており、イノベーションと結びつけて語られることもある。
中井久夫は「血液型性格学を問われて性格というものを考える」の中で、「新奇探究遺伝子」という言い方をして解説している(2009年刊『臨床瑣談 続』P.55〜P.56、みすず書房版『中井久夫集 10』P.208〜P.209)。
解説というか、まだ始まったばかりの研究なので生暖かく見守る、というスタンスの記述といえるかもしれない。
ちなみに以下は2024年のGIGAZINEの記事。
そわそわしがちなADHDの人は「探検家」のような遺伝的特性がある可能性 - GIGAZINE(2024-02-22)
https://gigazine.net/news/20240222-adhd-genetic-traits-explorers/
スキゾタイパル
ASDと誤認されていることも多いスキゾタイパル。
本人が困っていないことが多いので、医療につながりにくい。
別の観点として、INxJかつスキゾタイパルという人は比較的医療につながりやすいが、INxPかつスキゾタイパルという人は医療につながりにくいというのがあるかもしれない。
わたくしはスキゾタイパルという概念をかなり広くとっており、病的とはいえないレベルを指している場合もあることには注意。
サンクコスト効果
別名コンコルド効果。
Wikipediaを見てもらうのがいいかもしれない。
コンコルド効果 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%89%E5%8A%B9%E6%9E%9C
「せっかくここまで階段を登ってきたのに」という思いがネックになり、無駄なことにリソースを投入し続ける要因になる。
逆にxNxPの場合、あともう少し粘れば大きな成果につながったのに、突然飽きてしまったり別のことに熱中したり、あるいは物理的に遠くに行ってしまったりして、莫大なエネルギーを投入したものが無駄になってしまうことがある。
おわりに
xSxJ階段とxNxPジャンプについては、『分類しない暴力』の中で詳しく解説する予定だった。
分類しない暴力【A面】|cleemy desu wayo|note
https://note.com/cleemy/m/m3c861812c2a0分類しない暴力【B面】|cleemy desu wayo|note
https://note.com/cleemy/m/m438414762279
でもこの『分類しない暴力』については2025年5月4日現在、まだ記事が一つしか完成していない。
『分類しない暴力』の構想を練り始めてからあまりにも時間が経ちすぎていることもあって、xSxJ階段とxNxPジャンプについての簡単なメモをとりあえず先に単体の記事として公開しておこう、と今回思い立ったという次第。
今回の記事「xSxJ階段とxNxPジャンプについてのメモ」は『分類しない暴力』を構成する記事では「ない」。
もし『分類しない暴力』の中で同じことを解説するなら、もっと気合を入れてやることになると思う。
なお、中井久夫のいう「ヤマノイモ型」と「オリヅルラン型」の対比および「油絵法」については、わたくしがいま執筆中の記事「関わりたい人がいないということ」で解説する予定。
関わりたい人がいないということ|cleemy desu wayo
https://note.com/cleemy/n/n0e5af5951bcf
こちらはおそらく5万字を超えることになる記事。2025年5月4日現在、まだ上記のURLにアクセスしても記事はないはず。
予定としては5月中に完成させるつもり。
でもどうなるかは分からない。なんせxNxPなもので。


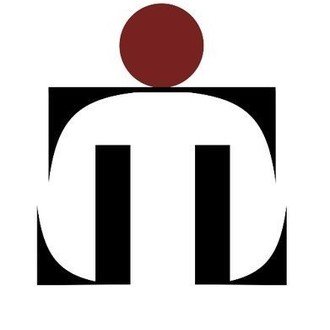
コメント