庵野秀明から富野由悠季へのインタビュー ZガンダムLDボックス特典資料より
TVアニメにおける「ロボットアニメ」というジャンルを変革し、今なお続くIPを作り上げた『機動戦士ガンダム』の監督、富野由悠季。
そのガンダムに続いて、TVアニメで社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』の監督である庵野秀明。
ロボットアニメ、いや日本のアニメ文化の歴史を語るうえで避けて通れないこの2人の巨匠。しかし、2人が公の場で面と向かって会話しているシーンは、ほとんどない。
最も有名なのは、庵野秀明が自ら同人誌として発行した『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 友の会』通称、「逆シャア本」に収録されているロングインタビューだろう。これは2023年に株式会社カラーにより再販され、今ではお気軽に手にすることができる。
しかし、これと同じタイミングで行われたもう1つのインタビューの存在を知る人は少ない。『機動戦士Zガンダム』のLD(レーザーディスク)BOXの解説書に収録されているインタビューだ。
本記事執筆の経緯
こう書いている私も、最近知ったばかり。先日投稿したジークアクスの記事のコメントで教えていただいた。インターネット様々である。コメントしてくれた方、ありがとうございます。
しかし、ネットで調べても全然そのインタビューの内容がヒットしない。最新のZガンダムの円盤特典を見ても、再録されている様子はない(と思われる)。
なぜ!?
今や日本トップレベルの映像クリエイターと、ガンダムの生みの親との対談なんて、すごく歴史的価値が高いと思うのだが。
ジークアクスを見てから、庵野と富野の関係性について人並みならぬ執着を持ちはじめていた私は、さっそく駿河屋でLDボックスを注文した。
当然、LDの再生機器なんてない。特典の冊子目的での購入だ。ジャケットが想像以上に美しかったのは嬉しい誤算だったが…それ以上にデカすぎて辛い。DVDの比ではない。収納場所に困る。
この興味深い資料が、この巨大なLDボックスを中古で購入しないと読めないというのは、あまりにも勿体ない。短いながらもすばらしいインタビューだったので、このインターネットの世界に引用して内容を残しておこうと思う。
なお、太字になっている箇所は原本では通常のフォントのまま。重要な箇所を読みやすくするために自分が編集している箇所であるということをご認識を。また、読みやすさのために改行や段落分けも自分が手を入れている。
引用し、私がコメントを残すという形で記載していくが、かなり密度の高いインタビューで、削るところがほぼなかった。著作権的にはアウトに限りなく近い。新品では入手不可能なコンテンツなので、ご容赦いただきたいなと思っているが…直近のコンテンツに何かしらでこのインタビューが再録されるようであれば、本記事は非公開にするつもりだ。
以下、インタビューの引用を行う。
庵野秀明による富野由悠季へのインタビュー
庵野(以下、A)
「Zガンダム」の企画というのは、放送の前の年、つまり84年の2月くらいからスタートしているんですが、その時は「聖戦士ダンバイン」の最終回近く。3月に始まる「重戦機エルガイム」の第一話直前ですよね。普通のTVアニメよりかなり早い段階から準備が始まっていたのは、どうしてですか?
富野(以下、T)
「エルガイム」から「Z」は直結だったの?
(中略)
一週間も空きがなかった。よくやったよね、信じられない。齢とったんですよね、今じゃ体力も気力もなくなって一年も前から思いつきもしない。
その話で重要なことがひとつあって。メモが始まる半年くらい前、「ダンバイン」の放送なかばで(83年秋頃)「ガンダム」はビジネス的には再開するだろうということを予想していたの。何もそんな話は聞かされてなかったんだけれど、「新ガンダム」のプランニングに勝手に入っていったんです。
「戦闘メカザブングル」「ダンバイン」と続けて2年やった。その時の周囲の状況を考えると、「ガンダム」が再浮上するだろうし、ビジネスとしてずっと続くんだろうと。ロボット物2本やって検討がついたんです。
このインタビュー当時(93年)の庵野秀明は、当時ガイナックスで「オネアミス」の続編として企画されていた「蒼きウル」がポシャった後。「エヴァ」の本格的な企画に入る前の状態である。
同じアニメ監督であり、アニメを今まさに「企画」しようとしている立場の人間として、Zの企画の成り立ちを気にしていたのだろうか。
そして、驚きなのが太字部分。まさか、サンライズのプロデューサーたちよりも先に富野が自分自身でガンダムの続編を構想していたとは。
あまり商業的な流行りに乗る人ではないという印象もあったので「ガンダムの続編なんて作りたくない!」ってイメージを持っていた。それが少し変わった。
しかし、監督になる前の経歴、「コンテ切りの富野」なんてあだ名がつけられていた時期の職人としての彼の活躍を考えると、納得がいく。このあたりに、宮崎駿とは少し違う彼のアニメ観が垣間見える。
アニメを芸術ではなく、ビジネスの世界のなかの商品として考える富野の「職業人」としての感覚が現れたエピソードだった。
「エルガイム」が「ガンダム」をやる前の捨て駒だったという、衝撃の発言のあとに、Zガンダムの主人公、カミーユの話になっていく。
T
でも「エルガイム」のシナリオが数本上がった段階で、僕にしては作り過ぎの世界観にしてしまったらしい、と気付いて、やはり「ガンダム」に行かざるをえないだろうなと。84年2月くらいから本気になりはじめた。
メモにカミーユ・ビダンという名が出てきたのは6月頃かな。その時点では本気になっていた。翌年の次期企画の話というのは、6,7月頃に出るものなんですよ。その時までには企画を固めようと、春の終わりの頃から主人公の名前探しを始めていて、彫刻家のロダンの弟子のカミーユ・クローデルの名前に行きついた。あの人の経歴(キャリア)が分かった時点で、カミーユを男の名前に使わせてもらおうと決めたんです。
実はカミーユ・クローデルのキャラクターを全部カミーユ・ビダンに引き移した。それが「Zガンダム」という作品にとって半分は不幸なんだけど、「エルガイム」で飛んじゃった気分を自分の中に引き戻すためには、カミーユのようなキャラクターでなければやれなかった。
A
カミーユ・クローデルって、その後映画にもなりましたけど、その頃は誰も名前も知らない人ですよね。半生を精神病院で過ごした女性で。カミーユも最終回で精神をやられちゃいましたが、それもクローデルに影響を受けて?
T
もちろんです。あの時は「エルガイム」の反動でクローデルみたいな人をモデルにしたんだけど、今ならうまく説明できる。
カミーユ・クローデルにとっての師ロダンの位置づけが、カミーユ・ビダンにとってのZガンダムだっていう。その構造が僕にとって一番シンプルにとらえられる。クローデルとロダンの関係というのは、愛人関係でありながら、じつはロダンの半分くらいの作品を彼女が作ってんじゃないかという。でも世間的には、クローデルの作品もロダンが作ったんだと見なされて、失意の中で彼女は精神をやられる。反対にロダンという人はそのおかげで美術史に残っていったわけ。
でもひとりの人間として考えると、ロダンが自分ひとりで成立していったかといえば決してそうではない。クローデルみたいな人もいたんじゃないか。と同じように、ガンダムだけで「ガンダム」が出来るわけではない。
要するに「表現される人と物との関係」を、クローデルとロダンの関係は象徴的に表しているサンプルだったんです。だからカミーユに惚れ込んじゃった。
カミーユにモデルがいたという話は聞いたことがあったが、「ガンダム」という物(ここではロボットという物だけでなく、作品というコンテンツの意味もあるように思える)と人との関係性に着目して選んでいたとは。
確かに、ガンダム作品の本質って何かと言われれば、ロボットのデザインや形だけではなく、繊細な主人公などの「人」の要素もシリーズの象徴となっていっている。シリーズ2作品目の主人公として、富野が「失いたくないガンダムのなにか」の要素をカミーユに見いだしていたのだろうか。
A
当時の談話で「僕には今の若い子がみんなカミーユみたいに見える」と語ってらっしゃったんですが。
T
それは感じていた。ロダンの時代だったら鬱病になって、それが高進していって病院に入れられてしまうという人も少なからずいたわけだろうけれど、今の時代はある部分それが風俗になることもままあるわけです。価値観や生活様式が変わったことによって、かつての異端児視されていたものが、TOKYO(原文ママ)という状況の中では風俗になっちゃってる部分が目につく。
ものすごく分かりにくい例で恐縮だけれども、例えばコンビニのおにぎり、僕にとってはおにぎりの味がしないんです。でも、今の子はそれがおいしいという…。味覚という不変に見えるような感覚でさえ、30年前と今では絶対に違う。
それと同じで、以前は異常と感じられていたものが普通の感覚の中にまで忍び込んでいる。それの良い悪いはわかりません。でも「Z」を作っていたころに感じたのは、カミーユみたいな少年が多くなって、オジサンにとってはそれは好ましい現象に思えなかったのね。
でも、これは自分の中で過去になった作品だからいえるんだけど、風俗で変わるものは、長い目で見ると大した問題じゃないんじゃないかってこと。結局その人のメンタルな部分がどういう育ち方から生まれてきたのかが重要なんで、風俗で変わる部分なんて大した問題じゃない気がしてきたね、最近は。
A
今では、「Z」を見ていた中高生が社会人になっていますからね。
T
作り方は意識してないんだけれど、やはり作品てその時代をモロに映しているな。作品ていうのは、作っているときは自分の意志や好みでコントロールできているような気がするんです。ところが7、8年のサイクルで見ると、やせても枯れても「あの当時のもの」ってわかるんだよね。全否定したにしろ不肯定したにしろその時代の反応だから、作品の中に全部時代が残っちゃうのね。口惜しいねえ、名作にならない。名作っていうのは時代を超えるものだから。
この時代に生きていた人間じゃないので、私は実感できていないが、当時も「キレる若者」みたいな論調ってのはあったのだろうか。たしかに、アムロよりはカミーユのほうが「感情で動く若者」的な要素は強かったように思える。
A
今放映している「Vガンダム」の主人公ウッソは、すごく素直な子に描かれていますが、監督の少年観に変化があったんですが?
T
違ってみえるんじゃないんですよね。何を作っているときもそうなんだけど、時代に引っ張られたくないと思ってる。子育てを終わった大人になった今なら理想的な子供……こうあってほしいという子供像をきちんと描かけているんじゃないかと思ったのね。子供という部分に限っていうとウッソみたいにあって欲しい、と思う部分は作品の中に上手く出ている。
問題なのは、そんな理想的な子供が今出てくる環境があるのか? と問うてみると、そんな子は絶対に生まれない世の中になってるんだよね。だから、ウッソが自立してくれるかは保証の限りではない。だから「Vガン」の最終回はファンタジーにしておかないと、ウッソが死んじゃう。ファンタジーにしきっています。
それも7、8年後に見ると「富野はVガンでやっぱあの当時のこと描いてたんだよね」と、みなさん言ってくれるんじゃないかなぁ。
「バブルがはじけて、みんながイジケはじめた大人の世界を、ウッソという子と対比させて描こうとしたけど、結局どっちつかずになっちゃったね」
と言われることが、今から想像つく(笑)。
「Z」のころは日本中が夢見心地の時代だったからカミーユを描けた。
「ロボット物であんな終わらせ方しちゃいけないよ」
「うん、知ってる。だからやったんだよ。1本くらいはそういう作品があってもいいだろう!」
って言えたのよ。
でも、今年から来年はもう言えないのよ。ずっと不況が続いて世の中全体が暗いんだから。今カミーユが出てきたらたまらないぜ(笑)。だからウッソは「なんでもかんでも生き抜け!」という話にしている。
A
いやあ「Vガン」は良いですよ!
これは「Vガンダム」の作品解釈としてもおもしろい部分だった。名前のとおり、ウッソという主人公は「ウソ」みたいな子供として、ある種ファンタジーとして割り切っていたのだなと。
そして、自然と作品製作の背景に時代の影響があるというのも納得がいった。たしかに、イケイケの時代で、キラキラとしたコンテンツばかりであったら、「Z」のようなダークな作品をぶち込みたくなるのもわかる。
そしてこの時の富野の「1本くらいそういう作品があっても」ということばを聞いた庵野が、「こんな終わり方な作品あっていいの?」と世間を騒がせるアニメを作ることになるとは…
T
作品を通してシリアスにものを考えるっていうのは僕の中で「Z」で終わってますね。じゃあなぜ「逆襲のシャア」を作ったのかというと、「Z」の企画が決まった時点で「この先シャアとアムロに決着をつけるまでの2、3本のシリーズをやらなきゃいけないだろう…」と気づいたからなのね。だから「Z」は途中でシャアを引っ込めたの
A
難儀ですね。この間、本放送以来久しぶりに「Z」を全部見たんです。僕も監督を体験したから分かるようになったんですが、かなり混乱が見えるんですよ。特に後半ハマーンを出してしまった時には、この先どうまとめるのかと。
T
まとまらないでしょう(笑)。
A
当時はカミーユという主人公がどうしても分からなかった。見直した時におぼろげながら分かったんですが、「あ、主人公なんだけど、この人は傍観者の役目を持ってるな」と。
それに加えて、さらにそれを傍観しているシロッコという人も出てきて、シャアはクワトロ大尉を演じ、アムロは7年間の情けない自分を恥じて、全員が混乱のさなかにいる(笑)。
そんな中で、アムロやシャアは、カミーユの中に昔の自分を見ているんですよね。よく同じ過ちを繰り返す描写を入れてるんですが、「愚行というのは繰り返さざるを得ない」というのを描こうとしてやったんですか?
T
その描写に関しては、はっきりした論理立てはありません。だから整理されていないし、混乱に見える。
(中略)
カミーユについては、初期設定については正しいんだけど、僕に問題があった。心の中の内省的な問題を繰り返し提示していって自閉症になる過程をよくわかっていなかった。カミーユを描くとき、シャアやアムロのような「本来その劇的空間の中に入ってきてはいけないような人物」を入れることによって描こうとして、心理的なプロセスを追えなかった。制作者として自閉症になっていくプロセスが分かっていなかったのが、分かりにくさのもう1つの原因ですね。
やはり僕はTV屋だから、芸人根性に徹した作り方の方が性に合ってるし、上手いらしい。カミーユ・ビダンは僕にとって荷の重いキャラクターだったのは確かです。
A
背負ってるものが重すぎますよね。もう1つフォウ・ムラサメというキャラクターは反対に上手くいってると思うんです。彼女はどこから生まれたんですか?
T
今のカミーユの話と連動しているの。カミーユをフォウみたいにシンプルに、「自閉症の坊や」として描きたかったんでしょう。今はもうフォウについては感覚的にしか覚えてないんだけど、とても好きなのよ。
ひとつ今にして分かったことがあるの。フォウ・ムラサメをやっちゃったから、カミーユは上手くいかなったんだね(笑)。彼女に吸われたんだ、というのを今思いだした。
A
2人とも結局、根は同じですよね。
T
フォウは表現はシンプルな設定にしているはずなんだけど、そうじゃないんですよ。カミーユ・クローデルをモデルにしたキャラクター作りを、フォウとカミーユの部分に全部集約したの。
あの頃、講談社でノベライズをしていたんだけど、5冊で完結した時に編集者に言われたことがあるの。「フォウ・ムラサメの部分は圧巻でしたから、いいです」って。その時は単純に喜んだけど、よく考えたら後は何にもなかったんだなあって(笑)。やっぱり「Z」はこれだけだった。何のために5冊も書いたんだ、2冊でよかったってガックリきた思い出がある。
その年の徳間書店のアニメグランプリで女のコのキャラクターで1位を取ったしね。出番が少ないのにね。それはもう計算じゃないのよね。だから混乱の部分も、フォウの上手くいっている部分も、全部計算じゃないんですよ。でも、フォウの後はカミーユ、バラバラになっちゃったけどね。
2人のカミーユ、フォウに対する評価が語られている。確かに、後半になっていくと物語の風呂敷がどんどんと大きくなっていき、カミーユのセンシティブな部分は目立たなくなっていった。良くも悪くも強烈なインパクトを与えていたカミーユという主人公が、物語の中心ではなく、傍観者的な側面を持ち始めていた気がする。
カミーユの消えていった人間的な部分が、フォウに「吸われた」という表現をしているのもおもしろい。この特典冊子には他スタッフへのインタビューもあるのだが、多くのスタッフがフォウとのエピソード(20話)について言及していた。それほどまでに、衝撃を与えたのだろう。
A
アニメーションはそれくらいあった方がいいですよ。フォウの前までは、カミーユ、小さいことにこだわってましたよね。そのあとは、シャアとアムロの役割まで全部背負っちゃったから。
T
あれはまぁ、かわいそうね、やっぱり。
A
それにハマーンとシロッコまで来ましたからね、4人分背負っちゃった。20話以降、カミーユは急に忙しくなりますからね。
T
ハハハッ。そんなのは予定してなかったものね。そりゃ気の毒だった。そりゃ最終回で、少しは休みたくなった気持ちも、分かるような気がするよね。
(’93年11月26日 上井草にて)
以上でインタビューは終了である。
Zガンダムの作品解説としても読んでいてかなり面白かった。逆シャア本と比較してしまうと文量は少ないが、それでも庵野秀明の富野由悠季への影響が垣間見えるようなインタビューだった。
計算づくじゃないアニメ作りや、作品としての終わり方。内省的なキャラクター作りなど、後のエヴァへの布石となるような要素を感じられる。
こうしてnoteにアウトプットしながら読むことでより深く読み解けた気がする。こんなのをありがたがる人は相当マニアックだと思うし、伸びないだろうと思うが、記事にできて良かった。
ジークアクスの放送後でもよいので、元気なうちにまた2人の対談が見たいものだ。
関連記事

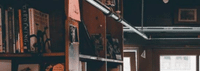
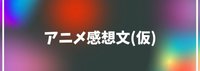
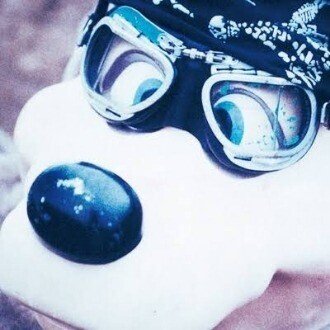
コメント