断面二次モーメント ~木構造のための構造力学~8
目次
第1回 計算書を読んでみよう
第2回 力のつりあい
第3回 モーメントとは?
第4回 反力
第5回 応力
第6回 断面について
第7回 図心・断面一時モーメント
第8回 断面二次モーメント(今回)
第9回 断面係数
第10回 許容応力度
断面一次モーメントと名前が似ています。ただ使い方などだいぶ違います。混同しないようにしましょう。断面二次モーメント(記号I)は非常に良く使うのでこうしきは暗記しておくと良いでしょう。
断面二次モーメント(記号はI)
断面二次モーメントとは、部材の変形しにくさで、たわみ・座屈などと関係します。大きいほど強くなり、記号はI、単位は長さの4乗で、ミリの場合「 mm4(4は4乗) 」のように表記します。
用途
・異なる断面の断面係数(Z)を出すため
・座屈のために利用する断面二次半径(i)を出すため
・曲げ剛性(EI)を出すため
・弾性座屈荷重(Pk)を出すため(曲げ剛性を利用)
・はりのたわみを出すため(曲げ剛性を利用)
といった感じで、直接この数値がわかったからといって、何かが分かるわけではありません。ですから何に使うかを覚えておく事がポイントです。
公式
断面2次モーメントは、断面1次モーメントと同様に、X軸、Y軸別に求める必要があります。X軸に関する断面2次モーメントは
Ix= bh3 / 12(3は3乗)
Y軸に関する断面2次モーメントは
IY= hb3 / 12(3は3乗)
となります。このX軸とY軸どちらを求めているのか、常に頭にいれておいてください。
断面2次モーメントの特徴
断面2次モーメントは様々なものに利用されますので、特徴は個別に覚えておく必要があります。基本的には、たわみは断面2次モーメントに反比例することを覚えておけば十分でしょう。つまりたわみについては断面2次モーメントが大きくなればなるほど、大きくなるのです。わかりにくいか・・・。
梁のたわみ
梁など横長の部材に物が乗っかりますと、下にたわみますね?構造計算では、このたわみを数学的に算出します。たわみ(記号δ:デルタ)とたわみ角(記号θ:シータ)です。
たわみ
たわむ前の材料の高さと、たわみ後の高さの変位した長さで表します。当然大きければ大きいほどたわみ量は大きくなります。そのたわみの最大を最大たわみ量といい、次の公式で導き出せます。
δ=C×Wl3÷EIここで、Cは、定数です。梁や荷重の形態によって、決まります。1級建築士の試験ではお馴染みですね(Cの意味は、一級編で解説いたします)。
Wは梁にかかる全荷重です。lはスパンですね。これらをかけ算したものをEIで割ってあげます。Iは断面2次モーメントです。Eはヤング係数です。ヤング係数については応力度のページで解説いたします。EIは構造計算ではよく出てくる組み合わせなので、「曲げ剛性」という名前がついています。ここで学習するのは、そのEIで割っている事です。つまりたわみ量はEIに反比例するということです。ヤング係数は材質によって決定する定数ですから、実際は断面2次モーメントの大小で反比例すると言う事です。Iが大きくなればたわみが小さくなると覚えておきましょう。
たわみ角(θ)
たわみを図であらわすと次のようになりますね。
このたわみの曲線をたわみ曲線というのですが、その接線と部材との角度のことをたわみ角といいます。こちらの公式も
θ=C'×Wl2÷EI(2は2乗)
とたわみの公式に似ていますね。こちらも断面2次モーメントに反比例します。C'も定数ですが、Cとは異なります。lが一個少ないですね。ここも重要です。θの単位は、ラジアン(rad)です。
たわみの特徴
くどいようですが、断面2次モーメントに反比例します。すると弱くなっているように感じますが、実はちがいます。たわみの量が小さいほど強くなります。断面2次モーメントが大きいとたわみにくいのです。lのなので、長さ(スパン)の3乗に比例します。つまり材料が長いほど、たわみやすくなります。しかも3乗なので、急激に変わってきます。建物で使える部材の長さが、ほぼ決まってくるのはそのためです。またW(荷重)は、大きいほどたわみやすくなります。当たり前ですが。
次回は断面係数です。断面二次モーメントは「たわみ」に関係しますが、断面係数は「曲げ」に影響します。曲げとたわみの違いを理解し、それぞれ使い分ける必要がありますね。今回と次回はよく見比べて学習してみてください。
いいなと思ったら応援しよう!
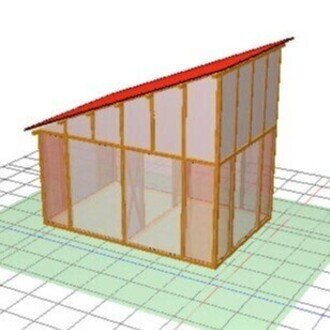


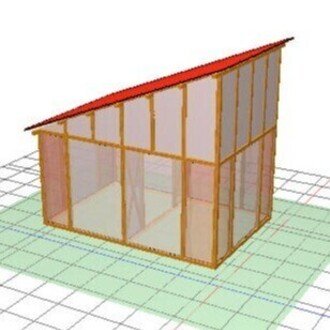
コメント