【ストップ!選択的夫婦別姓】家族秩序を崩壊させる夫婦別姓の問題点 ―関係各省庁での慎重な検討を 小田村四郎(拓殖大学総長)【平成8(1996)年3月 夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民委員会】
1、家族は社会秩序の基礎
御存じの通り戦後民法が改正されまして、戦前の民法における家の制度が廃止されました。かつての家の制度は戸主を中心とするいわゆる大家族制度が基本になっておりましたが、これを廃止いたしまして、いわゆる核家族、近代的小家族とも申しますが、これは夫婦と未成熟の子供で構成されます。この核家族を基本単位として編成されることになったわけであります。
ここで、民法が期待しておりました夫婦像、家庭像とはどういうものかと申しますと、一夫一婦制度が基本でございます。夫婦がお互いを尊重し、互いに助け合いながら共同生活を営んでいく、そうして夫婦の間に生まれた子供を愛情をもって育てていく。そして家族はその共同生活の名称として共通の氏を称することとしたのであります。わたくしはこの民法が描きました家族像というものは、社会秩序の基礎を形成するものでございますから、今後も尊重されるべきものであろうと思います。
御存じの通り、一九四八年に制定されました「世界人権宣言」におきましても「家庭は社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会および国の保護を受ける権利を有する」 と書いてございます。国際人権規約にも同様の文言がございます。また新憲法の基礎になりました、当初司令部から手渡されましたマッカーサー草案では、これも「結婚は両性の合意に基づく」というくだりの前に「家庭は人類社会の基礎である。」という言葉が入っておりました。ですからこれは世界を通じて普遍の原理と考えてよろしいと思います。
2、家名の存続は夫婦別姓論では片付かない
ところが数年前から「夫婦別姓論」という声が高くなって参りました。この問題で当初主張されておりました理由は、「今まで使っていた姓を変えるということは、社会生活で不利になる。」こういう理由が一番有力であったようでございます。図書館情報大学に勤務しておられました先生が、訴訟を起こした問題がございましたけれども、「今まで使っていた姓を変えると今までの業績が誰のものであったか分からなくなる。」というようなことがありまして、不便を感じることは確かであります。しかしこれは社会生活上の呼称の問題でありますから、戸籍上の問題ではございませんので、現在では通称としての旧姓の使用は社会で広く行われております。したがってこの問題は、解決済みになったと見てよろしいのではないかと思います。未だに問題があるとすれば、法制審議会で以前提案されましたC案、つまり戸籍上は同姓であるけれども、社会生活上呼称として、通称としての旧姓の使用を認めるということを決めればこれで保障されることになるかと思います。
その次に別姓論で主張されましたのは、一人っ子同士の結婚だと家名が絶えてしまうという話でございました。たしかに一人っ子同士は別姓で、その人が生きている間はよろしいんですけれども、それでおしまいになります。ですから決して別姓論で片付く問題ではございません。家の名を残すというのであれば、現在でも生まれた子供、つまり孫を養子にするという形で解決されておりますし、仮に別姓論を取ったとしても、そういう方向しかないわけであります。もしその間に死んでしまって断絶するということであれば、旧民法にある「廃絶家再興」という規定がございましたから、そういう規定をおけば、それで片付く問題であります。夫婦が別姓でなければならないということにはなりません。
3、家族の一体感より個人の権利が優先する別姓論
そこで結局、別姓論の根拠は、やはり「人格権」とか「アイデンティティー」とかいうことになってくるのであります。
夫であるとか妻であるとか、そういう役割自体が個人にとってのわずらわしい拘束になっている、これが「個人の自由」或いは「ライフスタイルの自己決定権」という言葉が使われていますけれども、自分の生き方は自分で決めるんだという、こういう個人の権利を拘束するものである。これを跳ね除けなければならないという主張が一番大きな主張ではないかと思われます。
つまり具体的に申しますと現在、社会の最小単位とされております家庭というものを解体いたしまして、個人を最小の単位としていく、家庭というものは、これは福島瑞穂弁護士は「ネットワーク」という言葉を使っておりますが、これは個人の一種の緩い結合体というようなものとして、個人の権利、自由をこれに優先する至上のものとするという考えであろうと思います。したがって夫婦別姓がどういうふうになるかという場合を考えるに当たっては、そういう主張が基本になっていることを頭に入れて考えないといけないと思います。福島弁護士は、「夫婦別姓はパートナーとどういう関係を作っていくかという点が問題なので、名前だけの問題ではない」といっております。つまり夫婦の一体感、家族の一体感よりも個人の自由、あるいは個人の権利が優先されるべきだという考え方でございます。
そこで具体的にどうなるかと言う事でございますが、別姓になった場合に、同姓よりも一体感が薄くなるのは当然であろうと思います。夫と妻の姓が違いますし、親と子供も違う、他人のような感じになる、「それはいったいどうしてだろう」という疑問が起こります。そこでその場合、夫婦関係や、子供の姓や教育、いろんな問題がございますが、それらは省きまして三点だけ申し上げたい。
4、別姓導入で事実婚は増加し結婚制度も否定へ
第一の問題は、「事実婚」、事実上の男女の同棲生活の問題でございます。別姓が採用になれば今まで、自分のアイデンティティ―が損なわれるからと結婚しなかった人も結婚するから「事実婚」はなくなると言いますが、「事実婚」は逆に増加するだろうと考えます。先ほど申し上げました「ライフスタイルの自己決定権」という主張が前提にございますので、したがって『法律婚』にするかどうか、つまり届け出をしようがしまいがそれは自分の勝手である、こういう考え方ですね。それともう一つは別姓になりますと、外から 外見上は夫婦であるかどうか、あるいは親子であるかどうかは分からなくなります。今までは同じで統一されておりましたが、これからは正規の夫婦で、別姓を名のっている人が多くなれば、一般に世間の目を憚って同棲生活を止めようという気持ちがあったものが、薄くなります。大手を振って事実上の夫婦生活ができることになってくるでしょう。また、夫婦間、婚約者同士で子供の姓をどうするか決められなければ、面倒だから事実婚にして しまえということもあるでしょう。また福島弁護士は法律婚によって姻族関係が発生する、つまり配偶者の家族と親族関係になることがわずらわしいと言っていますが、そういう理由で法律婚を嫌う人もいるでしょう。
いずれにせよ、この「事実婚」という問題は非常に大きくなってくるだろう。では正規結婚のメリットは何だろうということですけれども、同じ民法改正案で、嫡出子、非嫡出子の「相続分」の差別は解消することになります。そうしますと「法律婚」のメリットというのは、「相続権」と税務上の「配偶者控除」この二点だけになります。相続は死んだ後のことですから大変先のことです。それから、配偶者控除も共働きの夫婦には関係ございません。そうなると「法律婚」のメリットは何もなくなってしまうのであります。これも事実上の結婚が増加する原因になってきます。
福島弁護士の書かれた本を見ますと、外国でも「事実婚」が非常に増えてきております。例えば、スウェーデンでは二十歳から二十四歳までの間に事実婚をする者は61%に達する、また1月の末「朝日新聞」の家庭欄で特集をやっておりましたが、婚外子の比率がスウェーデンでは46%、アメリカでは20%、八木秀次さんの書かれたものによりますと、フランスでも3分の1が婚外子だという状況になってきているわけです。この別姓制度を取った場合に日本においてそういう状態にならないという保障は全くありません。福島さんはそれを見越してのことかも知れませんが、「法律婚だけを保護して事実婚を差別するのではなく、法律婚と事実婚は等価値であるという考え方をとるべきである」と言っています。更に福島さんの論文で「既婚はもう恋の障害ではない」とも言っています。一度結婚したものも自由に恋をして良いと言っていますが、おそらく別姓を主張してこられた方々は別姓が実現した場合に次ぎの標的を、「事実婚を法律上認知せよ」という事にするだろうと思います。
これは言い替えますと、「結婚制度」それ自体を否定することになる、つまり結婚しているかどうかという判別、識別は、それは二人が同棲しているかどうかと言う事しか判別の基準がなくなるのであります。
5、事実婚を公認した革命ソ連の惨状
そうして、かつて事実婚を公認した国が一つだけございます。それは革命後のソ連であります。ソ連は革命によりまして、エンゲルスの論文に基づいたのでしょうが、「家族はブルジョア的なものであるから解体しなければならない」ということで、結婚、離婚を自由化いたしました。近親相姦とか重婚とかいうものを、犯罪リストから除いてしまう、堕胎も公認されることになります。そして1927年に未登録の結婚(事実婚)を登録されている結婚(法律婚)と同一の等価を持つとしました。重婚でさえも合法となったのであります。二人、三人と結婚して良いことで、その結果想像もできない社会問題が起こりました。
一つは離婚と堕胎の乱用の結果、出産率が激減いたしました。人口が増えなくなったのです。それから、社会的には少年犯罪が激増いたしました。少年による暴行傷害、重要物の破壊、住宅への侵入略奪と殺傷、学校襲撃と教師への暴行、婦女暴行、そういうようなことで新聞記事は埋まったのであります。数百万の少女がドン・ファンの犠牲にされ、百万の家なし子が生まれた、と書かれています。さすがのソ連政府もこれは大変だと言うことで、反家族政策の誤りに気付きまして、1934年頃から政策を180度転換いたしました。家族の尊重、結婚、離婚の制限、こういうことを実行し、1944年には未登録結婚の制度を廃止いたしまして、今回民法改正の問題となっております嫡出子と庶子との「ブルジョア的な差別」も復活いたしました。
ところが、ソ連がそういう悲惨な実験をやったことに対しまして、福島弁護士の岩波新書の本によりますと、「ロシア革命の後、様々な政策が根本から見直され、一時的であれ、事実婚主義がはっきり採用されていたとは素晴らしいことだと思う。」と絶賛しているのであります。私は、別姓を主張される方々の本当の意図はどこにあるのか、ということをよく考えていただきたいと思うのです。
6、離婚の急増によって子供は被害者に
第二の問題は離婚の急増であります。別姓論者が「ライフスタイルの自己決定権」ということを強く主張している以上、「気が合えば結婚するが、気が合わなくなれば離婚する」というのは当然であろうと思います。家庭の維持と言うよりも、個人の自由、そういうものが尊重されるわけでありますから、おそらく離婚が急増するであろうと思います。現にアメリカでは、結婚したカップルのうち、半数が離婚すると言われています。そのうち70%が3年以内に再婚し、さらにその60%は再び離婚する、3回4回の離婚はざらにあるのです。フランスでも離婚率は3分の1です。結局そうなると被害者は子供であります。
アメリカでは子供の60%が18歳までに両親の離婚を経験し、その3分の1が親の再婚と2度目の離婚を経験するのだそうです。こうなりますと、継母、父の児童虐待が問題になっております。現在報告されているものだけでも年間2百万件を越えております。2月17日の「日本経済新聞」の夕刊でございますが、深刻化する児童虐待問題に対して、ニューヨーク州では、事件概要の調査記録を公開する法案に知事が署名したという報道がなされております。こういうような環境で育てられた子供が、少年非行や麻薬の汚染、十代の出産、そういうようなことに走るのは当然であります。私は、今回の沖縄の少女暴行事件に付きましても、こういう環境と無関係ではなかろうと思います。また、2月20日の「読売新聞」によりますと、フランスの大都市近郊の中学校では、90年代から犯罪が急増しております。学校に対する放火、恐喝、暴力、麻薬取引、そういうようなものが年間500件を越えるそうであります。パリ近郊の5県では、暴力にさらされる教師が授業ボイコットをやったと報道されております。
7、老人介護や祖先の祭祀もおろそかに
三番目は老年者の問題であります。老年者問題は現在の政治の重要課題でありますが、厚生省のゴールドプラン等におきましてその中心は在宅介護におかれています。この在宅介護は、夫婦家族一体での協力がなければ到底実行できません。しかし、姻族関係の発生を避けたいというような別姓論者の家庭で、配偶者の老親を介護するなどということは、考えられません。結局民法に書かれている親族間の扶養義務は空文と化し、厚生省の老人福祉プランは砂上の楼閣に終わることになるでしょう。
なお、こういうイデオロギーのもとでは、既に死んでいる配偶者の祖先の祭祀など、見向きもされないことになるでしょう。
先ほど申し上げましたように家庭は社会秩序の基礎であります。家族秩序が崩壊してしまいますと、これは社会が取り返しのつかない混乱に陥るわけであります。これを修復することはソ連政府のような革命的な絶対権力がなければ不可能に近くなるだろうと思われます。
現在「住専」問題が主流でございますけれども、これはあくまでも金の問題であります。別姓問題は、人間の問題、家庭に直結する問題であります。これだけの法案を何故急いで作らなくてはいけないのか、私は疑問に思います。物については実験してもよろしい、しかし人間は実験の対象にすべきではないのです。
選択だから差支えないではないか、という意見があります。しかしこういう無形のシステムは、法律上の支えがないと非常に弱いのです。私は慣習の力だけに委ねておいて、家庭の絆が磐石だとは思いません。ましてマスコミの風潮でお分りのように、その宣伝力は強大であります。別姓が若い人達の間で流行になった場合、何人もこれを阻止することは出来ません。この問題の重要性をお考え頂きたいのです。
8、法務省だけでなく関係各省庁をあげての慎重な検討を
そこで私のの提案と致しましては、こういうような大問題を議論しようとするならば、少なくとも法務省民事局だけに任せないで、あるいは法律学者だけに任せないで、内閣全体として取り組んでもらいたい、先ず家庭の崩壊の問題に現在悩んでいますところのアメリカやヨーロッパの実情を詳しく調べてもらいたい、外務省を使って結構でございます。あるいは調査団を派遣して結構でございます。政府が本格的に取り組んで、その原因を究明し、各国の対応策を調査し、わが国としてそういう事態にならないようにするにはどうしたらよいか対策を講じなければならない。
そういう問題ですから、これは一法務省の問題ではない。国民全体の問題なのですから、各省協力してこの問題を検討していただきたい。先ず総務庁に青少年対策本部がございます。文部省は生涯学習局、初等中等教育局、厚生省は児童家庭局、老人保健福祉局、労働省婦人局、警察庁刑事局保安部、法務省も民事局だけではなく、刑事局青少年課、こういうところを集めて、別姓問題を含めて慎重に検討していただきたい。これが私の提案であります。
最後にもう一点、宗教の問題を申し上げます。欧米ではキリスト教の伝統が色濃く残っております。アメリカはこれだけ社会的に混沌が起こっているに拘らず、尚世界一の政治的、軍事的、経済的な地位を保っております。これは私はピューリタン以来のキリスト教の伝統のおかげだろうと思います。ところがわが国にはそうした強力な宗教の伝統がございません。最後のとりでである家庭が崩壊してアトムになってしまったときに、その時社会がどうなるか。ソ連の経験で申し上げた惨状に陥るか、さもなければ人間には共同生活がどうしても必要でありますから、オウム真理教のような疑似家庭形態、上九一色村でも共同生活しておりましたが、一種の疑似家庭形態が生まれてくるだろうと思います。そうした邪教が天下を制覇しないとは限らないのであります。
以上、夫婦別姓問題についてご提案申し上げました。
(『家族解体のすすめ「夫婦別姓法案」に反対する』、夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民委員会、平成8年3月)

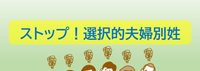

コメント
1なら別姓の国はみんな家庭崩壊してんのか?