祈り論考──ボカロシーンと社会構造、冷笑と祈りを見つめて
この記事は、Twitterにて書いてきた「祈りと光の凋落について」の連投をまとめ、更に補足を付したり編集を施したりしたものとなります。
こと、近頃アマチュアボカロシーンにて、私が「アツい」と言い続けてきた祈りの文脈について、総合的に考えていく記事となります。
1:祈りについての観念
まずもって、今までの論考と記述が不足していて、祈りと光の正体みたいなところまで話が進んでないんですが、少なくとも祈りと光は割と愚直と真摯の性質の上に成り立つものであるとは思っています。だから、一種の絶望みたいなものではありつつ、皮肉と冷笑とは対置されるのは確かだと思います。いうなれば祈りは、これら皮肉と冷笑への強烈なカウンターカルチャーとしての存在である訳でして、同時に「冷酷で画一なマジョリティ」への対抗でもある。ここから話は始まります。
補足として。
そもそも「祈り」の文脈、というものが如何なるものであるかについて、本稿においてはこれ以降日本の社会背景をベースにして考察しています。つまり、冷笑に代表される行動様式へのカウンターたる、一種の理念やイデオロギーとして「祈り」についてを論考しているものとなります。しかし、そこから照らせる事としては、飽くまで抽象的で包括的な祈りだけであり、むしろ実態・実行としての祈りについてはまた別の補助線や論考を挟む必要があります。ここで現代アマチュアボカロシーン(概ねNiconico及びTwitterを活動基盤とし、概ねボカコレの最終ランキングに加味すれば10位以下の規模感、かつDECO*27などのように基本的には企業案件含む職業としてのボカロ音楽活動をしていない。これら要素を総合的に勘案する必要あり)にて行われる祈りの様態や具体的な形に触れることは余りないですが、気が向いたら各論として書きます。また、以降のところで、祈りの様態のうち、呪いと祈りの重複や同一性については長々述べたりしています。それらについては、問題提起をしてくださったKAWAHAZEさんのお陰で追加した項です。この場に代えて、格別の感謝を。
以下に、ボカロ祈り文脈(と思っている)作品の例を挙げていくので、参考までに。
補足:祈りと現代新教義
3/12 12:15追記の項です。
祈り、祈り、と言いますが、原義的な祈りについて触れない限り本稿の定義はずっと曖昧だよな、ということで、今一度原義を振り返ります。
元は祈りとは、宗教的な意味合いと結び付くものです。形態はともかく、自然宗教であれ、なんであれ、神か仏か超常か、そういうものにこいねがうことを意味として持っています。なので、必然的に祈りに言及するとき、それは大なり小なりその人の「信仰」に寄与せずにはいられない訳ですね。それは名前の付いた宗教に限らず、アニミズム的なものであるとか、死後の世界の観念であるとか、それともスパゲッティモンスターであるとか。ひとつ体系立てられないような、個人単位に固有化されたものも含むと思います。むしろ現代日本についてはそっちの方が大きい気がする。みんな大体クリスマスはお祭り気分で、ハロウィーンもお祭り気分で、正月も除夜の鐘を聞いてお祭り気分で。既に体系立てられた宗教のイベントが三つも交錯していることにお気づきだと思います(し、こういう宗教や生活慣習の雑多さはしょっちゅう指摘されるところです)。ところが、およそ現代日本人の信じ祈りを捧げる「大いなる存在」(神とか仏とか運命)であるとかについては、多分見解の一致は見られないのではないでしょうか。私たちは、それなら何に祈りを捧げているのか?
これについて、私そろそろ作品にしようかと思っているんですが、私たち現代祈り人の中には自然宗教的な、緩やかな一つの意識が芽生えているように思います。私はこれを便宜的に「見えない手」と呼んでいます。生き方であるとか、教義的なものをすっぽり空洞化させて、単に私たちの願いを微かに伝えたり、それとなく背を押すようなごく僅かな気付きみたいなものに、神性を見出している気がするんですね。まさしく、超常の何かがあることを最初に見つけ出したような自然宗教的な興りだと思います。つまり、信じるべき法や教えというものは与えてくれないけれど、私たちの素朴な希求に対してはそれとなく力を貸してくれるかもしれない、気まぐれで放任主義のかみさまの使う「見えない手」は信じているのです。貸してくれるかもしれない、というのがポイントで、決して誰もが祈り信じれば必ず救われるわけではないとは分かっている。自分たちも懸命に信じはしないが、その代わりに向こうも必ず応えてもらう必要はない。そういうなんとなく遠くて近いかみさまを見ているのです。
とても体系立てられるものではないですが、強いて言えば既存の理性的な宗教に見られる「信じれば救われる救世の存在」はすっかり希釈された緩やかな絶望・救われなさへの感覚……もっと言えば救いはないという諦念と分断を反映したものがそこにあって、代わりにごく小規模な恵みだけがそこにあるという微かな安らぎと結合もまた同居している、「ちいさな宗教」があるんじゃないかと。
だから、私たちが祈るときは、そういう隣り合う誰かにだけ伝うようなささやかな救いを求めているのです。この、「信じればちょっと誰かが報われるといいな」という、救いへの不信と微かな期待を包括した擬似的な自然宗教こそ、現代人の目覚めた新教義(新宗教)なのです。神の恩寵(ご恩)と願いや信仰(奉公)は、ともにミニマリズムの波に乗ってこぢんまりとしたものになったのです。
この小ささ故に、生活や手に届く範囲の人々や事象への祈りが増えました。逆に今、世界平和や総人類への祈りは、少なくともこうした祈りの実践をする人々の作品においてはそこまで数が多くはありません。今後綴る、祈りの小規模なムラでの抵抗にも通じますが、自分のフィールド内でのみひとつ楽園を作るという思想の上では、その外側まで手が回らないのです。
現代新教義の見えない手は、そういう大きな大きな不信感や無力感と、その中で信じている微かな救いや結合の生存という、相反した思想の上で営まれています。これをどう受け取り、解釈するか。それはそれぞれに委ねたいと思います。
補足:祈り文脈作品の例示
これは私が好きなだけです。対人、こと特定の「あなた」と「わたし」の閉じた関係に絞られた言葉の紡ぎ方は、祈り文脈の特徴だと思います。時には「わたし」たる一人称の中で完結することもある、極めて内省的なものもあったり。とかく人と人との在り方について、洞察と思索が深く営まれることにひとつ核を観念出来るのではないかと。繋がれないもの、完全に分かれないものを、それでも不完全にでも繋げようという意識が祈りにあります。
本作に於いては、以下の歌詞が特徴かと。
いつか空が消えたら いつか光が絶えたら
受け入れてあなたと泣きたいのです
そして思い出し、笑いたいのです
この、無力と受容の中にいて、その中に紡がれる感情や思考への洞察こそが祈りかなと。長々述べると大変なので、ひとまずここまで。
これも祈り。ことボカロシーンというムラの中への祈りだと思います。この作品から祈りを見た人、多いのではないでしょうか。
まさに強烈な冷笑、しかもボカコレ的社会構造の一義的な価値尺度への抵抗だと思います。一義的な価値尺度については後述。
攻めの祈り。喪失とか、朝食とか、そういうものに代表される「生活の中の虚しさの手触り」について、深い思慮があります。すごく遠い距離への祈りです。
やはり本作にも無力感が横たわっている感じがします。
「誰も知らない星の隅で 枯れてゆく花を見た」との一文に象徴的な曲だと思います。
挙げればキリがないので、各論はまた今度。
3/12 12:20追記
この人を挙げないのは祈り文脈を語っておきながら大嘘過ぎるだろうと思い。
無力感や世界の残酷が前提にある前川ぺそさんの各種作品。まさにこれから取り上げる祈りのイデオロギーの中にあると思います。その切実な祈りと、それが何度となく折られ、破られ、それでも祈らずにはいられないことと。すごく具体的かつ身近な生活の香りを伴って祈りを実践している人の一人です。ほんとに、この人を聴けば私たちは、直感的に何を希求しているのか分かります。
2:冷笑の源流、無力の苗床
冷笑は虚無主義、或いは一義的な価値尺度に照らして劣等側の理論を内包しています。ここについて補足します。まずもって、冷笑流行の源流の一つを追うことで、その根底理念みたいなものが見え(ると思い)ます。ここは考証がたくさん必要なので、本当に、本当に皆さん考証と精査をよろしくお願いします(冷笑が何処から大きな潮流となったかは、もう本当に領域を横断しての考察が必要なくらい、有機的な成り立ちをしているはずなので、とても個人で網羅できるとは思えず……)。
それでは無力感(虚無主義)と一義的な価値尺度の劣等、これを概ねの社会情勢とボカロシーンで併せて見てみます。
まず虚無主義ですが、かなりこれは無力感、失望感に裏打ちされた観念です。およそ2020年周辺にこれを巻き起こした社会的なマイルストーンが……まぁ、挙げればキリがなさそう。私としては、やはり最大関心事のウクライナ戦争の影響もあるとは思います。が、他方で国内情勢の方がもっとダイレクトに心情に影響しそうなのでそっちを挙げたいところ。
コロナの影響もあるかな、とは思うのですが、そこから副次的に露見した「核家族第n世代説」を私は推します。何かというと、核家族という家族形態と現代社会の歪みがいよいよ顕在化したんじゃないかという説です。
というのも、核家族かつ共働き。これはとんでもない負担のかかる形態です。まして、愛着形成に必要な触れ合いと愛情について、ほとほと欠乏しがちなものであり、これが家族機能の低下をもたらすのです。つまり家庭内がまるで安全地帯ではなくなった上、そんな領域で耐えることを強いられるかのようにコロナの巣篭もり要請が直撃した。そう私は見ています。家族機能の喪失或いは弱化した家庭の中には、歪な権力勾配と加害:被害関係が存在します。補足的に例示すれば、極端な例がDVです。DV未満であれ、情緒の不安定な家族構成員がいるとき、そのことへの対応に莫大なエネルギーを消耗します。家庭という領域内では、精神的、物理的に暴力的な方が権力勾配の上位に位置でき、そこに加害:被害関係の完成を見るのです。つまり、家庭内のある種の対等関係は、とっくに真の意味で終焉を迎えているのです。ここがすごく重要。
加害:被害関係は、再生産されるんです。DVサバイバーが、DVをするようになる。悲しい話ですが、そういうケースはかなりあります。コロナで半強制的に家庭に押し込められた者が、加害:被害関係にこれまで以上に取り込まれ、抑圧と閉塞の中へ沈み込む。抵抗余地のない環境からの逃避不能というわけです。
この抵抗余地のなさこそが、まさに虚無主義の中にある無力感の醸成に大いに寄与している……と考えます。これはもはや核家族化して以来の社会構造で、大なり小なり日本の家族機能は全体的に落ちている。従って、程度の差はあれど、この加害:被害関係に潜む転覆不能な権力勾配に縛られていることを痛感した現役世代は、皆等しく無力感を感じているのだと。
話は逸れますが、な~んか少子高齢化もこれがデカい理由な気がするんですよね。無理な体制で営まれ、穴あきと化した家庭機能の中で育った我々平成世代。その歪と、もはや普遍化した家庭的トラウマを断ち切るべく、そもそも無理な核家族というシステムから離脱するのは必然ではと。もはや大家族の再形成は望めない訳です。私たちには歪さを内包した核家族の形成しか道がない。そこからの逸脱、脱出を試みてのシェアハウスムーブメントなんかもあった気がしますが、体感的にはそれもあまり多くない。いよいよ分断の時代なのだと思いますね。脱構造意識といいますか、後ほど述べますが、祈りの営みの特徴として備えている、被害:加害関係の再生産を行わない側面を、既に少子高齢化という社会問題は内包しているような気がします。もはや滅亡に向かうこと、それもまた祈りの一側面です。日本は割と祈りの国なのかもしれない。でもこういう諦めの形って、冷笑っぽいような……? と思った方、鋭いです。後述の、祈りと冷笑のルーツで触れます。
3:冷笑の源流、社会構造の固定化
ここまでが、日本全体に伏する虚無主義の苗床を記述した訳ですが、次に一義的な価値尺度とその劣等を説明します。
先程、加害:被害関係は再生産されると申しあげましたが、これって家庭から恐らく場を変えたとしても起こり得るんですね。つまり、家庭で被害者としての立場にいたものが、加害に回るフィールドがあるんですよ。それがそう、SNS上です。親から子へ、子から孫へ、そうして家庭単位でループし受け継がれていた流れが、今、社会全体を駆動させているんですね。
数多いた被害者は、そしてSNS上で一つのイデオロギーの上で連帯して、大きな大きな加害の再生産をしているのだと、私は思います。そのイデオロギーこそが冷笑であり、裏付けされているのは無力感であり、それの根拠として活用されるのが「既得権益」と「社会構造」、それによる一義的な価値尺度であります。 キーワードは分断なんですね。フェミニズムが照らし出した「見えない天井」が、独りでに暴走を始めたんです。男女の勾配、身分の勾配、学歴の勾配、先天的な能力の勾配…………。世はまさにマウンティング全盛期。あまつさえ、そうした加害:被害の勾配と関係は固定されており、超えられないものとして観念されます。かつてはそうした天井を是正し、公平と平等を目指した見えない天井は、時を経てその根本から変わってしまった……というよりその表皮だけを剥ぎ取って別物が乗っ取ったように思います。観念のミミック化。無力感の果てに、見えない天井を各々が観念し、不公平と不平等を武器に振りかざすようになったのです。むしろそうした固定化されたものという観念に浸かり、それらを武器としたのだと私は思います。あるときは、レッテルを貼ることで無理にでも勾配を生み攻撃するため。あるときは、自身の弱者性を用いての防御に。これが冷笑の根本じゃないかと。
ここで一点補足しますが、一義的な価値尺度とは一体なんなのか? もう少し直感的に形容すれば、それは「勝ち負け」です。勝ち組と負け組の観念が、特に激化しているのですね。世界総ランクマッチ。グローバリズムと資本主義の成れの果てとでも言えるかもしれないですね。腐敗した終わりなき競争社会、その延長に今があります。だから、近年の若年層における冷笑の代表例と言える「論破」も、言うなれば勝ち負けの観念の具現化です。論破は、グローバリズムの目指した共同体としての一体化とはまるで逆、むしろ序列をつけマウンティングを行い分断を促進する行為に他ならない。そういう、「イデオロギーが崩落した末に起こる基本理念の逆相化」が、これからはもっと顕在化しますし、この基本理念の逆相化という現象は、後に祈りの行く末……ポスト祈り論考でもテーマに取り上げます。
4:冷笑の補助線。ピエロのアナロジーについて
持てるものは即ち強者であり、既得権益。親ガチャ、学歴、先天的な能力や知能。その優劣。これは冷笑に深く隣接する理論付けじゃないかと。つまり、もはや構造上どうやっても変えられないものなんですね。ここで運命づけられている。
それに付随する興味深いものに最近見まして。
こちら。ピエメーターです。
人の勝ち組度を、様々な観点から定量的に推し量ってみようという試みです。かなりこれ面白いな、と思いまして。というのも、その尺度って基本的には「身長や顔の端正さなど」の先天的なもの、そして「学歴」「内定先企業」が主なんですよ。そして、割とその基準が高いのなんの。私もやってみて、見事最低評価でした。ガハハ(地味にダメージが堪えている)。
大事なこととして、その測量の正確さや信頼度はまぁ二の次三の次というか、その点はこの記事の制作者も非常に考えていることを補足します。かなり実験的というか、問題提起が主だと思います。
近年はとりわけ、ピエロが弱者の象徴的に語られ始めました。元々道化師というのは、その職業の性質からして弱者側でありますし、その反面で「権力に直接諮問できる」という性質も持っていました。機転や頭脳の明晰さは求められるものでもあります。これ、現代社会の弱者の「理想」なんじゃないですか? 弱者でありながら、権力勾配に何らかアクセスや干渉できる本質的には優秀な人間…………。無力感と冷笑の中でひとつ立身を見込むのであれば、これほどのアナロジーはないんじゃないでしょうか。
それこそ、ジョーカーに代表されるような。補足として。無敵の人という言葉が問題提起されたとき、やはりジョーカーってその象徴として描かれるというか。暴力と冷たいユーモアで以て、既存の冷酷な社会を転覆するというのは、まさに冷笑の持つ加害:被害関係の再生産の過程をなぞるような気がしてなりません。
やや話が逸れましたが、こういう虚無主義的な冷笑の世の中で台頭した新たなヒーローや能力者の形……みたいなものがあって、やっぱりこれも裏を見れば「あらかじめ構造は固定化されている」ことが前提にある感じがします。
余談ですが、この構造の固定化の観念は、努力をすればのし上がれるという努力論の反動でもあるというのは、誰もが一度は聴いたことがあると思います。前時代からの揺り返しを経て今があるというのは、どの文化や社会でも普遍的な事象です。特にバブルが弾け、失われた平成の停滞感も後押ししてます。この努力論、というのが割と重要になるので覚えておいてください。
包括として。
核家族化の反動による家庭機能の弱化。そこの第n世代の私たちは、家庭内でも少なからず覆ることのない加害:被害関係に置かれることで、無力感を醸成してきました。そこに社会構造の停滞や、出自により固定化された既得権益、それらによる不平等に気付いたわけです。
そうした構造に立たされる、もはや勝てない私たちは、被害者であることやレッテル張りを武器として振り回すようになった。
これが、世代的に冷笑が蔓延している理由と、その背景であると考察します。
5:アマチュアボカロシーンを見据える前に。夜風見式、ボカコレ村論の概要
この先の話をする前に。まだ出ていないボカコレ振り返り記事で語っている論考を一個、ざっくり説明することで今後の論の足しにします。題して、ボカコレ村論。
ざーっくり説明すると、ボカコレの数値はおよそ五つの層に分けられるという話です。うち、アマチュアボカロシーンを飛び越えてドメスティックさから離脱した第一層、アマチュアボカロシーンを牽引する村長衆の第二層、今ボカロシーンで影響力を持つ前衛実験の宝庫たる第三層、マジョリティとしてボカロシーンに所属する第四層、そして透明化するムラの外様の第五層です。
まず、ボカロシーンを村と形容したのは、ボカロシーンはドメスティックな「閉じた」世界だからです。外部からの流入はあれど、ボカロシーン内の流行は外部への流出はなく、内部で消費と拡張を経てガラパゴス的に変容します。ここで、本当は各階層に特徴的な作品傾向、各階層まで登るためのノウハウなんかもまとめて説明してボカロシーン村のカーストと構造を暴くのがボカコレ村論なのですが、ここでは祈りと冷笑の文脈を理解するために必要な概要だけに触れます。
ボカコレ村の五層の区分はこの通り。
ボカコレ村の外との結節点にして、グローバルへ開かれた「ボカロらしさ」の先駆。第一層。これの区分は簡単です。ボカコレ各種ランキング10位以内。ここではもはやボカロシーンの尖りや特異的な進歩全開の作品はごく珍しくなり、J-POPの様式とボカロシーンの特異性が融和した次世代音楽が台頭します。つまり大衆シーンの実用に耐えうるまで、ボカロシーンの土壌にて行われた実験性が洗練された段階といえます。ここは実はボカコレ村の外です。ドメスティックさに縛られず、外への解放がやっと許される場所だからですね。そのことについて、「売れたボカロPにはグランドラインへの橋が架かる」と形容したのは見事の一言に尽きます。
ボカコレ村論で提示した全五層のうち、2-4層についてはボカコレ村の中、つまりその中で文化や意識や試みが対流して熟成される層です。同時に、ボカロシーンというコミュニティ内にいることも示唆しています。概ね、ボカコレランキング10位以下から、Niconicoのインプレッション数値にして「いいね20以上、またはマイリスト10以上」が下限の基準だと思います。勿論色々と考察の余地や定義の余地はありますが、少なくともボカロシーンというドメスティックなコミュニティの中で一定の人脈と繋がりがある、またはそれだけの人を惹きつけられるだけの作品強度が伴っているならば、ボカコレ村の中にいると考えて良いと思います。
ならば最下層はというと、ここがボカコレ村の外です。透明化された層として、俗に言う「埋もれた」の範疇内です。
先述の第四層の下底の更に下、つまりボカコレ村において殆ど見向きもされずに透明化された作品や活動者の群れがあるのです。この層は、作品のクオリティ、活動強度、新奇性のどれか一点に致命的な欠落があることで陥る場所と定義しています。ことルーキーは、そのうち活動強度……つまり日頃の活動で培える繋がりや、投稿頻度による周知の能力が全く無から始まるため、まずここに欠落を抱えることとなるのです。そこを補わない限り、第五層──ボカコレ村の外縁という沼地から抜け出すことは出来ません。ここにこそ、「社会構造の固定化」という、現代社会同様の構造を抱えています。逆転不能な、硬直化した、先天的な定義づけをされてしまった残酷な勝ち負けの生産装置として、ボカコレは今もなお置かれているのです。それへの対抗力や下克上として、一時的に活動強度の欠落の補完を行える行為が、ボカコレにおける自薦活動でした。
ボカコレ村論は、ムラを観念することで、翻ってこのムラの外たる部分にスポットライトを当てることを第一理念として掲げた論考です。なのでここが肝であり、これからの祈りと冷笑の文脈にも大いに影響します。
ボカコレの作品数の肥大化と、絶え間ないルーキーの流入により、この第五層は拡張の一途を辿っています。この沼地へのアプローチや救済措置を、ユーザーなり運営なりが講じなければ、そこからじわじわ腐り出すのではないかという話です。ざっくり、ボカコレ村論についてはこれだけ押さえておけば後の祈り論考についても補えると思います。
6:これまでのボカコレと自薦の関係を概観して。社会構造の固定化への抵抗について
ここまでの話を辿れば薄々お気づきになっていると思いますが、ボカコレも多分、「既得権益」の性質があって、若年層を主たる要素として展開するボカロシーンで冷笑がブームになるのは、必然だったと思います。決して登竜門ではないと、そういうボカコレの欺瞞を感じた層がいた。特に2023年春ボカコレに至るまで、TOP100は一定の活動者だけが立てるステージでした。活動量と質の差であるといえばそれまでですが、少なくともこの時点で登竜門や発掘の機会であるということは既に欺瞞となっていて、またそこでの数値すらその祭きりで消費されるものに成り果てていたのですね。そこで得た知名度が、必ずしも蓄積して地盤となるとは限らなかった。のし上がりの為の土台としての意義すら、怪しかったわけです。祭のやぐらで高くなったと思った視界は、やはり祭の終わりに解体されるやぐらの運命よろしく、ボカコレ後には夢想と消えたのでした。
活動量やその駆け出しの時期は、まさしく先天的なものとしかいいようがない。若い世代は必然的に土壌固め0でボカコレに放り出されます。機材や音源などの質の向上も、金銭に大きく左右され、学生層で大半が構成されるボカコレではこれもまた先天的と言わざるを得ない。冷笑の背景の固定化、既得権益の前提と合致します。
まして「良作ですら埋もれる」「数字と質は一致しない」という生ぬるい慰め文句で収められる訳です。ボカコレのランキングや数値に憤慨した人、いますよね? つまりクオリティにおける技術向上の努力すら、虚しいものになってしまったのです。これがボカコレ最大の罪とも言えます。
構造の固定化に加えて、努力論すら焼け野にしてしまったボカコレ。ならばこの場で何が有効な努力足り得るのか? ……まぁ、有効な努力ってヤツがかなり都合のいい観念ではあるんですが、強いていえばこれが「自薦」であったんだと思います。だから私、自薦もちょっと構造的には頷くしかないんですね。例えば、同じランキングや序列がつくとしても、オーディションなどであればまた違いますね。あれらは言い逃れなく、クオリティの向上以外に術がない。他方、ボカコレは一貫してユーザーのアクセスが駆動原理でした。つまり社会構造や潮流とガッチリ繋がっている。だから、有効な努力が異なるし、そこに自薦活動が含まれるのは必然的だった。アクセスを直接的に得る手段が、RPや広告活動に依っていくのは当たり前なのです。電車の中の過剰な量の広告と同じように、もはや飽和しきった売り手たちの中でも、必死にアピールをするしかないんです。だって、いい製品であれば売れるかと言えば違うでしょう? 要は「目に留まったものが売れる」のですから。
だから、自薦が確かに向上心や承認欲求の結果という点にはあまり異存はないわけですが、少なくともそれがすべてというほど単純な話ではないと思うのですね。クオリティ、活動実績といったところでだけ真っ直ぐ勝負したかった人もいるはずです。それでも、必要に駆られての自薦行為が必要だった。但し、何かボカコレのシステムや駆動原理が違えば、もしかしたら有意に自薦は減ったか? といわれれば、それは断言は出来ません。だから、ボカコレの形態と自薦活動の結び付きや相互影響については、あまりしっかりとした根拠はないです。
しかし自薦というものが、確かに不平等に身を浸して攻撃に当てられる冷笑とはやや質の違うものであることは留意すべきだと思います。自薦も、およそ努力論の一種として見られるんじゃないかと。むしろそれらは、下克上の手段ですらあったのです、これについては、前章ボカコレ村論も参照のこと。逆に、ボカコレの自薦反対派のうちには、努力論のマッチョイズムが根付いている気がしないでもないんですね。つまり「努力は報われる」「潔い手段でこそ真である」「良いものであれば売れる」(某ラーメンハゲに言わせれば、ナイーブな考え方と呼べるかもしれません)という、ある種の潔癖な努力の業が理論構成に含まれることがある。これもこれで考えもので、それに耐えうる強靭さが求められる。
どのみち形は違えども、固定化された社会構造への努力論的な抵抗がボカコレにはずっと根付いてきたと思います(し、後述の祈りの
文脈は、まさしく固定化された社会構造への抵抗と転換なのです)。それでも、私は確かに催しの趣旨に逸れるという理由には首肯しつつも、自薦のいち類型へ事実上の禁止を突きつけたボカコレ運営の行動は、ある種の可能性の芽を根こそぎ焼き払ったようにみえます。
7:2025ボカコレ冬の欺瞞と幻想
2025年ボカコレ冬は、ランキングの目まぐるしい流動が特徴的でした。これだけは幸いだったなと思います。つまり、長らく固定化された構造の再現であったボカコレランキングが、遂に柔軟性を獲得したんですね。参加者の層が一年前と変わった、というのもあるかもしれませんが、これが大きかった。一時的に、構造固定の現実が取り払われ、誰もに希望がある(ようにみえた)擬似的ユートピアが実現したからこそ、またそこに一定の納得感があったからこそ、不満感がなかった。つまり、一定社会構造の呪いから解かれたことで、期せずして自薦などの下克上手段が不要になった(風に見えた)ことに意義があります。
でも、これはおそらく偶発的ですし、再現性はないと思います。この構造がなぜ打破できたかの分析と裏付けがない以上、次もそうだとは限らない。相互リターン付自薦という下克上手段はもがれたままで、また閉塞感に満ちた(風に思える)ボカコレになったとすれば何が起こるか、ちょっと考えてみましょう。
なんだかんだ、今も大多数は閉塞感を覚えていると思います。特にルーキーの新規層。ボカコレ村論で述べたことに繋がりますが、毎時ランキングというお立ち台の流動は、飽くまでボカコレシーンの「比較的上層」の出来事です。むしろ、そこにも乗れない日陰の裾野は、投稿数から見ても拡大の一途です。そこへの救済は? 肥大化するボカコレの作品数と、底の方で見つかりもせずに埋もれることへの対策は? 有効な努力や手段は?
およそ、この層には何かもっと強烈なアプローチがない限りは、何の光もない。事実、今回のボカコレのランキングは私の同期……概ね1-2年間の積み上げをしてきた人が主でした。
つまり、何らかの網やシステムに幸運にも拾い上げられた人たちなんですよ。私含めて持つ側、更にはボカコレ村の人間たちです。これって、社会構造の固定化ですよね。持たないものに厳しく、一定の努力の筋も閉ざされた今、明るいと思われた直近ボカコレにはとんでもなくどす黒い影が落ちている。私たちを照らしている光は、村の下までは届いていません。
さぁここで戻ってきました。光と祈りの凋落。
ボカコレはこれから、何ら追加の救済手段やフックアップを講じない限り、またユーザー主体でのフックアップが機能しなかった場合、縮小の一途をたどるのだと思います。冷笑の果てには無気力、ボカコレに根付く努力論的な意欲の焼失です。自薦努力という最後のボカコレドリームが縮小化したのが今として、少なくとも今回は擬似的であれ夢を見られました。つまり、実際的な効用はともかくとして、自薦をすればランクインも出来ていたという僅かばかりのケースが、宝くじ的な夢を魅せていて、それを頼りにまだルーキーの積極的な活動があったのです。もし次の夏にその幻想が完全に剥がれたとして、果たしてボカコレは祭りという体裁でどれだけ体面と求心力を保てるでしょうか。
もうルーキーにとって投稿する魅力はないのかも知れません。
8:祈りと冷笑の対比。異なる価値基準を目指して
無力感、そしてボカコレの数字という価値尺度の硬直性についてここまで触れてきました。こうしたボカコレへの冷笑が、ボカコレそのものへの、ひいてはボカロシーンへの不信と離別であるならば、これに対置する祈りと光は何者であるか。
ひとつの解を、合成音声のゆくえが出しています。
つまり、新たな価値尺度の創造です。ボカコレとは異なる「良さ」のフックアップを理念に掲げるゆくえレコーズは、まさに今のボカロシーンにおける祈りと光を象徴している。
祈りと光は、既存の領域と異なる新世界をこじんまりと生み出すことが特徴です。社会という広範さからの反動ですね。もっとも、ゆくえレコーズはコミュニティの垣根を越えた拡張までを標榜しているので、祈りの文脈には「やや半身浸っている」くらいのものだと思います。ここ要検討事項。
冷笑が、社会構造の固定化に軸足を置き、同時に理論武装に寄与している。その対置にある祈りは、私的領域といった身内__私にいわせれば「村」の中に価値を見出しています。まるで既存社会や構造から抜けようともがくように、よりドメスティックに深く潜っていくのです。まるで自治区ですね。異なる駆動原理や価値基準を備えた、新たなフィールドに身を置くのです。
ただし、飽くまで祈りはカウンターカルチャー、どこまでいっても冷笑と対置されるからこそであるため、ある意味では冷笑や社会から自由になっていないんです。おそらく無力感の点でルーツを共有するからです。
だから、祈りって実は冷笑と一部見解の一致するところがあります。アプローチが違うに過ぎないのです。ボカコレへの不信、特にボカコレがもはや登竜門ではないことについては冷笑姿勢と同質なのではないかと。その不信の上で見切りをつけて、祈りはもっと小さな価値へ転換を図ったに過ぎないのです。
祈りも冷笑も、やはりバックグラウンドは社会構造の固定化や無力感であります。ここから萌芽しつつ、両者は「解決法」が違うに過ぎない。本質的には同じものです。
冷笑は、無力感の方をなんとかしようというものでした。つまり、翻っては社会構造の固定化の方をこそどうにもならないと諦念しているんですね。冷笑の根本として、権力や社会構造は不変だから、その中でより下流に位置する者への攻撃へ転化し、絶えず加害:被害関係を再生産して、その過程で己の力や立場の優位を確認しているのが冷笑です。外向的な攻撃が伴います。冷笑は無力感を紛らわして安心を得る営みなんですね。だからマウンティングやレッテル貼りで、常に他人を一義的な価値尺度の中で劣等の方へ貶めることで、相対的な無力を緩和するんです。これが冷笑です。
じゃあ祈りはというと、これがアプローチの異なることで、無力感の方に諦念がある。権力勾配、加害:被害関係の逆転を図った冷笑に対して、祈りはもはや自身が被害側であることについてを受容してしまった。そこからすべてが始まります。その消極さ、大袈裟にいえば内向的な攻撃が行われています。最大の特徴は、加害:被害関係の再生産を、祈りは行おうとしないことです。そして、社会構造の固定化に、少なくともその手の届く範囲内で抵抗しようとしたことにあります。この理念こそが、まさにゆくえレコードにも通底するものです。
ところで、価値や優劣の再構築をした祈りですが、「新たな価値創造を行い固定化に抗うこと」と、「それはそれとして自分はつくづく権力勾配において下位に身を置くこと」は矛盾しないんですよね。だから、祈りをするとき、つくづくそのムラの中でさえ自身の価値を最低位として扱いがちです。それより、滅私の上で周りを満たす破滅性が散見されたり。
ここまでをまとめます。
祈りも冷笑も、無力感と社会構造の固定化が基礎です。祈りはそのうち無力感を諦め、冷笑は社会構造の固定化を諦めました。その末に、加害:被害関係の再生産の有無、攻撃性の指向性の対照など、二つは対置されるカウンターカルチャーとして成り立っています。滅私とマウンティングという、何を犠牲にし、何を下と置こうとするかの性質でも対照ですね。冷笑は断絶、祈りは結合を主として活動していることもまた対照です。
【対照表化したものがこちら】
祈り ──────── 冷笑
諦念事項
無力感 ── 社会構造の固定化
被害:加害関係の再生産
有 ── 無
攻撃対象
内向、滅私の精神 ── マウント性、外向
ただ、冷笑についてはマウンティングによる孤立と断絶を指向しつつ、その実「社会」という大集団、言うなれば世界マッチングの領域を前提としている点である意味グローバルな結合の上にあります。反面、新たな価値創造と身内のムラでの生存をする祈りは、ムラ故にグローバルからの断絶の上にあります。結局、祈りも冷笑もベースとなる世界が同じなので、構成要素そのものは対置されることはあれど完全に異質なもの同時ということはない。むしろ、双方は密接に文脈を共有しているわけですね。直線上の観念のうち、右か左か、という風に通じているに過ぎません。
補足:呪いと祈りは同じだって気付いた
ここで一作品、補助線を引きます。
呪いと祈りの同一性について。
呪いと祈りが同じだって気付いた
呪いと祈りについての論考はまた別で拵えます。が、軽く触れておくと、ここの対置や表裏性についてはちょっと語るべき領域を異にしていますので追々。
飽くまでここでは、イデオロギー的に対置できるものを論じています。そこで祈りに相対するものが冷笑であることを、ここまで論じてきました。
他方で、実際的な表現や実践の領域になると、もはや祈りと冷笑の対比においては表裏であることを飛び越えて「対立関係」になります。人を案じ願う祈りと、人を嘲笑し貶める冷笑は、イデオロギーの差異の結果、相容れない性質を持つからです。一方、祈りと呪いは同じカテゴライズが出来ます。図式で説明します。頑張ります。
イデオロギー的なところでは、祈りと冷笑で対置する。これを横軸と捉えます。現状に対するアプローチの方向で相反します。
他方、イデオロギーの実践に際して出て来た物事のうち、表裏の性質の違いを縦軸……これを祈りと呪いで対置します。
例えば、冷笑と祈りのイデオロギーによって異なる手法を挙げれば、ボカコレのランキングに対する姿勢としての表出です。この両者のスタンスの違いは具体化すれば一目瞭然ですが、切り取り方次第ではどちらにも積極的な側面と消極的な側面があるのです。
「ボカコレのランキングは硬直化しているが(社会構造の固定化の前提)、あの作品はバズりを狙った卑怯な手段でランクインしているため意味は無く下等なものである(レッテル張りによる無力感の相対的克服)」という一連の言動。これは冷笑のイデオロギーに即しています。
冷笑のイデオロギーについては、他者の手法にレッテルを張り非難することで相手の没落を将来的に叶えようとする祈りが含まれる反面、元々はそうしたレッテル張りをしなければ既存の価値観では敗北していることを暗に肯定している呪いの側面を持ちます。端的には、「あなたは幸福にはなれない」との冷笑の形式も、将来的な不幸を祈る一方で、過去や現在の相手の優越を呪う営みであります。
他方、「ボカコレのランキングには乗れないため、(無力感の前提)、せめて様々な作品を楽しむ祭としての意義を重要視しよう(社会構造による価値観の転覆による克服)」という一連の言動。これは祈りのイデオロギーに即しています。
祈りのイデオロギーについては、作品を楽しむという積極的な姿勢で意味を灯そうとする祈りの反面で、元々意味などはないことを逆説的に肯定してしまう呪いの側面を持ちます。端的には「あなたが幸せでありますように」との祈りの形式も、将来的な幸を祈る一方で、過去や現在の不幸を呪う営みであります。
呪いは、言うなれば呪縛です。相手を一度、呪いによってその状態に縛り付け、定義付けをなければならない営みとなります。だから、自分から見た過去や消極性(不都合さ)を相手に観念づけることになります。反面、祈りは希求であり、自分から見て将来や積極性(好都合さ)を相手に観念づけることになります。
八月無限日における祈りの一節は、恐らく「待って、置いていかないで」だと思います。イデオロギー的な祈りの中に、ここで祈りと呪いの側面を見出すならば、祈りは即ち自身にとって将来的にその誰かを引き留めていたいこと、自分にとって好都合の未来を繋ぎ止めたいということの読み解きが出来ます。反面、今に軸足を置くならば、去り行く誰かの面影という不都合が浮かび上がります。また、仮に自身にとっての好都合を相手に重ね合わせたとき(つまり相手が去り行くこと、その別離すら祝福するとなると)、去り行く誰かの面影を是としながらも、それを引き留める「待って」の言葉が呪いとしてその人に降り掛かることとなるでしょう。どうあれ、誰かを進んで解放しようというイデオロギーが祈りなのだとすれば、必然的に誰かが置いていかれたり囚われたりする、という代替性が見られるのです。
もう一作品取り上げて、呪いと祈りの操作についてを実践します。ここまで来るともう作品批評というか、構造分析とかと同じですね。
Oh…… Suki Suki Daisuki BIG LOVE……
失礼しました。
そうやって消した目をまだ覚えている
後悔というモチーフもまた、ボカロ祈り文脈では非常に良く取り上げられるもので、言うなれば内向きで、後ろ向き。この歌詞もまた抽象的ながら、祈りのイデオロギー的じゃないかと。どっちかというと、固定化の克服というよりは無力感の方をフィーチャーしています。諦念された方に目を向ける、裏返った祈りのイデオロギーですね。
少し補助的に言葉を付すと、「消した目」の持つ特別性や思い入れ、それを後ろ髪を引くような過去の残滓として「まだ覚えている」ということになります。過去は消極と結びつくので、つまり祈りの中の呪いとして根付くものの示唆であります。それを将来へ昇華させる祈りの側面を照らせば、一見としてそうした過去の後悔との決別を意味するように誤読しがちですが、しかし後悔は祈りのイデオロギーにおいて「無力感」と結びつくため、ここの超克は目標としては不適切です。多分みんな、祈りを標榜して歌詞を書いている人は、端からそうした後悔の過去をなきものとして葬り去ることを是とはしていないと思います。多分。
よって、この一節の表立った側面が祈りの中にある呪いとして、その裏面で将来を見据えたときには、飽くまで後悔の記憶たる「消した目を覚えながら」紡ぐものがあるのだと考察します。過去から今までの消した目(何かの表情の比喩であり、それと向き合えなかったことを消したという言葉に変形したもの。と仮定します)という象徴が呪いであるとして、将来に向けての祈りはやはりその目を消さないように向き合うこと──何らか感情と向き合いたいを希求する祈りが含まれているのではないかと思います。単なるオタク語りです。
で。
いつか空が消えたら いつか光が絶えたら
受け入れてあなたと泣きたいのです
そして思い出し、笑いたいのです
ここに繋がるってワケよ。
失礼しました。
やはり空が消え、光が絶えるということへの無力感と、そのものの受容はここからも推察できます。
~したい、という希求のフレーズもまた祈りの文脈の大きな特徴であるわけで、それを連続で述べるこの部分はとりわけ祈りであると思います。何しろ、泣くこと、笑うことが将来的な積極性の位置に据えられているものでして、そうでありたいと祈っているからです。この祈りの中に含まれる呪いを導き出すとなると、過去を振り返ればこそそうした感情の発露に向き合えなかったという後悔と通じるのではないでしょうか。
だから、コスモサーバーの一節と、ニアクエーサーの一節は、この祈り/冷笑のイデオロギー分類と、それに付随する表裏の分解技法たる祈り/呪いの四象限操作を使えば、それぞれ独立した分析と考察から同じようなテーマと経緯が導き出せます。本章では、その確認をしたに過ぎません(し、ぶっちゃけ間違ってることも全然あります。正解を当てることより、新規読解の提示に努めました)。
この、ニアクエーサーのセルフライナーノーツに収められている補遺には祈りがてんこ盛りに敷き詰められているので、是非とも読んでみてください。相対的な、人との結合を願う一方、根本的には別々のものとして分断されていることを認識した上で嘆いているような記述がたくさんあり、これはまさしくムラ的なコミュニティの中で新たな価値による結合をしつつもコミュニティ化という分断を内包する祈りのイデオロギーそのものだからです。相互作用、人と人の連携や相補性を求める祈りの本質が、そこにはあります。人に向かうものに先立ち、人からすごく多くを豊かに受け取っているなと、そういう感じの。言葉が。難しい。
長々したので、これで一旦この章は筆を置きます。とにかくとして、祈り/冷笑というイデオロギーの横軸、祈り/呪いという切り抜き方や指向性の縦軸の四象限があるという話でした。最後にそれらをざっくりまとめた図解を置いておきます。
9:祈りの逆相化、イデオロギーの反転
さて、この相反する冷笑と祈りからも薄々お察しの通り、バックグラウンドを共有している以上、両者はしがらみあっていくことになります。つまり、社会構造がこうである限りは片方の殲滅はあり得ないわけで、必ず揺り返しを経て世の中は移ろっていくでしょう。
ただし、ボカロはややその先を見ている気がするんですね。実のところ、先ほどからサブテーマとしてしばしば用いられてきたキーワードは、「努力論」でした。冷笑も祈りも、一種の努力の営みです。社会の固定化が顕在化する前から、姿形を変えた努力です。だから、冷笑は時に無気力と呼ばれますが、全然そんなことはない。むしろ、絶え間ない闘争努力なのです。
かつてのバブルでは努力は立身出世。つまり、地位や権力まで変化させられる、絶対的な立ち位置を変えられる手段でした。自分のスコアそのものが伸ばせた感じ。
そこから世に冷笑が蔓延してもなお、マウンティングや価値創造という風な努力方法においては、まだ相対的な立ち位置を変えられる手段としてなら有効だったわけです。自分のスコアはそのままに、集計方法を変えたり他の人のスコアを目減りさせたりしてランキングを上下する感じ。
ボカコレでも、一定そうした努力が生き延びていました。自薦行為は、歪ながらも絶対的な立ち位置の移動手段として。またはゆくえレコード初の企画は相対的な立ち位置の移動手段として。はたまた冷笑により楽曲構成や流行で論理武装したマウンティングによって。ここで自薦が規制されて絶対的な立ち位置の移動手段がほぼ潰える(≒薄く生き残っていた立身出世の時代の終焉)となると、残るはいよいよ本当に冷笑と祈りの時代です。人々はいよいよ、新たな価値基準を誂えるか、残ったボカコレの裾野でマウンティングに勤しむかという形になるのです。運営主体とユーザー主体の乖離が始まります。
ところが、片方の価値基準が機能不全に陥り信頼性が失墜したとき、そのカウンターとして展開されてきたもう片方も機能不全となります。ボカコレの価値失墜の次に真に権威と化すのはゆくえレコードで、そうなれば運営主体の思惑から外れて、祈りによる滅私とムラ性は途端に崩落することになります。元より、ゆくえレコーズは垣根を越えた拡張までを標榜しているので、ある意味権威的になるのは仕方ないような気もします。元より上下なく横並びでやっていくというのはムラ的な思想なのであって、主催の駱駝法師さんもそうした権威性ではないものを目指したかったそうですが、しかしコミュニティを横断的に拡大するという時点でもはや権威性と密接に結び付かざるを得ないのです。ボカコレ村論で言えば、もはやゆくえレコーズはボカコレ村を越えた第一層に身を置こうとしている状態です。なんたる矛盾。よって、ゆくえレコーズが権威性から離れるには、その規模感を縮小する──飽くまでボカコレ村の中での駆動に終始した小規模活動に落ち着くしかないと思います(し、きっと今更そうした方向転換はゆくえレコーズの一存では出来ないと思います)。
つまり、祈りが権力側に周り、その上下勾配のうち上に位置しながら新たな加害:被害関係の再生産を与える駆動部となるのです。当然、ムラ性は壊滅し、奇しくもヒエラルキーの上に構えることとなります。非権力を標榜し、下を是とし、構造再生産に抗った祈りが逆転した性質を帯び始めるのです。果てには社会構造の固定化から脱したはずの理念たちが、新たな社会構造を規定する新秩序となるわけで、無力感を受け入れたはずなのにいつの間にか権威となる。そんな全ての要素における逆転が起こってしまうのです。全ての理念があべこべとなって現れる、そうした逆相性については先んじて一義的な価値基準の章で触れています。
祈りの目指した新たな価値による克服は、祈りのイデオロギーの目指した闘争からの逃走と結合とはまるで逆、むしろ新たな価値による序列をつけマウンティングを行い分断を促進する行為に他ならない。そういう、「イデオロギーが崩落した末に起こる基本理念の逆相化」が、またしても発生してしまったわけです。祈っていたつもりが、冷笑を加速させることになる。
故に、祈りの次に来るのは冷笑です。
次は冷笑がカウンターカルチャーとして現れ始めます。恐らくこれが、近年の音楽性からの反動(過剰な音数、また綺麗で透明感のある音の本格的なコモディティ化)や世界的な流行との結び付き(特にK-POPやJ-POP内でのヒップホップの認知浸透)も加味するとなると、およそヒップホップと複合した文化性と精神を伴って台頭してくることになると思います。いや、これもまた、ヒップホップの「ミミック化」と言ってもいいかもしれません。ヒップホップが内包する反体制的思想、立身と自己効力感、Do it(つべこべ言わずやれ)の精神、小さな仲間意識(うちとよその関係)などの肝要な部分は根こそぎ空洞化し、その痛烈なディスや雰囲気という外見だけを纏った冷笑の中身を持つヒップホップもどきが、今後台頭するのだと予測します。冷笑とはまるで相反する精神と理念を持つヒップホップのイデオロギーも、また同じように逆相化してしまうのです。
冒頭に祈りと光の凋落において述べたのは、つまり今反体制として展開され草の根を標榜してきた祈りの文脈が、今度は体制として現れるようになることを意味しています。
そして、ボカコレという体制が徐々に凋落していく事も。それには、やはり自薦行為の規制にひとつ着火剤があるように思います。登竜門として掲げられた催事も、その実態が乖離していることが明らかとなりましたし、今まで下克上に際して一縷の希望であった行為も規制され、本格的に参加意義と恩恵に疑問符が付されてしまったことですね。だからこそ、先述のボカコレ言及にて、焼け野と評したのです。こうして、少なくともアマチュアボカロシーンにおいては、祈りの時代がいつまで持つかは完全に未知となりつつあります。或いは、もう衰退が始まっているのかもしれませんね。
終わりに:ポスト祈りのすすめと、ネット原風景世代
最後に。ポスト祈りのすすめと題して、ネットネイティブ世代との関連を提示して終わります。
私が、非ネットネイティブ最終世代ですので、やや思うところがあり。
祈りと冷笑は、どちらも一定の努力が通底し、また結合と分断を抱えたイデオロギーでした。しかし、これはまだネットの力学の駆動していない社会を原風景に持つから取り持たれている精神性なのではないかと思います。
まず、努力というものの有効性を、インターネットのアルゴリズムに支配された世界を原風景に持つものが信じられるのでしょうか? SNSには当然に冷笑で満ちていて、社会構造の固定化に立脚した思想で満ちています。それを幼少期から価値観の核に内包した世代が、どれだけ努力というものに意味を見出せるかについて、私は余りよい希望が見えないのです。また、努力にもコストパフォーマンスや効率性が一層強く唱えられ、そこにも機械のアルゴリズムが干渉する時代です。言うなれば、この後の世代を行くものたちの道は既に善意で歩きやすいように舗装されていて、必要程度の努力と労力でエスカレータ式に進んでいけるのではないでしょうか。それは、反面で道なき道という規格外を根絶やしにする行為でもあり、まさしく冷笑的な、構造の再生産に寄与しているように見えます。なにより、YouTubeやSNSなどの拡散は、紛う事なきアルゴリズムの采配です。殆どそれは天運とも言えるもので、またアルゴリズムの振り向きやすい傾向というのは、少なからず「恣意的に」決められています。その傾向へと画一化するように、仕向けられているように思えます。杞憂であってくれ。
つまるところ、もはや冷笑や祈りの内包していた努力的側面すら持たない層が、これから現れるのではないか? という問題提起です。故にポスト祈りであり、もはや定められた社会構造に囚われ、為す術のないことに甘んじる、真の無気力観念が現れるように思うのです。祈れも笑えもしない、虚無の時代が訪れます。
また、結合か分断を主として希求してきた反面で、もう片方を背景的な構造に抱えることとなった二つのイデオロギーですが、これらもまた変容を迎えます。
元より、ボーカロイド文化は人と人の結合と分断──「分かり合えるという理想」と「分かり合えなかった現実」の狭間で揺れる文化なのではないかと思います。が、この辺についてはめちゃくちゃいい記事がここにあるので、そこに全て譲るとして……(先行言説をきっちり出典を付したり引用したり、その上で述べられているガチガチの論考です。こっちの方を是非とも読んでください。)
ギリギリで現実に意識の本拠を置く私たち、非ネットネイティブ世代は、まだ現実の質感やネットが夢見た接続の理想を諦めていません。多分。
世界をネットで繋いで、大きな市場やプラットフォームとなって、そして手を取り合い理解していく。そんな、点と点を大規模に繋ぎ力を合わせる、人と人は分かり合えるという夢を見たグローバリズムを、私たちは知っています。それこそ結合の観念であり、誰かの気持ちを推し量り、それらへの理解や共感をすることについて、まだ諦めてはいないのです。そうした人のことを分かりたい、心と心で通じたい、という祈りの傍らで、やはり人は分かり合えないという分断も露見しました。国と国、その中の文化の違い、理解の違い、スタンスの違い、政治の違い。決して相容れないものがあることと、それによる決別と拒絶。そうした分断もまた、祈りの傍らで進んできました。
他方で、祈りの行く先は「人と人は完全に分かり合えないし、全て理解し切れない」という、根本的には人と人は例え隣人や親友や家族や恋人であれど別物であり、心と心が完全に融合するようには触れ合えないという分断ありきなことを眼差すことになります。冷笑にしても、結局は逃れようのない社会の価値基準とは、全世界を包括した比較により成り立つものであって、即ちどれだけ勝ち負けを競い孤独に進もうとしても、決して他人の存在との相対からは逃れられないという結合を直視することになります。
ネットの内外を眼差したからこそ、そのどちらをも理解しており、冷笑も祈りも等しく素養を持つのがギリギリで今の現役世代なのだと考えます。では、ネットの内に意識の本拠を置いたネットネイティブ世代は何を見ているのでしょうか。
やはりSNSは冷笑に溢れていて、基本は分断が目立ちます。男女、収入、容姿、頭脳、育ち等々のさまざまなドメインで優劣と勝敗を競う現代ですが、しかし全てのドメインで勝てるものなどはそういません。必ず何処かで、敗北のレッテルと向き合うことになります。誰もがそれぞれ分断と孤独を選びながら、全員が敗北者精神を持つことになる地獄の時代です。そこで負けていてもいいのだ、と新たな価値に転向する祈り手が現れるかどうかも未知ですが、一億総劣等時代の渦中にあるネットネイティブは、従来よりもより濃厚な孤独と絶望感の中にあることは想像に難くありません。縋れるような希望論は、等しく死に絶えた時代であるからです。もうドラえもんの技術が便利な時代の夢を見せてくれないように。
そして何より、もはやこの世代は人との心の結合をさして必要としていないのではないかとの疑問があります。人と人の煩わしさを伴わない、無機質な機械との対話が到来しています。Siri、Geminiなどの音声認識はその最たる例ですし、AIも相まってこの辺は興隆を極めています。過酷なマウンティングと闘争により、相容れないことと分断を加速させる冷笑からの反動で、最後には一人だけで完結する閉じた世界への回帰に落ち着いてしまうのではないでしょうか。もはや人の心や可能性を信じられず、分断だけが台頭し、祈りのような人と人の希求を失った人々の時代が。
これを、私は孤独の時代と呼びたいと思います。何の闘争にも置かれない代わりに、どんな結合をも望まない。より結合を希薄にして、分断を強めた孤独な時代が。死の時代ですよ。
冷笑による傷付け合いや、祈りによる理解しあえなさの肩透かしや。それらに疲れ果てた、ポスト冷笑/ポスト祈りの可能性を持つ世代を前に、どう生きるべきか。
ん~~~~~~そうですねェ……
私たちは、恋でもすべきじゃないですかね
なんなら、ドスケベで対抗するしか……
マジで言ってます。
祈りと冷笑のカウンター性、そして死とドスケベのカウンター性は実に半年前に指摘してました。なんとまぁ。
図式にしてこう。
結合←──比較的どっち志向か──→分断
ドスケベ(性)─祈り─冷笑─(死)ポスト祈り
全てに対する拒絶と分断の末、ポスト祈りは人類の集団自殺に等しい観念になると思います。だから、前の章で少子高齢化って割と祈りだよねって述べたんですね。構造の再生産を食い止めようとして、敢えて関係性を結ばないということを指向すると、祈りや冷笑、ひいてはポスト祈りになるわけで。
じゃあ強烈な分断のポスト祈りに対してのカウンターとなるのは何か。そう、融合せんとするくらいの恋慕、即ちドスケベですね。あの、本当にマジで言ってます。
元はDECO*27のラビットホールに代表されるドスケベムーブメントへの抵抗として生み出した言葉が
死はカウンターカルチャー
ドスケベに対抗せよ
であったんですが。
期せずして相補性の観念から、なんとドスケベ側がカウンターカルチャーとしての地位になりました。或いは、DECO*27はこうしたポスト祈りを見据えて、数十手先にコミットメントする一手としてあれらの楽曲を出したのかもしれません。ともすると、心底恐ろしい先見の明だと思います。
こんなこといっちゃ本当にアレですけど、ドスケベって精神も肉体も触れ合わないといけないっていう、究極的には融合を目的としたとんでもない観念じゃないかと。つまり、人の面倒くささや、優劣や、社会階層の差異や、そうした分断の全てを受け入れてそれでも人との繋がりを希求するムーブメント。もはや愛と還元しても良いような気がしますが、そういう流れが必要なのではないかと。祈りからドスケベまで辿り着くには、遂に分断や理解し合えなさという巨大な壁を越えなければならないという大変な課題が浮き彫りになりました。
そこで私が一つ、キーワードを提示します。 それは「融合」です。
A7CAE8 Project収録の拙作『波濤、融』の一節より。
偏執して、変質して、不可分の貴方達になろうね
また、A7CAE8 Projectの精神的後継である作品群、倒錯の夢収録の拙作『心奥の在り方』の一節より。
心の膜をすり抜けて、君の形を全て知りたいよ
実は全て、若干性に纏わる文脈を帯びた曲です。テトさんごめんね。でも融合したいっす、先生。テトさんにくっつきたいッス。
融合なんですね、つまり。表立って私が出しては来なかった文脈ではありますが、要するに相手と溶け合って、その肌の熱から精神の形まで、まったく全てを知っては同一化してしまいたいと願うこの想いこそ、これからポスト祈り時代に必要なのではないでしょうか。融合と結合の末、人との混ざり合いの中からしか生まれないものや育たないものがあるはずです。
祈りでは村的な小規模活動の中で新たな基準による、新たな価値の創造をしてきました。これをドスケベの領域まで根を下ろして、ひととひと、一対一のもはや家庭的な領域にて、何を生み出し、何を取り戻すことになるのでしょう。それはきっと、祈りの歩みの延長として、真に祈り手たちが望んだものであるように思います。奇しくも、この家庭的な領域への回帰は、かつて冷笑の背景としての機能不全の家族に理由を求めたところと対置しています。家庭機能の再生。その根本たる理由にアプローチするよう通じるのも含め、恐らくこの仮説は余り的を外してはいないんじゃないかと信じたいです。
本当に話がでっかく広がりましたが、割ときっちり畳めるくらいの整合性になりましたね。いつもこういうことを、諸領域を見ながら有機的に考えているので、また何処かで執筆しようかと思います。
それでは、よき祈りライフを。

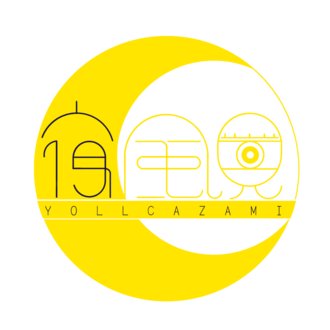
コメント