「気づいた人」が損しない組織文化にしたい
マネージャーをやっていると、嬉しい瞬間がたくさんあります。チームが目標を達成した時、メンバーが成長した姿を見た時…。でも、正直に言うと、同じくらい「うーん…」と考え込んでしまう瞬間や、ちょっと歯がゆい気持ちになる場面も少なくありません。
その一つが、チームの中にいる、「気づいちゃった人」の存在です。
「あ、この資料、前回の数字のままですよ」
「この進め方だと、後工程の〇〇さんが困るかもしれません」
「ログを見るとこのような警告が出ていそうなのですが…」
他の人が見過ごしがちな細かい点や、ちょっとした問題、先回りした気遣い…。そういうことに気づいて、声を上げてくれたり、サッと行動してくれたりするメンバー。チームや組織にとって、本当に、本当にありがたい存在のはずなんです。
ただ、現実はどうでしょうか?
気づけば、その「気づいちゃった人」ばっかりが、追加のタスクを抱え込んでいたり。
良かれと思って指摘したのに、「また面倒なこと言ってるよ…」みたいな、ちょっと冷ややかな空気が流れたり。
誰も見ていないところでチームのために動いてくれても、それが評価に繋がらず、「やって当たり前」みたいになってしまったり。
その結果、本人が「もう言うの、やめようかな…」「見て見ぬふりした方が楽なのかも…」なんて、モチベーションを下げてしまったり、最悪の場合、疲弊して会社を去ってしまうことだってあるかもしれない。
これは、マネージャーとしてとても悔しいし、もったいないことだと思うんですよね。その「気づき」こそが、チームをより良くする種で、大きな問題を防ぐためのセンサーかもしれません。
今回は、そんな「気づく人が損する文化」って、なぜ生まれてしまうのか? そして、どうすればそれを変えて、「気づき」が評価され、行動した人が「やってよかった!」と心から思えるような、「正直者が報われる組織文化」を、本気で作っていけるんだろうか?
というテーマについて、一人のマネージャーとしての悩みや考え、そして「こうしていきたい!」という決意表明のようなものを、皆さんと共有できたらと思っています。
ですので、何か具体的な解決策を提示するというわけではなく、ポエムに近い内容です。
こんな「気づいた人」いませんでしたか?
皆さんのチームにも、きっと顔が思い浮かぶ人がいるはずです。「あぁ、あの人、いつも頑張ってくれてるけど、報われてないかもな…」と。
私がこれまで見てきた中では、このような方がいらっしゃいました。
孤高のシステム守護神
システムの小さなアラートや、将来的なボトルネックになりそうな箇所に、誰よりも早く気づいてくれるエンジニア。彼のおかげで何度、大きな障害を未然に防げたことか…。でも、他のメンバーは日々の開発に追われ、彼の指摘の重要性をなかなか理解できない。チームとして適切なサポート体制を組めていないことに不甲斐なさを感じたり。「もっと良くしたい」が空回り
常に業務改善のアイデアを出してくれる意欲的なメンバー。「このツールを導入すれば効率が上がるはず」「この会議、アジェンダを見直しませんか?」彼の提案は的を射ていることも多い。でも、変化を嫌う一部のベテランメンバーからの抵抗にあったり、導入の手間を考えると「今はやめておこうか…」と判断がなされたり…。見えない気遣いの達人
チームの備品管理、新人のフォロー、会議室の予約…。誰かがやらなきゃいけないけど、誰もやりたがらない「名もなきタスク」を、文句ひとつ言わずに引き受けてくれるメンバー。チームが円滑に回っている部分は間違いなくあるのに、評価面談ではどうしても担当業務の成果が中心になってしまう。
こういう状況を目の当たりにするたび、「なんとかしたい」「彼らがもっと報われるようにしたい」と強く思うのですが、日々の業務に追われたり、組織の壁にぶつかったりして、なかなか抜本的な解決策を実行に移せていないのが、正直なところです。
なぜ「正直者」が割を食ってしまうのか?
この「気づく人が損をする」という、ある種、不条理な状況は、なぜこれほどまでに多くの組織で、根強く存在し続けているのでしょうか? もちろん、個人の性格や相性の問題もあるかもしれませんが、それ以上に、私たちの組織が抱える構造的な要因が大きいと感じています。
変化より安定を求める「事なかれ主義」
新しい提案や問題提起は、現状の安定を揺るがしかねない。現状維持バイアス。「面倒なことに関わりたくない」「今は問題なく動いているんだから、触らないでおこう」という心理が働きやすいのは、ある意味、自然なことなのかもしれません。ただ、その安定は、本当に持続可能なものなのでしょうか?「出る杭は打たれる」同調圧力
周囲と違う意見や行動をとることに、私たちは想像以上に抵抗を感じます。「ここで反対意見を言ったら、和を乱すかな…」「あの人だけ意識高いって思われたくないな…」そんな空気が、自由な発言を躊躇させてしまう。責任の所在が曖昧な「ふんわり」業務
誰が担当するのか明確に決まっていない業務や問題は、どうしても「気づいた人」「声の大きい人」に押し付けられがちです。これは、マネジメントの怠慢と言われても仕方ない部分かもしれません。短期的な成果を追い求めるプレッシャー
四半期や半期ごとの目標達成、目の前のタスクリストの消化…。短期的な成果が重視される環境では、時間のかかる根本的な問題解決や、すぐに効果が見えない改善活動は、どうしても優先順位が下がってしまいます。
これらの要因が複雑に絡み合い、「気づいても言わない」「気づいても行動しない」ことが、個人にとっては(短期的には)合理的な選択、いわば「処世術」のようになってしまっている。この構造そのものにメスを入れない限り、個人の意識改革だけでは限界がある、というのが私の実感です。
「気づき」が失われたら?
もし、この「気づく人が損する文化」を放置し続けたら?
チーム、そして組織全体が、静かに、しかし確実に、活力を失っていく未来が待っているかもしれません。
問題が「時限爆弾」化
メンバーの「あれ?」という気づきは、その時限爆弾を発見する貴重なセンサーです。そのセンサーが機能不全に陥ったら…いつ爆発してもおかしくない状態を放置することになります。組織が「ゆでガエル」状態
外部環境の変化や内部の問題点に対する「気づき」が共有されず、改善や革新が生まれなくなったら、組織はゆっくりと、しかし確実に競争力を失っていきます。気づいた時には、もう手遅れ…まさに「ゆでガエル」状態です。不信感がチームを蝕む
「頑張っても報われない」「正直者は馬鹿を見る」…そんな不公平感が蔓延すれば、メンバー間の信頼関係は崩れ、チームの一体感は失われます。表面的には問題なく見えても、水面下ではモチベーションが著しく低下していってしまう。未来を担う人材が流出する
問題意識が高く、主体的に行動できる、変化を起こせる人材ほど、この「損する文化」に強い嫌悪感を抱くでしょう。「この組織では成長できない」「自分の力が活かせない」と感じた彼らは、より良い環境を求めて、静かに去っていくでしょう。そして、残るのは…。
こうならないよう、私たちは本気でこの文化と向き合い、変えていく必要があると思います。
「言い出しっぺ損」ループから抜け出すためのアイデア
具体的にどうすれば、この根深いループから抜け出せるんでしょうか?
これは組織によって一概に言えないため、これが正解というわけではありませんが、これまでの経験も元にして考えてみました。
大切なのは、皆さんの会社の文化や状況、メンバーの顔ぶれを思い浮かべながら、「自分たちのチームなら、この要素を取り入れられるかも?」「これをヒントに、別のアイデアが生まれた!」といった感じで、自社に合った形を模索していただくことだと考えています。そのための、ちょっとした刺激になれば嬉しいです。
気づきポイント制度
提案や問題提起、他のメンバーへのナイスなサポートなどをしたら少額のお礼がもらえる。もしくは、それらのサポートが貯まれば特別休暇やスキルアップ支援、チームで使える備品購入などに交換できたら楽しくなるかもしれません。アイデア供養の場の設定
残念ながら実行に至らなかったアイデアや指摘も、決して無駄ではありません。きちんと記録・共有し、社内勉強会など「供養」する場を設けることで、「あの時の議論があったから、今があるね」と後から価値が見える化されることも。特に素晴らしい発想は「殿堂入り」として称え、「言ったことが無駄にならない」文化を育むのはどうでしょう。評価制度で工面
提案や問題提起、他のメンバーへのナイスなサポートなどを評価制度に組み込む。難しいかもしれないが、会社によってはミッション・ビジョン・バリューやクレドに値する行動をしたら評価するということもある。評価時にこれまでの気づきや取り組みをプロセス含めてマネージャーに報告してみる。提案実現サポートチームの用意
いい提案が出ても、「言い出しっぺ=実行者」になると負担が大きい…。それなら、提案の実現を専門にサポートするチームや役割を設けるのはどうでしょう? 言い出しっぺはアイデア提供に集中でき、実現可能性も高まるかもしれません。また、目安箱のようなものを設置しても良いかもしれません。今週の良い気づき!の紹介
チームや会社に貢献する「気づき」や「行動」をした人を、ストーリーと共に社内報や定例会で紹介。「あの人の行動、素晴らしいな」「自分もやってみよう」と思えるような、身近なロールモデルを示す。
といくつか並べてみました。これらはあくまで「タネ」です。
大事なのは、「どうすれば現状をもっと良くできるか?」という前向きな問いを持ち続け、固定観念にとらわれずに、多様な選択肢を探る姿勢そのものだと思います。
これらのタネが、皆さんの組織で「正直者が報われる」文化を育むための、何かしらのヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。
さいごに:あなたのチームの「気づき」を、未来を照らす灯火に
長々と語ってしまいましたが、私が伝えたい想いはシンプルです。
「気づく人が損をするなんて、絶対におかしい。正直者が、ちゃんと報われるチームを、組織を、本気で作りたい!」
「気づき」は、変化の種であり、成長のエンジンであり、未来を照らす灯火です。それを、一部の人の負担や犠牲の上に成り立たせるのではなく、チーム全員で大切に育み、組織全体の力に変えていきたい。
この記事を読んでくださっているマネージャー、リーダー、そして組織をより良くしたいと願う全ての皆さん。もし、少しでも共感していただける部分があったなら、これほど嬉しいことはありません。
文化を変える道は、平坦ではないでしょう。時間もかかるし、時には壁にぶつかるかもしれません。でも、諦めずに、一歩ずつでも前に進んでいきたい。
まず、あなたの隣にいる「気づいちゃった」あの人に、心からの「ありがとう」を伝えてみませんか? そして、どうすればその「気づき」がもっと活きるか、一緒に考えてみませんか?
その小さな行動の積み重ねが、やがて大きなうねりとなって、「気づく人が報われる」組織文化を創り上げていくと、私は信じています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
❤️スキをクリックしていただけると継続する励みになります!
最近X(旧Twitter)もやっています。
https://x.com/sudo5in5k


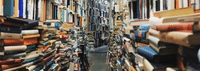
コメント
3この記事を観て前向きに検討させて貰った上での意見としては【気付きは勇気】。だからこその責任の所在を冷徹に明確化して体系的にエンパワーメントし続けたらいいかもしれません。一般的な民主的国家の政治家やワタシの様な匿名希望の傍観者を鑑みるに【社会的責任と発言権の影響力は相関する】≒説明責任のベネフィット。だからこその組織的なボトムアップを透徹的に行い続け、結果的に自浄作用のフレーム化が機能するでしょう。まぁ、【完璧な基準は存在しない】からこそ人生は面白いって権威が常々問うのですがね。駄文失礼しました。
ほんまそのとおり。ほとんどの場合気づく人は転職します。
世の中には気付かない人が恐ろしく多い。
実は見た目でわかるんだけどね。
なので細かいことをする人、数値に見えない事を給料にどう反映させるかを仕組みを考えればよいのさ
はじめまして。
とても興味深い記事でしたのでコメントを残します!
超下っ端にいる私の立場から言わせていただきますと、上の立場の人がこちらの気付きについて、このように「気付いて」くれることはとても嬉しいことです。
是非そのことを本人だけにで構いませんので、具体的なエピソード交えて褒めてあげてください。
皆が気がつくようなこと、誰でも褒められるポイントではなくて、「え!ここ気付いてくれたんだ!」って思うようなささいなことほど嬉しいですし、そこを褒めてくれた上司をきっと尊敬します。
私がパートをしている職場では年1回、匿名で感謝を伝えるカードを送り合うイベントがありますが、私はなるべくその人ならではの褒めポイントを見つけて書くようにしています。私のような下っ端でもできる、組織の環境を良くする動きだと信じているからです。
長々失礼いたしました。
うっしー様のような、下の気付きに「気付ける」上司がもっと増えますように…🙏