題:ジル・ドゥルーズ著 加賀野秀一訳「哲学の教科書 ドゥルーズ初期」を読んで
本書は若き日のドゥルーズの著作物である。「キリスト教からブルジョワジーへ」と「本能と制度」である。ドゥルーズがどういう著作物へ関心を寄せていたか、これらを通じてドゥルーズの思想の源を知ることができる。「キリスト教からブルジョワジーへ」はドゥルーズ自身の論文である。詳しくは述べないが、世界の中における内的生活が、他人たちの顔なる外部を通じて擦過すること、つまり精神と自然と国家を論じながら、キリスト教とブルジョワジーが結びついていることを記述している。「本能と制度」とは高校教師であったドゥルーズがベルグソンやマルクスなど六十六編のそれぞれ一頁あまりの短文を集めたものである。高校での教科書として使用したに違いない。本能とは欲望であり、それが制度とどのように絡んでくるかを生徒と論じようと編纂したに違いないテクストである。
訳者加賀野秀一が最初に「はじめに-ドゥルーズの出発点 若きドゥルーズへの遡行」として本書とドゥルーズ思想とを絡ませて論じている。また、訳者は「キリスト教からブルジョワジーへ」と「本能と制度」でも序文を書いて内容を紹介している。訳者加賀野秀一はドゥルーズとはあまり個人的には関係がなかったようである。「はじめに-ドゥルーズの出発点 若きドゥルーズへの遡行」を読んで、久し振りにドゥルーズに関する著作物を読むせいか、ドゥルーズの思想を忘れたというよりをあまり理解していないことに気付いて驚いたものである。やはり集中して読み、あるテーマに絞り論述するのが一番理解するうえで役に立つと思われる。この訳者の記述で一番関心を引いたのが「内在面」である。「潜在的なもの」と「可能的なもの」がサルトルからの影響があったことを初めて知る。
「内在面」とは、確か「千のプラトー」の語彙説明で書かれていたが「器官なき体」であり、可能性や多様性とも結びついていたはずであるが、結構やっかいな概念であり、詳細は調べてみないと分からない。訳者の述べる『概念は出来事であるが、内在面はそれら出来事の地平である』との言い方が的を射ているかどうもすぐには判断を下せない。『・・可能的なものは実在的なものに対立し、したがってそのプロセスは実在化=実現であるのに反して、潜在的なものは実在的なものには対立せずに、そのプロセスは現実化であるあるからだ』であるのはそのように思われる。サルトルからの影響であるらしいけれど、初めて知るような、知っていたような気もするが、今更調べる気も必要もないと思われる。
ここで「本能と制度」におけるドゥルーズ自身の序文を引用したい。『本能と呼ばれるもの、制度と呼ばれるもの、これらは本質的には、満足を得るための異なった手段を示している』である。「誰の満足」と問うて批判は可能であるけれども、その他の批判も可能であるけれども、言い得ていて妙である。この文章はドゥルーズの思考と表現の原点が示されている。なお、体制と力の関係に関する私の解釈を述べたい。体制が一極を集中する力をすさまじくさせると構成する要素のそれぞれや体制そのものに歪みが生じて分散化させて反作用する力を生み出させる。この作用反作用の力が社会学的にも成り立つことを指し示すことができるのである。
ドゥルーズの著作物は、ほぼ読み終えているため、主要著作物を読み返せば、また新たに発刊された「ドウルーズコレクション」なる文庫本も合わせて読んでみると、ドゥルーズの思想の全体が見えてくるかもしれない。なお、「本能と制度」における六十六編の引用短文は少ししか読んでいない。マルクスがこのような文章を書いていたとは驚きでもある。少しずつ読み進めれば、新たに読みたい魅力ある著者を見出すことができるかもしれない。
以上
いいなと思ったら応援しよう!



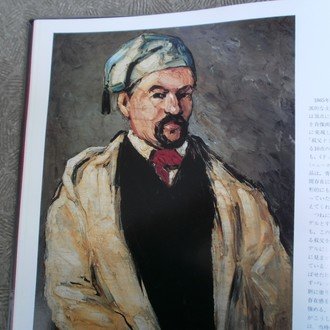
コメント