ロシア・ウクライナ戦争から3年。これまでとこれからを考える。東野篤子氏インタビュー。
ロシア・ウクライナ戦争が勃発してから3年。筆者も含めて、戦争の複雑な背景から、現状をどう捉えていいのかよくわからない…という方は多いのではないか。国際政治学者・東野篤子氏に、戦争の経緯や各国の思惑、さらにはトランプ政権の影響やBRICSの動きについてお話しいただいた。
ロシア・ウクライナ戦争「どこか遠い国の出来事」として捉えがちな方にこそ知ってほしい、国際秩序の今と未来を考えるヒントになれば幸いだ。
-ロシア・ウクライナ戦争が起きてから約3年が経ちますね。
東野:ちょうど今週で丸3年が経つタイミングですね。振り返ると、戦争の経緯は鮮明に覚えていますが、私生活の記憶が途切れ途切れになるほど、心を痛めた期間でした。私が専門としているヨーロッパという地域で、これほどまでに残酷な戦争が起きてしまったことに対して、大袈裟かもしれませんが、命を削ってでも取り組まなければならないと思いながら過ごしてきました。
-すごく繊細な話題ですし、状況も日々変化するテーマかと思います。ひとまずは取材当日2025年2月末の状況をベースに、お話をお聞きできればと思います。
東野:よろしくお願いいたします。
-本題に入る前に少しお聞きしたいのですが、東野さんが国際政治学に興味を持たれたのはなぜだったんですか?
東野:元々、ウクライナは私の研究テーマの一つのピースで、ヨーロッパ国際関係を中心に研究をしています。私は子供の頃、80年代の終わりまでイギリスに住んでいたんですね。
-そうなんですね。
東野:当時は冷戦の真っ只中で、イギリスでもマーガレット・サッチャー政権が、そうした緊張を意識した言説や行動をとっていました。ところが、80年代末に私が日本に帰国した途端、ドイツ再統一やソ連の崩壊、中・東欧諸国での自由選挙の導入など、それまで全く想像もつかないような変化が世界中で起きました。
-東野さんが日本に帰った途端に変化が訪れたんですね。
東野:世界が激変する只中で、日本にいることが歯痒くて仕方がありませんでした。自分自身でしっかり調べて、学ばなければいけない!と思ったのが高校3年生の頃です。そのまま、現在まで走り続けてきたというのが正直なところです。
-少し脱線してお聞きしたいのが、冷戦前後で世界はかなり変わったんですか。
東野:冷戦崩壊後、世界はより友好的な方向に向かう……多くの人はそのような幻想を抱きつつ、「本当にそうだろうか」というわずかな違和感も感じていたのではないでしょうか。今回のロシアによるウクライナ侵略は、その違和感こそが正しかったこと、ユーラシアにおける対立は形を変えて今も続いており、東西の分断も埋まってなどいなかったことに気づくきっかけにもなっています。
-その違和感って具体的にはどのようなものだったんですか?
東野:例えば、2008年のロシアによるジョージア侵攻や、2014年のロシアによるクリミア占領。私も当時、これらを平和なヨーロッパにおける例外的な不幸な出来事だと思いたかったわけですが、むしろこうした武力による現状変更が依然として防げないことこそがヨーロッパの本質だったことに気づかされました。
冷戦後の変化とロシア・ウクライナ関係の歴史。
-基本的には、2022年に全面軍事侵攻をしたロシアに非があるように思いつつも…それまでの経緯もあると思うんですね。長い歴史はありますが、ひとまず1991年ウクライナ独立から印象的な出来事を時系列にお話していければと思います。
東野:まずは、1991年の状況を簡単に説明します。当時は、まだロシア以前のソビエト連邦、ゴルバチョフ政権下でした。バルト諸国がソ連からの独立を宣言したものの、スムーズな独立とは言えませんでした。しかし、東西対立から脱しようとするゴルバチョフの発想がなまじ国際社会から支持されていたこともあり、ソ連はバルト諸国を一方的に武力鎮圧することを断念せざるを得ませんでした。
-なるほど。
東野:次に、ウクライナや、のちにロシア、ベラルーシなどといった旧ソ連の主要な共和国が、ソ連の枠組みから離脱することを画策し始めました。当時独立志向を強めていたウクライナのクラフチューク大統領に、ロシアのエリツィン首相が積極的に手を貸したことで、ソ連の崩壊が加速したのです。
-そもそもソ連崩壊は、特にロシアとウクライナによって起きたと。
東野:これは歴史的な事実です。しかし、現在のロシアのプーチン大統領から見ると、「ウクライナが騒ぎ立てたことでソ連が崩壊した。これは歴史上の過ちであり、正す必要がある」と考えているんです。
-そもそもロシアが手を貸したことが抜けおちているんですね。
東野:プーチンの頭の中では、そうした歴史観をベースにウクライナへの干渉を試み続けてきましたが、ウクライナを自らの「勢力圏」に収める決め手を欠きました。このため最終的に今回の軍事行動に至ったのだと思います。
-歴史観の違いから、現在の戦争にまで発展してしまったとも言えるわけですね。
東野:ロシア側の視点に立ってみると、現在は大きな過ちを訂正する期間であり、さほど罪悪感もないのでしょう。たとえ犠牲を払ってでも行うべき、正しいことだと考えているようです。この歴史観の違いが、ロシアとウクライナの間で決定的に食い違ったまま、現在に至っています。
-ソ連崩壊の際は協力していたのに、こじれてしまったんですね。
東野:悲劇的なボタンの掛け違いですよね。元々、ロシアとウクライナは「兄弟国家」と呼ばれることがあります。文化的な共通点も多く、そのこと自体は否定すべきではありません。しかし、ロシアは「兄弟国家」という言葉を言い訳に、ウクライナを意のままに動かそうとしています。ウクライナは1991年に主権国家として成立したわけですから、兄弟だといって自由を奪っていいわけがありませんよね。
独立後のウクライナと繰り返される政治の揺らぎ。
-独立後のウクライナは、国内も不安定な状況だったのかなと思います。
東野:独立後の政権は、ロシア寄りか欧米寄りか、外交の軸足をどちらに置くかで揺れ動いていました。独立直後のウクライナは、市民の生活水準も低く、汚職などの政治問題も多かったため、他国との関係強化を通じて豊かな国家を実現したいと考えていたのでしょう。
-ロシア/欧米どちらに寄るか揺れる中、2004年オレンジ革命が起きたわけですよね。
東野:オレンジ革命では、2004年の選挙でロシア寄りのヤヌコーヴィチが大統領に選出されましたが、これが不正選挙とされ、反対運動が起こってEU寄りのユシチェンコが政権を担うことになりました。
-選挙結果がひっくり返ったわけですね。
東野:これもロシアとウクライナ、そしてウクライナ国内でも、全く見え方が違うんです。ウクライナの親欧州的な人々からすると、「ロシアの介入によって民意と異なる大統領が選ばれたのだから、民意を正しく反映させなければならない」と考えて運動を起こしたわけです。一方、ロシアから見ると、「正当な選挙プロセスを経たのに、欧米諸国がウクライナ国内の一部の人々を煽って選挙結果をひっくり返した」と映っているんです。
-あぁ。ここでも全然違う景色が見えているわけですね。
東野:そうです。全てにおいて、ロシア、ウクライナ、欧米諸国、それぞれの見方がまったく異なるんです。
-ここで、少しお聞きしたいのが、こういった革命の裏に社会民族会議(SNA)やS14というような、ウクライナ国内の極右団体の影響があったとも言われていますが、これはどうなんですか?
東野:いわゆる極右と呼ばれる人々が存在したのは事実ですが、私としては、そういった極右団体がウクライナの本質を表しているとは思いません。
-ニュースや、ドキュメンタリーなどで「ネオナチ」などと強い言葉で語られることもあるので、すごく影響力があるのかなと思っていました。
東野:ロシア側は、右派セクター等の極右集団を誇張してウクライナを形容することで、道具として利用してきたんです。実際のウクライナの極右は、あえて例えるならば日本における暴力団のようなものではないかと思います。世界の国々から「日本ってヤクザの国で、⚫︎⚫︎組に支配されているんだよね?」と言われると、日本人としては違和感がありますよね。
-そうですね。
東野:それと同じような状況です。
革命の裏にある各国の視点の違い。
-次に2014年、こちらもウクライナ国内で起きた尊厳の革命(マイダン革命)が象徴的かと思います。
東野:革命の背景からお話しします。オレンジ革命後、EUとウクライナは良好な関係を徐々に模索し続け、ようやく2013年の東方パートナーシップ首脳会議で連合協定締結の最終段階に至りましたが、当初は署名する意思を示していたヤヌコーヴィチ大統領が、突然署名を拒否しました。
-へ?それはなぜですか?
東野:これには、ロシア側からの圧力があったと言われています。ウクライナは、ロシアを中心とした経済同盟であるユーラシア経済連合(EAEU)か、EU経済連合のどちらかを選ばなければならない状況に追い込まれたわけです。結果、それまで積み重ねてきたEUとの連合協定締結が実現しませんでした。これが引き金となり、革命にまで発展したのです。
-それが、革命にまで発展したのはなぜなんですか?
東野:当時、多くのウクライナ国民は、EUとウクライナのあいだで結ばれようとしていた協定の内容を十分に理解していませんでした。EUは魔法の杖ではありませんから、経済協力やビザ自由化に関する協定を締結しただけで、ウクライナが直ちに経済的に豊かになるわけではなかったのに、過度な期待を寄せてしまっていた。このため、ヤヌコーヴィチ大統領が唐突に連合協定締結を棚上げしたことは、一部のウクライナ国民にとっては繁栄への夢を奪われたように感じたのです。これに加えて、汚職や不正、経済政策の失敗など、元々溜まっていたヤヌコーヴィチ政権への不満が爆発し、革命にまで至ったのです。
-ウクライナ国内では、それほどEUへの期待が高かったんですね。
東野:国内の不満が臨界点に達していたのでしょう。東方パートナーシップ首脳会議はあくまできっかけだったのだと思います。この革命も、ロシア側から見ると、捉え方が大きく変わります。
-ロシアから見るとどうなんですか?
東野:ロシアからは「EUが協定という形で自分たちの縄張りに手を出してきた」と見えていたのでしょう。だからこそ、ウクライナに圧力をかけた。「ウクライナが有利なユーラシア経済連合を蹴ってまで、EUとの協定を結ぶなんてあり得ない。マイダン革命も欧米が煽った以外に説明がつかない」と考えていると思います。
-ふーむ。こじれていますね。。
東野:ロシア側の視点に立てば、わからなくはありません。しかし、「米欧がウクライナを煽った」と考えるのは、あまりにウクライナの民意を軽視しすぎではないでしょうか。ウクライナの人々は、少なくとも政権への不満があり、自由意志で異議申し立てを行ったわけですからね。
-それを「すべて米欧が煽ったこと」としてしまうのは、乱暴ではないかと。
東野:こういった態度も、ロシアはウクライナの主権を認めていないからこそ起きるのだと思います。
NATOとウクライナ、そしてロシアの反発。
-戦争の1年前、2021年「NATO非加盟を求める条約」をロシアが提出しましたよね。
東野:これについても、少し時を遡って、2008年のブカレスト首脳会議からお話ししますね。この会議で、当時の米ブッシュ大統領が「ウクライナとジョージアは近い将来NATO加盟国になる」という文言を首脳会議の共同声明に入れるべきだと突然主張したんです。
-突然!?
東野:当時ブッシュは選挙も控えていたので、国内のポーランド系有権者の票が欲しかったという背景もあったという指摘があります。しかし、この主張には、ドイツやフランスなどのヨーロッパのNATO諸国側も反対しました。ウクライナやジョージアは、まだまったくNATOに加盟できるような状況ではないと考えられていたからです。「時期尚早だ」と。
-あ、EUも反対したんですね。
東野:はい。しかし、アメリカが押し切る形で、ウクライナとジョージアの「将来的なNATO加盟」を共同宣言に入れてしまったんです。
-ウクライナがNATOに加盟する可能性は本当になかったんですか?
東野:NATOは、面倒なことを極端に嫌うんです。あらかじめ設定された基準に達していない国家を加盟させるメリットがなければ、冷たく接します。当時のウクライナは、近代化のための努力を少しはしていましたが、NATO加盟基準に達するには程遠い状態でした。レベルが全く違ったわけです。証拠に、ウクライナのNATO加盟はその後ほとんど進んでいません。むしろ、2000年代以降のNATOは、協調的安全保障という枠組みを作り、ロシアと対話を続ける戦略をとっていました。ウクライナやジョージアにはあまり目を向けていなかったんです。ちなみに「基準に達していない国に対して冷淡」であるのはEUも全く一緒です。例えば、ポーランドやハンガリーのような国でさえ、EU加盟に7~8年かかりました。経済的・法的な面で基準に達していない国家を加盟させることで、組織のレベルや求心力が下がることを恐れているからです。
-NATOとロシアが協調する世界線もあったのかもしれないのに。
東野:申し上げたとおり、NATO側としてはロシアと話し合いを重ね、協力する心づもりは十分にありました。しかし結果的にブカレストNATO首脳会合での宣言は、後にロシアにとってジョージア侵攻やクリミア占領の「口実」として用いられました。さらに、ロシアによるウクライナ全面侵攻直前の2021年に、ロシアはアメリカとNATOに対し、ウクライナのNATO非加盟を法的に保証することを求めた条約案を突きつけるに至ったわけです。
-ロシアは、とにかく「ウクライナはNATOに加盟するな。欧米に寄るな。」と言い続けているとも捉えられますよね。
東野:前提として、ロシアにはそれを言う権利はないんです。どのような条約や同盟を結ぶかは、ウクライナの主権に基づく選択であり、尊重されるべきです。そもそも、1975年にソ連も署名した「ヘルシンキ最終文書(全欧安全保障協力会議:CSCE)」に立ち返ってみましょう。
-「ヘルシンキ最終文書」?
東野:キューバ危機などで冷戦が激化した後、緊張緩和を求めて「デタント」という時期がありました。冷戦の対立が最も深刻だった時代を超えて、アメリカ、ソ連、ヨーロッパ諸国が参加し、妥協点を探って合意したのが「ヘルシンキ最終文書」です。国家主権の尊重や国家不可侵など、重要な項目が多く含まれていますが、その中の一つに「同盟選択の自由」が明記されています。この宣言に賛同した国家は、自由に同盟を選び、自由に同盟から脱退できるという内容です。
-冷戦時代に、素晴らしい取り組みがあったんですね。
東野:この宣言には、ソ連を含む30カ国以上の国が署名しています。ソ連の後継者であるロシアは、現在に至るまで加盟国であり続けていますから、「ヘルシンキ最終文書」の精神が引き継がれているべきなんです。ところが、ロシアは同盟選択の自由を守っていない。自分たちで約束したはずの原理原則を破っている。この原則に立ち返って考えると、ロシアのウクライナへの態度は全くよろしくないと思います。
トランプ政権とウクライナ戦争の未来。
-現在(2025年2月末)起きていることをお聞きしたいと思います。トランプの第二期が始まってアメリカが本格的に介入してきているようにも思います。
東野:ウクライナ国内では、就任前からトランプ政権への期待の声が大きかったんですね。バイデン政権はウクライナへの兵器支援に関して極めて慎重なスタンスでした。長射程兵器の制限解除も、極めて部分的にしか行いませんでした。全般に、ロシアからの反応がエスカレーションを招きかねない全てのことに、後ろ向きだったと言えます。トランプ政権であれば、もっと積極的になってくれるだろうと考えていました。トランプ政権一期目で、ウクライナに対してジャベリンなどの兵器を与えていたのも印象的だったのでしょう。
-東野さんは、どのように捉えてらっしゃいますか?
東野:今期のトランプ政権は、より振り切れた形で国際社会問題に関与しようとしているのではないでしょうか。力を持った国家同士でだけで解決する姿勢だと思いますね。また、今期はトランプ周辺にはイエスマンしかいないので、状況を深く理解できていないようにも感じています。結果、多くのケースで「どっちもどっち論」を重視する。ロシアもウクライナ、どちらも戦いをやめるべきだと。
-よくわからないから、とりあえずどっちもどっちだと。
東野:現状のトランプの意見を簡単にまとめると「侵略された現実はあるけど、諦めて受け入れ、その上でスパッと戦争をやめよう」ということかと思います。これは、ウクライナからしたら受け入れ難いですし、私が冷静にみても「ロシアが侵攻をやめるべき」と思いますね。
-そのご意見もよくわかるのですが、めちゃくちゃ素朴に考えると「一旦争いを止める」ってアメリカのスタンスは、良いことにも思えます。もちろんそんなにシンプルな問題でもないですが、戦争が止まることに期待もしてしまいます。
東野:私も、一旦収めることは、大変良いことだと思います。大賛成です。
ただし、ロシアが約束が守るのであれば…です。2014年のクリミア侵略から、2022年に至るまでロシアとウクライナの間では、およそ200回もの停戦交渉が行われ、大小含めて約25の停戦合意が結ばれてきました。が…ただの一つも守られなかった。2022年のウクライナ全面侵攻を止められなかった。
-ロシアに対する信頼性がないということですね。
東野:戦争が止まることは素晴らしいことですし、停戦に越したことはない。ですが、今までロシアが約束を守ってこなかったことにより、信じられる状況ではないんです。
アメリカ・BRICS・グローバルサウス。
-今期のトランプ政権は、なぜこれほどロシアとウクライナへの介入に積極的なんですか?
東野:理由は2つあると思います。1つ目は、トランプは自身が「平和を達成した大統領」として歴史に名を残したい、つまり自らの名誉心のようなものが働いているのかなと思っています。内容はともかく、平和に寄与した実績が欲しいのではないかと。
-ある種の勲章が欲しいということですね。
東野:そうですね。ただ、よく指摘されるのは、たとえ停戦に至ったとしても、トランプ政権後にロシアが体制を整え、満を持して再び侵攻するのではないかということです。停戦が成立しても、ロシア側の歴史観が変わらない限り、ウクライナを諦めることはないと思います。トランプ以降に再侵攻が起きると、「トランプだったら抑止できた」という声が上がるでしょう。ロシアもそういったアメリカの状況をよく理解しているので、この4年間は大きな侵攻を控えるだろうと言われていますね。
-先を見ると、停戦してもポジティブとは言い難いのですね。
東野:もう一つは、トランプ政権の人々が安易に言いがちですが「ロシア・ウクライナの問題をさっさと片付けて、中国に注力する」ためだと思います。アメリカにとって本当の敵は中国だと。いつまでもロシア・ウクライナに目を向けている場合じゃないということですね。
-その二つの理由から、介入に積極的であると。
東野:二つ目の理由についても問題はあります。中国に注力したいという理屈はわかりますが、現状の中国のロシアに対する立ち位置を見ていると、そんなに単純ではない。現在、ロシアに対する「制裁逃れ」の協力や、ドローンなどの輸出など、実施的な継戦能力維持支援などの流れをみても、中国は明らかにロシアの背後に立っているんですね。なので、ロシアを勝たせることは、背後にいる中国を勝たせることにもなってしまうわけです。
-あぁ確かに…!
東野:見方を変えれば、中国からしてみると、ウクライナとロシアが争い続けた方が都合がいいわけです。
-少し話題が変わりますが、中国とロシアも関わる話として「BRICS」の影響についてはどう捉えればいいですか?
東野:BRICSやグローバルサウスといったある種の連合が、今回の戦争をきっかけに広く知られるようになったと思います。ただ、それぞれの加盟国が何かしら統一の価値観を共有しているかというと、そういうわけではないと思います。
-意外と連帯感は薄いと。
東野:アメリカやヨーロッパなど「西側」に対する反感や反目を共有としてはいるのかもしれませんね。
-ニュースなどを見ているに、割と影響力があるようにも思っていました。
東野:BRICSやグローバルサウスといった連合を、中国側が巧みに利用しているという側面はありますよね。
-どういうことですか?
東野:一つ例を挙げます。2024年に中国がブラジルと共同で和平案を提出しました。内容を詳しく見ると大したものではないのですが、これがニュースで流れると「中国とグローバルサウスは連携している」と見えますよね。
-確かに巧みな戦略ですね・・・。
東野:中国は「この戦争は、米欧対グローバルサウスの戦いなんだ」と見せたいわけです。これは、「見せ方」としては非常に上手いですね。
日本がとるべき姿勢について。
-最後に日本は、どのような姿勢をとるべきとお考えですか?
東野:日本の多くの人は、ウクライナは遠いヨーロッパで起きているし、自分たちには関係ないと思われているかもしれません。支援に反対の声があるのも理解はできます。日本は島国なので、そういった侵略への意識が薄いと思います。ですが、これは日本にとって人ごとではないんですよね。ウクライナの状況は、私たち日本にも起こり得ることなんです。
-隣国と地続きなヨーロッパと比べるとそうかもしれませんね。
東野:ある日、どこかの国が、日本に攻めてきて国土の20%…北海道全土以上を侵略されたことを想像してみてください。今日からここは別の国家ですと言われても、簡単に納得したり、諦めることってできませんよね。
-想像すると、ゾッとします。
東野:ウクライナは今、そういう状態だということです。日本でも、南シナ海や尖閣諸島などの状況を考えると、ウクライナの状況は他人事ではない。昨年末にイギリスの新聞の『フィナンシャル・タイムズ』がロシアが、日本と韓国の原発など、有事の際の攻撃対象のリストを2014年時点で作成していたと報じました。さらに、台湾有事が起きたとしても、日本との距離を考えたら決して安心できませんよね。
-確かにそうですね。
東野:ですから、「武力による侵略を断固として許さない」と示すためにも、ウクライナへの支援、ロシアへの制裁は筋の通った態度だと思います。
「強い国が弱い国に攻め込んで、侵略されて占領されても諦める」この秩序が罷り通ることこそ、恐ろしいですから。何よりも怖いのは、世界的にこういった状況をどこか他人事として捉えるような論調に傾いています。とても恐ろしい状況ではないかと思いますよ。
-正直に言いますとお話を伺うまで「なんでウクライナの支援をしているんだろう」って思っていました。
東野:ウクライナを見捨てるのであれば、日本が同じ目にあった際に国際社会からの支援を得られないということです。日本がきちんとした態度を示し、グローバルサウスや小国と連帯していくような可能性はあるのかなと思っています。
これからの世界で失いたくないもの。
-では、最後の質問です。東野さんがこの先の世界で失いたくないものはなんですか?
東野:「根本に立ち返ること」でしょうか。「そもそも」ということに立ち返って考えることですね。今回の戦争にしてみても、私自身も、領土を取られたとしても停戦でいいじゃないか…と考えることがまったくないわけではありません。でも、そこに住んでいる人たちの生活は?占領されて、これまで大事にしてきた言語や文化を捨てなければならない人々の気持ちは?連れ去られた子供達はどうなるの?そしてそもそも武力による現状の変更を許していいのだっけ?そういう根本に立ち返ることで、状況に流されず、採るべき道を問い直すことができるのではないかと思います。
Less is More.
ウクライナ戦争が決して他人事ではないことをあらためて実感した。武力による侵略を許せば、その前例が世界各地に広がり、日本も例外ではなくなる可能性がある。「日本がどの立場をとるかが、未来の安全保障にも直結する」からこそ、遠い国の出来事と片付けず、今こそ国際社会の一員として、日本ができること、個人ができることをもう一度考え直すべきなのかもしれない。
(おわり)


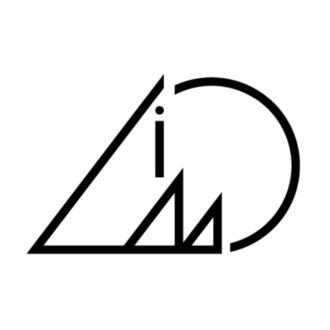
コメント