小規模自治体でローコード開発ツール(UiPath)を契約廃止したお話
お話の概要
弊社が契約していたUiPath(LGWAN-ASP)を解約しました。それに至った経緯とどうすればよかったのかを自分なりに分析しました。
弊社の構成
LGWAN-ASPのCloudPark「自治体向けRPA配信サービス」を契約し、LGWAN接続系とマイナンバー利用系(特定通信)から接続、インターネット接続系には、仮想マシン経由でアクセスする形式となります。
RPAの選定及び理由
RPAにはUiPathを選定しました。導入当時(R2年度)は、WinActorやbizrobo等が候補としてありましたが、以下の理由によりLGWAN-ASPのCloudPark(UiPath)を選定しました。
高速で動作(画面のセレクタ等)
LGWAN-ASPなのでどのネットワーク系からも使用可能
仮想画面越しにも動作可能
導入の理由
よく言われるように働き手不足による人的リソースの確保にあります。弊社では、職員定数計画に基づき、正規職員ではなく、会計年度任用職員(パート/アルバイト職員)を雇います。
しかしながら、人件費のコストカットを目的にしているために、人員増による見えないコスト(教育にかかるコスト、人間関係)を見ないフリをしているように感じたため、ちゃんと少ない正規職員でも回せるようにツールの導入をすべきと判断したためです。
契約の前に行ったこと
とはいえ、単純に導入するだけでは保守業者に依存することとなり、結局お金が発生することを懸念しました。
そこで僕は、自分自身もUiPathに詳しくなろうと、UiPath更新のハンズオン研修をある程度行いました。もちろんほぼ一人情シスの小規模自治体なので、業務時間内に行うことができず、プライベートの時間を削って行いました。
RPAに感じたこと
僕は前職の民間時代には、MagicXpaというソフトウェアを用いて、業務系システムを構築していたので、UiPathのようなローコードツールの雰囲気はスッと理解することができました。
普通の業務で利用する機能(MSOiffceの操作等)は充実してましたし、SMTPやブラウザの操作など本来難しいアプリケーション間の操作を、簡単に開発できるなあと感じました。
ただし、UiPathはIT未経験者にはハードルが高いとも感じました。コードを書く必要がある部分は、VBやC#で記述する必要がありましたし、各種プロトコルの知識が必要となります。
導入にあたって弊社が行ったこと
ツールそのものの難易度が高いと判断したため、僕は庁内に研修もしくは勉強会を行った方がいいと考えました。
そこで、庁内の有志を募り、定時後に僕のお手製研修資料をもとに、勉強会を実施しました(月1回程度)。
勉強会に参加した職員からは、「動くものを作れた楽しかった」と非IT職員から言われ、好評だったのではと思っています。
この勉強会は僕を含めた有志が勝手にやっている体で実施していましたが、首長やらが首を突っ込んできましたが、それは別の機会に…
いざ導入!
そんなこんなで導入がスタートしました。もともとはオンライン申請の業務フローの一部に組み込みましたので、導入や構築は業者さんにお願いし、独自に開発するライセンスをついでに契約しました。
クラウドサービスなので、契約するだけで使うことができて便利でしたね。
導入後
導入後にオンライン申請以外で何に使われたかを列挙…しようにも僕が作ったロボット1つです。導入3年間で、1つです。しかも単発動作するロボットです。
案件がなかったわけではありません。軽自動車税の処理やふるさと納税のワンストップサービスの処理にやってみない?という提案はしまして、現課も協力してくれそうな雰囲気はありました。
どうしてこうなった?
僕自身もそうだけど、勉強会に参加したメンバーや弊社職員はどうして使わなかったのか?感じたことを列挙していきます。
原因はヒト・モノ・カネに以下のように分類しました。
物理的なライセンス数による触れる機会の損失
弊社の予算の都合もあり、課一つ毎に1ライセンスを割り当てるということはできず、まずは自由に開発できる1ライセンスのみ導入することとなりました。
しかしながら、ライセンス数が少ないことと、開発できる環境が1端末しかなかったことから、職員の目に触れることなかったことが考えられます。
また、開発環境の構築も面倒であったのも要因の一つであります。その他ローコード開発ツールでは、最低21インチのモニタが必要であると感じました。弊社のノートパソコンの環境では、開発が難しく、普及しなかったものと考えました。
運用体制の未構築
次の経営層の無関心さにもつながりますが、導入後の情シス部門がUiPathを構築・運用・保守する体制がとれなかったのも要因の1つと考えます。
これは、常に僕が「RPAの運用のために体制を作ってくれ」と上層部へ要求していたのですが、実現せず、情シス部門ですら使用機会がなかったためです。
ほぼ一人情シスじゃあ運用なんて無理だよお!
経営層の無関心さ
例えば導入後の効果の検証がない、人件費の抑制や業務時間の削減などの具体的な目標がなく、そもそも導入しているかどうかも知らない/RPAが何かも分かっていないため、トップダウン的指示がなかったことも要因の一つだったと考えます。
定期的な勉強会/研修会の実施ができない
僕自身もさらなる知識の習得のため、UiPathのオンラインイベントに参加したりもしましたが、特に最近はAWSの勉強等に時間を使っているため、RPAをやっている場合ではありませんでした。
そうなってきますと、庁内の勉強会/研修会もやる時間がなく、どんどん忘れられていくことになりました。
研修を外部に委託することも考え、予算要求も行っていきましたが、予算の都合上、例えば5人分の予算しかつかない等の壁がありました。こうなってきますと、「誰に」研修を受けさせるのかが課題となりました。そして次の課題も浮き彫りとなりました。
職員の不安
自主勉強会に参加した職員からは、好評であった反面、こんな声をもらいました。
「こういったツールで業務改善を行うことはやるべきだと思うが、知識のある人に業務が集中してしまうことが想定される。」
これはおっしゃる通りです。弊社職員は、新しいツールやシステムを学びたがらない傾向があり、システム構築においても業者に丸投げをするし、国や県からくる通知を情シスに丸々転送したりと、社会人としてどうなの?と思うこともしばしば。
また、VBやC#の知識の前に、一般的なプログラミングの知識(例えば変数や型)も必要となり、非IT職員にはハードルが高すぎたと思われます。
職員の無関心さ
案件として、軽自動車税の業務やふるさと納税の業務で話を持ち掛けたこともあります。
しかしながら、軽自動車税の担当は情シスが全部作ってくれるんでしょ?的な空気でしたし、ふるさと納税の担当は「これでロボットを導入しても、会計年度任用職員を断ることはできない」といった空気でした。
また、RPAの習得による苦労よりも、人を雇ってその人にアナログな業務をさせる方が担当としては楽ですから、関心なぞなくなって当然だと思われます。ちゃんと人件費も把握してほしいものです。
小規模自治体でローコードツールは必要か?
職員数の少ない小規模自治体でローコードツールやノーコードツールは必要です。むしろこれができない自治体は人件費の増か業務の多さで死ぬと思います。
しかしながら、本気で運用を考えるならば、庁内の運用体制を構築し、現場職員に習熟させる環境を構築し、時には業者に委託することも必要と考えます。完全に内製で実施するには、そこそこの人数を抱えた自治体でないと難しいと考えます。
今後はどうする予定か?
私は今年度をもって、UiPathの契約を打ち切りました。理由としては、情シスの人員が減ったことと、標準化等の業務やそのほかの重い業務があるため、これ以上の運用が不可能と判断しました。
じゃあ今後はRPAを使わないかと言いますと、僕自身は引き続きUiPathを触っていこうと思いますし、弊社がβ化した関係でインターネット接続ができるようになったため、UiPathのCEやPAD等の無償で使えるものも活用していこうと考えます。
また、RPAである必要もありません。非IT系の職員が利用しないのであれば、僕自身がPython、VBAやPowerShell等を使って効率化すればよいので、情シスの業務は効率化できると考えています。
最後に、ノーコードツールもどうしようかなとも考えることがあります。DB(というかDBの設計・ER等)の知識も多少は必要となり、うちの職員で開発/メンテナンスができるのか甚だ疑問ではあります。とりあえずは、経営層が何か言ってくるまでは提案しないでおこうと思います。最近は、弊社内部の職員に諦めがついて、この人たちのためにいろいろ環境を整えても無駄な気がしています。僕の力不足ですね。僕IT職向いてないですね。
これから導入する自治体にお伝えしたいこと
いろんな導入自治体を見てきましたが、「シナリオの変更はどうするんですか?」と聞きますと、結構な割合で「業者にお願いします」「職員で直せる人がいないのでどうするか考えています」という返答がきます。
業者委託してでも人件費等のコスト削減につながるのであれば、導入に踏み切るのはいいと思います。ただ、シナリオの変更のトリガーは、例えば法改正による業務フローの変更だけでなく、画面の見た目が変わったり(例:OSのバージョンアップ等)、解像度の違いにより動作しないなど様々あります。そういった事態にすぐ対応できる体制は構築しておくことをお勧めいたします。

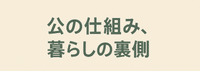

コメント
1うちでは、ノーコードツールを前提とした、業務システム開発を委託しました。
4月から運用開始予定ですが、開発したシステムに影響ないところで利用できる環境は確保しました。
活用・運用につながるかはこれからですが、情報部門が別のローコードを押していることもあり。。。(^_^;)