火山列島を倭国神話から考えるーー神話と歴史の研究・教育
学び舎の『ともに学ぶ人間の歴史』(中学校日本史教科書)の授業ブックレット№19(2024年11月)に書いたものです。
私は三・一一の陸奥沖海溝地震の後に地震・火山について講演を頼まれることが多く、それ以来、地震・火山の研究に従事するようになりました。その中で小学校や高校でも教室で授業をしましたが、地震・火山の神は須佐之男(スサノヲ)命・大穴持(オオアナムチ)命ですので、それを話しの導入にしました。ところがぽかんとしている生徒も多く、聞いてみると名前をしらないのだと分かって驚きました。
そんな経験をもとに書いた『歴史のなかの大地動乱』(岩波新書、2012)では、地震・火山神話を取りあげ、以降、日本神話を地震火山神話として捉え直すことを研究課題としています(右にふれた大穴持(オオアナムチ)命の「穴」は、火山火口あるいは鉱山坑道の穴です(益田勝実1968。西宮一民1979)。なお大国主命という神名は七世紀後半頃に作られた名で奈良時代にはほとんど使われていませんので、できる限り使はないようにしています)。
Ⅰ対アジア・アメリカ戦争は神話戦争であったこと
御承知のように対アジア・アメリカ戦争は日本が皇祖神アマデラスを掲げて戦った神話戦争でした。それに反発した戦後派歴史学の神話研究は、当時、唯一の実証的な『古事記』『日本書紀』研究とされていた津田左右吉の仕事を前提に出発しました。
しかし、津田の神話研究の特徴はまず記紀の描く「神話」は政治的あるいは文芸的な机上製作物であって、そもそも神話ではないという主張にありました。津田はフレーザー『金枝篇』をよく読んでいましたが、フレーザーは人類の精神史を「呪術の時代」から「信仰の時代」への変化と捉え、その長い過渡期に人間神Man-godの習俗を基礎にしたさまざまな神話が存在することを世界中から例示し、神格化された日本の天皇その一例としてあげています。津田はそれを逆に利用して、日本は原始未開の呪術の時代が続き、社会全体としては奈良時代になっても神話は現実の社会的意識でも世界観でもなく、天皇は儀式的な象徴のために「現人神」Man-godであるかのように役割を果たしたに過ぎない。神話が事実であった訳ではない。単一民族の日本は平和でそもそも政治というものに天皇は関わらないのだと論じたのです。
また津田の議論のもう一つの問題は、本居宣長・平田篤胤が国家神話の側面における至上神は顕神アマデラスであるが、民族神話の至上神は幽神タカミムスヒであるとしたことを無視したことです(なお神道嫌いで『老子』嫌いでもあった津田は『老子』を重視した平田をとくに無視したようにも思います)。津田はアマデラスもタカミムスヒもどちらも宮廷の貴族役人が机上で作ったものだが、アマデラスが最初に作られた神であるという意味ではアマデラスが日本神話の中心だとします。そしてムスヒ神は日本神話の神々の中でも一番最後に作られたもっとも机上製作の正確の強い神だとしました。津田の神話論の特徴は①日本における神話の不在と、②アマデラス中心主義の組み合わせだったといえます。
津田は近代帝国日本を誇りとした欧化主義者であり、天皇を敬愛する「明治人」として、彼の感じる天皇の姿や明治のアマデラス中心の神話理解を歴史に投影しました。そのような津田にとって、自分の記紀批判の仕事が神話の事実性を否定するものとして戦争勢力から攻撃されたのは不本意なことであり、それに対して筋を通して屈服しませんでした。これは見事なことで、戦後派歴史学はそれを尊重しました。また一九四六年一月一日のいわゆる「人間宣言」が「天皇を以って現御神(あきつみかみ)とし、且日本国民を以って他の民族に優越せる民族にして、延て世界を支配すべき運命を有すとの架空なる観念」としていた訳ですから、これは当時の社会の雰囲気そのものでした。
ただ、第一の日本における神話の不在、『古事記』『日本書紀』に書かれたものは神話ではないという津田説に無理が多いことは明らかで、たとえば石母田正・益田勝実などが相当のエネルギーで神話の実態を明らかにする作業に取り組んみました。彼らの仕事には国民をとらえた神話戦争の「神話」の実態を問おうという迫力がありましたが、残念ながらそれは体系化されない初歩的な作業に終わりました。それを引き継いだのは歴史学では岡田精司・溝口睦子などに代表される研究者で、彼らの体系的な仕事が現在の神話研究の基礎になっています。彼らは1970年代から倭国神話の至上神はやはり本居・平田のいうタカミムスヒであることを確定し、歴史神話学において津田の仕事は全体として過去のものになりました(なお、これも言葉の問題ですが、国号日本の成立した七世紀末期以降の「神話」については「日本神話」という言葉を使うのがよい場合もありますが、それ以前については倭国神話という言葉がふさわしい言葉だと思います)。
しかし、問題は岡田・溝口の代表する歴史神話学の側でも、肝腎のタカミムスヒがどういう神かに定説がないことです。岡田は男性太陽神であるとし、それは有力な意見ではありますが広く認められている訳ではありません。またさらに問題なのは、「古代史」学界においては石母田・益田のような神話研究の重視はいつのまにか消失したことです。私と同世代、あるいは少し下の世代の歴史家で神話研究を専門的課題としている人はおそらく五指に満たないという状態です。「古代史」学界は依然として津田の神話論の影響が強いままで、倭国神話の至上神がアマデラスか、タカミムスヒか、あるいは日本における神話と神話時代の存否という問題自体について現代的な思想的興味を失っています。私はこういう状態は歴史学の悪い意味でのアカデミズム化であって、戦後派歴史学の初心に反することだとは思いますが、歴史研究の作業は複雑でやるべきことが多く思うに任せないことが多いのもご存じのことだと思います。
さて、こういう状態の中で、教科書で神話をどう書くかは難しい問題です。たとえば、学び舎教科書は『古事記』『日本書紀』の神話を「太陽の女神とされる天照大神が、天から地上に神々をつかわし、その子孫が国を制圧して、最初の天皇となったという神話が書かれています」と説明しています。つまり後に説明します天孫降臨神話とイワレヒコ(神武)東征神話のことです。これは歴史神話学の常識とは異なっていますが、日本神話の至上神はタカミムスヒといわれますが、この神の性格は分かっていませんとは書けないでしょう。私も現在の学説状況では教科書にはこう書いておくほかないようにも思います。まずは問題の所在を周知し、具体的な研究と議論から進めるほかありません。
ただご承知のように、現代日本では学界や教育界、文化世界の内部、そしてそれと国民の歴史知識に非常に大きな落差があります。それを一つ一つ整理していく上で、この問題は重視しておくべきものだと思います。その例の一つとして、ここで専門的な神話研究と国民常識の落差を明瞭に示す例を一つあげますと、天石屋戸神話の主人公はアマデラスかスサノヲかという問題があります。驚かれるでしょうが、最近の歴史神話学の通説では天石屋戸神話の主人公はスサノヲであって、彼は太陽を攻撃して、天から五穀の種を以て帰った英雄であるとされます(水林彪1991、p.90。溝口睦子2009、p.122。菊地照夫2021)。東ユーラシアには天に太陽が二つあって地上が灼熱にさらされるので、勇敢な若者が太陽を攻撃して人々を住みやすくしたという神話が各地にありますが、それと同じです。オホヒルメ(大きな輝く女神=太陽女神)は溝口『アマテラスの誕生』が強調するように受動的で二次的な神でした(なおアマデラス=天照という神名は後に述べるような机上の製作物ですので、本来の倭国神話を論ずる際には使うべきではありません)。
Ⅱ『古事記』冒頭の天地初めの三神とは何か
歴史教育に関わる方で、『古事記』『日本書紀』の神代の部分を精読された方は、現在どの程度おられるでしょうか。『古事記』を読まれた方は、下記の『古事記』冒頭部を記憶されているでしょうか。
「天地初めて発(あらは)れし時、高天原に成りませる神の名は、天御中主(アメノミナカヌシ)神、高御産巣日(タカミムスヒ)神、神産巣日(カミムスヒ)神。この三柱の神は、並(とも)に独神と成りまして、身を隠したまふ也」
この「三柱の神」を造化三神といいますが、この三神がどういう神かは歴史神話学の大問題です。ここでは私見を簡単にいうことにしますが、まずアマノミナカヌシという神は北辰(北極星=太一)の神です。つきそう北斗は柄杓を持っていますから水神で、この神は倭国神話では「久比奢母智(クヒザモチ)神」(杙瓠(くいひさご)。柄をつけた瓢簞の神)といって、天に男、地に女の二神がいます。
水神は月と縁が深く、日本の月の女神は伊勢外宮のトヨウケ姫が有名です。古くは伊勢神宮の中心はこの月神トヨウケ姫を祭る外宮と、「神風の伊勢」といわれる伊勢国の風雷神、伊勢大神を祭る荒祭宮にありました(荒祭宮は伊勢内宮正殿のすぐ真北にある別宮。参照、筑紫申真1962)。アマデラスが内宮に祭られるのは七世紀末から八世紀初頭ですが、その神格はアマノミナカヌシと習合するところから出発していたという吉野裕子『大嘗祭』(弘文堂、1987年)の意見に私は賛成です。
造化三神のトップがアマノミナカヌシになったのは天武天皇の時代です。天武は、道教を国教にしていた唐にならって日本でも道教国家を作ろうとしました(新川登喜男1999)。天武の諡(おくりな)は「天渟中原瀛真人(あまのぬなはらおきのまひと)」といいますが、その「渟(ぬ)(沼)」は葦原中国に対応する天の葦原で、その中央に「瀛」という中国の神仙思想のいう東海の神山があり、天武はそこに棲む真人(仙人)です。天界の中央の神山の主ですから、天御中主(アマノミナカヌシ)と同じ意味になります。中臣氏は天武の下でアマノミナカヌシを祖神とし、伊勢神宮の祭主となりますから伊勢内宮には「天武=天渟中原瀛真人=アマノミナカヌシ」がいたと考えられていました。天武はようするに中国道教のいう天帝で、日本の天皇号そのものなのですが、この意味で、日本の神学・神話学の研究の先駆者、本居宣長・平田篤胤がアマノミナカヌシは中国的な神だとしたのは正しかったことになります。ただ、この神が持統が立てた神宮を拠点とする伊勢神道の主神となり、幕末まで日本神道の主神であったことは認めなければなりません。なお、現在、多くの人びとはこの神の名を知りません。それにも関わらず、教科書に吉田神道・垂加神道などの固有名詞がのっていて一種の暗記の対象となっているのは、実際上、日本史における神道史を無視するものです。むしろ神道史の基本としてアマノミナカヌシが長く主神であったことを記載すべきでしょう。
そうしなければ本居・平田が、このアマノミナカヌシ以前の倭国神話の本来の至上神は『古事記』冒頭節の二番目、三番目に出てくるタカミムスヒ・カムムスヒであったとしたことの画期的な意義が理解できません。しかし、タカミムスヒ・カムムスヒの復権は一時的なものにとどまりました。現在ではこの神の名を知っている人も少ないのは日本の民族文化の異常さをよく示しています。私は戦後派歴史学は神話研究を始めるにあたって津田ではなく、厳密に本居・平田を読み直すところから出発すべきであったと考えています。
なお本居が『古事記伝』で展開した神道神学では、この二神の神名語尾のムスヒをムスコ・ムスメのムス(産す)であって万物生成の神であり、民族神話の主神であるとしています。このタカミムスヒの神殿は奈良で奈良文化財研究所に行かれることがあれば、奥まで行きますと、参詣することができます。平城京東院の宇奈太理(うなたり)坐高御魂(タカミムスヒ)神社です。これが都城の付属神殿であることは上山春平『埋もれた巨像』のいう通りです。
Ⅲ天孫降臨神話についてーー本来の司令神はタカミムスヒ
さて私はこのタカミムスヒはどういう神なのかについての本居の見解は神学としては成立するとしても神話学的には抽象度が高すぎると思います。つまりこの神は、高千穂に神が降りてきて天皇家の祖先になったという天孫降臨神話の至上神・司令神です。対アジア・アメリカ戦争以前は、これがあたかも事実であるかのように語られ教えられたのですが、肝腎なのはその中身です。
故(かれ)、爾して天津日子番能邇邇藝(あまつひこほのににぎ)命に詔(の)らして、(イ)天の石位(いわくら)を離(はな)ち、(ロ)天の八重の多那(たな)雲を押し分けて、(ハ)伊都能知和岐知和岐弖(いつのちわきちわきて)、(ニ)天の浮橋に宇岐士摩理蘇理多多斯弖(うきじまりそりたたして)、竺紫(ちくし)の日向の高千穗の久士布流多氣(くじふるたけ)に天降り坐しき。
これは『古事記』の天孫降臨条ですが、その意味は皇孫ホノニニギが(イ)天蓋から押し放たれた岩船に乗って、(ロ)天に上る八重の噴煙を押し別けて、(ハ)稜(いつ)の霊(ち)(雷(いかつち))が涌く中を、浮橋のように岩雲や火砕流が浮き沈みそそり立つ高千穂峰に天降ったということです。天=天蓋は中国も日本でも昔から岩盤でできているという宇宙観です。だから天石屋戸があるのですが、そこには割れ目もあって緩んだ岩を押し離して船にして神が降りてきた。これは巨大な火山弾でしょう。ようするにこの神話は高千穂峰の噴火の時に火山雷のように神が降り立ったという火山神話なのです。ゼウスが雷電の神であり、火山の神であるのと同じことです。ギリシャと日本は火山地帯ですから神話がよく似てくるのです。
平田『古史伝』は下記の『日本書紀』顕宗三年条に注目して、タカミムスヒは天地鎔造神であり、日本神話の創造神だとしました。
我が祖高皇産霊(タカミムスヒ)、預(はや)く天地を鎔造(ようぞう)する功有り。民地をもって、我・月神に奉れ。
「鎔造」は鎔鉱炉の「鎔」に「造る」ですから、鎔鉱炉のようにして天地と日月を創造したということです。世界の創造は火山の大噴火によって行われたということです。八世紀にさかのぼる文字史料でここまで明瞭な宇宙創造神話(コスモゴニー)は世界にもなかなかありません。日本には宇宙創造神話(コスモゴニー)として見事に整った神話がある。それを子どもたちに伝えること、それを通じて日本社会の常識を変えていくことは歴史学・神話学にとって非常に大事なことです。ここで、これ以上詳しいことを説明する余裕はありませんので、「古代史」の史料読みの訓練のある方は、この天地鎔造神話が新嘗祭の祭儀神話の基本であったことについて菊地照夫(2016年)を参照していただきたいと思います。
Ⅳイサナミの国生み神話ーー五世紀以前、古墳・弥生時代の神
火山神話は倭国神話の基本でした。つまり松本信広『日本神話の研究』などで明らかなように、イサナミ・イサナキの国生み・神生み神話も同じ火山神話です。天の浮橋は天孫降臨神話と同じ噴火にともなう岩雲などのイメージで、彼らはその噴火雲に乗っかって、下を見たら水だらけだから掻き回して、そこに降りて「八尋殿」(高殿)を立ててミト((三角))のマグワイをして、国土、神々を生んだという物語です。三角形は世界中で女性性器の象徴です。天孫降臨神話でもホノニニギは降臨の後に海辺で出会ったコノハナサクヤ姫と八尋殿であう訳ですから同じ構図です。
これは南太平洋、特にポリネシアやインドネシアの火山神話の系統を引いたものだというのが松本以来の神話学の定説です。興味深いのは次のインドネシアのモルッカ諸島のセラム島の神話です(大林太良、1991年)。
昔、天父神と地母神が性交していた。子供のウプラハタラ、弟ラリヴァ、妹のシミリネは住む場所がなく、ウプラハタラが天を上に押し上げた。この天地分離の際に大地震が起こり、火が地中から生まれ、山々がそびえ立った。ウプラハタラは、樹脂の火球を天にほうり上げて、日と月を作った。
天空ウラノスと大地ガイアが性交しているので、子供がその鬱陶しさに耐えられず、クロノスが大鎌をふるってウラノスの陽根を切り取り、天地が分離した。
天父神はイサナキ、地母神はイサナミ、ウプラハタラはスサノヲ、ラリヴァはツキヨミ、シミリネはオホヒルメにあたることは明らかです。天地が分かれた時に大地震が起きて大地が割れて、そこから火が噴き出して山ができ、同時に月と日ができたというのですから、天地鎔造の神話やイサナ二神のジャパネシア創造神話と同じことです。
なおイサナミは神を生むのですが、神生みの最後に火の神を生み、その時ミホトに大火傷をして死んでしまい出雲地下の「根の堅州の国」に行ってしまう。「堅州の国」とは「鍛すの国」、つまり鍛冶の国ということで、地下の鍛治の国です。ギリシャ・ローマ神話では、へファイストスだとか、バルカンだとかが火山の地下でトンテンカンしていたのと同じことです。
さらにイサナキのイサナは「鯨=勇魚」であることについてもつけ加えておきたいと思います(保立2021)。そしてキは男の意味で、イサナミのミは女の意味ですから、イサナ神神話は鯨男・鯨女の神話ということになります。原田大六はこの雌雄の鯨神がマグワイをして列島を生んだというのが国生み神話だといっていますが、たいへん南方の雰囲気が強いものです。
Ⅴカムムスヒと神祇官の齋竈(いつへ)神殿
次ぎは造化三神の最後のカムムスヒがどういう神であったかという問題です。平田『古史伝』は、これについて「神皇産霊神は女神に坐々(ましま)して産霊(むすひ)の内事を掌給ふなる」「御厨」の「炊(かしき)」「竈(かまど)」の神であると示唆しています。中村啓信「タカミムスヒの神格」(『古事記の本性』おうふう、2000年)も同じ結論です。学界ではまったく無視されてきましたが、これが正しいと思います。
私は、『歴史のなかの大地動乱』で八・九世紀の地震と火山噴火の通史を書きました。その時は平田のものをまったく読んでなかったのですが、神話研究に進んだ後に、やはり読んでおかねばということで本居『古事記伝』を読み、あわせてその注釈書として平田の『古史伝』を読みました。ショックだったのは『古史伝』が八・九世紀の火山史料を集めて見事な分析をしていたことです。平田というと狂信的な超国家主義者だというのが一般的な見方ですが、これはただの不勉強にもとづく偏見で、実際に読んでみて偉い学者であることを知りました。日本の学問は江戸時代と明治時代でがらっと変わり、その中枢はほとんど欧米風、近代ヨーロッパや近代帝国を讃美する官僚的な学問になってしまいました。もちろん学問を実証的なものにしていくのは学者の職業的義務で、その中で対アジア・アメリカ戦争の後、学問が進展してきているのは事実です。しかし人文学全体をみた場合、本居・平田のような日本独自の学問は大事なものです。
さて、学び舎教科書には「『常陸国風土記』に書かれた富士山と筑波山」というコラムがあります。つまり『常陸国風土記』には「神祖尊(カムミオヤノミコト)」という偉い母神が富士山に行ったところ、富士の女神が今日は新嘗祭の日だから母親でも宿をすることはできませんと言われ、何という娘だと言って怒って、筑波山に行き、筑波山でも今日は新嘗祭だけれども何しろお母さんですから歓待しますと言われて、それで富士を呪い筑波を褒めたという話しがのっています。そのせいで富士はいつも雪に閉ざされて誰も登らない、筑波はみんなやって来る良いところになったという訳です。
平田はこの「神祖(ミオヤ)尊」を「母神」であるとし、カムミオヤノミコトと読んでいます(『古史伝』一四九段)。カムムスヒは神産巣日(カムムスヒ)御祖命とも表記されますので、「神祖尊」と同じだというのです。『風土記』注釈のうちでも『東洋文庫』の吉野裕による解説は「祖神(おやがみ)は母神で、おそらく産霊の神である」としていますが、これが正しいでしょう。このとき母神は「諸神の処を巡り行でました」とありますから全国を回ったのですが、富士は火山で、筑波は地下で固まったマグマだまりが地上に露出したもので火山ではありませんが、男体山より女体山の方が高く磐座が嶮しく、火山と思われていたのだろうと思います。「神祖尊(カムミオヤノミコト)」は全国の山の神の母親で、火山の女神たちはその娘だったのでしょう。
教科書にもあるように、この物語で面白いのは富士の女神は「今日は粟(あわ)の新嘗(にいなめ)の収穫祭の夜で物忌の最中なので、申し訳ないが駄目です」といったということです。この新嘗は新たな穀物を竈で調理する儀式ですから富士の女神は、その日は竈の世話で大忙しだったということになります。そしてその竈は噴火口のイメージでした。実際に八六四年の富士噴火の一〇年ほど後に書かれた都良香(みやこのよしか)「富士山記」では、山頂の噴火口が「炊甑」といわれていて、その底に周囲を青竹の林でかこまれた純青の「神池」があって、「甑(こしき)の中」からは「常に気ありて蒸し出づ」、「甑の底を窺うに、湯の沸騰する如し、その遠くにありて望まば常に煙火を見る」といわれています。火口が竈であってそこに甑がはめ込まれているのが火山だというのです。詳しくは右の『歴史のなかの大地動乱』をみていただきたいと思いますが、ほかにも火山は大地に埋め込まれた竈・甑・瓫・壺などのイメージで描かれていますし、噴火のことを「蒸す」といっている史料があることも注意を引きます。
さて、そもそも竈は日本にはない文化で、五世紀に韓国から入って来たものです。竈・窯業・鉄工などの技術、火の技術が一挙に入って来たのですが、それと一緒に竈神の習俗もやって来たのでしょう。大雀((仁徳))大王の「民の竈はにぎわいにけり」などという話しもその中で作られたのです。そういう時代に火山を竈とみる自然観がうまれた、カムムスヒの神格が成立した訳です。これは世界の神話に普遍的なことです。たとえば、「出エジプト記」でシナイ山へ降臨してモーゼに神託をあたえたエホバもまずは雷神として現れますが、その部分を一部省略して引用しますと「雷と稲妻と厚い雲とが山上にあり、ラッパの音がはなはだ高く響いた。シナイ山は全山煙った。主が火の中にあって、その上に下られたからである。その煙は竈の煙のように立ち上り、全山はげしく震えた」とあります。シナイ山は火をあげる竈だということです。
こうしてタカミムスヒは火山雷の男神、カムムスヒは火山の竈の女神で二神が協同して噴火して世界を作るという世界創造神話ができたのでしょう。面白いのはタカミムスヒとカムムスヒ、男の神と女の神、どちらが先にできたのかということで、韓国からの竈の普及状態からみてどうも女神の方が先にできたようです。かって益田勝実は『火山列島の思想』で「山は、まず火の神であることにおいて神なのである。この自明なようなところへ、日本の神道史学の山の神の探究をもどしたい」と、火山を無視しがちな従来の山岳信仰論を批判したことがあります。「山の神は火の山の神として生きており、静止した山の威容によってではなく、その躍動的な活動によって神としての力を確認させた」「<神の火>が日本民族の精神史の課題とならざるをえないのは、このような不断の民族的体験にかかわっている」というのです(益田1965)。それにつけ加えておけば妻を「山の神」というように日本の山神は女神であり、カムムスヒはその頂点にいる「神祖尊」だったということになります。
なお、このカムムスヒの神殿がどこにあったかというと、先にふれた平城京の宇奈太理坐高御魂神社は内裏の東院区画にありましたが、そこから広場をこえて西にいったところに神祇官がありますが、そこの齋戸(いつへ)神殿にありました(「戸」は「へ」と読んで竈の意味)。『竹取物語』に石上麻呂が大炊寮の屋根燕の巣を探って、誤って竈の上に落ち死んでしまったとありますが、この竈は「八十嶋の竈」と呼ばれる日本を象徴する竈でした(保立2010)。ただこれは実際に炊飯に使うので、その南側に神祇官を置いて祭祀だけの竈を作ったのです。こうして平城京では宇奈太理坐高御魂神社と神祇官齋竈(いつへ)神殿は東西にならんでタカミムスヒとカムムスヒが鎮座することになりました。
Ⅵアマテラスの登場と至上神の交代
七世紀半ば過ぎまでは確実にこのタカミムスヒとカムムスヒが日本神話の至上神だったのですが、まず天武の時代にアマノミナカヌシが至上神の位置につきました。しかし、これが天武の死によって破産すると奈良王朝は王権神話をあまり重視しなくなります。その表現が最初に引用した『古事記』冒頭節の最後に「この三柱の神は、並(とも)に独神と成りまして、身を隠したまふ也」とあることです。神話の神は自ら「独神」となって身を隠したという訳ですが、これは神話の神の位置が低下したことを、アマノミナカヌシ・タカミムスヒ・カムムスヒ自身が身を引いたという形で表現した一節です。
これは律令制の支配や官僚機構の法律思想や儒教文化が本格的に展開する時代の雰囲気の中で神話の時代が完全に終わったということです。もちろん、儀式の神としてはタカミムスヒとカムムスヒはカムロギ・カムロミと名を変えて残っていますし、アマノミナカヌシは伊勢神道の神として残るのですが、すでに実際には神話の至上神ではありません。それに代わってアマデラスが名義上は至上神の地位を占めます。『古事記』冒頭節の「身を隠したまふ」というのは、代わりにアマデラスが登場したという意味を含んでいます(金井清一2022年)。
そもそも「天照」という神名は王が国土に「照臨」するという中国儒教の文言から流用したもので、本居流にいえば「漢心」の神、一種の概念神・理念神です(平松秀樹1993年)。持統は夫の天武とは違って現実的な女帝であまり神話や宗教にこだわる女性ではなかったと思いますが、中国と同じように天皇の祖先神を祭る場は必要ですから、それを都から離れた伊勢にもっていくという判断をしたのでしょう。また持統の諡(おくりな)は「高天原広野姫天皇」といいますが、この高天原の女神とは明らかにアマデラスのことです。奈良王朝の形成を実際上主導した持統の権威は決定的でしたから、しばしばアマデラスに持統のイメージが入っているといわれるのも正しいと思います。ようするに伊勢内宮には天武がアマノミナカヌシとして持統がアマデラスとして合体して祭られていたのでしょう。ここで本来の太陽女神としてのオホヒルメの性格は大きく変わりましたが、前述のように外宮のトヨウケ姫は月の女神ですから、それに対照させて内宮の神は、結局アマデラスに代表された訳です。
なお「天照」という修飾語は本来は月にかかるものであったことも明らかになっています(神野富一1999)。太陽は空間自体を明るくするもので、「天照」はむしろ青く暗い夜空を満月が照らす様子の描写なのだと思います。太陽神を「天照」としたこと自体が「漢意」のやり方で伝統的な語法に忠実なものではありませんでした。なおアマデラスという名前は『万葉集』には一切でてきません。また『更級日記』の記主も、この神の名前を知らなかったということもよく知られています。アマデラスの神名が流通するようになったのは正確に確認してませんが、11世紀半ばくらいからではないかと思います。
さて下記は神話戦争の旗印になった天壌無窮(てんじようむきゆう)の神勅です。昭和の皇国主義の下で「神武・綏靖・懿徳・安寧ーー」という天皇系図を小学生が暗記させられたことがよく強調されていますが、この神勅も文部省著作『小学国史』(上巻, 1940年)以降の国定教科書の冒頭にかかげられました。
「豊葦原千五百秋瑞穂国(とよあしはらちいほあきのみずほのくに)は、是、吾が子孫の王たるべき地なり。爾(なんじ)、皇孫(すめみま)、就(い)でまして治(しら)せ。行矣(さきくませ)。宝祚の隆(さか)えまさむこと、当に天壌と窮り無けむ」
『日本書紀』(九段異書一)
以上のような経過からも明らかなように、これは律令国家の御用学者が作った「漢意」そのものの美文です。これは本来の神話といううべきものでないというのは、実際上、学界の一致点です。なお『現代語訳 老子』(ちくま新書)で解説をしたことがありますが、「天壌無窮」とは本来は『老子』第七章の「天長地久」を言い換えたもので、『老子』の趣旨は「天は長大であり、大地は久遠である。それを前にして私の存在は無となるが、しかしそれによって始めて自分が自由な自分になるのだ」ということです。だから、これを王権の自画自賛に使うのは滑稽なことですが、唐の玄宗皇帝は、『老子』本章を典拠として自分の誕生日を「天長節」と称したのですから、これは東アジア全体の問題です。
いろいろな意見はあるでしょうが、私は、そのような背景を説明し、『老子』の文章も紹介して、小学生に、この天壌無窮(てんじようむきゆう)の神勅を紹介して漢文の勉強をしてもらったらどうかと思います。歴史的事実である以上、皇国主義教育の下でこういう文章を暗記させられたという事実は小学生に伝えた方がよいのではないでしょうか。
おわりに
私見では、倭国神話の時期区分は、五世紀に前期的な神話の集約としてのイサナ神神話からムスヒ神神話に変化し、そのムスヒ神神話が七世紀まで続き、天武が道教的なアマノミナカヌシを至上神として神話時代の終焉を告知し、持統の時代に神話ならざるアマデラスが伊勢に誕生したということになります。
歴史学が、この問題を整理しなければならないのは、本居・平田、さらには柳田国男と折口信夫が見つめてきた民族宗教としての神道の意味を確認するためでもあります。そのためには本居・平田が切り開き、日本の神話の至上神をタカミムスヒ・カムムスヒとしたことの意味を、火山列島日本の現状の中で捉え返すことが必要だと考えています。ジャパネシアが火山・地震列島であるということは神話時代からまったく変わらない、私たちの運命であり、原発のことを考えても、私たちはそれをよく見つめ直さねばなりません。
さて、御承知のように、そういう解明の基礎を作った本居・平田の産霊神道は明治国家の皇国主義の中で系統的に排除されました。産霊神道の排除はいちはやく1889年の宮中三殿、つまり賢所(かしこどころ)(伊勢神宮の八咫鏡の形代)、皇霊殿、八神殿の三殿の建設によって決定されます。そこではカムムスヒ・タカミムスヒは八神殿に祭られる神に押し籠められました。三分の一のさらに八分の二ですからムスヒ二神は一二分の一以下という地位です。また出雲の大国主命も出雲大社のみの神と扱われたこともよく知られています。
これによって歴史上始めて日本神話の至上神はアマデラス唯一神であるということになり、それを前提として大日本帝国憲法の明治天皇告文は「天壌無窮の宏謨(こうぼ)に循ひ惟神(かんながら)の宝祚(ほうそ)を承継し」と述べ、同憲法第一条において「大日本帝国は万世一系の天皇之(これ)を統治す」と規定された訳です。それは神話戦争としての対アジア・アメリカ戦争の思想条件となった『国体の本義』に、「大日本帝国は、万世一系の天皇、皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給う。これ、我が万古不易の国体である」と引き継がれたことはいうまでもありません。
私は、このような神話の問題を歴史の研究と教育がどう考えるべきかについて、もう一度議論することが必要だと考えます。これはさまざまな考え方があると思います。その議論の状況はたとえば遠藤芳信(1992)が教育学の立場から論じていますが、今後の議論の参考のために、以下、1955年に発表された益田勝実の「海さち山さちーー神話と教育」という文章の一節を長くなりますが引用して御紹介したいと思います。
戦後の歴史教育は、神話をもって語り始められる従来の歴史教育の否定から出発した。神話を考古学で置きかえて、確固とした事実をもって教える。こういう態度は基本的に正しいものであった。
しかし、(中略) 神さまの話は古代の天皇家が自分勝手にねじ曲げてつくったものだ、とだけきめこみ、それをネグレクトして進むところには、皇室神話にねじ曲げられない神話本来のものをあきらかにして、それによって祖先たちの魂の歴史をさぐり、そこに反映している祖先たちの生活のたたかいの経験を豊かに汲み上げていく道はひらけない。生徒たちが実際に魅力を感じている事実を認め、それを正しく発展させることができない。まして、子供の世代の科学的な勉強が親たちの世代へおし上げ、社会全体の歴史認識が新しい方向へ進んでいくような契機も見いだせないであろう。神話の本質をあきらかにし、歴史的に正しく位置づける必要を、社会科の良心的な教師たちは、今痛感している。
引用文献
上山春平『埋もれた巨像』岩波書店、一九七七
遠藤芳信「社会科古代史教育における神話と祭記の位置づけ」『北海道教育大学紀要』43巻第1号、1992年
大林太良『神話の系譜』講談社学術文庫、1991年
金井清一「身を隠したまふ神」、同『古事記編纂の論』花鳥社、2022年
神野富一「万葉の月――照る・照らす小考」『甲南女子大学研究紀要』(36) 、1999年
菊地照夫「ヤマト王権の新嘗と屯田ーー顕宗三年紀二月条・三月条に関する一考察」、同『古代王権の宗教的世界観と出雲』、同成社、2016年
菊地照夫「スサノヲ神話の形成に関する一考察――出雲降臨神話をめぐって」『出雲古代史研究』25号、2021年
新川登喜男『道教をめぐる攻防』大修館書店、1999年
筑紫申真『アマテラスの誕生』講談社学術文庫、2002年
中村啓信「タカミムスヒの神格」同『古事記の本性』おうふう、2000年
原田大六『実在した神話』学生社、1966年
平松秀樹「天照らす考ー照臨の思想との関わりにおいて」『古事記年報』35号、1993)
保立道久『かぐや姫と王権神話』洋泉社新書、2010年
保立道久『歴史のなかの大地動乱』岩波新書、2012年
保立道久「老荘思想と倭国神話」伊東貴之編『東アジアの王権と秩序』汲古書院、2021年
西宮一民校注『古事記』、新潮日本古典集成、1979年
益田勝実『火山列島の思想』筑摩書房、1968年
益田勝実「海さち山さちーー神話と教育」『益田勝実の仕事』5、ちくま学芸文庫、2006年
松本信広『日本神話の研究』東洋文庫、1971年
水林彪『記紀神話と王権の祭り』岩波書店、1991年
溝口睦子『アマテラスの誕生』岩波新書、2009年
吉野裕子『大嘗祭』弘文堂、1987年
なお「保立道久の研究雑記」https://note.com/michihisahotate/にいろいろ書いていますので御参照ください。

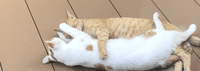
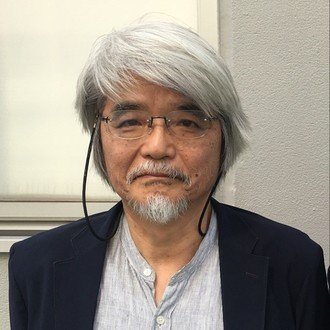
コメント