奥山俊宏教授(上智大学 文学部新聞学科)の質問への回答
質問1)
「弁護士 徳永信一」名義のXアカウントは11月24日午後、「外部通報と内部通報の区別もわからず真実相当性の必要に思い至らなかったのが奥山教授」と投稿しました(https://x.com/tokushinchannel/status/1860558793047966067)
これは徳永信一先生のご投稿であること、間違いありませんでしょうか?
■質問1に対する回答:
確かに僕の投稿です。↓もとの投稿を再現します。
"だから元局長の告発書(外部通報としての)を見た弁護士はみんな公益通報として保護されないと言っていますよ。真実相当性が無いからですよ。 これがあるはずだと憶測を述べたのが山口弁護士。外部通報と内部通報の区別もわからず真実相当性の必要に思い至らなかったのが奥山教授。"
質問2)
上記のご投稿は私(奥山)につき、「外部通報と内部通報の区別もわからない」との事実を読み手に示すものですが、それは真実ではありません。
たとえば、筆者は昨年9月5日、兵庫県議会の百条委員会で、次のように内部通報と外部通報を区別して述べており、その原稿はインターネット上で公開されています。
「西播磨県民局長だった人による文書の送付先は、当初、報道機関など外部でした。ですので、ここで言う内部公益通報には該当しません。しかしながら、その後の4月4日、西播磨県民局長だった人は、兵庫県の正式な内部通報窓口に通報したというふうに報道されています。これについては、内部公益通報に該当し…」(https://slownews.com/n/nd7f71de04bff)
これを見れば、私(奥山)が外部通報と内部通報を区別して話していることは明白です。
こうした私(奥山)の言葉はインターネット上で簡単に探し出すことが可能であり、にもかかわらず、私について、「外部通報と内部通報の区別もわからず」と述べるのは度し難いことであり、デマに該当する、と考えられます。
これについて、徳永先生のコメントをいただけないでしょうか。
■質問2に対する回答:
まず、第1点は、「外部通報と内部通報の区別もわからない」という表現(以下「本件表現2」といいます。)は、事実の摘示ではなく、意見論評です。最高裁判例は、証拠をもって立証できるものが事実であり、立証できないものが論評だとします(最判平成9年9月9日)。奥山教授の理解度ないし習熟度は証拠をもって立証できるものではなく、あくまでも評価であり、意見論評の範疇にあります。
さて、本件表現2は、山口弁護士の憶測を引き合いにだして「真実相当性」について焦点を当てるという文脈を背負っています。そこでいう「外部通報と内部通報の区別もわからない」は、明らかに内部通報と外部通報の保護要件の違い、すなわち、前者については「思料」が保護要件ですが(法3条1号、5号1号、6号1号)、後者は「真実と信じる相当な理由(真実相当性)」が必須の保護要件とされています(法3条3号、法5条3号、法6条3号)。
その「区別」について意識した文脈があります。ところが奥山教授は、真実相当性の有無について論及することなく告発者の探索は禁じられていると主張しておられるようです(百条委員会証言)。つまり、奥山教授の告発者探索の禁止に関する言及は、「外部通報と内部通報の区別」を弁えていないものと評価できます。
奥山教授の発言(本件通報においても通報者の探索が禁じられている)は、「保護要件の違いに関する外部通報と内部通報における区別」を弁えていないものであり、これを前提事実とする意見論評です。滑稽なことに、これを「度し難いことであり、デマに該当する」と大上段に振りかぶっていう奥山教授のご主張は、法的知識に基づくリテラシーに欠けた告発だという僕のコメント(意見論評)を裏付けるものになります。正当な論評(Fair comment)の要件を充たすものだと自信をもっています(名誉毀損訴訟におけるフェアコメントの要件は、前掲最高裁判決を
ご参照)。増山県議と奥山教授とのやりとりの一部をX上で拝見しましたが、増山県議に軍配を上げざるをえません。奥山教授の事実摘示と論評表現との区別(ここは名誉毀損訴訟に習熟する上で一番重要な関所になります。ここは表現の自由の中核である意見論評の自由に対する重要なセンス、すなわちリテラシーです。)に関する理解が不十分だと思えます。他方、これを弁えて理解した兵庫県民のリテラシーは大したものだと評価しています(「情況」のインタビュー記事参照)。
質問3)
上記のご投稿は私(奥山)につき、「真実相当性の必要に思い至らなかった」との事実を読み手に示すものですが、それは真実ではありません。
たとえば、筆者は昨年9月5日、兵庫県議会の百条委員会で、真実相当性が必要である場合に繰り返し言及しており、次の言葉はその一例です。
「2号通報、3号通報といった外部への内部告発については、その通報内容について信ずるに足りる相当な理由、真実相当性と呼んでおりますけれども、それがあったことが公益通報者保護法による保護の対象となるための要件となっています」(https://slownews.com/n/n1d2b4e5d3589)
場合によって真実相当性が必要だと私(奥山)が考えていることは、筆者が百条委員会で述べた内容を聞けば、それだけで容易に分かります。あるいは、筆者がインターネット上でだれでも見られる状態で発表した原稿に目を通せば、それだけでも容易に分かることです。
こうした私(奥山)の言葉はインターネット上で簡単に探し出すことが可能であり、にもかかわらず、私について、「外部通報と内部通報の区別もわからず真実相当性の必要に思い至らなかった」と述べるのは度し難いことであり、デマに該当する、と考えられます。
これについて、徳永先生のコメントをいただけないでしょうか。
■質問3に対する回答:
「知っていることと、分っていることとは違う」という格言に思いをいたしてください。奥山教授は、内部通報と外部通報とでは、真実相当性などの保護要件の違いがあるということを知っているにもかかわらず、告発者の探索の禁止という通報者の保護が問題になっている局面で、その保護要件の違いを無視して探索の禁止を論じておられます。実際の適用場面において保護要件の違いを失念していたと判断するしかないわけです。うっかりミスなのではないでしょうか。そのような誤解に基づく証言を百条委員会の場でなされたわけですから、「わかっていない」と判断されてもしかたがなく、僕はそれをもって「真実相当性の必要に思い至らなかった」と表現しているわけです。もし確信に基づくものであれば、論評のレベルにおける見解の相違でしょう。これをデマ(事実に反する扇動的な宣伝)だというデマを流すのはいかがなものでしょうか。
奥山教授は、真実相当性の保護要件については知っているといっています。ご存じだと僕も確信しています。しかし、肝心な法適用の場面でそのことを失念しておられます。そういう初歩的ミスを犯すようでは、これを理解している、あるいは習熟しているとはとてもいえません。とても「専門家」とはいいがたい。そういう生半可な知識をもった人に対する揶揄と諦めの表現が「あいつはなんにもわかっておらん!」という日常言語に込められているのだということに学んでください。類似の事態を評する格言としては「論語読みの論語知らず」というのもあります。
質問4)
「弁護士 徳永信一」名義のXアカウントは11月22日、山口弁護士を名指しして「改心したようです」と投稿しています。(https://x.com/tokushinchannel/status/1859961894779625673) 他方、山口弁護士は、自身のブログで2025年1月27日、意見を変えたとの噂がFacebookやXなどで流れていることに触れて、「もちろん意見を変えたことは一切ありません(なぜそのような風説が流れるのか不思議でなりませんが)」と書いています。
(http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2025/01/post-b6ef05.html)つまり、徳永弁護士の「改心したようです」とのご投稿は真実ではなく、デマである、というふうに考えられます。 これについて、徳永先生のコメントをいただけないでしょうか。
■質問4に対する回答:
僕は、山口弁護士が百条委員会で行った証言のパワポ原稿を読んで勉強させてもらいました。うまく整理されていてとても参考になったのですが、13頁(第3段)に、怪文書の真実相当性に関する言及があるのですが、これを読んで仰天しました。そのことは『情況』のインタビュー記事にも言及してあるので省略しますが、率直にいってこれは公益通報の専門家としての発言ではなく、社会活動家の発言だと思いました。告発文書の真実相当性の具備を検討すべき流れの中で、「県民局長クラスの職員による外部通報である以上、通報事実について単なる伝聞憶測ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述があると思料され」とあり、肝心の告発文書の通報対象事実の「真実相当性」の具備が吟味検討されることなく、山口弁護士の揣摩臆測をもってスルーされているのですから。僕はこれをみて、山口弁護士は、告発文書の内容を読んでいないのだと推論的に判断しました。なぜなら、告発文書には五百旗頭氏の死亡原因が斎藤知事の人事にあるような憶測からはじまり、伝聞やうわさ話であることを明示し、斎藤知事の下で働く職員らに対する実名指摘による悪意ある誹謗中傷に満ちていたからです。もし、これを読んでいたら、前記のような表現を行うことはないはずだという推測は合理的です。そして僕は繰り返し繰り返し、山口弁護士の弁護士としての社会的評価を低下させること必至である上記発言をXで行いましたが、ついに山口弁護士からは何のコメントもありませんでした。僕の厳しい批判にもかかわらず、何らの応答もないことに照らし、僕は、山口弁護士は僕の批判をもっともなものとして受け入れ、上記の考えを事実上入れ替えたと判断したのです。それが「改心したようです。」の表現の基礎です。
ところで奥山教授によれば、山口弁護士は、令和7年1月27日に「むろん意見を変えたことは一切ありません」とブログで発言されていることを根拠として僕の表現がデマだとしているようです。しかしながら、山口弁護士は、一体全体なんについて自らの言説にかかる「意見」を変えていないと表現しているのでしょうか。僕の知る限り、山口弁護士は、僕の指摘(告発文書を読んでないのだろう。読んだのならあのような、「県民局長クラスの職員による外部通報である以上、内部資料等や関係者による信用性の高い供述があると思料した」という軽率な発言はしないはずだという推論(事実に基づく批判)に対する反論は未だになされていないようです。「意見を変えたことは一切ありません」という言明は、漠としてなにを否定しているのかもわかりません。つまり、僕の前記推断に対して否定なのかすらわかりません(多分、そうではないと思います)。
すなわち、山口弁護士が、敢えて、県民局長の怪文書を読んだ上での発言であるとか(例えば、「読んどるわい。その上での発言じゃい」)、怪文書に真実相当性がある根拠(例えば、実際に誰から証言を得てるとか。内部資料等があるとか)に
ついて具体的に語らないままです(彼の指摘には、幹部職員の通報だから根拠があるはずだという浅薄な推論しかありません。おそらく匿名にしたのは幹部職員がかかる怪文書をばら撒いていたということを隠したかったのでしょう。それが単なる
フェイク文書だということがただちに判明するからです)。ですので、従前の自らの発言(本件告発文書は真実相当性を充たしている「はずだ」。)についても言及していないところをみると、やはり,自身の発言が間違っていたことを自覚しているという意味において「改心」されたのだなと今でも感じている次第です。
つまり、僕の前記発言は、前提たる事実(山口弁護士は告発文書を読んでいないのではという僕からの不名誉な批判(山口弁護士は、きちんと問題の告発文書も読まずに、真実相当性があると思い込んで証言している。)に対する山口弁護士からの反論がないという事実に基づく合理的な意見論評であり、「公正な論評」、すなわちアメリカの連邦最高裁にいうフェア・コメントだということができると考えております(前掲最判参照)。
以上のとおりです。再反論、突っ込み、なんでも歓迎します。「情況」でも語ったとおり、僕の「弁護士德永信一」というクレジットを信じて斎藤知事を応援した多くの兵庫県民の判断の正当性に対する責任を背負っていると考えております。僕の
投稿を「デマ」だと論評されるのであれば、公開討論でもなんでも応じて自身の正当性を論じるつもりです。大げさに言うと僕の発言を理由に事態と情況の真実を判断し、奥村教授や山口弁護士による不当な論評が間違っていると判断して斎藤知事に投票した良識ある県民の判断の正当性を守るために僕がしなければならない義務・責務・使命だと考えている所以です。
兵庫県民111万人がなぜSNSの真実を信じ、マスコミなどのオールドメディアに背を向けたのか。昨年の地滑り的逆転現象についての分析を極めることは、オールドメディアから敵視され、イーロンマスクやザッカーバーグのSNSを基盤にしたトランプが圧勝したのか。そして日本ではオ―ルドメディアとの敵対を掲げた立花というトランプと同じく怪しげな(だと、オールドメディアによって捉えられていた。)人物を押し上げたのか。そんな現在という不可解な「情況」を解明し、その構造を理解する上で不可欠な知的営為こそが、知識階級であるはずのインテリに期待されている作業のはずです。「情況」の塩野谷恭輔の巻頭論文「戦後80年の症状」は読まれましたか、僕は感心しました。彼の問題意識を支持します。神の手から真実を奪った近代的知性は、唯物論的無神論のなかで、再び真実を見失ってしまっているのです。僕の使命は、まず、そのことを見つめることで、我々の現在地を明らかにすることです。そのなかの題材として統一教会に対する解散命令請求をという宗教弾圧とオールドメディアが背負っていた公的真実という幻影の崩壊があります。さてこの先、トランプや立花といった怪物たちが引き裂くように切り開いていく現在の向こうにどんな真実がみえてくるのでしょうか。悪夢かもしれませんが、先の見えたリベラルの幻想とはちがうものでしょう。僕は知的な好奇心と期待でわくわくしています。
以上

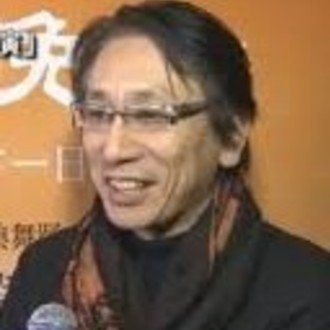
コメント