【メモは資産】過去の自分と記憶を"同期"する方法
“頑張れ”という言葉が、私には一番堪える。
――なぜなら頑張る方法がわからないからだ。
大学の同期はみんな、毎日真面目に授業を受け、レポートを書き、テスト勉強をし、テストで良い点を取って単位を取る。
それに対して私は、授業中はイヤホンをつけてDiscordで話したりYoutubeを見たりする。レポートはいつも適当な海外サイト3つくらいから引っ張ってきて和訳して調整し、提出。テストは勉強をしないから、まるでガチャに頼っているようなもの。
こんな生き方は良くないとわかっている。でも、努力の仕方がわからない。
自分がどう「努力」すればいいのか、何を目指して頑張ればいいのか
――その方向すらわからずに、日々をただ消化するように送っていた。
なにか、他の勤勉な人の「努力」を上回る、画期的な方法はあるのだろうか? 私はそんな、「一発逆転」の方法を考えて、彷徨っていた。
筆者はこんな人です!
筆者の著書はこちら! 【Amazonベストセラー1位ありがとうございます!】
※カテゴリ。本全体では81位
ブックカフェで読書していると…
ある水曜日、私は授業を”自主休講”してショッピングモール内のブックカフェに行った。
私はカプチーノを注文した後、隣の書店で読む本を探していた。
そんな私がふと目にしたのが、いわゆる「自己啓発本」の数々だった。ショッピングモールにあるブックカフェには自己啓発やビジネス書がずらりと並んでいる。
私はいくつかの本を手に取って、読んでみた。自己啓発本に書いてあることは当たり前で心象的なものが多い。早起きしろ、早く寝ろ、モーニングルーティンを大事にしろなど、いかにも「正論」らしい文句がずらりと並んでいた。
「ほっといてくれよ…。」
思わず愚痴を零した。
一方で、「メモを書け」「日記を書くとよい」といったアドバイスが共通して書かれていることに気づいた。
「これは何の意味があるんだろう?」
正直なところ、私には文章を書くスキルなんてない(当時)。だから、いざ日記といっても、最初はどこから手をつけていいのかまるで見当がつかなかった。ただ、ふと思いついたアイデアを書き留めておけば、レポートを書くのに役立つかもしれない。
そんな淡い期待を抱きつつ、私はメモを書いてみることにした。しかし、そんな都合良く書くことが思いつくわけがない。
そこで他の本も何冊か読んでみると、いくつかの本には、「人の脳は言葉よりも情景を覚える方が得意」と書いてあった。
それを見て、特別なアイデアが浮かばなくても、日々の行動履歴をざっと書き留めることから始めてみた。
半年後
数か月がたったある日、大学のレポートやプログラミングの勉強内容を整理するために、さらに詳しい文書を作ってみようとした。
私は普段は何もやろうと思わないのに、ふとしたときにやろうとする。思い返してみても、何のきっかけもないので、書いている本人もよくわからない。
書式やテンプレートを調べ、見出しや章立てをきれいに整え、加筆する。書き終わった直後は大きな仕事をやり遂げた気がして、妙な達成感もあった。
しかし、半年ほど経っても、その文章が読まれることはなかった。後から探そうとしても、大量に文章があってどこにあるか分からない。それに、綺麗に見える文書でも、自分で見るとなにか冗長だし、どこに何を書いたか全く覚えていない。
書くのに何時間かけたか分からない、「努力の結晶」とも言える文章の塊が、全く役に立たない。
――衝撃だった。文章を書いたら役に立つと、どこの自己啓発本にも書いてあったから。
「メモや文書って、何のために付けたんだろう?」
私は落胆した。なんのために膨大な時間を注いだんだろう?レポート課題を効率的に書くために作ったのに。蓋を開けてみれば無価値な落書きを大量に作っていたのだ。
「自分のために作る文書は浪費である」
――どこかで聞いたことがある有名な言葉だ。
一筋の光
そんなとき、ふと目に入ったのが、同時期に書き続けていた日記だった。見直してみると、その日の行動や感想を思いつくまま書き殴っただけだ。
しかし、そんな酷い文章でも、驚くほど当時の様子がよみがえってくる。雑然としていても、自分で書いたものだから行間を読むのに苦労しない。
学校とか、人に見せたら間違いなく再提出を要求されるくらい雑な文章でも、自分で読むと凄く効率的で、何を言いたいのかすぐに分かった。
学校では「人に読ませる文章」を作る訓練をしてきたけれど、「自分が読むための文章」というのは別物だということに気づいたのだ!
フォーマットや体裁にこだわりすぎるよりも、何をして、何を感じたかをストレートに書いたほうが、後から記憶と“同期”しやすい。旅行に行ったときの景色はなんとなく覚えていても、飛行機のどの席に座ったかは覚えていないのと同じだ!
ここから私はいくつかの教訓を得た。
自分用に”加工した”文書は役に立たない
文書は作るよりも管理コストの方が大きい
他人向けの文書はフォーマットがあったり、行間を埋める工夫を凝らす必要があるが、そのほとんどは慣習で自動的に決定される
これをはっきりと理解すると、私は事実や思ったことを雑然と書くようにした。もう文書化を明確にする必要はない。適当にやったことや思ったことを記録すればいいのだから。
それから、日記を読み返すだけで、過去の自分と対話しているかのような感覚を得られるようになった。以前取り組んだプログラミングの失敗例や参考サイト、どんな本を読んでどう感じたか、といった情報が瞬時に手に取るようにわかるのだ。
役立った…?
ある日私はWebメディアの取材を受けた。私が書いた本についての取材で、「思い出の場所があれば教えて欲しい」と言われたので、中央大学に行くことにしたのだ。
聖地巡礼や校内の案内をしたのち、私は被写体になりながら記者からいくつか質問された。
「学会でスペインに行ったのはいつでしたっけ?」
先生は私の代わりに答えた。
「確か去年の2月26日だったかな?」
私はすぐにパソコンを3回クリックすると、こう答えた。
「2月24日の10時の便です。その日は前日から空港泊していて、第3ターミナルの5階にあるドーナツ状の椅子で猫みたいに寝ていたのですが、6時半に先生に肩を叩かれて起こされました。」
お読み頂きありがとうございます。noteで書いて欲しいことがある方は、こちらのコメントかXのツイート、DMなどでお願いします。
(できる限り対応します。)
いいなと思ったら応援しよう!
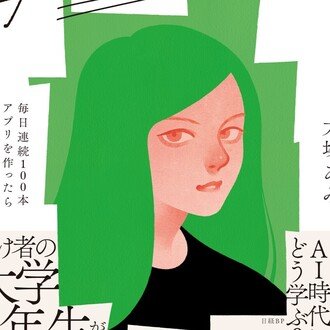

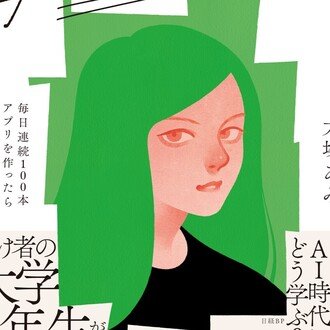
コメント