弱々しくも力強い物語について【YOUR/MY Love letter感想】
もうしばらく、シャニマスに関する文章を書いていなかった。確認してみるとアンカーボルトソングの予告を受けて書いたのがもう1年前で、そういえば最後もアルストロメリアだったのだなと気が付いた。
直前に登場したイルミネーションスターズの『はこぶものたち』には、「君と君の無数の隣人のために」というコピーが添えられていた。そのシナリオも勿論素晴らしかったという前提の下、あえて誤解を恐れずに言うならば、それはコピーを目にした瞬間に想像し期待したものとは少し形が違っていて、そのことで自分勝手に不完全燃焼な思いを抱えていた。私は、隣人に視線を向ける"君"の話ではなく、隣人の話を期待していたのだ。
だからこそ『YOUR/MY Love letter』の予告編が公開された時、全てが腑に落ちた気がした。そうか、最初から対になるようにしていたのか、と。
"街"というモチーフを通して、繰り返す日々の中で少しずつ変化していく人を描いた前作から1年が経った。果たして、今度はより直接的に"人"そのものの営みにフォーカスを当てたシナリオが登場したのである。
その演出を目にした瞬間、文字通り体が震えた。期待通りの主題だったからこそ、興奮するのと同じか、それ以上に恐ろしくもあった。それは内容如何によっては、シャニマスというコンテンツに対して抱いてきた感情を全てひっくり返さなければならなくなるかもしれないほどの劇薬だからだ。
今作には、性別も年齢も異なる様々な"名もなき人たち"が登場する。彼らには相変わらず絵も声も存在しないが、従来登場してきたモブとは明確に扱いが異なる。その多くに主観人物としての役割が与えられているのだ。次々と視点を移り変わりながら、淡々と描かれていく生活。自らに与えられた役割をこなしながら、懸命に日々を生きる。劇的なことなど何もない。ありふれた絶望をため息で堪え、なけなしの気力で自分の心を奮い立たせる。それは、どうしようもなく存在する"現実"そのものだ。彼らはあくまで作中人物ではあるが、そこに我々の姿が重ねられていることは疑うべくもない。
どこまで明示的かに関わらず、書き手側が受け手側を描くという行為は、常にある種の暴力性を孕んでいる。本来、作品から何を受け取るかは個人の自由だ。しかし、書き手が作中に受け手、あるいはその象徴を実体化させてしまえば、あたかもそれが書き手の意図した"正解"であるように感じられてしまうこともある。場合によっては、自分が否定されたように感じる人もいるかもしれない。実際、私自身そうした作品に対して強い憤りを抱いた経験もある。シャニマスは今回、その領域に真正面から切り込んできたのだ。
『アイドルマスター シャイニーカラーズ』は、言うまでもなくアイドルをプロデュースする作品である。"主役"となる彼女たちがいて、そこに寄り添う主観人物としてプロデューサーがいる。カメラは常に彼女たちを中心に捉え、その周囲は彼女たちを取り巻く環境を構成する背景に過ぎない。当然、事務所外の人物に固有名詞が与えられることは極めて稀だ。ゲーム的に言えば、絵も声もないモブ。まさしく"名もなき人たち"であり、彼らに舞台装置を越える役割が与えられることは基本的にないし、本来その必要もない。
一般には"プロデューサー"も似た位置づけとなりやすいポジションの人物ではある。ADVの主観人物は、プレイヤーの自己同一視を妨げないよう極力個性を排して描かれるケースが多いからだ。しかし、シャニマスはそちらの道を選ばなかった。彼に個性となる明確な理想を抱かせ、ノクチルで過去を創り、SHHisで無力さを描いた。初期は今よりも各アイドルに合わせてチューニングされているような気配があり、アイドル毎に別人格が存在しているようにも感じられたのだが、そうした言動のブレも徐々に抑えられるようになり、今では完全に独立した個としての像を結びつつある。
また、そういった彼の変化と時期を同じくして、サブキャラクターであるはづきさん・天井社長に対しても、過去や家族といったエピソードを付与することで同様の掘り下げが行われてきた。
そうして今回、彼ら三人に向けられていたものと同様の眼差しがついに、時折カメラに映り込む存在に過ぎなかったモブの人々、"名もなき人たち"へも向けられることとなったのである。
元々シャニマスに登場するモブはいかにも"どこかに居そう"な造形が多かった。話を回すためだけの悪意が押し付けられるようなこともなく、かといって漠然とアイドル達を応援する概念というわけでもない。そういう意味では、通底する思想自体は今までと変わらない。ただ、それをここまで拡張するというのは、アイドルゲームとしては相当に思い切った構成ではある。
アイドルたちの添え物ではない、あの世界に生きる独立した"主役"として"名もなき人たち"が描写される。極めつけは、アルストロメリアの三人とプロデューサーを、彼らと同列の存在として登場させていることだ。
今作においては、アルストロメリアの三人の仕事上の悩みは描かれない。でも、それは彼女たちに悩みがないことを意味しない。彼女たちが何に苦しみ、何を乗り越えてきたか、我々はその軌跡の一部を知っているからだ。
だから、彼女たちと"名もなき人たち"が重ね合わされても、それを違和感なく受け入れることができる。一人頑張る人と、それを見守る人。歯磨き粉を買い忘れ、人を見過ごす。そして、光を当てようとする人が現れる。
これまで長い時間を掛けて「特別」な存在として描いてきたアイドルと、その他大勢の人々を並べて見せること。それは決してアイドルの光を否定する行為ではなく、全ての人が「特別」なのだという人間讃歌に他ならない。
"名もなき人たち"の人選も丁寧だ。受け手側を描くということの暴力性を警戒し、注意深く多様性を確保しようとしている様子が感じられる。年齢・性別・職業といった分かりやすい属性は勿論のこと、それぞれが歩んでいく結末――当然彼らの人生は今後も続くが――すらも画一的にはしていない。
普遍的な愛の形である親子は、物語としてはドがつくほどの王道だろう。先生と生徒という垣根を越えて同じアイドルを見つめる二人も、アイドルものという観点ではオーソドックスだ。
中でも個人的に白眉だと感じたのが、コンビニ店員である徳丸銀之介さんの存在だ。作中において、彼は誰からも分かりやすい光を与えられることはない。それでも最後に春の訪れを感じた彼は、たしかに少しだけ前を向いている。それは描かれなかった中に何かのきっかけがあったからかもしれないし、繰り返すだけのように感じていた日々の中で、積み重なるものがあったのかもしれない。本当のところは彼にしか分からない。
でも、それでいいのだ。アルストロメリアの、アイドルのファンではなくても、一人で勝手に前を向いていい。アイドルに会ったからってファンにならなくてもいいし、いつまでも顔を知らないままでいてもいい。それがアイドルマスターという世界の中で描かれたという事実そのものに、何だかとても救われたような気持ちになってしまった。今作は正しく「"すべての"名もなき人たちへ」宛てて書かれているのだと信じることができた。
また、『流れ星が消えるまでのジャーニー』に登場していたのであろう、幸田彼方さんの存在も重要だ。過去に登場していた"モブ"に対して物語を与えたという例を入れることで、今作だけではなく、これまでに登場した全てのモブも同様に"名もなき人たち"であるという目配せがされているのだ。
あの誰よりも長くコンビニに勤めている彼は、実はストレイライトのファンなのかもしれない。あるいは、役者を夢見てバイトで日銭を稼いでいるのかもしれない。あのカメラマン見習いの青年は、いつか人生が変わるような映像に出会ったことがあるのかもしれない。あるいは、幼い頃に親に褒められた手持ちカメラの映像が原体験なのかもしれない。
彼らの名前は明かされない。今後その内心が描かれることもないだろう。しかし、彼らにも名前があり、彼らだけの人生がある。そういうことを描いている。わたしの主人公はわたし、なのだ。
いやそうは言ってもね、という人もいる。だから今一度、これまでに何度も繰り返されてきた、いつものような話に立ち返らなければならない。
シャニマスにおいて、あるいはプロデューサーにとって、「普通」であることと「特別」であることは矛盾しない。そして、その特別さこそがアイドルとしての輝き(≒魅力)そのものであるという言説がしばしば登場する。
では、シャニマスにおける「特別」とは何を指しているのか。諸説あることは承知の上で現時点での個人的な見解を述べるなら、それは「主体性の発露」である。自分で決める、自分で選び取る、ということ。決断の是非をジャッジするのではなく、選んだ心そのものを尊いものとして扱っている。
他方の「普通」は、一般に言われる"特別ではないこと"ではなく、他者が役割を代替可能な存在であることだ。だから、両者が対立することはなく、普通でありながら特別という言説が成立するのだ。
今作のアルストロメリアの描き方にも、それが表れている。彼女たちを冠としたシナリオでありながら、その実アルストロメリアである必然性が存在しないのだ。コスメ・ラジオ・式場、これまでのコミュで描いてきた具体的な三人の仕事を登場させることで、全てが同じ世界に地続きに存在していると実感させる役割は果たしている。それは間違いなく重要な要素だ。
しかし、それが別のアイドルの別の仕事だったとしても、今作のシナリオは問題なく成立させることができるのだ。他のアイドルにもファンはいる。代わりにそちらを登場させればいい。物語には何の破綻も生まれない。今更改めて言うまでもなく、アルストロメリアは「特別」な存在である。それと同時に、今作のシナリオを描く上で掛け替えのない存在、ではないのだ。
そう考えれば、本作自体が今もなお苦しみもがき続けているSHHisの二人へのメッセージ、あるいはエールのようにも思えてくる。
今の彼女たちにはステージの上しか見えていない。自分の姿を正しく見ることができない。ならば、誰が彼女たちに光を当て「特別」を与えるのか。二人の視線が合って互いの姿を認める瞬間を、ずっと待ちわびている。
(『モノラル・ダイアローグス』で少しでもいい方向へ進んでくれると嬉しいが、"ス"をみる限り、まだまだ道のりは長いのかもしれない…………)
最後に本作で最も印象に残った箇所の話をして、この文章を終える。
作中で甜花さんは「想いはどこまで届くのか」と何度も自問する。そうして終盤、自分で出した答えを「名無し」こと遠野陽呂美さんへ伝えていた。
それでいいんだ……という驚きがあった。こんな物語のクライマックスで「想いの力は強い」って、耳触りのいい言葉を宣言しないのか、と。
でも、思った以上にすんなりと納得してしまった自分がいて、そこで初めて、自分もずっと同じように感じていたのだということを自覚した。
プロデューサーは帰り道に夜空を見上げ、星が綺麗だと言った。人々が作り出すクリスマスの街の灯りを見て、祝福を捧げた霧子さんと同じように。この物語には「世界のすみずみまで」「すべての名もなき人たち」へ届けという願いが、紛れもなく込められている。しかし同時に、それは叶わないのだという現実に対して、悲しいほどに自覚的でもあるのだ。
アイドルマスターという大きなコンテンツの一部とはいえ、いちソーシャルゲームの、いちシナリオに過ぎない。この物語は全ての人には届かない。どれだけの祈りを込めたとしても、想いが伝わる力は弱いから。それでも、いつか遅れて届いたときは、立ち上がってカーテンを開く力になればいい。そうしてこの物語を世に放つ、その誠実さがたまらなく好ましい。
『YOUR/MY Love letter』を生み出してくれた制作陣に感謝するとともに、この物語に辿り着くことができた自分の幸運を噛み締めたい。
それでは。
2X歳 会社員
私がシャニマスを始めたのは昨年の1月末だ。きっかけは最初の記事に書いた通りで、始めてすぐにメイドあさひが実装されたのをよく覚えている。
当初は始めてから1年間は定期的に何かしらの文章を書き残しておくつもりだったのだが、結果的にそれは予定よりも随分早く途切れてしまったことになる。いわゆる三日坊主――実際は4ヶ月だが――とは少し違っていて、書くモチベーションがなくなったというわけではない。ましてやシャニマス自体に飽きたわけでもない。むしろ逆で、自分の中でシャニマスという存在の大きさがある閾値を越えてしまったからである。書けなかったというよりは、むしろ意識して書くことを止めていたという方が正確だ。
まとまった分量の文章を書く目的は人によって様々あるだろうが、私にとっては、"思考の記録"という意味合いが圧倒的に強い。なにしろ人の記憶というのは曖昧なもので、時間が経つにつれ必ず変質していく。客観的な事実ならまだしも、感情の面で正確な記憶を維持することはほとんど不可能だ。それは仕方がないし、勿論悪いことばかりでもないのだけど、たまには後生大事にとっておきたいと思うような感情を見つけることだってある。
言葉はその助けになる。自分で記録した文章を読みながら、時間が経って細部がぐずぐずになった記憶を、型へ流し込むように補強していく。そうすることで、手ぶらよりも遥かに鮮やかな感情を呼び出すことができる。
文章を書くことは、自分を模写するような作業だ。何度も何度も自分の心を覗き込んでは、書いたものが実物とズレていないか確認して、修正して、確認して、また修正する。それを一文一文繰り返していく。
ただ、記憶なんてあやふやなものに比べて、言葉の強度は少し高すぎる。そうして書いている間にも、記憶はその形を絶えず変化させていく。より正確に言えば、書き出した文章に寄っていってしまう。だから、とにかく気が焦る。早くしないと、書きたかったはずのものが分からなくなってしまう。でも、感情の伴わない上辺だけの言葉で間に合わせても全く意味がないし、そうしたくもない。巧く書くことは目的じゃない。より正確に書くことこそが重要なのだ。いつか、それを使って"その時"を思い出すのだから。
そうして書くためのハードルは、自分にとって大切なものであればあるほど高くなる。元になる感情が、より損ないたくないものになるからだ。
実際のところ一番書きやすいのは、上限を100として80ぐらい気に入っている"結構好き"レベルのもの。書く内容に困らない程度には好きでも、扱う感情自体は手頃サイズだから、比較的気が楽なのである。
シャニマスも、最初はむしろ書くことを目的にして読んでいたぐらいだから、何の気負いもなかった。でも、想定以上に早く"結構好き"を越えてしまったものだから、文章を書くためには相応の覚悟が必要になってしまった。コンテンツの性質上、絶え間なく新しい物語が投下されるという背景もある。そのスピードに合わせて文章を書くために、物語の咀嚼をおざなりにはできなかった。書くことありきで、感情を消費したくなかったのだ。
いつか何かを書くかもしれないと、大切にしまい込んでいる物語たちがある。時折取り出して眺めてみては、どんな言葉が相応しいかを考えてみる。そのまま放っておけばいつかは劣化して、何も書き残せなくなる時が来る。それでも、それが自分にとって尊いものであったはずだという感情の輪郭だけは覚えている。無理に言葉にしようとして元の形を損ねてしまうよりも、その方がずっといい。心にそういう箱があって、ある時シャニマスはそこへ入れることにした。だから、文章を書くことは止めていた。
それでも今回こうして筆をとった理由は、改めて言うまでもないだろう。

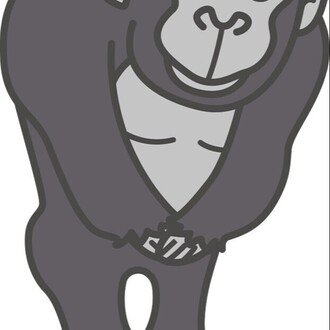
コメント