立ち退きのお話【前編】
こんにちは、Jokerです。
ちょっと前にTwitterで「立ち退き」について沸いたときに
書いたツイート
長年住んでもらった人を、てめぇが新築建てたいから出てけだと!
— Joker🃏🍄 (@Kilya_as_Joker) July 19, 2021
金も積みたくない、ってか?
なんて性分だ!!
「こんなボロい借家に住んでもらって申し訳ねぇや!わかりやした・・いや皆まで言わんでくだせぇ!もうお代は結構でげす。タダで住んでくだせぇ!」
こう言って私は使用貸借契約を(文字数)
こちらに対して、知ってる人からは「人でなし」や「だから大家は・・」といった叱咤激励のお言葉を頂戴し、また知らない人からは、「どうやったんですか?」というDMを頂きましたので、noteを書くことにしました。
以下は、私が実際に行った「立ち退き」事例です。
古い情報ですし、あぁ、こんなこともあったんだなっていうくらいのお気持ちでお読みください。
書いてて長くなったんで、前置きは無料にして、2回に分けます。
ちなみに商売つぶしで、たくや社長に手口をバラされていますww
説明しよう!使用貸借契約とは無料で部屋を使ってもよいという契約であり、うまいこと使用貸借契約に切り替えると借地借家法が適用されなくなりスムーズに立退きが https://t.co/umpmFedGKA
— たくや社長(不動産) (@fudousanlove) July 20, 2021
こちらで「あ、わかった!」って人は読む必要全くなっすぃんぐ!!
それでも良いという人は、前編読んでから読み物として後編読んでください。
きっかけは東日本大震災だった。
2011年3月11日のお昼ごろ、司法書士事務所で働いていた私は、阪神尼崎駅の横で信号待ちをしていた。そのとき、奇妙な揺れが長く続いて、信号機や電信柱からつり下がっている電線が揺れていたのを覚えている。
遠方地だったため、その時はまだ未曽有の大災害になっていたとはつゆ知らず、真っ先に思い浮かんだのは、実家が持っていた築40年超の旧耐震の借家たちのことだった。
関西の方にも、過去に大きな地震があった。
1995年1月17日午前5時46分に発生した「阪神・淡路大震災」が発生したときは、まだ中学生だったが、そのときのことはよく覚えている。
かなり離れた大阪市内でさえ、びっくりするぐらいに揺れた。
築80年以上の屋敷に住んでいたからかと思うが、倒れもせずよくもってくれたと感謝している。
この大震災の後に、ある判決が神戸地裁で言い渡された。
「よって被告は、総額1億2,883万8,179円を支払え。」
(神戸地判 平成11年9月20日)
https://osakahonbu.zennichi.or.jp/customers/trouble/detail/427
阪神・淡路大震災により中古賃貸マンションの1階が押しつぶされ、借主が死亡した事案において、建物(築31年)に設計施工上の欠陥があって通常有すべき安全性を有しておらず、設置の瑕疵があったとして、築16年後に建物を取得した貸主の土地工作物責任を認めた判決である。
これはかなり衝撃的だった。
従前より使用収益させるかわりに家賃を得る大家には、賃借人がケガ等をした際に、賠償責任を負うというのは、頭ではわかっていたものの、突然やってくる天災に対しても、不可抗力条項としては認められないというものだった。
この判決があった後は、大家の責任への認識が広がっていったかと思う。
当時、このリスクをカヴァーできるものはなかった。
(借主に対し、天災を原因とした損害保険特約もなかったと思う。
知らんけど。)
そういう情報は法学部出身なので、それとなく頭に入っていたし、親もそろそろあまり家賃の取れもしないあの古い借家のことで頭を悩ませていた矢先の東日本大震災だった。
「これはヤバい。賃借人は全員じーさんばーさんだ。若くても、家が倒れりゃ死ぬ。これは早急に対応しないとヤバい。」
そう感じた私は、知り合いの大工さんにすぐに相談して、借家の状態を見てもらった。
「あ、こりゃあかんな。ようもってる方やで、若ボン。」
すぐさまそう言われた。
この棟梁はこのエリアでようさん戸建建ててきてはった人やから信頼できる。潰すしかない、と悟った。
そして私は、大卒後、長年勤めた司法書士事務所を辞めた。
後編へつづく。


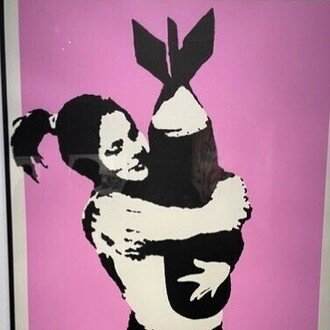
コメント