そこをバミって!バミリテープの由来と「元祖テレビ屋大奮戦!」井原高忠(文芸春秋)
「バミる」という言葉はご存じですか?
「ケツカッチン」から「ツーショット」、今では「撮れ高」などまでテレビ業界用語が一般化しています。そのひとつ「バミる」という言葉は、どのぐらい認知されているのでしょうね。出演者や大道具小道具の位置に目印をつけることで、マークするための粘着テープをバミリテープと呼びます。
映像や舞台関係の方々にはおなじみの言葉で、飲み会の幹事が「歓迎会の店はバミりました」というふうにまで使われています。<場所にブックマーク=場所を見る=バミる>というように語感と意味が近いので、知らない人もニュアンスで意味がくみとりやすく、あるていど一般的にも使われている言葉のように思われます。
でも、「バミる」の由来は「場所を見る」ではないようなのです。
テレビ・バラエティの父である井原高忠さんの本から
井原高忠は、ある世代のテレビ業界人には尊敬と憧れを持って語られる存在です。日本でテレビ放送が始まった翌年の1954年、井原は日本テレビに新卒第一期社員として入社します。1953年の開局時にはラジオ、新聞、映画など他業界から集めた人達で始めたのですね。ですからまさに日本で初めてのテレビプロパー世代です。大学時代にすでにプロのジャズミュージシャンとして活躍していた井原は、入社後に「光子の窓」「巨泉・前武ゲバゲバ90分」「九ちゃん!」「11PM」など多くの名番組を演出・プロデュースしました。(2014年に亡くなられていますが、日本テレビで少しでも追悼企画やってほしかったなぁ…)
井原を「テレビバラエティの父」と評する方もいます。確かに井原は、現在のバラエティ番組にも応用されているプロトタイプを、いくつも残しました。しかし、井原らしい「音楽」と「踊り」と「笑い」を織り交ぜたドリーミングな番組テイストを思うと、個人的に「テレビヴァラエティショウの父」というハイカラな表記が似合うように思っています。
井原のかかわった本は、本人の著作で1983年に文芸春秋から出版された「元祖テレビ屋大奮戦!」と、2009年に恩田泰子との共著で愛育社から出版された「井原高忠 元祖テレビ屋ゲバゲバ哲学」の2作品があります。今回の「バミる」で読み直してみたのは「元祖テレビ屋大奮戦!」です。
テレビ創世記の証人が「バミる」の事実をバミる!
記憶をたどると、はじめて「テープでバミって」と言われたのは1979年に小劇場の仕込み現場でした。その時は語感から<バミる=場見る>なのだろうと理解しました。その後にテレビ番組制作にかかわるようになり、その現場にもバミリテープは存在していました。テレビはエンタテインメントの世界では後発ジャンルですから、使われている多くの符牒(業界用語)は舞台や映画などから持ち込まれています。そのため舞台発の呼び名だと勝手に思っていました。
しかし、「バミる」は故坂本九の大ヒット番組「九ちゃん!」(1968年)の現場で誕生した言葉で、まったく思い込みとは違う由来を井原の「元祖テレビ屋大奮戦!」を読んで知ることになります。
ー立ち稽古の時に、ビニールテープで立つ場所を全部決めてしまう。これも、今はだれでもやりますが、日本で最初に始めたのは僕なんですが、そうしてテープの位置をカメラのぞいて、補正をしていく。照明(アタリ)を決めていく。-
まず、ビニールテープで目印をつけるのを始めたのは井原だったのですね。
ーこのビニール・テープでマークをつけることを、今では日本テレビ以外の局でも「バミる」というんですが、その由来が面白い。NTVの技術局員で福井さんという方がいて、この人がなんでもチョロッと失敬するのがうまい。どこの方言が知りませんが、この失敬することを「バミる」と言い、バミるのがうまいこのダンナで「バミダン」と呼ばれていたんです。-
来た!来た!来た!
ーこのバミダンが愛用するテープだから、これをバミテープと言い、そのバミテープでフロアにマークを付けることを「バミる」と呼ぶようになった-
「バミる」の語源はあだ名で、由来は今でいう借りパクらしいです!
ちょっとだけの検証と考えたこと
ネットを検索するとバミリテープという品名にもなっているし、由来を「場を見る」と書いてあるのもみかけます。そんな世の説明を訂正すべきだというほど自信もないのですが、ちょっとだけ考えてみます。
舞台上の立ち位置に目印をつけることなどは、テレビ以前の舞台で昔からあったことは想像に難くありません。ただこの「バミる」と言い方がビニールテープとセットで生まれた言葉なら、井原の説明は納得できます。日本で粘着テープが普及したのは戦後のこと、段ボールの普及とともにガムテープも使われるようになったといいます。3Mがビニルテープを開発したのは1946年ですが、それから日本に入ってきて、当初は設備補修用などで使われる特別なものだったようですから、テレビの現場で気軽に目印として貼れるように汎用化したのが60年代後半というのは合っている気がします。
創世記のスタジオ用テレビカメラは大きく重いうえに、床に這うケーブルも太く動きを邪魔し、しかもフォーカスも限られていました。カメラの融通が利かなければおのずのアングルは限られるので、出演者の動きもシンプルだったと思います。そして当時は生放送が主体で、現在とは違い出演者も含めた入念なリハーサルを重ねていました。立ち位置も覚える時間があったと思われます。
テープの目印が必要になったのは、テレビタレントが忙しくなり、技術が向上して動く出演者を工夫した画角で撮影することが可能になったからと考えると、60年代後半というのもわからなくありません。
ただし!井原はジャズマンでした。戦後のジャズマンはホラ吹きが多いのですよねぇ~。オモシロがってまじめな時にとんでもないホラを吹いたり、見てきたような作り話で人をからかうのです。またそれがちょっとイカれた戦中派のジャズマンたちのチャーミングなところだったりします。ただ井原高忠は氏も素性もよく良識人だから大丈夫!…と思いたいなぁ。でも初期のテレビ屋さん達はどこか怪しい雰囲気があるからなぁ~・・・となってしまう割り切れなさが、すごく困るし良いのです。
読んだら発見が多すぎて、次もこの本から。
書き始めるときに、著者はすべて敬称略にしようと決めましたが、どうしても井原さんと書きたくなるほど尊敬しています。読み直して改めてそう思いました。出版された当時は、著名なテレビ人が一般読者に向けて書いたテレビ業界ウラ話風だった思われますが、令和の時代に読み直してみるとテレビ関係者やメディアに興味のある人たちが、テレビの在り方を再確認できる至言や示唆が随所に発見できます。
一回につき一冊で書き続けていくプランを早くも撤回し、次もこの「元祖テレビ屋大奮戦!」からの発見にします。例えば、日本のテレビはアメリカカをお手本としましたが、アメリカでもお手本が西海岸か東海岸かで演出が違ってくることや、井原さんが目をつけてヒントにしたアメリカの番組「ラーフ・イン」と「キャンディットカメラ」が、今もバラエティの下敷きになっていることなど触れたいことが多々あります。どれにしようかなぁ~。
悩み多く試行錯誤、いまだにnoteに対する自分の立ち位置がバミれません。

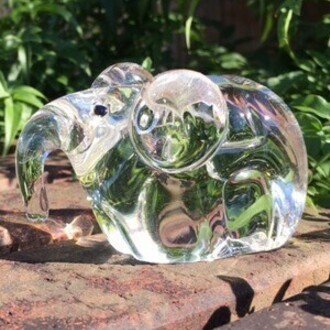
コメント