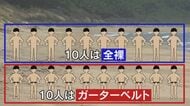「これは本当に深刻な問題なんだよ」
警視庁公安部のある幹部が厳しい表情で語った。
その問題とは、日本の先端技術が外国に流出してしまう事件が相次いでいることだ。

2023年6月、国の研究機関である「産業技術総合研究所」の中国人研究員が、地球温暖化対策にも関わる“先端技術”を中国の企業に漏洩。
この中国企業は、その後中国国内でこの技術についての特許を申請している。
企業からも情報が流出していて、2020年には、携帯電話大手「ソフトバンク」の元幹部が、ロシアのスパイに機密情報を漏洩したとして逮捕されている。
“危機感”公安トップがセミナー開催も
まるで映画のような実際の事件は後を絶たないが、実はこれでも氷山の一角で、危機感を募らせた警視庁は、公安部の“トップ”がセミナーを開催するなど対策に乗り出した。
いったいどういうことなのか。
警視庁公安部の捜査関係者を取材し、どのようにして技術が流出するのか、その手口を紹介する。

そもそも日本の先端技術が流出してしまうと、どんな損失があるのか。
経済の分野では、競争相手であるライバル国への優位性を失い、日本経済の衰退につながるのは明白だ。
さらに、軍事転用されれば、安全保障上においても日本、ひいては国際社会が脅威にさらされる。先端技術とはまさに国の生命線にも等しい貴重な情報だ。
警視庁公安部に1日100件以上の相談
そんな技術流出について取材を進めると、まず衝撃的な数字が出てきた。
捜査関係者によると、公安部のもとには、先端技術を持つ企業や研究機関から「技術情報が奪われているかもしれない」などという相談が毎日のように殺到していることがわかった。

その数は、1日に100件を超えることもあるという。
技術流出は事件として報道されなくとも、相当の数の企業や研究機関が、日々、危機を感じるトラブルに遭遇していたのだった。
では、どのようにして日本の先端技術が流出するのか。
「美しすぎる女スパイ」がアメリカの軍事情報を入手
その代表例として【スパイ工作による技術流出】が挙げられる。
大ヒット映画「007」や「ミッション:インポッシブル」では、魅力的なキャラクターを持つスパイが、巧みな話術や格闘術を駆使して敵国から重要情報を奪い取る姿が印象的だ。

このようなスパイを主役エンターテインメントは非常に楽しいものだが、実在するスパイは非常にやっかいな存在だ。
実際に起きた事件では、2010年にFBI(アメリカ連邦捜査局)によって逮捕された「美しすぎるスパイ」ことアンナ・チャップマン氏が世間を震撼させた。
ロシア人の彼女はアメリカ人になりすまし、ニューヨークの不動産会社の社長を演じながら、アメリカの核弾頭開発計画などの軍事情報を探っていたとみられている。

その方法は色仕掛け。
彼女はその容姿を利用して、国防総省の高官たちに近づいた。
その後、ロシアに送還された彼女は、銀行の顧問に就任。
そして当時大統領だったメドベージェフ氏から勲章を授与され、政界にも進出。
ロシアが国をあげてスパイを厚遇する姿勢が明らかになった事件だった。
そんなスパイが正体を隠し日本にも潜んでいるのだ。
捜査関係者は、「スパイたちは今の時代ならではの手法を使ってくる。」と近年の諜報活動の一端を語ってくれた。その手法とはSNSを利用したものだ。
現代のスパイはあなたのSNSをチェックする
スパイはターゲットのSNSを通じて、扱っている技術情報のみならず、投稿内容から趣味や嗜好、さらには帰宅ルートまで把握するという。
そして、SNSでのメッセージのやりとりを繰り返し、会う約束をとりつけたり、道ばたで偶然を装って話しかけたりして接触を図る。
ターゲットからしてみれば、見ず知らずの外国人から接触があったとしても、相手が自分と同じ趣味や価値観を持っていたら警戒感が薄れるという。

そして、スパイたちの交流方法はいたってシンプルだ。
「旅行のお土産」だと言ってプレゼントを渡す。
また、家族が病気だと聞けば、病院にまでお見舞いに来て親身に寄り添う。
その距離の詰め方は、日本人が情に弱いということをよく知っていると言わざるを得ない。
親交が深まるとスパイは次の段階に進み出す。
ターゲットに要求を始めるのだ。

ターゲットが勤める会社に興味を持っていることを示し、「今後の勉強のために会社のパンフレットをもらえないか?」といった内容だ。
実は、この小さな要求が1つのポイントとなっている。
これは、まず小さな要求から始め、徐々に目的としている要求を承諾させるテクニックで、心理学の世界では「フット・イン・ザ・ドア」と呼ばれている。
要求拒否も「あとの祭り」…スパイから脅迫
その手順通り、スパイは会社の公開情報などハードルの低い要求を繰り返し、その度に少額な報酬をターゲットに支払う。
そして要求は徐々にグレーゾーンにまで踏み込んでいく。
すると、ターゲットの心理的な抵抗感が弱まってくる。
そして最後の仕上げと言わんばかりに、本来の目的へ。

「会社が保有する機密情報が欲しい」と打診してくるのだ。
ターゲットは関係が壊れるのを恐れ、すでに要求が断りづらい状態だ。
だが、もし勇気を振り絞って断ったとしても、スパイはこれまで被っていた仮面を脱ぎ捨て、一転して脅してくることもあるという。
相手は情報機関で人心掌握術を徹底的にたたき込まれてきたスパイだ。
これまで積み重ねてきた交流で、ターゲットの弱みを握るなんて造作もないことなのだ。
ロシアのスパイに従ってしまった日本人社員の末路
そんな事例が過去に日本で起きたことがある。
冒頭で紹介した、2019年、通信会社大手「ソフトバンク」の統括部長だった元社員が自宅から会社のサーバーにアクセスし、機密情報を不正に取得し、翌年逮捕された事件だ。
元社員は在日ロシア通商代表部の男から繁華街で突然話しかけられ、気付けば2人は会食を交わす仲となった。

そして、ロシアに帰国するという男は、自分の後任だというロシア人の男を元社員に紹介した。
後任の男はこれまでと同様、元社員との関係を深めていく。
そして案の定、会社の情報を求めるようになった。
1回あたり20万円の報酬を支払うなどという条件だった。
エスカレートする要求に、元社員は要求を断ったこともあったが、男から言われたある言葉に恐怖した。
「あなたの住んでいるマンションを知っている。」

実は、後任の男は、ロシアの情報機関「SVR=対外情報庁」に所属する、スパイとみられる人物だった。
結局、元社員は要求を断ることができず、機密情報をコピーしてしまったのだ。
ロシア人の男は事態が明るみになっても、警視庁の出頭要請に応じないまま母国に帰国した。

元社員をそそのかしたとして、書類送検され起訴猶予となったが、二度と日本に来なければいいのだから痛くもかゆくもない。
一方、元社員は2020年の裁判で不正競争防止法違反の罪などで、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を受けた。後悔しても仕切れない結末だったろう。
この事件での諜報活動はある意味わかりやすく、1人1人の危機管理と、自制心で防ぐことができるものだ。ただ技術流出にはさらにやっかいな手口が存在する。
中国系企業から「技術の指導依頼」装ったケースも
次に【経済・学術活動を通じた技術流出】を紹介する。
これは主に中国人が関与する「産業スパイ」の話になる。

ある日本の研究機関に中国系企業から「技術の指導をお願いしたい」という依頼をするほか、知識・技術をもった日本の研究者を中国に招いたり、日本の研究機関に中国のスタッフを派遣して見学したりと、徐々に関係を深めようとするのだ。
きっかけを作って、接触した研究者を懐柔したり、研究所に赴いて研究内容を盗み見たりと、どうにかして先端技術を奪おうとするケースが散見されているという。
まだまだ他の手段もある。
中国系企業からの「ヘッドハンティング」「共同研究・業務提携」「合弁・買収」「海外展開」「商品サンプルの要求」などの打診。

このような合法のアプローチを装って、研究者に接触する手口はいくらでもあるのだ。
もちろん、なかには善意のある純粋な提案をする企業もあるが、経済大国である中国からの打診は、一見魅力的なものも数多く、簡単には拒絶できないために悪意がある「産業スパイ」にひっかかってしまう可能性があるのだ。
機密情報を欲しがる留学生の正体は…
さらに、技術の流出をもくろむのは企業だけではない。外国からの留学生からもその触手が伸びることもある。
実際にあった例で、日本の大学で熱心に授業を受けていたある国の留学生が、「研究の機密情報を教えて欲しい」と教授に強く迫るようになった例があるという。
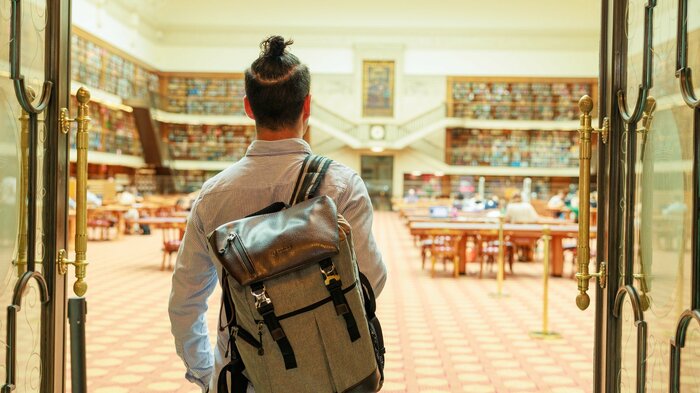
その学生の登録された母国の住所を調べると、ある軍事関連の大学ものだったことが判明。
学生は出身校を隠して日本の大学に潜入していたとみられ、一歩間違えれば先端研究の情報が外国の軍に渡る可能性があった。

こうした実情に危機感を抱いた警視庁公安部は12月17日、企業や研究機関を対象としたセミナーを開いた。
講演をしたのは公安部トップである、中島寛・公安部長だ。
中島氏は「大学や研究機関は海外との人材交流を盛んに行うオープン化が進んでいる反面で、その特性から狙われやすい傾向がある」と指摘した。
この日集まった約120人の研究者らは真剣な眼差しで講義を聞いていた。もはや他人事とは言えない事態にあることがうかがえる。

警察庁は、技術流出につながる不審な動向があれば、関係機関や警察に相談するよう求めている。一度流出してしまった情報は二度と取り戻すことはできない。
技術流出のリスクに対して一層の危機感を持って、冷静に対処することが重要だ。
(取材・執筆:フジテレビ社会部・警視庁サブキャップ 池田圭司)