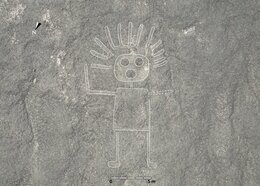体験の貧困がもたらす「“周りを頼っちゃいけない”という壁」
周りの友達が、当たり前にできていた体験が、まったく欠けていた子ども時代。それは、人間関係の貧困をもたらしたといいます。そのことは、人生の選択肢を狭めたと、ヒオカさんは感じています。
ヒオカさん
「私の周りには、本当に信頼できる大人、気にかけてくれる大人、心配してくれる大人がいなかった。家庭の中で、親が大変な状況だと、話し相手がそもそもいない。偏った価値観を親に押し付けられ、進路も、本当は違う道があったのに、反対された。
相談できて、気にかけてくれる大人がいないと、“自分は大変な状況にいる”ということに、気づくことすらできない。そもそも助けを求めていい状態なのか、自分の状況を客観視できない。
自分の大変な状態を、自覚できるかどうか。自覚できたとしても、助けを求めていいのかどうか。助けを求めようにも、支援情報をキャッチできるかどうか。支援とつながったとしても、うまくコミュニケーションできるかどうか…
私も大変なときに、いろいろな窓口に電話したが、いい対応が得られなくて、突き放されるようなことがあった。そういうときには、本当に心が折れてしまう。
二度と助けを求めちゃいけない、周りを頼っちゃいけない、という壁が何重にもある」
「スタートラインが違う…」体験は、親の所得あってこその“特権”
親の経済状況がもたらす体験格差。それによって被る課題を、身をもって感じてきたヒオカさん。そんな彼女が、特に問題だと感じていることがあります。“すぐ身近に、自分たちとは境遇の違う子どもたちがいる”ということに、周りの同年代の理解が、及んでいないということです。

ヒオカさん
「運よく大学には行けたが、家庭からの援助はゼロ。奨学金を借りて、体調を崩してでもアルバイトしないといけない。パソコンなんて買えないし、格安シェアハウスを転々とする生活。
仕送りをもらっている子たちからすると、そんな私が物珍しく見えたみたい。
“なんで資格取らないの?” “なんで免許取らないの?” “なんで留学しないの?”って、悪気なく聞かれた。
その子たちは、親に塾に行かされて嫌だったとか、習い事を強制されて嫌だったとかって話をするが、私からすれば、自分が、何が好きで、何が嫌いかに気付ける機会を与えられていることって、“特権”だなって思う。
そんな体験を、親の所得でできてしまうというのが当たり前な中で生きている。小さいころから、同じぐらいの所得の家庭の子と育っているから、自分と違う境遇の子がいるってことが実感できない。
みんな、横並びで、ヨーイドンってスタートして、大人になって収入を得ていく、みたいに思っているが、実際はそうじゃない。教育に投資してもらえず、進学をあきらめないといけない子がいる。家庭環境によってトラウマを抱えてしまった子がいる。ものすごくハンデを背負った状態で、社会に出て、稼いでいかないといけない子がいる。スタートラインが違うっていうことが、全く認知されていない。
困難を背負った人が、隣で生きていること、家庭環境にどれくらいの差があるのかということを、もちろんニュースでは知っているんだろうけど、身近な存在としては実感できない。その子たちが悪いっていうことではなく、そもそも、そういう社会ができあがっている」