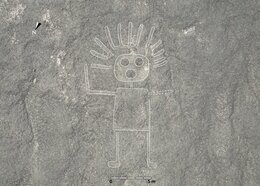子どもの“体験”と聞くと、習い事やスポーツクラブ、夏休みの家族旅行などが思い浮かびます。そんな幼児期の体験活動について、文科省では来年度から、受けた教育や、家庭環境も含めて、その後の将来にどのような影響を与えるかについての大規模調査に乗り出します。「体験ってそんなに大げさなもの?」と思ってしまいますが、貧困によって、限られた体験しかできなかった当事者に話を聞くと、「体験の有無は、子どもの将来に大きな影響をもたらす」という現実が見えてきました。
「どうしようもなく悔しくて…」体験をあきらめ続けた子ども時代
子どもの教育格差の解消に取り組む、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンの調査によると、子どもたちが接する“体験”には、家庭の経済状況に応じて、格差が存在していて、世帯年収300万円未満の家庭にいる子どもの“3人に1人が、学校以外での体験が何もない”と回答したといいます。

そんな貧困家庭の当事者で、いじめや不登校を経験しながらも、独学で大学に進学し、現在はライターとして活動するヒオカさん(27)は、「子どもの体験格差は将来に大きな影響をもたらす」と、自らの経験を発信し続けています。
ヒオカさんは、中国地方にある小さな農村地域に生まれ、父と母、姉の4人で暮らしていました。父は、ことあるごとに母に手をあげ、病弱だったために、転職と失業を繰り返していました。母のパート収入と合わせても、経済状況はとても不安定なもので、そのことは、ヒカオさんの体験を大きく制限しました。
ヒオカさん
「本であったり、ゲームであったり、周りの友達がふつうに持ってるものが、私の家には全くなかった。長期休みに、友達は、家族と遠出するが、私の家では、そういったものは全くない。みんなが、習い事だったり、スイミングスクールだったり、ピアノ教室だったり、通信教育だったりに通う中で、自分は何一つやらせてもらえない。
その理由が、どう考えても自分の家の経済状況だというのは、なんとなく悟っていて、それはどうしようもないと、どこかであきらめた。
小さい子がずっと、あきらめろ、あきらめろ、あきらめろって…あきらめるしかないっていうことを、積み重ねて、積み重ねていくと、人生に希望を持てなくなる。生きる意欲が減少してしまう。自分から何かをつかもう、みたいな思いがなくなってしまう。
いつ崩れるか分からない綱渡りの生活の中で、毎日が必死なときって、生きている意味が分からない。生きていても、しんどいだけだった。
あきらめてはいるのだけれど、でも、どこかで、ずっと悔しくて、どうしようもなく悔しくて…」