人生何周目ですか?
noteを巡回していたら、ちょっとユニークな記事を見つけた。最近、「人生何周目」という表現をたまに見かけるが、それについてモヤモヤした感情を綴った記事だった。
自分には全くない感覚だったので、少し面白く読めた。
この記事によれば、日常会話における「人生何周目」という表現が受け入れられない、とのことだ。「あの子ってしっかりしてるよね、人生何周目なんだろう」といった文脈の例を挙げ、「年下を褒める」という意味合いでこの言葉が使われることが多い、と指摘する。
シンプルに褒めればいいのに、自分より優秀な年下を褒める「逃げ道」と解釈しているのが新鮮だった。つまり、自分がその年齢だった時よりもはるかに「大人」な振る舞いを目にしたとき、人生を何周かしてその所作を身につけたのだろう、ということである(もちろん比喩として)。
最近、転生モノというジャンルのアニメや漫画が流行っているが、その影響ではないか、とも分析している。
*
僕はいわゆる転生モノのアニメは見たことがないが(そういうのが流行っているのは知っている)、普通にこの言葉をよく使う。主に、奥さんとの日常会話である。
ただ、「所作が大人っぽい」ことに対して使うことはない。どちらかというと、「人間な感覚の鋭さ」だ。他人の心がよくわかり、ものの道理を理解している、という方向性である。これはわりと天性のものだと思っていて、わからない人は高齢になってもわからない。
人間的な感覚に優れていると、人生を周回するうちに身につけた能力なんだろう、ということで「あの人、人生何周目だろうか」という表現になる。年齢は関係ない。人生何周もしてそうだ、ということも話題にすることはあるけれど、どちらかというと「あの人は一周目っぽいよね」という感じで使うことが多い。
バカにするわけではなく、あの人は一周目っぽいので、まだあまり人間界のルールがわかってないかもしれないから、優しくしてあげよう、的な感覚である。
*
転生モノというジャンルが最近流行っていることは知っているが、むしろ輪廻転生の世界観は伝統的(仏教的)なものである。宗教的な価値観に強く結びついているので、日本をはじめアジアで受け入れられている理由はよくわかる。死後、どのようにして復活するのか、といった世界観は、けっこう信仰の根幹に関わる部分なので、デリケートな地域もあるだろう。
僕は輪廻転生を信じているわけではないが、その背景のロジックは理解している。要は、人々に「善なる行い」を説くための方便なのだ。「善いことをし、徳を積めば、報われますよ」と。
それに対する反論として、「そうはいっても、悪事の限りを尽くしてるやつが幸せに暮らしているのに対して、自分は徳を積んでいるのに一向に報われない」ということを言う人もいる。なので、それに対して、「今世での徳は、今世で報われるとは限りません。でも、きっと生まれ変わったら、来世に反映されますよ」というロジックなのだ。
つまり、人生を何周も繰り返して、より良いステージに上がっていこう、ということなのである。なかなかアクロバットな論理だ。
これでいくと、「人生何周目」という言い方もしっくりくる。前世で徳を積んだ人だから、今世でも徳深い人なんだろう。逆に「人生一周目」の人は、まだまだルーキーだな、と。
*
輪廻転生というのはアクロバットな論理だし、全く科学的ではないので、現代社会ではあまり真面目に信じられてはいないかもしれない。少なくとも、他者の霊が今生まれようとしている人間に憑依するようなことは現実には考えにくいだろう、とは思う。
しかし、科学ではまだよくわかっていないこともたくさんある。人間には、潜在的に備わっている能力や記憶がある。人間には魚の鰓の痕跡もあるし、尻尾の痕跡もあるらしい。DNAの中には、前世どころか、これまでの進化以前の生物の記憶が奥底に眠っているということだ。
そのうち、何が「顕現するか」というのは人によって違いがあるような気がしている。つまり、人の気持ちがよくわかったり、異様に察しが鋭いというか、感覚が鋭い人がいる。そういう人を見ると、人生を何周かして、そういった感覚が顕現した人なのかな、とちょっと思ったりする。
所作や知識が大人びているというよりは、人間というものをよくわかっている、という感じだろうか。不思議なことに、「察しが悪い人」というのは、一生察しが悪いままだ。察しがいい人は、幼少の頃からその能力を発揮する。
やっぱり、そういう人を見ると、年齢にかかわらず、人生何周かしてそうだな、と素直に思ってしまう。現代的でもあるが、伝統的でもあり、なんとも不思議な考え方だ。
サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。


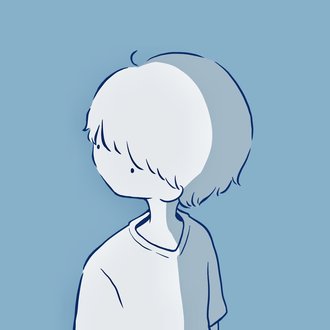
コメント