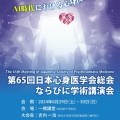https://sanwa-co.com/9784862515612-2/
◆推薦◆
[東京大学名誉教授・島薗進]
・・・この意見書は、司法の場のみならず、教育研究の場で、また政策課題の考察・討議や被害者支援活動の実践現場などにおいて参照されるべき、おおきな意義をもつ文章であると信じ、ここの推薦する次第である。
[国立民族学博物館名誉教授・竹沢尚一郎]
・・・これまでの日本政府や福島県の実態調査は十分なものであるといえず、辻内氏の研究はこの点を実証的に明らかにしたばかりか、避難者にインタビューを行うことによってその声も数多く収集しており、その意味で被災者支援の観点からも大きな意義がある。
[京都南法律事務所・弁護士・井関佳法]
「被害実態を可視化して伝える力」
・・・高松高裁は辻内意見書を詳細に紹介したうえで、区域外避難者の慰謝料の判定しました。まだまだ不十分ではありますが、低額慰謝料の流れの中、辻内意見書は、区域外避難者の被害も甚大であることを裁判所に認めさせる力を示しました。
[福島県南相馬市メンタルクリニックなごみ・精神科医・蟻塚亮二]
・・・従来PTSDの原因となるトラウマ体験とは、戦争や事故などによる個人的暴力であった。これに対して辻内が「社会や政治の仕組みや構造がもたらす暴力」が「個人の生活や人生に対して影響を与えてPTSDを発症させる」という、社会構造に踏み込んだ新しい概念は刮目に値する。
目次
第1章 はじめに:意見書の趣旨
1-1.持続可能な開発目標(SDGs)に向けて
1-2.筆者らの調査・支援・研究活動の経緯
1-3.「誰ひとりとして取り残さない」を目指して
第2章 調査研究の概要
2-1.調査研究の目的
2-2.調査研究の特徴
2-3.アンケート調査の対象と方法
2-4.本調査におけるストレス度の測定
2-5.本調査で行った統計解析の概要
第3章 精神的ストレス度の11年間の調査結果と先行研究との比較
3-1.11年間の精神的ストレス度の調査結果
3-2.世界における災害研究との比較
(Tsujiuchi T.:PlosOne,2016原著論文をもとに和訳・加筆)
3-3.東日本大震災後の研究との比較
3-4.交通事故災害との比較
第4章 PTSD症状に影響する身体・心理・社会・経済的要因
4-1.2012年SSN埼玉調査データから
(Tsujiuchi T.: PlosOne,2016原著論文をもとに和訳・加筆)
4-2.2013年NHK福島調査データから
(辻内ら:心身医学,2016原著論文をもとに加筆)
4-3.2015年NHK全国調査データから
第5章 原発避難者と地震津波避難者との被害の質の違い:2015年NHK全国調査データから
(Tsujiuchi T.: JapanForum,2021原著論文をもとに和訳・加筆)
5-1.年齢と性別の構成
5-2.心理的影響の違い
5-3.社会的影響の違い
5-4.経済的影響の違い
5-5.4つのグループのストレス度の比較
5-6.4グループ比較からみえる原発事故避難者の特徴
第6章 2016年以降の首都圏調査データにおけるK6の分析
6-1.2016年調査の結果
6-2.2017年調査の結果
6-3.2018年調査の結果
(岩垣・辻内・金ら:心身医学,2021原著論文をもとに加筆)
6-4.K6の経年変化(2016年・2017年・2018年・2020年・2022年)
6-5.考察:原発事故被害者のストレスと社会・経済的要因
6-6.まとめ
6-7.本研究の限界
第7章 原発避難いじめの実態調査
7-1.いじめ調査結果の概要
(辻内:岩波「科学」,2018a、明石書店,2018b 掲載論文をもとに加筆)
7-2.アンケート自由記述の分析
7-3.原発避難いじめの事例
7-4.原発いじめに対する文部科学省調査の検証
7-5.原発避難いじめの構造
第8章 福島原発事故に認められる構造的暴力
8-1.構造的暴力によるPTSD仮説
8-2.構造的暴力の上部構造
8-3.構造的暴力の下部構造
(辻内:ナラティブとケア,2019掲載論文をもとに加筆)
8-4.原発事故はまったく収束していない
第9章 事例分析:原発事故被害者10人の物語
ー心理・社会・経済・身体的ストレスの解読ー
9-1.中間貯蔵施設建設による自宅・ふるさとの喪失と、娘たちの被ばく
新田さん(52歳・男性),6人世帯,帰還困難区域
9-2.生きがいの喪失、孤立、未来の喪失
飯盛さん(56歳・男性),2人世帯,帰還困難区域
9-3.長期にわたる避難所生活と賠償金をめぐる家族関係の悪化
真野さん(59歳・女性),4人世帯,帰還困難区域
9-4.ふるさと喪失・生きがいの喪失と、多数の持病を抱えた一人暮らしの苦難
高瀬さん(68歳・男性),1人世帯,帰還困難区域
9-5.乳幼児を抱えた母子避難と、知人友人関係の悪化
前田さん(33歳・女性),3人世帯,緊急時避難準備区域
9-6.コミュニティ・ふるさとの喪失による孤独と、胃がん・脳梗塞による身体不自由
吾妻さん(86歳・男性),1人世帯,計画的避難区域
9-7.家族分離による家族関係の悪化、子どものいじめと避難者への差別・偏見
三峰さん(40歳・女性),5人世帯,避難指示区域外
9-8.避難先での母親の事故死と、幼い子どもとの孤独な母子避難
中山さん(37歳・女性),3人世帯,避難指示区域外
9-9.妻の難病と事故後に生まれた四男の先天性心疾患、福島と首都圏との二重生活と家族分離の苦悩
笹森さん(48歳・男性),5人世帯,避難指示区域外
9-10.平穏な日常生活の破綻、原発事故後の離婚、母子避難の孤独と病気
神山さん(29歳・女性),4人世帯,避難指示区域外
9-11.おわりに
第10章 結論
10-1.本書で示した調査結果より明らかになったこと
10-2.分断の解消に向けて
10-3.『居住コンセプト』という新しい避難・帰還政策の提言
10-4.「避難する権利」および「避難を継続する権利」
10-5.第37回人権理事会本会合(2018)指摘事項のフォローアップ
10-6.総括的提言
付録資料 最新調査分析結果をもとにした政府に対する要望書
(2023年3月7日)
引き続く原発避難者の苦難を直視した継続的かつ実行的支援を求める要望書
第1 要望の趣旨
第2 要望の理由
【研究助成】
【引用文献(ABC 順)】
【謝辞】
【執筆者紹介】
著者プロフィール
辻内 琢也(ツジウチ タクヤ)
愛知県生まれ。幼少期を南アフリカ共和国で過ごす。浜松医科大学医学部卒業。東京大学大学院医学系研究科・内科学ストレス防御心身医学修了。博士(医学)。千葉大学大学社会文化科学研究科(文化人類学)単位取得退学。東京警察病院内科、東京大学医学部附属病院心療内科、健生会クリニック心療内科・神経科診療室長、早稲田大学人間科学部助教授、ハーバード大学難民トラウマ研究所(HPRT)・マサチューセッツ総合病院精神科リサーチフェローなどを経て、早稲田大学人間科学学術院教授、早稲田大学災害復興医療人類学研究所所長。
1995年発災の阪神・淡路大震災において、被災地医療に従事。調査研究論文「阪神淡路大震災における心身医学的諸問題(Ⅱ);身体的ストレス反応を中心に」にて第11回(1997年度)日本心身医学会『石川記念賞』受賞。2011年発災の東日本大震災後は、福島県から首都圏への避難者に対する医学・心理学・人類学的調査を行うとともに、震災支援ネットワーク埼玉(SSN)副代表として支援活動を行っている。「原発事故広域避難者のトラウマに対する社会的ケアの構築」にて、第16回(2014年度)『身体疾患と不安・抑うつ研究会賞』受賞。「福島原発事故首都圏被害者に持続する甚大な精神的被害-人間科学的実証研究から-」にて、第20回(2021年度)日本トラウマティック・ストレス学会・学会奨励賞『優秀演題賞』受賞。





![[意見書]フクシマ型PTSD”今やらねばならぬこと”(三和書籍)2024年8月15日発売](https://resize.blogsys.jp/4cbeebb1d3263b3cdecd37ac6f3cb4ad911c2c7e/crop1/120x120_ffffff/https://livedoor.blogimg.jp/tsujiuchi_labo/imgs/3/4/3453cfb5-s.png)