皇位継承で旧皇族が復帰する案について少し考えてみた
皇位継承問題と男系・女系
産経新聞が皇位継承問題について、ある記事を掲載しました。産経新聞は皇位継承問題について男系継承にこだわり、旧皇族を復帰させて男系継承を維持する案を推していますが、安倍内閣から菅内閣に変わった今、政府や自民党の中枢には、皇位の男系継承に理解があるとは言い切れない人物もいるということだそうです。
ここでいう男系継承とは、わかりやすくいえば、皇位に就く人の父親を代々遡っていくと必ずどこかで過去のいずれかの歴代天皇に至るということで、この原則からはずれた天皇がこれまでのところ一人も存在しなかったことは周知のとおりです。
そして現在は、皇族の人数が少なくなっていることから、このままでは男系の継承が困難になるとされていて、女系容認(父親だけでなく母親も含めて過去の天皇につながれば良いとする考え方)でいくか、それとも皇族の範囲を広げて旧皇族(意味はこのあと説明します)の人を皇族に入れるか、という議論が行われています。
(リンク先の皇室の構成図参照。現在の皇族で皇位を継承できる人の少なさがわかると思います。現在の皇室典範では、男系であるだけでなく男性でないと皇位を継承できません)
旧皇族の復帰論
今回の記事では、賛否などの議論はいったんおいて、皇位の継承者を確保するために仮に後者の考え方に立って、旧皇族の人を実際に「復帰」させるとしたら、どのように制度を整えることになるのか、またどのような問題が生じうるのか、思考実験として考えてみることにします。
なお私の著作『13歳からの天皇制』の第5章、第7章と第11章でも、関係する議論をできるだけ中立的な観点で紹介していますので、是非ご一読ください。
★上記の拙著で、後述の「貞成親王」を「貞也親王」と変換してしまった誤記がありますが、ご容赦ください。
「旧皇族」という概念の意味
まず詳しい人にとっては今更解説不要でしょうが、ここで「旧皇族」とは何か、改めてまとめておきましょう。
ここでいう「旧皇族」とは、室町時代に成立した「伏見宮」と呼ばれる皇族の一つの家の男系子孫の人々を指します。南北朝時代の崇光天皇(1334年-1398年) 現皇室の先祖)の子の栄仁(よしひと)親王は、様々な状況に翻弄されて皇位に就かず、伏見に居住して、その家は「伏見殿」(伏見宮)と称するようになりました。
栄仁親王の子の貞成(さだふさ)親王(1372年-1456年)も皇位には就くことがなかったのですが、貞成親王の2人の子のうち兄(彦仁王)が後花園天皇となって現在の皇室につながり、一方、その弟(貞常親王)(1426年ー1474年)とその子孫も、そのまま代々伏見宮を名乗るようになったのです。
近代より前は、天皇の子孫であってもある程度の代を経ると、皇位継承の見込みがない場合、「源氏」などの姓を与えて皇族からはずして臣籍降下させたり、出家させるなどの扱いが一般的だったようですが、この「伏見宮」の家は、代を重ねても臣籍降下することがなく、天皇は出さなかったものの、子々孫々まで皇族として「親王」の地位を続けていくという扱いを受ける家になったのでした。
皇族から国民へ
この伏見宮の子孫が、近代の久邇宮家、東久邇宮家、竹田宮家などで、これらの各家は、天皇を出さないまま皇族の地位を保ち、第二次世界大戦が終わった後、1947年に皇族の地位を離れて一般国民となりました。
この伏見宮の子孫の人々がこの記事でいう「旧皇族」で、家としては11家があり、皇籍を離脱した人数としては51名にのぼりました。
一番わかりやすくまとめていうと、「旧皇族」というのは、室町時代の後花園天皇の弟・貞常親王の男系子孫ということになります。そして後花園天皇自身の子孫が今の皇室です。
現在の皇室とこの旧皇族の人々の先祖を男系(父方)でたどっていくと、最も近い共通の先祖は、後花園天皇とその弟・貞常親王の父親、つまり600年以上前の室町時代の貞成親王ということになるわけです。
さらにいえば、この旧皇族の人々に最も近い男系祖先の天皇は、そこからさらに100年ほどさかのぼった南北朝時代の北朝・崇光天皇です。
現在、皇室に男系の継承者が少ないので、その対策として旧宮家を再び皇族に戻すべきだと主張する意見が、主に保守的なメディアで唱えられています。
皇族復帰の手順を考えてみると
さて、ここで賛否はおいて、仮に実際に旧皇族の人々を皇族に「復帰」させるとしたら、どのような手順を踏むことになるのでしょうか。
まず現在の皇室典範を見ると、「皇族」とは、「皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王」(第5条)とされています。
このうち「親王」とは天皇の子と孫の男子であり、「王」とは天皇の曾孫以下の子孫の男子のことです(第6条)。
旧宮家はこの第5条のどれにもあてはまらないように見えますが、室町時代の崇光天皇の子孫ではあるわけですから、仮に旧宮家の人が復帰すれば、「王」にあたるものとして位置付けることが考えられます。またまったく別な規定を設けることも考えられるでしょう。
同意してくれた人を皇族に?
さて、具体的な「復帰」の形を考えてみましょう。
まず、一定の過去の旧皇族の人物およびその子孫をすべて一律「皇族」にする法令を作ることはできるでしょうか。
これは各人の意思を無視して、その身分を国民から皇族に強制的に変えるということであり、日本国憲法のもとでは許容されないというべきでしょう。この問題は、本記事の最後でまた説明します。
そこで、対象となるそれぞれの人から個々に同意をとりつけようとしたとすると、当然、同意が得られない場合もでてきます。特に一定の家族の内部で同意する人と同意しない人とが混在する可能性も考えなければなりません。その場合、次のことに注意が必要です。
同意する人と同意しない人がいたら
まず既婚者の場合、夫は皇族になることに同意したが妻が同意しなかったら一体どうなるのでしょうか。夫だけが皇族で妻が非皇族ということにするしかありません。(ちなみに夫が皇族で妻が非皇族という夫婦は、現在の皇室典範は想定していないと考えられます。)
また、親は復帰に同意してもその子が復帰に同意しない場合はどうするのでしょうか。親だけが皇族となってその子孫には皇族の身分はつながっていかないことになりますが、これではそもそも皇位継承にとってプラスの効果がなく、皇族に復帰させる意味自体がなくなってしまいます。
逆に、子だけが皇族になることに同意して親はそのままというパターンもありうるのではないかと言われそうですが、現実問題としては若い世代ほど現代的な価値観になるでしょうから、そういうパターンは実際には起こりにくいでしょう。
さらに子が未成年とか幼児の場合はどうするのでしょう。少なくとも子が成人になってから同意をするかどうか確認するべきでしょう。
これらに加えて、兄弟のうち片方だけが同意した場合は、たとえば兄が皇族で弟が非皇族ということになります。
以上まとめると、旧皇族からある人物が皇族になる一方で、その妻や兄弟や子は皇族ではないという事態も考えられることになります。いずれ天皇の妻や兄弟や子が皇族でないということも起こりうるでしょう。
(復帰の具体的な手順の一つの案として、皇室典範を改正して養子縁組可能としたうえで、個別に現在の皇族の「養子」になってもらうとか、女性皇族の相手として「婿入り」してもらうという意見があるようですが、これは結局、個々に同意をした人が皇族になるという前述の方法の一種ということになります。養子になるのも結婚するのも、同意がなければできるわけがありません。)
現在の財産や仕事についてどう扱うか
さて、理屈や方法はともかく、とりあえず一定の人が皇族に復帰することが決まったとして、それに伴う実務の処理にも課題がいろいろと出てきます。
一例として、旧皇族の人が会社員として生活しており、住宅ローンを組んで自宅を購入していた場合はどうなるのでしょうか。
この自宅は、本来その人個人の財産ですが、現実問題として皇族用の新たな邸宅に住むことになりますから、もはや自宅には居住しないことになります。
それでは、住まないままで自宅を財産として保持したり、他人に賃貸したりすることはできるでしょうか。
日本国憲法によれば「第88条 すべて皇室財産は、国に属する。」とあり、不動産のような高額の財産を皇族が個人として所有するという事態は想定していません。住宅ローンも同じことで、数百万や数千万の債務を皇族が個人的に負う事態も想定外です。
第三者に損害を与えるわけにもいきませんから、何らかの特別な立法措置によって、政府がその不動産を接収して売却したり、税金を使ってローンの弁済をしたりするしかないでしょう。
さらに現在ついている職業を退職しなければならないことにもなるでしょう。会社員、取締役、公務員、自営業、いずれにしても続けることはできなくなります。(純然たる名誉職的なものは別として。)
いずれにしても旧皇族の子孫の人たちも、今現在、社会において国民として経済的関係や利害関係の中で生活し活動しているわけですから、さまざまな影響が各方面に波及する可能性があります。
同意があれば基本的人権を剥奪できるのか
先ほど「皇族に復帰するにしても、本人の同意が必要」という言い方をしました。
これは、本人の身分を一般の国民から皇族に変更するということは、国民としての基本的人権を剥奪、または制限するのですから、そのような重大な変更を勝手に国が行って良いはずがないという当然の理屈です。
まず、皇族は国民に保障された基本的人権を持たないのでしょうか。それとも、皇族も国民の一部ではあるが基本的人権に特殊な制約を受けているのでしょうか。
これはどちらも理論的には成り立ちうる考え方ですが、憲法学の世界では、どちらかといえば前者の方が有力なようです。つまり天皇や皇族は国民とは異なる身分であり、身分に伴う特権や義務があるだけで、基本的人権の保障された国民とはそもそも別枠の存在だ、という考えです。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
たとえば上記の日本国憲法の条文を見ると、皇族には、居住、移転及び職業選択の自由は保障されていないと考えられます。これは、「皇族にも自由があるが制限されている」と解釈することもできますが、そもそも「皇族は対象外だ」と考える方が、より自然のようにも思えます。
ともあれ今の時点では、旧皇族であっても国民であることは言うまでもありません。
ここで憲法の第11条を見てみましょう。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
基本的人権が「侵すことのできない永久の権利」なのであれば、勝手に国が国民から剥奪したりすることができないのは当然のことですが、さらにいうと、そもそも、仮に同意があったとしても基本的人権を放棄することなどできないのではないかという疑問が起こります。
祖先が旧皇族であった国民が、自分の同意で、皇族になるために基本的人権を放棄できるというなら、それ以外の国民も、別な分野で、別な理由に基づき、やはり自分の同意で基本的人権を放棄できるということになってしまわないでしょうか。
国民的議論が起こった場合の政治的インパクト
また若干違う角度で考えてみましょう。現在、皇位継承について「男系か女系か」「旧皇族復帰はどうか」という議論は、一部を除いて必ずしも世間一般では盛り上がっているとは言えません。これが国民的議論になり、さらに国会でも取り上げられるようになったら、どうなるでしょうか。
そうなった時に、最も注目されて議論が盛り上がるテーマは、「男系か女系か」の部分ではなく、「そもそも一般国民の基本的人権を剥奪または制限して皇族にすることが妥当なのか」という部分だと思われます。
そのような形で注目され議論を呼ぶことは、国民の皇室観そのものに大きなインパクトを与えて変動させる可能性があるでしょう。
このように、国民である人が皇族に「復帰」するというのはなかなか難しい論点を含んでいるのですが、深く立ち入るとキリがないので、さしあたってはここまでにしておきます。
女性と皇族の結婚では既に起こっていた問題
ただ一つ最後に付け加えるならば、このように「同意があれば、国民の人権を剥奪して、別な『皇族』という身分にできるのか?」という問題は、この近年の皇位男系継承の議論で初めて浮かび上がったたわけではないことに注意が必要です。
この問題は、一般国民の「女性」が男性皇族と結婚して新たな「皇族」になる時に、実は既に起こっていたことなのですが、これまでほとんど話題とされていなかっただけなのです。この点は、下記の過去の記事もご参照ください。本記事で触れた話題と共通する部分も少々含まれています。
よろしければお買い上げいただければ幸いです。面白く参考になる作品をこれからも発表していきたいと思います。

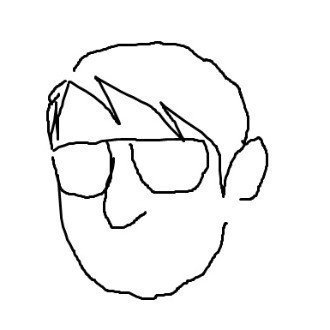
コメント