予備校が浪人生の成績データを公表しないのはなぜか
「2:6:2の法則」?
「浪人すれば成績が上がるのか?」誰しも気になる疑問だと思います。受験界隈では何となく「2:6:2の法則」などと言われているようです。つまり、浪人生のうち成績が上がる人は2割、6割は現状維持、2割は下がってしまうという俗説です。ただし、それを裏付ける統計データは見つかりません。一応それなりに流通している話なので、受験業界の体感値には近いのだろうと思われます。
河合塾講師・新野元基氏はこう言う
この件について、まず河合塾講師の新野元基先生の見解を見てみましょう。
「浪人しても成績は上がらない」という俗説に対して、新野氏はまず、やはりエビデンスがないと述べます。エビデンスがない以上それは主観的な意見にすぎないとした上で、では「浪人しても成績は上がらない」という意見を言いたがるのはどんな立場の人たちか、という話にスライドさせていきます。要するに、それはポジショントークなんじゃないかと言いたいようです。しかし私から見ると、この文章の中には非常に不可解なところがあります。
何しろ私ですら、浪人生全体の何%が成績が上がり、第一志望校に受かったか知りませんからね。
皆さんご存じのように、河合塾は最大規模の全国模試をしている予備校です。現役生も浪人生も同じ模試を受けます。ということは、現役生から浪人生になった受験生たちが、どのような成績推移を辿るのか、統計的なデータを簡単に取ることができるということです。どう考えても難しい統計処理ではありません。誰にでもできます。そんなデータを予備校が分析しないということがあるでしょうか?絶対にありえないと思います。(次節で証明されます)
大規模な模試を実施している各予備校は必ずデータを持っています。浪人生のうちどれくらいの割合が本当に成績が上がるのか。上がり幅の期待値はどれくらいなのか。予備校内部の人は知っているはずです。どうして予備校はそのデータを公表しないのでしょうか?
もし、「2:6:2」のような俗説が間違っていて、本当はもっと成績が上がるのだとしたら、予備校はそのデータを絶対に公表するはずです。これほど強力なアピール材料は他にないからです。しかし実際にはデータを隠しています。この事実から考えられることは1つしかありません。それは予備校にとって都合の悪いデータだということです。
河合塾は平均で偏差値5以上上がると言うが…
河合塾は自身のホームページではデータを公表していません。しかし、ダイヤモンド・オンラインの取材に答えて、「河合塾の内部データ」なるものを示しています。(下記リンク有料記事)
取材に答えたのは河合塾進学教育事業本部教務企画部の柏木智部長です。これで証明されたのは、河合塾の教務企画部ではたしかに浪人生の成績上昇幅に関するデータを取って分析しているということです。なお、この記事の見出しでは「内部データを初公開」と謳っていますので、やはりこれまでは河合塾はそのデータをどこにも公開していなかったことが分かります。
興味深いその中身ですが、どの教科も1年で偏差値が平均して概ね5以上上がるのだそうです。(有料記事のため具体的な数字の転記は控えておきます。)よって2ランク上の大学を狙えると柏木智氏は言います。たしかに偏差値が5も上がれば2ランク上を目指せるでしょう。しかしこの数字は極めて眉唾ものです。まず、どのようなデータを用いたのかが何ら不明です。ただ最終結論の数値だけを示されても説得力がありません。裏では様々なフィルターをかけて、成績が上がっている生徒ばかりを抽出してから平均を取っていると思います。(また、柏木氏は驚愕の数字も挙げています。河合塾の浪人生の入塾時の平均偏差値は約50なのだそうです。そんなに低いのかと驚きました。)
もしこの数字がどこに出しても恥ずかしくない公正な統計データなのであれば、河合塾の公式ホームページに載せるはずです。それをなぜダイヤモンド・オンラインの有料限定記事でこっそり出すのでしょうか。なお、ダイヤモンド・オンラインは「お受験」系の情報を掲載する雑誌であり、受験に向けて保護者を煽るような記事を頻繁に掲載していることで知られています。いわば予備校とは「なあなあ」の関係にあります。予備校にとって都合の良いデータを掲載することはダイヤモンドにとっても都合が良い、そういう関係性です。
河合塾にお願いしたいのは、保有している模試の生データを、自社で都合よく分析するのではなく、大学の教育学の研究室に生データのまま提供して、専門的な統計分析をしてもらってほしいということです。利害関係のない第三者機関が分析すべきです。よろしくお願いします。
ちなみに、この論点について大学による研究データとしては下記のものがあります。生データは予備校がくれないので、仕方なく大学生たちに高校時代の成績を聞き取り調査して追跡調査の代用にしています。この研究室に予備校が生データを提供すれば、必ずや精密な分析結果を出してくれるでしょう。
大学受験における浪人の効果 西丸良一 佛教大学社会学(2006年)
https://core.ac.uk/download/pdf/291802316.pdf
この研究結果について詳細に論じることはしませんが、浪人生の偏差値上昇幅はせいぜい3程度のようです。私がこの論文を見るところでは、おおよそ「2:6:2」の法則は外れていないように見えます。
浪人の判断は慎重に
浪人したら成績が上がるのかという問いに対しては、せいぜい「2:6:2」程度であろうと考えるのが妥当でしょう。そう考えておいた方がいいです。それは浪人を考えている大半の高校生にとっては、冷や水をぶっかけられるような数字だと思います。自分は上位の2割に入れるはずだと信じるのは勝手ですが、その信念にはどの程度の根拠があるでしょうか?よくよく慎重に、冷静に考えたほうがよさそうです。(たとえば、河合塾の偏差値が50もない人が浪人しても、一日何時間勉強できるのでしょうか。それほど長時間は頑張れないはずです。一日の時間の大半を無駄に浪費してしまうのではないでしょうか。)
「成績が下がるなんてそんなバカな」と思われるかもしれませんが、単純な話です。こなせる勉強量が少ない人は、新しく覚えるスピードと忘れていくスピードが釣り合ってしまい、それ以上伸びなくなるのです。維持するだけで精一杯になり、少しサボれば成績が下がってしまうようになります。そして、浪人していくら時間があっても、毎日毎日決まりきった科目の勉強を続けるのは相当飽きますので、案外勉強量は増えないものなのです。現役の頃は学校生活などで忙しいですが、実はそれがちょうどいい気分転換にもなっていたのです。
浪人しても成績が上がる見通しは不透明です。それでも浪人して成功するのはどんな人でしょうか。それは、前年に1点差で落ちたような人です。合格ボーダーライン付近で、誤差の範囲で不合格になってしまった不運な人は、翌年には合格できる可能性が高いです。浪人生の合格者数を稼いでいるのはこういう人たちだと思います。実際、各予備校は成績優秀な浪人生を集めるためになりふり構わない勧誘をしています。受かるのは元々優秀な生徒たちだと認めているようなものです。
以上の現実を見れば、浪人することは極めてハイリスク・ローリターンであり、一般的にはとても勧められません。指導者であれば、まず止めるのが良心だと思います。
成績が上がらないことも覚悟せよ
ここからさらに話を深堀りしてみたいと思います。そもそも日本人はなぜ浪人なんかするのでしょうか?浪人してでも少しでも偏差値の高い大学に行きたいと思うのはなぜでしょうか?それはもちろん、日本が学歴と就職先が紐づいた学歴階級社会だからです。それ自体が歪んだ構造だとしても、少なくとも自分だけは勝ち組になりたい。というか、その意志が強いのはたいてい保護者のほうです。世の親たちは、自分の子どもだけは勝ち組にさせたいと激しく欲望しています。だから浪人受験市場などというものが存在できるのです。ただし、昨今では現役志向が強くなっており、浪人は不人気です。親よりもたぶん子どもたちのほうが、歪んだ競争志向から自由にものを考えているような印象があります。子どもたちの健全な姿勢を見て大人のほうがはっとさせられることもあります。浪人してでも上を目指すというような無理のある発想が淘汰されていくのは好ましいことだと思います。
中には、どうしても叶えたい夢があって、そのためには大学受験で合格する必要がどうしてもあり、完全に挫折するまで挑戦しないと気が済まない、という人もいるかもしれません。そういう生徒がいたら、指導者としては応援しないわけにはいかないでしょう。というか、それこそがあるべき浪人理由だと思います。もし思いのほか成績が上がらなかったとしても決して後悔しないこと。そこが極めて重要なポイントだと思います。
関連記事:
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

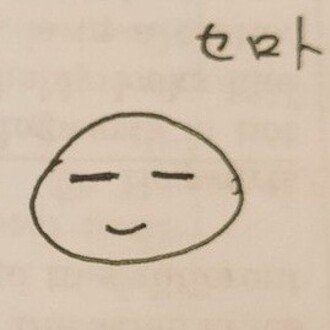
コメント