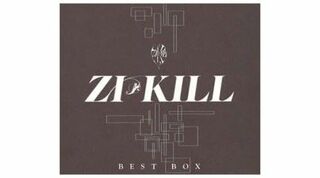ロスジェネエリートの空疎とヒステリー発作
ここで両者の「世代」を確認してみたいのです。
斎藤元彦 1977―:東京大学経済学部卒、元総務官僚、兵庫県知事
石丸伸二 1982―:京都大学経済学部卒、元三菱東京UFJ銀行勤務、前安芸高田市長
いずれも「ロスジェネ」(1970-84年頃に生まれ、バブル崩壊後の“氷河期”に就職活動を行った世代)ど真ん中のなかで、就職には成功したエリートであることが分かります。
この世代は、私にとっては、東京大学に着任して最初に指導した「初期の学生」の世代に当たっており、いろいろ気づくことがあるのです。
端的に言えば、エリートとして仕事には就いたけれど、時代に恵まれず、十分に力が振るえなかった子が少なくない。斎藤、石丸の両氏がそうだ、といっているわけではなく、あくまで一般論として、です。
人間は20代、30代に経験した仕事、そこで成し遂げたことなどが、その後の人生を決めるといっても過言ではない。
私の初期の学生たちを見ても、いまや40代、立派な東大教授になっている子もいますし、職位が安定するや、あっという間に「アームチェア」管理職化して、自分では何もせず、政治にばかり終始する残念な連中もそこそこ散見します。
高度成長期なら、かなり多くの人が、若い時期、本当に汗を流して、実際に意味のある案件を成立させ、手ごたえを持って前進できた。
大学などで言えば本当に自分のライフワークを推し進め、60代、70代になっても現役として仕事を続けておられる。
私が現在もご指導いただく素晴らしい実例として、甘利俊一先生や杉原厚吉先生のお名前を挙げておきます。
私自身いま現在も、本来の仕事をすべて自分で手を動かして、自分のラボは動いています。
ところが、いまの40代あたりには、そういう機会に恵まれなかった人が少なくないのです。