同僚や友人に勧める可能性がどのくらいあるか?
「勧めるか」って、対象の良さだけでは決まらないよね。
某製品のアンケート
先日、会社で使っている某製品で、「この製品を同僚や友人に勧める可能性はどのくらいありますか?」などのアンケートが出てきた。
自分の場合、製品自体は良いと思っているものの、勧める可能性はほぼ無いと評価した。
まず、自分の場合この製品は会社で使っており、同僚も既に使っていることがはっきりしている。そのため、そこにわざわざ勧めるというのはおかしな話である。
また、自分には友人は居ないと思う。「交流がある人」に範囲を広げてみても、普段の状況を考えて、自分がそれらに勧めるという行動をとる可能性は低いと判断した。
なぜ勧める先を限定するのか
この質問において、勧める先はなぜ「同僚や友人」に限定されているのだろうか?
日常生活において、ものを勧める先は同僚や友人だけではない。
たとえば、記事を書くことでインターネット上の誰かに勧める、という場面もあるだろう。
「勧めるか」という観点は、ただ単に「良いと思うか」とは異なる評価軸である。
単に「良い」だけでは、勧めたくなるとは限らない。
良さに大きく感動したら勧めたくなるかもしれないし、逆に「独り占めしたいから勧めない」と判断するかもしれない。言及はするけど教えない田村ゆかり…なんてのもあったなあ。
さらに、勧める先を「同僚や友人」に限定することで、勧めるハードルをさらに一段上げることになる。
勧める先を限定する理由として考えられることの一つは「嫌いな相手に勧める可能性の排除」である。
通常は良いと思ったものを勧めるだろうが、逆に不便だと思っているものを嫌がらせのためにわざと嫌いな相手に勧める、という可能性も考えられる。
勧める先を「友人」に限定することで、このように「嫌いな相手」を勧める先から外すことを狙っている可能性もある。
ただし、それにしては勧める先は「友人」に限定されておらず、「同僚」も入っている。
人によっては、「同僚」の中に嫌いな奴が居るかもしれない。
すると、勧める先として「嫌いな相手」が排除しきれず、「嫌がらせのために勧める」が入ってくるかもしれない。
とはいえ、何も条件を付けないよりは減る可能性はあるだろう。
「同僚や友人」の定義を再考する
これまで、「同僚」の定義を「同じ会社で働く人で、世代が近い人」だと仮定してきた。
しかし、よく考えたら、そうとは限らない。
たとえば、ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』では、いわゆる「フレンド」のことを「同僚」と呼ぶ。
この「同僚」は、SNS上などで交流がある人をコードで指定して作ることもある。
ということは、そのような「同僚」が見ている可能性が高いと考えられるSNS上での発信により勧める行為は、「同僚に勧める」行為であるとみなせる可能性がある。
そう考えると、「友人」についても、ゲームの「フレンド」の(誤)訳である可能性もありそうな気がする。
別の質問の候補を考える
製品を同僚や友人に勧める可能性を調べたいのであれば、「この製品を同僚や友人に勧める可能性はどのくらいありますか?」という質問でも全く問題ないだろう。
しかし、製品がどのくらい良いと思われているかを調べるなど、目的が違う場合は、この質問では適切な結果が得られない可能性がある。
そこで、この質問のかわりとなる質問の候補をいくつか考えてみた。
まず、単純に勧める先の条件を外した「この製品を勧める可能性はどのくらいありますか?」が考えられる。
答える側としては、同僚や友人に勧めやすいならば同僚や友人に勧めることを考えればよいし、インターネット上やその他の場面で勧めやすいならばそれらの場面を考えればよい。
単に「良いと思う」だけでなく「勧める」というハードルは残しつつ、より好意的な回答が得やすくなるだろう。
他の可能性として、「この製品を紹介するとしたら、どの程度好意的に紹介しますか?」も考えられる。
勧めるか勧めないかを考えるのではなく、まず「紹介する」ことを前提にしてしまうのである。
紹介のしかたとして、
良かったので、おすすめする
悪かったので、不満を書き連ねる
中立的に、メリットとデメリットを紹介する
など、様々なパターンが考えられる。
ただし、「なぜ紹介することになったのか」を考えたとき、「スポンサー契約をしている」という可能性も出てくるだろう。
すると、悪いことを書かず、いいことを書くことが求められてしまうかもしれない。
こう考えられるのを防ぐため、「スポンサー関係や、誹謗中傷でなくても悪いことを書くと消されてしまう可能性などは考えず、自由に表現できるとする」という条件を明示するのもいいだろう。
さらに、直球で「この製品はどのくらい良いと思いますか?」と聞く選択肢もある。
いわゆる星の数での評価は、多くがこのパターンだろう。
もちろん、この場合「勧める」ハードルは無くなる。それがいいか悪いかは、調査の目的によるだろう。
まとめ
「この製品を同僚や友人に勧める可能性はどのくらいありますか?」という質問は、単純な「この製品はどのくらい良いと思いますか?」という質問に比べて、
単に良いと思うだけでなく「勧める」かどうかを聞いている
しかも、その勧める対象が「同僚や友人」に限定されている (ただし、これらにはゲーム上のフレンドなども含まれる可能性がある)
という特徴がある。
「勧める」か、という観点は、良い製品であっても
相手も既に知っていると予測できる
ものを勧める場面が無い
勧める先が居ない
独り占めしたい・広まらないでほしい
などの理由で勧めない可能性があり、単に「良い」かとは別の評価軸である。
アンケートを実施する側は、調査の目的によって、
この製品を同僚や友人に勧める可能性はどのくらいありますか? (そのまま)
この製品を勧める可能性はどのくらいありますか? (勧める先の限定を外す)
この製品を紹介するとしたら、どの程度好意的に紹介しますか? (紹介するのを前提にする)
この製品はどのくらい良いと思いますか? (「勧める」ハードルを無くす)
など、適切な質問を選ぶのがよいだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

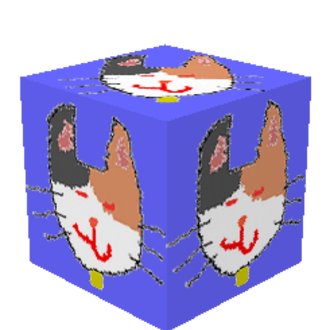
コメント