40代からのひきこもりは危険!長期化するとどうなる?専門家が解説する予防と対策」
こんにちは、精神科薬剤師 京大右京です。今回は、「
この記事を読んでいるあなたは、自分や家族、友人など、身近な人にひきこもりの状態にある人がいるのではないでしょうか。ひきこもりとは、様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念です。
ひきこもりは、若者だけの問題ではありません。内閣府が令和元年に実施した調査によると、満40歳から満64歳までの人口の1.45%に当たる61.3万人がひきこもり状態にあると推計されています。また、ひきこもり状態になってから7年以上経過した方が約5割を占め、長期化する傾向が認められています。
40代からのひきこもりは危険です。長期化すると、心身の健康や生活環境、経済的な問題などが深刻化し、社会復帰が困難になります。また、親や配偶者などの介護や死別などのライフイベントが発生した場合、孤立や自殺などのリスクが高まります。さらに、社会保障制度や支援サービスの不備や不足もあり、適切な支援を受けることが難しい場合もあります。
では、40代からのひきこもりはどうすれば予防や対策ができるのでしょうか。私は精神科薬剤師として、以下のような方法をおすすめします。
予防40代からのひきこもりを予防するためには、以下のようなポイントが重要です。
仕事や趣味など、自分に合った社会的役割を見つける
家族や友人など、信頼できる人間関係を築く
心身の健康を保つために、適度な運動や睡眠、食事などを心がける
ストレスや悩みを抱え込まずに、相談できる人や機関を探す
自分の感情や思考を客観的に観察し、自己肯定感や自己効力感を高める
これらのポイントは、自分自身の価値観や目標に基づいて実践することが大切です。また、無理せずに小さく始めてみることも効果的です。例えば、仕事や趣味など、自分に合った社会的役割を見つける
自分の興味や能力に合った仕事を探す
趣味や学びのために、オンラインやオフラインのコミュニティに参加する
ボランティアや地域活動など、社会貢献できることをする
家族や友人など、信頼できる人間関係を築く
家族や友人と定期的に連絡を取る
気軽に話せる相手を増やすために、SNSやチャットなどを利用する
コミュニケーションのスキルを向上させるために、本や動画などを参考にする
心身の健康を保つために、適度な運動や睡眠、食事などを心がける
毎日決まった時間に起きて寝る
食事はバランスよく摂り、水分や栄養補給も忘れない
運動は自分の好きな方法で行い、無理のない範囲で続ける
ストレスや悩みを抱え込まずに、相談できる人や機関を探す
家族や友人など、信頼できる人に話す
専門家や相談員など、プロの支援を受ける
電話やメールなど、気軽に相談できるサービスを利用する
自分の感情や思考を客観的に観察し、自己肯定感や自己効力感を高める
マイナスな感情や思考に気づいたら、それが本当かどうか疑ってみる
マイナスな感情や思考をポジティブなものに置き換えてみる
自分の長所や成功体験を思い出してみる
対策40代からのひきこもりが発生した場合は、早期に対策することが重要です。対策するためには、以下のようなプロセスが必要です。
現状の把握と目標設定
支援機関の選択と連絡
支援プログラムの実施と評価
現状の把握と目標設定まずは、自分自身または家族がひきこもりの状態にあることを認めることが大切です。否定的な感情や思考に囚われずに、冷静に現状を把握しましょう。その際には、以下のような点に注意してください。ひきこもりは病気ではありません。社会的参加が困難になった状態です。
ひきこもりは個人の責任ではありません。社会的要因や心理的要因が影響しています。
ひきこもりは恥ずかしいことではありません。多くの人が経験しています。
ひきこもりは一人で解決できることではありません。支援が必要です。
現状を把握したら、次は目標を設定しましょう。目標を設定することで、ひきこもりからの社会復帰に向けて、具体的な行動や計画が立てやすくなります。目標を設定する際には、以下のようなポイントが重要です。目標は自分自身の意思で決める
目標は現実的で達成可能なものにする
目標は明確で具体的なものにする
目標は段階的で小さなものから始める
目標は評価や修正ができるものにする
これらのポイントは、SMART法則と呼ばれる目標設定の方法に基づいています。SMART法則とは、以下のような頭文字を持つ言葉で表される原則です。S: Specific(明確)
M: Measurable(測定可能)
A: Achievable(達成可能)
R: Relevant(関連性)
T: Time-bound(期限)
例えば、「外出する」という目標をSMART法則に沿って設定すると、次のようになります。S: Specific(明確)
外出するという目標は、どこに行くのか、誰と行くのか、何をするのかなど、具体的に決める
例:近所のコンビニに一人で買い物に行く
M: Measurable(測定可能)
外出するという目標は、どれくらいの距離や時間をかけるのか、どれくらいの頻度で行うのかなど、数値で表せるようにする
例:徒歩5分以内のコンビニに10分以内で買い物に行き、週に1回以上行う
A: Achievable(達成可能)
外出するという目標は、自分の能力や環境に合わせて、無理のない範囲で設定する
例:コンビニは近所にあるし、一人で行けるし、買い物も簡単だから、達成可能だと思う
R: Relevant(関連性)
外出するという目標は、自分の価値観や長期的な目標と関連していることを確認する
例:外出することで、社会とつながる感覚や自信を取り戻したいと思っているから、関連性があると思う
T: Time-bound(期限)
外出するという目標は、いつまでに達成するかを明確に決める
例:今月中にコンビニに一人で買い物に行くことを目指す
以上のように、SMART法則を用いて目標を設定することで、ひきこもりからの社会復帰に向けて、具体的な行動や計画が立てやすくなります。また、目標を達成したら、自分自身を褒めたりご褒美をあげたりして、モチベーションを高めましょう。
支援機関の選択と連絡次に、ひきこもりからの社会復帰に向けて、支援を受けるために必要な支援機関を選択しましょう。支援機関とは、ひきこもりの方やその家族に対して、相談や支援を行ってくれる機関のことです。支援機関には、以下のような種類があります。
ひきこもり地域支援センター
市町村が設置する相談窓口で、ひきこもりの方やその家族に対して、相談や情報提供、支援機関の紹介などを行ってくれる
[ひきこもり地域支援センターの一覧]を参照して、最寄りのセンターを探す
ひきこもり支援ステーション
厚生労働省が開始した新しい事業で、ひきこもりの方やその家族に対して、相談支援・居場所づくり・ネットワークづくりを一体的に実施する
[ひきこもり支援ステーション事業]を参照して、実施団体を探す
ひきこもりサポート事業
厚生労働省が開始した新しい事業で、市町村が地域の特性に合わせて任意に事業を選択し、実施する
[ひきこもりサポート事業]を参照して、実施団体を探す
精神保健福祉センター
都道府県が設置する相談窓口で、精神障害や心の問題に関する相談や情報提供、支援機関の紹介などを行ってくれる
[精神保健福祉センターの一覧]を参照して、最寄りのセンターを探す
医療機関
精神科や心療内科などの医療機関で、精神的な症状や問題に対する診断や治療を受けることができる
[医療機関検索]を利用して、最寄りの医療機関を探す
これらの支援機関は、自分の状況やニーズに合わせて選択することが大切です。また、複数の支援機関と連携することで、より効果的な支援を受けることができます。支援機関を選択したら、電話やメールなどで連絡してみましょう。その際には、以下のような点に注意してください。
支援機関の営業時間や予約方法などを確認する
自分の名前や連絡先などを伝える
自分の状況や相談内容などを簡潔に伝える
支援機関からの回答や提案などを聞く
相談日時や場所などを確認する
支援プログラムの実施と評価最後に、支援機関から提供される支援プログラムに参加しましょう。支援プログラムに参加することで、ひきこもりからの社会復帰に向けて、具体的なスキルや知識を身につけることができます。支援プログラムには、以下のような種類があります。相談支援
支援機関の相談員や専門家と一対一で話し合い、自分の状況や目標、支援の必要性などを共有する
自分に合った支援プランを作成し、実行するためのアドバイスやサポートを受ける
居場所づくり
支援機関の施設やオンライン上で、ひきこもりの方やその家族、支援者などと交流する
自分の居心地の良い場所を見つけ、自分らしく過ごす
他者とのコミュニケーションや協調性などの社会的スキルを学ぶ
ネットワークづくり
支援機関が主催するイベントや活動に参加し、ひきこもりの方やその家族、支援者などと関わる
自分の興味や関心に沿ったグループやコミュニティに参加する
社会とつながる感覚や自信を取り戻す
これらの支援プログラムは、自分の状況やニーズに合わせて選択することが大切です。また、複数の支援プログラムを組み合わせることで、より効果的な支援を受けることができます。支援プログラムに参加したら、以下のような点に注意してください。
支援プログラムは強制ではありません。自分のペースで参加することができます。
支援プログラムは秘密厳守です。自分の個人情報や相談内容などは、他者に漏らされることはありません。
支援プログラムは評価されます。自分の目標達成度や満足度などを定期的にフィードバックすることができます。
支援プログラムは改善されます。自分の意見や要望などを伝えることで、より良い支援プログラムになる可能性があります。
以上のように、支援機関から提供される支援プログラムに参加することで、ひきこもりからの社会復帰に向けて、具体的なスキルや知識を身につけることができます。また、支援プログラムに参加することで、自分だけではなく、家族や友人などの周囲の人々とも良好な関係を築くことができます。
まとめ40代からのひきこもりは危険です。長期化すると、心身の健康や生活環境、経済的な問題などが深刻化し、社会復帰が困難になります。しかし、40代からのひきこもりは予防や対策が可能です。予防するためには、仕事や趣味など、自分に合った社会的役割を見つけることや、家族や友人など、信頼できる人間関係を築くことなどが重要です。対策するためには、現状の把握と目標設定を行い、支援機関を選択し、支援プログラムに参加することが必要です。
私は精神科薬剤師として、40代からのひきこもりに関する最新の統計データや専門的な知識をもとに、このブログ記事を書きました。この記事が、ひきこもりの方やその家族、支援者などにとって、有用な情報やヒントになれば幸いです。もし、この記事に関するご質問やご意見がありましたら、コメント欄にお気軽にお寄せください。また、この記事が気に入ったら、SNSでシェアしていただけると嬉しいです。それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?


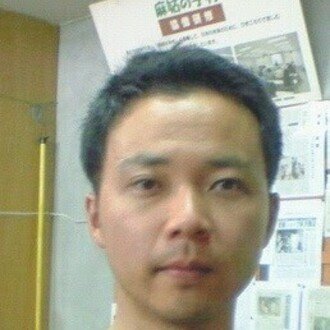
コメント