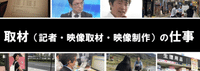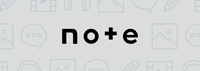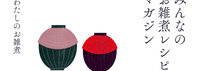藤井聡太の素顔に迫るため、雑煮について尋ねてみたら
「藤井家のお雑煮には、どんな具材が入るんですか?」
これは、2017年、私が初めて藤井聡太さんに単独インタビューした時の1問目の質問です。
当時15歳にして将棋界の顔、寡黙で冷静沈着、慎重にことばを選ぶ藤井さんからどうことばを引き出すか、我ながら苦肉の策だったなと、振り返ると恥ずかしくなります。
私は6年前から将棋を取材してきました。藤井さんは、驚くほどに謙虚な方だと思います。
インタビューではいつも「自分が思っていること」を的確にことばにし、それを超えるようなことは言いません。
成し遂げている偉業からすれば「もうちょっとかっこつけてくれてもいいのに」と感じるほどです。
記者として向き合ってきた、藤井さんの人柄と、そのことばについてお伝えしたいと思います。
「科学文化部」ってご存じですか…?
はじめまして。河合哲朗(34歳)と申します。NHKの記者です。
所属は「科学文化部」(通称:かぶん)という部署です。
社会部や政治部は聞きなじみもあると思いますが、NHKには「科学文化部」という部があるのです。
取材テーマは「宇宙」「原発」「医療」「ノーベル賞」から、「音楽」「漫画」「芸能」「IT」など……けっこう幅広いです。
専門性を持った比較的くせの強い記者たちが複雑多岐にわたる取材に奔走している、なかなかユニークなチームだと思っています。
ちなみにこちら、最近「かぶん」で始まったWEB連載シリーズ「推し研」。けっこう評判いいです。まだ第一弾で、今後記事が増えていきます。
(サイカルジャーナルのサイカルは、サイエンス&カルチャーの略です)
私は「かぶん」で文化取材を担当しています。
この記事を書いている間にも、嵐の櫻井さん相葉さんの結婚発表、さいとう・たかをさんの訃報が入りました。これらも文化記者の取材領域の1つです。
将棋を“打つ”と言って恥をかいた私が将棋担当に…
将棋を取材するようになったのは2015年から。ついさっき「専門性を持った記者」とか言いましたが、すみません、実は将棋に関しては担当になるまで完全なる“素人”でした。
思い返すと、将棋との唯一の接点は小学生の時。当時やっていた朝ドラ『ふたりっ子』(ヒロインが女性棋士を目指す物語)の影響で、親にプラスチック製の将棋セットを買ってもらったことがありました。
兄にボロボロに負かされて、センスのなさにがく然とし、盤をひっくり返して「礼儀がなってない」と精神面さえも否定されてからは、自然と将棋とは距離を置いてきました。
それから20年以上たった今、通勤電車で詰将棋アプリの解答にいそしむ程度には、将棋に夢中になっています。
かくして「経験値ゼロ」で将棋の取材を始めた私。“素人感”を悟られないよう、“付け焼き刃”で知識を詰め込んで東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」に乗り込みましたが、一瞬で見破られました。というか、失言で墓穴を掘りました。
私「ここで○○さんが“打った”一手ですけど…」
棋士「…あの、将棋は“打つ”じゃなく“指す”なので、気をつけるといいですよ」
そこからは恥を忍んで、「教えてください」のスタイルで取材を続けてきました。棋士の皆さんはとても心の広い方が多く、こんな私にも丁寧に将棋のことを教えてくださりました。
担当となってからの6年間は、将棋界で大きな話題が続いた時期でした。人工知能=AIを搭載した将棋ソフトが現役の名人を破るという“事件”。
羽生善治さんによる「永世七冠」の快挙もありました。そして、藤井聡太さんという棋士の登場です。
2016年に中学2年生で最年少棋士となり、その後の歩みがそのまま将棋界の新たな歴史になっている藤井さん。
デビュー時から取材を続けていますが、正直、もう去年くらいからは「すごさ」を形容することばが尽きました。
この5年ずっと「すごい」ので、日々のニュースで「すごい」をどう更新したらいいのか、悩んでいるレベルです。
▼藤井さんの「すごさ」をまとめた記事はこちら▼
藤井さんから“名言”を引き出したいのだけど…
藤井さんはこの春に高校生活を終えましたが、それまでは「学業との両立」を理由に個別の取材はほとんど認められてきませんでした。ただ年に1回だけ、1社30分ほどの単独インタビューの機会が与えられます。
NHKのニュース番組では、年始の放送で各界の著名人への「新春インタビュー」を紹介することがあります。
今をときめく藤井さんへの単独インタビューはこの枠に採用されることが多く、「お茶の間に藤井さんの“名言”を届けよう!」と、記者としては力が入ります。
当時の記録を探してみたら、プロ入り1年目を振り返る、初の単独インタビューの文字おこしがありました。
私「ちなみに、藤井家のお雑煮には、どんな具材が入るんですか?」
藤井「ああ、そうですねー、いやあまり気にしたことがなかったんですけど。ただ、みそではないんですね。しょうゆで」
私「瀬戸市(藤井さんの地元)では、お餅って丸いんですか?」
藤井「そうですねー、ちょうど愛知県は丸と四角の境界くらいかなと思います。うちは四角ですね…」
雑煮と餅のジャブで間合いを探るも、特にほぐれた実感もなく、時間も惜しいので本題に。
この日、私が藤井さんから聞きたかったのは「タイトル獲得」という目標について。将棋界には「竜王」「名人」など8つのタイトルがあり、これらを獲得することは“トップ棋士”の証となります。
デビューから29連勝という大記録を達成した藤井さんがタイトルについてどう考えているのか、聞きたいと思ったのです。
私「早くも、“いつかはタイトルを”という期待の声も聞こえてきます」
藤井「プロ棋士になったからにはもちろん、その舞台に立ちたいという気持ちは強いですし、それに向けて努力して行きたいと思っています」
私「タイトル戦の舞台に立つ自分は、想像できるものですか?」
藤井「それはこれからの自分の成長にかかっているので、早くその舞台に立てるだけの実力をつけたいと思っています」
この日の取材の中で藤井さんは、一貫して、私が質問した「タイトル」ということばを「その舞台」と言いかえて話しました。
おそらくですが、プロ1年目の立場で「タイトル」を語ることに“恐れ多い”ような思いがあったのだろうと思います。
「中学3年生にしてこの自制心」と驚きましたし、そのような心中も想像せずに力強いことばを引き出そうとした自分が恥ずかしくもなりました。
藤井さんはことし、早くも3つめのタイトルを獲得して「三冠」となっていますが、こうした“謙虚さ”は、今もまったく変わりません。「三冠」達成後の会見でも、今後の「八冠」の可能性を問われ、こう話していました。
「まずは実力が今以上に必要になるので、現時点でそれを意識するのではなく、より実力を高めた上で、そういったところに近づくことが一つの理想なのかなと思います」
“10秒の沈黙”と“完璧な日本語”
藤井さんへの取材で、もうひとつ気がついたことがあります。
ふだん多くの人をインタビューしていて感じるのですが、人と人との会話では誰でも、言いよどみや語順が前後するようなことが頻繁にあります。
それでも意味は通じますし、私たちも日常会話では“完璧な日本語”なんて話していないものだと思います。
こちらは、藤井さんのインタビューの文字おこしです。
まず気がつくのは、私の質問に対して藤井さん、ほぼすべて「そうですね…」。
字数にして5文字ですが、肌感覚としてはこの間およそ10秒。
(10秒って、短いと感じるかもしれませんが、相対しての10秒、かなりの静寂になります。ぜひ一度、心の中で、1・2・3…と数えてみてください。それも、目の前には藤井さんがいる前提で。)
その沈黙のあと、藤井さんが話すことばには、言いよどみがほとんどありません。語りはじめから終わりまでが一直線に進み、語順が前後するようなことも極めて少ないのです。
この“完璧な日本語”。文字おこしでことばを見ることの多い、記者だから感じる一面かもしれません。
おそらく藤井さんは「そうですね…」の沈黙で、自分の考えを整理し、その考えを言い表す最も近いことばを探しているのだと感じます。
藤井さんとのインタビューでこうした沈黙があるたびに、「私の質問の何手先まで読まれているんだろう…」といつもそわそわします。
現場の記者「いちばん聞こえない」説
記者にとって、勝負の世界に最も近づけるのは、やはり対局当日の取材です。
対局中、記者は別室で待機し、モニターで進行をチェック。終局すると急いで対局室に移動し、対戦を終えたばかりの棋士から話を聞きます。
棋士の声を間近に聞けるとても貴重な機会なのですが、これが、かなりの集中力を要します。
というのも、終局後の棋士の声は、想像以上に小さいのです…。
ことし8月24日・25日の王位戦第5局、藤井さんの発言をノートに走り書きしたメモは、こんな感じです。
「5八金と上がったが、単に●●●とかで強くいく必要があったか。4四角と上がられると、次●●●が難しくて少し損をしてしまったかなと思った。9七桂と跳ねて●●●の変化で、こちらの玉が寄らなければ、飛車を取れるのが大きいと思っていた。」
随所でがっつりと聞き逃しています。
文字通り耳を傾けて取材しているのですが、こうなることはしばしば…。
といっても、これは無理もないのです。将棋の対局は長い場合2日間にわたって行われます。
棋士は想像を絶するエネルギーを消費し、記者が取材するときは、体力的にも精神的にも消耗しきった状態。声をかけるのが申し訳ないほどです。
もとより決して声の大きい方ではない藤井さん。終局直後となると、聞き取れるか聞き取れないか、微妙なボリュームの小声となります。だいたいここに、カメラのシャッター音が加わり、心が折れます。
取材後、記者たちが「これであってたかなぁ…」と不安げにノートを見つめる光景にも見慣れてきました(だいたい、ICレコーダーで聞き直すことに…)。
おそらく、ネット中継で対局を見ている方々の方が、私たちより、よほどはっきりと対局者の声が聞こえていると思います…。
▼ちなみにこの日の原稿はこんな感じになりました▼
コロナ禍で将棋の現場にも変化
藤井さんというと、世間を大きくにぎわせたデビュー後の29連勝を思い出す方も多いと思います。連勝が重なるたびに報道陣の数が増え続け、無数のカメラが対局室を埋め尽くしました。
藤井さんの後方からしかカメラを構えられないメディアも出るほどで、今振り返れば、絵に描いたような“3密”です。
▼2017年6月 竜王戦・決勝トーナメント(29連勝 達成直後)▼
藤井さんの活躍はその後も変わらないどころか、さらに大舞台で大記録を打ちたて続けています。ただ、コロナ禍で、現場の状況は大きく変わりました。
今は、対局室に入れる報道陣の数が制限され、代表社のみが撮影を行い、写真と映像を各社で共有しています。
▼2021年6月 王位戦・七番勝負 開幕局▼
私はテレビの代表社としてこの夏の「三冠」達成の過程を各地で取材しましたが、藤井さんが目の前で成し遂げている偉業に比べ、会場はいつもがらんとしています。
幸運にも歴史的瞬間に立ち会っている身としては、感染対策が最優先だとは理解しつつも、どこか少しさみしくも感じるのが正直なところです。
突然やってくる“名言”
藤井さんを追う5年間の中で、とても胸に響いたことばがあります。
去年7月、初タイトルとなる「棋聖」を獲得したあとの記者会見。
「AIが発達する今、人間の棋士の存在意義は?」と問われた藤井さんは、やはり10秒ほどの沈黙のあとで、こう語りました。
「今の時代においても、将棋界の盤上の物語は不変だと思います。その価値を自分自身、伝えられればと思っています」
率直に言って「かっこいい」と思いました。
はじめに書きましたが、藤井さんはいつも慎重にことばを選んで話すので、自然と「控えめ」なことばを口にすることが多い印象です。
そんな藤井さんから、突然こんな「かっこいい」ことばが出ると、「藤井さんは、心の底からそう思っているんだな」とわかるだけに、いち取材記者としてグッときてしまうのです。
▼当時の取材をWEB記事にしています▼
藤井さんは10月から、史上最年少「四冠」をかけて、最高峰の舞台「竜王戦」に挑みます。相手は豊島将之竜王。棋界の頂点に立つ2人の勝負をしっかりと取材したいです。
そしてこれから先も、藤井さんからどんな「心からのことば」が聞けるのか、楽しみです。
トップ棋士が語る“藤井聡太”
9月、私はトップ棋士に藤井さんについて話を聞くという貴重な取材機会を得ました。
ここで、その一部を紹介させていただきます。
“永世七冠” 羽生善治 九段
「すべての棋士が、藤井さんがどんな将棋を指すかに注目しています。最高峰、最先端の将棋を見せてほしい」
“前竜王” 広瀬章人 八段
「正直言うと、よくいる若者だなという印象が強いんですけど、指し手が恐ろしく正確で鋭いので、ちょっと不思議な感覚です。一緒にいても特にすごいオーラをまとっているわけではないんですけど、盤を前に対じすると、力の違いを見せつけられる」
“元王座” 中村太地 七段
「藤井さんは、人より明らかに精度の高い羅針盤を手にして航海している印象です。海が広くて何も目標物がないように見える中でも、しっかりと進むべき方向を把握することができる」
勝負の世界に生きる棋士にとって、藤井さんは“最大のライバル”です。
それでも、このように語る表情からはどこか、藤井さんという才能が同時代に現れ、共に将棋の真理を追究できることにわくわくしているようにも感じました。
こうしたトップ棋士のインタビューも交え、藤井さんの進化に迫る番組を放送します。
クローズアップ現代+「藤井聡太 最強への道 史上最年少“四冠”なるか」【総合】10月7日(木) 午後7時30分~
将棋ファンの方はもちろん、あまり詳しくないという方にも、将棋の世界の魅力が伝わるとうれしいです。
▼関連記事はこちら▼
―――――――――――――――――――――
科学文化部 記者 河合哲朗
2010年入局。前橋局、千葉局を経て、科学文化部で文化取材を担当。最もうれしかった取材はみうらじゅんさんにインタビューできたこと。趣味は地方のレコード屋とサウナ巡り。
▼過去の取材記事はこちら▼