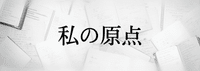探検と冒険の違いを知っていますか?洞窟探検で人生が変わった深く長い話
突然ですが、探検と冒険の違いって知っていますか?
似ているように見えて、実は違います。
漢字をよく見てください。「けん」の漢字が違いますよね。
冒険の「険」は「危険」の「険」。「危険を冒す」と書きます。
一方の探検の「検」は、検査や検証の「検」。「しらべる」という意味です。探検は、自然に挑んだり、記録に挑戦したり、達成感を味わったりすることが目的ではありません。
誰も行ったことがない場所や限られたスキルを持った人しかいけない場所に行って、そこを調査すること。それが探検です。
これは洞窟探検で人生が変わった1人のカメラマンの話です。
山に登らない“山岳班”カメラマン
洞窟って聞いても、正直、あまりイメージが湧きませんよね。ああ、ゲームで魔物が出てくるところだよね。修学旅行で鍾乳洞に行ったことがあったなぁ。そのくらいの印象じゃないでしょうか。
私、門田真司は、NHKの報道カメラマンの中で唯一の洞窟取材班(自称)。 現在はインドネシアのジャカルタ支局に勤務しつつ、東京にある映像センターの「山岳取材班」のメンバーでもあります。山岳取材班は、様々な山の取材をするための専門知識や技術を持ったカメラマンの集団です。
みんなが高いところを目指して山を登っていくのに対し、私は地下に潜っていくアンダーグラウンドなやつ。大学時代から洞窟探検を始め、かれこれ20年以上。たくさんの洞窟を取材し、ニュースや番組を出してきました。
あ、山に登らないとは言いましたが、実は山も大好きですよ。たまに山の取材もやります(笑)
※"洞窟取材班"門田カメラマンが携わってきた洞窟番組はこちら※
洞窟は常に変化している
ところで皆さん、「世界で一番深い洞窟はどこか」知っていますか?
実は、洞窟の規模を表すには「深さ(入り口からの高低差)」「長さ(総延長)」「大きさ(一つの空間としての容積)」という主に3つの概念があります。
世界で一番「深い」洞窟は、現段階ではベロブキナという洞窟。ジョージアという国にあり、深さは-2212mあります。
世界一「長い」洞窟は、現段階ではアメリカにあるマンモスケイブシステム。つい先日、全長が670kmを超えたというニュースが飛び込んできたばかりです。これは直線距離で東京-広島間とほぼ同じ距離です。
そして一つの空間として世界最大の容積を持つ洞窟は、現段階では中国・貴州省にあるミャオティンです。容積は1000万m³以上(東京ドーム8個分以上)。地元に住む少数民族からは「龍の巣」としておそれられています。この洞窟、私の洞窟取材のノウハウとネットワークを駆使して、3年かけて番組を作りましたが、詳しい話はまた後ほど・・・。
さて皆さんお気づきでしょうか?
全て「現段階では」です。実は洞窟は、いまだに世界中で新しい洞窟や、未知の空間が発見されていて、その深さや長さ、大きさの数字や順位は常に変化しているのです。
たとえば世界一深いベロブキナ洞窟ですが、私が大学生の頃(2000年代)は世界一ではありませんでした。当時、世界で一番深い洞窟は、深さ-1700m程のクルーベラという別の洞窟。その後、探検家たちが困難な場所を突破して奥に進んだり、未知の空間を見つけたりして、ベロブキナが数年前に世界一深い洞窟になったのです。
第2位となってしまったクルーベラも、現在-2199mまで探検が進んでいて、トップのベブロキナとの差はわずか13m。もしかしたら、この記事を書いている間にもクルーベラが世界最深の洞窟の座を取り戻しているかもしれません。
私が取材した世界最大のミャオティンも2013年のイギリスの探検隊の調査によって、世界一の大きさであることがわかりました。
山や川、海などと違って洞窟は、いまだにどこが一番長いのか、深いのか、大きいのか確定していません。狭く、暗い地下の洞窟ではヘリや潜水艇などの乗り物を使うことができません。衛星写真や航空写真で写すこともできません。完全に真っ暗なので、その全貌を見ることすら困難です。
この科学が発達した21世紀で、人類が己の力のみで実際に行かなければ、どんな形状なのか、どこまで続いているのか、何があるのか全くわからないのが洞窟なのです。いまだに誰にも発見されていない未知の洞窟もたくさんあります。
洞窟こそ、この地球に残された最後の地理的なフロンティア。
人類が誰も足を踏み入れたことのない場所に自分が初めて到達したとき、そこに何があるのか、何がいるのか。それこそが洞窟の最大の魅力、そしてロマンです。
洞窟探検を語ると止まらなくなります。
実は私がNHKに入るきっかけも洞窟でした。
探検部の格言「金で買える安全は買え」
登山家だった父の影響で、私は高校時代は登山部に所属していました。
大学に入学したときに「探検部」という聞いたこともない部活に出会います。
ただ山を登って下りるだけではない活動をしていた探検部にひかれ、洞窟探検にのめり込んでしまいます。
「ジャングルでヘビや虫を食べているの?」
「山や湖で未確認生物を探しているの?」
探検部と言うとよく聞かれますが、そんなことはありません。
私が所属していた立命館大学探検部は研究機関や行政機関などと組んで、通常では到達できないような困難な場所での学術的な調査を行うことが目的でした。
普段は厳しい訓練や合宿ばかりやっているので、よく体育会系と間違われるのですが、大学での分類は“学術部”です。
歩いて行くことができる「横穴洞窟」ではなく、ロープを使って登り降りする垂直に落ち込んだ「竪穴洞窟」を専門としていて、もっぱら大学の体育館の壁面にロープを張って登り降りの訓練をしていました。そのため大学ではスパイダーマン的存在で有名でしたが、“学術部”です。
格言は「金で買える安全は買え」
可能な限り危険を回避し命を大切にしろ、使えるものはなんでも使え、危険を冒すことが目的ではないという先輩方の教えでした。そのため海外に探検に行くときは、資金や物資を提供してくれるスポンサーの獲得も大切な仕事でした。
立命館大学探検部は主に山、川、洞窟の3パートで活動していて、私は山と洞窟のパートに所属し、全国各地や海外の洞窟探検に明け暮れていました。明け暮れ過ぎて留年して5回生になり、さらには就活もしていなかったので、気づいた時には卒業してプータローになっていました。
未知の洞窟を発見したら、NHKに発見された
そんな時、1本の電話がかかってきます。
「去年あなたたちの探検部が中国の奥地で巨大洞窟を発見したと聞いた。その巨大洞窟の番組を作りたいので協力してくれないか」
NHKのディレクターを名乗る人物からでした。
確かにその前年、私は1980年代から続く立命館大学探検部第8次日中共同中国洞窟調査隊の日本隊隊長として、中国の研究機関とともに中国南部の洞窟の調査を行いました。
そして深さ300mを超える竪穴洞窟や新種の昆虫などを発見。新種の昆虫は国立科学博物館の名誉研究員の方から論文としても発表されました。
でもその成果は「洞窟の世界」では有名でしたが、一般の人が知るようなものではなかったはず。さすがNHKの情報収集力。一体どこからそんな情報を手に入れたのだろう。
不思議に思いながら、連絡を取ってきたディレクターと会いました。
思う存分洞窟の話を終えると、ディレクターは若干疲れ気味な様子に見えました。
そして突然、こう言い出したのです。
「門田君、君はかなり面白いことをやっているね。熱いね!
プータローでしょ?この先どうするの?
決まってないならNHKの就職試験を受けてみたら」
「NHKはね、僕とか君みたいな変わった人も多いんだよ(笑)
君は最前線に出る映像取材(報道カメラマン)が向いていると思うよ」
えっ、NHK?どうせ落ちるだろうと思い、ディレクターには何も言いませんでしたが、調子に乗ってコソッとNHKを受けることにしました。
すると、まさかの内定・・・
内定者として「NHKスペシャル 神秘の巨大穴 天坑」の中国ロケに同行しました。
「実はNHKに合格しました」
ディレクターに伝えると相当驚かれたので、まさか本当にNHKを受けるとは思っていなかったようです。
高さ200mの洞窟の壁面にロープを設置しているところ。
今思えば数時間に及んだ私の話に疲れて話を変えたかっただけかもしれません。ともあれこれが報道カメラマンとしての第一歩でした。
禁欲の初任地 高知県
2006年、NHKに入局した私は最初に高知放送局に配属されました。
「よーし、洞窟の取材をやるぞー」
と思っていた私は出鼻をくじかれました。
洞窟の取材うんぬんの前にカメラマンとしてのスキルが、それ以上に取材者としての能力が全くダメだったのです。当然です。洞窟探検しかやってこなかった自分が、いきなり取材に出て通用するわけがありません。
そもそも文系だった私はカメラなんてデジカメくらいしか触ったことがありません。失敗や反省ばかり、上司や先輩を悩ます日々が続きます。
私は心に決めました。
「高知にいる間は洞窟の取材はやらない」
自分の好きなことよりも今は取材や撮影のノウハウを身につけなければ、この先、何もできない人間になってしまう。高知放送局にいた3年間は山岳取材班にも所属せず、ひたすら取材や撮影のノウハウを磨き続けました。
少し話がそれますが、NHKの報道カメラマン(映像取材)は撮影するだけが仕事ではなく、自分で調べて、提案して、リポートや番組を制作する力が求められます。
企画から提案、撮影、原稿、時には編集やナレーションまですることもあります。自ら取材して撮影する、取材力と撮影スキルの両方を鍛える必要がありました。
沖縄での大発見 世界最大規模の遺跡が
そして、3年間の洞窟禁欲生活を終えて次に配属されたのは、なんと沖縄放送局でした。
沖縄といえば…そう、洞窟です!
皆さんご存知の通り、沖縄といえば日本一洞窟が多い県ですよね!沖縄は、島の大部分が石灰岩に覆われた日本一の鍾乳洞大国なのです!
私にとっては天国のようなところでした。
だから沖縄では思う存分洞窟を、と思っていたのですが現実はそう甘くはなく、当時、沖縄は普天間基地の移設や尖閣諸島の問題で、息つく暇もないほどの忙しさでした。
それでも研究者とともにとある島の洞窟で絶滅した哺乳類の化石を見つけたり、洞窟の中に残る沖縄戦の痕跡を取材したりと、なんとか時間を見つけて洞窟取材に取り組みました。
中でもいちばん心に残っている取材は、石垣島にある洞窟の取材です。この洞窟から、骨から直接年代測定できたものとしては日本最古となる、約2万年前(旧石器時代)の人骨が発見されたという情報をいち早く手に入れ、ニュースで報じました。最も古い日本人の骨、つまり私たちのご先祖様かもしれない人の骨が発見されたことをスクープしたのです。翌年にはさらに古い、約2万4000年前の人骨が発見されました。
当時、石垣島では新空港の建設が進められていて、その地下で多くの洞窟が発見されていました。
偶然にも私はNHKに入局する前に、その洞窟群の調査をしていたのです。そのため、地下で多くの化石が発見されていたこと、その化石がある貴重な洞窟が空港の建設により無くなってしまうかもしれないことを知っていました。
東京の科学文化部の記者とも連携し全国に向けてニュースを放送すると、日本中でこの洞窟を保護する機運が高まりました。
その後、専門家たちによる大規模な発掘調査が行われ、さらに多くの人骨が見つかりました。これまでに見つかった人骨は1100点以上、最も古いものは約2万7千年前のもので、旧石器時代の人骨が見つかった遺跡としては、日本のみならず世界的に見ても最大規模の遺跡であることがわかったのです。
この貴重な遺跡は国の史跡にも指定されて、発掘が終わった現在は滑走路の横で眠っています。
現在、この貴重な遺跡を今後どのように保存し活用していくのか、有識者による検討が進められています。いつの日か、今よりもっと発掘や分析の技術が進歩したとき、再びこの遺跡が開かれて新たな大発見があることを期待したいと思います。
富士山の洞窟も取材 そして盟友との出会い
そして、この沖縄放送局時代にもう一つ大きな洞窟取材を行います。
2013年に富士山が世界遺産に登録され、富士山のNHKスペシャルを制作することになりました。富士山?あれ、山じゃないか。
違います。私に取材の声がかかるといえば、そう、洞窟です。
取材現場は樹海の洞窟。冷えて固まった溶岩でできた洞窟で、氷穴ともよばれ、内部は氷で覆われています。このNHKスペシャルは富士山の「水」を巡る謎を解いていく内容で、この氷が重要な取材対象でした。
ただ洞窟といっても私の専門は主に石灰岩でできた洞窟、いわゆる「鍾乳洞」です。氷穴を取材するのは初めてでした。15mほどの竪穴をロープで下りなければならないところもあり、0度前後の気温で足元も悪い中、デリケートな撮影機材をかばいながらの撮影は困難を極めました。しかし光を当てると輝く氷の世界は言葉で表せないほど美しく、その苦労を忘れるほどでした。
この取材で同い年の坂本敬ディレクターと出会います。当時は甲府放送局に所属。大きなザックにヘルメットやロープをくくり付けて鼻息荒くやってきたガタイのいい私と、中肉中背で「俺、洞窟初めてっす。閉所恐怖症なので怖いっす」とか言っている茶髪のひ弱?そうな感じの坂本ディレクター。初対面でしたが、見事に正反対だなという印象でした。
その後、タッグを組んで様々な洞窟番組を作ることになろうとは、お互いこの時は全く予想していませんでした。
洞窟のような長い話はまだまだ、次回、中編へ続きます。
中編はこちら。
後編はこちらです。
門田真司 ジャカルタ支局カメラマン
2006年入局。高知・沖縄・福島・いわき・東京を経て、ジャカルタ支局所属。これまで多くの洞窟、山岳、海外取材を行う。沖縄では離島や自然を、福島では原発事故の避難区域を中心に取材。日本洞窟学会に所属し、数々の洞窟を調査してきたが、実は暗くて狭いところはあまり好きではない。現在はインドネシアのジャングルに眠る古い洞窟壁画を取材中。
NHKには探検家がまだまだいます・・・
学生時代にエベレスト登頂した、山村武史 カメラマン
子どものころから蝶を追い続け世界的発見につなげた斎藤基樹 記者