「バズる(?)アウトリーチのすすめ」イベント参加報告
2019年7/22に東大本郷で開催された「バズる(?)アウトリーチのすすめ」というイベントに参加して来ました。
人文学系研究の危機が議論されるようになって久しいですが、日頃サイエンスコミュニケーションや、専門研究とメディアの関係、社会にとっての高等教育のありかた、などを考えている人間としては、人文学系研究者の方々がアウトリーチに関してどの様に考えながら取り組まれているのかは、非常に関心のあるところでした。
主催は、歴史学の研究者のネットワーク「ヒストリアンワークショップ」 @HistWorkshop というところで、2016年から活動。「リサーチショーケース」などの一般向け研究発表イベント等を開催されているとのこと。最近は関西でも活動を行っているということで、今回司会は京都大学の大学院生の方がやられていました。
今回の趣旨
・学術(特に人文学系)のアウトリーチについて、何をすればよいのかわからない院生やポスドク研究者の不安に答える
・具体的に何をすればよいのかという方法論に加えて、なんのためのアウトリーチかなど議論
【登壇者】
■北村紗衣(武蔵大学):シェイクスピア・舞台芸術史 @saebou
・TwitterからWikipedia、フェミニズム批評まで広く活躍
・著書『共感覚から見えるもの ―アートと科学を彩る五感の世界―』勉誠出版、2016年5月
・近著『お砂糖とスパイスと爆発的ななにか』(書肆侃侃房)
■古川萌(東洋大学):イタリア・ルネサンス美術史 @cari_meli
・「壺屋めり」名義で展示会のフォローアップ講演会を開催
・イラスト入り書籍『ルネサンスの世渡り術』(芸術新聞社)も上梓
■丸尾宗一郎(講談社):「現代ビジネス」編集 @miduwo
・人文社会科学者たちのオピニオンを広く世に発信する講談社の必殺仕掛け人
・お仕事の一覧はブログ「natsumekinakoの日記」を参照
【SNS注意事項】
・登壇者には発表内容がSNS等に発信されることは了承済
・質疑応答パートでは発言者がわからないような内容であればOK
【北村先生発表】「ワイルドならどうする?」
■自己紹介
・北海道士別市出身
・東大「駒場の表層文化論」出身 なんでも興味をもったらやれという所
・KCL(キングス・カレッジ・ロンドン)で PhD取得。古い本の譲渡や書き込みの歴史。800冊を調査した。
・タイムエージェントか探偵のようなお仕事。さながら「秘密情報部Torchwood」。
・専門はシェイクスピア、舞台芸術史、フェミニスト批判。
■ワイルドならどうする?
・19世紀の劇作家 オスカー・ワイルド
・「ルビッチならどうする?」(How Would Lubitsch Do it?)という言葉がある
・エルンスト・ルビッチはハリウッドの映画監督でシェイクスピアをモチーフにした「生きるべきか死ぬべきか」や、「桃色の店」(ピンクのみせ)など、玄人にファンが多い作品を多く作った。
・ルビッチは映画監督のビリー・ワイルダー(ヘップバーンやマリリン・モンローの映画を撮った)の師匠で、ワイルダーは困った時に自分の師匠ならどうすると考えた。
・オスカー・ワイルドは、「批評とはそれ自体が独立した芸術である」とした。その意味でワイルドは私の師匠。
・ワイルド曰く、
「世の中には噂になるより悪いことがひとつだけある。噂にならないことだ」
(There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.)
(「ドリアン・グレイの肖像」より)
・つまり、今の言葉で言えば「悪評でもよいからバズらせろ!」
・ちなみに、ワイルドの発言はいついったのかわからない発言が結構残っている。おそらくパーティや社交場等での発言と思われるが、それは今で言うツイッターだろう。チャーチルもそのタイプ。従って、それら二人の発言のソースをたどると見つからないことがよくある。
・ワイルドならどうする → Get Wild!
・ワイルドが現在生きていれば絶対にツイッターをやっていて、嫌いな舞台をけなして大炎上しているはず
■私のアウトリーチ活動
・英日翻訳ウィキペディアン要請プロジェクト
・はてなブログで観た舞台と映画のレビューを必ずかく(北村先生は年間200本観劇する)
・Wezzy の連載 「お砂糖とスパイスと爆発的な何か」→書籍化
■英日翻訳ウィキペディアン養成セミナー
・現在224件の記事がある。面白い記事としては、
オナイダ・コミュニティ
塩レモン
放屁師
もみあげ
スローテレビ
など
・ウィキペディア財団で日本で唯一選ばれた
https://15.wikipedia.org/people/kitamura-sae.html
■はてなブログ https://saebou.hatenablog.com/
・リチャード2世の授業で馬が出る演出かどうかについて議論するなど
・エフェメラ(芝居のチラシ)や本への書き込みなど、社会のなかで水に流れるよう情報を残す
■Wezzy の連載 https://wezz-y.com/archives/category/column/ssaen
・「お砂糖とスパイスと爆発的ななにか」書籍化
・表紙はツイッターで知り合った緋田すだちさん
■だいじなこと
・絶対に原稿を落とさない
・継続が信頼とバズを生む とにかく書いて発信する
【古川先生/壺屋めり】「美術展覧会に合わせたアウトリーチ」
■自己紹介
・イタリア・ルネサンス美術史の研究者
・16世紀イタリアの美術史で2017年 京都大学人間・環境学研究科で博士号
・ツイッターが主なアウトリーチの場だが8割は日常のことをつぶやいている
・ツイッターは学部生から始めたので研究に直結するとは考えていなかった
・趣味でイラストや漫画も描くのでイラスト付き鑑賞ガイドを製作
・論文を読んでネタを見つけて漫画を書く
・楽しいからやっている
■UFFIZIバーチャルミュージアムでの体験
・京大博物館で2013年に開催
http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/modules/special/content0033.html
・日立の技術で超高精細画像
・学生時代、ガイドブック「巨匠がかたるルネサンス」を作成
・画家が作品描いた趣旨を漫画で語るという形式
・後にパワーアップバージョンも作成
■鑑賞ツアーの企画
・ヴェネツィアルネサンスの巨匠たち 国立新美術館 2016年
https://www.fashion-press.net/news/22787
・国立新美術館内のカフェで解説したところ、人数も少なくて成功した
・ティツィアーム ヴェネツィア派展 東京都美術館 2017年
https://www.tobikan.jp/exhibition/h28_titian.html
・ダビンチ、ミケランジェロ、ラファエロはルネサンス三巨人として知られているが、その頃ティツィアームも強い人気があったがあまり知られていない。
・最初は展覧会の近くのレストランでランチをしながら解説したが、ランチでは時間とれないし、残りの解説を会場で行なおうとしたら騒がしいと注意された。
問題点
・公共の場で身動きが取りにくい
・落ち着いて話すことができない
・混雑していると統制がとれない
・自分で募集しているので参加者が内輪に
そこで、
・新聞形式にした記事をネットプリンの形で公開し自分でコンビニで印刷してもらう
・それぞれ100部程度プリントアウトされた
・歴史家ワークショップとの共同開催にした
■「3倍楽しむ」イベント
ミケランジェロと理想の身体 国立西洋美術館 2018年
https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2018michelangelo.html
・展示と私ともう1人の解説とで「3倍」楽しむというイベントを企画
・90人の定員。複数の講師と団体がバックにつくことで集客が拡大
ルーベンス展 バロックの誕生 国立西洋美術館 2018年
https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2018rubens.html
・同じく3倍楽しむイベント
・解説者は小松浩之氏、京大の先輩
・図像学のことは会場で説明されているから、背景としてある当時の人々の考え方や、当時絵画が外交としてどう利用されていたか、など
■情報発信とリスク管理
・「炎上」を未然に防ぐ
・ツイッターは歴史の込み入った説明をすることに向いていないので、ブログのリンクを貼る
・リプライのハードルを上げる
・自分以外の人に下読みをお願いする
・無意識に書いている誰かを傷つけるような表現をチェックしてもらう
・重箱の済をつつける人を確保
・ちょっと寝かせる
【丸尾宗一郎】「鈍重で持続可能な自己啓発」
■自己紹介と今日のお話
・東大教養学部 社会学
・2012年 講談社入社、現代新書志望だったが、FRIDAY、週刊現代などに配属され芸能スキャンダルなども追う
・2018年6月より現代ビジネスへ
・アウトリーチのコツや社会が学問に求めるものなどを追求
・バズった学術系記事の特徴・共通点
・編集者が考えていること
■タノ先生、ヤフーを震撼させる
・甲南大学・田野大輔
私が大学で「ナチスを体験する」授業を続ける理由
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56393
新聞でも話題に
ヒット理由
(1)ナチスの体験授業という突飛さ
(2)全体主義は容易であるというメッセージ
(3)自分もなりうるという我が事感
つまり、(1)新事実、(2)新解釈、(3)実存に根ざした共感
■鈍重で持続可能な自己啓発
・自分と関わること
・世界の見え方が変わること
■北村先生、はてなを震撼させる
ウィキペディアが、実は「男の世界」だって知っていましたか
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/57657?media=gs
・打ち合わせでたまたまウィキペディアの話が出る→「え、面白いですか?」
(1)新事実がある
(2)些細なところに男女の不均衡
(3)たしかにほかにもあるかも
・18世紀の百科事典における男女の不均衡
・21世紀を生きる私との間に抜き難い関係がある
・身近な話題から18世紀へ
・研究することの意味を示せる
■どうすれば実存に根ざした共感を得られるか
・テーマを身近なものにする
・ニュースをうまく用いる
・著者の経験を用いる
これを残念なものにしないのが難しい
■女子のサラダとりわけ問題
東北学院大 小宮友根先生
私がゼミ飲み会で「女子のサラダ取り分け」を禁止することがある理由
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58852
■税金泥棒問題
帝京大学 石川敬史先生
納税額の低い人を「税金泥棒」とみなす社会は、どう克服されてきたか
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65447
・人権の思想史
・爆発的に読まれた
・ロック、カント、ドストエフスキー
・なぜ人々が人権を発明したか
・時勢もあり迫力を持って感じられる
■裏技としての「授業体験記」
・学生と対峙していてどう感じるか
・早稲田大学 森山至貴先生
女子学生が抱いた“ある嫌悪感”から考える「女子のフェミ嫌い」問題
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59206
・駒沢大学 山崎望先生
極右・ルペンに「共感する」と言う学生に、政治学はどう向き合えるか
https://t.co/RviYfEHC4x?amp=1
・成城大学 野口雅弘先生
「コミュ力重視」の若者世代はこうして「野党ぎらい」になっていく
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56509
■公共性について
・「この道しかない」を揺さぶることが「公共性」「公益性」
・稲葉振一郎「公共性論」
・読者は、環境を所与として受け取るのではなく、変えられるものとして考える
■生活現実と専門とすり合わせ
・「家庭の天使」「内なるマギー」北村先生
絶対読んだ方がいい
・将基面貴巳「人文学としての日本研究をめぐる断想」
https://t.co/W7yxFrb5IR?amp=1
・学問の「私事化(面白ければいいじゃん)」ではダメ
・生活現実を一つのまとまりととして発信していく
・編集者はめちゃくちゃツイッターを見てる
・ニュースに対する見方など
・論文、専門書の紹介は有り難い
・その本を紹介するだけで記事が出来る
・本も売れるのでwin-win-win
・外大 小野寺拓也 感情史
女性が「怒る」ことになぜ社会は不寛容なのか
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65868
■一番大事なのは覚悟かもしれない
・発表すると必ず批判を受ける
・みんなが気分がいい発表はない
・どんな分野にも「警察」はいる(警察は大事)
・ただ、理念型を出す人がいないと議論もできないのでは・・・
・最後に必要なのは覚悟ではないか
【休憩】
司会よりアウトリーチの意義について質問
北村
・良い市民、良い消費者、良い観客を育てたい
・芝居や映画は、後の世代に見てもらわないと成り立たない
・人文学潰しではシェイクスピアがしばしば標的にされるが、AKBやジャニーズがシェイクスピアを扱っていることを皆知らない。
つまりシェイクスピアは普通に流行っている。
・文化遺産として価値があることを示したい
・私は喧嘩することが平気、それが苦手な人はおすすめしない
古川
・社会に貢献するというより、面白いことを共有したい
・昔起こっていて現代にも通じることは結構ある。あからさまに同じだということはあるが、似たようなことが昔もあった。そこから現代に通じることに注目。
・ジョルジョ・ヴァザーリという世界で最初の美術史家の研究をしていた。彼はむちゃくちゃプロパガンダを展開し、歴史を捏造した。
・どうしてもエンタメに分類されがちだが、そうではないというという所を共有したい
丸尾
・分野に対する愛を批判される覚悟があるかどうか
会場から質問
ぱうぜ
Qブログは書いているのに原稿は書いてないと批判されることがあるが
北村
・私は「過書字」、書いてないと不安になる
・たくさん書くのが苦じゃない人は向いている
古川
・私は原稿を落とす人
・ツイッターばかりいじっていると怒られると思うときはある
・ツイッターの更新が少ない時は締め切り落としている時
なかのひろき 東大出版会
Qツイッターで仕事依頼したいと思える人の特徴
丸尾
・文章が書けるかどうか。一般向けは文法が違う
・バランス感覚。極端なことを言わない。
・面白いかどうか
奥田げんき
Qツイートで話が通じない相手をなぜブロックしないのか
北村
・最初から通じると思っていない
・学生に、言い返していいと示したいから、
反撃することに意味がある
古川
・喧嘩は苦手
・そういうリプがつかないような発信をしている
大場
Q研究とは関係ないところでバズって一人歩きしてしまい、業界から誤解を受けることがあり得ると思うがどうか
北村
・駒場の表象文化論出身だから、そんなことは気にしない文化で育った
古川
・京大時代のボスも表象文化論学会会長
・3つの専門をもてと教えられてきた
丸尾
・テニュアがない人に対してはそこは気をつけている
・アウトリーチが悪いことではないという環境を作りたい
Q理系のアウトリーチに興味がある。本来アカデミアはバズりを鎮火させることにあるのではないか。どこに価値があるか。
北村
・バズったことについて学会をやるべき
・お湯の方が水より速く凍る ムペンバ効果
・学会でもすぐに取りあげる、それが学者として大事
・学会にそういう人がいないとダメ
・TOKIOは人類史的にとても興味深い事をやっているが、そもそも学会の人間がTOKIOを知らなかった
Q意図と異なるターゲットにファンがつくリスクがある。セルフブランディングとして成功しているのか?
北村
・ターゲットを設定すること自体に違和感。内輪になりやすい。それより訳の分からない人がいて良いのでは。
・今の世の中は内輪化に問題があるので、もっとマスに届いて欲しい
・ファンがほしくてやっているわけではない
・強いていえば高校生か大学生
・女性は顔が出ると卑猥なメッセージが来ることがあるが、セキュリティ案件にするしかない
Q SNS初心者向けにアドバイス
北村
・みんながやる必要はない
・全ての研究者に出来ることは、論文の図表をウィキペディアコモンズにして再利用可能にして欲しい
【個人的感想】
・「学問としての人文学の価値とはなにか」を考える上で、社会との接点の一つであるアウトリーチという視点で捉える、というスタンスで聴いていた。
・確かに世の中でバズった話題を歴史に照らした深い考察で解説する事は、興味深いし深さもあって面白い。
・ただ、その為に人文学が存在しているとしてしまうと、現代に生きない研究は価値がないことになってしまう。
・北村先生のスタンスは、批評=芸術=研究という立場でもあるので、現代の作品や現代で観ることができる作品の批評をすれば、すなわち価値に繋がっているのかも知れない
・一方、古川先生は芸術鑑賞に歴史という視点から捉えるという学術的な価値を発揮している一方で、イラストやツアーと言った方法論でマスにアプローチしようとするスタンス。
・人文学は研究者本人や学会の人たちが面白いと思うことが価値であるところにベースを置きつつ、アウトリーチとはその中で大衆受けする部分を届けるということかも知れない。
・多くの人文学系学術研究が税金を原資とした科研費で行われていることを考えると、一定の納税者の理解が必要である事は確か。そのためにもアウトリーチ活動は一般論としては重要。
・結局は納税者、つまり一般国民が、文化をどの様に考え、どの様に楽しみたいのか、その際にどの様な専門家を必要としているのか、その要求に応えるために普段どの様な研鑽を積む必要があり、その為の資金に対する理解をどのように得るのか、という問題に行き着く。
・アウトリーチこそが価値の源泉としてしまうと、アカデミズムの果たすべき役割を見失う危険がある。
・人文学を「役に立つ」という視点で定量化すると、エンターテイメントとしての芸術の経済価値として評価されかねない危険がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
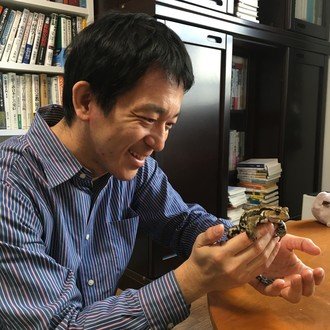

コメント