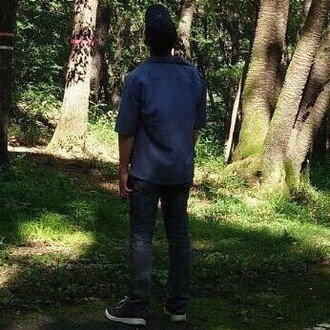絵を描きたくても描けない大人へ。その5『天才にはなれません!!』
才能とは一体なんでしょうか?
身長や体重や血圧のように、才能は数字では測れません。
この“才能の捉え方”と、ある“思考のクセ”が僕らに絵を描かせるのを止めたり、諦めさせたりします。
この2点を納得し、腑に落とすことができれば、絵を描くことを恐れず、楽しく絵を描き続けることができます。
5.天才にはなれません!!
僕らは時として才能を大げさに捉えすぎていることがあります。
「自分って才能ないのかも…」
こう思ったこと、みなさんありませんか?
ありますよね?
1度や2度じゃないですよね?
どうしてこのように思ってしまうのでしょうか?
これも、その4『年齢は関係ない!?』でお話ししたように、生存本能の働きでしょうか?
(気になったかたはその4を覗いてみてください⬇️)
これは、生存本能の働きによるものではありません。
才能の捉え方と思考のクセが大きく影響を与えています。
まずは才能の捉え方から考えていきましょう。
①才能の捉え方
世の中には天才と呼ばれる人たちがいます。でも、僕らは天才にはなれません。天才はすでに天才です。なろうとしてなれるものではないのです。そして、天才かどうかを決めるのは自分ではなく、他人です。もっと言えば、メディアや社会や時代や世間です。死後、ようやく認められるひともいます。ですから、天才を目指す必要など最初からありません。
「いや、そんなのそもそも目指してないし…」
という反論が聞こえてきそうですね。
しかしながら、僕らは思うようにうまく絵が描けなかったり、期待していた評価が得られなかったりすると、凹んでしまいがちです。最悪の場合、筆を断つひともいます。
よく考えてください。僕らは天才ではありません。うまく描けなくて当たり前、高い評価が得られなくて当たり前なんです。
ちょっと切ない話になってしまいましたが、絵を描き始めて間もないひとの絵が、多くのひとから高い評価を得られたとしたら、それはもう天才です。
僕らは天才を目指しているわけではないのですから、高い評価など気にしなくて良いのです。
僕らはただ、好きで絵を描くだけです。楽しいから絵を描くのです。
才能を大げさに捉えないでください。評価はあとからついてくるものです。
才能というのは、頭で考えているだけでは、何もわかりません。実際やってみて初めてわかるのです。
ですから、興味のあることは、片っ端からやってみることをオススメします。やってみて「楽しい!」となれば続ければ良いし、「つまらない…」となれば辞めれば良いのです。失うものは何もありません。
やらないで悶々とした時間を過ごすほうが勿体ないですよね。
実際にやってみて自分で納得した上で「もう辞める、自分には向かない」となれば、未練はまず残りません。興味の矛先は次へ向かいます。次の興味のあることに、トライしてみれば良いのです。
何かを始めるときには、才能のあるなしなんて考えるだけムダなんです。それよりも、“興味があるかどうか”、“好きかどうか”、を優先してください。
そして、実際にやってみてからは、上手い下手、上達速度は判断しないことをオススメします。
“楽しいかどうか”、“またやりたいかどうか”、“続けたいかどうか”を優先してください。
この絵を見て、どう思いますか?
(正直恥ずかしいです(^^;)
約3年前の僕がデジタルで描いた愛猫の絵です。
次に最近アナログで描いた同一猫の絵を載せます。
どうでしょう?(背景は気にしないでください)
とても同じ猫とは思えません!
でも、約3年前のあの絵を描いたとき、僕は楽しくてしょうがなかったんです(^^)
あのとき、「なんて自分は下手くそなんだ! やっぱり辞めた!」となっていたら、3年後、この絵を描くことはなかったわけです。
才能なんて考える必要はありません。
興味があるからやってみる。楽しかったら自然と続けられます。楽しくなかったら、また別のことをやれば良いのです。
僕らは天才にはなれないのですから、気楽にいきましょう(^^)
②思考のクセ
才能の捉え方の他に、もう1つ厄介なのが、思考のクセです。
それは、“比較”です。自分と他の誰かを比較することです。
これは相当根深いです。比較なんて良くない、と思っていたとしても、無意識で比較しちゃってる場合がほとんどです。
そう、“比較”は“無意識”で行われます。
なぜか?
学校教育の影響が大きいと言われます。
学校教育は比較を前提に成り立っています。比較することで、優劣を決定しています。そして、それが当たり前です。当たり前ですから、学校生活だけでなく、日常生活にも影響します。
「どこどこのだれそれはどうこうなのに、それに比べてあんたは…」
このような物言いは少なからず聞いたことありますよね。
ただ、“比較”自体が悪いわけではありません。問題はそのあとです。
僕らは“比較”し、そのあと“ジャッジ”する思考のクセがついています。
ジャッジとは《良し悪しを判断する》という意味です。
例えば、SNSの投稿を見ていて、素晴らしい絵を発見したとき、「このひとの絵はなんてすごいんだ! それに比べて僕の絵はぜんぜんダメだ(>_<)」となってしまいます。
あるいは、《いいね》の数のほうがわかりやすいかもしれませんね。「あのひとの絵はこんなに《いいね》がついているのに、それに比べて僕の絵は《いいね》が少ない…」
そうなると、冒頭の「自分って才能ないのかも…」に繋がっていきます。
“比較➡️ジャッジ”は僕らの脳に刷り込まれ、肌に染み付いています。
ちょっとやそっと意識したくらいでは、このクセはなかなか抜けません。ですので、このクセが直せなかったとしても落ち込む必要はありません。まずは、『“比較➡️ジャッジ”は思考のクセ』なんだということを知識として持っていてください。
知識として持っていれば、誰かと比較して落ち込んだとき、気付くことができます。気付くことができれば、立ち直りを早められます。
正直、このクセは僕自身まだまだ抜けてません。
落ち込んでは立ち直って、落ち込んでは立ち直ってを繰り返しています(^^;
このままではいけないと最近始めたのが、“学ぶつもりで絵を観る”ということです。
最初から学ぶつもりで絵を観ていると、比較ではなく、分析や探求になります。
「この星空はどうやって描いているのだろう」
「この絵はどんな画材を使っているのだろう」
「どうすればこんなに自然に夕焼け空の鮮やかな雲が表現できるのだろう」
こうなると、「ちょっと自分でも描いてみよう」となります。あくまで練習です。盗作は絶対ダメです。
こうやって練習することによって、今まで描けなかったものが描けるようになったり、新しい表現技法を身に付けたり、と絵の上達に繋がります。
“比較➡️ジャッジ”のクセを辞めようとしなくても、最初から学ぶ姿勢でいれば、比較が発動する前に、分析・探求が起こり、結果的に絵の上達へと繋がっていきます。
“学ぶ姿勢”、これオススメです。
まとめ
今お読みいただいているこのシリーズ記事は、絵を描く最初の一歩を踏み出していただくことを目的としています。そして、その一歩が二歩、三歩、四歩、五歩と繋がっていくことを願って書いています。
少しずつ絵を描く心の準備ができてきたでしょうか? そうであればとても嬉しく思います(^^)
次回はシリーズ最後の『6.誰にもバレずに絵を描く方法!?』を書いていきます。
それではまた、次の記事でお会いしましょう(^^)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?