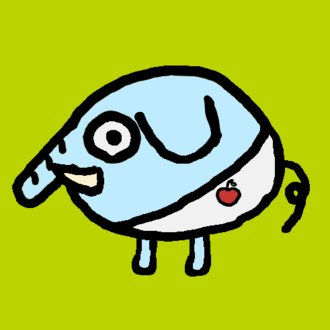1日が短すぎる人へ
気づいたらもうすぐ師走。今年も1年が一瞬で過ぎ去っていった。
大人になるにつれて1日や1年がだんだんと短く感じるようなるのは、
多くの人が理解できる現象ではないでしょうか。
この現象は「ジャネーの法則」として、提唱されています。
テレビやYouTube動画などでも紹介されていて知っている人も多くいるかもしれません。
この法則について周辺情報を調べてみると、「脳の老化(不活性化)」や「脳への刺激不足」などが理由として挙げられている記事が散見されます。
ふむふむ、確かにそれもありそう。
ただ、今回はそういった理由に対して異議(別説)を申し立てたいと思います。
身近な反例をいくつか挙げてみます。
学生時代当たり前のように通っていた1時間の通勤ルートを数年ぶりに体験するととても長く(あるいは目的地が遠くに)感じませんか?
初めて行く場所は帰り道よりも行き道のほうが長く感じませんか?
このようなありふれた日常は年齢に依存しないと私は思います。
私の直近の話をすると、先日西表島に行ってカヌー&トレッキングツアーに参加しました。
朝早くに出発し、カヌーでは波に揺られ、ぬかるんだ山道を進み、大きな滝に圧倒され、帰り道では岩場に腰掛けコーヒーとサーターアンダギーを堪能し、とても充実した時間を過ごすことができました。
そして、ツアー終了後に驚きました。まだ13時なの?!?!
そう、つまるところ、
時間の感じ方は「予測と実態の差」に依存していると思うのです。
人間を含め生物はどこまで行っても相対的な存在です。変化量に対して敏感です。
血糖値は急上昇(血糖値スパイク)が身体にとって良くありません。
匂い、味、恋愛感情など、時間が経つと段々わかりにくくなります。
時間も同じじゃないでしょうか。
自分の予測と実態の差が変化量となり、主観的に捉えられる。
つまり、「時間単位の情報密度」を日常(=予想できる範疇)に対して変化をつけることで長い時間だと自分をだますことができると考えています。
上で敢えて「変化をつける」と書いたのには理由があります。
それは、上振れだけでなく下振れをした場合にも該当すると私は考えているからです。
転職をして新しい職場で働き始めたり、異動で新しい部署に配属されたり、業務の進め方がわからず己の無力さを痛感する。誰もが1度は同じような経験をしたことがありますよね。
あの日、1時間どころか10分経過するのがとても長く感じなかったでしょうか。
「え、まだ16時!?あと2時間もあるじゃん…。暇だな、眠いし早く帰りたい…」
この経験からも日常の情報密度に対して大きく下振れした日も、
予想から外れたとして時間を長く感じてしまうのだと推察されます。
普段仕事などで多忙を極めている人が休日になにもせず布団でずーっと寝ていたような場合もきっと同じなんでしょうか。
(私は行動派なのでそのような日がなく実感はありませんが…)
以上を踏まえ、1日が短く感じる現象を克服する方法を考えました。
それは、朝早くに起き、午前中に密度の濃い時間を過ごし、午後はなにもしないでのんびりという過ごし方です(休日限定)。
休日であっても寝すぎずに、朝は6時に起き、掃除洗濯自炊をしましょう。
趣味がある人はその後すぐに始めましょう。
周りの人や店が活動を開始し始めたら買い物やお出かけをして午前中には家に帰ってきましょう。
そうすると、高い充実感を得ているのに時間がまだまだたくさん余っているはずです。
この体験こそ、1日を長くするために必要な要素なのではないでしょうか。
そう、上記の西表島のツアーと本質は同じです。
流れる時間の早さに、自身の人生の薄っぺらさを憂いている方は悲観せず、
ぜひ自分の時間の感じ方のコントロールをしてみてください。
時には詰め込んだ活動をするのではなく、なにもせずぼーっとするのも大切ですよ。
本日は以上です。
お読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?