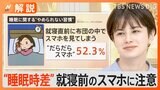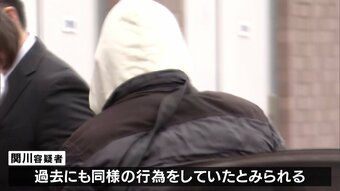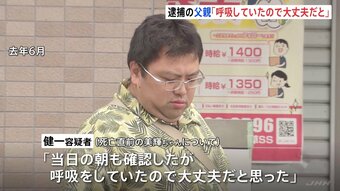物価の高止まりが続く日本経済は慢性デフレという30年にわたる病を克服したのだろうか?
デフレ循環から好循環への正念場。大企業は賃上げを価格転嫁も中小企業は?

日本のデフレについては、長年人々の心理が大きく影響しているというのが東京大学大学院経済学研究科の渡辺努教授の分析だった。物価が変わらないとみんなが信じている。だから賃上げも要求しない。賃上げを要求しないから、企業は価格転嫁せず、価格は据え置かれる。だから物価は変わらないという社会通念があまりにも強く、これが永久凍土で溶けないという状況が続いていたのがデフレだった。
――この1年半ぐらいで変化してきたのか。

東京大学大学院経済学研究科教授 渡辺努氏:
よりはっきりと変化が見えてきていると思います。

東京大学大学教授 渡辺努氏:
22年の春ぐらいから四つのことが起きたと。まず一つ目の「インフレ『予想』」は私の言葉ですが、物価が上がるのではないかとみんなが思い始めたということです。そうなると消費者はどうするかというと、それまでは値段が上がるとそこでは買わないで、ほかの店に行って買うとかで値上げから逃げるというのが典型的な日本人の行動だったのですが、逃げずにその店で高いものを買うという行動をとり始めた。
――結果的に値上げを受け入れる。
東京大学大学教授 渡辺努氏:
そうです。そういう意味でのインフレへの耐性みたいなものが高まってきたと。企業は当然その辺につけ込んでいくわけです。
――怖くて値上げができなかったものが転嫁できるようになった。
東京大学大学教授 渡辺努氏:
価格転嫁が進んでいくと、賃上げしないというのはさすがにありえないということになっていくので、それで春闘で頑張って賃上げということになっているわけです。

生活コストが上がっているから賃上げを要求し、企業はその要求を受け入れる。受け入れると人件費が上がるから価格に転嫁する。結果、物価が上がる。
――これがぐるぐる回っていけば、デフレ循環から好循環に移ったということだ。好循環に移ったと今言えるのか。
東京大学大学教授 渡辺努氏:
この1年半ぐらいかけてとりあえず物価を上げて、賃上げについても1回春闘で頑張って上げてみたということで、いろいろなことをやりながら1周ぐるっと回ってみたというのが今の状態だと思います。ただ、デフレ循環はもう20何年間、20何周やっているわけです。こんなことをやっているところは世界中ないわけですが、この歴史のもとでとりあえず好循環の最初の1周をやってみたというのが今の状態なので、好循環が安定したとは言い切れません。
――ある程度続けて好循環が回らないと、好循環に移ったとは言えない。
東京大学大学教授 渡辺努氏:
私は好循環サイクルがいいと思っているわけですが、デフレ循環の方が良かったという方がいるわけです。一つはシニアで、例えばリタイアしてある程度の資産を持ち、年金で生活しているという方だと、インフレが毎年起こるような状況は資産の面でも年金の面でも好ましくないわけです。中小企業の経営者に聞いても、やはりデフレ循環の方がよかったと。毎年賃金を上げ続けなければいけない。自分のところはそんな余裕はないと。価格に転嫁すると言っても、そんなに簡単にできないとおっしゃるわけです。

――8割以上の人は給料は変わらないか下がると思っているから、好循環はなかなか起きない。
東京大学大学教授 渡辺努氏:
まさに両方のサイクルが綱引きをしているような状態で、ちょっと気を許すとデフレ循環のサイクルに戻ってしまう確率もそれなりにあると私は思っています。
――労働者の賃上げ要求を企業が本当に受け入れるかどうか。これができるかどうかがまさに正念場だ。
東京大学大学教授 渡辺努氏:
大企業は価格を支配する力も強いので、賃上げを受け入れてその分を転嫁するということができていると思います。ただ中小企業はサイクルの中では非常に弱い部分で、賃上げ要求はするのかもしれませんが、企業のオーナーとしてはそれを価格に乗せることが難しいのではないかとか、足元の収益で吸収することも難しいのではないかとなっているので、なかなか要求を飲めないという状況が起きてしまっています。