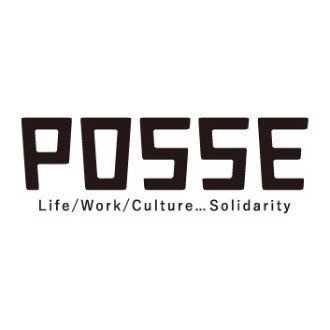【期間限定ためしよみ】アマゾンの「当日配送」を支える人々を追って──岩本菜々
いまや多くの人が利用するネット通販業界の頂点に君臨し、「当日配送」「送料無料」などのサービスを展開するAmazon。
佐川急便やヤマト運輸がAmazonの荷物の引き受けから撤退するなか、なぜここまでスピードを追い求めたサービスを実現できているのだろうか?
POSSEメンバーで、労働者の組織化にも取り組んでいる岩本菜々が、現場で働く配達員のインタビューをもとに、過酷な現場の実態を描き出す。
公開期限:2月12日(月)まで 好評発売中! 岩本菜々
『POSSE vol.55 特集:物流危機を救うのはAIと規制緩和か?』
※本記事は、『POSSE vol.55 特集:物流危機を救うのはAIと規制緩和か?』に掲載された記事です。本書では、ほかにも物流業界のさまざまな現状を描き出す記事を掲載しています。ぜひご覧ください。
POSSE学生ボランティア
1999年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程在籍。2020年、大学3年生の時にPOSSEに参加。以来、若者の労働・貧困問題に取り組んでいる。2023年3月からはアマゾンで働く労働者の組織化にも取り組んでおり、大阪のアマゾン倉庫で働く労働者の1週間にわたるストライキを支援した。
物流大手が「負担が大きすぎる」と逃げ出したアマゾンの宅配サービス
アマゾンは日本市場に2000年に進出後、ヤマト運輸や佐川急便などの物流大手を活用しながら通販サービスを拡大してきた。しかし、荷物の急増に伴う人手不足を理由に、佐川急便は13年にアマゾンから撤退。またヤマト運輸は「従業員の負担が増している」という理由で、17年にアマゾン「当日配送」サービスから撤退している。
そんな状況下にも関わらず、アマゾンは2023年以内に物流拠点をさらに11箇所増やし「当日配送・翌日配送」が可能な地域を大幅に拡大させている。大手が軒並み撤退し、社会全体でも物流問題が叫ばれる中でなお「当日配送」サービスを拡大し続けるアマゾン。その物流を支えているのは、地域の小さな宅配業者(デリバリー・プロバイダ)と、アマゾンから個人事業主として直接仕事を請け負うアマゾン・フレックスの人々だ。大手物流各社がアマゾンから手を引いた穴を埋めるかのように、アマゾンは2019年にアマゾンフレックスの正式運用を開始。アマゾンフレックスとデリバリープロバイダを中心とした、独自の配達網を組織してきた。配送追跡サービス「ウケトル」によると、17年4月にはわずか6%だった自社配達の割合は、20年には40%にまで急増している。(注1)
大手が軒並み「負担が重すぎる」とギブアップした当日配送。それをアマゾンフレックスやデリバリープロバイダで働く労働者なら「運ぶことができる」のは、一体なぜだろうか。筆者は、2020年から3年間、デリバリープロバイダとアマゾンフレックスを兼業しながらアマゾンの荷物の宅配を行ってきた配達員の緑川さん(仮名)にインタビューを行った。このインタビューをもとに、「当・翌日配送」を実現するドライバーたちが、どのような働き方をしているのかを見ていきたい。
アマゾンフレックス
アマゾンフレックスとは、配達員がアマゾンから個人事業主として直接業務を請け負い荷物を運搬する仕組みのことだ。アマゾンフレックスの仕事は、軽貨物運送事業を行う軽自動車であることを示す「黒ナンバー」を取得した車を持つドライバーであれば、アプリで登録手続きが完了次第、誰でもいつからでも始めることができる。アマゾンフレックスの求人ホームページを見ると、「自分のペースで、自由に働ける」というスローガンのもと、すぐにスタートできる気軽さと、働きたい時間帯を自分で選べる自由度がアピールされている。
仕事は、アプリ上に並んだオファーを取得することによって行う。アプリにはその時に取得可能なオファーが並んでおり、それぞれのオファーには、稼働時間と報酬、荷物を取りに行く配送拠点が明記されている。それぞれのドライバーは稼働したい日時の配達ブロック(稼働時間帯)を選択し、そのブロックの配達業務を完了することで報酬を得るという仕組みだ。1ブロックの長さは、およそ3時間〜8時間程度。報酬は季節や時間帯によって異なるが、2023年冬現在は、時給換算で1時間につき2,000円ほどが相場だという。
アマゾンフレックスに表示されるオファーの数は、期間によって大きく増減する。最も多くのオファーが出されるのは、ブラックフライデーやプライムセールなどのセール期間中だ。アマゾンはセール期間中、ここぞとばかりに報酬額を時給あたり3000円くらいまで引き上げたり、稼働率が高い人に対するインセンティブ(追加報酬)を提供することで、フレックスに登録しているドライバーに稼働を呼びかける。
セール中にはインセンティブや高い報酬で優遇される一方、閑散期に真っ先に仕事を失うのもまた、フレックスのドライバーだ。閑散期はオファーが少なく、1日中アプリに張り付いていてもほとんど仕事が取れない日もあるほどだという。そのため、アマゾンフレックス1本で生計を立てられる人はほとんどおらず、多くがウーバーイーツや出前館など他のプラットフォームワークと兼業をしているほか、デリバリープロバイダの請負としての仕事と兼業している人も一定数いるという。
ここからは、アマゾンは各地域にアマゾンフレックス登録者をプールしておくことで、セール時などの荷量の変化にも柔軟に対応できる体制を作り上げていることが見えてくる。
デリバリープロバイダ
一方で、通常時の荷物の配送を中心的に支えるのはデリバリープロバイダだ。デリバリープロバイダとは、アマゾンから配送を委託された、各地域の中規模の宅配業者のことだ。契約先は公開されていないが、10社前後が名を連ねているとされる。そのさらに下に、各社から配達業を請け負う二次下請けの中小宅配業社がエリアごとにいくつも連なっている。
ドライバーの多くは、この二次下請けである地域の宅配業者から個人事業主として仕事を請け負う、三次下請けとして仕事をこなしている。報酬は日給単位で支払われ、その相場はおよそ15,000〜20,000円ほど。拘束時間は多くの場合、週3〜5日、1日の労働時間は12〜13時間だ。アマゾンフレックスよりも報酬は低いが、事業所によってシフトが組まれるため収入が比較的固定的で安定しているという理由から、デリバリープロバイダを主要な収入源として選ぶ、あるいはアマゾンフレックスの兼業先に選ぶ人は多い。
「速さ」を追い求めた先に
「アマゾンの配達を請け負っている車は、ボコボコになっている場合が多いですね。とにかく急かされるので、事故を起こしやすいんです」。多い時で、7時間の配送で約200個の荷物を配り切ること。これが今、アマゾンの配達員が課される荷物の数だ。関東地方在住で、アマゾンフレックスの仕事と、デリバリープロバイダーの仕事を両方請け負い生計を立てている緑川さんは、この個数をなんとか間に合わせるため、休みなく車を走らせる。
忙しい時には、1つの荷物を配るために割ける時間はたったの2分。緑川さんが担当する地域は山がちで、車が入れない細い路地や階段も多い。足腰の負担を覚悟で、2リットル水が9本入ったダンボールや組み立て家具などの重い荷物を持って数百段の階段を駆け上ったり、未舗装の獣道を歩いたりしなければならないこともある。それに加え、時間指定がある荷物はその時間に訪問できるように調整し、1度訪問しても不在だった家には繰り返し訪問したり電話をかけたりして、なるべく持ち戻りが出ないようにしなければならない。
配達中は、公衆トイレやコンビニのトイレを探して車を停車する数分間さえ、ノルマ達成のためには命取りになる。そのためトイレに行きたくならないよう、夏場以外は仕事中にできるだけ水を飲まないようにしているという。「この仕事を始めて3年経ちますが、トイレに行けないためこれまでで2回も膀胱炎になり、それがさらに悪化して炎症を起こし、腎盂腎炎にもなりました」。緑川さんはそう話す。
AIに仕事量を決められる
配達員に荷量や配送ルートの指示を出すのは、アマゾン独自のAIを用いた配送アプリだ。配達員は仕事中、アルゴリズムにより一方的に荷量を決められ、アルゴリズムで計算されたルートと範囲に従って荷物を運ぶ。
AIによって配送範囲やルート、荷量が決定されるようになったのは、2021年のことだ。それまでは、それぞれの配達員が担当する配送範囲は現場の配達業社が決めていた。また荷物を運ぶルートは配達員それぞれの裁量次第であった。しかしAI導入以降、配達コース決定の裁量が現場から奪われ、1人1人の荷量とコースがアルゴリズムによって組まれた状態で荷物が拠点に運ばれてくるようになった。その結果、これまでよりも1人が受け持つコースの範囲が大幅に広がり、負担が増しているという。時には1度の配達で都道府県をまたぐ範囲や「市の南側全域」といった広範囲を任されることもある。時間指定の荷物がその広いエリアに散らばっているため、何度も長距離を行ったり来たりしなければならない。
それに加え、AIの導入以降、荷量の増加にも拍車がかかった。「2021年ごろは、1日あたり160個割り当てられたら『多いな』と感じていました」。当時ですら、12時間以上かかって何とか終わらせることができた数だ。でも、今ではその荷量をはるかに超える数を配っており、2022年には1日に配る数は多いときで200個を超えた。今や1日270個割り当てられることもある。アマゾンフレックスで運ぶ荷量も同じように、この数年で大幅に増えている。2020年には7〜8時間のコースで最大120個ほどが割り当てられていたが、今では多い時で180〜200個が割り当てられる。1時間におおよそ25個、多い時は30個こなさないと、時間内に配り切ることができない数だ。「法定速度を遵守していては、とても達成することはできません」と緑川さんは打ち明ける。
労働者の熟練と創意工夫の結果を吸い上げ、ノルマを引き上げる
数年前から激増した荷物を捌くため、配達員たちはトイレを我慢したり、移動を素早く行うなどの方法で対応しているほか、日々創意工夫を凝らし、必死の思いで自身の配達技術を磨いている。荷物の積み方や積むスピードも、新人とベテランでは全く異なる。配達中に崩れないように、かつ取り出しやすいように100個を超える大小様々な荷物を軽バンの荷台に置くためには、かなりのコツがいるという。荷物を配るルートも、AIに頼るばかりではなく、時には経験に頼って最も効率の良いルートを自分自身で組むこともある。緑川さんの場合、慣れているエリアであればAIの指定ルートにほとんど頼る事なく、自分の知識を元にさらに効率の良いルートを組んで配達している。
これまでなら、こうして効率化を図り工夫を凝らせば、配達現場にはその分だけ余裕が生まれていた。自分の熟練によって勝ち取ったその自由時間は、自分の裁量次第で休憩時間などに充てることができた。しかし今は皮肉なことに、配達員による創意工夫の成果は即座にアプリによって把握され、ルート決定の技術は吸い上げられ、ノルマをさらに増やすための道具として用いられてしまう。アプリ導入により、アマゾンはアプリに記録される情報から全国のドライバーの何万件もの運転状況、ルート、配達できた荷量を細部にわたり把握することができるようになったからだ。普段回るコースの荷量がアルゴリズムによって増やされることを、ドライバーの間では「コースが育つ」と言う。ドライバーは何とか時間内に配り切ろうと、アプリによって指定された荷量を必死にこなす。そのエリアのドライバーが、アプリの要求通り、あるいはそれ以上の数を捌けるようになると、荷量の上限を学習したAIが、さらに荷量を吊り上げ、どんどんコースが「育つ」…。人間の労働強度の限界へと突き進むAIに配達員たちが必死の思いで食らいついていくうちに、負担が増しているのだ。
上がらない報酬
これまで見たように、荷量が大幅に増えたことにより、現場はこれまでよりはるかに労働強度が高く、ルート決定や荷物の積み方にもより高い精度が要求されるようになってきている。それにもかかわらず、ベースの報酬はこの数年間ほとんど変わっていない。緑川さんの働く地域では、アマゾンフレックスの仕事で得られる報酬は、時給換算で約2,000円。ガソリン代などの経費は全て自分持ちなので、実際に手元に残る額はさらに少ない。インフレでガソリン代が1リットル170円を超えることもある昨今、経費が嵩んでいることでますます手取りが減っているという。
セールなどの繁忙期のオファーの値段が以前より高く設定されるようになったこと、ある一定期間の稼働率が高い人に対してインセンティブ(追加報酬)を支給するキャンペーンの回数が増えたことで、臨時収入は増えた。しかし、そうしたオファーの値上げやインセンティブ支給は不定期であるため、あてにはできない。直近のセールでは、報酬も大幅には上がらず、インセンティブ支給もなかったという。
デリバリープロバイダの下請け会社のもとで働く配達員は、さらに条件が悪い。緑川さんの場合、二次下請けから徴収される手数料10〜20%を差し引いた、17,000円ほどが支給されていた。そこからガソリン代などを引くと、15,000円しか手元に残らない。荷量によっては拘束時間が12時間を超えることもあるため「こうなるともう、コンビニバイトの方が時給が高いですよね」とため息をつく。
アマゾンフレックス──アカウント停止の恐怖で、労働者をアプリに従わせる
倍増するノルマ、上がらない賃金。その中でもアマゾンフレックスの配達員たちが自らルート組みや荷物の積み方に関して必死に改善を図ってまで荷量を全て捌こうとする最大の理由が、稼働率が高いアカウントや成績が良いアカウントに対する優遇措置と、誤配や持ち戻りが多いアカウントに対して行われる「制裁」だ。成績が良いアカウントには、他のアカウントよりも早くオファーが公開される「アーリーアクセス」が付与されたり、セール期間などの繁忙期に稼働率が高い人(1週間で40時間稼働した人、などの条件がある)には、先ほども見たようにインセンティブが付与されることがある。インセンティブの総額は、場合によってはセール期間3週間ほどで20万円を超える。つまり、常にアプリ上で好成績を叩き出し、セール時に集中的にオファーを取得するなどすれば、一定の報酬を得ることができるのだ。
一方で、成績が悪いドライバーへの制裁は手厳しい。「アマゾンフレックスの労働者が何よりも恐れるのが、いわゆる“垢BAN”です」。垢BANとは、アマゾンから一方的にアカウントを停止されることを指す。オファーを直前でキャンセルする行為を繰り返したり、未配や時間指定の不履行、誤配などを多く出してしまうと、ある日突然アカウントが停止され、その瞬間にアマゾンの仕事を失い、失業してしまう。その上アカウント停止の基準は公開されておらず、いつ自分がその対象になるかはわからない。優秀な成績を残し続けているドライバーであっても、安心はできない。ある東北地方で働いているアマゾンフレックスのドライバーは、数ヶ月ずっと持ち戻りの荷物をほとんど出していなかったにもかかわらず、1度持ち戻りの荷物を多めに出してしまった途端アカウント停止の警告が出たという。そのためドライバーはアカウントを停止されないように、アプリにどれほど無理な要求を突きつけられたとしても、従順に従うしかない。緑川さんはこれまで、年間を通じて好成績を維持し続けてきた。しかし、数年単位でアカウント停止をされず、配達員資格を維持し続けられている人は、緑川さんの周りではそれほど多くはないという。
デリバリープロバイダ──アプリと事業所による二重の指揮命令
アマゾンフレックスの配達員がアカウント停止の恐怖の中で荷量の達成に追われる一方で、デリバリープロバイダのもとで仕事を請け負う配達員たちは、アプリと事業所による二重の指揮命令のもとで過酷な労働に駆り立てられている。デリバリープロバイダの下請けの事業所で働く配達員たちは、フリーランスという業務形態であるにもかかわらず、事業所によってシフトが組まれ、出社時間も指示される。仕事中は、労働過程をアマゾンのアプリによって管理されている。
その上、事業所が抱える荷物の量によっては、アプリで指示される以上の業務を事業所から指示されることもある。アマゾンが配布しているアプリは、1日13時間以上、週60時間以上は働けない設定になっており、労働時間の上限を超えるとオファーが取得できなくなる。しかし東京ユニオンによると、事業所によってはダミーアカウントを使うように指示し、規定時間以上に働かせる所もあるという。(注2)各地で労働組合による異議申し立てがあったこともあり、ここ数年で状況は改善されつつある。しかし数年前までは未配があった場合「配り終わるまでは戻ってくるな」と指示して1日13〜14時間働かせ、週60時間の稼働時間を超えるとダミーアカウントを使わせて仕事に当たらせるという行為が蔓延していたため、際限のない長時間労働がまかり通っており、現場は疲弊しきっていたと緑川さんは指摘する。
個人事業主として「無権利状態」に置かれる配達員
また、長時間労働や多すぎる荷量のせいで事故を起こしたとしても、その事故の結果は基本的に、ドライバーの「自己責任」として処理される。
緑川さんはデリバリープロバイダから仕事を請け負っていた2021年の夏、1度追突事故を起こしてしまったことがある。その時の緑川さんは、ドライバーとして働き始めて1年と少し。まだ運転技術も十分でない中で1日で150個以上のノルマを持たされ、長い時で14時間休憩なく配り続ける日が続いていた。当時は家に帰っても、毎日荷物を配り続ける夢を見ていたという。
連日の長時間労働に疲れ切っていた緑川さんは車を走らせている途中、追突事故を起こしてしまった。フロントガラスにヒビが入り、車の前部がぐしゃぐしゃに潰れてしまうほどのひどい事故だった。自分自身も首に鞭打ちを負い、追突してしまった相手も、軽症で済んだものの怪我を負った。強いショックの中、慌てて委託会社に連絡をすると、開口一番言われた言葉は「そうですか。じゃあ別の車を持って行かせますね」だった。てっきり、代わりのスタッフが車に積んでいた荷物を回収しに来てくれるという意味だと思った。すると到着した委託会社のスタッフは運転してきた軽バンを指し、緑川さんに「新しい車を用意したので、今からこの車に乗って残りの荷物全部配ってきてください」と告げたのだった。
緑川さんは愕然としながらも、とてもこの後もう1度稼働できる状況ではない。病院に行かせてほしいと主張した。
「あの時はとにかく、言いくるめられないよう必死でした。ドライバーや巻き込まれた相手の状態よりも、コースに穴を開けないことの方が大事、という会社の態度には正直驚きました。そのあとドライバーが動揺してまた事故を起こすかもしれない、ということは考えもしないのですね」。
緑川さんは、事故を起こしてしまったショックと、相手に怪我をさせた心苦しさから、一度は運転をするのが怖くなり、ドライバーを辞めようかとも考えた。しかし結局は、車を自腹で廃車に出し、新しく中古の軽バンを購入して仕事に戻った。治療費や車の修理費は、アマゾンからも委託会社からも1円たりとも出なかったという。
また、配達先を自分たち自身で選べないにも関わらず、配達中のトラブルも「自己責任」で引き受けなければならない。緑川さんは以前、配達中に暴力を振るわれたことがある。配達先の隣の家の前に車を停めていたとき、その家から高齢の男性が出てきて「とっとと移動しろよ」と大声を上げ、突然緑川さんを後ろから殴ったのだった。突然の理不尽な仕打ちと、抵抗できない立場に立たされている悔しさで、車に戻った後に涙が滲んだ。知り合いのドライバーにも、配達中にTシャツが破けるほど乱暴に掴みかかられた人もいる。しかし、そうした事件があっても、配送センター全体で注意喚起がなされることもなければ、配達員自身が危険な行為に及ぶ客への配送を断ることも実質的には不可能だ。
アマゾンの配達を支えるもの
アマゾンが取り扱う配達物の数は近年増加を続け、21年には7億個を突破した。この莫大な荷物の配達を支えているのは、ヤマトや佐川などの大手運輸会社が「過酷すぎて割に合わない」という理由で手を引いた穴を埋めるように稼働する、アマゾンフレックスやデリバリープロバイダの下で働く配達員たちだった。
大手各社が達成できなかったほどの荷量を、アマゾンフレックスとデリバリープロバイダの配達員たちに運ばせることが可能になっている背景には、AIを使用したアプリの導入があることが、緑川さんの話からはうかがえる。アマゾンは配達員たちをアプリによる独自のアルゴリズムのもとで実質的な指揮命令下に置くことで、アプリが全面的に導入される前の数倍の労働強度を配達員に課すことに成功している。そして、こうしたアプリの厳しい命令に配達員を従わせるため、アマゾンフレックスにおいては「アカウント停止」の恐怖をチラつかせる。デリバリープロバイダにおいては、アプリと事業所による二重の指揮命令のもと、配達員に対し大手には実現できなかった荷量をコンスタントに押し付けることに成功していることが見えてくる。
その上、配達員たちは自分で配送先や荷物の数を選べず実質的な指揮命令下に置かれているにも関わらず、「個人事業主」であるという理由で労働法上の保護の枠外に追いやられ、仕事が原因で事故を起こしたりトラブルに巻き込まれたとしても、その危険を全て「自己責任」として引き受けなければならない状況に置かれている。(注3)
アプリの言いなりにならないために
このような、一方で配達員を実質的な指揮命令下に置き、他方の手で業務中に生じるあらゆる危険を「自己責任」で引き受けさせるアマゾンの働かせ方に、配達員たちが常に黙って従ってきたわけではない。アマゾンは依然として「直接の雇用関係にない」という主張のもとで、配達員たちの交渉を退け続けている。しかし、フリーランスであるという理由から労働組合法上の労働者にあたるかどうかが議論の的になっており、正式な団体交渉権が確立されていない中でも、配達員たちはさまざまな方法で異議申し立てを行い、AIによる一方的な荷量の押し付けや、報酬未払いなどの不当な行為に対して対抗している。23年の10月には、デリバリープロバイダの下請けとして働く、東京ユニオン・アマゾン配達員組合長崎支部に所属する33人の配達員が「集団ボイコット」(実質的なストライキ)を行い、繁忙期のボーナスである「インセンティブ」の不払いに抗議を行なった。緑川さんも、今年の7月ごろからインセンティブの不払いに対し、SNSで同じ被害に遭っている仲間に繋がって状況を聞き取り、SNSで告発を行なったり、アマゾンのサポートセンターに繰り返し問い合わせを続けたりするなど、粘り強く要求を続けている。
こうして声を上げることで「成果」も勝ち取られているようだ。緑川さんを含めた多くの配達員が不払いの実態についてSNSで発信を行なっていたある日、7月のプライムデーから2ヶ月以上続いた未払いに対し、アマゾンが初めて「この度遅延が発生しており、ご迷惑おかけして申し訳ありません。今週中に支払い手続きを進めます」という公式アナウンスメールを配達員に一斉に送った。そして翌週には、緑川さんの周囲の人が抱えていた未払いのうち、ほとんどが解消されたという。
アプリによって実質的な指揮命令下におきながらも「フリーランス」として契約することで労働法上の保護の枠外へと追いやるという現象は、ウーバーなどのプラットフォーム企業を中心に世界中で共通して見られる。そんな中でも、そこで働く配達員や運転手たちは、アプリをオフにするなどのストライキを通じて闘っている。例えば2019年には、ウーバーで働くドライバーたちに、毎週水曜日には24時間アプリをオフにして「ストライキ」をしようと呼びかける取り組みがアメリカを中心に始まり、その試みはイギリスやブラジル、オーストラリアなど世界中に広がった。(注4)いくら企業側が配達員は「フリーランス」であり、労働法が適用されないと主張したとしても、企業が実際に配達員たちの労働力に頼りきっている事実に変わりはない。そのため、労働法上の保護がされないストライキであっても、実際に配達員たちが仕事を止めれば企業にとっては大きな打撃となる。配達員たちは、アプリをオフにして「注文を受けない」ことによって、自分たちの労働力そのものを交渉力に変えているのだ。
日本では、まだまだそうした動きは数少ない。しかし、一方的に増やされ続ける荷量、上がらない賃金、度重なる未払いによって、配達員の不満は累積している。その上、アマゾン側の状況を考えてみても、佐川急便が完全撤退、ヤマト運輸も当日配送から撤退し、荷物のおよそ4割をアマゾンフレックスとデリバリープロバイダを中心とする自社物流網に依存しているとされるいま、アマゾンは彼らの要求を無視できない状況に追い込まれていると言えるだろう。
「私は、生活インフラを支えているという誇りを持ってこの仕事をしています。だからこそ、不払いなどの問題が起こった時に真摯な対応をされないと、尊厳を踏み躙られているように感じるのです」と緑川さんはいう。オファーを取得しない「ボイコット」、SNSを通じた社会発信(注5)、訴訟…実質的な労働法の適用を受けられない状況の中でも、様々な闘い方が目の前には開かれている。日本においても、配達員による「アプリの言いなり」になる今の働き方への異議申し立てが広がっていくことを期待したい。
注釈
1 日本経済新聞「「隠れ宅配」誰が運ぶ Amazonの荷物、半数が統計外」2021年12月22日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC06B4H0W1A201C2000000/
2 東京ユニオン「アマハイニュース 第3号」2022年9月9日 https://www.t-union.or.jp/data_files/view/48/mode:inline
3 個人事業主として働く配達員らの労働者性をめぐっては、さまざまな論争が交わされている。今年の9月には神戸在住でデリバリープロバイダのもと働く男性の仕事中の負傷が「指揮命令を受けて働く労働者に当たる」として労災認定された。
4 https://www.vox.com/2019/5/8/18535367/uber-drivers-strike-2019-cities
5 アマゾンは2023年6月、アマゾンフレックスのアプリ上で配達員に対し、仕事内容についてメディアの取材を受けたり、アプリの写真を公開した場合は守秘義務違反に当たり配達員資格を失う可能性がある、という内容の通達を出した。
▼掲載号のご購入はこちら!
▼【20%OFF】お得な定期購読のお申し込みはこちら!
▼特集のほかの記事
【特集】物流危機を救うのはAIと規制緩和か?
◆「規制緩和」がもたらしたトラックドライバーたちの過酷な現状
──物流2024年問題と労働組合への期待
川村雅則(北海学園大学教授)
◆高速道路で「重大事故」が増加する?
──「2024年問題」でトラックの速度規制を緩和
今野晴貴(NPO法人POSSE代表)
◆外国人ドライバーは流通の「救世主」となるのか?
本誌編集部
◆アマゾンの「当日配送」を支える人々を追って
──前編
岩本菜々(POSSE学生ボランティア)
◆ヤマト運輸の個人事業主・パートたちは「大量リストラ」といかに闘ったか
──軽貨物ユニオンの取り組み
高橋英晴(軽貨物ユニオン執行委員長)
◆「最高益」なら還元しろ!
──アメリカのトラック・ドライバーは年収2500万円へ
本誌編集部
POSSEの編集は、大学生を中心としたボランティアで運営されています。よりよい誌面を製作するため、サポートをお願いします。