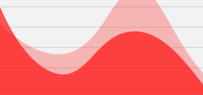激動の時期を乗り切るには
高いレベルの自制心が必要
過去に経験のない大きなリスクを伴う状況において、冷静さを失わず、柔軟な思考を持ち続けるのは難しいかもしれない。そのような環境で、私たち人間が示す本能的な反応は、過去に成功をもたらした方法に固執するというものだ。それが普通であり、すでに慣れ親しんだ状況であれば、うまくいく場合もある。しかし、新しい問題解決策が必要とされる新しい状況では、古いやり方に従うことを前提に行動すれば、失敗のもとになりやすい。
問題は、大きなリスクがある未知の環境に身を置くと、しばしば不安が高まり、それがきっかけで自分の手足を縛り、イノベーションを妨げる反応を示してしまうことだ。これは「適応のパラドックス」と呼ぶべき現象である。学習し、変化し、適応する必要性が最も大きい時ほど、私たちは古いアプローチを選びがちになる。新しい環境に適していないアプローチで行動し、お粗末な意思決定をして、有効性の乏しい問題解決策に走ってしまう。
激動の時期を乗り切るためには、リーダーが高いレベルの自制心を発揮しなくてはならない。それを筆者らは「計画的な冷静さ」(Deliberate Calm)と呼んでいる。ここで言う「計画的」とは、ある状況をどのように経験し、その状況にどう反応するかについて、自分に選択肢があると認識していることを意味する。そして「冷静さ」とは、古い行動パターンに支配されることなく、どのような反応が最善かを理性的に検討できることを指す。
「計画的な冷静さ」は、適応のパラドックスを解消する手立てになる。これを実践することにより、リーダーはこれ以上なく過酷な状況にあっても、意図を持って、独創性を発揮して、客観的な視点で行動することが可能になる。またこのアプローチは、ことのほかリスクが大きい局面で、過去に経験したことのない試練に直面した際に、学習と適応を通じてその状況に対処する助けにもなる。「計画的な冷静さ」を行動の習慣として身につけると、不確実性への向き合い方が変わる。すなわち、これは一つの「習慣」と位置づけるべきものなのだ。
「計画的な冷静さ」の実践
架空の例を使って説明しよう。ジェフは日用消費財メーカーの営業責任者で、勤務先は売上げの不振とテクノロジーおよび市場の激変に直面している。業績を改善する必要があるという警告を上司から告げられたジェフは、激しい重圧といら立ち、不安を感じている。この状況に対し、過去にうまくいったやり方で対処しようと考え、上司には「問題は解決します」と請け合う。これまでの2倍の努力をして、売上げを増やすために全力を尽くせばよいと考える。
しかし、古いやり方では新しい状況に対処できず、苦しい状況が続きかねない。もし、過去に有効だった「アメとムチ」型の手法が効果を発揮しなかったとしたらどうするか。実際、この時直面している状況では、売上目標を設定し直したり、インセンティブ制度を設けるなどして成果主義を強化したり、チームのメンバーに発破をかけたりするアプローチは、効果がなく、
それに、古いアプローチを実践してさらに頑張るというアプローチがいつまでも実を結ばなければ、パニックに陥りかねない。そうなると、ジェフは同じ方法論をいっそう強力に推し進めようとするだろう。新しい現実に適応して、新しい問題解決策を見出そうとはしない。
では、ジェフが「計画的な冷静さ」を実践する場合はどうすべきか。まず、深呼吸して、自分の置かれた状況をじっくり検討することから始める。その後、その状況について上司と率直に話し合う。その際、自分がすべての問題の解決策を知っているわけではなく、古いアプローチが効果を発揮しなくなっていて、競争環境の変化により、売上げを維持することがますます難しくなりそうだと率直に伝える。
これによりジェフの不安が完全に解消されるわけではないが、古いやり方に頼ることで偽りの安全を感じようとする姿勢は現実から目を背けるものにすぎず、その安らぎは長続きしないのだと理解する意味は大きい。古いやり方にしがみつくのではなく、根底にある問題を表面に引っ張り出し、居心地の悪い気持ちに打ち勝って、新しいアプローチを模索するための対話を始めたほうがよい。新しい対応の仕方を見出すための方法を提案したり、新しいアイデアを生み出すための支援を求めたりすることも可能になる。