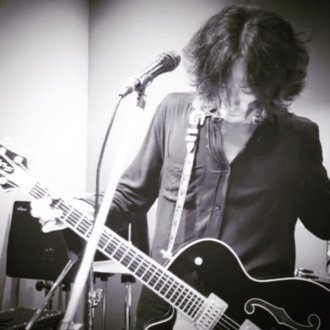全部、たいしたことではない。
時折、この世の中を「死なせてくれない社会」だと思うことがある。延命措置が発達すると、死に対して脆弱になる。何としてでも生きろと言われて、死ぬことが許されなくなる。楽になることが許されなくなる。風通しが悪くなり、息苦しさを覚えるようになる。生が日常なら、死もまた日常である。死ぬことが非日常に設定された社会では、永遠に生きるつもりで日々を送るようになる。モノを増やし、情報量を増やし、堆積物に埋もれるようになる。死という自然が排除されて、人は必ず死ぬということを忘れる。そして、いざ、誰かの死を目の当たりにした時に、慌て、悲しみ、ジタバタする。死を意識することで、ちょっとは生きやすくなる。
バイク事故に遭った時、強烈な痛みと共に安心感を覚えた。すぐには言語化できなかったが、事故に遭ったことで「具体的な問題が起きた」ことが嬉しかったのだと思う。頭の中で観念を転がしているだけとは異なる、具体的な痛み。後日、バイクは廃車となった。金銭的には大幅な損失だが、安心感の正体は「罪からの解放」だと思った。事故が起きるまでは、バイクを手放すだなんて考えてもいなかった。当たり前に共にあり、死ぬまで乗り続けるだろうと思っていた。そんな「当たり前にそこにあるもの」が消えてなくなった時、私の生き方も変わらざるを得なかった。自分では手放せないものを、代わりに手放してもらったような感覚を覚えた。
モノを持つということは、同時に責任を伴う。モノを持っておきながら、それを大事に扱うことができていないことは、想像を超えたストレスを与える。それは、大袈裟な言葉で言えば罪だと思う。無意識の間に罪悪感を溜め込み、所有物の責任に押し潰される。だが、永遠に生きるつもりでいる私たちは、なかなかモノを捨てることができない。安全が保障され、安心が保障されているように見える世の中では、今よりも「いつか」が大事になり、いつかのために今を犠牲にするような生き方に侵食される。小さな死の体験が、その幻想をぶち壊した。死は、すぐそこにある。当たり前のことだが、死ぬ時には、金もモノも持って行くことはできない。
生かしてやれないことは罪になる。その罪から解放されたのだと思う。少なくとも、自分にはその罪があると言うことを自覚させてくれた。それが、嬉しかったのだと思う。増やすのではなく、減らす。本当に大事なことに集中する。能動的な変革が断捨離なら、受動的な変革が事故や病気や災害なのだと思う。自分では捨て去ることのできないものを、自分を超えた力が半ば強制的に引き剥がしてくれる。変容せざるを得ない、ある意味「これまでの自分が一回死んで、新しい自分になって生まれ変わる」とも言えるような、破壊と再生。死は、忌避すべきものではない。死が、教えてくれることがある。
それは「全部、たいしたことではない」ということだ。やがて訪れる死に対して、私たちは平等だ。勝ち組も負け組も、金持ちも貧乏人も、等しく死ぬことを経験する。万物は流転する。調子がいい時は、誰でもメンタルは強くなる。問題は、逆境の時だ。元気な時に「この調子で行こう」と思うように、逆境の時も「この調子で行こう」と生きることが、自分の軸を作る。逆境も続かない。万物は流転する。できることを、一つ一つやればいい。何もできない時、じっと耐えるだけでも、忍耐という善ができる。調子がいい時も、調子が悪い時も、よし、この調子で行こうと思うことが、自分の軸を作る。本当は、逆境なんてないのだと思う。順境も逆境も続かない。すべてに等しく終わりが来る。その点において、一人残らず絶好調なのだと思う。全部、たいしたことではないのだと思う。 坂爪 圭吾 様
見舞い先
9月の日曜礼拝に参加した高校3年の◯◯◯◯です。「バイクにのって死ぬのは好きですか」と聞かれたのを思い出して手紙をかいています。言われたことないセリフすぎて「わたしこの物語の主人公じゃん!」ってなりました。坂爪さんは「事故りたいから乗るんですよ」と言ってて度肝抜かれました。今回は生きててよかったです。あの日、はじめましてのセリフばっかりで本当に楽しかった!家に帰ってからも2日くらい頭が熱くて、あつくて。バス停で「よく来たね」と見おくってくださってドキッとしました。
坂爪さんに出会ってから「私から学べ!」という気概で堂々と教室にいられるようになりました。勉強もやらず、遅こく、早退ばっかりの私の存在自体がなんかもうめちゃくちゃ教育的かなって。どんなに何もしてなくても、成績がクソでもそんなの関係ないように誰よりも元気に過ごしてやろうって思えました。「ここにいちゃいけない」と思っていた頃より数段イケてるマインドです。そしたら教室で友達が沢山できました。3年生になったらもう友達をつくる時期も遊ぶ時期も終わってる、勉強しかしちゃいけないって思い込んでました。そんなわけなかったです。
人生で出会うみーんな遊び相手だって思いたいです。坂爪さんの文章を読むと、デッカさに感動します。神社の御神木が思ったよりデカくてグっと見上げたときのデカすぎて変な感じと似てる気がします。デカすぎて畏怖すら感じます。遠近感がよくわからなくなって目がバグって自分のものさしじゃ測りかねて、そんなのどうでもよくなります。
先日、共通テスト(坂爪さんの時のセンター試験)を受けてきました。休み時間に外に出たら雨なのに空が明るくて、レースみたいな雲の流れがきれいでした。大学いって社会に出て、、みたいなことを考えていると、生きるコトを「難しそうなモノ」に置きかえちゃってるなって思います。
椿とサザンカを見分けられるようになりました!葉っぱ2枚入れておきます。どーっちだ!私がどんなでも態度を変えないでいてくれるお花も空もやさしく励まされます!こんがらがっても、元気なくても「この調子、この調子」と唱えて、やりたいコトを始めるときは「時は満ちた!」と天をあおいで、これからもそうやって過ごします。
坂爪さんもきっとこの調子です!!
〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山302
坂爪圭吾
連絡先
LINE ID ibaya
keigosakatsume@gmail.com