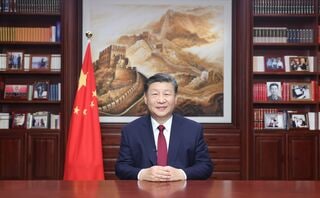能登半島地震が問う冷徹な現実
熊本地震においても、復興不能な人口規模の地域は事実上の集落の解体が行われました。7700億円とも言われた復興予算も、それなりの割合が未執行(計画には盛り込まれたが、現地でのマンパワーや高齢化した住民のニーズに見合わず計画実施が見送られた)になっています。
さらに、地域の産業をどう復興させるかという論点もあります。
例えば、輪島市は日本でも大変重要な文化財でもある輪島塗の産地ですが、これらの産業を維持するために、政府が被災した事業者などに対して特融の制度を定めても、借り手の側がそのまま廃業してしまうリスクさえも存在します。
制度融資をいくら拡充しても、すでに借り手である事業者が高齢化している以上、仮に無利子無担保であったとしても、3年ないし5年の融資期間の先に自身で事業を担っているのかという点で確かなことは何も言えないからです。
結果的に、40代、50代の事業者のみが挙手をする形にならざるを得ず、文化を文字通り支えている70代以上の職人は廃業するか、他の事業者のもとで働くしかなくなるでしょう。
そもそも、輪島市や富山県氷見市も含め、日本海側の各地域に一定の人口が維持されてきた背景には、日本海側が長く我が国の海運の大動脈であり続けたという歴史的背景があります。
ただ、能登半島北端も、日本海側の海運の衰退とともに繁栄の理由を失って産業的な優位性を失い、結果として過疎化が進みました。いくら輪島塗が日本を代表する文化的事業であっても担い手を失いかねない現実に直面するわけです。
日本の“名宰相”とも謳われる田中角栄は、「山間部の60戸しかない集落では、病人が出たら戸板で運ばなければならない。そういう人たちのために12億円かけてでもトンネルをつくることが政治の役割だ」と喝破しました。
ただ、2C1Pacific氏も記載しているように、1億人の人口のうち高齢化率が1割程度であった70年代の日本と現在とでは、住民が求める生活の水準がそもそも異なります。
地域の電化率だけでなく、上水道やネットインフラはもちろんのこと、救急や産科小児科を持つ相応に設備のある基幹病院や子どもでも通うことのできる学校など、子育て環境がなければ地域で子どもを産み育てることができません。
その病院も含めた子育て環境も、厳しくなる人口減少と財政の問題から、石川県では奥能登の医療集約を進めようとしていたことは冒頭に述べた通りです。住民が安心して子どもを産める環境でなければ地域人口など増えるはずもないのですが、人口全体が減少してしまうとこれらの都市機能を維持することができません。
子育て世帯は勤労世帯ですので、結果的に子育て環境とよりよい仕事を求めて都市部に出ていくのもまた当然の帰結です。
このように、我が国の人口減少は画一的に起きていることではありません。子育てが可能で、地域で次の世代を育てることのできる地域以外は人口ボリュームを維持できず、生活機能と職場が失われ、衰退に拍車がかかるということです。
そういう地域に残るのは、どこに暮らしていても一定額の支給が得られる年金生活者と生活保護世帯、および市役所町役場などの公的部門だけです。
そういう生産性を失った地域が、今回の大地震のような激甚災害を受けて損害を被ったとして、その復興で災害の前の生活を取り戻すような公費を投じることが、どこまでならば妥当なのか、冷静に議論しなければならないでしょう。
 焼け野原になった輪島市の一角(写真:新華社/アフロ)
焼け野原になった輪島市の一角(写真:新華社/アフロ)