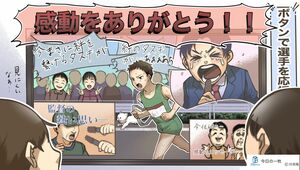格差拡大という「副作用」
僕の理解では、「テクノロジーベースの個別最適な学び」の効果に関する研究のエビデンスは混在しており、「何とも言えない」というのが現状だと思います 。しかし他方で、多くの研究が、ネガティブな「副作用」の存在も示しています。
その最大のものは、「子どもたちの間の格差を広げる恐れがある」ということ。
文部科学省は「誰一人取り残すことのない」という冠を「個別最適な学び」の前に付けていますが、これは、「『個別最適な学び』には、誰一人取り残さないようにできるパワーがある」というよりも、むしろ「子どもたちを取り残す危険性があるので、そうならないよう(そのような「個別最適な学び」を行わないよう)気を付けなくてはいけない」という警鐘と捉えるべきだと僕は考えています。
実際、(少なくとも米国における数十年の)歴史が示唆しているのは、「テクノロジーベースの個別最適な学び」は「取り残される子どもたちの数を増やしてしまう恐れがある」ということなのです。
例えば、アメリカにおいて、「学習の個別化」の代表格として取り扱われることも多いMOOCs(Massive Open Online Courses)。MOOCsは、日本語にすれば「大規模公開オンライン講座」、すなわち、様々な大学等の講座が掲載されたオンライン上のプラットフォームのことを指します。各講座のページには、教材のみならず、講師による解説動画や、理解度をチェックするためのテストなども掲載されています。多くの場合、受講料は無料です(修了証書等を取得する場合を除く)。
10年以上前、アメリカでこのシステムが導入された際には、「誰もが自分の興味があることを、自分自身のペースで学ぶことができる!」「家庭環境や居住地域にかかわらず、質の高い大学の講義にアクセスすることができる!」と、大きな期待が広がりました。
しかし、時が経つにつれて明らかになったのは、「こうしたツールは、(無料であるにもかかわらず)学力面あるいは学習環境面で恵まれた層の学習者たちに最もメリットがある」、逆に言えば、「恵まれない層の学習者にはあまりメリットがない」ということでした。
そして、こうした学習者が学習を継続する上で最大のボトルネックになったもの、それは、文部科学省が強調する「自ら学習を調整しながら粘り強く学習に取り組む力」だったのです。