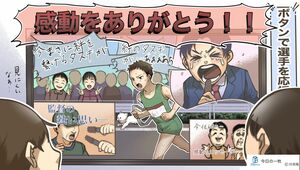「生身の人間」による個別指導は成果をあげたが…
「そもそも論」から立ち返って考えてみましょう。そもそも、なぜ「個別化」、そして「最適化」が必要なのでしょうか?
文部科学省は「全ての子供に基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、思考力・判断力・表現力等や、自ら学習を調整しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するため」には、「個別最適な学び」が必要だと主張しています2。確かに、直感的には、大人数教室での一斉指導(一方通行型の講義など)よりも、自分の理解度に合った内容を、自らのペースで学ぶことができた方が、効果的に学ぶことができそうな気はします。しかし、この感覚は本当に正しいものでしょうか?
歴史を紐解けば1984年、アメリカの教育学者、Bloom(Benjamin S. Bloom)は、「完全習得学習(Mastery Learning)」という指導法を用いて、マンツーマンの個別指導を行った場合、通常の大人数・講義ベースの授業と比べて、生徒のテストの点数を大幅に向上させることが可能であることを発見しました3(その差が標準偏差二つ分だったことから、「2シグマ問題」と呼ばれます)。
「完全習得学習」とは、ものすごくざっくり言えば、「学習・指導→形成的評価(テストなどによるチェック)→クリアできなかった点に関する追加学習・追加指導(もしすべてクリアできていた場合には、次のレベルへ進む)」といったプロセスを、学習目標全体が達成されるまで繰り返す、という学習・指導方法です。なるほど、これは確かに、「個別化」「最適化」の有効性を示す一つの証拠になりそうな気がします。
しかし、この実験と、現在の我が国における「個別最適な学び」の議論で大きく異なる点が一つあります。
それは、Bloomの実験で行われたのは、生身の人間(チューター)によるマンツーマンの指導であるのに対し、現在の「個別最適な学び」は、テクノロジーの活用が前提とされている点です(現に、文部科学省も「ICT環境を最大限活用し、『個に応じた指導』を充実していくことが重要」としています4)。
これはある意味では当然のことで、小規模の実験とは異なり、現在進められようとしているのは、日本全体の「教育改革」です。すべての学校において、人間によるマンツーマン指導を実現しようとすれば、すさまじいコスト(教師の数、時間、負担)が必要となり、それはさすがに非現実的です。
しかしここで、AIドリルなどのテクノロジーを活用すれば(すなわち、「人間による子どもたちの見取りと支援」の代わりに、「ビッグデータとAIを活用したフィードバック」を行うことにより)、低コストで、同様の効果を実現できる可能性があるのではないか、ということです。では、果たして、(現在の水準の)テクノロジーによる学びの個別最適化は、生身の人間によるそれと、同様の成果を得ることが本当に可能なのでしょうか?