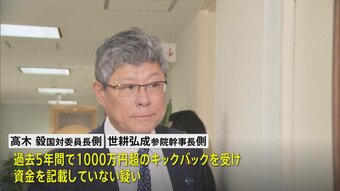官民ファンド1390億円支援も中国との競争で苦しい状況に。価値獲得が課題
なぜJOLEDはうまくいかなかったのだろうか。電気産業に詳しい早稲田大学大学院の長内厚教授は今回の原因について次のように話す。
早稲田大学大学院 経営管理研究所 長内厚教授:
モノさえ良ければ売れるという考え方の限界が来た。新しい技術を開発する、製品を開発する、そこまではできるのです。いいものは作るのですが、大量生産のプロセスあるいはその先の大量販売のプロセスといったところまで全体を含めてビジネスを考えられていたのか。安く大量に作るあるいは大量に顧客を見つけてきて大量に売るというような価値獲得というプロセスに踏み込めなかったというところが非常に大きな問題だと思います。
――ソニーやパナソニックの持っていた技術があり、しかも政府の公的支援もあって、それでもうまくいかなかった。どうすれば日本の電気・電子産業は復活できるのか。
早稲田大学大学院 長内厚教授:
日本は戦略=技術だった。この考え方をまず改めていく必要があって、どうやって他社よりも優位なポジションにつくか、どうやって他社よりも独占的な地位を築くか、技術はそのための一手段でしかないという素朴な経営の話をもう1回思い出す必要があるような気がします。

JOLEDは2015年の設立当初から官民ファンド「INCJ」の支援を受け、これまでの累計は1390億円に達している。
――2017年に取材した時、これはゲームチェンジャーになるといいなという期待を持ったのだが、残念ながらうまくいかなかった。経営の問題もあると思うし、他にもいろいろな敗因があると思うが。

明星大学経営学部 細川昌彦教授:
大きな流れの一つの局面として捉える必要があります。他の分野でも同じようなことが起こっていいます。流出という言葉がいいのかどうかわかりませんが、日本がかつて強かった分野の技術が韓国に流出し、韓国から中国に技術流出が起こり、そして中国がそれを重要産業として巨額の補助金を投入して大量生産をして、大規模に生産するものですから価格はガーッと落ちて他の企業がついていけなくなってしまうから市場が席巻される。こういうことが今までも液晶パネルで起こり、太陽光パネルでも起こり、電池でも起こりということです。
――みんな日本が最初に開発して生産も始めたが、気づいたら価格競争で負けて日本からはそういう産業がなくなってしまった。

明星大学経営学部 細川昌彦教授:
まさに有機ELでそれが起こっていて、シェアのグラフを見ると一番上に中国のBOE。中国企業がまさに今大規模に投資をして増産に次ぐ増産です。
――サムスンやLGがトップを行っているのかと思いきや、中国がトップだ。
明星大学経営学部 細川昌彦教授:
パネルメーカーはもう完全に中国が席巻しているということが今のパターンで起こっているわけです。そういう流れで非常に苦しい状況になるということだと思います。
――優秀な技術者がいて政府も一定の支援をして、それでも国際競争に勝てないという例がいくつもある。どうすれば日本のエレクトロニクス産業は復活できるのだろうか。妙案はないか。
明星大学経営学部 細川昌彦教授:
今のような国際環境を頭に置いた上で、まず大事なことは技術の流出から始まっているということだから、技術の管理がいの一番に大事だと思います。競争相手の中国は大量の資金を調達できる。補助金もすごいですから。そうすると、資金という面で大規模な投資ができるだけの支えを公的に継続的にやれるかどうかということも大事です。もっと大事なのは売り先としてのマーケットがちゃんと育つかどうかというところだと思います。今申し上げたようなことは、これから先の半導体にとってものすごい教訓になると思います。