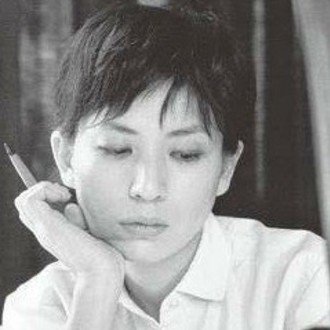遠野遥『破局』にまつわる講義
正直、タイプってわけじゃない。(と言いつつ、冒頭が好きで読むのを決めた)
話の内容も文章も全然私の好みとは違う。それでも、高揚感、そしてそのあとにやってくる満足感と虚脱感まで味わわされてしまった。
おそらく1日に何人もの人が『破局』を読んでいて、そのうちの何人かは『破局』について感想をつぶやいていて、そこには大体「すごい!」「面白い!」の言葉が並んでいる。それも当然だ。『破局』は面白くてすごい作品だから。
でも、その“すごさ”や“面白さ”をどれだけの人がちゃんと説明できるのだろう?ひょっとしたら、『破局』に正面から本気で向かい合って、その芯を捉えるような重いタックル(読解)をできるのは私だけなのでは?という傲慢で危険な誇大妄想が頭をもたげてしまったわけで、今こうして一向に進まない駄文を書き散らかして苦しんでいる。
そして、遠野遥の『破局』について書くはずだったのに、気づいたら初めの3000文字は全く違う本の解説を褒め称えているだけになっている。飛ばしてください。
さて、よい作品解説とはどんなものだろうか? 私のなかでは、福田恆存の「『老人と海』の背景」(新潮文庫『老人と海』旧版)がダントツだ。
たった20ページの解説で19世紀から20世紀にかけてのヨーロッパ文学と(当時の)現代アメリカ文学の変遷を追って、その課題を洗い出したうえで、ヘミングウェイの『老人と海』が文学史上、いかに革新的で優れているのかを証明しているのです。本当にすごい!
私がこの解説を長々引くというのは、つまり、福田翁を踏襲しながら、『破局』の革新性について解説しようという不遜な思いがあるわけで……(もちろん解説がめちゃくちゃよくて引きまくりたいというのもある)だから、
長いと感じる人は、よく分からない解説や引用がでてきた時点で、当然読み飛ばしてもらって構いません。むしろ、遠回りさせてごめん。本当に宇宙的遠回りだから。
具体的に言うと、ヘミングウェイの名前が出てくるまで飛ばしてもらっても大丈夫。
では、講義の方を始めさせていただきたいと思います。
福田恆存はこの解説で、小説における個性が行き詰まっていくのを追いながら、個性をけちょんけちょんに否定していきます。
まず、以下のように、小説における個性についてざっくり述べて、それが近代の個人主義を経て尖鋭化するのを確認していきます。
われわれはよく、作品のなかに、作者の個性を、あるいは登場人物の個性を求めます。それがなにを意味するかと申しますと、ある特殊な過去の経験を背負っているひとりの個性が、べつの経歴を背負っている人物や環境と出あって生きにくさを感じながら、悩むことによって、ますます自己の特殊性を、いわば個性を発揮するのがおもしろいというわけであります。(『老人と海』p.152)
だが、ひとびとはそれだけでは満足できなくなってきました。近代の個人主義は、他人とはちがう自分という意識をめいめいが自覚することを要求するのです。AはB'に棲んでいるBと違うことはもちろん、おなじA'に棲む他の人間ともちがうまぎれもないAでありたいと思いはじめたのです。(『老人と海』P.152-153)
19世紀のヨーロッパの小説は、そのような個人主義的な要求に応えて出現し、そんな小説に読者もまた「この作品こそ自分のために書かれたんだ!」と感激するようになっていきました。
でも、読者の誰もが、これは「自分だけ」の気持ちを描いてくれたと感じたのであれば、それは「自分だけ」の気持ちではないはずで、ここで矛盾が生じます。つまり、「ヨーロッパの近代小説は個性を発見し、個性を描き出し、個性的であろうとめざして、あげくのはてに個性をみうしなってしまったといえましょう」。
WW1後、イギリスでは「意識の流れ」、フランスでは「自意識の文学」というものが隆盛したのだけど、福田恆存はこれを「要するに個性を追求していきづまったところに現れた一種のあがき」と辛辣に切り捨てます。
AがBと、あるいはBがAと、ちがう特殊性をもはや描けなくなったとき、いいかえれば、AもBもけっきょくおなじものとしか思えなくなったとき、さらに個性的なもの、特殊なものを追求しようとすればAやBをながめている自己をとらえるよりほかに手はなくなります。(略)残された唯一の手は、ABをながめるながめかたに、その作家独自の個性をだすことでありましょう。(『老人と海』P.154-155)
まあ、そんなことをしていても、どんどんこんがらがって、ついに個人主義の限界まで到達してしまいましたとさ。
ご多分に漏れず、ヨーロッパ文学を輸入した近代日本文学(特に、日本で独自の発展を遂げて一時期の主流でもあった“私小説”と呼ばれるジャンルなど)についても大体同じことが言えるでしょう。あの、クソじめじめした自意識のやつね。
で、その間にあった文学のことはいろいろすっ飛ばすことにして、ヘミングウェイを筆頭とするアメリカ文学は、この精神のいきづまりを、ヨーロッパとは全く別の方向から突破しようとするのです。
かれら(筆者注:ヨーロッパ)にあっては、精神を否定するものは、やはり精神です。自意識過剰を否定するものは、やはり自意識です。それに反して、フォークナーやヘミングウェイは、肉体とかその情念とかいうものを信じています。(略)かれ(筆者注:ヘミングウェイ)は、精神とか思考とか自意識とかいうものを、いっさい認めないのですが、その否定のしかたが、精神を精神によって、思考を思考によって、自意識を自意識によって否定するのではなく、それらすべてを肉体や行動への無意識な信頼によって否定しているからです。(『老人と海』P.163-164)
もちろん、ヘミングウェイが精神を否定するうえで、内面描写を全く書かなかったというわけではない。
私の個人的意見を申し添えておくと、ヘミングウェイの描写には、肉体を通してその動作に付随する快・不快くらいは伝わってくる。鱒釣りとかキャンプの描写とか普通に心踊るし、闘牛のシーンも血が湧き立つ。
そして、「内面黙説法(byジェラール・ジュネット)」=“内面を極力書かない”ということによって、逆に読者がその内面を想像できる“余白”のようなものが生まれている。その結果、“内面があること”自体の肯定・強化に繋がっているとも言える。
実際のヘミングウェイの意図がどこにあったのかは分からないけど、普通の人にとっては、ヘミングウェイを読む場合でも、“登場人物の内面はある”というのがスタンダードな読み方だったと思うので、このような読み方となる。(と書いたんだけど、そもそも作品によって叙法が違うからヘミングウェイを一括りにはできなかったよね!今の忘れて!でもやっぱ忘れられたら困るからぼんやり頭に入れといて!)
まとめると、ヘミングウェイ=アメリカ文学の段階としては、これまでのヨーロッパ文学で主流だった自意識・精神・内面を否定して、肉体・行動描写に走っていき、その快楽と虚無を書いた。今、仮にこれを〈旧時代の虚無〉とでも名付けておきましょう。
浅薄で安易すぎる見立てをするのならば、日本の小説家からは、大江健三郎、中上健次、村上龍の名前を挙げてみてもいいかもしれない。
では、『破局』についてはどうだろう?
(ここから盛大なネタバレを始めます)
主人公の陽介は大学4年生で、毎日公務員試験の勉強と筋トレと自慰をしている。そのような「筋トレと自慰と勉強を繰り返すだけの日々」は、「特別記憶に残ることもなく」過ぎていく。
反復される行為は、機械的なものとなり、一つ一つの行為に重みや意味はなくなり、行為者の無感覚を引き起こしていく。
作中におけるセックスについても、概ね同じことが言えるだろう。正直、あまり楽しそうには感じない。語り手が「私はもともとセックスをするのが好きだ」と宣言しているとは、とても思えない。
むしろ、灯のことを思いながら、観覧車に向かって自慰をしているシーンの方がなんとなくイキイキしていないだろうか?
(観覧車のイルミネーションに照らされながら反り返る男性器から、私は、65年前に芥川賞を受賞した小説(元都知事の『太陽の季節』ですね)の、勃起した男性器で障子を突き破る場面を思い出した。 そう言えば作中には、スポーツ・筋肉・セックスといったマッチョイズム的な記号がこれでもかというほど氾濫していて、その過剰な男性性が行き着く先に「破局」があるのだと諷刺しているように読めなくもないがどうなのだろう)
評や感想のなかで、「私はもともとセックスをするのが好きだ。なぜなら、セックスをすると気持ちいいからだ」(p.68)という衝撃的な文がよく引用されているが、次の文の方は見落とされている。
そして、私はセックスをするのが好きだが、セックスをするには人間に近づく必要があるから、なかなかうまくはいかない、とも思った。(『破局』p.23)
その方が気持ちよく感じるからという理由で、左手で自慰を行うのと同じようには、セックスはできないだろう。相手は自分の左手ではなく、生身の人間のわけだから。そして、彼はセックスをするのに人間に近づいた結果、次のようなことを考える。
勃起した男性器を押しつけられるのは、いったいどんな気分か。興奮するか。もっと押しつけて欲しいか。熱いか。硬いか。何とも思わないか。どうでもいいか。汚いか。不快か。頭にくるか。悲しいか。苦しいか。泣きたいか。許せないか。早くこの時が過ぎてほしいか。(『破局』p.36)
この疑問文は、麻衣子の気持ちを想像したときのものだけど、それが自分に対していきなり使われる場面がある。
かわりに服の上から大胸筋を触らせてやると、灯は嬉しそうに笑い、それを見た私も嬉しかったか?(『破局』p.32)
(略)ゾンビが出ないうちに灯を押し倒した。これは相手の同意がない場合、罪にあたる行為だが、灯は私の下で幸福そうに笑っていた。それを見た私も幸福だったか?(『破局』p.108)
このような疑問形に、私はヒヤリとさせられた。この疑問形からこれまでのすべてが崩れていきそうなくらいの破壊力を感じないか?
このように、(ラグビーを除く)肉体・行動描写が極端なほど抑制され、そこに付随するはずの感覚が省略され、特に異性との接触の描写には、水を差すかのような疑問形のノイズが挟まってくる。『破局』では、肉体が全く肯定されていないのだ。そこが〈旧時代の虚無〉とは違う。
じゃあ、〈新時代の虚無〉とは何なのかについて考える前に、
ここで、もう一冊の新潮文庫を取り出すことにする。カミュの『異邦人』。
文庫本の背を見れば、思いっきしネタバレをしているご丁寧なあらすじを読むことができる。
母の死の翌日海水浴に行き、女と関係を結び、映画をみて笑いころげ、友人の女出入りに関係して人を殺害し、動機について「太陽のせい」と答える。判決は死刑であったが、自分は幸福であると確信し、処刑の日に大勢の見物人が憎悪の叫びをあげて迎えてくれることだけを望む。通常の論理的な一貫性が失われている男ムルソーを主人公に、理性や人間性の不合理を追求したカミュの代表作。(新潮文庫『異邦人』の内容紹介より)
ポイントを押さえた100点満点の要約ではある。ただ、果たしてそれは正しい作品理解なのか?
たしかにムルソーの言動は変ではあるが、その言動と思考には彼独自の一貫性があるように思えてきて、それが周囲と合わないだけのような気もしてくる。読んでいるうちに、ムルソーが不条理なのか、ムルソーを取り巻く社会が不条理なのかが、私には分からなくなってしまった。
結局、『異邦人』では、「異邦人」であるムルソーが描かれていると同時に、ムルソーから見たときの「異邦」「異邦人」たちが描かれてもいるのだ。
また、ジェラール・ジュネットさんが言うには、『異邦人』は、「思考についてのほぼ全面的な黙説方を伴った内的焦点化」だそうです。なんじゃそりゃ?って感じだと思うので、もう少し簡単に言うと、ムルソーの内面描写なしに、その行動だけが、ムルソーの内側から語られている状況(もっと言えば、ムルソーは自分の行動や知覚するものについては語るけど、それについて自分が何かを考えているのかいないのかを語らない)らしい……すみません、私もよく分かってない。
個人的には、ジュネットが言っていることは、え~そうかな~?という感じだけど、少なくとも『破局』の叙法は『異邦人』のそれとは違うと私は思っている、ということだけは言っておきたい。
(ジェラール・ジュネットの叙法理論を使って『異邦人』と『破局』の共通点について論じる面白くてタメになる記事があったので、より精緻で詳しい議論が知りたい人はぜひ。私はジュネットを読んでいないので大いに参考にさせていただきました……https://note.com/sekizawa_teppei/n/n6754802c6970)
『破局』や『異邦人』、『コンビニ人間』について「サイコパス」「異常者」呼ばわりする感想をたまに見かけるが、それは「自分には、自分が共感・理解できない作品を読む能力がありません」と示しているようなものだ。自分を正常側の人間だと言えてしまうのも、おめでたい。
そして、このような安易なくくり方によって、それぞれの小説の重要な差異を見落とす致命的なミスが発生してしまうのであれば、それは悪手でしかない。
もう一度『破局』を注意深く読んでみる。すると、陽介をサイコパスだと感じるのは、実は読者だけで、作中の登場人物の目で彼の外面の言動だけを見ると、かなりの好青年にしか見えないことが発見できる。
(『異邦人』のムルソーは、ママンの葬式のために休暇を取る際、主人に対して、自分が思った通りにそのまま「私のせいではないんです」と言ったあとに、「こんなことは口にすべきではなかった」と思い、その後は「誤りを犯さなぬように」振る舞っている。彼は周囲とのズレに自覚的で、特に、裁判官や弁護士との絶望的なズレに苛立っている。 『コンビニ人間』についても、主人公である恵子の外面の言動と内面が連動していて、恵子は、他人からしたら異常と感じ取れる言動をすることがある。そして彼女は、周囲と自分とのズレにはある程度自覚的で、バイト先の同僚の話し方や服装を真似して、“擬態”している。 しかし、陽介においては、そのようなズレが発生せず、スムーズに周囲に溶け込めている。なお、『破局』における、このような“語りの二重構造”については、豊崎由美氏がすでにより詳しく指摘している。https://qjweb.jp/journal/32530/)
そして陽介の場合は、内面が読者に対してこんなにも提示されているのにかかわらず、そこには、読者にとってノイズだと思うようなものばかりが詰め込まれていて、解読が不可能となっている。でも、それは彼の真の内面を隠蔽するための意図的な工作なんかじゃなく、本当にそれが彼の内面のすべてなのだ。
陽介からは、そこにあるべきはず(だと読者が想定しているところ)の内面を読み取れない。自意識や精神といった内面的なものを否定していたとしても、それを否定しているのは精神でも肉体でもない“何か”だ。(例外はあるにせよ)むしろ、肉体的な描写は抑制され、肉体すら否定されている。まるで心身二元論を嘲笑うかのように、2つがバラバラになって、バラバラのまま、それぞれが殺されている。精神も肉体も否定した先に残っているものこそが〈新時代の虚無〉なのだ。
また、先述のとおり、読者には陽介の内面?が提示されていて、行動と結び付いていないことがすぐに分かるけど、
麻衣子と灯からは外面しか見えないから、陽介の行動を“性欲”というコードによって、解釈するしかない。女性陣はこの共通のコードによって、“性欲に負けて恋人以外の女とセックスをした”というストーリーを陽介から読み取るが、
そのような読みでは、捉えきれない何かモヤモヤしたものが残る。陽介は、たしかに彼女たちが思うような“性欲猿”かもしれないが、あるいはそうでないかもしれない。私は彼女たちの解釈を強いて〈誤読〉とすることにしたい。
そして、陽介は、灯と麻衣子の行動から内面を読み取らない(というか、内面を自分のなかのコードを使って解釈しない)から、彼女たちは読者からみて、かなり不気味でヤバい女に見えたりする。
なぜ、灯は自室でいきなりかくれんぼを始めたのか? なぜ、灯は自室に幽霊がいるというメッセージを送ったのか? なぜ、灯は陽介の性器に話しかけるのか? なぜ、麻衣子は、陽介と別れたあとに彼を襲ったのか?なぜ、麻衣子は陽介に自分のトラウマの話をし始めたのか?少なくとも読者には全く分からない。かと言って、読者が彼女たちの内面を推測しようとしても、それがまた〈誤読〉である可能性が残されている。もしかしたら、みんな陽介みたいに言動と内面にそんなに関連性がないかもしれない。
結局のところ、『破局』の登場人物たちが変、というよりは、これがコミュニケーション(だと私たちが思っている)ものの実態で、私たちのそれが「破局」せずに成り立っていることの根本的な不思議さと危うさを、この作品は示してくれている。
実は、この問題は序盤から出てきていて、「自分がずっとツバメだと思っていた鳥が、実はスズメだったことに気づいた」膝のよく分からない話に象徴されている。
だけど、やっぱり俺とお前は違う人間で、もしかしたら同じ景色を見て、同じことを考えた時間もあったかもしれないけど、でも、やっぱり違うものを見て、違うことを考えてた時間のほうが、圧倒的に長いんだと思うし。だから、俺が一番よく見る鳥はスズメだけど、お前が一番よく見る鳥は、スズメじゃないかもしれない。カラスとかも、けっこう見る気がするし、お前が一番よく見る鳥は、スズメじゃなくてカラスかもしれない。(中略)それから俺は、スズメの色を木みたいだって言ったけど、お前は俺の意図とは違って木の葉っぱのほうを思い浮かべて、もしかしたら緑の鳥をーー(『破局』p.16)
私たちは、個人の思考や感情、言動にはある程度の一貫性があって、それは他者とかなりの割合で共有できるものだという前提で、お互いにコミュニケーションをとっている。でも、そんな共有コードなんて本当はなくて、現に分かり合えない他人が思考や感情のない、ホラー映画に出てくる「ゾンビ」のように思えてきて恐怖を感じることもある。
きっと、私たちが皆お互い「ゾンビ」なんだよ、「ゾンビ」。
……ここまで来たところで、やっと『破局』の内容に入っていくわけだけれど、正直気が乗らない。
それっぽい読みは提示できるかもしれないけど、それが妥当な読みであるとは私には思えない。麻衣子と灯が陽介を〈誤読〉するのと、同じように評者は『破局』を〈誤読〉するしかないのだ。ここからは、完全なる蛇足を披露することになる。 もちろん、主人公の陽介の行動原理や性格的特徴を“精神分析”しても、ほとんど意味がない。この前提に立ったうえで、いくつかのことに触れておきたい。
『破局』の作中には、似たようなシーンが多くある。このようなときは、反復される場面に目くばせしつつ、そのニュアンスの差異についても考えなければならない。
(やたら逮捕される巡査部長のニュースとか、やたら陽介の顔を見てくるチワワと女の子とか、ファーストフード店のくだりとかね。そう言えば、この作品、“構図”の反復と反転も重要なんですよね、逃げる女と追いかける男との構図であったり(そして女は逃げ切る)、初めの場面でタックルで相手を倒す男が、最後の場面でタックルで相手に倒される男になったり……そういう構図の美しさをぜひご覧あれ!)
私がここで考えたい場面は、“陽介が灯のために自動販売機で飲み物を買おうとする”場面で、これは、膝の新歓ライブ最中に体調不良になった女性(灯)を介抱するために飲み物を買う場面と、二人が北海道へ旅行した際、灯のために自販機で缶コーヒーを買おうとする場面だ。
ひとつめの場面では、具合の悪い女性のために飲み物を買っておくのは社会的に当然であると言わんばかりに、陽介の行動は非常にスマートで、水と温かいお茶の両方を用意している。 対してもうひとつの場面では、灯に缶コーヒーを買ってやりたいと思っても、近くには自販機がなくそれができず、そのときに陽介はいきなり涙を流す。
二つの場面では、規範/社会的な自己と、欲望/私的な自己とがそれぞれ表されていて、対照的である。と当初の私は思ったのだが……
ただし、この“~したい”というのは、“自分は灯(麻衣子)の彼氏だから、彼女を喜ばせたい”など、限定付きの欲望であることが多い。 たとえば、性欲についても、灯とセックスをするまでの過程でも、陽介は、彼女の同意のサインだと思えるようなものを次々拾い上げていって事に及ぼうとするわけだけど、その裏には、「セックスの機会を、私はみすみす逃したことはないだろう」という「チャンスを逃してはならない」「据え膳食わぬは……」みたいな規律があったりするんじゃないかな。 そして、陽介はチャンスを逃さないことによって、結果として、麻衣子と同意のないセックスをすることになる。
“~しなければならない”という規律によって、自身の“~したい”という欲望が制御されていることは、すでに多くの人が指摘しているけれど、規律の方ばかり見ているのは片手落ちのように私は感じる。“~しなければならない”によって、“~したい”が増幅している可能性もまた指摘できるからだ。
その点、灯との関係というのは、“(セックス)したい”と、“(灯の彼氏として彼女をよろこばせ)なければならない”とが見事に一致し、奇跡的なマリアージュを遂げているのだと考えられなくもない。
また、“~しなければならない”の究極体というのは、陽介が語る「ゾンビ」のことだろう。
そう、全員ゾンビになれ。今からお前らはゾンビだ。(中略)ゾンビだから何度でも立ち上がるのは当然だし、ゾンビは痛みや疲れなんて感じない。死んでるわけだから、何もわからない。自分よりでかいやつにタックルするのは怖いかもしれないけど、そういう恐怖もなくなる。ゾンビは怖いと思わないから。むしろ怖がられるほうだから。(『破局』p.60)
自分の感情も感覚も捨て、何度でも立ち上がって自分よりも強大な敵にタックルし続ける。
陽介は、部員の前で「ゾンビ」について熱く語るのだが、しかし、そのような理想は、部員にも佐々木にも決して理解されることはなく、陽介は温度差に苛立ち、やがて失望していく。
さらに、「ゾンビ」のように「俺は何度だって蘇るよ」と灯に誓ってみせたはずの陽介は、彼女の「ゾンビ」のような性欲についに負け、「体力的に限界」を迎えてしまう。
さらにさらに、「そんなはずはないだろう」という陽介の思いも通じず、彼が殴った「逞しい体」を持つ「敵」は、実は「ゾンビ」なんかではなく、倒れたまま二度と起き上がってはこなかった。
しかし、陽介にタックルを食らわせた2人の警官は、「雲ひとつないよく晴れた空」を見ることもなく、暴漢に恐怖を感じることもなく、「危険を顧みず」、淡々と「躊躇なく」、鍛え上げられた肉体の「でかい」陽介を確保しに行った。彼らは、まさに陽介の理想を体現した「ゾンビ」だったのだ。
「十分な勢いと重さでもって正確に私の体の芯を捉えた」タックルに倒れた陽介は、彼らを尊敬し、彼らを信頼し、彼らに任せておけば安心だとまで思うようになった。
警官が、私の体を優しく押さえていた。彼の手はとても温かく、湯につかっているかのように、心地よかった (『破局』p.141)
この結末には、なんとなく『異邦人』と似たような読後感があって、私は「陽介、よかったね……」と涙ぐみそうになった。ムルソーが「世界の優しい無関心」に安寧を見出だすように、陽介は、自分を倒した「ゾンビ」にシンパシーを感じ、心からの賛辞を送って眠りについたのだと思う。この物語に、私と同じような救いを感じた人がいることを、私は心から願っている。
引用文献 遠野遥『破局』(河出書房新社 2020年) 福田恆存「『老人と海』の背景」(新潮文庫『老人と海』より 1979年)
参考文献 カミュ『異邦人』(新潮文庫 1954年) 村田沙耶香『コンビニ人間』(文藝春秋 2016年) 関澤鉄兵「遠野遥『破局』(アルベール・カミュ『異邦人』とジェラ―ル・ジュネット『物語の詩学』からも)」(https://note.com/sekizawa_teppei/n/n6754802c6970)) 豊崎由美「『破局』遠野遥は、文芸界のニュースターだ! 二重構造を生み出す語りを書評家・豊崎由美が熱烈考察」(QJWeb8月6日付の記事)(https://qjweb.jp/journal/32530/)
気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます!