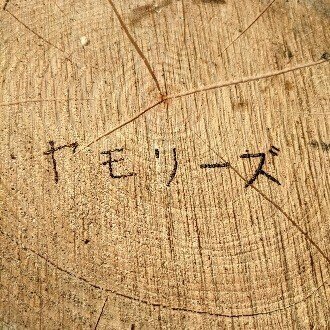木はいかにして水を吸い上げるのか?
どうも!
馬龍山の間伐が終わり、ホッとした5期生原田です。
さて、今回は木と水のお話です。
薪づくりをしながら、含水率について考えていたらふと、「そもそも、木はどうやって樹高の高さまで水を吸い上げているのだろう?」と気になりました。木の成長には水と光が必要で光合成をして育っていくと、いうことは学んだ記憶はありますが、水をどうやって葉っぱまで運ぶのかは記憶にありません(忘れてるだけかも・・・
と、いうことで気になったことはgoogleで大抵は解決します。
自分のメモ代わりにまとめましたので、気になる方は読んでみてください!
浸透圧
木や植物の細胞には「細胞液」という液体が詰まっています。人で言うところの血液ですね。人は心臓というポンプを使って血液を循環していますが、木はこの「細胞液」の濃度を巧みに操り循環させています。
濃度でなぜ水が動くのか?それは浸透圧の働きによるものです。
浸透圧・・・半透膜(フィルターのようなもので分子の大きさで通れたり通れなかったりする)で分けられた部屋に濃度の違う液体が入っていれば、薄い→濃いの方向に水は移動します。[ざっくり]
そして、細胞はこの半透膜の性質を持つ膜に覆われています。
根っこ
根っこは水を吸い上げます。これで終わりでは記事の意味がありません笑
水を吸い上げる仕組みは先程の浸透圧にあります。根っこの細胞には様々な栄養分が取り込まれていて、細胞液は濃い状態です。薄い→濃いの方向に水は移動するので地中の水は根にどんどん取り込まれていきます。これがポンプのように働き、水を押し上げます。これは根圧と呼ばれて、水を吸い上げる仕組みの1つ目です。
葉っぱ
葉っぱは人間言うところの口で、二酸化炭素を吸い込み酸素を吐き出しています。その際に葉っぱの持つ水を水蒸気として放出します。これが蒸散という働きです。これにより葉っぱの細胞液は濃くなります。何度も出していますが、水は薄い→濃いの方向に移動したがるので、下から水を引き上げます。
根が水を押し上げ、葉が吸い上げる。この仕組だけではまだ十分ではありません。20mときには100mの高さまで水を引き上げるには、サポートが必要です
毛細管現象と凝集力
根から吸い上げられた水は、道管と呼ばれるとても細い管を通って幹を上ります。この道官に秘密があります。
まず道官には「毛細管現象」という現象が起きます。これは、細い管の内側の液体が管の中を上昇する働き[ざっくり]です。透明なストローでもよく見ると少しだけ水面が上がっているのがわかります。毛細管現象は管が細ければ細いほど強く働くので、道官の中にはストローとの比にはならない力が働いています。(この他にも毛細管現象を強く引き起こす工夫が道官にはありますが今回は割愛)
そして水で満たされた道官の中では「凝縮力」も働きます。水は、お互いにくっつき合おうとする性質があります。[ざっくり]コップに並々水を入れたときに水が盛り上がるのも凝縮力の一種です。道官の中で細い水柱となった水はさながらロープのように、上から引っ張られても切れることはありません。
まとめ
以上4つの力が働いて木は水を運んでいるのです!
調べてみると、やっぱり自然ってすごいなぁと思い知らされます。水のシステムを見ても非常に合理的で最適化されている。まだまだ、木から学ぶことは多そうです。
それでは5期生原田でした!